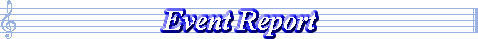
劇団岸野組1990プロジェクト公演
森の石松外伝4 誰かが誰かを狙ってる
2010.06.06 @東京都中央区・博品館劇場
あらすじ
清水の次郎長親分の代参で金毘羅様に刀を納めてから、芝居の物語になりそうな騒動に何度か巻き込まれつつも、清水に向かって着実に歩を進めている森の石松(岸野幸正)。突然降り出した雨に、そこにあったお堂でしばしの雨宿りをしていると、同じような旅人が次々と駆け込んでくる。ぎこちないながらも、たまたま出逢ったひとときを楽しもうと、石松が皆に話しかけていると、その外からきな臭い匂いが漂いこんだ。どうやら、お堂に火をかけられたらしく、逃げ道もない様子。絶体絶命かと思われたが、場数を踏んだ石松の経験と機転でどうにか脱出した。
これは、どう考えても狙われたのに違いない。そう思う理由には事欠かないここに集まった一同。渡世人の石松や丈八(関智一)は恨みを買う覚えには事欠かないだろうし、女一人旅のお冴(横山智佐)や浪人の小文吾(志賀克也)にもなにやら事情があるらしい。お鈴(飯塚雅弓)を連れた女衒の半蔵(くじら)も、商売上どれだけ正直にやっていても恨みはどこかで買ってしまう。そんな一同は腕の立つ石松と同道して、何かあったら守ってもらえないか、と頼み込む。最初は渋っていた石松も、最終的には「同じ方向に向かうのなら」と同意した。
そして6人で通りかかったとある宿場町。いつ危険が襲ってくるか分からない状況が分かっているのかいないのか、石松に促されて見世物小屋へ。そこで催眠術師(橘U子)の技を目にするも、石松はそうそう信じはしない。それなら自分に向かってやってみろ、と術をかけさせた。その場では術が効かなかったものの、芝居小屋を後にしてからその術を思い返し、その間にかけられていた言葉の意味を理解すると、石松は妙な具合になっていた。
次の宿場町へ差し掛かったところで、誰かを狙ってやくざ者2人が襲い掛かってくる。侍ではあったものの、事務方だった小文吾はお冴、お鈴、半蔵に被害が及ばないように守り、丈八と石松で切ったはったに突入しようとした時、石松に異変が発生した。相手に殴りかかろうとすると、体が硬直して動けなくなってしまうのだった。丈八一人では防ぎきれず、いよいよ本格的な危機かと思われたとき、剣術修行の旅の途中の永倉新八(奥戸裕子)が通りかかり、やくざ二人を退散させた。これからも修行の旅を続ける新八に、石松は「信じるものを見つけろ」との言葉を餞に送って、それぞれの旅を再開した。
誰が誰に狙われているのか分からずに、それでも一緒に歩き続ける6人が、とある峠を越えようとしたとき、道の脇から清水が湧き出しているところのそばで、絵を描いている老婆おうい(山路清子)と出逢う。おういと絵や出生の話をしつつ、清水でのどの渇きを癒そうとしていると、不意におういがそれを静止する。絵の具の色を変えてしまうようなものが入っていたらしい。小文吾が確認してみて、砒石だと分かる。再び辛くも難を逃れた一同は、陽もくれるので、おういも連れて麓の町へと下っていった。
その晩、宿を求めた旅籠で、あくどい高利貸しに主人が金を借りたばかりに、いまやどうにもならなくなってしまった母と娘に出会う。「人のことにかまってる余裕があるのかい?」と、お冴やたまたまそこにいた江戸の香具師の元締め、新門の辰五郎(大倉正章)に忠告されるものの、どうしても放っておけずに、一同はかつてその家にあった値打ち者の茶器を盗み出すことにするのだった。
女衒になる前は盗賊だったという半蔵の活躍で、無事茶器は盗み出したが、後始末を彼とお鈴がしているうちに、裏を見張っていた小文吾が、二人はどうしたかと聞きにきて、そのまま戻っていった。そのまま3人でそこに残っていた丈八、石松、お冴のところに、土地の代官が捕り手を連れて現れた。まだ荒事となると体の利かない石松は、それでも何とか立ち向かおうとするが、捕らえられるのも時間の問題のように思われた。そこに辰五郎親分が現れ、かつて彼の元にいたという代官を威圧して、事なきを得た。まだ戻ってこない半蔵とお鈴、そして小文吾。石松たちがいぶかしんでいると、小文吾らしき浪人が東に走っていったと、辰五郎が言う。なぜ自分たちを窮地に残したのかを確かめようと、石松たちも後を追っていった。
石松たちが小文吾たちに追いつくと、そこではいまや斬りあいが始まりそうな気配が満ちていた。忍びらしきものと一緒に刀を抜いている小文吾、そしてやはり刀を抜いている半蔵と、短刀を構えるお鈴。石松たちにはわけが分からないので事情を聞くと、藩主と世継ぎが相次いで世を去った水口藩をそのまま堅持しようと、小文吾は江戸の藩邸に、世継ぎのめどが立ったという文書を届けに走っていたのだった。前藩主は名君の誉れ高く、新藩主と目される人物もその路線を踏襲しようとしているので、水口藩としてはここで取り潰されるわけにはいかない。そのため、公儀の隠密と判明した半蔵とお鈴を始末しないわけにはいかないのだった。一方で半蔵とお鈴も、究極的には民衆の幸福のために働いているはずで、水口藩のそうした行動を阻止したときにどうなるのか、と石松に問われた時に任務に対して迷いが生じた。
そうした流れを見て取って、小文吾は対決から説得へと方法を切り替えるが、忍びたちは死人に口無しとばかり、皆をまとめて始末しようとする。石松や小文吾、丈八、半蔵が戦おうとするが、石松がまだ例の状況なので、皆倒されるか、というところで、新門の辰五郎がたまたま登城していたおういや術師を連れてきて、石松にかかった術を解かせた。元に戻った石松たちの立ち回りで、忍び立ちはここは利あらずと見て、下がっていった。そして、結局、小文吾の嘆願と石松の説得に応じて、お鈴が上申の文書を破棄するのを半蔵も黙認、水口藩は安泰ということになった。
しかし、それだけで騒動の全てが終わったわけではなかった。まだ一行の中に狙う狙われるの関係はあったのだった。かつて、石松が出入りの果てに死なせてしまった一人の渡世人、彼がお冴に誇らしげに石松と遣り合って死ねるんだ、と話したことから、お冴は石松を狙うようになった。しかし、憎い仇が実は義理や人情に厚い人物と知って、敵意を持ち続けていられなくなり、お冴はわだかまりを水に流した。
そして、さらには丈八も一宿一飯の義理で石松を狙っていたのだ。これまでに石松を倒す好機はいくらでもあったのに、そうしなかったのは、憧れの石松のその人となりを見極めて、他の人に話せるように、とのこと。丈八の憧れ、義理、そうした思いを正面から受け止めた石松は、こちらもその気持ちに応えるしかないと、対決に応じる。二人がそれぞれの力を尽くして戦っていると、銃声が響いた。一瞬早くそれに気がついた石松のおかげで、誰にも被害は及ばなかったが、忍びのその行動には小文吾が激怒。「口封じをしたいのなら、私を倒してからにしろ」との啖呵に、忍びたちは今度こそ本当に退いていった。結局、決戦中にも周りが見えていた石松と、そうでなかった自分との間の差を感じ取った丈八はここで矛を収め、全ての騒動がこれで収まった。
そして、もはや狙われる気遣いもなくなったそれぞれが、それぞれの道へ向かって旅立つ時が来た。江戸へ向かう小文吾、郷里へ帰るお冴、当てのない旅を続ける丈八、清水へ向かう石松、江戸には戻れないので、これから落ち着き先を探す半蔵とお鈴、それぞれが信じる未来へ向かって歩き始めていった。…もうちょっとだけ、6人での旅は続きそうな気配だったけれど。
感想
今回、まーちゃんの活動全体を見ても、もしかしたら初めてのタイプの役だったんじゃないか、と思うんだけどね。自分の信じてるところと、行動の(予想されうる)結果に大きな隔たりがあって、そこでどうするか…っていうのが見所だったんじゃないかなって感じ。ストーリー全体にいろいろな要素を入れてあったから、お鈴だけにスポットが当たってるわけじゃないけど、その葛藤とかを見せられる限られた時間の中で、しっかりとした演技をやってたんじゃないかって思う。あと、短刀を抜くシーンもあって、それははっきりと初めてでしょ(笑)。RPG系の作品やってても、多分戦士方面ってなかったはずだしね。まぁ、実際の立ち回りはなかったとはいえ、そうした場面での動きもあったからね。そのうち立ち回りにも対応する…のかな(笑)? さらに言えば、普段から石松に対してツッコミ満載だったから、それも新鮮って言えばそうだし。そんなこんなで、まーちゃんに関して言えば、「こうやってやれる役の幅が広がっていくんだろうな」ってことを実感として感じながら見てた。
全体では、テンポのよさやコミカルさの中に、ちょっとしっかりと考えさせるような言葉だったり行動だったりが入ってて、このあたりが岸野組のカラーなのかな、と。この時を含めて3回行ってるけど、毎回そうしたところは入ってきてるからね。今回、いろんな立場の人たちが入り乱れた物語なんだけど、メインの6人は、自分の信じるもののために行動するっていうところは共通してて、だからこそ、そこから湧いてくる力っていうようなテーマ性はよく見えてきたのかもしれない。そこが明確だから、しっかりと何かを感じ取って帰ってこられるんだろうね。……まぁ、セットとかは、今回あまり作ってなくって、観客の想像力にお任せみたいなところがあったから、そこがもうちょっとしっかりすると、場面に対する想像がより膨らんだかもしれないけどね。博品館はビルの8階だから、搬入が大変かな?
ともあれ、まーちゃんからも、芝居全体からも何かを受け取ることが出来る舞台だったっていうのは確かなことだし、そこでまーちゃんが新しい何かを得たようにも思うから、こっちが見に行った意味もあるし、まーちゃんが出た意味も十分にあったんだろうな、と。また、どこかで舞台に立つときがあったら、どんな芝居をまーちゃんが見せてくれるのか、また新しいものや気持ちの動きを期待したいと思う。
|