1969年 4月11日(金)②
年上の大学同級生男性「学友の死に寄せて」
本ホームページでは、高野悦子の文学部日本史学専攻の同級生(1967年入学)の男性、Tさんが2010年に自費出版した自伝「還暦からの旅立ち─回顧録」を入手した。部落研の子ども会活動で一緒の時期もあり、自伝の一章『学友の死に寄せて』には、高野悦子についての思いがつづられている。Tさんと会って当時の話や自伝の一章の背景についてうかがった。
一緒に卓球をした子ども会
高野悦子は二十歳の原点序章1967年5月11日(木)に以下の記述をしている。 部落研の子供会活動に初めていった。卓球サークルに入ったが、全体の感じとしては卓球をやれて楽しかったことと、子供達がガサガサしていることの二つを感じている。
 T:高野悦子と同級生だが、最初知り合ったのは部落研だった。
T:高野悦子と同級生だが、最初知り合ったのは部落研だった。1年生の時に入った部落研で知り合って、同じ「地域パート」で一緒に子ども会の活動をした。西大路三条の地域での活動で週に1、2回。夜、数人で一緒に大学から市電で行ったりした。私は子どもに卓球と英語だった。
部落研☞二十歳の原点序章1967年5月10日
西大路三条☞京都市壬生隣保館
部落研に入ったのは、出身が田舎の方で差別が激しい地域だったんだけど、その地域で私の家庭は地主のいわゆる末裔だった。それに対して幼いころから抵抗があって、封建的身分制の名残である差別に対してずいぶん疑問を持っていた。“差別というのは何なんだろうか”というね。あと中学生の時に学校の活動で取り上げられたこともあった。
そういう漠然とした問題意識を持ちながら立命館大学の歴史を選んだ時に、どのクラブに入ろうかなあと考えていたら、部落研があったので、入ってみようということになった。
 施設には卓球ができるスペースがあって台と用具もいくつかあった。中学・高校時代に卓球の選手だったんで卓球ができたから、小中学生に指導をした。その時に彼女も子どもと卓球の相手をしていた。そのシーンは今でも覚えてる。
施設には卓球ができるスペースがあって台と用具もいくつかあった。中学・高校時代に卓球の選手だったんで卓球ができたから、小中学生に指導をした。その時に彼女も子どもと卓球の相手をしていた。そのシーンは今でも覚えてる。私は本気ではなく子どもたちの相手をしてるだけだった。本気でやったら向こうから帰ってきたボールを打ち込んで一発で終わり。それは子どもは好まないんで、指導と言っても適当にかわして一緒に遊んでやってた。
彼女も卓球ができた。うまかったよ。二人でラリーをするというか、彼女は私とラリーができる腕前だったということだけど、ずいぶん熱心にするんだ。子どもに見本を見せるためだけでなく、自分たちも楽しんでた。子どもたちが集まってない時に手持ち無沙汰でラリーしたこともあった。
彼女は顔つきから一挙手一投足まで真剣に真面目に取り組んでいて…、ラリーも本当に真剣にやってた。だから私は3年浪人で年上だったけど非常に気に入ってた。
卓球のラリーとは連続してボールを打ち合う意味、上級者はスピードの速いラリーで練習をする。
卓球☞巻末高野悦子略歴「水泳が得意で、新聞部、卓球部、生徒会で活躍」
1967年6月16日(金)で地域の実態に次の記述をしている。
ハルちゃんは中学三年だが、英語をやったが本当に出来ない。
 英語も教えたな。施設には机もあって、英語は中学生で1対1で「教えて」という者を教える。「教えてほしいものを持っておいで」って。
英語も教えたな。施設には机もあって、英語は中学生で1対1で「教えて」という者を教える。「教えてほしいものを持っておいで」って。でも私が当時接した子に限って言っても、もう全く“教える”というレベルじゃなかった。子どもたちに学びたいという気持ちはあったんだろうけど、学校でろくに授業を受けてない。英語に限らず学習レベルはゼロに近くて、教えるのが気が引ける状態だった。
彼女とは一緒に卓球の指導したり英語を教えたりしてたから、日常の会話はしてたと思う。ただ個人的に声をかけたり、親身に話を聞いたというところまではなかった。何より彼女はあまり自分からしゃべらなかった。でも寡黙だけど陰気じゃなくて、雰囲気は明るくてね、いつもニコニコとしてたな。
1967年10月12日(木)で活動の感想について口から出た言葉を残している。
私は「やりがいのあることだと思うけどいつもその苦しさにしりごみしている」といった。
子どもの数は結構いたが、接していて感じたのはね、子どもたちは来ている学生に対して関心を持っていて、教えてもらいたいという気持ちがあった一面で、絶えず心の中では“よそ者に対する警戒心”のようなものがあったことだった。われわれ学生に対して“よそ者を心から受け入れるという気はない”ということを察した。 和気あいあいとしていたわけではなかった。常に大人である学生たちを試していた。「何をしにきたのか」と。
和気あいあいとしていたわけではなかった。常に大人である学生たちを試していた。「何をしにきたのか」と。学生が手抜きのようなことをすると厳しい言葉を浴びせたり、ものすごい目でにらみつけることがあった。その言葉を私自身が直接言われたことはなかったが、子どもたちのあの厳しい目を受け止めることはできなかった。
そういう面で彼女は慕われていた。子どもたちが彼女に対して嫌みを言うこともなかった。彼女は常に真剣だったし、へ理屈を言わず黙々とニコニコとやってたから。
地域活動は、地元の組織と部落研の合意の下に行われた。政治的勢力争いの一面があったことは否めない一方、部落研では差別の実態を知り、活動を通じて自らを成長させるという取り組みでもあった。しかし子どもたちの大半にとって、そのようないわば“大人の事情”は関係なかった。
1967年11月23日(木)に振り返って次の記述をしている。
「現実の差別の実態を学び、解放運動に寄与する」といくら何べんこの言葉をとなえていたにしろ、実際は自己満足を得ていただけであった。しかもその自己満足は偽善的なものであった。
実際に地域での活動を経験して私が感じたのは、当時の都市での差別問題は、田舎とはちょっと違うというものだった。私の出身の田舎も差別はあったが、学校とか生活・経済レベルそのものはそれほど変わらないのに、伝統的な“あの地区は”というらく印を押す封建的身分制度の遺制だった。だから“あの地区”という中に優秀な者もいて有名大学に進学するのもいる。それが差別のイメージだった。ところが都市での差別は全然違った。らく印もあっただろうが、それ以上に当時深刻なのは圧倒的な貧困だった。そこに現に貧困層が集団的にいるということが問題の本質だった。封建遺制よりむしろ、住宅とか環境の整備、それにそれぞれが所得が付けばという…。都市の差別には田舎とは別の問題があると考えなくてはいけないと実感した。
私が接した子どもたちは、あの時代の都市の貧困層の犠牲者として生きてたということだった。そういう貧困層の中にいる子どもたちに教えるということにためらいがあった。“指導する”とか“教える”とかボランティアとか、そういう欺まん性を…子どもたちが私の心の中に見抜いてるような気がした。
1年だけのサークル活動
高野悦子は1968年1月10日(金)で次の記述をして、部落研を辞める決意を残している。
部落研、退部の決意
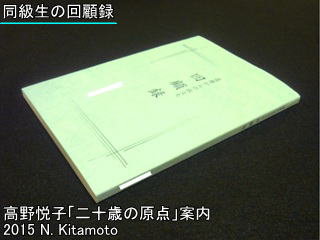 T:私は学校の授業にあまり出てなかったこともあって、一時は地域に入り浸って、青年の家に行って泊まったり食事をごちそうになったこともあった。
T:私は学校の授業にあまり出てなかったこともあって、一時は地域に入り浸って、青年の家に行って泊まったり食事をごちそうになったこともあった。ただ地域以外の活動はあまりせず、その活動も1年間くらいだった。
自分の関心や課題は封建身分制の遺制としての差別であり、都市の差別じゃなかった。それはもう差別意識の問題というより、貧困を解消する政治問題だった。となると右か左かとか、社会党か共産党かとか、解放同盟がどうだとかの選択をしていく世界で、政治色が強くなる。
当時の部落研で言えば、それは共産党や民青の影響力だった。部落研は民青が中心になっていく。「民青に入ったら」というのが結構あった。
さらに立命館大学の場合は、共産党・民青系とそれに対する反共産党・反民青系の党派的な紛争の色合いも有する同和教育問題が起き、自治会活動での争点にもなって政治的対立が先鋭化した。部落研はその渦中になった。
☞同和教育問題
民青☞1967年12月13日
しかし民青のような政治的な組織に入りたくないし、入れない。“シンパ”はみんなそうだっただろう。ところが「組織を拒絶した」と言われてしまう。学生として社会正義の実現に少しは役に立とうとするが、現実的には政治的な組織が強くなって、それに入れない。そこで葛藤があるわけだ。
それに私自身は組織活動そのものが基本的に嫌いだった。大学入学前に2年間、あるキリスト教の一派を称する宗教の信者で、その宗教から脱退した。そうしたらその一派では“脱退した人間は天罰を受ける”“地獄に落ちる”“見つけ次第殺す”と。だから大学に入っても恐怖感が長く続いた。そういうこともあって組織というのは魅力があるけど入り切れない。
人間は純粋にはあくまでも独り、孤独なわけだから、組織で包み込むのは難しい。組織はあくまで戦うという目的で組織してる。民青も全共闘も、宗教も政党も全てそう。戦う以上、組織は人間の個人に対して絶対的になってしまう。だから組織の中で長くいると人間は埋没し教条主義的になる。そうしないと自分で自分自身を振り返った時に組織しか支えるものがないから。それが今の私の考えだ。
もう部落研は私の目的や感覚と違う縁がない世界だった。付いていけない。もう地域に行く気持ちもなくなり、離れていった。
2年生からはほとんど行ってない。決別して辞めたと言うより在籍したまま顔を出さなくなった。だいたい授業がなかったから大学そのものに行かず、アルバイトだけしてた。
彼女が部落研を辞めたのも政治問題に耐えられる子じゃなかったんだろう。差別に対して純粋に関心と正義感は持ってた思うけど、政治的に付いていけない。
そういう面では、今思えば、私と彼女は似てたのかもしれない。ただ“自分は何のために生きるのか”それだけについて考えて、屈折して育った私は周りに振り回されない抵抗力のある人間だったけど、本当に純粋な彼女は周りに振り回されて不幸な面があった。
高野悦子と同学年で部落研から離れた者は他にも複数いた。
Tさんは当時の用語で言えば「民青シンパ」にあたる。民青シンパと言われる人には、民青や共産党の主義主張には共感するものの、その体質には疑問を持つというスタンスの人が少なくない。民青系全体では、全共闘ほどの多様性はないが、それでも一枚岩やひとくくりに捉えられるものではない点に注意する必要がある。
清心館前で─学友の死に寄せて
以下「還暦からの旅立ち─回顧録」の一章、『学友の死に寄せて』から引用する。
静かにねむる君に語りかけます。憶えていますか、私は君の学友でした。同期生とはいえ、4歳も年上の私には近寄りにくいところもあったのでしょうか、あまり話す機会はありませんでした。
昭和44年、春も終わり、清心館入口の階段に座って、ぼんやりと広場を見ていた私に君は話しかけて来たのです。君の写真そのままに、少し前かがみに、はにかむような笑顔で私を見つめて話しかけました。
多分、「お久しぶり、お元気ですか」と云われたように思います。私はその時、どのように言葉をかけたのでしょう。憶えていないのです。君には、セクト的なつれない表情に見えたのでしょうか、とすれば、少し君を傷つけたかもしれません。
当時すでに、学生間は政治的感情で大きく割れていました。全ての感情が、この理解できない隔たりに支配されていたのかもしれません。君の目にはその時、私はどのように写っていたのでしょうか。
昭和44年、春も終わり、清心館入口の階段に座って、ぼんやりと広場を見ていた私に君は話しかけて来たのです。君の写真そのままに、少し前かがみに、はにかむような笑顔で私を見つめて話しかけました。
多分、「お久しぶり、お元気ですか」と云われたように思います。私はその時、どのように言葉をかけたのでしょう。憶えていないのです。君には、セクト的なつれない表情に見えたのでしょうか、とすれば、少し君を傷つけたかもしれません。
当時すでに、学生間は政治的感情で大きく割れていました。全ての感情が、この理解できない隔たりに支配されていたのかもしれません。君の目にはその時、私はどのように写っていたのでしょうか。
 T:後悔してるのは、1969年、3年生のあの時にもっと話さなかったことだ。
T:後悔してるのは、1969年、3年生のあの時にもっと話さなかったことだ。それまで学校に疎遠になっていたのが、3年生の時は一般教養なんかと違ってゼミがあったし、授業に出なくても清心館地下の生協食堂で食事をしたりするために学校に行っていた。
清心館入口の角に階段があって、そこで私は座ってひなたぼっこか何かしてた。
そうしたら彼女がトコトコトコと私の前に来た。「お久しぶりです。お元気ですか」ってニコッとして…。かわいかったよ。
本当に久しぶりで、自分も彼女もあまり学校に行ってないから、偶然。それでも西大路三条で一緒に活動してたから覚えてたんだろう。
その時に彼女を無視したわけじゃない。「おー、元気か」くらいのことは言ったと思う。私は嫌みも言わないし。ただ、それくらいのもので、私には「ちょっとお茶でも飲もうか」というセンスがなかったから。
彼女が亡くなるちょっと前だった。今から振り返ると、あの時もっと話をしとけばと…。
高野悦子と会ったのは1969年4月から5月で、その日付の特定は難しいが、日記の記述や当時の状況などを考慮すると、1969年4月11日(金)の可能性がある。
Tさんは1969年5月、同級生の友人の求めに応じて、民青系による全共闘のバリケード排除に加わった。ヘルメットに角材(ゲバ棒)のTさんは、民青系と全共闘の衝突の中で逃げ遅れ、全共闘側に集中的な攻撃を受けて気絶する。さらに拘束されるが、民青シンパにすぎないとして解放される。しかし一連の暴行によって頭の骨を折り、全身を強く打つ大けがを負った。それ以来、友人などと心理的に距離を置くようになったという。
ただ、人間として満たされない自由を求め、又、巨大な社会の敵を意識しての絶望の果ての死なら、私はひと言、君に云いたいのです。それは、生き抜く者の為に時を共有し、美しきやすらぎの言葉を与え続けてほしかったと。君は詩情豊かな天才でした。それを君自身は未熟として認めようとはしませんでした。しかし、その苦悩に満ちた、絶望の淵からかなでられる言葉の美しさは、君でなければ歌えないものでした。
目に見えぬ巨大な敵を、感性という触覚で捕え、ひとり苦しんだ末の言葉を、君の詩情豊かな詩人の心のさけびとして、私は確かに聞きました。私にはない感性なのです。私の生きる力は屈辱を肥やしに、内に秘めた怒りだけで、人の心を打つ美しい言葉はありません。食を得る為の日々の繰り返しのなかで、私の前を遮る小さな敵を相手に、40年の歳月を送ったのです。
君は自由を求め、資本家をにくみ、権力をにくみました。しかし、君の触覚が捕えた敵は「まぼろし」かもしれません。確かに、資本主義社会である限り、資本家もいます。国家権力もあります。でも、それが何だというのでしょう。
元々、この世に生ある限り、どこにも自由などありません。生きる事、その事が不自由の波間に漂うことなのです。だからといって生を断ち切る自由さえないのです。
目に見えぬ巨大な敵を、感性という触覚で捕え、ひとり苦しんだ末の言葉を、君の詩情豊かな詩人の心のさけびとして、私は確かに聞きました。私にはない感性なのです。私の生きる力は屈辱を肥やしに、内に秘めた怒りだけで、人の心を打つ美しい言葉はありません。食を得る為の日々の繰り返しのなかで、私の前を遮る小さな敵を相手に、40年の歳月を送ったのです。
君は自由を求め、資本家をにくみ、権力をにくみました。しかし、君の触覚が捕えた敵は「まぼろし」かもしれません。確かに、資本主義社会である限り、資本家もいます。国家権力もあります。でも、それが何だというのでしょう。
元々、この世に生ある限り、どこにも自由などありません。生きる事、その事が不自由の波間に漂うことなのです。だからといって生を断ち切る自由さえないのです。
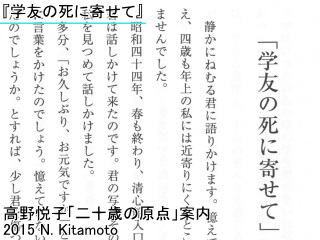 今と違って、立命に限らずあの時代の大学生は多かれ少なかれ社会正義を求めるという意識があった。就職云々より社会正義が何かということに引っ張られた。まだ貧富の差が大きくて、豊かな家庭から大学に行くのはその格差の中での加害者側じゃないかという感覚が、あのころの学生にはあった。
今と違って、立命に限らずあの時代の大学生は多かれ少なかれ社会正義を求めるという意識があった。就職云々より社会正義が何かということに引っ張られた。まだ貧富の差が大きくて、豊かな家庭から大学に行くのはその格差の中での加害者側じゃないかという感覚が、あのころの学生にはあった。大学はある面で非常に憧れの世界だった。しかも憧れの世界は正義だと、大学へ入って社会正義を実現する人間になるんだと、こういうふうに教育されたわけだ。
彼女は感性豊かな詩人だった。感性が違って、抜群の感性だった。
言葉は人の心を打つ。詩人の役割は言葉を美しく人に伝えるということだ。彼女は生きてればそれができたはずで、美しい言葉を奏でることができた。それを失ったのは惜しい。あの時代の社会の閉塞状態が感性の鋭い人間を押しつぶしてしまう。
人間の存在そのものが何かという…。 結局人間というのは大したもんじゃなくて、ただ生きなきゃいかんというだけのことだ。
君の亡くなった後に、遺稿をもとに詩集が出版されました。当時、巷では賛否両論であったと聞きました。40年後の今、読み終えたとき、私にはこの詩集を賛否両論に論ずべきものでもなく、文学的にも政治的にも評価の対象にするべきではないと感じました。ただただ、本人も云う未熟な心の叫びを聞くだけでよいのだと。あの時代に生きた若者の迷いと苦しみを知るだけでよいのだと。それは、私達の心の一部でもあったのです。そして、残されたご遺族にとっては、失った愛する者の生きた証が世に出ることによって、人々の記憶の内に生き続けていてほしい、との切ない思いだけなのだということ。それだけで充分ではなかったかと私には思えたのです。
高野悦子の死は日本史の同級生を通じて聞いたのではないかと思う。彼女の死に対して、当時の学内には悲痛感はあまりなくて、どちらかと言えば、政治的に批判的に始末されたという印象だった。民青の人間が批判的に見てるなというね。私も死ぬのは根本的にアホだと思った。死ぬのは、ばかばかしいとね。だけど、それを政治的に始末するのはどうかと思った。民青の連中が政治的に見て「全共闘に行ったから死んだ」とか、そういう話には違和感を持った。
 彼女の本が出ていることは知ってた。本屋で見かけたから。私も“どうせ死ぬくらいのガキが書いた本だ”とバカにしてたのかもしれない。ずっと読んだことはなかった。それが当時の同級生のみんなが高野悦子、高野悦子と言うから、還暦を過ぎてふと読んでみようと思った。
彼女の本が出ていることは知ってた。本屋で見かけたから。私も“どうせ死ぬくらいのガキが書いた本だ”とバカにしてたのかもしれない。ずっと読んだことはなかった。それが当時の同級生のみんなが高野悦子、高野悦子と言うから、還暦を過ぎてふと読んでみようと思った。本屋で開いて見たのが高野悦子「二十歳の原点」(新潮文庫)にあるニコッと笑った写真。“あの写真の通りに清心館前で私に声をかけてきたよな”ということだった。完全にあのままで私に声をかけてきた。それがものすごく印象的で『学友の死に寄せて』を書いた。
彼女自身も自分は「未熟である」って書いてるように、本当に未熟な子だった。でも最後の笛を湖に沈ませる詩には感動した。あれが子ども会活動で卓球に真剣に取り組んでいるのを見た時に感じた彼女の感性なんだったなあ。
ただ当時はピアノを弾けるとは知らなかった。彼女のピアノを一度聴いてみたかったものだね。
☞1969年1月15日「「独りであること」、「未熟であること」、これが私の二十歳の原点である」
☞1969年3月16日「ホテルの宴会場にピアノがあった」
※敬称は略した。注は本ホームページの文責で付した。
インタビューは2014年3月8日に行った。
魅力ある方だ。大学卒業後多くの会社や職業を転々とされて、現在は一国一城の主として企業経営されているが、その人生経験に裏打ちされた言葉は信頼を得ているに違いない。
地元の文芸活動にも参加されており、この時は「『本能寺の変』について異説から作品をまとめてみたい」と話されていた。
この人の心意気こそ在野の立命史学。そんな気がした。
本ホームページへのご意見・ご感想をお寄せください☞ご意見・ご感想・お問合せ
