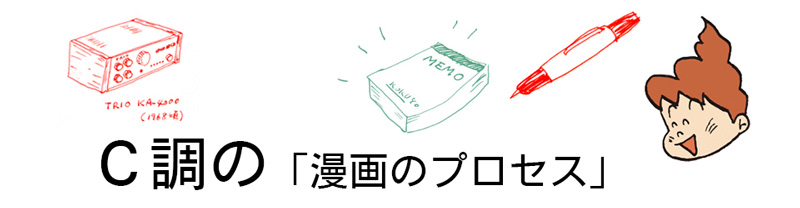
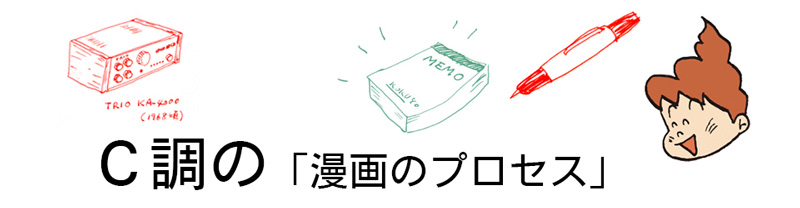

c調です! お元気?
seesaaブログより面白い。「漫画コミュニケーション」
2020/11/06 金 1954
seesaa
あの、失われし自己を求めての著者も
今日はお仕事だったです。
上段の、( 神光 )とメモってあるのは、神光について、あの神光と達磨のことが
描かれている文献があるのだすが、その名前名称がちょっと今、出てこないです。
それはよいとして。 え?よくない? また、それは後日。
今日はそれで、自己実現と、漫画がどうして生まれるのかといったことを
自身のことを、作品と織りなして書き綴っているこのブログというか、
それが、漫画のプロセスなわけです。
で、どうしてこれを私がやっているか、やって来たかという理由としては
何だか、自分のルーツみたいな、本来の書証としたいことでもあるのです。証明みたいなものです。
それが、結実しているのが「漫画のプロセスt」と、漫画コミュニケーション」の2冊です。
これは私個人のことだけでなくて、おそらくテーマからすれば、どなたにも当てはまる普遍的なありようだと思います。
=====
それでは、今日の本代です。今、本代と変換なったですが、実際は本題です。
9月に、amazonさんで5万円本買っちゃったことはお話しした通りです。
お陰様で、概念道具なことが解ったですけど。
今日はよくある、自立のことのお話しです。私は民生委員となっている今でも、
自立ということを念頭に置いています。
何故かというに、自立が出来れば公的な援助もそれほどには、必要ないからです。
これはでも、あくまでも(あくまでものこと)心的な自立のことですので
お間違えのないようにお願いします。
私ら、河原先生の時のこと、後年には、般若くん漫画のことが常にこの、本題である漫画のプロセスのことの中心課題として置いているのですが、
実際に、自分の漫画、つまり、他とは全然、別の実存としてある作品を生むには
本人の(心的)自立が欠かせないことです。
漫画を生み出すことと、精神的自立をなぞらえているわけでもないです。
おそらく、このブログお読みになっている誰か、どなたかも、入選突破となれば、そうなった暁には、おそらく私の言っていることがとても、腑に落ちて解ると思います。
字面だけで、通ったのではダメです。
丁度、それは達磨の安心の神光のようです。神光も、心は(物理的に)そのものとしては、本人自身では認識出来ないもの(?)といった屁理屈をさらって、理屈で解っても、解ったことにならないのと同じです。
実存が本質に先立つので、実際は、私らは漫画のプロセスを書くにあたっては、その辺を感じ取って、さらにはくみ取って、自らのこととしていただければとの思いから書いたものです。
漫画コミュニケーションはそれの、さらに奥に入ったものです。
で、逆から述べさせていただくと、自立や、その人の希望を妨げるものは、何といっても不安心や、恥かしい、恐いなどの感情です。
これは、感情、心のことなので、そのように実際、起こるのですし、
それを、私たちはどうにも出来ません。
出来るのは、「無」に入ることですが、これも、少し年期も要ります。
年期なんか、なくてもよいです。「無」とかに、なれなくとも大丈夫です。実存の扉は誰にも、いつの時、境遇であっても開かれているからです。
=====
何が恐いのか(?)多分、私の河原先生の時の場合は、5ヶ月描けないでいた。それは、実際に、
昨日のブログで本心をあかしたように、自分は「自分を出して、嫌われるのが恐かった」のです。
恐いと、そのように自分自身を認識すると、恥かしいとか、こんなではダメだとかの自己否定がすぐに出ます。
果ては、どんどんそんな思いは進行します。
森田療法のたとえでは、こうしたありようを、??? とにかく、そのような思いは
どんどんと進行します。
つまり、神光みたいに、逆の途を走ってしまうことになります。
でも、心配には及ばずで、安心していいのは、人間というものには、そうした逆の、誤った方向を自ら、是正できる力が備わっているからです。
このことは、信じればよいです。
本元に戻りますが、これで、私は多分、河原先生のその、課題に際して、自分を出したら嫌われてしまうのじゃないか(?)これが、個性ある漫画、というか、自分の漫画を描くのに、(描いて出すのに)阻害していた元凶だったのだと思います。
実際、描いた漫画は選考に入ったわけですけれども、とても、タッチにしてもぎこちないです。
ストーリーにはきちんとなっていますが、それにしても、ありようがぎこちないです。
これは、味とも言えますけど。
木訥とした、書きぶりですし。
でも、こんなことはお年頃の子供だったら、よく見られることです。こうしたことが、実際は大人にもあるのです。
こういうことを、如実に、ものを言っているのが、マズローの防衛と成長のテキストです。
防衛と成長のこのテキストを、成長のことなのだからと、時系列的に発達の流れと見るから、解りにくいので、実際は、恥とか、不安とかがあって、したいけれども(ここでは、描きたいということ)嫌われたくない、そんな思いから素の自分が出せなくなってしまうわけです。
入選したいことがあって、それを可能にするにはですから、逆をやればよいのです。
不安や、恐怖心があって、自分が出せないというのはよくあることです。大人になってからでもあります。
内的力豊かな人ほど、その傾向や味わうことは強い。
だけども、自分で自分のセラピーが出来る人というのは、おそらく、希です。
若い人には特に難しい。セラピーしなくても、どこかでそれは突破されることなので、
安心してよいです。
↑ ここで言っているのは、自立のことです。赤ちゃんにもある、人間の妙味な力というか、自立するのが当たり前、本来みたいな、人間、人としてのそれは本質のことですから。
考えることはないです。
人というのは、そのように出来ている = 達磨の安心。 = 盤珪。(ござっての)
この、主張は(たぶん、私の極めて解りやすい)主張は、マズローの防衛と成長の項で
言っていることと同じです。
森田正馬はこれを、自分のにきび面が恥ずかしければ、堂々と、それを、前に出せと言っています。
これは、ものの喩えでなくって、前回か、前々回ブログ記事の、悟るための態度の真骨頂とも言えるものです。
それと、E・フロムの「愛するということ」(ベストセラー)をまた、引き合いに出すのですが
意識の上では、愛されないことを恐れているが、無意識では、愛することを恐れているとあって、
この訳のわからないみたいなテキストの意味は、
親からの処罰を受けることになるからです。
これは、何だか、育ちの過程でずっと、引き継がれてきた、謂わば、なんて言うか
「こうしたことを、行えば処罰される」という、本人が培ってきた、法則のようなことです。
パブロフの犬のことは美奈さんご存じだと思います。あの、ごちそうを見ると、食べもしない、食べられもしないのに、画像とか見せられるとそれだけで、よだれが出るという
あの、有名な解説です。
これは、親というものが、ものの解った親ではなく、自分(母)ではなくて、別の他人に思いを向けると、それでは面白くないので、端的に言えば「それなら出ていけ」と言われる。
人間なんて、バカなもので、そこまで出来た親などというのは、あまり、いないのです。
むしろ、(よくて)怒り出します。
なんで、お前は私への愛情を他に持っていくのだ、と。いうわけです。
こんなことも、E・フロム著作の中で言っているナルチシズムの喩えです。
そうして、この辺りで、本人が(おそらく)優しければ、そこでの葛藤というものは
かなり強くなります。
親に理解がないからです。
ですから、毒親の概念を取り扱った本では、スーザンフォワード)
まるきり、親が悪いのです とも、はっきりと述べてあるわけです。
本人は悪いとは言えないのです。
ですけど、毒親の概念は注意深くかみくだく必要があります。
スーザンフォワードの、ラストでの描き方も、そのため、微妙です。
自分はこれで、ただ単に、漫画描くのに5ヶ月かかったのか、どんくさいのじゃないか”
とも、なるのですが、
これが、鈍くさいばかりでもないのです。
多分に、元々は、恐れから、それがために、自己を卑下したり、表出するに、葛藤を
大きく生むのです。
これはでも、難しいことです。
マズローならずとも、他の心理学でも、神経症が根にある人というのは
実際、物事を成し遂げるのには、多大に難しいと言っていることが上げられます。
でも、それは、大変だかもしれないですが、出来ないことではないのです。
困難極めることになるのが、半ば、神経質の人の定めだにしても、それは、叙述、述べてきた理由の所以です。ですので、突破できないことはないのです。
私は、この辺のことを漫画のプロセスで言っているので。
でも、これのことを、表向き「なるほど、そうか!」とやったのでは
叶えられないのです。
もうでも、そのことはお分かりと思います。
それは、そのものが所信だからです。
あの、失われし自己を求めての著者もそのことを言っています。
60年、70年代にはいい本があった。
でも、今回の内容のことを、心理学や哲学の素養のない方たちに、言っても
無駄です。この意見は、バカにしているという意味ではないことは力説しておきます。
内的力とかひとえに言うのですけど、
こうしたプロセスを通る人たちばかりではないからです。
このブログを見に来てくださる人たちが、80名か(控えめに)おりますが、
その人達、皆さんは、ご存じのはずであるだろうからです。
私は出来れば、心理学者の立場を借りてまたは、禅や、哲学の立場から、飯田かったのですし、
それに過ぎないことだとも言えるからです。
こうした途を通ることなく、成人する人もいますし、それはそれで佳いのです。
このことは肝に銘じておく必要があるでしょう。
だから、「気をつけないといけない」」のです。
次回からは、禅のこうした悟りについて、実際の方法について述べていこうと考えても
います。
それには、河原先生だったら、まず、自分が実践(つまり、結果の出ること)してみててからというに違い在りません。
河原先生といいますのは、それだけの気概をお持ちの方だったのです。
ですので、「描き方? そんなものはね、自分ですること!」と喝破されたのですし
それには、誰も異論をはさめる者はおりません。