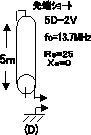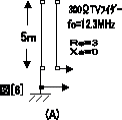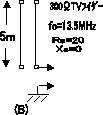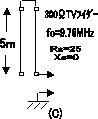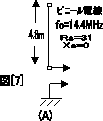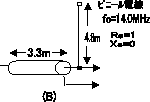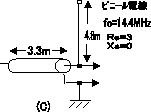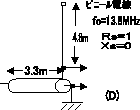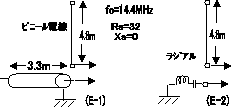No3
図5
図5(C)、(D)は同軸ケーブルの先端をショートしてそくいていしたものです。
図5(C)の接続では19.2MHzで給電部インピーダンスが最小になり(A)の約2倍の周波数になり先端ショートで長さ5mの同軸ケーブルの共振周波数を測定していることになります、当然アンテナとしての動作は期待できません。
(D)はシールドと接地間を給電点としたもので図5(A)とほぼ同じ結果です、同軸ケーブルの芯線はほとんど影響はないようです、アンテナとしては良好です。
この結果アンテナとしての動作が確認できたのは図5(B)と図5(D)でどちらも同軸ケーブルとは関係なく単なる短縮率が0.91程度の導体としての働きでした。
図6(A)〜(D)300ΩTVフィダーで同様に測定してみました、
図6(A)は1/4λの共振周波数の測定とおなじです、図6(B)、(C),(D)ともアンテナとして動作良好です、図6(C)は先端短絡でエレメント長が長くなるため共振周波数は低下しています、面白いのは図6(D)の接続で給電点インピーダンスは110Ωとかなり高くなっています、これはちょうどホールデットダイポールアンテナの半分として動作していることになります。
図7はラジアルエレメントとしての動作を確認するための測定です。
図7(A)は比較するための基準の接地型アンテナでアンテナエレメント長さが4.8mで共振周波数は約14.4MHz付近になります、給電点インピーダンスは30Ω前後であればラジアルとしての動作は良好と判断します。
ラジアルエレメントは5D−2V、K=0.63で3.3mです
図7(B)はアンテナエレメントは接続されていますがよく見ると給電点と並列に3.3m長さの同軸ケーブルが接続されておりアンテナエレメントを外すと同軸ケーブルの共振周波数を測定している事と同じで給電点をショートしている事になります。図7(C)も給電点の片側が接地されていますが図7(B)と同じです。図7(D)も給電点の接地側が異なるだけでこれも図7(B)と同じことがわかります。
図7(E−1)は1/4λに共振した同軸ケーブルで接地していますが書き直すと図7(E−2)のようになり直列共振回路を通して接地しています、図7(A)とほぼ同じ結果ですが余分なものを通して接地しているためRsが少し高くなりました。ラジアルエレメントとした同軸ケーブルは単なる共振回路としての動作になります。