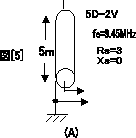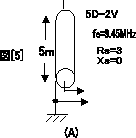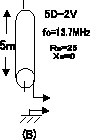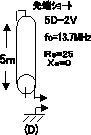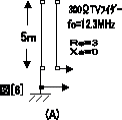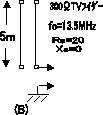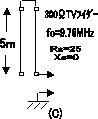嘇傾儞僥僫僄儗儊儞僩偲偟偰偺應掕
恾5偼愙抧宆傾儞僥僫偲偟偰偺摦嶌忬懺傪挷傋偰傒傑偡丅
5俢-2倁偲斾妑梡偺300兌俿倁僼傿僟乕丄價僯乕儖揹慄偺3庬椶偱挿偝偼傒傫側5倣偱偡丅巊梡偟偨5俢-2倁摨幉働乕僽儖偺5倣偺嫟怳廃攇悢偼9.45俵俫倸偱抁弅棪偼俲亖0.63偵側傝傑偟偨丅
恾俆乮倎乯偼摨幉働乕僽儖偺奜懁摫懱傪愙抧偟拞怱摫懱傪傾儞僥僫僄儗儊儞僩偲尒棫偰偰偄傑偡丅
應掕寢壥偼俼倱亖0丆倃倱亖0偱偡丄偙傟偼愭抂奐曻偺1/4兩摨幉働乕僽儖偲摨偠忬懺偱偡丅俼倃偵愙懕偟偰傕壗傕庴怣弌棃偢傾儞僥僫偲偟偰偺摦嶌偼婜懸偱偒傑偣傫丅
恾俆乮俛乯偼奜懁摫懱傪僄儗儊儞僩偵傒偨偰偨傕偺偱偡丅
應掕寢壥偼嫟怳廃攇悢偑曄壔偟俥倧亖13.7俵俫倸偵忋偑傝俼倱亖25兌丄倃倱亖0偵側傝愙抧宆傾儞僥僫偲偟偰偼懨摉側抣偱偡丅偙偺帪拞怱摫懱傪奜懁摫懱偵愙懕偟偰傕愙抧偟偰傕傎偲傫偳曄壔偼偁傝傑偣傫丄俼倃偵愙懕偡傞偲廫暘怣崋偑庴怣偱偒傑偡丅偙偺寢壥摨幉働乕僽儖偼拞偵暔偑媗傑偭偨抁弅棪亖0.92偺懢偄僄儗儊儞僩偲偟偰摦嶌偟偰偄傞帠偵側傝傑偡丅
恾俆乮俠乯偼愭抂抁棈偟偨1/4兩摨幉働乕僽儖偱摨恾乮俙乯偲摨偠愙懕偱偡丄廃攇悢9.45俵俫倸偱偼俼俽偑戝偒偡偓應掕晄壜擻偱偡丅廃攇悢傪曄壔偝偣傞偲傎傏擇攞偺廃攇悢19.2俵俫倸偱俼倱亖俁丄倃倱亖0偵側傝傑偟偨丅1/2兩偱嫟怳偟偰偄傑偡丅
恾俆乮俢乯偼摨恾乮俛乯偲摨偠愙懕偱應掕寢壥傕傎傏摨偠偱偟偨丅
埲忋傛傝摨幉働乕僽儖傪傾儞僥僫僄儗儊儞僩偵偡傞応崌偼奜懁摫懱偑巟攝揑偱拞怱摫懱偺塭嬁偼傎偲傫偳側偔抁弅棪偼摨幉働乕僽儖杮棃偺俲亖0.63偼揔梡偱偒偢俲亖0.92掱搙偺晛捠偺揹慄偵側偭偰偟傑偄傑偡丅
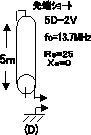
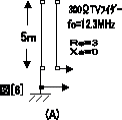
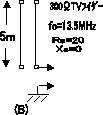
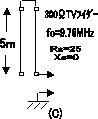

恾俇偼斾妑嶲峫偺偨傔偵摨條側應掕傪偟偰傒傑偟偨
恾俇乮俙乯偼300兌俿倁僼傿僟乕偱挿偝俆倣偱偼嫟怳廃攇悢偺應掕偲摨偠偱廃攇悢偼俥倧亖12.3俵俫倸抁弅棪俲亖0.82偲側傝丄俼倱亖3丆倃倱亖0偲傎傏抁棈忬懺偱偡丅俼倃偵愙懕偟偰傕傎偲傫偳庴怣偱偒傑偣傫丅恾俇乮俛乯偼俼倱亖20兌丄倃倱亖0偱庴怣傕偱偒傑偡丄僼傿僟乕偺曅懁偑傾儞僥僫僄儗儊儞僩偲偟偰摦嶌偟偰偄傑偡丅
恾俇乮俠乯偼廃攇悢偑掅壓偟偰偄傑偡偑俼倱丆倃倱嫟惓忢抣偱愭抂傪抁棈偟偨偨傔僄儗儊儞僩挿偝偑挿偔側偭偨偨傔偲峫偊傜傟傑偡丅庴怣壜擻偱偡丅
恾俇乮俢乯偼俼倱亖110兌偲崅偔側傝傑偟偨偑嫟怳廃攇悢偼摨恾乮俛乯偲傎傏摨偠偱僼僅乕儖僨僢僪僟僀億乕儖傾儞僥僫乮200兌乯偺偪傚偆偳敿暘偱摦嶌偟偰偄傞偲峫偊傜傟傑偡丅