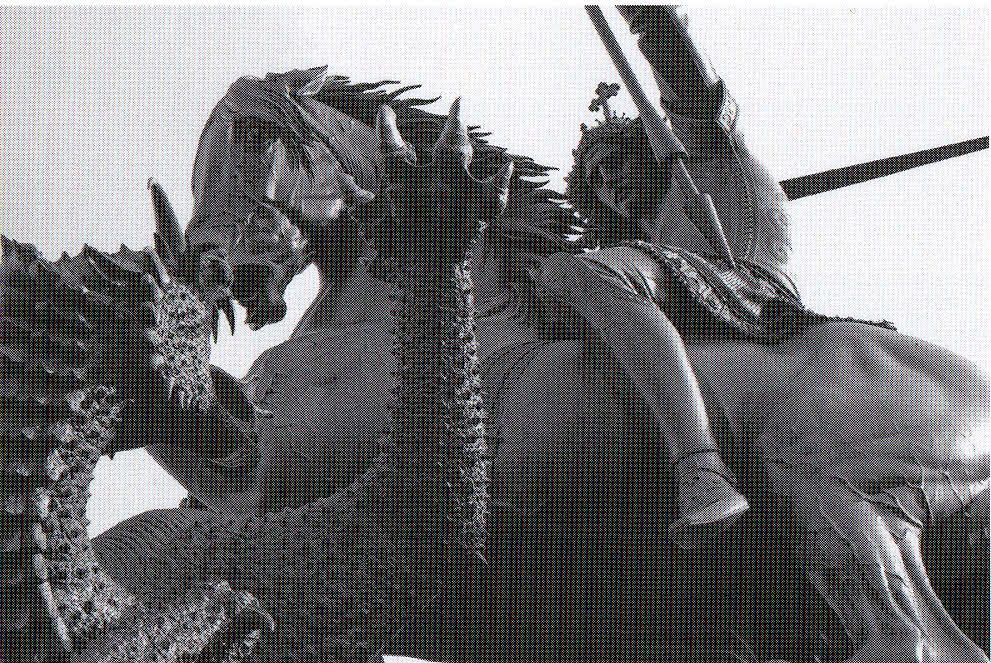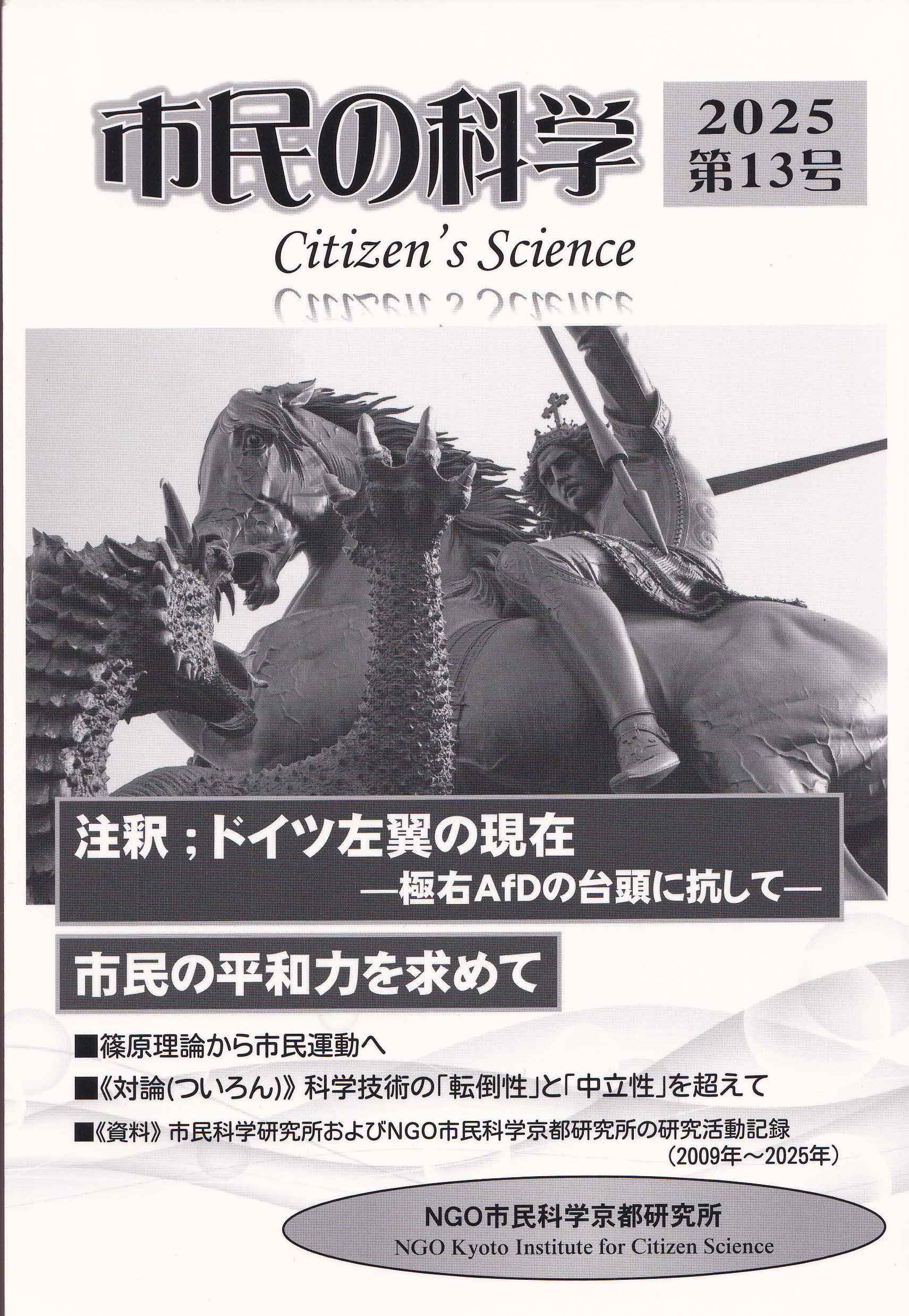|
市民の科学第13号 2025年11月
目 次
終刊にあたって(中村共一)
新たな取り組みに向けて――「市民のための科学をめざす」について――(重本直利)
《特集I》市民の平和力を求めて
特集Iにあたって(中村共一) 7
市民の平和力とは何か――実践としての「永遠平和」――(中村共一) 10
非武装永世中立と市民の平和力(重本直利) 33
銃のない世界―銃器の使用価値という視点から――(宮崎昭) 63
コロナ禍の緊急事態宣言と市民の平和力――平和力の源泉は地域社会にある――(三宅正伸) 75
【声明文】「ガザ地区」への大規模攻撃・殺戮を非難する(市民科学京都研究所、2023・10・27) 94
《特集Ⅱ》篠原理論から市民運動へ
特集Ⅱにあたって(宮崎昭) 95
〔絶筆〕『反哲学入門』と交換様式論――Tさんヘ――(篠原三郎) 96
〔遺稿〕「希望」としての「交換様式」論――Tさんヘ――(篠原三郎) 101
「ベッドより」を拝読して――死と向き合われた最期の短歌――(眞島正臣) 104
生産力理論、管理の二重性論争、そして交換様式論ヘ――篠原三郎〈遺稿〉「『希望』としての『交換様式』論」に寄せて――(重本直利) 112
篠原三郎さんは「アソシエ―ショニズムの科学」を提起する(中村共一) 122
篠原さんが考え残したこと(前編)――柄谷行人との出会い――(宮崎昭) 136
篠原さんが考え残したこと(後編)――木田元『反哲学入門』に挑む――(宮崎昭) 148
《コラム》土に生きる――農作業二題――(中川在代) 158
《特集Ⅲ》注釈一ドイツ左翼の現在――極右AfDの台頭に抗して――
特集Ⅲにあたって(照井日出喜) 161
第1部注釈:ザ―ラ・ヴァ―ゲンクネヒト(照井日出喜) 163
《論評}ザ―ラ・ヴァ―ゲンクネヒトという「左翼のあり方」(重本冬水) 177
第2部注釈:オスカ―・ラフォンテ―ヌ(照井日出喜) 188
《論評》流れのままに漂うのは、死んだ魚のみ(重本冬水) 209
第3部注釈:グレゴ―ル・ギジ(照井日出喜) 216
《論評》グレゴ―ル・ギジの「左翼の挑戦」(中村共一) 233
あとがき(照井日出喜) 246
《対論(ついろん)》科学技術の「転倒性」と「中立性」を超えて
対論にあたって(青水司十重本直利) 256
「原子力技術と自然・人間の転倒性」と資本・国家の支配――幻想としての原子力平和利用――(青水司) 258
社会に対する科学者の科学的責任(SSRS)――「科学の価値中立性」批判と責任倫理――(重本直利) 289
「法人犯罪」への問い――JOC事故の判決文より――(重本直利) 312
【声明文】東電福島第一原発のトリチウム汚染水の海洋放出に反対し、撤回を求める(市民科学京都研究所、2023・8・22) 317
《資料》市民科学研究所およびNGo市民科学京都研究所の研究活動記録(2009年~2025年)
編集後記 執筆者紹介
|