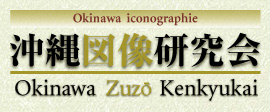【日時】2009年2月1日(日)
沖縄図像研究会では鍛冶神図像とその祭祀風習に関する久々のフィールド調査を行いました。
【調査地】
①沖縄市、知念さん宅→②糸満市、大城さん宅→③佐敷、知念さん宅→④佐敷、大城正榮さん宅
【概要】
鍛冶屋の末裔、佐敷の大城正榮さんの調査ですでに鍛冶神図像の存在が確認されていた上記四件の元・現鍛冶職のお宅を訪問し、鍛冶神図像を実見するとともに、聞き取り調査を行ないました。OZKのフィールド調査としては、従来ほぼ未開拓であった南部での図像状況が複数件確認できた点がひとつの進展です。
今回実見した四件の鍛冶神図像は、北部で確認された「沖縄の鍛冶神図像」の定型と、構図および描かれた内容の点で共通するものですが、描法・技術・図像要素など細部には多様なバリエーションも認められます。とくに中心となる鞴の神が、三面六臂の「三宝荒神」の形態を基本としながら、男性神(①)、女性神(③)、観音菩薩風(②)、中性的(④)と多様な姿をとる点は注目されます。構図では、②に一部左右の反転が見られますが、中央またはやや上方に鞴の神、その下方に箱鞴と箱差しの女性、それらの手前に横座の男性と前打ちの鬼たちと、細部にいたるまで定型・類型性を保っています。
聞き取りから、この四件のお宅では戦後すぐ、または数年後の時期に、専門の画家に依頼して「鞴の神」の画を描いてもらったことが判明しました。彩色は鮮やかで保存状況も比較的良好ですが、残念ながら②は上半分に絹の断裂欠損など痛みが激しく、早期に適切な修復・保存処理をすることが望ましい状態でした。このため同家族内では処分したほうがいいのではという話も出ており、実際、同家にあった「千手観音」の画は、すでに首里観音堂で処分されたとのことでした。今回の四件のお宅では、親や兄の代まで鍛冶職だったことから風習祭祀を維持継続していますが、今後世代が改まるにつれ、図像・風習の消失の危険性が高まることが予想され、できるだけ早いうちに調査をすすめておく必要性を感じました。
「フーチヌ神(鞴の神)」の配置場所は、仏間の仏壇最右の龕(①③)または床の間(②④)です。すべて額装で、サイズは縦40〜50cm前後、横20〜35cm前後と比較的小幅です。
〈祭祀について〉
鞴祭(フーチユヌユーエー)はいずれも旧暦11月7日に行なわれました。その際には、豚のチラガー(顔の皮)(①)もしくは重箱に詰めた三枚肉(②)、鶏(羽を拡げて立たせ、嘴に葉を銜えさせる)(①②)などを供物としました。また、なかには翌8日に金床の祭(カナカノユーエー)を行ない(①)、数年毎に始祖と伝わる奥間カンジャーを訪ねる今帰仁廻り(①③)や、勝連ウマーイ(廻り)(①)、東ウマーイ(③)を行なう風習もありました。系譜を辿ると、一族内で鍛冶職を始めた頃は、いずれもおよそ明治初期くらいに溯るものと推察されます。当時、職を失った士族が手に職(技術)をつけて地方に下ったことと何らかの関係があるかもしれません。
より詳細な報告はまた何らかの形でまとめたいと思います。

①知念さん宅(沖縄市)
・作者:柳光観(日本画家)
・製作年:1969年
・サイズ:46.2×24.8(縦cm×横cm)
*額の内寸(本紙サイズは計測なし)
・記銘:「一九六九年酉歳旧 月 日
画号 柳光観、謹画」(額背面左下隅)
・素材技法:絹本着色(金・銀色も使用)

②大城さん宅(糸満)
・作者:不明(日本画家)
*首里の北森(ニシムイ)で活躍の画家か?
・製作年:1951年
・サイズ:38.0×22.8
・記銘:「 卯
西厂一九五一年旧十一月七日建立」
(額背面右側に朱書)
*横に小さく「御生レ日ウードシ年旧十一月七日」と 鉛筆書きあり。
・素材技法:絹本着色

③知念さん宅(佐敷新開)
・作者:福田さん(近所の看板屋さん)
・製作年:1980年頃(家屋の新築時)
・サイズ:50.2×35.0
・記銘:不明(裏面確認せず)
・素材技法:紙本着色(水彩?)

④大城正榮さん宅(佐敷津波古)
(本HP鍛冶神図像の21番)
・作者:那覇の絵師
・製作年:昭和21年(1946年)*戦後すぐ
・サイズ:38.0×22.3
・記銘:なし
・素材技法:絹本着色
copyright (c) 2009 沖縄図像研究会 All Rights Reserved.