


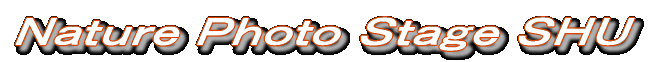
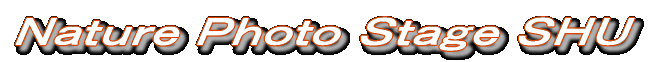
ネイチャーフォト・ステージ 秀
新世代大型赤道儀


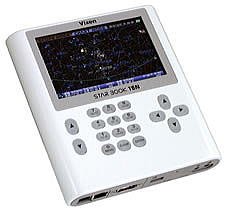
AXD赤道儀メーカー希望小売価格 ¥ 1,029,000 (税抜 ¥ 980,000) |
|
| ●AXD-TR102三脚 | メーカー希望小売価格 ¥ 168,000 |
| ●AXD用ハーフピラー | メーカー希望小売価格 ¥ 58,800 |
| ●ピラー脚 AXD-P85 | メーカー希望小売価格 ¥ 77,700 |
| ●AXDウェイト 1.5kg | メーカー希望小売価格 ¥ 6,300 |
| ●AXDウェイト 3.5kg | メーカー希望小売価格 ¥ 12,600 |
| ●AXDウェイト 7kg | メーカー希望小売価格 ¥ 16,800 |
| ●AXDマルチプレート | メーカー希望小売価格 ¥ 34,650 |
|
※特価は後日記載します。
※発売時期は10月末~11月頃?になると思われます。
|
|
| 問い合わせご注文はこちらからお願いします。 | |



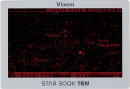
|

ネイチャーフォト・ステージ秀