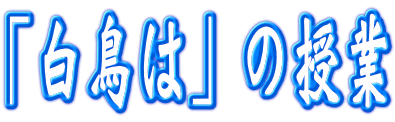
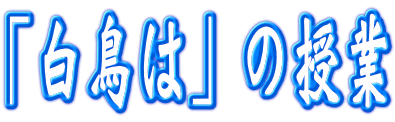

| 若山牧水 | ||||
|
| 主な発問と指示 | 留意点 |
| 1 それぞれ音読する。 「それぞれ,3回読みなさい。分からない言葉,読めない文字はとばしてかまいません。」 |
○ 音読は自由にさせます。間違った読みも認めます。読めない文字などはとばしてよいと指示をします。白鳥(はくちょう)も認めますが,すぐ(しらとり)に訂正します。 ○ 自分が読めない文字をきちんと認識させることが大切です。そして,それは恥ずかしいことではなく,分からないことを学んでいくことが勉強なのだということを学級の共通理解にしておきます。 |
| 2 分からないことばや難しいと思ったことを書き出す。 「分からない言葉や難しいと思ったことをプリントに書きなさい。 「分からない言葉を発表しなさい。」 3 分からない言葉の説明をする。 |
○ まず,分からない言葉を整理して,意味が分かるようにします。児童の全く知らない言葉は,教えますが,漢字や同じような意味の言葉などを連想させて,できるだけ,自分たちの力で,意味も調べます。 ○ 4年生以上では,国語辞典は必須です。国語の時間は,辞書を片手に授業するぐらいの気持ちで取り組みます。 ○ 物語文などの授業では,意味調べの時間を必ずとり,時間が不足するときには,必ず宅習等で調べさせるようにします。 ○ ここでは, ・かなしからずや ・あを ・ただよう が予想されます。 |
| 4 音読をする。 個人で読んだ後に,指名読みをします。何人か読んでもらうとよいでしょう。 「自分が読み取った内容を表現して,自分なりに読みなさい。声をそろえる必要はありません。」 「自分に今できる最高の読みをしなさい。」 |
○ ここでは,正確に読めるかを耳を澄ませて聞いています。たくさんの児童の声でも,聞きたいと思う児童の声を聞く耳を持つ力量を身に付けたいものです。特に気になる子どもの声は意識して聞くようにします。 ○ 指名読みでは,子どもの意欲も尊重します。しかし,教師の意図も生かします。ただ,並んでいる席の順番に読ませるだけでなく, ・読み取る力のある児童が,どれだけ内容を理解した読みをするか。 ・読み取りの苦手な児童が,どの程度読むか。 ・どの児童を指導することで,他の子どもの読みを一歩深めることができるか。 などの,教師のねらいや意図によって,指名読みさせる児童を決めたりします。 音読ひとつでも,形式的に流さないことが大事です。 |
| 5 内容を読み取っていく。 ① 「白鳥」からイメージできるものを発表してください。 ②「空の様子」や「天気」「海」などの情景を発表してください。 ※ 「一羽の鳥」か「たくさん」かを話し合っておくことが大事です。 ※ 雲があるかどうかも話し合っておきます。 |
○ 「しろいとり」から児童の想像力を広げます。「白」という漢字や,イメージも大切にします。ただ,想像を広げさせるのではなく,教師がねらいとするものを見失わないように気をつけます。ほっておくと,どこまでも想像が広がってしまいます。 ・ただ一羽の鳥 ・たくさんの鳥が飛んでいる。 ・青い海や空を背景に,一点の鳥がきわだつ ・真っ白い美しさ ・真っ青な空 ・いい天気である。 ○ 一羽の鳥の手がかりは, ・かなしからずや ・ただよう ○ 雲について話し合うことで,「一点の白」と「青」と「あを」の単純化された世界をイメージさせます。 |
| 6 音読を入れます。 自分の読み取ったイメージを表現する読みです。 子どもの表現に,的確に指導を入れます。子どもと一緒に読みを作っていく作業です。 |
○ 「なぜそう読んだか」,「その思いが伝わったか」を児童にといかけながら,表現力を高めていきます。教師の聞く力が求められます。的確に指示したり,ほめたりします。 ○ 子どもを追い込むことは,決して悪いことではありません。いい読みができたり,他の子どもたちからほめられると,子どもは本当によい顔をします。 形式的に「よかったです」とか,「じょうずでした」「拍手をしましょう」なんて言葉でごまかさないことです。何回も練習して,いい読みが生まれたとき,子どもは自然と拍手をします。そして,読んだ子どもは,表現する喜びを味わいます。 |
| 7 さらに深い読み取りに挑みます ① 「染まず」と「染まらず」ではどう違いますか。 ※ 「ら」があるのとないのでは,どこが違いま すか。 ※ 「染まらないぞ」と思っているのはだれですか。 第2,第3の矢までは準備しておきましょう。 ② そういう白鳥を,みなさんはどう思いますか。 ③ 牧水はどう思ったのですか。 |
○ 大変難しいところへの挑戦です。「「染まず」とはどいうことですか。」とか「「染まず」とはどんな感じですか。」といった曖昧な発問よりも,私は,比較させる方が子どもたちは考えやすいと思います。この発問のねらいは,「染まず」には,自らの意志が感じられることに気づかせることです。「染まらず」でもその意志は感じられますが,「染まず」の方が,主体的です。 こういう問題を学級の知恵を出し合って乗り越えると,次へ急激に発展していきます。じっくり考えさせましょう。 ○ 白鳥が,空にも海の美しさにも自らの意志で染まらないことの確認です。 ・絶対染まらないぞと思っているんだ。 ・強い意志があるんだ。 ・何で美しいものに染まらないのかな。 といった意見が出てくるとよいですね。絶対「かなしい」とは言わないはずです。 ○ 牧水は,「かなし」と言ってることに,気づかせます。子どもにとっては,意外な展開なはずです。ここまで,くると謎解きです。 どんな美しさにも染まらないとよい意志を持った白鳥が,なぜ「かなし」なのか。 |
| 8 核心に迫る読み取り ① なぜ,牧水は美しいものに染まらない白鳥がかなしいと思ったのですか。 9 表現読みをする。 |
○ 子どもたちは,大いに悩み,苦しみます。知恵を出し合います。そして,そこに自分と重ねて白鳥を見つめている牧水の姿を発見したとき,子どもたちは短歌のすばらしさ,日本語のすばらしさを感じ取ります。「哀し」「悲し」「愛し」という意味が,ここで生きてきます。「りっぱだ」「美しい」という意味も加えてやります。自らと白鳥を重ね合わせている牧水の姿が見えれば,いいのです。教師が補足してやってもいいですし,読みの深さの度合いに個人差があってもいい。 間違えた答えなんてありません。みんなで知恵を出し合うのです。発言しない子どももしっかり考えます。そして,友達の意見に納得したり,反発したりして自分の考えを明確にしていきます。それが,学校で,みんなで一斉に授業する意味です。そして,学級の子どもたちに力がついてくれば,自らの力で「短歌の世界」を味わい謎解きを楽しむようになってきます。「子どもに学力をつける」というのは,そういうことだと私は思います。 |