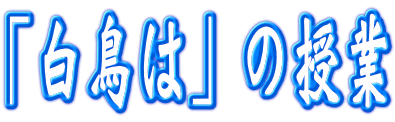
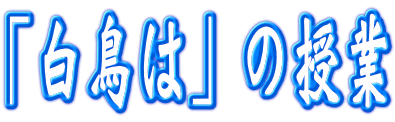

| 若山牧水 |
| 教材研究を深める | 授業の流れ | 児童の反応 | 国語のメインページ |
| 1 教材研究を深める |
| 「白鳥」 |
| 「白鳥は」と「白鳥が」ではどう違うか。「白鳥が」よりも「白鳥は」は自分に近い印象を受ける。白鳥を自分から突き放して,客観的に眺めているのではなく,白鳥を自分の中に置いて,自分の姿と重ねながら,歌っていると考える。 「しらとり」と読む。「はくちょう」とは読まない。名もない白い鳥と考える方がよい。白い色は,潔癖である。青い空や海を背景に,くっきりとした美しさを見せている。私は,一羽と読む。 |
| 「かなしからずや」 |
| 「かなし」は,漢字では,「美し」(美しい),「愛し」(いとおしい,かわいい),哀し(共感する,愛する,せつない),悲し(絶望的な気持ち)が考えられる。 「かなしい」は,辞書的には,①心がひどく痛んで泣きたくなるような思いがする。また、そのように思わせるさま。②情けなくて残念な思いだ。また、そのように思わせるさま。 「や」は,感動を表す「や」と考える。 「かなしからずや」は,「ああ,かなしくないのか。ああ,きっとかなしいことだなあ。」という意味。 |
| 「空の青」「海のあを」 |
| 空は大きい。広い。雲ひとつない澄んだ美しい青空が広がっている。海も広く大きく,全てを包み込む大きさを持っている。 「海のあを」は,空とは違うあおい色である。ひらがなで書くことで,さまざまな「あお」が想像できる。「藍」「碧」「蒼」「青」(濃いあお,深いあお,暗いあお)が考えられる。 それぞれに美しいあおだが,ひらがなで書くことですべてのあおを含ませる。すべてのあおをイメージさせる。 |
| 「にも」 |
| 「にも」は,「空の美しさにも海の美しさにも染まらない。」という意味である。他のどんなあおにも,また,どんな美しさにも染まらないという意味である。「も」には,「絶対染まらないぞ」という強い意志が感じられる。 |
| 染まず |
| 「染まず」は,「染まらず」とは違う。「染まらず」よりも,「染まず」には,作者の強い意志が感じられる。「染められる」のではなく,自ら「染まらない」と主張している。「たとえ,どんなに大きく美しい空であっても,どんなに深い海でも,染まらないぞ」という意志を感じさせる。「白」は,どんな色にでも染まる色である。だからこそ,染まらないためには,強い意志が求められるのである。 |
| ただよう |
| 「ただよう」は,漢字では,「漂う」。「漂流」などが連想される。目的もなくさまよっている感じを受ける。ゆらゆらふらふらしている。水面と空中に浮かんで揺れ動いている感じである。波や風に揺れ動いている,弱さを感じさせる。 |
2 私の読み |
| 白鳥はかなしくないのだろうか。いやきっとかなしいことだろう。あんなに美しい空や海にも染まろうとすることもなく,ひとりぼっちで,真っ白いままで空と海の間をただよい続けている。 そんな白鳥が,私はいとおしい。その姿は美しいと私は思う。白鳥よ,どんなに自然が大きく美しくとも,その中で,くっきりと自分の姿を写して漂いながらも飛び続けてほしい。 白鳥よ。その姿は,どんな芸術の色にも染まることなく,ひたすら自分の短歌の世界をつくろうと悩み苦しんでる私の姿だ。 |
| 牧水は,一人砂浜で,海に向かって立っています。創作に悩み,一人散歩にでも出てきたのでしょうか。それとも,旅の途中でしょうか。空は,快晴です。雲ひとつありません。海は,その青さを吸い込むように,深くあおく穏やかに広がっています。 一羽の真っ白な鳥が,そのあおさの中を漂っています。それは,真一文字に空を切り裂くような力強い飛び方ではありません。おだやかに,海に遊び,空に遊びしながらのんびりとしています。しかし,その真っ白な姿は,決してあおい海にも空にも,とけ込むことはありません。空や海の美しい自然の中にあって一点の際だつような美しさを持っているのです。 |
3 若山牧水 |
| 若山牧水は,宮崎県の東郷町で生まれました。 牧水については,東郷町のホームページにアクセスすると詳しいです。 |