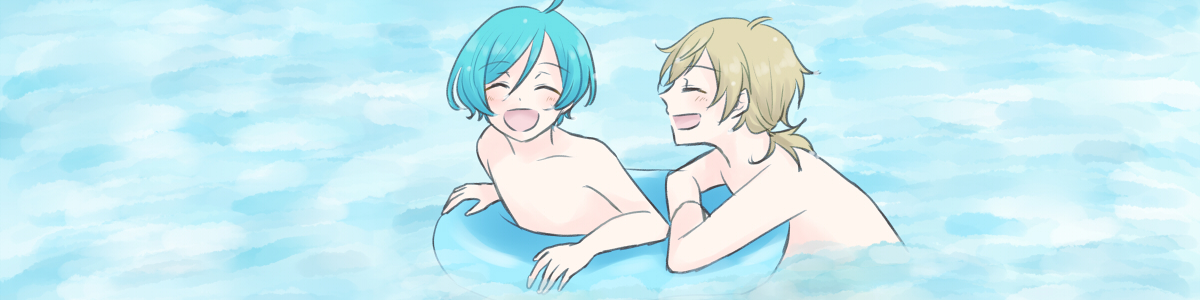永遠の唄
第15話
「おはよう、理緒」
「あ、ちゃん!待ってたよー!」
理緒が自分の胸を爆破して、早3週間。彼女が病院に入院している間、は相変わらず学校を休んで歌手活動をしたり、毎日見舞いに、歩たちと鉢合わせしないよう授業中に来たりしていた。
肋骨が砕けているはずなのに、当の本人は至って元気にしている。その暢気な様子には呆れ、しかし安心した。
「…ねぇ、メロンはぁー?」
「昨日あげたじゃない。毎日持ってくるのは無理だって、何回も言ってるでしょ?それに、自分から入院したようなものなんだから少しは我慢して」
「はうー、メロンー…」
のお叱りに理緒はしゅんとうなだれる。すると、病室の扉が開き、メロンを手に持った香介がやってきた。
「ほらよ」
「うわー、編目もようのメロンだーv」
「ラザフォードからだよ」
「はうぅ~、アイズ君はやさしいな~」
彼からそのメロンを受け取ると、これ以上にないというほど幸せそうに目を輝かせ、メロンに頬擦りまでした。その様子にそんなにメロンが好きなのかとと香介は呆れ、目を合わせて苦笑する。
「よかったね、理緒」
「うんっ!ほら、こーすけ君、切って切って」
「……………」
明らかに嫌そうな顔をする香介。しかし、ぶつぶつと文句を言いながらもきちんとメロンを切り始める。何だかんだ言って結局切ってやっている彼に、優しいのか情けないのかとは眉を下げて微笑んだ。
ちゃんも一緒に食べようよと理緒に誘われ、もメロンを一切れ貰い、かじりつく。口に広がるメロンの瑞々しさと甘さに、自然と頬が緩んだ。
「…理緒」
メロンを頬張る彼女達を見ながら、香介が声をかける。何だろうかと思い、は目線だけをそちらに向けて、メロンを食べ続けた。
「こっからどうやって鳴海弟を倒す気だ?」
「あ!気がついたんだ。こーすけ君も賢くなったね」
その言葉に香介は理緒から目を逸らす。この様子だと恐らくアイズに指摘されたのだろう。無理もないかもしれないとは思った。
も初めはただ逃げるためだけに危険を冒して肋骨を砕いたのだと思っていた。しかし、それは逆に自分が犯人だと自ら言っているようなものだ。それに理緒の性格を考えると、ただ逃げるだけだなんてことはしないだろう。そのことに気が付いたは思考を巡らせ、そしてこの結論に至った。
理緒は歩を正面から倒すためにこのような綱渡りをしたのだ。だから、まだこの戦いは終わってなどいない。いや、むしろこれからが本当の勝負だと言えるのだ。
「とりあえず必要なものがあるんだけど、頼まれてくれる?」
理緒と香介の会話を聞きながら、メロンを口に含み、は小さく溜息を吐いた。…自分もいつまでも逃げていないで、勝負するべきなのかもしれない、と。
数日後、理緒をブレード・チルドレンだと見抜いて彼女の病室に来た歩たちと勝負をしたと、香介からに連絡が来た。その勝負に勝ったのは理緒たち。しかし、ひよのの思わぬ行動により、4人は再戦をすることになったらしい。話を聞いただけではあるが、それでもひよのの大胆で度胸のある行動には十分驚いた。彼女は本当に何者だろうかと思わず疑ってしまう程に。
また連絡するまで病院に行くのは避けておいてほしいと香介に言われ、は了承した。もし今病院で歩たちに出くわしてしまえば、も共犯だということが知られてしまうからだ。それを隠すために姿を消しているのに、ここで見つかってしまってはまるで意味がない。理緒のことが心配ではあったが、しかし、我慢するしかなかった。
そしてその2日後、今度は歩たちが勝利したと伝えられた。その戦いによって理緒の傷口が開いてしまったとも知らされ、心配すると同時に無茶した彼女を叱ってやらなければとも思った。しかし、全員無事であったことに対する安堵は隠せない。また歩の成長ぶりに驚き、感心し、嬉しく思った。
明日からまた学校に行くことができる。理緒の見舞いには、次の休みに歩たちに見つからないように行こうか。そう思っていると、夕方、の家で電話が鳴り響いた。誰からだろうかと疑問に思いながら、手にとって通話ボタンを押し、耳に当てた。
「はい、です」
『やあ、久しぶりだね。元気にしてたかい?』
「え…?」
聞き覚えのある、しかし久しく聞いていなかったその陽気な声に、は驚愕した。
「カノン…?」
『当たりだよ。久しぶりだね』
「うん…、どうしたの…?」
以前の彼との会話を思い出し、嫌な予感がして、は表情を固くさせる。しかし、それと裏腹にカノンは相変わらず穏やかな口調で話した。
『もうすぐそっちに行くから伝えておこうと思って』
「こっちに来るって、まさか…」
『うん、君たちを…ブレード・チルドレンを、抹殺する』
穏やかに、しかし冷たく言い放たれた言葉に、は目を見開いて驚き、受話器を落としそうになった。
嫌な予感が的中してしまったのだ。前から彼はブレード・チルドレンはいないほうがいいと言っていた。それをアイズと必死に止めようとし、清隆にも説得を頼んでいた。それなのに、彼のその意志は今も何も変わっていない。いや、むしろ強くなっている気がする。
信じられない。そう思って声を震わす。
「そん、な…、嘘でしょ…?」
『嘘じゃないよ。勿論…君やアイズも、この手で殺す』
「っ!!」
『…それじゃあ、また日本で』
「ま、待って!!」
電話を切ろうとするカノンをは思わず止めた。しかし頭は真っ白で、後の言葉がまるで出てこない。言葉を詰まらせているとしばらくして電話は切れ、は受話器を抱えてその場にずるずると座り込み、うずくまった。
「そんな、どうして、カノン…」
はアイズや香介や理緒、それからカノンとは全員幼馴染みだ。しかしそのの幼馴染みの中でも、アイズとカノンは特に特別な存在だった。幼い頃はいつだって一緒にいて、色々なことをした、かけがえのない親友。それなのに、どうして…。
は長い間、そのままの状態でいた。あまりにも悲しすぎたからだろうか、不思議と涙は溢れてこなかった。
アイズは今頃どうしているのだろう。もしかしたら、彼のほうがショックを受けているかもしれない。しかし、今連絡しても何も変わらない。意味がない。
彼を止めることはできないのだろうかと、は一人頭を抱えた。
2009.07.05