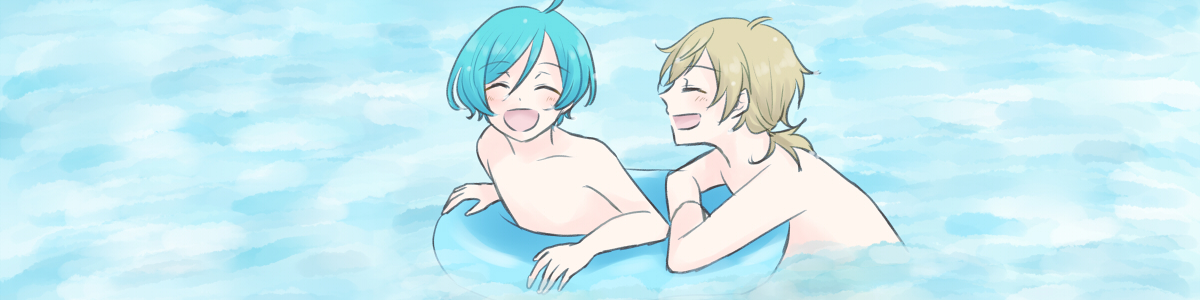永遠の唄
第14話
「清隆様の弟さん、見事なもんだよ。瞬間的に正確な犯人像を描き出して網をかけるんだもん、すごいすごい」
翌日、と理緒、そして香介の3人は、公園でクレープを食べながら今後について話をしていた。理緒が学校での歩の様子を嬉しそうに話す。
「たいした観察力と推理力ってとこか?」
「あれはそれだけじゃない、一種の超能力だよ」
「さすが清隆の弟、ね」
彼の能力には清隆のそれ同様、毎回驚かされるものだ。クレープを食べながらは感嘆の息を零した。
「鳴海弟を挑発するみたいに学園内で殺すからそうなるんだぜ」
「仕方ないじゃない、急なことだったんだから」
「それに…、こんなに素早く攻めてくるとは思ってなかったから」
と理緒の固い表情を見て、香介は溜息を吐く。
「そう怖い顔するなよ。そりゃあの嬢ちゃんの情報能力はすごいが…、でも容疑者をどうにか10人程度に絞れるくらいさ。あとは手詰まり打つ手なし。俺らを捕まえられるもんかよ。ムダなあがきさ」
「こーすけ君のばーか」
理緒の呆れたような声に香介はきょとんとした。この様子だと本当に気付いていないらしい。
「鳴海君はそんなに甘くないよ。彼には私たちを捕まえる術がある」
「そう、あたし達はブレード・チルドレンなんだよ?肋骨が一本ないっていうごまかしのきかない烙印があるじゃない。胸の辺りを触られたら一発でバレちゃうよ」
だからこそ、が彼らから逃げる必要があったのだ。念のためと調べられて肋骨がないことが知られたらおしまいだ。は自分の欠けた肋骨辺りに手を添える。これだけはどうやってもごまかすことなどできはしない。
「……しまった!!鳴海弟、肋骨のこと知ってやがったか!!」
「知ってるからこそわずかな痕跡を足がかりにしようとしたんだよ」
それだけの情報が集まれば、犯人探しなど苦ではないのだから。
「……だが待てよ」
香介が口元に手を当てて呟く。
「月臣学園にいるブレード・チルドレンは理緒やだけじゃないから……」
「容疑者に含まれるブレード・チルドレンは、あたしとちゃんだけ。新聞部部長がひと通りの情報収集を終えたら、包囲網が完成してあたしたちは逃げ場なし…、負けってこと」
香介の発言を遮って言う理緒のその言葉に、彼はしばらく考える。しかし、何かを思いついたように微笑して再び口を開いた。
「…いや、負けじゃない…。逆転の道があるぜ」
二人はきょとんとして彼を見る。
「お前たちだって気づいてるんだろ?まだ包囲網は完成してない。そして、情報を処理し網を張ってるのは、実質あの嬢ちゃんだ」
…まさか。
はある一つの結論に辿り着き、それを彼が言うことを恐れた。しかし香介はにやりと笑って、が想像した通りの言葉を述べる。
「――そうさ、殺しちまえばいい、あの嬢ちゃんを。これで勝てるぜ」
また人殺しをしなければならないのか。それも、関係のない人を、…ひよのを。
香介から目を逸らすように理緒を見た。そして、彼女の目を見て驚く。彼女も香介と同じように笑ってはいたが、その目にやる気は感じられなかった。まるで、他に策があるのだと言うように。
は理緒のその表情に一安心し、二人がひよのを殺す作戦を相談しているのを何も言わず黙って聞いていた。
「…あとはいつ部室に爆弾を仕掛けるか……か」
作戦が決まり、それをすんなりと受け入れた香介がそう呟く。しかし、最適の時間を考えだした彼の頭を理緒が軽く叩いた。
「こーすけ君のおバカさん。これで納得するから負けちゃうんだよ」
「…なんだと?」
「第一、ちゃんが何も言ってこないの、何とも思わなかったの?」
あ、と声を出して呆然とを見る。本当に気付いてなかったのかと、彼を見ては顔をしかめた。
「本当にひよのさんを殺すつもりだったら、私怒るよ?」
「ほらね」
その様子に香介は苦笑して、不機嫌なの頭を撫でる。
「弟さん、あたしがそう動くこと最初っから予想してるもの」
情報収集を秘密に行うことは難しい。だからあえてあのように、情報処理にかかる期間などもひよのに宣言させ、犯人に彼女を殺さなくてはと思わせるように誘った。恐らく歩は犯人が部室に爆弾を仕掛けると見抜いているだろう。もしこのままこちらが部室に爆弾を仕掛けに行ったら、二段に張られた包囲網に捕まってしまう。
理緒がそう説明する。それを聞いた香介が、訊ねた。
「ならどうすんだ?嬢ちゃんは殺せない。その上肋骨の烙印がある限り、鳴海弟に見つけられる」
「――じゃあ」
理緒は綺麗に笑って答える。
「包囲網の鍵、肋骨の欠落を確認できなくすればいいんじゃない?」
肋骨の欠落を確認できなくする方法。そこまで考えて、ははっとする。
まさか、自分の肋骨を爆弾で砕くつもりか。
確かにそうすれば、欠けた肋骨も元からなのか爆発で砕けたのかはわからなくなる。しかし、それはあまりにもリスクが高すぎる。よほどうまくいかない限り、死んでしまう可能性が高いのだ。
理緒が自分を信じきっているのは知っている。しかし、だからといってそんなことをするのは危険すぎた。
そう考えていると、不意に理緒の悲鳴が聞こえてきた。急に聞こえた声に反応して目をやると、大きな犬が理緒に飛び掛かってきている。
「助けてよ~、こーすけくぅ~ん、ちゃぁ~ん」
「あらあら…」
香介が犬を追い払っているのを見ながら、理緒のギャップにはいつになっても慣れないとは苦笑した。
犬を理緒から放して呆れた顔をしている香介の横で、理緒は再び呟く。
「…とにかく、勝つのはあたしだから。弟さんにはまだ踏み込めない場所があるもの」
「踏み込めない場所?」
「そう。安全の保障がない、ただ自分を信じる力だけが勝敗を決める領域……」
先程が考えたことを実行するつもりだ。その言葉で確信し、眉を曇らす。それに気付いた理緒は、大丈夫だよとの手をとって握った。
――どうか、彼女が助かりますよう…。は、ただそう祈ることしかできなかった。
結局その翌日、理緒は計画通りに胸を爆破させ、病院へと運ばれた。そして、無事に命をとりとめたのだった。
2009.07.05