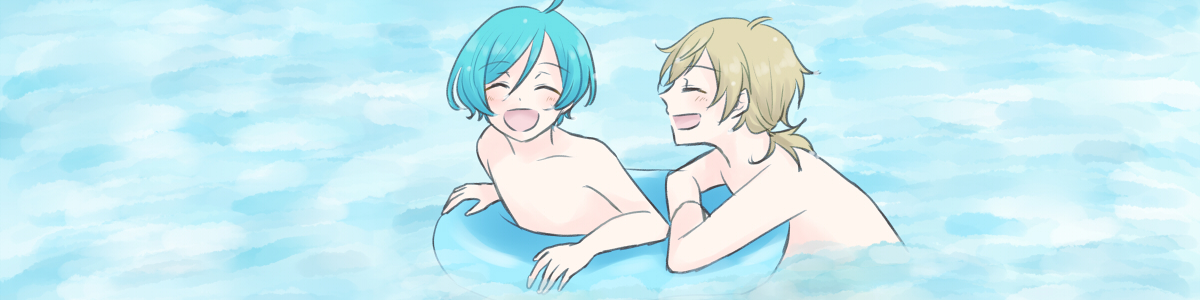midnight call
第17話
『……続いて、気象情報です』
テレビをつけていると、ニュース番組が天気予報に切り替わる。すっかり天気を気にするようになったは、夕飯を食べていた手を休め、画面をじっと見つめる。今外で降り続けている雨は、どうやら日付が越えるまで降り続けるらしい。そして、明日には濃い霧が出ると予想されている。濃い霧が出る日は、テレビの中では霧が晴れてシャドウが暴れる日。タイムリミットは今日だったらしい。完二を救い出せたことにはほっとした。しかし、念のため、今日もマヨナカテレビをチェックしなければならない。
日付が変わる瞬間、は自室で電源の入っていないテレビを見つめる。0時を指した瞬間、画面がぼんやりと明るくなった。しかし、そこに映る物は何もない。本当に誰も死なずに済んだのだろう。は今度こそ本当に安心して、ベッドへと入った。
「う……うぃース!」
月曜日になり、完二が学校に復帰した。それに伴い、放課後にたちは屋上に集まる。先に屋上で待機していたたちに、完二はお疲れっス、と躊躇いがちに挨拶をする。もうすっかり体調はよくなったようで、はほっと安心した。
しかし、先日と打って変わったその態度に、千枝は思わず笑った。
「ぷっ……意外に敬語じゃん」
「や、だってその……先輩だったんスね」
すんません、と完二は謝るが、たちは全く気にしていない。あの頃の自分たちは完二にとって確かに迷惑な存在だったのだ。その上、当時の完二は誰にも心を開けないでいた。そんな状態で、相手に敬語など使うわけがない。
「えと……ありがとう、ございました。あんま、覚えてねえけど……」
完二の礼に当然のことをしたまでだとたちは微笑む。人が殺されそうになっているのを知っていたから助けただけだ。それよりも、と雪子は本題に切り替えた。
「私たち、教えて欲しい事があるの」
「はぁ」
「さっそくだけど、あん時会ってた男の子、誰?」
完二は初めきょとんとした様子だったが、たちがいたときに会っていた人物、それも男の子となると限られてくる。誰のことか察しがつくと、急に慌て始めた。
「ア、アイツの事は……オレもよくぁ……つか、まだ二度しか会ってねえし……」
「二人で学校から帰ってたじゃんよ?何話したの?」
「や、えと……最近変わった事ねえか、とか……ホントその程度で……けど、自分でもよく分かんねんスけど、オレ……気付いたら、また会いたい、とか口走ってて……」
「男相手に」
千枝の追求に、完二は居心地悪そうにしつつも頷く。あまり触れてほしくない部分だろうが、既に何もかも見られているのだ、今更誤魔化すつもりはないのだろう。
完二は、口煩くすぐに喚いたりする女性が苦手で、男性と居たほうが楽なのだという。だからもしかしたら自分は女性に興味がないのではないか、と苦悩していたようだ。特に例の少年に対して「また会いたい」と思わず言ったため、余計だろう。
男同士のほうが楽、という点において陽介はうんうんと頷く。男ではないが、同性同士のほうが楽というのはにも理解できた。も男性は少しばかり苦手意識を感じているし、異性とは価値観などが違うことが多い。や陽介が疲れるというわけではないが、やはり千枝や雪子といたほうが余計な気を使わなくて済むと感じている。
「それで、気持ちは落ち着いたのか?」
「もう大丈夫っスよ。要は勝手な思い込みだったって事っスよ。壁作ってたのは、オレだったんだ」
「どういうこと……?」
がぽつりと問う。たちも首を傾げているため、完二は言葉を付け足した。
「あ、ええと……ウチ、こー見えて代々“染物屋”なんスよ。……あ、知ってんのか。親は、染料は宇宙と同じ……とか、布は生きてる……とか、ま、ちっと変わりモンで。んな中で育ったもんで、オレ、ガキの頃から、服縫うとか興味あったんスよ」
しかし、完二は男で、その上体格もいい強面だ。外見とはあまりにもかけ離れた趣味に、からかわれたり珍しがられたりということがかなり多かった。そんな奇妙なものを見る目に耐えきれず、気がつけば暴走族とまで言われるほど――実際はその暴走族を懲らしめていたのだが――になっていたらしい。
そこまで喋ったところで、完二ははっとし、慌てだした。
「んだオレ?何一人でベラベラ喋ってんだ……あー、今の無しで。……なんかオレ、だいぶカッコ悪りっスね」
「そんなことない、逆にカッコいいさ」
「いや、全然ダメっスよ……」
が微笑み褒めるが、完二は照れくさそうに天を仰いで苦笑する。その表情は以前と比べて晴れやかだ。
「ハハ……こんなん、人に初めて話したぜ。ま、今まで言う相手も居なかったんスけど。やっぱオレ、男だ女だじゃなくて、人に対してビビってたんスかね。なんか、スッキリしたぜ」
「意外に純情じゃん……つーか、いい子じゃん……」
「い、いい子は、やめろよ……」
「ははは、図体でかいのに照れんなって」
千枝の言葉に、完二は顔赤らめて反抗する。そんな可愛らしい様子に、陽介は笑った。たちも思わずくすりと笑うと、完二は少しばかり拗ねた様子を見せる。
正直は、完二に対して恐怖を感じていた。初めて噂やテレビで知ったときは彼を暴走族と認識していた。「暴走族」という肩書だけでも十分恐怖心を煽られたのに、その外見も大きく強面でいかにも暴力を振るいそうで、その後実際に対峙したときの迫力に更に恐怖心を植え付けられていた。しかし、彼の内面の苦悩を知り、こうして真剣に向き合い、話を聞いて、彼に対する恐怖心は少しばかり和らいだ。彼は本当はとてもいい人なのだ、と知ることができた。そうであっても恐怖心がすぐになくなるわけではないが、少なくとも彼と今後接していくことはできるだろう。
「んで、二度目に俺らと会った後の事だけど、何か覚えてる事無いか?ほら、俺らの事、シメんぞーっつって、追い払った後だよ」
「あ?えっとー……うち戻って……部屋でフテ寝決め込んで……あれ、そういや誰か来たような……」
「誰か来た!?どんなヤツだ!?」
「あ、いや、そんな気したってだけで、誰も来てないかも……」
食い入るように訊ねる陽介に完二は押され、言葉を自信なさげなものに変える。そんな曖昧な返答に千枝は、はっきりしてほしいと言いたげな表情を向けた。しかし実際はっきりと覚えていないのだろう。完二は必死に頭を働かせる。
「あと思い出す事っつや……なんか変な、真っ暗な入口みてえのとか……気がついたらもう、あのサウナみてえなトコにブっ倒れてたっス」
「真っ暗な入口……それってもしかして、テレビだったりしない?」
「あ……?あー、言われてみりゃ、んな気も……てか、なんでスか?」
「あ、ううん……ちょっと思っただけ」
頭を傾げる完二に雪子は首を傾げる。完二にペルソナ能力が備わったとは言え、まだ協力してもらえるのかはわからないのだ。そんな人に必要以上のことを喋って頭を混乱させてはいけないと判断したのだろう。
「警察には、何か訊かれたか?」
「あー、お袋が捜索願とか出しちまったんで、ちっとだけ訊かれたっけな。今と同じような事言ったら、ワケ分かんねーって顔してたっスけど」
それはそうだろう。そんな非現実的な話、普通警察が信じられるわけがないし、たちだって実際目の当たりにするまで信じなかった。
たちは、顔を見合わせて今までの情報を整理し、脳内で推理した。そんな様子に、完二は口を開く。
「あーと……先輩ら、もしかして探偵みてーな事やろうっての?」
「んー、まあ、そんなとこ」
「なら、オレも頭数に入れてくんないスか。酷ぇ目に遭ったのが“誰かの仕業”ってんなら、十倍にして返さねえと気が済まねえ」
「マジ?そりゃいい、すげー戦力じゃん!どうよ、リーダー?」
完二の言葉に、たちは目を輝かせる。シャドウと戦うのは死と隣り合わせだ、戦力は多ければ多いほど心強い。貴重なペルソナ使いが自分からそう言ってくれると、こちらとしては大変ありがたいのだ。も快く歓迎すると、完二は宜しくっス、と気合を入れた。新しい仲間に、たちも口々に宜しく、と歓迎の言葉を贈る。完二が仲間になったところで、一行は一度テレビの中に入ることにした。
「しっかしよく食うな、お前……話ちゃんと聞いてたか?」
「んあ?ひーへるっふお」
「飛ばすな!」
テレビの中に入る前に、まずは状況確認も兼ねて、完二に今起きている出来事を一つ一つ丁寧に説明した。しかし、完二は食べることに夢中で、いまいち反応を返さない。痺れを切らした陽介が確認を取ったため、完二は一度食事を中断させた。
「あー、えっと、テレビを使って殺人……?って事ぁ、撲殺で決まりスね?」
「ちげー!テレビで殴ってんじゃねーよ!どんだけ聞いてねーの、お前……」
案の定、全く把握できなかったようだ。はやっぱり、と苦笑した。しかし、非現実的なことの連続であるので、きちんと聞いていても理解しきれるかは疑問である。見てみればわかる、という千枝のフォローに、完二は頷いた。
「けど、犯人の手口、雪子ん時と同じだったね。まずさらって、それからテレビに入れる」
「うん……怖いね」
さらわれたときの記憶がない、というのは、テレビに入れられる混乱もあるのかもしれないが、恐らく薬を使われているのだろう。そんなものは、事前に把握できていないと構えられない。どうしたら事件を未然に防ぐことができるのだろうか。
「つーかさ、例のテレビ、最近、けっこー面白くね?」
そうやって空気を重くしていると、ふと傍で声が聞こえた。例のテレビ、という言葉に反応してたちはそちらを振り返る。例のテレビ、なんて最近の話題は一つぐらいしかない。マヨナカテレビだ。
「“次に出んの誰?”とか、気になるな」
「オレ前から、次はぜってーアイツって思ってたんだよ。名前なんだっけ、1年の暴走族上がりの……」
「次は誰と思ったって?」
完二が傍にいることにも気付かず盛り上がっている男子高校生たち。やはりあの内容は外部にも筒抜けなのか、と思うと同時に、一番見られたくないものを面白いと言われて気分がいいわけがないと完二を気遣おうとすると、完二自らが立ち上がり彼らを見遣った。そこで彼らは初めて完二の存在に気付き、焦った様子を見せる。
「そいつぁ多分、“巽完二”って名前だな……ちなみにゾク上がりじゃなくて、ゾクを潰した方だけどな」
「え、いや、その……」
「誰だテメェら……!」
完二の気迫に、男子高校生らは悲鳴を上げて慌てて逃げて行った。それを見届け、完二は威嚇をやめ、溜息をついて席に戻る。
「んだよ……つまんねーな」
「やり切れないね……殺人事件との絡みとか、よく知らないで言ってんのかもだけど、同じ学校の子なのに……」
「関係ねーとか、自分は大丈夫だとか、観客気分なんだろ……次に誰が狙われるか、分かんなくなって来たってのによ」
彼らの気持ちもわかるからこそ、たちは複雑な気分だった。自分たちもつい最近まで、自分の身近に事件が起きたり、知っている人が被害に遭い、殺されまでするなんてことがあるなんて全く思わなかった。しかしやはり、自分たちが知っている人々が命の危険に晒されていた状況を面白がられるのは、とても腹立たしいことだ。
「ところで、今回の事で、“被害者は女性”っていう共通点は崩れちゃったね」
「そうだね、もう一度見つめ直さなきゃ……」
「もう一個の読みは何だっけ」
「“山野アナの事件と関係ある人が狙われる”……これは、どうかな?」
「……まだ分からないな」
「外れた、とまでは言えないか」
「けど、山野アナと直接関わったのは、ほんとはどっちも母親の筈なんだよな……」
気持ちを切り替えて推理に取りかかったが、雪子が攫われたときとほとんど進展は見られない。素人の自分たちにはこれ以上の推理は難しく、明確な道筋が得られないことに落胆した。
「なんだ先輩ら、手がかり無しスか?じゃーここらでオレが、すんげーの出しちまうぜ?」
「なんだ、それ?」
そう言って完二がポケットから取り出したのは、紙きれだった。たちは、の手に渡り開かれたその紙に顔を寄せ合い、見つめる。
「今日、オレが復帰したら、なんか目障りなのがチョロチョロいたんスよ。先輩やオレが行方くらました事、面白半分にかぎ回ってやがったんで、没収してやったんス。ま、書いてある意味は、よく分かんねんスけど」
「分かんないんじゃん……」
「メモか?いくつか項目があるな……。演歌ヒットチャート、女子アナランキング、テレビ報道番組表……。テレビ報道?山野真由美4月11日、小西早紀4月13日……」
「なんだこの日付?4月11日……?」
がメモの内容を読み上げる。前者二つは恐らくメモの書き手の趣味だろうが、テレビ報道番組表と書かれたその項目だけすぐには意味が分からない内容だった。山野真由美はともかく、小西早紀という一般の女性についてのメモなんて何故取っているのだろう。
「あ、遺体が発見された日……は、そっか、始業式の日だったから、12日か。11日はその前の日だけど……」
「小西先輩の遺体が出たのは15日だ。忘れらんない日だからな……え、微妙に何の日か分かんねえぞ?てか、“テレビ報道番組表”ってどういう意味だ?“小西早紀4月13日”って何だ……?」
「……もしかして、小西早紀がテレビ報道に出た日か?」
の推理に、たちははっとする。確かに顔は隠されていたが、小西早紀は殺害の直前、第一発見者としてマスコミからインタビューを受けていた。マスコミのおかしな質問内容に困惑しており、も呆れていたことが印象に残っている。山野真由美についても同様で、殺害直前に不倫報道で騒がれていた。
「おい待てよ……天城も確か、インタビューされたよな?あのインタビュー流れたの、いつだった!?」
「た、確か、学校休んでた間……えっと……あっ、土手で君に会った日。ほら、私、和服で……覚えてない?」
「いや、覚えてる」
「買い出しに行った日だから、ええと……4月15日!私が事件に遭ったの、確かそのすぐ後」
「完二、お前の出た、例の特番は!?」
「あー、あれっスか……あのおかげで、お袋マジギレして酷ぇ目に……」
「いーから!」
「え、えっと、日にちまでは覚えてねっスけど……先輩らと会う、チョイ前っスよ」
たちは顔を見合わせ、頷いた。雪子と完二の話によって推測は確信に変わる。被害者は、全員誘拐される直前にテレビで報道されていたのだ。
「じゃ、犯人の狙ってるのって、“テレビで取り上げられた人”……?」
「事件のニュースにばっかり目が行ってて、全然気付かなかった……」
「偶然にしては出来すぎだ」
「そうだよね、それ以外共通点なんてはっきりしないし……」
「ああ……考えてみれば、天城の件で失敗したのに、やり直さないで、狙いを完二に移した。その事も、テレビ報道っていう犯人なりのルールがあるって考えれば、一応頷ける」
「そっか、そうだよね……犯人二度来る可能性あったんだよね……ヤバ、考えてなかった……」
「テレビ繋がりの線、全然あるな……つまり被害者は、単に事件関係者じゃなくて、その中でも“メディアで有名になった人”か」
「きっと、そうだよ……」
「でも……そうなると動機は何なんだ?テレビ出たら殺すって、どういうんだ?あー、くっそ、よく考えたら全然解決できてねーよ!なんで俺、もっと頭良くねーんだ……!」
被害者の共通点はわかっても、犯人の動機が全く見えない。テレビ報道に出たから殺す、なんて全く理由が結びつかないのだ。その上、一度失敗したらもう一度テレビに入れるのではなく、次のターゲットに移っている。犯人にとっては殺せたかどうかなんてどうでもいいのだろうか。ターゲットの共通点が見えても、犯人像が浮かばないとなると、まだ当分この事件は解決できそうにもない。
「なんで落ち込む事あんスか?オレ、先輩らスゲーって思ってるんスけど」
犯人が特定できない落胆から俯いている中、完二は一人前を向き、口を開く。その声に、たちは顔を上げ、完二を見遣った。
「だって先輩ら、結局オレの事気づいて、体張って救ったじゃねえスか。十分だぜ、それで」
「うん、そうだね。私だって、助けてもらった。解決はまだでも、もう二人も救ってる」
「それは、そうだけど……」
「それに“次は完二くんじゃないか?”っていうみんなの推理は、ちゃんと当たってたよ」
「惜しかったよね」
「あ?事件の前から分かってたんスか?なら来んの、もちっと早めがよかったっスよー」
完二の冗談に、一斉に笑い声を上げた。完二や雪子、二人の被害者の声に、たちは救われた気分になった。未然に防ぐことはできなかったが、命を救うことができた。それだけでも今は十分だ。焦っていても何も見えてこないし、本職の探偵でも警察でもない自分たちがここまでわかっただけでも進歩なのだ。
「ま、こんだけ分かってりゃ、次こそは先回り出来そうだし、タイホも時間の問題かもね」
「それに、今度こそ犯行終わりって可能性もあるかも知れないし」
「だといいけどな……二度も邪魔してやったんだ、いい加減懲りて欲しいぜ。とりあえずは、今まで通り雨の日にテレビチェックするって事だな」
「うん、そうだね」
完二を助けたからと言って、犯人が捕まったわけじゃなく、まだ油断はできない。次こそは未然に防ぎ、被害者を危険に曝さないよう気をつけねばならない。
「そういえば……来週、林間学校だ。雨降らないといいけど。1、2年合同だから、完二くんも一緒っすね」
「マジスか?学校か……かったりーなぁ……あ、次のビフテキ、そろそろ頼んでもらっていいスか?焼けるまでに、残り一気にいっちまうんで。……ここ、先輩らのワリカンなんスよね?」
「じゃ、行こうか。あの子に新しい仲間、紹介しないと」
「あん?どうしたんスか?……わーったっスよ、じゃ、安いトコで、ラーメンでいいス。あ、やっぱペアセットのたこ焼きか……?どっちがいいスかね?」
「全部却下」
「ええっ!?」
ブラックホールかと疑うほどの完二の腹は無視して、たちはテレビの中へと向かった。入り口ホールでは、いつものようにクマが待っていた。クマはたちの姿を見ると、真っ直ぐに向かって駆け寄ってくっつく。もそれに応えるように頭を撫でた。
「あー……言われてみりゃ、居たような……クマだったのか……」
そんなとクマのやり取りを奇妙なものを見る目で見つつ、完二は呟く。救出時完二は疲労困憊していたため、記憶が曖昧だったらしい。
「つーか、何で“クマ”?」
「知らん」
「クマも知らん。ずっと悩んでるの」
「な、なんか、かわいいじゃねえか……さ……触っていいか?」
「おさわりはお断りクマ」
「先輩は触ってんじゃねえか!」
「女の子は特別クマ」
「なっ……んだとコラァ!テメ、調子乗んなよ!?」
つーんとそっぽを向くクマに、完二は怒鳴る。二人のやり取りを見ていた雪子は、どこをどう琴線に触れたのか、爆笑していた。今までしかろくに触ろうとしなかったから知らなかったが、誰でも触っていいわけではなかったのかと少し申し訳なく感じた。曖昧だがクマはどうやらオスのようであるから、男に触られるのはあまりいい気がしないのだろう。完二はごつい外見をしているため余計に。
「ちっ……あー……ところで、気になってたんスけど、天城先輩もさらわれたんスよね?」
「え……うん、完二くんの前に」
唐突に話題を変え話を振られた完二に、雪子は首を傾げた。たちも何だろうかと完二に注目する。
「てこたぁ、先輩もなんかこう、さらけたんスか?」
「そ、それは…その…」
「どんなだったんスか、先輩の……」
雪子が戸惑っていることに気づかず、完二は迫る。確かにこの中で完二が一番最後であったし、自分以外のシャドウがどんな感じだったのか気になるのだろう。しかしシャドウというのは本来自分の認めたくない内面の部分だ。そんなものを本人の口から言えるはずもなく、耐えかねた雪子は思わず完二の頬を平手で打った。
「うごおっ!」
「あ、ごめん……スナップ効いちゃった……」
「あ……アゴが……」
「今度からは、もっと、優しくするから……」
「もっと……優しく……?」
「アホだ、こいつら……」
二人のやり取りに、たちは何をしているのかと呆れる。完二はともかく、雪子の根っこはここまで残念だったというのは未だに慣れない。千枝以外心から気を許していた人がいなかったからだろうが、深く関わる前の雪子は誰から見ても高値の花のような存在だったのだ。そんな彼女のイメージとギャップがありすぎる。本音を出してもらえるようになったのは純粋に嬉しいが、こればかりは慣れるのに多少時間がいる。
「そうそう、カンジが仲間になった記念に、クマからこれをプレゼントするクマ!」
「お、これだな、例のメガネ」
クマはふと、完二の眼鏡を取り出した。完二もそれを受け取るが、その眼鏡を見て不可解な表情を浮かべる。周りがああ、と呆れた顔を浮かべる中、雪子だけは目を輝かせてその眼鏡を見つめている。
「早くかけて」
「あ?は、はあ……でも、オレのだけ違わねえスか?」
そう言いつつも、完二は律義にその眼鏡をかけた。そして、一瞬の静寂に包まれる。
「に、似合う……うぷぷ……ぷぷ……あはははは!」
完二の眼鏡――鼻眼鏡姿に、雪子は耐えきれず吹き出し、大爆笑をする。それに釣られ、たちも次々と笑いだした。
「ハハ、すげー。お前のは、マジ似合ってるよ!」
「ふふっ、お、おかし……っ!」
「ちゃんとしたのあるのに、ユキチャン、こっちにしようって聞かないクマよ」
「つまんねー事してんなよ、あぁ!?」
「な、なんでクマにキレるクマ!?」
「よこせオラっ!」
完二は鼻眼鏡を投げ捨てると、クマが手に持っていたもう一つの眼鏡を奪い、かける。しかし、その眼鏡も鼻眼鏡だった。再びの鼻眼鏡姿に、雪子の大爆笑はエスカレートする。
「ウププ、あはははははは……!」
「スペアの方を奪われたクマ……カンジ、実は好きね、ソレ?」
「アハハ、くるしー!」
一連の流れがおかしくて、たちは笑いが止まらなかった。当の本人は怒り、鼻眼鏡を霧の向こうへと思い切り放り投げた。自分たちは大変面白いが、かけさせられた本人にとっては何も面白くないのだろう。
「こっちが、本物クマ。やっと渡せたクマね」
「要らねえモンならスペア作ってんじゃねーよ……」
「あはは、クマ、ナイス!」
「くっそ、てめーら!いつか、ぜってーやってやっからな!」
「あはははは!」
完二以外の全員は、暫く爆笑の嵐でその場から動くことすらできなかった。は笑いながら、こんなに心から大笑いができたのはいつ振りだろうかと、嬉しさを感じていた。
2014.07.07