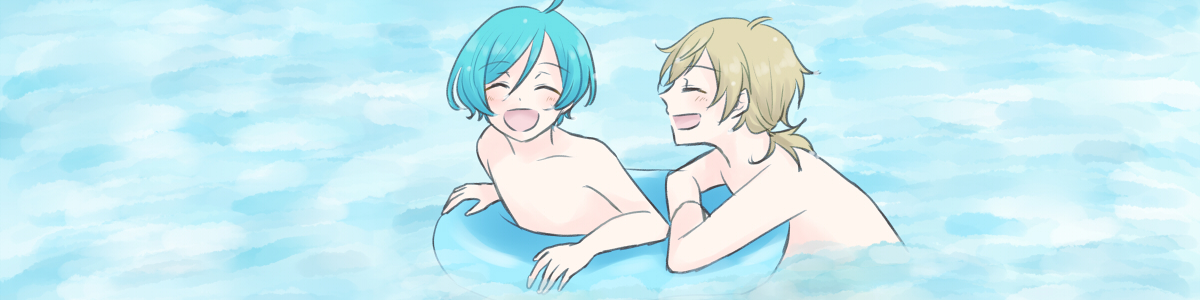midnight call
第10話
4月30日土曜日。長い間学校を休んでいた雪子がようやく復帰した。教室にやって来た彼女は、たちに元気に挨拶をする。疲れは完全にとれたようだ。それだけでなく、影と向き合ったことにより、何だかすっきりしたように感じる。
昼休みになると、は千枝と雪子に、一緒に屋上で昼食をとろうと誘われた。は喜んで頷く。しかし、千枝の手には昼食だけでなく紙袋もあり、何なのだろうかと首をかしげた。その紙袋の正体は、屋上に辿り着くとすぐに判明した。
「いきなりですがさん!ワタクシ、里中千枝と、天城雪子からプレゼントがあります!」
千枝はそう言いながら紙袋をに渡す。本当に、いきなりプレゼントとはどうしたのだろうか。は思わずきょとんとした。その様子に雪子は微笑む。
「中身、見てみて」
「う、うん」
は言われた通り、紙袋の中のものを取り出す。手触りは柔らかく、大きいのか折り畳まれている。
「えっ、カーデ?」
取り出して広げてみると、それは鮮やかな色をしたカーディガンだった。の様子に、千枝はにっこりと笑みを浮かべる。
「そう!あたしも雪子も制服の上に何か着てるしさ」
「ちゃんも着たらお揃いみたいになるかなって思って、昨日千枝と買いに行ったの」
だから千枝は昨日落ち着きがなかったのか、とは昨日の千枝を思い出して納得した。
「結構薄いから夏でも肌寒くなったらちょうどいいかなって。あと眼鏡に合う色を選んでみたんだけど…って、迷惑じゃない?」
「ううん!全然!嬉しい!ありがとう!!」
千枝が不安げにそう聞いてきたので、は勢いよく首を振った。迷惑なわけがない。むしろ、予想外のプレゼントがとても嬉しかった。
「さっそく着てもいいかな?」
「うん、もちろん!」
はカーディガンに腕を通す。大きさはぴったりだった。先程まで少し肌寒く感じていたのが、今はとても暖かい。
「ど、どう?」
「うん、すっごく似合ってる!」
「思った通りね!」
作戦成功、と二人ははしゃぐ。も嬉しくて笑みを浮かべた。そして、これからは毎日このカーディガンを着て学校に来ようと決めた。
「あれっ?がカーデ着てる!」
昼食を食べ終え教室へ戻ると、陽介がきょとんとした顔で声をかけてきた。もこちらを見る。真っ黒な制服の上から着るには目立つ色であるため、二人だけでなく、他のクラスメイトからの視線も感じ、恥ずかしくなっては下を向いた。
「どう?いいでしょ!あたしらからのプレゼント!」
「へえ、似合ってるね」
「うん、似合ってる!」
「でしょでしょー!」
そんな彼らのやり取りに、褒められ慣れていないは更に恥ずかしくなり、頬を染める。そんなの様子に千枝は気がついた。
「あれっ!照れてる?かわいいっ!」
「えっ?わっ!」
千枝はそう言うと、急に抱きついてきた。はびっくりして小さな叫び声をあげる。
「あ、ずるい千枝。私も」
「どーぞ!」
千枝が離れると、今度は雪子が抱きついてきた。も戸惑いながら抱き締め返す。友達と抱き合うなんてことは小学校以来だったは、照れながらも嬉しく思い、笑った。隣から陽介の羨ましがる声が聞こえた気がした。
放課後、雪子が復活したということで、改めて事件の話をしようとたちは屋上に集まった。雪子は少し遅れて、両手に湯の入ったカップ麺を持ちながら合流してきた。
「お待たせ。千枝はおそばの方だよね」
「サンキュ!お~この匂い、たまらん…部活前のこの一杯の為に生きてるね、うん。これ、あとどんくらい待ち?」
「全然、まだよ」
千枝にカップ麺を渡しながらそう言い、雪子も腰を下ろす。
二人とも見かけによらずよく食べるな、とは思った。も小腹は空いていたが、カップ麺を食べるほどでもなかったので、チョコレートを買って食べることにしたのだ。
「で、なんだっけ。…あ、雪子に事情を聞くんだったよね」
思い出したように千枝がそう言い、陽介は頷く。そして、話を切り出した。
「なぁ、天城さ、ヤな事ムリに思い出さす気は無いんだけど…改めて、聞かせて欲しいんだ。…さらわれた時の事、やっぱ何も覚えてないのか?」
「うん…落ち着けば思い出すかなって思ったけど、時間が経つ程、よく分からなくなっちゃって…ただ、玄関の…チャイムが鳴って…誰かに呼ばれたような気は、する…」
そこまで話して、雪子は首を振る。やはりそのあとは覚えていないらしい。
雪子の話からすると、やはりその来客が犯人である可能性が今のところ一番高い。しかし、玄関からチャイムで呼び出した上での犯行、ということになる。非常に大胆だ。
「目撃者が無いか警察も洗ってんだろうけど…あんま期待できねーな。すぐ身元割れるようなナリで歩き回んねえだろうし」
ましてや、犯行手段は“テレビの中に突き落とす”だ。万が一警察が犯人を突き詰めても、手段がわからず決定的な証拠も見つけ出せないだろう。
「なんでこんな事すんだろ?」
「そこまでは、犯人に聞いてみなきゃ分かんねーな…けど、ひとつ大事な事がハッキリした…人が次々“向こう”に行ってんのは偶然じゃない。こっちに居る誰かが、さらってテレビに放り込んでるんだ。…こいつは“殺人”だ」
そこまで言って、陽介は思い出したかのように雪子を見て、話を変える。
「あ、そうだ、言ってなかったな。俺とコイツで、犯人挙げちゃうことにしたからさ!この事件、正直警察には無理そーだけど、俺らには“力”があるからな」
「ああ、俺たちが捕まえる」
「う、うん…」
雪子は戸惑いながら頷いた。千枝は勢いよく右手を上げる。
「あたしもやるからね!あんな場所に、人放り込むなんてさ。も、絶対ブチのめす!」
「千枝…」
「あ、私も!」
も慌てて声をあげた。せっかくにも力が生まれたのに、何もしないのは嫌だ。今度こそ、皆の役に立ちたい。
「私も…やらせて」
雪子の唐突な言葉に、たちは驚いて雪子を見る。
「どうしてこんな事が起きてるのか知りたい。それに…もし自分が、殺したい程誰かに恨まれてるなら、知らなきゃいけないと思う。もう、自分から逃げたくないの」
雪子は、意志を固めた強い目をしていた。本気だ。
「おっし!じゃあ、全員で協力して、捕まえてやろーぜ!」
「うん」
たちはしっかりと頷く。でも、と千枝が口を開いた。
「どうやって犯人捜す?今んとこ、手がかり無しだよね」
「狙われたの、私で三人目だけど、これで終わりなのかな?もし、次に狙われる人の見当つくなら、先回りできない?」
「先回りか…なるほどな、いいかも」
もしまだ事件が続くのなら、いい考えだ。陽介は頷いた。
「じゃあ、今までの被害者の共通点挙げてみようぜ。一人目、女子アナの“山野真由美”。二人目、“小西早紀”…先輩。三人目、“天城雪子”。えーと、全員の共通点は…」
「女性である」
「だな」
「女性ばっか狙いやがってぇ!許せん!きっとヘンタイね」
の回答に陽介は同意する。千枝は激怒した。雪子は、もう一つ挙げる。
「あと、これは?“二人目以降の被害者も一人目に関係してる”」
「あ、そっか、雪子も小西先輩も、山野アナと接点があった…」
「確かにそうだよね」
小西早紀は山野真由美殺害の第一発見者、雪子は山野真由美が宿泊した旅館の娘だ。事件関連かは疑わしかったが、インタビューも受けている。二人とも、山野真由美との接点は十分ある。ということは、今のところ、山野真由美の事件に関わりのあった女性が狙われていると考えられる。
「で、これも多分だけど、次もし、また誰か居なくなるとすれば…」
「雨の晩に、“例のテレビ”に映るのかな!?雪子ん時も、それっぽいの流れたし」
ああ、と陽介頷いた。そして、推理を続ける。
重要なのは、被害者がテレビの中に入れられる前にも、ぼんやりながらマヨナカテレビに映ったという事実だ。まるで犯行予告のようである。そうだとはっきりわかったわけではないが、情報の少ない今はそれを当てにするしかない。次に雨が降ったら気を付けなければ。
それが今の段階の結論であった。
「ところでソレ、もう出来てんじゃね?」
陽介は唐突に千枝たちの持つカップ麺を指差した。話に夢中になっていてすっかり忘れていたが、とうに待ち時間はすぎているだろう。
「うおっと、そうだった!いっただっきまーす!」
千枝と雪子は慌ててカップ麺の蓋を開け、食べ始めた。空腹を誘ういい匂いが辺りに広がる。空腹を抑えるため、はチョコレートを一つ口に放り込んだ。
「な、先生、ヒトクチ!とりあえず、ヒトクチ味見!」
「うっさいな!アンタも買えばいいじゃん。…ったく、ヒトクチだけだかんね」
陽介のせがみに、仕方ないなと千枝は折れ、陽介にカップ麺を渡した。それを見るも、どこか羨ましそうだ。それに気づいた雪子が声をかける。
「くんもちょっと食べる?」
「じゃあ、ちょっとだけ」
礼を言いながらも雪子からカップ麺を受け取った。そして二人は同時に箸を運ぶ。
「う、う、うメェェェ…オレ、まじ、腹ペコの子羊の気持ち分かるわ~」
すると、二人は千枝たちに返すどころか、次々に箸を進めていってしまった。その勢いは、凄まじい。予想外の光景に、は目を見開いた。
「ギャー!何してんの、おたくら!」
千枝の叫びにようやく二人は我に返ったように動きを止める。中身を確認し、慌ててカップを千枝たちに返した。千枝たちも、カップの中身を見る。
「具ごと全部いかれてんじゃん…」
「お、おあげ…」
どうやら、彼らがすべて食べてしまったようだ。千枝は陽介たちを睨む。
「何したか、分かってんでしょーね」
「い、いやいやいやいや!待て、ごめん、悪かった!代わりに肉!肉おごっから!」
陽介は慌ててそう言う。すると、恨めしそうにカップを見つめていた千枝がぴくりと反応した。
「肉だぞ、肉!?き、聞こえてる?」
「肉…!?」
再び発した陽介の言葉に、千枝は顔を上げる。目は輝いていた。どうやら、カップ麺の恨みよりも肉を食べられることの嬉しさのほうが千枝にとっては大きいらしい。
「おあげ…」
「まーまー、雪子、肉で手打とうよ。カップ麺なんて、いつだって食べれるし。ね?」
すっかり元気になった千枝は、未だにショックを受けている雪子を励ます。雪子はちらっと千枝を見、また視線を空のカップに戻した。
「…脂身少ないのなら、いいよ」
「よっし、協議の結果、肉で許す!」
雪子はしぶしぶ了承した。千枝は満足げに大きく頷く。
「脂身少ないのって、フィレ?あー、フィレ肉、なんて芳醇な響き!フィレ、フィレ、フィレ、フィレに~く~」
「お、おい、もちろん同罪のお前も、強制参加だからな!」
陽介の必死の言葉に、も慌てて頷いた。そして、たちは肉のためにその場を移動することにした。
「いや~、ホントちょうどよかったぜ。今日から始めたんだよな、ビフテキ」
陽介とが千枝と雪子に肉を奢るためにやって来た場所は、肉屋やレストランなどではなく、ジュネスのフードコートだった。どうやら、さすがにフィレ肉は高すぎると判断したらしい。
「ウチとしても名産広めんのには協力したいし、それに、立派な鉄板もある事だしさ」
「焼きソバ屋の鉄板じゃん…まあいいか、肉は肉だし。フィレ肉とは程遠いけど…」
千枝は呆れてそう言った。しかし、肉なら何でもよかったらしく、嬉しげに肉を見つめている。
「雪子、大丈夫?苦手なんじゃない?」
「うん。悔しいから、食べる」
雪子は肉を睨みながら返事をする。脂身の多い肉は苦手らしい。しかしそれで何も食べることができないよりは、肉を食べたほうがましだと判断したようだ。
「でさ、さっきの話だけど、結局、犯人ってどんなヤツなんだろ」
肉を口に運びながら、千枝は先ほど屋上で話していた話題を再び起こす。陽介は腕を組み、考える素振りを見せた。
「山野アナだけ見れば、動機は恨みっぽいよな。不倫相手の奥さんとかさ」
「でも柊みすずって、アリバイがっちりでしょ?旦那さんとも前から別居中らしいし」
「そうなのか?お前、やけに詳しいな…」
千枝のその言葉に、陽介は目を瞬かせる。どうやら陽介はそのことを知らなかったらしい。にもそれは初耳だった。
「じゃあ二件目だ。小西先輩は…一件目の死体の発見者だった。犯人が同じだとすれば、先輩が狙われたのは…」
「口封じのため」
「うん、俺もそう思う。例えば何か、証拠を握られちゃったとかでな」
陽介は難しい顔をしながら頷く。
しかし、犯人は被害者をテレビの中に入れただけだ。警察に気づかれるような証拠なんてあるのだろうか。
「しっかし、田舎は退屈そうだと思ってたら、信じられない事ばっかだなぁ…」
事件について推理していると、不意に気になる声がたちの耳に入ってきた。
「おっと、新メニュー発見伝」
「あれ?この前の刑事さん?」
たちが声のするほうを見ると、スーツをだらしなく着た若い男性が立っていた。この男性には見覚えがある。確か、始業式に山野真由美の殺害現場で見かけた刑事だ。
その刑事はたちに気がつく。そして、歩み寄ってきた。
「あれ、キミ、堂島さんトコの…」
「どうも」
どうやらと男性は、あのとき以外にも面識があったらしい。彼はどこか気まずそうに苦笑いを浮かべた。
「あはは…えっと、そうだ、ちょうどよかった、うん。堂島さん、今日は定時で上がれるからって。菜々子ちゃんにも伝えてくれる?」
「はい、わかりました。ありがとうございます」
は微笑んで刑事に会釈をした。菜々子ちゃんとは、恐らく堂島の娘だろう。
足立はふとたちのほうを見回し、人の良さそうな笑みを浮かべた。
「ども、足立です。堂島さんの部下…ていうか相棒ね」
「お仕事大変そーっすね?」
陽介がそう言うと、足立は一瞬呆けた。そして、眉を寄せる。
「え、ああ、世間は面白がってるみたいだけど、僕らはそういうワケにもいかないからね」
「あの、やっぱ、小西先輩が狙われたのって、口封じなんですか?」
「あ、あー、いいとこ突かれちゃったね。イタタタタ…なんて、はは」
陽介はそう言及してみる。すると、足立は情けない様子で空笑いをした。そして、話を始める。
「もちろん、その辺は僕らも考えてるさ。彼女、山野アナの遺体発見後に殺されたでしょ。もし口封じだとすると、彼女以外の人が見ても、証拠だと分からない物が遺留品にあったとかね。とすると、犯人は、小西早紀に非常に近しい人かも知れないよねぇ。柊みすずの周りからは何も出ないし、あ、僕の推理、イイ線行ってるかも…」
そこまで話して、足立ははっとする。刑事にしては部外者に話しすぎではないだろうか。口が軽い人なんだな、とは苦笑いをする。
「あっと、また喋りすぎ?」
また、というと、以前も同じことがあったのだろう。足立は慌ててたちを見回した。そして、頭をかく。
「い、今の内緒ね…まあ、犯人は警察が必ず捕まえるから。それじゃ!」
足立は逃げるように早足で去っていく。どうも、頼りなさそうな人である。
「あ~…確かに、警察には任せておけないなぁ…」
千枝も足立の去っていったほうを見てそう呟いた。表情からして、他の皆もと同じような印象を受けているに違いない。
「おあっ、しまった!肉がゲンナリしてる!」
「肉、肉、うるせーよ…」
千枝の叫び声に肉を見ると、もうすっかり冷めきってしまっているようだった。せっかく焼きたての状態であったのに、もったいない。
たちはひとまず、二人が肉を食べ終えるのを待って、テレビの中へ入ることにした。
「すごい…ここ本当に、テレビの中なんだ」
テレビの中の世界で、雪子は不思議そうに辺りを見回した。
テレビの中に入る際、と雪子は画面に手を触れさせてみたが、やはりその手はすんなりとすり抜けた。それを見て、本当に力を手に入れたんだなとは実感する。
広場の奥から、クマが歩み寄ってきた。メガネをかけていない雪子は、間近に来たところでようやくクマの存在に気がつく。
「あの時のクマさん…夢じゃなかったんだ」
「ユキチャン元気?クマね、ユキチャンとの約束守っていいクマにしてた」
「そっか、えらいえらい」
雪子は微笑んでクマの頭を撫でる。クマは気持ち良さそうに笑った。その可愛らしい光景に、自然との頬も緩む。
陽介はクマの様子に呆れつつも、口を開いた。
「ま、まあ、このクマきちのためにも犯人見つけようって事になってさ」
「私も、仲間に入れてもらったの。一緒にがんばろう」
「うん!一緒にがんばろうって思ってたクマ!だからユキチャンに、用意してたクマよ!」
クマはそう言って、どこからかメガネを取り出した。雪子はそのメガネを受け取る。
「そっか、みんなかけてるの、コレなんだ。ありがとう、クマさん」
クマに礼を言い、雪子はメガネをかけた。そして、周りを見渡す。
「ほんとだ、霧が晴れて見える…」
先程までの光景がまるで嘘であったかのようにはっきりと変化した視界に、雪子は驚いた。やはり、初めはびっくりするものなのだろう。
「ところでさ、なんでそんなにメガネ持ってるワケ?」
「よくぞ聞いてくれたと言いたいですぞ!」
千枝の疑問に、クマは威張るような仕草をした。そして、自慢するように言う。
「これ、クマが作ってるクマよー」
「え!」
たちは驚く。まさか、クマが自分で作っているとは思わなかったのだ。
「クマはココに住んで長いから、ココで快適に過ごす工夫は怠らないクマ」
「クマくんすごいね…!」
「エヘヘ、でしょでしょ!?」
が褒めると、クマは嬉しがった。メガネを作ってしまうとは、器用なものだ。しかし、指もないクマの手で、どうやってメガネのような細かいものを作っているのだろうか。工具らしきものもどこにも見当たらない。
「でも、クマさんはメガネしないの?」
「おっと、それ訊いちゃう?またまたいい質問クマ!」
クマは調子よくそう言う。そして、胸を張った。
「何を隠そう、クマはこの“眼”自体が、レンズになってるクマ!知らなかったクマ~?」
「知らねーよ…」
陽介は呆れ、ため息混じりに呟いた。どうやら陽介は興味がないらしい。その様子を見て、クマは怒った。
「な、なに大して興味無い的なフリしてイジワルしてるクマか!クマは凄く器用クマよ!見るクマ!指先がこんなに動いてる!」
クマは手先を動かしてみせる。しかし、指もないクマの手は、動かされても器用さはまるで感じられない。
「分からんわ!」
「いでっ!」
そんなクマの様子に耐えかねたらしい陽介は、クマを思いきり突き飛ばした。クマは倒れ、その勢いのまま、起き上がりこぼしのように戻ってきた。陽介はクマには厳しいのだな、とは思った。
「あれ、何か落ちたよ?」
クマが倒れたときに何かが落ちたらしい。雪子は床に落ちているものに気付き、拾い上げた。
「あ、それ、ちょっぴり失敗したメガネ」
「あーこれ…」
「ちょ、ちょっと雪子?」
は雪子が拾ったものを認識する。そして、雪子が今までかけていたメガネを外し、拾ったメガネをかけることに驚いた。
「あはは、どう?」
雪子はそのメガネをかけると、笑いながらこちらを向いた。雪子がかけたのは、パーティー用の鼻メガネ。まさか雪子が自分からそのメガネをかけるとは思わず、は開いた口が塞がらなかった。
「…似合わない」
「えー、そう?あはは」
急に雪子のキャラが変わった気がする。いつもは冷静なも、この豹変ぶりにはさすがにひきつった笑みを浮かべていた。
「ユキチャン、それ、気に入ったクマ?」
「鼻ガードついてるし、私、これがいい」
「おやめなさい!」
真顔でそう答える雪子に、千枝はすかさず突っ込みを入れる。これが素の雪子の姿なのか、さすがに千枝は対応し慣れているようだった。
「クマったなー、それ、本物のレンズ入ってないクマよ。こんな事なら、ちゃんと用意しておけばよかったクマ」
「なんだぁ、残念」
雪子は心底がっかりしたような表情をして、鼻メガネを外し、本来のメガネをかけ直す。そして、その鼻メガネは千枝に差し出した。
「はい、次は千枝ね」
「はぁ?ちょ…しょーがないなあ…」
こういうときの雪子はとめられないのか、千枝は仕方がなさそうに鼻メガネを受け取った。そして自分のメガネを外し、それをかける。
「う…ぷぷっ!」
すると、急に雪子が吹き出した。あまりにも突然の出来事に、たちはぎょっとして雪子を見る。
「あはは、あははっはっはっはっは!」
「どういう流れ、これ…」
雪子はお腹を抱えて爆笑しだした。は先程からの雪子の様子についていけず、ただ呆けた顔で彼女を見ることしかできない。
「あ、天城さん…?」
「出たよ、雪子の大爆笑…あたしの前以外では無いと思ってたのに…」
千枝は呆れる。千枝の言動からして、千枝の前では昔からよくある光景なのだろう。まさか雪子がこんな性格だったとは。
「こんなメガネじゃ、捜査になんねーっしょ!?てゆーか、どう考えたって鼻はウケ狙いじゃん!」
「みんながクマを置いてくから、ヒマすぎてこんな事になるクマ!」
千枝は雪子にそう突っ込みを入れる。その言葉に反応して、クマは口を尖らせた。陽介は苦笑いを浮かべる。
「ま、まあでも、天城が元気出たみたいでよかったよ、うん…」
「ち、千枝の、かお…ぷっ…ははは、おかしー!ツボ、ツボに…う、ぷぷっ、くるし、お腹いたい、あはは…」
雪子の爆笑は止まらない。どうやら今日は外に出て解散したほうが良さそうだ。
たちは雪子の様子に呆れた笑みを浮かべながら、雪子をつれてテレビの外へ出ていった。
2011.06.18