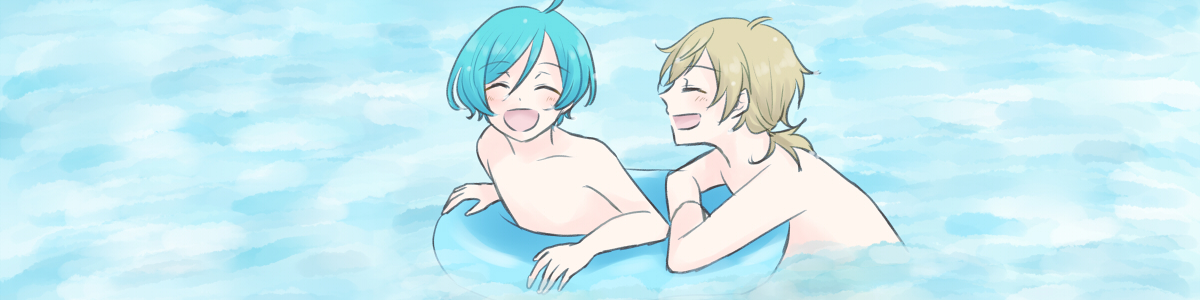midnight call
第9話
「相棒?親友?仲間?くっだらない」
「?」
「…え?」
突然聞こえてきた声に、たちは振り返った。にとって聞き慣れた、しかし聞き慣れていない声。そして、見慣れた姿がそこにはあった。
「あ…っ!」
「しゃ、シャドウクマ!!」
は思わず後退りをする。なぜならそこにいたのは、自分だったからだ。
この世界で自分と同じ姿の人間が現れるということ。それはつまり、自分の影、自分のシャドウが現れた、ということだ。
目の前にいるは、影という証拠である金色に輝いた瞳を細める。口はつり上がり、嘲笑を浮かべていた。
「相棒とか仲間とか、どうせこの場限りでしょ?事件が解決したら、はいさよなら。親友だって、ただのうわべの付き合い。どうせ相手のことなんかどうでもいい、自分を立てるだけのただの道具」
の影はそう吐き捨てた。何を言っているのだ。は自身の影の言葉が理解できずにいた。そんなの様子に気づき、影は更に顔を歪める。
「意味わかんないって?思い出してごらんよ!中3の、卒業前のことを!あたしが引っ越すって知って喜んでたやつのことを!」
「っ!」
影の言葉に、は目を見開く。その出来事には覚えがあった。思い出したくない、過去の出来事。
「あいつ、影で『いなくなって清々する』って言ってたよねえ…親友だと思ってたのに!!」
「やめて…」
は耳をふさいで拒絶を示す。しかし、それだけで影の声が遮断されるはずはない。影の言葉は次々との頭に入ってきた。
「所詮あいつは自分を立てるためにあたしを利用してただけ。周りのやつだってみんなそう。誰も悲しむやつなんていなかった。あたしを利用していただけだったんだ。それで知った。友情なんて所詮、幻想だって!」
「いや…」
の制止の声など影の耳には届かない。の影は言葉を重ねていく。それはどれもにとって聞きたくないものだらけだった。
「だから、遠くに引っ越してゼロの状態で高校に入ってもろくに友達も作らなかった。人見知りが激しくて消極的だから仲いい子ができなかった?嘘ばっかり!ほんとは自分で壁をつくって誰も寄せ付けなかっただけ。馴れ合うなんてバカらしいってね!」
「ち、ちが…」
が否定の言葉を発して、ようやく影が反応を見せる。影はわざとらしく首をかしげてみせた。
「違う?どこが?自分からは誰にも近づこうとしてないくせに。誰かと仲良くなったところでどうせまた裏切られるってね!」
「やめて…もうやめてよ…」
「あーあ、ほんと、仲間ごっことか親友ごっことか、くっだらない。バカじゃないの!?」
「やめて…!」
は強くそう言う。の影は、わけがわからないとでも言いたげにを睨んだ。
「何で?これがあたしの本音。そうでしょ、あたし!!」
「ちがうっ!!」
「!ダメだっ!!」
陽介はの言葉を遮ろうとする。も頭ではわかっていた。しかしとまらない。は勢いのまま叫んだ。
「あんたなんか、私じゃないっ!!」
急に影は笑いだし、影から黒いもやのような何かが広がる。の視界は一気に真っ黒に染まった。意識が遠くなっていく。
そして、はそのまま気を失った。
頭に声が響く。随分と久しい声だ。
『、引っ越すの?』
『うん、親の都合で、卒業したら遠くに…』
『そっか、寂しくなっちゃうね…』
ああ、あのときの記憶だ。は思った。思い出したくなかった、つらい記憶。
寂しくなっちゃう、なんて嘘だ。記憶の中の親友に向かっては頭の中で言った。するとまた、別の声が聞こえてくる。
『引っ越すってさ』
『聞いた聞いた。どうよ?』
『やっとあいつから離れられて清々するに決まってんでしょ。この3年間どんなにウザいと思ってたか。いっつもあたしにくっついて、何をするにもあたしと一緒。ほんと、ウザかった』
の頭にその忌々しい会話が鳴り響く。かつて親友だと思っていた相手の、はっきりとした拒絶の色を見せたその言葉。当時、はその会話を偶然耳にしてしまったのだ。
『の取り柄とか、勉強しかなかったよね。勉強を教えてもらうときしか役に立たなかったとか、ほんとないわー』
『ほんとほんと。一緒にいるならもっと役に立てよってね』
この会話に、は絶望した。今まで仲良くしてくれていたのは、全部嘘だったのか。私を拒絶しなかったのは、勉強だけのためだったのか、と。
そのときから、人が信じられなくなった。元から内向的で友達をつくることが苦手だった。しかし、高校に入って新しい友達ができても、あのときの記憶が頭にちらついて、本当に自分は好かれているのだろうか、嫌われてはいないだろうかと以前以上に疑ってしまうようになったのだ。そして壁を作ってしまい、誰ともそれ以上仲良くなることはなくなってしまった。
「う…」
「あっ!ちゃん!」
急に意識がはっきりして、は目を開いた。倒れていた体を起こす。体が重い。
「大丈夫?」
千枝はまっすぐを見る。はすぐに気を失う直前の出来事を思い出した。そして影の存在を再確認する。あれを全部、皆に見られてしまったのか。は俯き、拳を作った。
「…つらい思い、してきたんだね」
不意に、頭に重みを感じた。は思わず顔を上げる。目の前の千枝は、悲しそうな顔を浮かべていた。頭の重みは、千枝の手だ。
「そんなことがあったら、人を信じられなくなるのもおかしくないよ。友達に壁を作るのも、くだらないって思うのも」
「でも…」
は顔を歪める。それを見て、は口を開いた。
「そういう面だけがの全てではないだろ」
「この世界で一緒に天城を探した時間は決して長くはない。でも、この短時間でも、ちゃんとわかったぜ。は他人想いの優しい、いい奴だよ。それは嘘じゃない、本物だ」
そんなことない、とは否定する。そんなことあるよ、と陽介も首を振った。
「ちゃんの影はくだらないって言ってた。でもそれは、過去に信じてた友達に裏切られて、人が信じられなくなったから、だよね?」
「あたしたちは裏切らないよ、絶対。事件とかペルソナとか関係ない。ていうかあたしもやな部分見られちゃったし、離れるのも今更っしょ」
皆からのあたたかい言葉に、は堪えきれずに涙を流す。皆はこんなに自分を、自分の影を受け入れてくれているのだ。影が言ったことだけが本音ではない。そう言ってくれた。自分も認めて、受け入れよう。は決心をした。
「…友達を作るのがこわくて…気づいたら心のどこかでくだらないって思うようになってた。それを、今まで見ないふりしてた…ごめんなさい…あなたも、私だね…」
がそう言うと、影は頷き、輝きと共にのペルソナに変化して、その場から姿を消した。
「雪子…大丈夫?ホントにケガとか無い?」
「うん…ちょっと、疲れただけ…」
たちはテレビの外へ出て、一旦フードコートで落ち着くことにした。雪子をベンチに座らせ、休ませる。
雪子はこう言っているが、疲労は相当溜まっているのだろう。は思った。メガネをかけていた状態で自身の影を暴走させてしまっただけでも、ひどく疲れてしまったのだ。メガネのない状態で数日間ずっとあの世界に居続けた上、シャドウを覚醒させてしまったとなれば、疲労はのものとは比べ物にならないはずだ。
「なにか思い出したことはある?」
はそっと雪子に声をかける。雪子は少し思考を巡らせていたが、暗い表情を浮かべ、俯いた。
「うん…何も思い出せなくて…ごめんね」
「いいって、いいって!雪子無事だったんだから、十分だって」
「そうだな」
そもそも、疲労しきったこの状態で思い出すことのほうが難しいのだろう。雪子が無事だったのならば、それでいい。
「けど、天城が今までの二人と同じ手口で、その…殺されかけたってのは、間違いないよな」
陽介は言いづらそうに口を開く。そして、考えを巡らせながら言葉を繋げていった。
「それと、マヨナカテレビに映ってたのは、本当の天城じゃなく“もう一人”の方だった気がする。天城が現実で抑え付けてたモンがあっちの世界で現実になった…って事なのか?」
「そういえば、クマくんもそんな事言ってたけど…」
たちは推理しようと必死に頭を動かす。しかし、現状ではわからないことがあまりにも多すぎる。陽介は頭をかき乱した。
「あーダメだ。ますます分っかんね。犯人って、一体どんなヤツなんだ?」
そう唸る陽介を見ながら、も眉を寄せる。にも見当がつかないのだろう。そして、諦めたようにため息をついた。
「とりあえず、今日はこの辺にしようか」
「うん、難しい話はまた今度にしよ?雪子、早く休ませたほうがいいし、あたし、家まで送ってくからさ」
その言葉に、陽介ははっとする。どうやら推理に夢中になりすぎて、雪子の体調のことをすっかり忘れてしまっていたらしい。申し訳なさそうに雪子を見た。
「そうだよな…悪い。天城の疲れ、ハンパじゃないもんな。ていうかもか…」
「え、わ、私は大丈夫だよ。メガネかけてたし」
急に話をふられて、は咄嗟に両手を振った。しかし、気を遣われるほどではないとは思ったが、疲れが溜まっていることは確かだ。
「でも、ちゃんも早く帰ったほうがいいよ。ね、途中まで一緒に帰ろ?」
千枝は雪子を立ち上がらせながらそう言う。雪子も救出したことだし、この様子だと今日はもう解散なのだろう。は素直に頷き、と陽介に別れを告げて、雪子を支える手伝いをしながら一緒に帰宅することにした。
家に帰ると、は真っ先に自室のベッドに倒れるように飛び込んだ。疲れがひどい。これ以上動きたくない。リビングのほうから母親の声が聞こえてきた気がしたが、疲労による眠気に襲われ、それに抗えずには目を閉じてそのまま眠りについた。
翌朝、は体の重さに耐えながら学校に向かった。テレビの中に入った日はいつもだるさを感じていたが、やはりシャドウを暴走させたときの疲れは半端ではなかったらしい。
「ちゃんおはよう!」
「あ、おはよう」
教室について席に座ると、すぐに千枝も登校してきた。千枝は自席の椅子に座り、後ろを向く。
「体、大丈夫?」
「ちょっと、だるいかな…」
「やっぱりそうだよね…」
千枝は苦笑する。恐らく千枝も、自身の影を出してしまったときの疲れは尋常ではなかったのだろう。
「雪子ね、やっぱり相当疲れてるみたいだから、しばらく休ませることにしたよ」
「うん、そうだね」
雪子の疲れを考えると、そうしたほうがいいだろう。は頷いた。
はふと昨日の出来事を思い出す。自分の嫌な部分を見てしまい、それを皆にも見られてしまったこと。あのとき皆はそんなを受け入れ、なおも友達であり続けてくれた。しかし、今改めて考えてみると、やはり、本当に受け入れてくれたのだろうかという不安の方が勝っている。あの場の勢いで言ってしまっただけなのではないのか、と。
「ね、ちゃん」
そう考えていると、不意に千枝から声がかかる。は自然に俯いてしまっていた顔を上げた。
「ちゃんのこと…“”って、呼んでいい?」
「え?」
千枝の唐突な発言に、は思わずきょとんとした。その様子を見て、千枝は慌てて両手を振る。
「あ、や、嫌だったらいいんだけどね、うん」
「ぜ…っ!全然嫌じゃないよ!」
「ほんとっ!?」
がそう言うと、千枝の表情は一気に輝いた。ずいぶんと嬉しそうな顔だ。
「じゃあ、これから“”って呼ぶね!も“千枝”って呼んでいいからね!」
そう言われ、は嬉しいような困ったような表情を浮かべる。そういえば、生まれてこの方友達を呼び捨てで呼んだことはなかった。
「えっと…ち、千枝」
は呼び捨てで千枝の名前を言ってみる。しかし、案の定呼び捨ては何とも変な感じがした。
「…ちゃん」
「あはは、無理に変えなくていいよ!」
苦笑してそう付け足すと、千枝も笑った。どうやらに呼び捨ては無理のようだ。
「おーっす。お前ら何してんの?」
「お、花村にくん」
そんなやり取りをしていると、陽介とも席にやって来た。は二人に挨拶をする。体は大丈夫か、と訊ねられたので、大丈夫だと伝えた。
「お互いの呼び方についての論議!」
「論議って…何だそりゃ」
千枝が胸を張ってそう言うと、陽介は吹き出す。バカにしたなー!と怒る千枝に、別にバカにしてねーよ!と陽介は返していた。
皆のこんな雰囲気が好きだ、と陽介たちのいつもと変わりないやり取りを見ながらは思った。彼らのあたたかなこの中に、自分も入っていいんだと思うと、嬉しくて仕方がなかった。
2011.06.11