|
更新したのでCtrl(コントロール)ボタンを押しながらF5を押してください
公務員がアルバイトをしてよいのか、という疑問があろう。よく調べると、私の場合、校長に届けておけば違反ではない事が分かった。
都立杉並工業高校に異動となったとき、私自身はアルバイトや、はては評論家になるなんぞ夢にも考えた事はない。杉並はよい学校だとの噂で希望しただけである。
杉並に異動後の1972年のある日、府中工業で担任をした清水章男君がソニーに受かってオーディオ関連で大活躍していた時のことだ。清水君から電話があり、「先生、僕の記事がNHK出版の『電波科学』に載りました。読んでください。すぐ送ります」、「え!そうか。それはよかったなア」。
翌々日か、その雑誌が届いた。私は相対論の本と、オーディオ関連の雑誌は『ラジオ技術』と『トランジスター技術』しか読んでなかったので、清水君の記事が電波科学に載ったことは知らなかったのだ。読むと各社自慢のオーディオ関連ヒット商品の特集で、彼がソニーの代表として記事を書いたのだ。上司からの指名で記事を書いたわけだが、それだけ彼がオーディオ関連で優れていたことの証明でもある。
すぐ清水君から電話があった。「どうですか?」、嬉しそうに声を弾ませて言った。「いいね、いいね。出世したナア」と言うと、「そんなことありません、先生のお陰です」と、謙遜した様子が分かる。「ところで先生、先生を紹介しますから、アンプを作って投稿したら、いかがですか」と、思いもかけない言葉が飛び込んだ。「編集長は谷さんという人ですが、窪田先生は僕の恩師である事やアンプ製作では右に出るものはいないと思いますと、紹介しておきますので、先生から相談してみてください」と言う。
嬉しいこと、この上ない。早速、谷編集長に「拝啓、本来なら、お会いしてお話すべき事柄ですが、・・・」との出だしで、清水君のこと、自分はオーディオアンプの設計・製作に興味のある者であること、出身は東京電機大学であることなどを書き綴って手紙を出した。
すぐ返事がハガキできた。内容ははっきり覚えている。「世の中、真空管から半導体に移ったのに、いまだにオーディオアンプは真空管の記事が多い。若い人の進出を期待している。トランジスターアンプの設計の基礎と、そのアンプ製作記事を書いて送ってください。400字詰め原稿用紙20枚以内、図面数枚」という具体的な要望まで書いてあった。
これが私がオーディオ界にデビューするきっかけである。
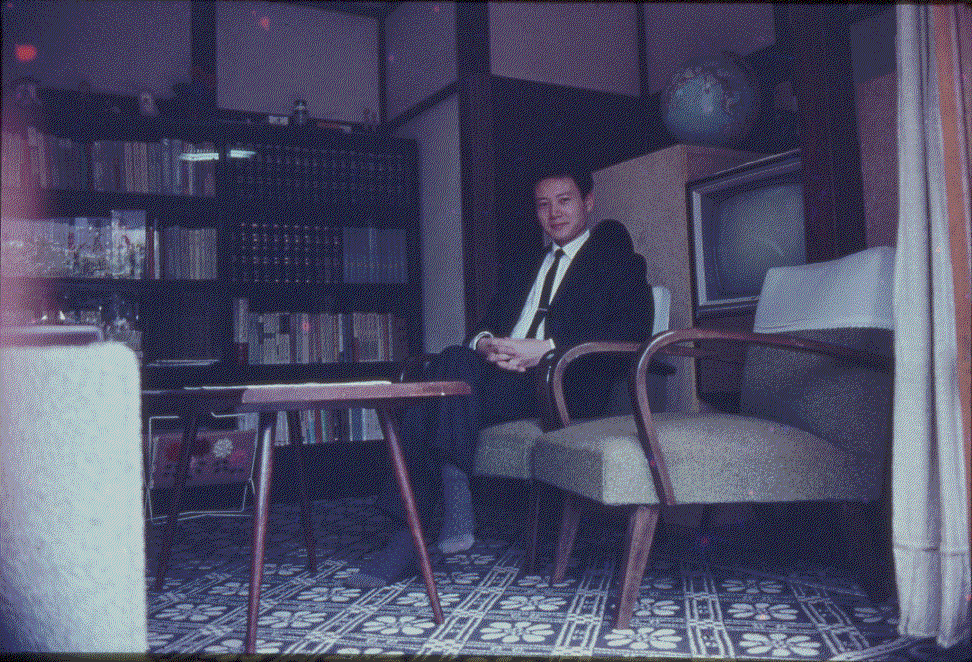 写真:武蔵小金井の借家にて。結婚する前の年だったから26歳。私の後部に見えている大型スピーカー ↑ (立ったら私の顎の辺りまである)は、府中で担任をしていた時、清水章男君に手伝ってもらいながら自作したスピーカー。駆動するアンプも自作だった。清水君はソニーを受験して合格。オーディオ関連で大活躍して業績を残した。 写真:武蔵小金井の借家にて。結婚する前の年だったから26歳。私の後部に見えている大型スピーカー ↑ (立ったら私の顎の辺りまである)は、府中で担任をしていた時、清水章男君に手伝ってもらいながら自作したスピーカー。駆動するアンプも自作だった。清水君はソニーを受験して合格。オーディオ関連で大活躍して業績を残した。
ずっと後のことであるが、その一つに車載用のCDプレーヤーで振動に強い構造を開発した事が上げられる。誤解を招くといけないので追加するが、清水君一人で、そんな大それた事が出来るわけではない。ソニーの開発技術陣とフィリップの共同開発である。現在の車載用DVDプレーヤーの原点となった。
書棚にアインシュタインの書いた「The Meaning of Relativity 3rd ed.」1950年/Princeton University Press が見える。
話を戻そう。一ヶ月くらいかかっただろうか、精魂込めて作ったアンプと原稿を持って、宇田川町の日本放送出版協会まで行った。すでに僕とコンビを組む編集部の人が決まっていた。富田さんという同年輩の青年だった。十年以上のお付き合いが始まった。
この原稿が採用され雑誌に載ったのは1972年8月号である。その後は毎月のように原稿依頼がきて書いた。やがて、オーディオ評論も書かないかとの薦めがあった。もちろん承諾した。『電波科学テストルーム』というタイトルの、各社の新製品のテストをする。実際に測定器を使って特性も書く。メーカーにとっては厳しいページだ。毎月十年以上やった。
その間にアンプの製作記事もある。ヤマハの開発したV−FETという三極管特性を持つ半導体出力段のアンプを製作したのは世界で僕が初めてだろう。ヤマハでは私の回路とは異なる独自の回路で、素晴らしいアンプを商品化した。音質は私のものより良い。負けたって感じだ。
しかし、この頃になると<窪田アンプファン>という言葉が独り歩きし始めた。嬉しい。
評論記事やアンプ製作だけでなく、CDの開発も富田氏と一緒に追っていった。CDはソニーとフィリップスの共同開発したものだが、開発初期のDAD(デジタル・オーディオ・ディスク)から電波科学では富田氏とコンビで取材を続けて掲載していった。1978年頃からだ。拙著「すぐに役立つビジュアルシステム応用百科」1988年12月27日発売/誠文堂新光社刊から抜粋であるが紹介すると、最初compact disc(CD)を発表したのは1979年4月、オランダのフィリップ社であったが、これは直径11.5cm/60分であった。しかし、ヘルベルト・フォン・カラヤンが「ベートーヴェンの第九交響曲全曲が入るようにしてくれ」と要望したため、CBSソニーの強い意見もあり、結局直径12cm/74分40秒になった。
ちなみに「ベートーヴェンの第九交響曲」の演奏時間は指揮者や楽譜の取り方によって様々で、多くの従来のLPレコードや演奏会の時間を調べると最大74分である。
74分40秒というのは “規格” であり、最近の録音可能CDブランクディスクは80分くらい入る。ただし、これは規格外だから、再生出来ない場合もある、という事を承知しておく。
最終的にはCDは、プレーヤーも同時に、1982年10月1日、全世界一斉に発売されたものだ。そのときの第1号ディスクが手元にある。いい音だ。ただしプレーヤーは残念ながら10年ほどで故障した。
じつはレーザーディスク(パイオニアの登録商標/この信号はデジタルではない。アナログである)は、CDより一年早い1981年の発売で、これも電波科学が追い続けて記事にしていた。富田氏とのコンビは1985年まで続いた。
時代は変わっていくものだ。コンピューター時代に入って行く。電波科学も発展的廃刊となり、名称が『エレクトロニクスライフ』となり、編集長も代わった。私の記事も激減。無くなったわけではないが、コンピューター関連の記事が多くなった。
私の記事が激減したのを知ったMJ誌の当時の編集長大泉さんが、私に目を付けた。「MJで書いてくれないか」ということだ。もちろん私は「エレクトロニクスライフ誌」から依頼があれば書くが、MJ誌で製作記事が書けるので、すぐ承知した。
余談だが、私がMJ誌に移った事を知った読者が約五千人、一斉に「エレクトロニクスライフ誌」(旧電波科学)からMJ誌に移った事が綴込みアンケートハガキで分かったそうである。
この頃は「音楽の友社」や「ビデオコム」、その他多数の原稿依頼が舞い込んで最も忙しい寝る暇のない頃だった。
次の写真は富田さんと札幌にカートリッジの専門工場がある品川無線(グレース)に取材に行った時、品川に本社がある朝倉社長ともご一緒だったので、取材が終わったあと、一緒に大倉山のスキージャンプ場(標高307m)に立ち寄った時の写真である。札幌の街が一望できる。
ここは1972年冬季札幌オリンピックのジャンプ場として有名だが、じつは創設されたのは古く1923年であった。現在は札幌最大の公園になっているが、スキー選手がジャンプの練習をしている時は公園は閉鎖される。
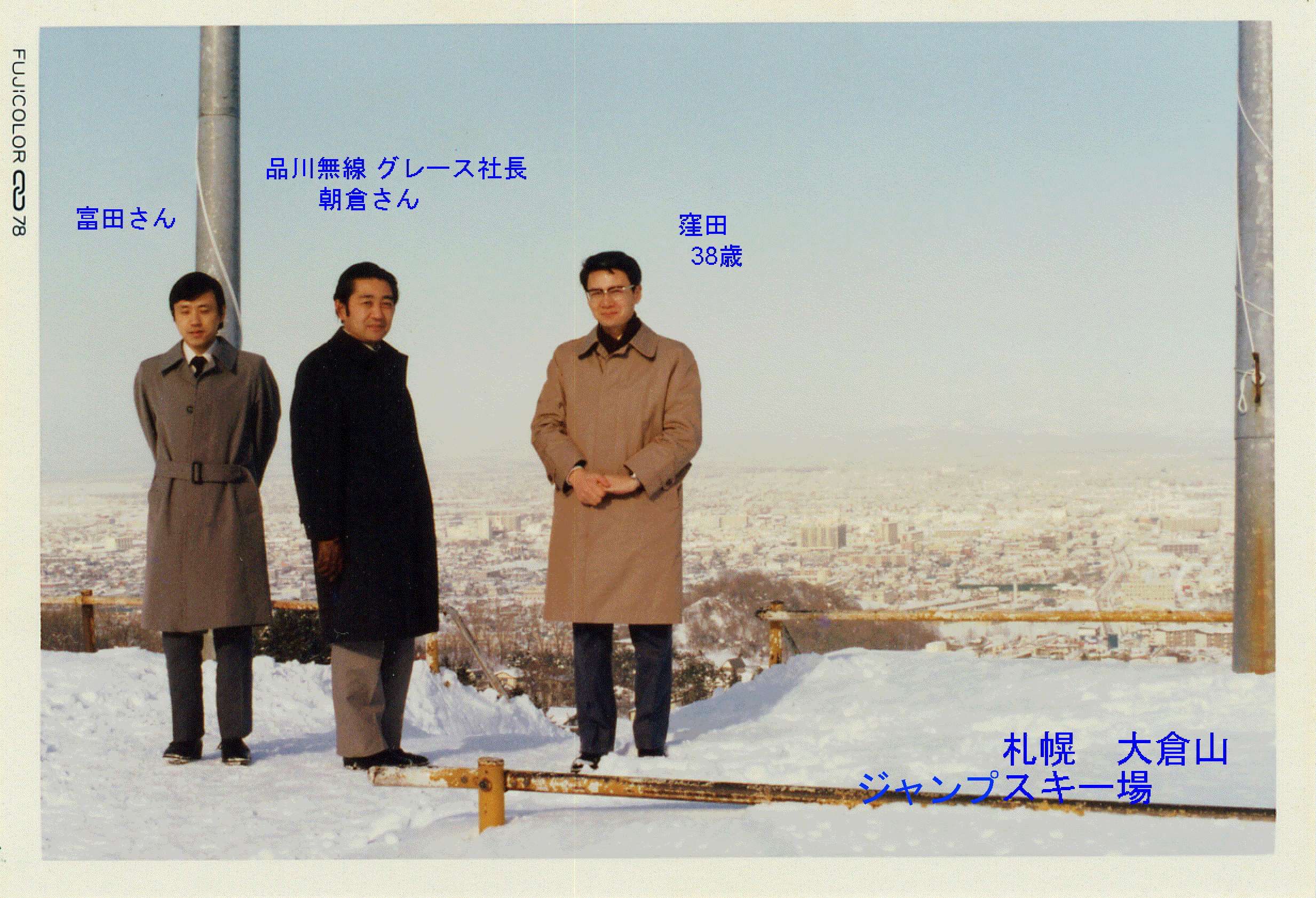 札幌の街が一望できる 札幌の街が一望できる
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
もう少し前、30代〜に戻ろう。都立杉並工業高校の教師生活は楽しかった。校長や教頭先生も含めて先生方のレベルが俄然高い。
私は都立は次に述べる学校で計三校経験したが、最も良かった。生徒の学力や質も他二高より遙かに高い。私が二足のわらじを履いていたのはみんな知っていたが、それを恨んだり、妬んだりする先生は一人もいなかったと自分では思っている。むしろ生徒諸君から慕われている様子を見て、私を尊敬してくれるようにも感じた。
嬉しい思い出を書かせて戴きたい。上述したようにCDは1982年10月1日、全世界一斉に発売されたが、9月初めには、既に私は知っていた。そのため新学期9月初めの職員会議の際、終了した時点で数分間、私の話を聞いてくれませんか、と前もって司会者に頼んでおいたので、このCDの事を説明させてもらった。
従来のLPレコードも持ち込み、2つを両手に持って、「こちらが従来のアナログLPレコード、こちらが来月10月1日に全世界同時発売される予定のデジタルによるコンパクトディスク、略してCDとよばれるレコードです。LPレコードは片面30分〜40分程度ですが、このCDは裏面はなくて、表だけで74分40秒入ります。そしてLPレコードはキズが付きますね。そしてノイズもパチッパチッと出ます。でもこのCDは表面が透明なアクリル膜で保護されていてキズは付きません。もし内部までキズが付いても、小さいキズならば音楽信号がデジタル化されているので、前後の信号をうまく繋ぎ合わせる信号を自動的に作ります。これはソニーの特許ですが、オランダのフィリップス社と共同開発したものです」などと説明しながら、CDをわざと床に転がしてみたりした。・・このCDは第1号ディスクだったので、やや心配だったが(*^_^*)。
「LPレコードは針で音楽を取り出しているが、それはどうなってるのかね」と聞かれた先生もおられた。
「レーザー光線です。その反射で音楽信号をデジタル化した1と0を読み取るようになっています」と説明したが、多くの普通科の先生方は<難しい>という顔をなさっていた。無理もないと思う。まだデジタルという言葉がこんにちのように普及してなかった時代だから。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
女子は毎年何人かはいたが、ある年10人ほどいたときのある日授業中ぺちゃくちゃと雑談をやめないので「うるさい!口にチャックを付けろ!」と怒鳴って怒ったことがある。こういう事があっても、遠足や修学旅行では、担任でもないのに、いつも私にくっついてくる。男子も含めて20人ほどの記念写真が、手元のアルバムにあるが、女子生徒が私の腕を組んでいる。ほかにも可愛い子が腕を組んで私の肩に頭を乗せている写真がある。男の子が入ろうとすると、それをはね除けて、腕を力一杯組んで、私にくっついている写真もある。修学旅行の時のものだ。三十代中頃だ。もちろん上記三人の女子生徒の名前は写真を見て思い出すが、意外とその時の情景を覚えていない。アルバムを見て「あア、こういう事もあったんだ」と、遠い昔に想いを馳せる。
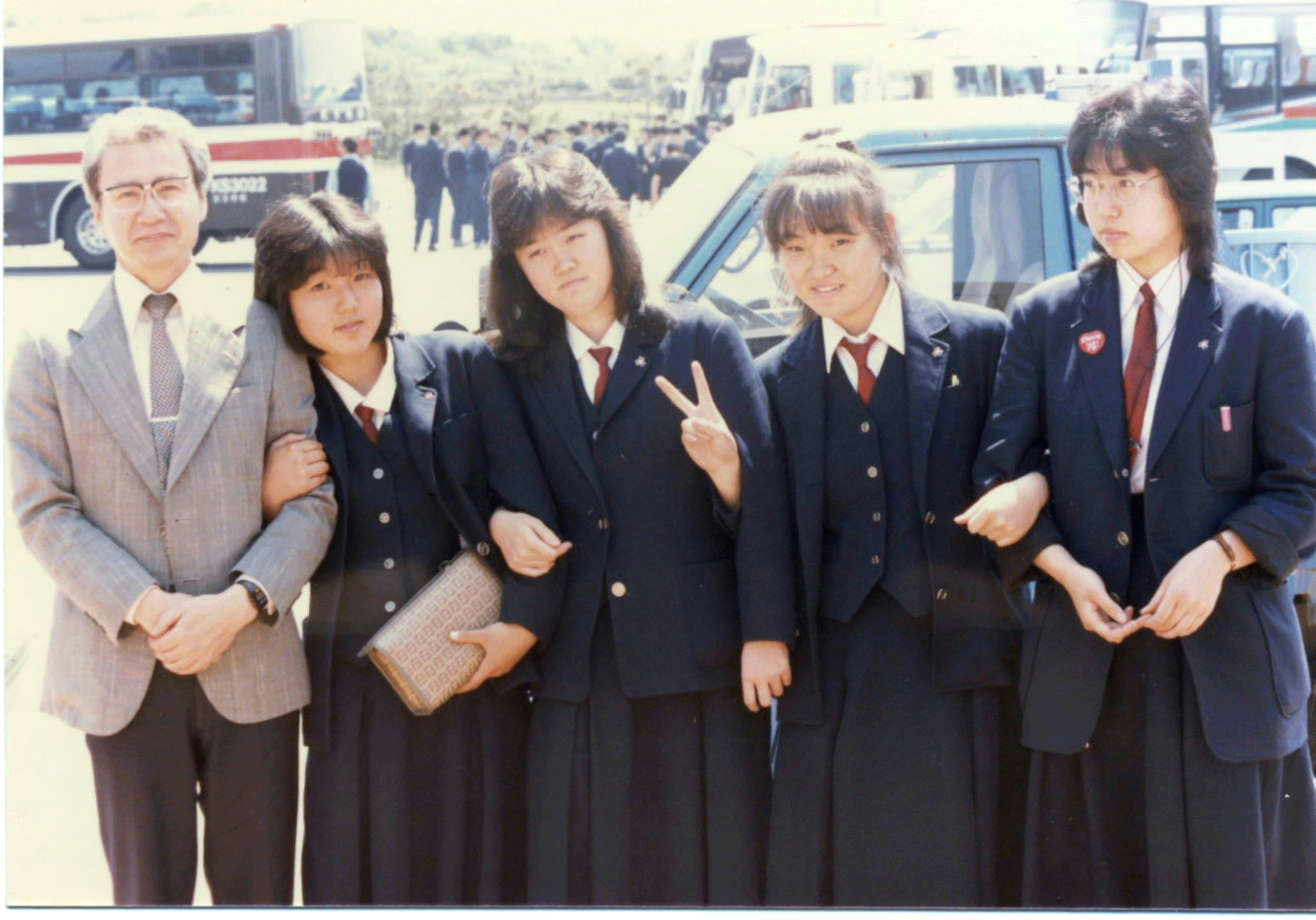
一件だけはっきり覚えている事がある。これは忘れられない。上述の修学旅行は四国の金比羅宮、屋島、栗林公園、岡山に来て鷲羽山、後楽園などであったが、岡山で宿泊する時、かなり長時間の自由時間があり、男女数人が「先生の育ったおウチや景色を見たい」と言い出して、「恥ずかしいなア」と照れたのだが、どうしても行きたいと言うので、バスに揺られてウチまで来たことがある。
「ここに高校までいたんですね」と感激する生徒や、庭の木々に触って離れない子がいたり、全員がうっとりしていた。
「子供の頃よく遊んだ丘に行こう」と畑道を登って広い丘の上に連れて行った。そこからの景色にみんなびっくりして、
「わ〜」と歓声を上げた。<都会の子だな〜>と、みんなを愛おしく思った。
「海が見えるだろう、あれが瀬戸内海だよ」
「その向こうに見えるのが四国だ」
「屋島にも行ったよね。こっちの方向なんだ」と真南を指差して「残念ながら途中に島があって屋島は見えないんだ」とも説明した。
みんな「来て良かった」と興奮していた。ある女子生徒が「栗林公園も綺麗だったけど、あれって造られた美しさよね。
でも、この景色って自然よね。自然のままの田園風景で、きらきら光る川もあって、あれって魚が飛んでるんじゃなくって。
この広い丘、後ろは山、先生、こんな自然の中で育ったなんてうらやましい」と、詩人のような感想を語ったのが印象に残っている。ぼく自身も<連れてきてよかった>と安堵の念でいっぱいだった。
しばらくして、母から聞いた話であるが、ぼくが先頭を歩いて丘に登っている時、後方の2〜3人が、畑で農作業している人に、「こんにちは」と声をかけて挨拶したそうだ。そして、その農家の人、何人かが生徒達の挨拶に応えたあと「一番前の人は、たかしちゃんじゃろう、いま挨拶したのは生徒さんじゃなあ、都会の子は偉いのオ」と話し合ったそうだ。修学旅行の途中だった事などを母に説明したが、たまらなく嬉しくて涙が出た。
追加:次のメールがきましたので、要旨を載せておきます。
「初めまして、僕は○○大学の学生で、経済学部なので相対論には縁のない者ですが、僕が岡山の出身であることを知っている友人が先生のホームページの自伝を紹介してくれたので、拝読しました。先生のお人柄がにじみ出ている文に感動しました。僕も卒業後は故郷へ帰って高校の教師になりたいと思います。先生ほどの人望の厚い教師になれるか心配ですが、努力します。ところで余計な事ですが、修学旅行の時、生徒さんが先生の生家を訪ねた話も感激しました。その時のルートを教えてくださいませんか。帰省したとき、僕も車で行ってみたいのです。修学旅行の時の生徒さんの人数や服装、お家(うち)に入ったのかどうかまで、立ち入った事で恐縮ですが、教えて下さると、僕には一層の糧になります。どうか宜しくお願い致します」
窪田:嬉しいお便り有り難うございました。
岡山からのルートですが、生徒たち(男子2名、女子3名/学校の制服)と一緒に来たのは、岡山〜赤穂線で西大寺駅〜南回り牛窓行きバス〜途中の吉塔(きとう)で下車です。村の人に訊けば「あそこだよ」とすぐ教えてくれると思います。
生徒たちと行った時は、すでに弟は結婚していて、私の家ではなかったので、家の中には入りませんでした。弟は日立の岡山支店に勤務中、そのヨメさんと父母は“窪田果樹園”をやっていたので、留守だった。
と、こういう事ですが、何十年も前の話なので、バス停も変わっているかも知れないし、父母はすでに他界、弟は心筋梗塞で手術後療養中、果樹園は枯れ木のまま等々、淋しい現状になっています。
余談ですが、俳優の志穂美悦子さん(本名塩見悦子さん)は僕と同じ県立西大寺高校の出身で、この土地の方です。西大寺駅前の交番で聞けば生家を教えてくれるかも知れません。“寅さん” にもマドンナとして出演された女優さんですので、訪れると喜んでくれるでしょう。また、美人画で有名な “竹久夢二生家記念館” も、吉塔に来る県道をもう少し(と言っても30分以上かかるかな)牛窓方向に進めば在るし、風光明媚な牛窓オリーブ園などもあるので、ドライブがてらに行かれたらいかがでしょう。
話を戻すが、私の30代という時代は日本は最も世界に進出し、躍進し、突っ走っていた頃だ。自動車の輸出は世界一、半導体技術もシリコンバレーに恐れられて「日本人は勤勉でよく働く、細かい作業の出来る民族」と世界に工業大国として、その名を轟かせていた。
ちょうど、その頃、中国から “教育使節団” が日本政府に働きかけて、「日本の工業大国の教育現場を視察したい」との要請があり、東京都が都立杉並工業高校を候補の一つにあげた。それで、使節団の第何組だったかは定かではないが、本校を視察に来たことがある。
私も指名された。ちょうど私は通常の授業ではなく、実習で、アンプの動作原理を教えて、実際にオシロスコープで波形を見せながら実習していた時だったが、黒板に得意のプッシュプル回路を書いて説明もした。彼らは真剣になにやらメモを取っていたが、この程度でも当時の中国では珍しかったのだろう。
−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−
十数年以上同じ学校にいると、異動の話が持ち上がる。私はどこにも行きたくなかったが、校長の勧めでは断るわけにはいかない。「王子工業高校から、杉並に来たいという先生がいるのだが、交代で行く気はないかね」と。別に断る理由はないし、お世話になった校長先生に逆らうことはないので、承諾した。
|