
1.自己紹介
6.ひとこと
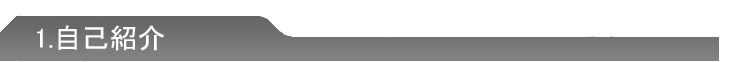

〈本格的に東大をめざした勉強を始めた時期〉
高2秋
〈生活パターン〉
6時頃起床→学校で内職→登下校時に電車で単語など暗記物→帰宅後問題集を解く→12時ごろ就寝
〈各教科の勉強法〉
◎現代文
東大特進で定期的に過去問の添削をしてもらいました。
◎数学
高2(勉強開始時)
基礎がままならなかったのでチャート形式の問題を全て解き、解きながらうっすらと暗記しました(やりながらなんとなく解き方が思いつく程度)。
高2(夏以降)
大学への数学スタンダード演習1A2B,3Cを中心にして問題を多く解きました。
高3
高3に入っても数学の点数が安定しなかったため勉強のやり方を変更し、
問題を解いたらその問題のポイント(偶奇分けをする、多変数だから一つの変数を固定する、対称性に注目する...etc)をまとめ、それをやり方に詰まった時思い出せるようにしました。
◎化学
高2
全範囲が終わっていなかったため学校の教科書傍用問題集を解き、知識が必要となる分野(無機、有機)の暗記をしました。
高3
学校で配られた重要問題集を繰り返し解き、その後化学の新演習を繰り返し解きました。
苦手科目だったのでなんとも言えないですが化学は他の科目より反復練習が必要だと思います。
また、最終的には計算速度や正確さなども重要になるのでそこも意識することも必要だと思います。
◎物理
高2
全範囲終わっていなかったので教科書傍用問題集を力学、波動、電磁気の順に何度か解き、理解が曖昧な点をつぶしていきました。
高3
学校で配られた重要問題集を繰り返しとき、新物理入門という参考書で理解を深めました。
物理は問題をなんとなく解いていて、なんとなく公式を覚えたりしていると見逃しがちになる点が多くあるので、疑問に思ったことがあっあらその場で解決するようにしました。
◎英語
高2(勉強開始時)
単語文法がまったくわからない状態だったので夏休みまではとにかく単語文法を固めました。
使用したものは学校配布の単語帳と文法問題集です。
高2(夏以降)
東大を志望してからは東大形式の問題を解くようにしました。
リスニングはこの時期に開始し、シャドーイングとディクテーションをやりました。
高3
英語に割く時間はあまりなかったのでなまらない程度に東大形式の問題を解きました
高3では理科に時間を割かなければならないので英語は高2までである程度見通しをつけておくのがよいと思います。
〈過去問の利用について〉
◎現代文
東大特進で添削をしてもらい、重要なところのみ復習しました。
◎数学
10月ごろから直近5年分くらいを除き順に解いていき、各問題で重要な点をまとめていきました
◎理科
10月ごろから物理化学のセットで本番同様に時間を測り解きました。
◎英語
夏休みに開始
直近5年分くらいを除いた部分を英語の力がなまらない程度にやった
〈参考書レビュー〉
◎英語
・キムタツ英語リスニング無印・super
…東大形式のリスニングの問題が多く演習できる。また、superの速度に慣れていると多少難化しても点数がぶれなくなる
・河合塾 東大英語(紺色の市販のもの)
…東大形式の問題が多く解ける
◎数学
・駿台、河合の東大模試の過去問
…時間を測って解くことで点数をどういう問題で稼ぎ、どういう問題は捨てるかの練習になる。どの問題も重要な要素を含んでいるので繰り返し解き直してしっかりと身につけることも大事
◎化学
・化学の新研究
…知っていると理解が深まる解説が多く載っており、読み込むのも辞書がわりに使うのもあり
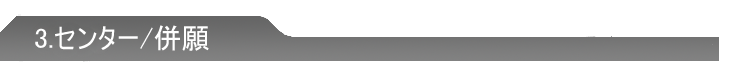
〈併願校とその合否〉
併願校なし
〈センター対策〉
12月初旬までは地理のみを参考書を用いて概要をつかむ
→12月初旬から地理と現代文の過去問を解く
→12月中~下旬からほかの科目もセンターにシフト
→地理は予備校のセンター模試過去問を解いた
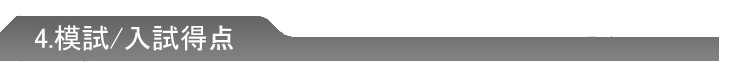
夏駿台C 河合A
秋駿台A 河合A
〈センター得点開示〉
計785点
〈東大得点開示〉
数学65
英語86
国語35
物理30
化学32
総合248
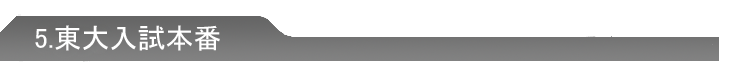
〈自分の受験会場こんなところでした〉
自分の行った受験会場は理系の受ける教室で1番大きい教室で試験開始前にカメラのフラッシュや音で気を散らされる可能性があります。
室温は特に問題なかったですが必ず温度調整のできる服装で行きましょう。
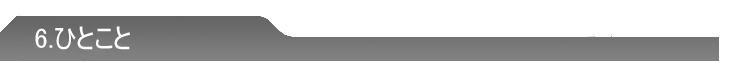
自分は勉強開始時点ではとにかく周りの優秀な人たちより一歩も二歩も遅れているという意識を持ち、どうやって差を埋めるか考えながら勉強を進めました。よほど才能がない限り小さいところの積み重ねで簡単に抜けるし抜かされます。心配ならばやれるだけやりましょう。油断は禁物です。最後まで気を抜かずに。