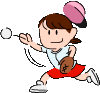リスクマネジメントの心得7カ条 (2007年8月sportjustより)
1.子どもの心身の安全第一
ジュニアスポーツの指導で一番大切なのは、「子どもの心身の安全を守ること」。活動中のどのような場面でも、
これを第一に考えて指導するようにしましょう。
2. 施設、設備、用具。器具の安全に気を配る
グランドが荒れていないか、道具の劣化が進んでいないかどうか、
施設、設備、用具、器具の安全面をチェックすることも忘れずに。
練習前の安全確認を習慣にするとよいでしょう。
3. 「ほうれんそう」を心がける
子どもの健康状態を把握するために、また、自分の指導法が間違って
いないかどうかを確認するために、子どもや保護者、母集団、他の指導者と連携し、ほうれんそう(報告、連絡、相談)
を心か゜けましょう。
4. 医、科学の基礎知識を身につける
子どもを守ためには、子どものからだにかかわる医学的な知識ゃ、救急救命の知識、トレーニングにかかわる知識
落雷のメカニズムなど自然科学なかかわる知識など、さまさ゜まな知識が必要です。
講習や研修などに積極的に参加して、正しい知識をみにつけておきましょう。
5. 基本的な法的知識を身につける
ジュニアスポーツと法律に関わる「無知」はリスクのもと、指導者にどのような法的責任があるのか。
講習や研修などで必要最低限の知識を身につけ、事故の予防に努めましょう。万が一、事故が
起こってしまい、訴えられてしまったときは、早めに専門家「弁護士など」に相談しましょう。
6. 保険に加入する
万が一の事故に備え、(財)スポーツ安全協会の「スポーツ安全保険」と、(財)日本体育協会の
「公認スポーツ指導者総合保険」に加入することが、リスクマネジメントの第一歩です。
7. 同じ事故を繰り返さない
こ;れまでに起きたジュニアスポーツの事故の事例を集め、その原因などを知り、自分の団で同じ事故を
を興さないように気をつけましょう。
団活動によるトラブル事故
法律用語解説 (スポーツネットジャパンより)
本質的危険性
① スポーツルールは、スポーツ本来の特質と併せて、安全で
楽しく、意義ある活動として推進されているが、スポーツの安全性
とはルール制限内の安全であり、スポーツを行う者同士がルールに
従って事故を起こした場合は、本質的危険の不可避的事故であると
みなされ、違法性が阻却される。
② 本質的危険性とは、スポーツルール範囲内で起こりえる、スポーツ
そのものの危険性の事を示すのだ。この範囲内で起こった怪我などに
かんしては、誰の責任でもなく、そのスポーツに参加するにあたり、
あらかじめ予測でき、それに同意したとみなされるのである。
いわゆる、危険の同意に当てはまる。
③ ただし、スキー場などは、見知らぬ者同士が接近して接触する可能性
は数秒足らずであるから、競技者同士が危険な結果を承諾しているとは
いえないと最高裁判所で判断された判例もある。
④ スポーツルールは、公平に安全にスポーツを行うために必要不可欠
であり、それらをきちんと守るように日々指導することが重要だと考える。
以上スポーツネットジャパン2003年6月 第19号掲載のものより抜粋した。
トラブル
スポーツ少年団の活動中に発生するトラブルや怪我など、予期せぬことが多々発生する、
我々指導者として細心の注意を払いかつ実践していても発生する、
そんなか中2001年8月号のスポーツジャストの36頁にこんな記事が
表題 スポーツ法律相談
ソフトボールの試合中の衝突事故
この試合は年齢40歳以上の男女混成による試合であった、
加害者チームが攻撃中セカンドにいた走者はヒットでサードを回ってホームへ
向かった、被害者である捕手(女性)は外野からのワンバウンドで返球された
ボールをホームベース上て゛腰を落として受けようとしていた、そこで加害者は、
左足を被害者の両足の間に滑り込ませるスライディングをこころみました、
これにより加害者は被害者を転倒させ、左膝後十字靭帯断裂の傷害を負わせた、
加害者が適切な対処をしないため、被害者は3年の消滅時効期間が過ぎる前に
告訴に及んだ、
判決は被害者の主張を支持し加害者に賠償責任がある旨を決定した、
裁判所は、ある試合で許されるプレーの範囲は、その試合の趣旨や参加者によって
変わってくること、
プロスポーツやそれに準ずるスポーツの場合は、激しいプレーが求められ、これに応える
選手の肉体的な条件は同等といえる、きわどいスライディグに対しても負傷を回避する
能力を捕手に期待できるなら、この方法をとったとして過失とはいえないとしている。
こんな記事が載っていますのでじっくりと読んでみてはいかかがでしょうか、
大変参考になると同時に活動方法の再検討が、
たとえルールがあっても許容範囲があること、そして男女は明確に区別されること、
今の世の中何かといえば男女平等が叫ばれる時代にスポーツの世界だけは別もの
らしい、裁判とはこんなものでしょ、
昨今の少年野球も男女混成チームが増えてきている、我がチームにも過去には女子
選手がいたが、決して別扱いはしなかった全て平等扱い(極めて合法的)で大過なく
素晴らしい活躍だった、かえって軟弱な男子より逞しくさえあった、
これからの試合男女混成チームと試合する場合極めて慎重にやらざるを得ない
ような気がするが、これじゃーやる前から負け試合みたいなのだが、
混成チームとは試合が出来なくなるおそれがあるが、?
又判決から得られる教訓として以下が記されていた、
1. ルールに従って安全の確保に努めましょう。
2. ルールを手直しして安全を図りましょう。
3. ルールは安全の要請に支配されます。
例え野球規則等で認められていることであっても場合によっては、加害者、被害者
になり得ること、
そして団の管理責任者である代表者、監督者、コーチ等の指導者には賠償責任が
及ぶということ、
いわゆる勝負重点主義による落とし穴がそこにある、
我々指導者は心しておく事でしょう、
そんな中でもやはり勝負事は勝たねば、野球は格闘技であることを忘れてはならない、
勝負絶対、根性野球で現在の柔な子供たちを鍛え上げねばますます世の中が
混乱する、
非行の低年齢化がどうの昨年度と比較して今年はどうのと数字遊びをしていては解決
しない、結果が起きてからなんだかんだともつともらしく騒いでみたところで
なに一つ解決しない、
健全育成とは何か、国語の勉強してもなんにも解決しない、なにかといえば
健全育成、健全育成と熟語をならべて机上で話しているが、現場に出て
ほこりと汗と涙にまみれて、あるときは怒り、あるときはほめ、あるときは一緒に悩み、
指導する者、される者が一体にならなければ何にも解決しない、
法律や規則ですべて解決すれば何にもいらない、だからこその健全育成、
一緒になってやることが、健全育成と思う、机上だけで健全育成と言ってほしくない、
真っ向からぶち当たってこその健全育成、
あれやつちゃいけません、これもいけませんそれもだめで何があるんだろう
いかんことはいかん、いいことはそれでいい、
こんな指導を今後とも続ける所存。
平成13年8月23日(木曜日)の日本経済新聞の記事から
日本経済新聞朝刊の13版の中頃にチェンジアップというコラム
で野球評論家の豊田泰光氏の野球には誤審はないという見出し
いわゆる野球の試合中にいろいろ発生する審判のミス、時には試合を
左右しかねない誤審であってもたとえそれが事実であっても
野球での事実は違うという、こんな書き出しがある私も少年野球に関わって
20年程連盟の少年部の審判員である、この豊田氏のような考えの人が
いるから、野球かつまらなくなるし審判に対する不信感が増幅する
誤審はやはり誤審なんです、誤審が頻繁に出る審判員は最早審判として
の資質がないといわざるを得ない、即刻止めるべきです、
我々少年野球の審判員は絶対に誤審があってはならない、なぜか
それは純真に野球に打ち込む少年らに大人への不信感を与えては
ならないからです、
野球に限らず間違いは絶対あってはならないのです、
それを許す風潮が現在の世相を醸し出しているといわざるを得ない、
いかんことは、いかんことなんです、
こんな評論家も最早無用なものではないでしょうか、
兎に角読んでいて無性に腹が立った。