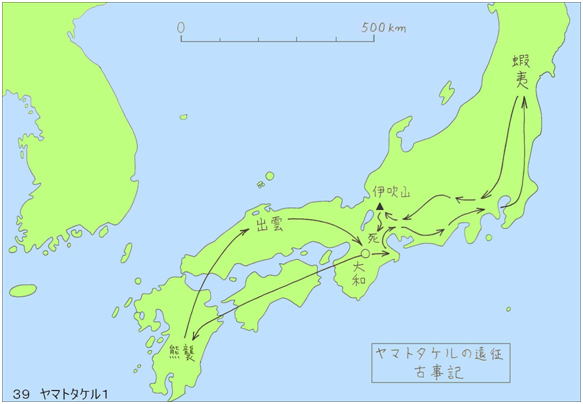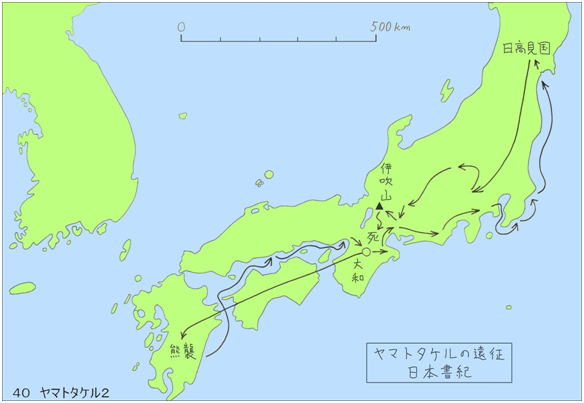19 日向三代(中)
日向国は宮崎県の旧名で、古くは鹿児島県を含む地名でした。そのために、日向三代の都といえば、南九州にあったと思われがちです。しかし神話の日向は、南九州ではあり得ません。福岡をさしています。このことについて考えてみます。
神話によれば、日本列島はイザナギとイザナミが生んだことになっています。つまりイザナギ以前には、この世に日本列島は存在しませんでした。それでは、イザナギ以前の天皇はどこに都を置いたのかといえば、朝鮮半島というほかありません。その朝鮮半島から見れば、九州全体が南海・南国・日向です。したがって神話の日向は、九州、特に福岡をさすと考えるほうが自然です。
イザナギは妻の墓を出雲に訪ねたあとで九州に帰り、ミソギ(禊)をしました。その場所を筑紫の日向の橘の小門(おと)の阿波岐原(あはきはら)といいます。
筑紫は筑紫島(九州)で、日向は福岡地方です。橘は福岡市東区にある立花山のふもとで、橘の小門は多々良川の河口の港をさします。多の津付近です。その港から南へ数キロ宇美川をさかのぼると、粕屋郡志免(しめ)町に御手洗(みたらい)という地名があります。ここには神功皇后が手を洗ったという地名説話がありますが、実はイザナギのミソギ(禊)に由来します。御手洗のすぐ南西に福岡空港があり、空港の東西に博多区青木の地名があります。青木は阿波岐原の名残だと思います。古地図には、青木ヶ原と書いたものがあります。
1812年に書かれた『福岡城下町と博多近隣図』という地図には、「青木ヶ原、比恵川の向、席田郡青木村」とあります。『太陽コレクション・地図・第三号西海道・南海道1977秋季号』(平凡社)の特別附録にこの地図の複製があります。
イザナギは宇美川でミソギをしてから、日向の都に帰ったのでしょう。その都は宇美川の上流、宇美にあったと思われます。
 |
後に邪馬台国が南九州を征服したときに、日向の地名が南九州に移されたのでしょう。その征服は、ホデミ(スサノオ)によって行われました。神話によれば、ホデミには山幸彦という別名があり、その山幸彦が、隼人の先祖の海幸彦を倒したといいます。
山幸彦は、海神の宮を訪ね、海神の助力を得て海幸彦との戦いに勝利し、海幸彦を臣下にしました。この話は、スサノオが魏への使者として成功したあと、南九州を征服したことを暗示します。おそらくその史実から、山幸彦の神話が作られたのでしょう。
『日本書紀』によると、景行天皇が南九州を征服したときに、日向の地名を付けたと書かれています。しかし景行天皇と孝安天皇は、和風諡号が似ているために間違えやすいのです。したがって、この話も本来は孝安天皇(スサノオ)の伝承だと思います。
景行天皇………オホタラシヒコおしろわけ
孝安天皇………オホやまとタラシヒコくにおしひと
『日本書紀』には、日向三代を葬った山の名前が書かれています。福岡地方には、その山とよく似た名前を持つ山があります。
ニニギ……可愛之山(えのやま)……粕屋郡宇美町の井野山(いのやま)
ホデミ……高屋山(たかややま)……前原市の高祖山(たかすやま)
ナギサ……吾平山(あひらやま)……福岡市南区の油山(あぶらやま)
これらの山に本当に墓があるとは信じられません。しかし、三つの山を神体山とする神社が、それぞれの山のふもとにあります。しかもその神社には、日向三代が祭られています。三つの山は日向三代の聖地に違いありません。そこで、このことは「三代の都」と題して、あとであらためて取り上げます。