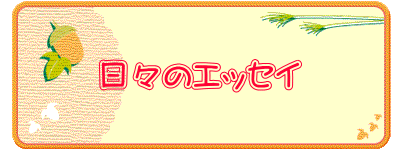
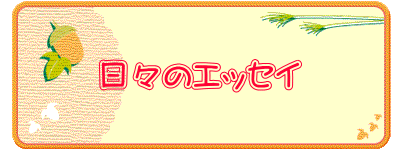
永遠に続きそうだった暑さも、9月に入ると、しだいに和らぎますね。季節はちゃんと巡ってくるものです。
お月見と聞くと、9月の半ばを思い浮かべますが、今年のお月見は来月初めのようです。満月でなくても、涼しくなった秋の夜空は、じっくり見上げてみたくなります。
お月様の絵本といえば、『おやすみなさい おつきさま』が日本でも定番です。
1947年、戦後すぐに発刊されたアメリカの絵本。もはや古典枠ですが、この絵本が出るまでと、出た後のエピソードが綴られた『おやすみなさい おつきさまが できるまで』(評論社)を読みました。
うさぎのぼうやが眠りにつくまでの70分間の様子が描かれた、心落ち着く絵本です。緑色の子ども部屋だけで完結する物語で、一見、同じ絵が繰り返された、間違い探しのような(たとえば、時計の針がページごとに変化している)シンプルな絵本に思えるのですが、実は作者と画家と編集者とで、綿密な打合せが行われていました。
同じ部屋の画面が続いているのではなく、微妙に視点が変わっていて、そのさじ加減が絶妙です。
画家さんは、原案では主人公を人間、しかも黒人の男の子にしたかった、とか、出版されても初めは批判も多かった、など裏話を知ることが出来ます。
うさぎのぼうやが、身の回りの物一つ一つに「おやすみ」と声をかけていく気持ちに共感します。寝る前のひととき、今日の自分を見守ってくれた人、モノたちの存在を一つ一つ確認して、そこにいてくれる幸せに包まれ、安心したいのでしょう。
「おやすみなさい」の言葉は、大切ですね。
「おやすみなさい」が繰り返される日本の絵本としては、『よるはおやすみ』(福音館書店)が好きです。作者のはっとりさちえさんは、子どもたちがワチャワチャ群れる絵で知られていて、このお話でも、たくさんの子どもたちが出てきます。
家族や友だちに「おやすみなさい」を言うだけじゃ飽き足らず、海へジャングルへ、宇宙へと「おやすみ」が広がっていくのが、子どものイマジネーションらしく可愛いな。
夜は、闇とつながり「こわい」感じがするものだけれど、北欧風な明るい色彩のこの絵本が、夜の楽しさを教えてくれます。
みなさんも、お月様を見上げてみませんか?
さて、先月から船橋市郷土資料館で、『船橋のこどもたち展』をやっていて、3階の企画室で私の本が展示されていますので、お知らせまで。
入り口付近には、どーんとD51の車体が設置されています。
館内は、どこも綺麗で涼しい。階段にポスターが貼ってありました。
鈴木真実さんの絵本とともに、私の単行本や絵本、アンソロジーなどを自由に手にとって読むことが出来ます。
江戸から明治、大正、昭和・・・、子どもたちの毎日がどんなふうだったのかが、展示で垣間見られ、「ずいぶん変わったなぁ」と思うところも、「ぜんぜん今と変わってない」と親しみを覚えるところもあり。
昔の子どもの夏休みの宿題。尋常小学校5年ということは、11歳くらいでしょうか? 字が綺麗で、しっかり書いていますね。
好きな給食ランキング。ソフト麺やミルメーク、懐かしい。揚げパンは人気ですね。
着物姿の少女たちの遊びを描いた”すごろく”は、明治43年12月『少女世界』の付録でした。ゲーム機なんて無い時代、年末年始を控えた12月号だからこそ、家族や友人で遊べる付録が選ばれたのでしょう。絵の女の子たちのスタイルを真似る少女たちも多かったのだろうなと想像します。
展示は9月15日まで。
My Funa 9月号に、紹介記事を載せて頂きました。
フルーツ特集の号で、美味しいブドウが食べたくなります。
実りの秋をお迎えください!
2025年 9月
トップページへ
前回のエッセイへ
次回のエッセイへ