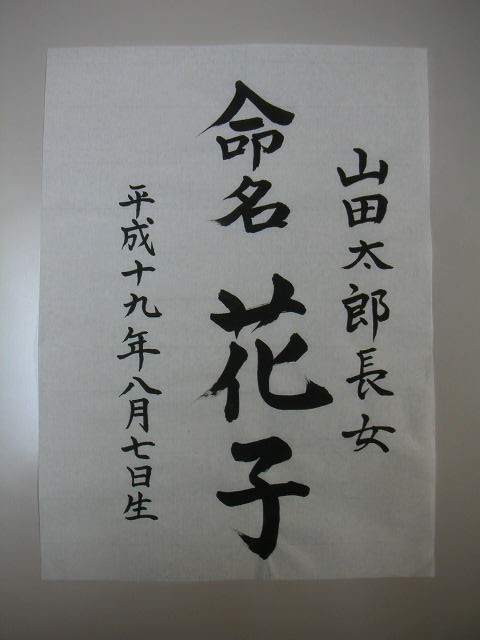
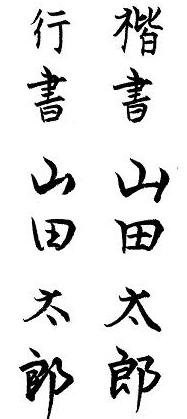
●赤ちゃんのお七夜に毛筆の命名書はいかがですか
身長,体重を書き添えたら一生の記念になりまよ
- ★命名書1000円,ハンコの文字版同一名3点で1000円
- ★郵送代360円(レターパック360郵便)
※お客さまの方で、用紙は歓迎いたします。こちらで用意できるのは,写真の通り,半紙しかありません
返信メールが届いたら
返事メールから書込みしてください
〒住所」へ
| 命名書の一例 | 文字版の楷書と行書の一例 |
|---|---|
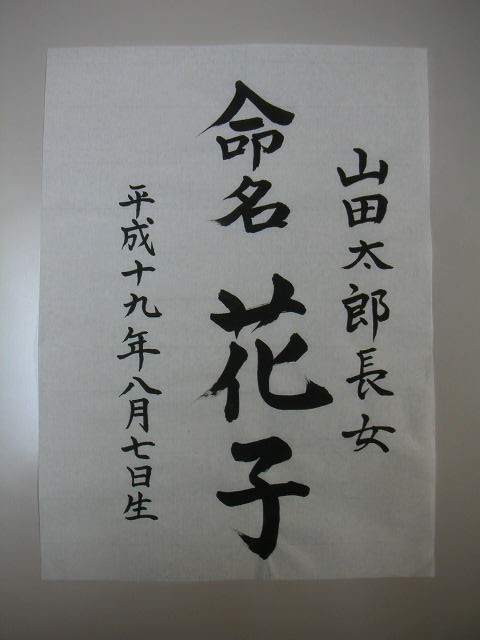 |
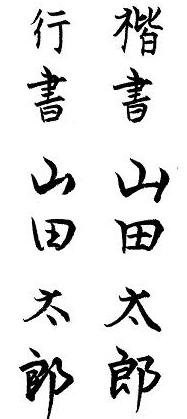 |
赤ちゃんの行事ごと
このホームページは小谷吉秀にて制作し更新もしていますCopyright&Copy2006-2017