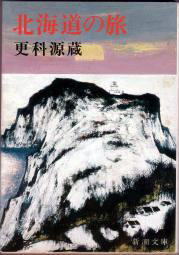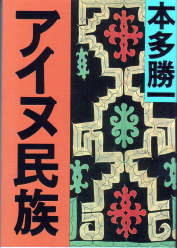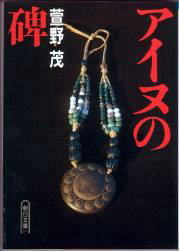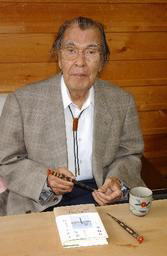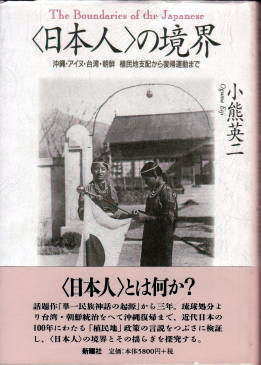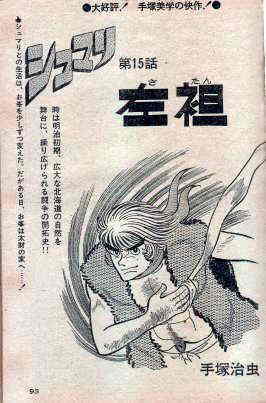 |
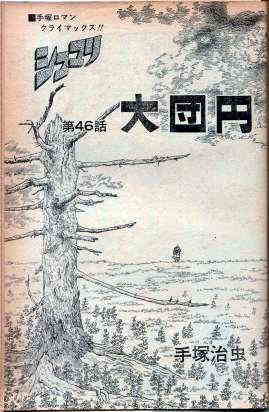 |
| 『シュマリ』 手塚治虫 作 小学館 発行 多分、1970年代の後半頃、隔週漫画雑誌「ビッグ・コミック」かビッグ・コミック・オリジナル」のどちらか忘れたが、連載途中に気付き、同誌を定期購読していた友人に頼んで切り抜いておいてもらった。 まぁ、単純な二極対立構造の物語りではなく、読み物としては面白い。 和人でありながら”シュマリ”とアイヌ名を口にし、北海道(蝦夷)の大自然に面と向かって闘いながら開墾し牧場を作り、子供も作り、隠されていた五稜郭の軍用金を巡っての思惑、、北海道王国としてのエゾ共和国を夢見る太財一族、薩摩・長州の官人達の北海道支配、そして政争、和人進出の為に追いやられるアイヌ民族。 シュマリは言う。 『アイヌの土地を借りてくらしているのだ』 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 手塚治虫さんの著書で持っているのは『ブッダ』ぐらいだと思う。 餓鬼の頃、『鉄腕アトム』の連載を見ていたし、『ジャングル大帝』はわくわくして見ていた覚えがあるのに、買ってまでの気がしない。 (『ブラック・ジャック』は取次店でバイトしていた時、昼休みに在庫商品の棚に並んでいるのを・・・役得ですがな) 思うに、鉄腕アトムで言えば手塚さんのアトムに対する(つまり”ロボット”)思い入れの深さが嫌だったのだろう。 だから、同じロボットでも『鉄人28号』(横山光輝 作)の方が・・・好きだった。 これって、単に、子どもやのに敷島博士によって作られた鉄人28号を操縦するわ、車に乗るわ、銃を撃つわ、豪邸に何故か一人で住んでるわ、恐れを知らずにどんな敵にも向かって行くわ、頭が切れるわ、冷静やわの、金田正太郎君に憧れていただけかもねぇ? |
|