











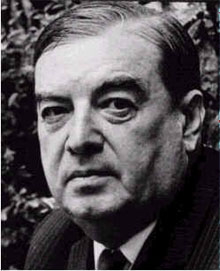




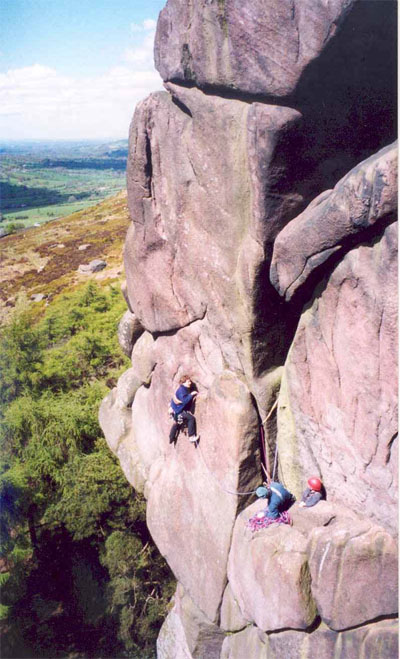



遊びと言う語
遊びは、自由な行為である
遊びの世界は仮構の世界であり、遊びのなかの行為は「本物ではない」
遊びにおける場所的、時間的限定性と規則の支配
遊びの形式的特徴についてのまとめ
遊びと祭式儀礼
闘う遊びの文化的機能
裁判・訴訟と遊び
ルールに従う戦争と遊び
詩と遊び
哲学・学問と遊び
音楽と遊び
中世から近代へ、ヨーロッパの文化、19世紀における真面目の支配
現代文化とスポーツ
スポーツの職業化
<中間的考察と反論>
近代スポーツは社会との「有機的結びつき」を欠いているか
遊びにおいて規則は絶対的か
フットボールの規則は変化しなかった?
五輪大会毎に規則が変わったアーチェリー
規則のない遊びもある
一人遊び
愛媛の漁村のお祭りにおける大人の遊び
文化となるとき遊びはその特徴を失う
釣り天狗、遊びに勝ち誇り、人に伝えること
<遊びの世界の完結性という見方への反論>
子どもは無制限に遊ぶ
仕事と遊び、生活時間の配分
戦いは試合が始まる前にも終わったあとにも存在する、遊びの世界は閉じていない
現実世界も仕事も、限定されたものとして現れる
遊び自体もその根は「現実」の中にある
ホイジンハの議論についての暫定的な結論:人間は「ホモ・ルーデンス」だとは言えない
オリンピック・ベルリン大会とナチスの戦争政策
「遊びと戦争」再論
スポーツは世界平和を促進する機能をもっているか
(1)「游漁の説」における多獲しない「品位」ある釣り
釣りの「真旨」
(2)初期の露伴における趣味と職業
儒教的職業倫理、西国立志篇、英国の釣り論・スポーツ論
英国のスポーツ論の影響
18世紀英国の書『完全なる釣り人』
ジェントルマンの遊びとしての釣り
露伴の多趣味
(3) 露伴の釣りの実際、キス釣りからスズキ釣りへ(数釣りから水上の楽しみへ)
自然を楽しむ、鱸(スズキ)釣り
「労働的の釣り」と「大名釣り」
「労働的」な釣り―補追、森下雨村の例
二種類の釣りがある
「游漁の説」 の再検討
「まめやか」と「疎懶」
仕事と趣味との関係に対する現実の露伴の態度
(4)遊戯娯楽と仕事との関係の変化
露伴の仕事と生活の変化
趣味・娯楽と本来の職業の「主客の転倒」
道具の「詮議」、「論弁思索」も趣味娯楽
釣りに関連したテーマでの著作は仕事なのか遊びなのか
京大は一年で辞職した
博士号は自分から求めて取得したものではなかった
(5) 露伴の思想
井上哲次郎の「日本主義」
露伴の非国粋主義
露伴の「以民為本」思想
露伴の反戦/非戦思想
(6)露伴にとって仕事/職業とは
仕事の必要性
露伴の経済
(7)趣味と学問
雑学か博学か、田辺元の「雑学」批判に対する山本健吉の反論
「博学篤志、切問近思」
山本の露伴理解についての若干の疑問
露伴の自由な知的探究活動は優れた「雑学」だ
君子露伴
「口演」された小説『幻談』
(8)結論
遊ぶために遊ぶ
自己を拡げることの愉快
遊びと聖なるもの・神秘的なものに関わる活動との区別
物質的利害関心から行なわれる遊びもある
タイプによる分類の1)アゴーン、競争、競技
タイプによる分類の2)アレア、運に頼る遊び
補論:子どもも偶然の遊びを好む。回り将棋の面白さ
タイプによる分類3)ミミクリー、模擬ないし模倣
タイプによる分類 4)イリンクス
パイディアとルドゥス
ホビーは機械文明への「復讐」
「遊びの社会性」そして「遊びを基礎とした社会学」
「混沌の社会」と「会計の社会」
「中間社会」と賭けごと
現代の産業社会と賭けごと
「遊びの堕落」
遊びと社会変革
<カイヨワの議論に対する若干の疑問と反論>
1.カイヨワの遊びが狭すぎる点について。または自然志向の遊びがあることについて。
釣りと家庭菜園づくりの遊びについてのデュマズディエの説
カイヨワの「純粋な消費」という遊びの定義は不適切
遊びの種類(カテゴリー)の拡大
カイヨワが自然志向の遊びを無視するのはおかしい
自然志向の欲求、衝動というものがある
2.「遊びの虚構性」、「遊びは人を現実世界から切り離す」に対する反論
子どものごっこ遊びと大人の演劇との違い
劇による「現実との距離」
ルールは虚構を作り出すか
身体を行使して行う戦いは「虚構」か
遊びのルールは通常の法律を停止するか
遊びの虚構性とはルールの理想性のことか、理想と現実
競馬と大学入試
イリンクスにおける虚構性
遊びによる切り離しと遊ぶ人の意思
すべての遊び・スポーツが現実的である
自然という現実を相手にした自由な遊び、釣り
現代高度産業社会における「疎外」の批判
「仕事は厳しいもの」は「仮定」
遊びと内発的動機
外発的報酬に依存する社会の問題点
快楽と楽しさの違い、エピクーロスの快楽説との違いと共通点
遊びと仕事と楽しさ、内発的報酬と外発的報酬
「自己目的的活動の報酬」を明らかにする
自己目的的活動の構造
自己目的的経験とフローの「理論モデル」
フロー活動の構造
「ゲームの楽しさ―チェス」
深い遊び、ロック・クライミングとフロー経験
ロック・クライミングにおける「恍惚」の経験
諸活動を、個人の技能に関して精密に目盛ること
ロック・ダンスにおけるフローの測定
ロック・ダンスの調査のやりかた
外科医の仕事―手術におけるフロー
マイクロ・フロー活動
<疑問と意見>1.「楽しさ」と「フロー」は異なる
<疑問と意見>2.「楽しさの理論モデル」の基礎になる調査の偏り
<疑問と意見>3.プロテスタントの宗教倫理における「フロー」の解釈について
<疑問と意見>4.様々なフロー、フローと楽しさ、楽しさと自由
三昧のフロー
楽しいフローと苦しいフロー
楽しさと自由との関係
<疑問と意見>5.「楽しさ」を指標とする社会全体の「再構造化」について
ハックスレーの『すばらしい新世界』、仕事への労働者の配分
成長、進歩・発展を追求する人間
家事の「再構造化」について
結論
遊ぼうと企てる?
遊びは「イニシャティブをとる重荷からの解放
自然現象にも遊びがある
ガダマーにおける「遊び」論と芸術論
ガダマーの芸術概念
芸術経験の普遍性
中間的medialであること、主客未分であること
音楽家の演奏・Spielが「中間」的、「媒介」的であること
ガダマーの遊びの解明は芸術の「存在論的解明」に役立ったか
遊びは「主体」と関係なしに起こる?
遊びは本来「自然」におけるもの?
スポーツは遊びの意識なしで行われる?
人間の遊びの特徴
没頭し夢中になることは遊びだけの特徴ではない
ガダマーの遊び論に関する結論
西村も「中間的medial」であること強調する
西村も光や風の戯れから議論を始める
遊びにおける解放感は「企ての主体」であることからの解放感
遊びの祖型「いない・いない・ばあ」
<私の反論>
遊びは偶然の「同調」で始まるのか
かくれんぼの再考
シーソーとブランコの遊びについて
「遊びはもっぱら現実態である」への反論
遊びをやめる自由はない?
遊びは倦怠によって終わる?
同調の関係は遊びに特有のものではない
仕事においてもまた「往還運動」がなされる
独楽回し、技量を要する遊びの西村の分析
独楽が回ったときの喜びは「ほらね・やっぱり」?
遊びの同調関係が主客の支配関係へと転ずる?
独楽回しの練習における工夫
難しい技への挑戦、「障害を仕組む」
独楽回しを振り返る、主体と客体の逆転
できることと支配とは異なる
主体的企ての存在
西村の遊び論への反論のまとめ
第六節 「学び」/教育としての遊び、ヴィゴツキーの遊び論
ヴィゴツキーの説に対する私の意見と若干の反論
第七節 「遊び=学び」論からの脱却へ、加用文男の説
遊びとは何か―要約と私の考え
釣りは遊びである。わたしは、還暦を迎えるのを機会に、それまで就いていた職業/仕事を辞め、釣りをして遊んで暮らすことにした。最初、私は、職業/仕事で行なうのではなく、かつ個人的な好み、楽しみから行う活動は遊びであり、遊びには様々なものがあるが、そのなかに主として体を使う遊びがあって、それがスポーツなのだと考えていた。スポーツは絵を描いたり音楽を演奏するなどの芸術的活動でも、小説を読んだり郷土史を調べたりする知的精神的活動、楽しみでもなく、体を使って遊び、身体運動を楽しむ活動である。そこで、釣りはスポーツの一種であると思われた。残るのは、釣りはいかなるスポーツであり、他のスポーツとどう違うのかということになる。
ところが、前章で見たように、一般にスポーツと言うときに最初に頭に浮かぶのはワールドカップやオリンピック大会で行われているような「近代スポーツ」であるが、その多くは職業化されていた。したがって、「体を使う遊びはスポーツだ」とは単純に言うことができない。また、スポーツは「見て」楽しむものでもあるが、「する」活動としてのスポーツは、子どものスポーツクラブでの活動、中高生の部活、「社会人」スポーツを含め、その多くは学習塾や予備校での勉強と同様、将来職業として就くことを目指し行われており、遊びとしては行われていないということも見た。つまり、どちらかといえば、スポーツ(「するものとしてのスポーツ」)は遊びではないことになるように思われた。そうだとすると、釣りをスポーツの一種だと考えることには問題があることになる。
私は、身体を使った遊びである釣りを、遊びであったり職業であったりするスポーツの様々な特徴と比較することで、かなりの間、混乱した、堂々巡りの考察を行っていたように思う。たとえば、釣りには「素人と本職の漁師の区別はない」という説がある。このことを、他のスポーツのプロの選手(あるいはプロ志願者)と単なる休日だけの愛好家との歴然たる違いと比べて、どう考えるべきか。また、ほとんどの釣りでは競争はしないが、スポーツでは競争、勝敗を争う試合・ゲームが多い。しかし、ゲーム=競技スポーツであっても、愛好家が楽しんで行うケースとプロが体を張って勝敗を争うケースとでは戦い/競争の強度は全く異なる。釣りが非競争的であることは楽しみで行われる愛好家のスポーツと比べるべきか、それともプロの戦いと比べるべきか。多くのスポーツには、「見る」人と「する」人が分かれ、「見て楽しむ」人のためにプロが「する」スポーツと、「見て楽しむ」だけの「スポーツ」(娯楽)と、愛好家が「する」遊びのポーツという3つの側面があるが、釣りはほとんどもっぱら「する」スポーツである。「他のスポーツ」と比べるとき、他のスポーツのどの側面と比べるべきなのか、等々。
しかし、遅まきながら、私は、つぎのように考えることで、今述べたような問題のほとんどが解決されることに気がついた。「する」スポーツは仕事で行う場合と遊びで行う場合がある。そこで、スポーツに、職業化に向かう内在的な要因があるとすればそれについての考察は必要かもしれないが、遊びである釣りは、遊びで行うスポーツと比べればいい、ということに気がついた。これは言わずもがなの、全く当たり前のことかもしれないが、ある種の混乱から抜け出ることができた。したがって、以下では釣りと、遊びである限りのほかのスポーツの比較をおこないながら、釣りがいかなるスポーツなのかを考えた。
しかし、私は、はじめから「釣りは遊びだ」と言っている。その際、「遊び」については既知のこととして前提しているが、その点が気がかりになり出した。私は、還暦で退職後、職業を持たず、「晴釣雨読」で残りの人生のほとんどを釣りをして暮らすつもりである。私は「釣りをして遊んで暮らす/釣りという遊びをして暮らすことにした」のだが、その「遊び」は「遊びで株をやる」、「あの人は遊び人だ」、あるいは「かけた魚を遊ばせずに一気に抜き上げる」などと言う時の、どの「遊び」の意味とも異なる。私は、「本気ではなく遊びで、釣りをして暮らす」ことにしたのでもないし、私は働くべきであるにもかかわらず、働かずに「ぶらぶらして暮らす」ことにしたのでもない。また私は、他のさまざまな趣味やスポーツと異なる特定の釣りという「遊び」が好きで選んだのであり、ただ強制されず自由に行動することにしたというわけでもない。そこで遊びという言葉について、あるいは遊びという活動と他の活動の違いについて、もっと、はっきりさせる必要があると感じた。
そこで「遊び」という活動の特徴、遊びと言う語の意味をはっきりさせようと、ホイジンハ『ホモ・ルーデンス』、カイヨワ『遊びと人間』、チクセントミハイの『楽しみの社会学』、西村清和『遊びの現象学』など、何冊かの本を読み考えてみた。また、『児童心理学講義』におけるヴィゴツキーの遊び論、および『発達』誌上に掲載されている加用文男の遊び論なども読んでみた。 とくに第2節では、釣り好きであった作家・文学者、幸田露伴の遊びと仕事についての考え方を彼の実際の生の在り方と関連付けながら考察してみた。
これらの人々が遊びとはいかなるものであると考えていたかを明らかにし、それらと一種の討論を行い、それを通じて自分の考えをはっきりさせるようにしてみたい。
最初にホイジンハ/里見元一郎訳『ホモ・ルーデンス』(<ホイジンガー選集>1、河出書房新社、昭和46年)を読んで考えた。中央公論社刊で高橋英夫による邦訳もある。
写真はJohan Huizinga,英語版Wikipediaによる。

著者のホイジンハ(1872-1945)は、巻末の訳者解説などによると、オランダ生まれ、1905年にライデン大学の歴史学教授になった文化史家で、その名を広く西欧に知られた人だという。33年には同大学の学長にも就いた。
ホイジンハは『ホモ・ルーデンス』の「まえがき―導入」冒頭で、人間の本質的特徴は理性・知性や、労働にあるのではなく、遊ぶことにあると述べている。そして、そのことを論証するために、彼は「遊びをこの世に存在するすべてのものの中の固有の一要因として抽出する」のだという。言い換えると、彼は、東西の多くの古代社会を調べて、これら古代文化のなかに遊びの要素が含まれていることを明らかにする。そして彼は言う「文化はその根源的段階においては遊びの性格をもち、遊びの形式と雰囲気のなかで活動する」と。また、ホイジンハは、遊びに関する、彼以前の研究の傾向、すなわち、遊びを、動物としての過剰エネルギーの放出といったように生物学的機能との関係で、あるいは大人になってからどのように役立つかという遊びとは別の目的との関係で説明するやりかたを退ける。
彼は動物も遊ぶことを認める。もちろん人間の子供は遊ぶ。しかし、彼は「動物の生活や子供の生活のなかでなく、文化のなかでの遊びの機能に探求の眼を向ける」。慣習・法律も、商業・技術も、学問・芸術も、「人間社会に固有で偉大な活動には全てはじめから遊びが織り込まれている」。彼は子犬がじゃれあい、人間の子供たちがただふざけあって遊ぶ「簡素で幼稚な遊び」とは異なる、「形が明確」になり、社会的に伝達され、多くの人に共有されるようになった活動である遊び、文化となった遊びを取り上げ、「遊びの本質」を明らかにしようというのである。
言葉がすでに遊びである。言葉は「簡単に言えば名指すのに使うもので、言い換えれば物事を精神の領域へ高める」ことだが、「言葉を創造する精神は遊びながら次々と素材的なものから思考されたものへと飛躍する。抽象的表現の背後には象徴的言葉〔高橋訳では、比喩〕があり、象徴的言葉の中に言葉の遊びがある」。あるいは「神話を通して昔の人はこの世のできごとを解き明かそうとした。---神話がこの世のことを飾るのに用いた気まぐれな想像のイメージの中で、創作の才をもつ精神は冗談と真面目の境目で遊んでいる」。また、「昔の共同体は世界救済の保証に役立つような聖なる行事、つまり、潔(きよ)め、犠牲、秘儀などを、言葉のもっとも直接的な意味において純粋な遊びの中で行った。神話や祭礼儀式のなかに文化生活の偉大な活動、たとえば、法と秩序、商業と利益、技術と芸術、詩、知識と学問などの真の起源がある。しかも、これらはすべてまた同時に遊びの世界に根を張っている」。
そして彼は『ホモ・ルーデンス』第3章以下で、実際に東西の多くの古代社会を調べ、その文化のなかに遊びの要素が含まれていることを明らかにしている。一般的には、文化が進むにつれ遊びと文化の関係は変化し、「遊びの要素は次第に背景に退く」が、文化はその根源的段階においては遊びの性格をもち、遊びの要素が重要な役割を果たしている。「この研究でなされるべきは、真の純粋な遊びを文化の基礎であり、かつまた〔祭礼儀式と並ぶ〕一要素であると指摘することだ」と言う。
続いて、しかし「言語はこのような一般的範疇を---終始変わらぬ明確さで識別することは決してなかったし、それを1つの言葉で把握することもなかった」と言い、「すべての民族が遊ぶし、その遊びは驚くほど似ている。しかし、にもかかわらず、すべての言語が遊びの意味を近代ヨーロッパ語のごとく確実にしかも同時に広い内容をもって1つの言葉で把握しているわけではない」と言う。ギリシャ語には、子どもを意味する語と語源的に関係のあるパイディアー、重要でないというニュアンスを帯びたアチュロー、そして戦い、競技を意味するアゴーンという三つの語があると言う。そして彼は以下で見るようにアゴーンをとりわけ重視する。パイディアーとアゴーンと言う語は次の節で述べるカイヨワの中でも重要な役割りを果たす。
ホイジンハは日本語が近代西欧諸言語によく似た、明確な単語、「遊ぶ」を持っていると言う。だが、日本語の「遊び」という語は、明らかに、上でホイジンハが「定義」したような近代ヨーロッパ諸言語のspel、Spiel、play(以下では英語のplayで代表させることにする)の意味するものと同じであるとはいえない。「遊び人」と言うときの遊び、「物見遊山」というときの遊び、あるいは「遊興」などと言うときの遊びなどは上の「定義」のなかには含まれていない。彼の定義する遊びは「きまった時間と場所の限界の中で自ら進んで受け入れかつ絶対的に義務付けられた規則に従って遂行され」る競争や競技、闘技、そして演劇と音楽であり、すべて、playされるものである。
ホイジンハも、古語を含め日本語の遊びは「真面目という反対語を持っており」、「一般的な遊び、緊張を解くこと、娯楽、気晴らし、物見遊山、休養、遊蕩、賭博、無為、怠けること、仕事につかないことなどを意味する」、あるいは競争・闘技とは「一線を画」しているなどの的確な指摘と補足説明を行っている。日本語に翻訳された本の中で「遊び」と言う語がつかわれるにしても、日本語をnative languageとする我々が遊びという語で思い浮かべるイメージとは違っているところがあることに注意が必要である。
暫定的に、現代日本語の常識に従って言えば、遊びの活動とは、法的あるいは道徳的義務や責任を果たすために行なう1)のではなく、また、ほかの目的、例えば生活のために、行うのでもなく、その活動を楽しむために行うような活動だと考えることができる。
一方、ホイジンハは、演技や演奏、競技、スポーツなどが「遊び」playだと言う。例えば、近代以前、音楽の演奏は宮廷に雇われた音楽家によるプロの仕事として行われていただけでなく、広く庶民の間の遊びとしても行われていたであろうが、演劇はむしろほとんどプロによって行われていたはずである。だが、ホイジンハはプロかアマかに関わりなく、競技も音楽も劇もすべてplay・遊びとみなす。確かにヨーロッパの諸言語においては、劇も音楽も、スポーツも、すべてplayする活動であり、それを行う人はplayerである。
しかし、俳優や音楽家やスポーツ選手たちが、仕事として劇、音楽、スポーツを行うとき、彼らは「専門職業人」として行っているのであり、彼らは「遊ぶ人」でも「遊び人」でもない。それらは、一般サラリーマンがレジャー活動として行う、釣りやゴルフ、草野球などのような、自らが楽しむことを目的とした活動、つまり遊びとみなすことは決してできない。
第2章で述べたが、ホイジンハがこの書を書きつつあった19世後半になって「近代スポーツ」が誕生し、当初はアマチュアによって行われる遊びの活動であった。ホイジンハが実際本書の後半で書いているように、20世紀に入ると次第に、スポーツのプロフェッショナル化が進んだ。これは一般的な社会学的捉え方であるが、私もこれに従う。
しかし、ホイジンハは、アマチュア・スポーツも含め近代スポーツの興隆は、彼がplay・遊びとみなすそれ以前の社会における一群の活動の、衰退、変質、「転身」を意味するもので、アマチュアによるスポーツからプロスポーツへの変化については重要な意味を見出しておらず、プロとアマの区別を主題的に扱うことはしていない。
他方、わたしがこの章で考えたいのは遊びについてであり、playについてではない。すでに第2章においてもスポーツにおけるプロとアマの違いを問題にしたが、この章では遊びについて考えようとしている。その際、ヨーロッパ語のplayによって意味される語と現代日本語でいう遊びの区別は重要であり、ホイジンハの『ホモルーデンス』を翻訳で読むときには、「遊び」と言う語に注意しながら読む必要があるのである。
さて、ホイジンハが文化的意義をもつものとして考察対象とするする遊びは具体的には「競技に競走、見世物に出し物、踊りに歌、仮装の集いに馬上の槍試合」など「社会的な遊び」である。そしてこれらは「何かのための闘い」である遊びと「何かの演技である」遊びの二つに、大きく分けられるという。(「演ずる」、「演技する」は、高橋訳では、「何かを表現する」である。)
また、彼は、遊びが「どんな分析も論理的解釈も寄せ付けない」、「おもしろさ」という「絶対的に根本的な」要素を有すること、あるいは「遊びはわれわれ〔現代人の〕意識にとっては真面目さに対立すると考えられている」こと、しかし、「賢明とあほう」〔賢愚〕、「真と偽」、「善と悪」などの対立の埒外にあることなど、いくつかの「遊び」の特徴に触れた後で、遊びの「形式的」特徴を以下のように述べる。
「遊びはなによりもまず第一に自由な行為だ。命令された遊びはもはや遊びではありえない。せいぜいそれは、遊びの義務的焼き直しに過ぎない。自由というこの性格によって始めて、遊びは自然の営みの過程〔生存の必要〕を乗り越えたものになる。遊びは自らそこへ余分に付け加わったものであり、衣装のようにその上にまとわれるものだ」。ここには仕事ないし労働とは異なる遊びの積極的な意味が語られている。遊びは生存・生活の必要からやむを得ず行なうものでも、また他者の命令にしたがって行なわれる活動でもなく、自分から進んで行なう活動でしかも「自然の営みを乗り越える」活動である。遊びは「素材的なものから思考されたものへと飛躍する」ことであり「精神の領域へと高」まることである。人間は他の動物と違って、地上で裸体で暮らすことには満足できず、「衣装をまとって」、精神の世界に羽ばたくことを求める。遊びは、逃れることのできない生存の必要のゆえに行なわれる活動の労苦からの一時的脱出であり、楽しみを享受する活動なのである。
また、遊びは「肉体的要請によって課されるものではなく、なおさら道徳的義務によって課されるものではない」とも言われている。おそらく、ホイジンハは、道徳義務はカントがいうように普遍妥当性を有する絶対的な命令と考えるのであろう。だが遊びは、何かの求め(「要請」)に従って行われるものではなく、また、なおさら、なにか絶対的な「命令」のようなものによって「課される」ものなのでもない。遊びは要求や命令に従って行われるものではなく自由に行われるものだと言うのである。
だが、とホイジンハは言う、「成年に達し、責任能力を持った大人にとって、遊びはしなければそれですむであろうといった程度の一つの機能である。遊びは余計なものなのだ。---遊びはいつなんどきでも延期できるし、中止もできる。------遊びは仕事ではない。それは「自由時間」に行われる」。たしかに仕事は契約やその他の約束など他者との関係の中で行われるもので、勝手に自分のしたいようにしたり、途中でやめたりすることはできない。とくに雇用されて行なう仕事では自由度は非常に小さい。だが、遊びはそうではない。自分の意思だけでいつでも、やめようと思えばやめられる。延期も出来る。また、仕事(労働)は必要な活動である。仕事をしなければ生きていけない。他方、遊びによって空腹を満たすことはできない。過労はさけなければならないが、(適当に休息をとり)普通に仕事を行っているかぎり、遊ばなくても死にはしない。そして、人は、仕事においてこそ他の人から評価されたり、賞賛を受けたりするのであり、人は仕事を通じて自己を実現することができる。だとすれば、遊びは無しで済ませられればそのほうがよい。おそらくホイジンハはそう言いたいのであろう。
汽車ごっこをしていた子供を抱き上げて父親がキスをしようとすると、機関車であるその子は「機関車に口付けをしないで。でないと客車たちが、本物じゃないと思っちゃうよ」と言う。遊びの、この「本物でない」ということのなかには、「劣等感の意識、つまり、最優先的と目される「厳粛さ」に対する「あほらしさ」〔高橋訳では、「楽しみ事」〕の意識が横たわっている。---しかし、この「ただの遊び」が、しかし、「ただ何々」に過ぎないという性格を一時完全に棚上げして、大真面目に---行なわれることもある。----遊びとまじめの対立は常に流動的だ」とホイジンハは言う。彼は、「日常」、「ありきたりの」、あるいは「本来の」生活は、どちらかといえば「真面目」で、本物の世界であり、遊びの世界は「仮構」に過ぎぬ、「劣等」なもの、「あほらしいもの」とする。
私は、チェスなどの盤上のゲームは「仮構」の世界における、「仮構」の戦いだと言うことには異論はないが、次に見るように、一般に遊びやスポーツなどが規則によって作られたものであるということと関連して、「仮構」の世界における活動だと見なすことには異議がある。カイヨワは『遊びと人間』で、ホイジンハの説にいくつかの修正を加えつつ、遊びの「特質」を述べているが、ホイジンハと同じく遊びの「仮構性」を説いている。カイヨワの議論を検討した後で、一緒に、この遊びの仮構性という議論に反論を行なおうと思う。
ホイジンハは、遊びが「利害を度外視した性格」を持っており、「必要や欲求の直接的満足を求める生活過程の圏外に立つものであり、しかもその過程を一時差し止めてしまう。遊びはそれ自体だけで完結する一時的行為としてその生活過程のなかに割って入り、行為すること自体に含まれた充足感のゆえに行われる」という。この文は、人々が個人として遊ぶ場合について言われているのではないと思われる。個々人が休暇をとって釣りやゴルフなどをして遊んでいる最中に、緊急の用ができたからと会社から呼び出しがかかる。あるいは家族旅行中に子どもの具合が悪くなって、旅行を打ち切って帰途につくというように、遊びの中に「利害」や「必要」が割って入り、遊びを差し止めるという事態は想像できても、その逆の事態、仕事のなかに遊びが「割って入る」という事態、つまり職場で、仕事を突然中断して遊びを始める、あるいは仕事をしながら遊ぶなどということは現代産業社会においては想像できないからである。
ホイジンハが言う遊びが生活過程のなかに「割って入る」というのは、遊びが社会的文化的機能を獲得し、生活過程や仕事と同等ないしそれ以上の役割りを有するものとして、年中行事などとして社会生活の中に組み入れられることを指しているのだと思われる
彼は上の文に続いて、遊びは「まず最初」「休息」として「われわれの前に現れる」という。そして「休息/遊び」は、毎日「規則正しく繰り返」され、「生活一般の伴奏となり補充となり、その一部分になる。----個人に対しては生物学的機能として欠くべからざるものであり、共同体に対しては、---それが生み出す精神的社会的きずな、つまり簡単にいえば文化的機能のおかげで欠くべからざるものとなる」と言う。こうして、社会的に労働時間を限定し、「祝日」や「休日」を設け、そして共同体として祭りを行なうなどして、人々が仕事を休み、遊ぶことができ、かつ相互に精神的な絆が得られるようになる。前の個所では「責任能力を持った大人にとって、遊びはしなければそれですむであろうといった程度の一つの機能である」、あるいは遊びは、必要があれば「いつなんどきでも」「延期したり中止したり」することができるものである、と言われていたが、それは個々人に関して言われていたことで、社会として、共同体としてみるとき、遊びは「必要」で「欠くべからざるもの」となり、簡単には「延期したり、中止したり」できないものになる。
このようにして、休息/遊びは社会的・文化的機能をもつようになり、「食物摂取、繁殖〔生殖〕、保育といったような純生物学的過程を越えたより高い世界に属」するものに変化する。動物も遊ぶが「人間の遊びは---何かしら高められたものであり、祝祭と式典の領域、つまり聖なる領域の中にその場を見つける」という。彼は個々人が日常生活のなかで行う遊びや休息は「しなければそれで済む」ことだとその意義を認めてはいないが、遊びと休息が共同体の行事となり、「祝祭と式典」として行われるときには、文化としての高次の意義を持つと言うのである。
私が朝おきて顔を洗うとすれば、私は60数年間生きてこの世に存在していたのでなければならず、そしてそのためには私を生んだ親が存在し、等々と無限の過去に遡る連鎖のなかで、私が顔を洗うという出来事が生ずるのであり、また私の行為はなんらかの点で無数の人々、無数の出来事と関連をもつという具合に、「現実世界」、「日常」生活におけるできごとは、時間と空間において果てしない広がりを持っていると考えることができる。
しかし、「チェスは最初の指し手ではじまり、キングが詰んだら終わる」。その第一手の前にいかなる指し手も存在せず、キングが詰んだあとにはいかなる手も存在しない。遊びの世界には、ルールによって決まっている明確な始まりと終わりがある。また場所も決まっている。ホイジンハは、時間的限定性よりも場所的限定性の方がより目立つという。遊びはすべて、「実際に作られるか、観念的に想定されるか、そのいずれにせよ、意図的にか、もしくは自明のこととして、前もって作り上げられる」遊び場の中で行なわれる。競走は、「実際に作られた」決まったコースの中で行なわれる。チェス・将棋は盤と駒があればどこででも行なえるし、有段者なら、それらがなくても、頭の中でコマを動かして戦うことができる。チェス・将棋は「観念的」に「限定された」空間でも遊べる。遊びは神聖な行為と同じ形式で行なわれる。つまり、「垣根を持って囲まれた神聖な領域で」行なわれるという。
遊びにおいて人々は日常性から脱却する。人々は遊びの周りに秘密主義を張り巡らす。そしてそのなかではありきたりの生活の法や慣習は差し止められ、われわれは「別人」になる。こうした「遊びの別人化の特徴と秘密主義は仮装舞踏会でもっとも明確に示される」。
ホイジンハは「遊び場の中では独自の、絶対的秩序が支配する。----遊びは秩序を創造する」。「すべての遊びがそれぞれの規則をもっている。それは遊びを作り上げる仮の世界で通用すべきものとして定められている。遊びの規則は絶対的強制力をもち、疑いをさしはさむ余地はない」という。日常生活の中でわれわれは様々な法律、規則、慣習的秩序などに従っている。しかし、それらの支配は不完全である。法律違反、規則の無視は珍しいことではない。
しかし、遊びの規則に従わなければ、遊びそのものが成り立たない。また、人間の物質的生活が属する、自然的世界の秩序とその規則つまり自然法則は人間のどうすることもできないものである。生存、肉体の維持にかかわる日常生活において、われわれは自然法則の支配から免れることはできない。しかし、われわれは、「遊びにおいては、この物質的生活の制限を抜け出て、自由に精神界に羽ばたく」とホイジンハは言う。キリスト教の神が自然的世界を無から創造し、絶対的に支配するように、精神は規則によって遊びの世界を創り出し、自由に、秩序を作り出し、絶対的な支配を行なう、と言いたいのだろう。遊びの世界は規則によって創造され、そこでは規則が絶対的に支配する、という考えについては、あとで検討してみよう。
こうして、総括的に、「遊びは自由な行為であり、「本当のことではないとして」〔高橋訳では<本気でそうしているのではないもの>として〕ありきたりの生活の埒外にあると考えられる。にもかかわらず、それは遊ぶ人を完全にとりこにするが、だからといって、何か物質的利益とむすびつくわけではまったくなく、また、他面、何かの効用を織り込まれているのでもない。それは自ら進んで限定した時間と空間の中で遂行され、一定の法則ないし規則にしたがって秩序正しく進行し、遊ぶ人々の間に規則遵守の共同体を作り出す。それは自らを好んで秘密で取り囲み、あるいは仮装をもってありきたりの世界とは別のものであることを強調する」、とホイジンハ言う。
だが、また、子供の「ごっこ遊び」あるいは大人の演劇と、共同体として行われる祭礼儀式は異なってもいる。なぜなら、子供の「ごっこ遊び」の演技は単なる模倣でしかないのに対して、祭礼での演技は「季節の移り変わりを表し、また星座の上がり下がり、作物の成長と実り、人間や動物の誕生、生と死などの観念を形象化して演ずる」遊びである。「彼らは存在するものすべてをおおう秩序を聖なる遊びのなかで演技する」のである。子供の遊びと古代文化の祭礼儀式とを比較すれば、後者には「より多くの精神的要素」がある。
また、祭礼の行為は単に演じ、表現する遊びではない。それは遊びでありつつ、同時に、清め、祈り、救済の約束、等々であり、人々に直接的な楽しみを与えるだけでなく、共同体の安寧と福祉を人々に確信させるという、高次の機能を果たしている。こうして、「聖なる遊びは、共同体の繁栄のためになくてはならぬものであり、宇宙的洞察と社会の発展を内に秘めていながら、しかし常に遊びであり、----必要と真面目の味気ない世界の外で、それを超えて成し遂げられる行為」である、とホイジンハは言う。
ホイジンハはすべての古代文化が「遊びの中で遊びとして発展」することによって生まれたというが、とりわけ彼は演ずる遊びが聖なる祭式儀礼へと発展したことを重視する。というのも、祭礼は人間が地上の俗世界、「必要と真面目の味気ない世界」の中だけで完結する、物質的存在ではなく、聖なる世界においても生きる存在である、いや聖なる世界の中にこそ人間の真の存在があるということ、つまり、人間の精神的な超越性をもっとも明瞭に示す活動だと考えるからである。
人間が生まれつき「他の人より優れたい、第一人者でありたい、そんな人として尊敬されたいという憧れ」を持っている。「讃えられ、名声を得たいという願望」が「子どもの生活から最高の文化的業績に至るまでのすべて」の領域を貫いており、「自己および自己集団の完成を目指す原動力として働く」。
誰かが商売で大儲けをしても尊敬は得られないだろうし、それが社会の利益だとは受け取られないかもしれない。しかし、遊びによる「名誉と尊敬は勝者の属する集団全体に直接の利益をもたらす。---遊びで得た成功は個人的なものから集団的なものへきわめて移行しやすい」。
古代ギリシャにおいてもローマにおいてもまたアラビアにおいても、また中世キリスト教世界の騎士道、日本の武士道においても、徳の語源となった言葉は力、男らしさの概念を土台にして生まれた。「徳、名誉、高貴、名声ははじめから競争という遊びの領域内にあった」という。彼は上杉謙信の名をあげながら、日本の武士道についてもふれている。彼は「闘う遊び」がすべての文化と結びついていた、つまり「文化は根源的段階において〔競技・闘技の〕遊びの性格を持ち、遊びの形式と雰囲気のなかで活動する」と言う。 こう述べたのに続き、「文化生活の偉大な活動、たとえば、法と秩序、商業と利益、技術と芸術、詩、知識と学問など」が神話や祭礼儀式の中にその「真の起原」を持っているとともに、「これらはすべてまた同時に遊びの世界に根を張っている」ということを7つの章で具体的に論証している。
法律や裁判制度は近代社会の文化の重要部分である。「古代ギリシャ人の間では裁判沙汰になる原告被告の争いはアゴーン、つまり確たる規則に縛られた闘争とみなされ、合い分かれて争う両派は聖なる形式にのっとって調停人の判決を乞い求める」。裁判は「賭け事遊びであり、競走レースであり、さらには言葉の勝負である」。「法廷」はギリシャ語で「聖なる円陣」と呼ばれた聖域で、日常世界から切り離された特別の空間であった。「一段と未開の法概念になればなるほどチャンスの要素、間接的に遊びの要素が、---前面に押し出され」、神託、神明裁判、くじ占いなどによる決定と、法の裁定とが同じこととを意味した、という。
〔注:神明裁判とは、正しい者には神の加護があるという考えに基づいて、熱せられた鉄を持っていられるかどうか、熱湯の中に手をいれて、やけどがすぐに直るかどうかなどの方法で有罪無罪を決定する方法である。しかし、神明裁判、神託、クジ占いのいずれも、その方法やその結果(判決)に従うかどうかには遊びの特徴である自由は存在せず、当時の人々にとっては、「面白さ」とは無関係のきわめて厳粛なものだったと思われる。どうしてこれらが「遊び」だとされるのか、私にはわからない。〕
闘技は一定の規則に従って行われる戦いであり、闘技は遊びである。血が流れるかどうか、殺し合いになるかどうかは、遊びであることを否定する基準にはできない。決闘はどちらが正しいかを、つまり神の裁きを、知るために行われた最終的な方法のひとつであったが、中世のヨーロッパでは軍隊同士の戦闘の代わりに、双方から選ばれた一定数の戦士による決闘で片を付けることがしばしば行われた。このような形で行われる戦争は相互の約束や協定に従って行われるもので、儀式的で遊びの要素を含んでいる。このような形の戦争は古代ギリシャにも中国の封建制時代にも見られる。
ホイジンハは、「敵味方の双方が相手を対等と認め、お互いに名誉ある公正な行為を要求」し、「名誉に反することは規則に反する」という意識をもつがゆえに、「国際法はその起原を闘技的世界に発している」という。だが、遊びの要素が後になって次第に消滅して、近代戦、国家の総力戦がおこなわれるようになった。戦争と遊びとの関連についてはあとで、もう一度ふれることにする。
一般に文化活動は社会の初期段階では遊びと広範な関係を持っているが、より高度な社会になると関連性を次第に失う。しかし、詩は変わらずに遊びの世界と深く結びついている。ポール・ヴァレリーは「詩は言葉と言語をもってする遊びだ」といった。詩はその本来の起原から歌、音楽、舞踊と離れがたく結びついている。劇は、演ずるという語が競技を行うことを意味するplayであることからもわかるように、元来競技の領域に属していた。古代ギリシャにおいては、観客は「さながらフットボール試合の観客と同じように」、劇の競演を楽しんだ。
12世紀ヨーロッパの学校・スコラでは悪口と中傷にみちた知識・学識の競争が真っ盛りだった。中世の大学生活のいっさいは遊びの形式をとっていた。学問的口頭談話の形をとる、果てしない討論、華麗に飾り立てた儀式、各国民別の集団組織、あらゆる分野における分極対立、これらはすべて競争と遊びの領域に入る。学問は哲学を含めてその本性上論争的であり、論争的なものは闘技的なものから切り離せないとホイジンハは言う。
彼によれば、19世紀のヨーロッパでは、産業革命の技術的成果の過大評価により、労働と生産が偶像視され、「生真面目で散文的な実用的観念---と市民的福祉の理想が」支配する。19世紀に遊びが放棄され、真面目が文化を支配したことは、男子の服装に「空想的要素が消えたこと」、「色彩に乏しく、形式ばることもなくなり」、「いつも変化しない」「ただ真面目な」だけのものになったことに表れている。「布地もスコッチ産の荒い織物が幅をきかせ、フロックコートが式服---に祭り上げられ、----背広にその座をゆずった」ことのなかに何よりも明白に現れている。この「文化現象における男子の服装の平均化と硬直化」は決して過小評価されてはならず、「このなかに、フランス革命以後の精神的、社会的変革のすべてが表現されている」とホイジンハは言う。
しかし、「折にふれて行われる余興から」、組織化された遊び、「常設され訓練されたチームの集団的遊び」への発展が、とくにイギリスにおける球技の発展によっておこり、そこから近代的スポーツ制度が生み出された。スポーツ制度において「規則はより厳重になり、いっそう詳しい細則が練り上げられた。達成目標はより高められた」。「体系的組織化と訓練強化が絶えず進」み、「職業専門家と素人愛好家の分離」が生じて、プロスポーツにおいては「任意性と天衣無縫の大らかさ」はもはや見られなくなった。スポーツは「純粋に遊びの領域から離れていき、---遊びでも真面目でもないものになってしまった」。スポーツは「本来の文化過程」からはずれてしまい、「祭祀との結びつき---は完全に失わ」れて、「それは全く奉納されないものとなり、----その社会の構造とはなんら有機的に結びつかなくなった」とホイジンハは言う。
彼が述べている、遊びのスポーツ化、制度化・組織化、職業化などは『スポーツと文明化』でエリアスが詳しく述べていることの概括的だが正確な先取りと言えるだろう。だが、スポーツ制度は、産業、労働、市民的福祉を理想とする経済的実用的関心、つまり真面目だけが支配している社会における、遊び全般の「真面目への転身」の表れの一部なのであり、それは本来の意味での遊びではない、とホイジンハは言う。
チェスや(トランプの)ブリッジなど「知能の遊び」も、「公認の選手権制度、公開試合、記録の公式登録」などによって「スポーツ化」されている。しかし、気晴らしや子どものように楽しむことは期待できず、「それは精神的能力をただ一面だけ鋭敏にして魂の実りを忘れた完全に不毛な技量であり、よりよく活用できたはずの知的、精神的緊張を相当量に渡って歪曲し、浪費してしまうものだ」。
他方で彼は遊びのスポーツ化つまり体系的組織化、訓練強化、職業的真剣さの強化など、「遊びを真面目なことに変貌させる傾向」とは反対の現象を指摘する。つまり、「最大トン数の郵便船とか、大洋最短航路」だとかを「実利的理由」よりも「記録達成」のために目指すことが、商業、産業のなかで行われている。ホイジンハはこれは「スポーツにおいて取り上げられた記録の概念が経済の分野で幅を利かす」ようになったことの表れだという。他にも、大企業の部門間で行われている業績達成競争、あるいは、大企業が内部に「スポーツ団体を作ったり、労働者を職業能力の観点からだけでなくサッカーの観点からもみて採用する」ことなどを指摘し、これらは「まじめが遊びに変質しながら、しかも真面目で通っている」ことをあらわす矛盾した現象だと彼は言う。
ホイジンハは、現代社会におけるスポーツの職業化、プロ・スポーツを主としたスポーツの発展という現象は現代社会の「混沌」あるいは「矛盾」を意味しているという。彼はスポーツは「遊びでもないし真面目でもないものになってしまった」と言う。そうだろうか。 アマの「純粋な遊び」であるスポーツはプレーヤー自身の楽しみのために行われ、観戦者の存在は必ずしも必要としない。だが、プロスポーツは観客なしでは存在せず、プロ・スポーツにおいてはプレーは観客の存在と一体である。プロスポーツにおけるプレーは職業活動であり、(古代あるいは前近代社会におけるのとは違って現代では)職業は真面目に真剣に行われるべきものだとするなら---学者も大学教授として給与を受け取っているかぎり同じはずだが---それを行う選手・プレーヤーにとっては真面目に、真剣に行われるべきことがらである。彼/彼女は遊んではいられず、スポーツは「遊びではない」。(このことはすでに第1節で述べた。)観客にとって、観戦は気晴らしであり遊びである。こうしてプロスポーツにおいてはそれを構成する要素である選手のプレーには真面目だけがあって遊びはなく、もう一方の要素、観客の観戦には遊びだけがあって(ホイジンハが言う意味での)真面目は存在しない。すると、この両要素を切り離して別々に見ればたしかに「スポーツは遊びでも真面目でもない」ということになろだろうが、しかし一体のものとしてみれば、「スポーツにはプレーヤーの職業の真面目と観客の観戦の遊びの両方がある」と言える。
「慣例化」された産業社会においては人々は仕事において遊び半分にではなく真面目に自分の任務を果たさなければならなくなった。しかし、遊ぶことは権力者や有産上層階級の人間だけに許されており、農民や労働者、庶民には許されるべきではないというのでなければ、働く人々の遊びへの欲求も充足される必要がある。その一部は人々が(限られた)余暇に自分で行うスポーツや芸術の活動において満たされるだろうが、それだけでは十分ではない。こうして遊びあるいは余暇活動が不十分だと感じている多くの人々のために、プロによって職業として真面目に行われるスポーツや音楽会などを見たり聴いたりして楽しむ機会を社会が提供してくれる。<BR> ホイジンハはとりわけスポーツを「遊びでも真面目でもない」ものとして槍玉に挙げるが、分離の程度に違いはあるかもしれないが、コンサートホールで行われる音楽会でも、同じように音楽を聴いて楽しむだけの聴衆と、真剣に演奏するplayer・演奏者との分離、「遊びと真面目の分離」が支配している。しかしその一方は他方なしには存在せず、両者は切り離すことはできない。したがって、見方を変えればそこには「遊びと真面目の両方」が存在している。ただしそこには「見るもの」と「行うもの」という一種の社会的な「分業」あるいは活動の分割ないし分裂が生じているということを付け加える必要があるが。
とはいえ、社会の発展につれて音楽や詩などの分野以外の、経済や法律や学問などほとんどすべての分野で仕事(文化)と遊びとの結びつきが次第に失われて来たというホイジンハの指摘は否定できない。
ホイジンハの言う、仕事(労働)からの遊びの分離・排除と言う現象はエリアスの言う「慣例化」である。また、16~17世紀の宗教改革による「勤勉・禁欲」倫理の拡大(ウェーバー)、「資本の原蓄」過程における労働の強制(マルクス)、英仏などの国で都市に流入する農民を「ミゼラブルな人間の屑」としてアジール(矯正院)、救貧院(ワークハウス)などに収容・監禁し「強制的に働くことを教え込み、人格(魂)を矯正する」ことを目指し、大人の再教育を施したこと(フーコー)など、主としてヨーロッパ近代の歴史に関する諸説に照らしても、労働からの遊びの排除・分離というホイジンハの捉え方は間違っていないと思われる。
私は第2章で、幼児は遊びながら学び、学童は学習・訓練によって学ぶと言ったが、19世紀ごろから学校制度が発達すると、子供たちは、各自の家で遊んであるいは親の仕事の手伝いをして過ごすのではなく、学校に通って学習し訓練を受けるようになった。はじめから、学校の目的は知識や技能を与えることであり一緒に遊ばせることではないと考えられていたであろうし、教育は一定の厳格さ、真面目さを伴って行われたであろう。(体罰まで行われたかどうかは別問題である。)こうして、一定年齢の子供たちは、遊びながら学ぶのでなく、学校で勉強するようになった。現代の大人は真面目に仕事に取り組むための「再教育」は必要ない。すでに子どものときにこの態度を身につけているからである。学校制度の一般化もまた近代社会における遊びと真面目の分離傾向を促進したと思われる。
ホイジンハは近代社会を「聖なる祭」をうしなった「混乱」、「矛盾」だらけの社会と見る。だがこの見方は、神聖な儀式と祝祭に満ちていた中世社会の肯定的見方と関係がある。2)
たしかに現代のスポーツは古代の競技のように「聖なる祭りの一部」ではなく、金銭と名誉を求めて、「闘技的本能をむき出しに」して真剣に闘うアスリートの祭典であり、せいぜいのところ国威の発揚を図る場でしかない。しかし、このようなスポーツのありかたは、まさしく、現実の社会のあり方と深く結びついていると思われる。
有機的〔たぶん英語のorganicに相当するオランダ語で書かれているだろう〕結びつきとは部分と部分が互いに無関係にあるいは機械的に結び付けられているのでなく、生物の諸器官organのように各部分が互いに支え合って存在していることを言うのだろう。ところが、現代(資本主義)社会の特徴をエリアスの言葉で慣例化と呼ぶなら、明らかにスポーツは慣例化された資本主義社会と有機的に結びついている。
近代社会は産業社会であり、中世の自給自足的農業社会とは異なり、(社会主義社会は別として)資本家と労働者(そして商人)が主役であるような社会である。18世紀から19世紀にかけて生まれた近代スポーツは当初、利害関心なしに、闘うことを楽しむだけの目的で追求するジェントルマンと呼ばれた富裕階級を中心とする少数の者によって行われた。「遊びが次第に真面目に受け取られ、---規則が厳重になり」「組織化と訓練強化」が進んだことにより、「職業専門化と素人愛好家の分離」が起こった。それはホイジンハの言うとおりだろう。
しかし、「スポーツが遊びの領域からはなれ」、「闘技本能むき出し」の、プロによる真剣な戦いに変化したという彼の主張が的確に当てはまるのは20世紀とくに第二次大戦後のプロスポーツの隆盛においてであろう。だが、プロ・スポーツの隆盛はそれを見て楽しむ大衆の存在なしには不可能であり、(マスメディアの発達という要因も考慮すべきだが)スポーツの「楽しい興奮」によって、「慣例化」した仕方で(つまり規則正しく正確に)行われる労働の中では抑制されている「自然的感情」を表に出し、カタルシスを得ることの必要な多数の人々、つまり労働者階級の登場によって可能になったのである。現代社会には、一方に、スポーツを職業とし、真剣・真面目に闘う、ほんの一握りのアスリートがおり、また他方に、8時間労働制の下で、スポーツを自ら行って楽しむことは十分にはできないが、時々は競技場に行って応援したり、あるいは平日でも家でテレビ観戦をすることはできる(あるいは、スポーツを見て楽しむことで我慢せざるを得ない)、多数のサラリーマン・労働者がいる。
「楽しい興奮」を可能にしてくれるプロスポーツは人々の精神を活性化し精神衛生を保つことに寄与し、健康で勤勉な労働力の供給に貢献しているのだから、資本主義の仕組みを肯定するかどうかは別として、大いに資本主義社会を支えている。他方でこのサラリーマン・労働者は、自給自足の中世の農民とは異なり、資本によって生み出され、資本主義企業によって雇用されることにより存在しているのだから、資本主義社会によって支えられている。(しかし、こんなわかりきったことはわざわざ書く必要がないようにも思うのだが。)とすれば、「遊びでも真面目でもない」とホイジンハは言うが私の見方ではその両方であるような、プロスポーツのあり方は慣例化された資本主義社会ときわめて密接な関係があり、「有機的に結びついている」と言うべきだろう。
要するに、ホイジンハのいう「真面目の支配」とは、生活上の必要を満たすこと、金銭を稼ぐことを大切な務めと考え、職業に真剣に打ち込むことであり、「慣例化」にしたがって生活することである。だが、エリアスの言うように、プロのスポーツは「楽しい興奮」を人々に与え、慣例化圧力を緩和してくれる社会的な仕組みであり、スポーツは資本主義の支配する産業社会が要求する「真面目」を可能にする大衆文化であり、なるほど宗教などのような高級文化の「本来の文化過程から外れて位置している」ように見えるかもしれないが、社会の構造ときわめて密接に結びついている。まさしくスポーツと現代社会は「有機的に結びついている」。
とはいえ、私は、現代社会において、人はスポーツや音楽などの芸術を「見る」あるいは「聴く」などすることしかできず自ら行なって楽しむことは出来できないと言いたいわけではない。資本主義の仕組みが根本から変わらなくても、あるいは(生涯)労働時間の大幅な短縮が制度的に直ちに実現しなくても、私たちが物質的消費へのこだわりと職業/労働への意味付与を減らし、世間の常識に従うことをやめ、自分の生活スタイルを変えることができれば、われわれは相当程度自由時間を拡大し、スポーツや芸術を自ら行なってたのしむことができる、と私は思う。
この文章では、まず、ホイジンハが優れて(つまり文化へと発展する)遊びであると考える二種類の遊びは、他の日常生活あるいは現実の生活と違って、「規則」によって作られているということ、あるいは遊び手が規則に従うことによって初めて成り立つということが言われているだろう。
サラリーマンが、朝おきて、食事をし、職場に向かう。これは毎日、ほぼ規則的におこなわれることだ。しかし、規則にしたがっている、規則により支配されている、とは言いがたい。他方、職場における仕事も、あるいは職場に向かう途中の道路の交通も、就業規則や道路交通法という規則に従って行なわれる。すると、規則に従って行なわれるということは、「現実」や「日常」の世界と区別される遊びの特徴ではないはずである。複数の人が一緒になり、あるいは活動を共有するときには、カオスに陥ることを避け、活動がうまくいくようにするために「規則」が必要なのである。
では、単に遊びの規則が遊びの世界を支配するということではなく、遊びの規則は「絶対的強制力をもっており、疑いをさしはさむ余地はない」ということをホイジンハは強調したいのだろうか。現実の人間世界はまず存在し、後に、規則(法や慣習)が作られたのであろうし、私の退職後の生活のようにほとんど全く規則を欠いた生きかたもある。法や規則の妥当あるいは支配は決して絶対的なものではない。これに対して、少なくともホイジンハが考察の対象としている遊びに関しては、規則があるというだけでなく、規則を無視してはそもそも遊びが成立しないと言える。とくに、テニスや100m走その他の「戦いの遊び」を始めるためには、遊び方、つまり競技・ゲームの規則を知っているだけでは遊びにはならず、その規則を「絶対的に」守らなければ、勝ち負けが決まらない。またホイジンハは論じていないが「演戯の遊び」も、遊びの参加者である観客が暗黙の規則あるいは約束にしたがうことで成立する。舞台で話している人物は、俳優の江守徹ではなくて、ハムレットであり、合板と木材で作られ白く塗られたものは、大理石でできた王宮の壁だ、等々の「劇」の約束、広い意味での規則を守って観客が参加するのでなければ、劇の世界は崩壊してしまう。
だが、こうした、規則によって成り立つ遊びの場合においては、規則が絶対的に支配し、規則が犯されるや否や遊びの世界は崩壊するということになるのだろうか。「遊びの規則が強制力をもつ」といえるのは、遊び手が規則に対して少しの疑いももたずに、規則どおりに遊ぶ場合であろう。しかし、規則に疑いが生じたり、話し合いの結果、変更されたりすることがあるだろう。たとえば、年齢差のある子供が遊んでいるときに、途中で年下の子のミスを「ノー・カウント」にするなど、譲ってやるということがある。途中から、「ハンディ」をつけてやることに規則を変更するわけである。その場合には、変更の多少にかかわらず、その以前の規則は不完全であった、しかし不完全ながらその遊びの世界は存在していたということだろう。そうだとすれば、規則が絶対的なものだとは言えないはずである。歴史的なケースで考えてみる。
しかし、最初のフットボールの規則が変わったのではなく、それに似た、しかし別の新しいスポーツ、新しい遊びが作り出されたのだと考えることもできる。「フットボール」が次第に行われることがなくなり、現在では誰も行なわなくなっているとしても、「フットボール」は昔のまま相変わらず存在しており、だれかやる人が出てくれば、前と同じように行うことができる。そしてそれをやりたい人は元の規則に従って行なう。現在行なわれていないのは、たまたま、それをやりたいと思うものがいないだけだ。そう考えれば、最初の「フットボール」の規則は変わっていない。そのように言うことも可能だと思われる。
しかし、現在のサッカーやラグビーが生まれるまでの間、かつての「フットボール」に新しい規則が付け加えられて変化していく途中のスポーツについてはどう考えるべきか。これまでたとえば20回の規則の変更がなされたとすれば、20個の異なるスポーツが新たに生まれたが、それ以前のそれと少しずつ異なるスポーツもすべてそのまま存在していると考えるべきなのだろうか。
NHKのあるラジオ番組(2012.2.14月曜夜「渋谷スポーツ・カフェ」)に出演したアーチェリー選手、オリンピック銀メダリスト山本博氏の話では、アーチェリーはオリンピックごとにルールが変わっている。変える理由は、少しでも(放映を見ている)観客が面白く感じるようにする、つまりアーチェリーの観客を増やすための工夫だという。この話を聞いて、アーチェリーの規則は変わっておらず(以前のまま存在しており)、今、山本氏らがやっている競技はアーチェリーの名を僭称する別のゲームだと考える人はあるまい。
写真はModern competitive archery, 英語版Wikipediaによる

上で見た「規則の絶対性」という主張は、規則によって成り立つ遊びについて言われていることである。だがそもそも規則のない遊びも多い。一人遊びではとくに無数の、規則のない遊びが存在する。ホイジンハは、一人遊びは文化的機能を持たず、文化になりえないと考えているので、そもそも彼の言う遊びのなかにはくわえていない。彼が文化的機能を持つ「高級」な遊びとして取り上げているのは競技と演技である。だが、これら文化的機能を持つ、「高級な」遊びだけが遊びではなく、一人遊びも含め、規則のない多くのほかの遊びがあるということは認めなければならない。
他の人と何かを競い、戦って勝つことに楽しみを見いだす遊びばかりが遊びではなく、一人で遊んでも楽しいし、他の人々と一緒に遊ぶにしても、「競い」、「戦う」のでない、楽しい遊びもたくさんある。そして競技、戦う遊びでない遊びは「演じ」、「表現する」遊びだけではない。釣りや山菜取り、磯遊び、ダイビング、山登り(山歩き)、ハンググライダー、海水浴、競技ではない限りのサーフィン、スキー、スノーボード、ヨット、サイクリング、などいくらでも、規則のない遊びを上げることができる。詳細で厳重なルール・規則が必要なのは基本的に勝ち負けの判定を必要とする競技、戦う遊びにおいてである。自然を相手にし、自然のなかで遊ぶときには規則は必要ではない。繰り返しになるが、競技である遊びは人間相手の遊びであるだけでなく、勝ち負けを争う遊びだからこそルールが必要なのであり、人間相手の遊びでも、競争でなければ、規則は必要がないのである。英国ならパブで一杯やりながらしゃべったり、議論したりする、日本でなら職場の仲間と花見に行き、一杯飲みながらカラオケをやるというような遊びにホイジンハが考えているような規則は存在しない。
少しわき道に入るが一人遊び、つまり競技でも演技でもない遊びを考えてみよう。私自身が子どもの頃にやったことのあ主な遊びだけでも、凧揚げ、紙飛行機、コマ回し、ブランコ乗り(など校庭、公園の遊具を使った遊び)、積み木、おもちゃを使った遊び。ホッピング、フラフープ、自転車の三角乗り、竹馬、穴を開けた二つの空き缶を紐で結びそれに乗って、手で紐を上に引くのにあわせて交互に足を前に出して歩く遊び、3本の棒を、端を突き出して縛って三角形にし、立て、水平部分に足を乗せ、上に突き出た部分をハンドルとして両手で掴み、三角形の面を左右に回転させるようにしながら前進する遊び、リム(自転車の車輪から、外側のタイヤやチューブ、内側のスポークなどを取り外した輪)の溝に棒を当てて、押し、輪を転がしながら前に進む遊び。これらは長く続けられるか、早く進むことができるかなど、「競争」することもできるが、1人で遊んでも十分楽しい。マットの上で、寝そべってごろごろ横に転がったり、飛んだり跳ねたり、でんぐり返りをする。シャボン玉。近所の池でカエルやザリガニやメダカを捕まえる。捕まえたカエルを引き裂きその足で、あるいはザリガニの殻をむいた身でザリガニを釣る。セミやトンボを取る。川や池に棒切れや石を投げ込む。川原から水平に石を投げ水切りをする。草むらで、棒切れを振り回し草をなぎ倒す。登下校の道で石をけりながら歩く。夏、たらいに水を張って水を掛け合う。木登りをする。張り出した木の上から下の川に飛び込む。砂場で穴を掘ったり、山を作ったりする。土手の斜面を転がる。冬、ソリや(竹)スキーで、坂や斜面に積もった雪の上を滑る。雪だるま、カマクラを作る。ひざくらいまで積もった雪の原を駆け回る。雪を踏みつけて迷路をつくり、そのなかで鬼ごっこをする。積もった雪の上に前を向いてあるいは後ろ向きに倒れて顔や体の跡をつける。田んぼや池に張った氷の上を長靴ですべる。ミカンの皮を剥きばらばらにした実を皿に載せておき、糸のついた縫い針を投げつけて刺し、引き上げて取る(取った者は食べることができる)。これは二人以上で行なうが、取った数を数えたりはしないから、競技ではない。木の枝を「刀」にして振り回すチャンバラ。これはふつう2人でする遊びである。二人以上でやる、勝ち負けを争うさまざまな遊び:相撲やトランプの「七並べ」、メンコ、ビー玉、(「五寸釘」を使い地面に刺さっている相手の釘に向かって投げてぶつけて倒す)「釘倒し」には、ごく単純なルールがある。複数で遊ぶ、ルールのほとんどないか全くない遊びとして、馬跳び、おしくらまんじゅうを上げることができる。
私はこれらの遊びを民俗学やその他の本で調べたのでなく、思いついたまま上げたのであるが、このように、一人、あるいは複数で遊ぶ、ルールが全くないかほとんどない、多くの遊びがある。これらはホイジンハでは、アゴーン(競技・闘技)と区別されて、パイディアーと呼ばれる幼稚な遊びに入れられるだろう。
私の住む愛南町家串地区(人口約300人)の牛鬼は、持ち上げられたときの体高は2m程度で、ウバメガシで作った楕円の胴回りと籠状に編んだ竹で作られ、体表はシュロ皮(葉鞘)の繊維で覆われている。祭りの日には、担ぎ手たちの気分しだいで、何回でも、どこででも、神輿とぶつかり合う。県道の真ん中で、あるいは農協前の広場で、ぶつかり合い、押しまくって相手が崩れれば勝ちだ。ただそれだけである。
写真は家串地区の秋祭りにおける牛鬼と神輿の鉢合わせ。牛鬼の頭部は右側にある。尻から突っ込んでいく。
画像は愛媛県愛南町教育委員会生涯学習課文化振興係よりお借りした。
 以前は、若者と高齢者の二チームに分けて担いでいた。だが最近は村内に残って真珠貝養殖業を継ぐ若い人が減ったことに伴い住民の数が減り、また高齢化が進んだために、以前のようなチーム編成は不可能である。それぞれ15人以上の担ぎ手が必要と思われるが、その人数が確保できない。また、当日、酔っ払って脱落者がでるたびに担ぎ手が入れ替わったりする。チーム編成はいい加減である。「社会的な遊び」だからといってルールなどなく、義務も任務もない。また勝ち負けも儀礼としての意味を特に持っていない。だが、ふだんの仕事の疲れや村民の間に生じうるわだかまりを解消し、皆大いに騒ぎ、楽しみ、へとへとになるまで遊ぶ。英国、中世のフットボールもルールはないも同然であった。「ポスト近代」国家における人口の減少した漁村で、同じように、規則やルールに縛られた「スポーツ」ではない、単なる娯楽、遊びが再び生まれたとも言えるだろう。(ただし、私がこの村に住みはじめてから7年目、2013年の秋から、牛鬼は「台車」に載せられた。担ぎ手不足がはっきりしてしまったのだ。)
以前は、若者と高齢者の二チームに分けて担いでいた。だが最近は村内に残って真珠貝養殖業を継ぐ若い人が減ったことに伴い住民の数が減り、また高齢化が進んだために、以前のようなチーム編成は不可能である。それぞれ15人以上の担ぎ手が必要と思われるが、その人数が確保できない。また、当日、酔っ払って脱落者がでるたびに担ぎ手が入れ替わったりする。チーム編成はいい加減である。「社会的な遊び」だからといってルールなどなく、義務も任務もない。また勝ち負けも儀礼としての意味を特に持っていない。だが、ふだんの仕事の疲れや村民の間に生じうるわだかまりを解消し、皆大いに騒ぎ、楽しみ、へとへとになるまで遊ぶ。英国、中世のフットボールもルールはないも同然であった。「ポスト近代」国家における人口の減少した漁村で、同じように、規則やルールに縛られた「スポーツ」ではない、単なる娯楽、遊びが再び生まれたとも言えるだろう。(ただし、私がこの村に住みはじめてから7年目、2013年の秋から、牛鬼は「台車」に載せられた。担ぎ手不足がはっきりしてしまったのだ。)
一人で遊べる遊びは競技ではないから、勝敗を決めるためにどうしても守らなければならないものとしての規則はもちろんない。他の遊びと区別する「遊び方」の規則もきちんと「決まっている」わけではないが、子供同士の間では実際にやって見せることにより、すぐに教えることができる。簡単に入手できる空き缶や棒切れなどで作った用具を使い、手足や体を動かすという程度の変幻自在のものである。各自が遊んで楽しければ、それでいいのであり、それがいかなる遊びであるかを言葉で示す必要もない。そして、各自が一人で勝手に遊ぶ限りにおいては、偶然であれ意図的であれ、その遊びは前回どおりに行われるとは限らない。どんどんちがったものになる可能性があるがそれでもいっこうに構わない。
かつて、ヴィトゲンシュタインは「私的言語は不可能だ」といった。言語の使用においては一定の規則に従うことが必要だが、私的に作った規則にもとづく、自分だけの言語なるものは存在し得ない。というのは、ただ一人では、規則にしたがっていることを確かめるすべがないからである。言語活動は他のひととの間でゲームを行う場合と同様、反則があったときにそれに気づき訂正して、規則に従っていることを確かめ合いながら行われる活動だ。野家(のえ)に言わせれば、言語活動は「共同体的実践」なのである。(野家啓一「言語と実践」<新岩波講座哲学>2『経験 言語 認識』(岩波書店、1985)
一人で遊べる遊びでも、たとえば、前出、作家/画家の玉村豊男が新聞の随筆欄で、子供のころ家で繰り返しやった「高跳び」について書いたように、遊び方を他の人に説明したり、他の人とその遊びについて話し合ったりしようとする場合には、その遊び方を言葉で説明できなければならない。それを繰り返し行うことが可能であるためには、遊び方が一定したものでなければならない。しかし、自分で楽しむ限りにおいてはあやふやで、他の人に説明ができなくてもいっこうにかまわない。もし「あれ」をやりたくなったら、やってみればいい。記憶が不確かでうまく遊べなければしかたがない。別の遊びをやればいい。遊びはいくらでもある。「これ」あるいは「あれ」をきちんと言葉で伝えなければならないのは、他者との関係においてだけである。そして遊びは基本的に自分が遊んで楽しむためにあるのであって、人に説明するためにあるのではない。
上で列挙した、子どもの頃に私がやった一人遊びも、その大部分は名前がないし、他の子供たちのやっている遊びを見、それを真似てやったのだ。一人では思いつかないが、特に説明されなくても、見よう見まねでできる遊びは多い。私は、遊びにコミュニケーションが必要ないなどと言いたいわけではない。立ち上がることであれ言葉を話すことであれ、ほとんどあらゆることがコミュニケーションを通じて、他の人から学んでできるようになるが、遊びも大部分はそうである。特に、複雑な大人の遊びは、教わらなければ、全くできないか、できても拙劣にしかできるようにはならない。しかし、積み木遊び、マットの上でごろごろしたり跳んだり撥ねたりすること、川や池に棒切れや石を投げ込むこと、棒で草をなぎ倒すこと、積もった雪の上に寝転がってみることなど、一人で考え出して、あるいはなんとなく思いついて、あるいは勝手に手足が動いて、楽しんだ、単純素朴な遊びもある。
そして手製の道具を使うなどする、もう少し複雑な遊びは、だれかが最初に、思いついたのだろう。ルールがあろうがなかろうが、人から教わったものであろうと自分で思いついた遊びであろうと、楽しむことができればよい。こどもにとっては、学校での「勉強」や家の「お手伝い」は、教師や親からやるように言われたことを言われたとおりに、やりたくなくてもやらざるを得ないことである。遊びは、こうした勉強やお手伝いから逃れて、「楽しさ」だけを追求しようとする活動であり、大人の場合も、職場でのあるいは家庭でのやむを得ない仕事から解放される「自由時間」に、まず、楽しさを求めて行う活動であって、私は、規則が、あるいは、規則に自らを拘束することが遊びの本質的特徴だとは思わない。
またホイジンハは単なる遊びに過ぎない賭けごとは「精神にも生活にも何ら寄与するものをもたない」がゆえにそれ自体は「不毛だ」という。他方、彼は古代の多くの民族において、神による裁きを知る方法としてサイコロを投げたことについて述べている。彼は、サイコロを投げて、真実、あるいは正義を知ろうとすることが後に裁判や法などの制度あるいは文化に結びつき、「文化の土台」になったと判断されるかぎりでのみ、「賭け事」という遊びの意味を認める。
彼はこうして、遊びを文化や社会の歴史的発展との関係で位置づけ、評価しているが、結局、彼が批判していた、生物学的機能との関係で遊びを説明するやりかたと同様、遊びを外なる目的との関係で論ずることになってしまっている。
また遊びが文化として社会的なものとして定着することは、遊びの性質を変化させてしまうことにならないか。遊びが「肉体的要請〔あるいは物質的利害〕によって課されるものではなく、なおさら道徳的義務によって課されるものではない」という本質的特徴を失うことにならないか。彼自身ももし「遊び自身が文化になるという事実が明らかになると利益度外視の特徴は消えてしまうのではなかろうか」と問うている。だが、彼はその問いに対して否定で答える。「なぜなら遊びが役立とうとしている目的は」〔以下は高橋訳による〕「直接の物質的利害の、あるいは生活の必要の個人的充足の外におかれているからである」。神にささげられた行為としての遊びは確かに集団の福祉に役立つが「それは生活の必需物資を手に入れることを直接めざした手段とは別のやり方で執り行われる」のだからとホイジンハは言う。
たしかに文化となったときにも遊びは、労働とは異なり、物質的な利害実現の手段として行われるのではない。そして、祭りにおける諸活動は、日常の規則とは異なる規則が適用される場所で行われ、また、祝うこと自体が目的であるような、つまり楽しむことだけを目的とする自己完結的な活動だ(結果において共同体の利益になる)という点で、祭礼儀式が遊びと同じ性格を有するという、彼の主張は理解できる。
しかし、彼は、遊びの第一の特徴として自由であることを挙げた個所では、「遊びが文化的機能となったときにはじめて、第二義的に、当為とか、任務とか義務といった概念との結びつきに縛られるようになる」とも言っていた。そして、実際、決められた行事として、演技が祭礼の中で行なわれるとすれば、役割が予め決まり、練習をしなければならないだろうし、当日に、必ず自分の役割を果さなければならないし、成功すれば名誉になるかもしれないが、失敗すれば譴責されたり、大きな恥をかくことになるかもしれない。「いつ何時でも延期できるし中止もできる」ものではなくなる。
闘技あるいは競争についても同じことが言える。遊びで行なわれるのであれば、参加は自由である。そして、そこで楽しんで終わりである。しかし、それが、学校の運動会でクラス対抗の選手として出場するというのであれば名誉がかかってくる。勝てば女子/男子に「もてる」だろうが、負ければみじめになる。文化といって間違いないと思われる国体や甲子園に出場ともなれば、懸っているものはずっと大きくなるだろう。遊びとは別の目的が遊びの自由と楽しさを損ねてしまう。
遊びは楽しむことを目的とする活動であり、義務や責任に基づいて行う活動ではなく、自由に行なうことができる活動であるという特徴を持つ。自由な活動であるということが、遊びを楽しいものにしている。
私は、第2章3節の「自由時間のスペクトル」ではチームで行う競技などでは、他のメンバーの面倒を見るなど「他人のため」に行うことも、その遊びが好きで楽しいという人にとっては楽しくなる、と言った。しかし、(一人で遊ぶのであれ複数で一緒に遊ぶのであれ)自由に、気ままに行われていた遊びが何らかの理由で「行事」となり、他者との約束のもとで行われるようになれば、楽しさは最初に比べて減るだろう。そして、「より高級な」社会的遊びとなって、義務や任務との結びつきを強めれば強めるほど、代わりに賞賛などの社会的評価を受けるかもしれないが、遊びでなくなっていく。
また、遊びが文化と見なされるかどうかということは他者による評価が前面に出てくることである。だが、その遊びが後の世の人々によって、あるいは研究者など他者によってどう評価されるかは、遊んでいる人々にとっては全く関係のないことである。「遊びはそれ自体だけで完結する一時的行為としてその生活過程の中に割って入り、行為すること自体に含まれた充足感のゆえに行われる」とホイジンハも言う。当の人々が、仕事でも義務でもなく、他者の評価や学問的研究と関係なく、遊びたいと思って遊ぶということが遊びであることの最も重要な特徴だと私は考える。
ホイジンハは「人は遊びに勝ち誇り、それを他人に伝えることができるという事実のなかにすべての遊びにとって非常に本質的なものがある」といい、「この点で釣り天狗は最もみごとな典型だ」という。彼は一人遊びも含め、すべての遊びにおいて、うまくいったことを誇り、「他人に伝える」ことが本質的な要素として含まれていると考えている。
しかし私には必ずしもそうは思われない。文化となっている遊びに加わる人、つまり、長年、決まった日に行なわれ、大勢の人が集まるような競争、闘う遊びに加わる人は、その勝利、成功が直接他の人々に知られることを求めて、その競争に加わるのだろう。しかし他の人に認められることをとくに求めない、他の人に自分の遊びを見せたいと思わない遊びはいくらでもある。「釣り天狗」は釣りと全く関係がないと私は言いたい。人はしばしば「天狗」になるかもしれない。天狗になる傾向の人は釣りにおいても天狗になるだろう。だが釣りは一定の技術を必要とはしても、ゴルフのパーや水泳や陸上競技のタイムのように自己の力をコンスタントに発揮できるスポーツではない。しばしば初心者が大物を釣ってベテラン を悔しがらせる。ビギナーズラックと言う言葉がもっともよく当てはまるのが釣りである。
2013年7月30日の新聞にロシアのプーチン大統領が川を背景にやや大きな魚を持って立っている写真が載っており、「プーチン氏“フィッシング詐欺”?」という見出しがついている。読んでみると、この写真はロシア大統領府が公式サイトに最近公開したもので、プーチン氏が休暇で21キロの大魚を釣り上げた際の写真だという。ところがこれは以前の古い写真の転用だという説がネット上に流れ、また釣りの愛好家も、写真から判断すると魚の重さはせいぜい10キロ。21キロは大げさだとネット上で主張する「騒ぎに発展」しているという。要するに「写真や映像で頑健なスーパーマンぶりを誇示する手法にほころびが目立ち始めた」というのだ。
写真の真偽はどうであれ、プーチン氏がこの写真で大物を釣ったと自慢していることはたしかであり「釣り天狗」ぶりを示している。しかし、彼は単に釣り好きで「釣り天狗」であるだけではなく、柔道や乗馬を始め様々なスポーツを好んだし、スポーツ中の写真がしばしば「公開」されている。こうして「天狗になる」つまり自分が何かにおいて人に勝ることを誇示しようとする人は、釣りにおいてだけではなく、何においてもそうしたいのであり、プーチン氏は自分の頑健さを誇示するためにスポーツを好んだのだろう。
ホイジンハはこの一箇所においてだけ、「釣り」という語を用いている。だが、釣りの楽しさを書くかわりに、「釣り天狗」であること、つまり他人に自慢することを好む人についてだけ書いている。私は、他のところで、釣りについての「随筆」を書いている。釣りについて人に自慢したり、自慢でなくても何か釣りについて書くことは、釣り固有の楽しみではない。釣りをしても自慢しない人、何も書かない人は多い。どんなことでも自慢したがる人はいるだろうし、どんなことでも「随筆」の材料になる。それはコミュニケーションを求めることであろう。プーチン氏は政治家としてコミュニケーションを重視するのは当然である。しかし遊びはコミュニケーションとは異なる。
文化的な、あるいは社会的な遊びは、同時に、コミュニケーションを求める遊びであり、他者の評価を気にする遊びである。だが、すでに上で多くの「一人遊び」があることを示したように、コミュニケーションを目的としない遊びはいくらでもある。そして釣りはそのような遊びの一つである。釣りは魚が釣れるかどうかだけが問題であり、誰の評価も、いかなる人とのコミュニケーションも問題ではないような遊びである。そしてこれこそ完全に自由な、遊びに内在する楽しさを味わうことだけを目的とする遊びだと私は考える。(とはいえ、私は人がいかなる遊びをもっとも楽しいと感じ、もっとも好むかは人により異なる、「蓼食う虫も好き好き」と考える。他の人と語らい一緒に遊ぶことが楽しい、あるいはチームワークによる遊び(競技、ゲーム)の中でこそ楽しいと感じる人が沢山いることを否定しようとは全く思わない。
そう考えれば、遊びだけが、他の活動の中に割って入ったり、他の活動を差し止めたりするのではなく、他の活動が遊びを差し止めたり割って入ったりするとも言えることがわかる。
私は還暦を機に退職し、その後は一切仕事には就いていない。現在の私にとっては、遊びの中に、時々、必要な生活過程、食事を作ったり、洗濯をしたりすることが「割って入って」くる。私が主に行なっている種類の活動は遊びであり、その中に短時間の他の種類の活動が一時的に入ってきて、遊びを差し止めるのである。しかしそれら必要な活動も、遊びと無関係な別の現実ではなく、遊びを行なうために必要な活動である。神であれば、食事や、洗濯などは不必要である。ただ遊べばよい。生物である人間は、遊ぶためにも生きてゆかねばならず、生きてゆくためには食べたり洗濯したりもしなければならない。
資産家というほどでなくても家と多少の土地を持っていれば、好きな畑仕事を楽しみながら自給自足に近い生活を送り、遊び時間もたっぷり確保するということも可能だが、一般的には人は何らかの職業について生活するのだから、遊びに当てる時間を制限されてしまう。しかし、「運」や「社会の仕組み」や「生活の必要」がその人の一日の、また一生の、生活時間の割り振りのありかたを自動的に決定するのではない。必ずしも必要からではなく、「寝食を忘れて」仕事に打ち込む人もいる。こうした人の場合、遊びは生活過程に「割って入り込む」ことすらできない。また「必要」の幅は、企業の宣伝や世間の常識に安易に従って行なう贅沢な消費を減らすことで縮小可能だ。あるいは、仕事のなかで出世することこそが「人生」だなどと考えなければ、残業や休日出勤を減らすこともできるし、60歳あるいはそれ以前に退職することもできる。こうして人は自分で労働・仕事に当てる時間を減らし、遊びに充てる時間の配分を増やすことが可能である。
遊ぶ人の観点にたってみると、遊びはある瞬間に突然始まり、同様にある時点を境に急に消滅するとはいえない。たとえばアマチュア棋士の高段者が将棋の県大会の決勝戦に臨むとしよう。(プロ棋士の将棋でも全く同じことが言えるが、プロの対局は遊びではないので、アマ棋士を例に取る。)彼は対局の何日も前から、対戦相手のこれまでの戦いの記録を研究するだろう。このときにすでに遊び=対局は始まっていると考えてもおかしくないだろう。そして本番では、勝負がついた後、高段者の場合にたいてい行われる「感想戦」で、その戦いを振り返りながら、少し違った形で、もう一度戦う。そして本番で惜敗したのであれば、彼はその後しばらくの間あるいはもっとずっと後まで、その戦いでの指し方をあれこれ振り返り、別の手を考え続けるかもしれない。つまり、この将棋の県大会の決勝戦はどこで始まりどこで終わったかは、「遊ぶ人」からすれば、はっきりしていないと言っていいはずだ。
「演技の遊び」については、たとえば演劇を見て楽しむ観客は「演技の遊び」の参加者である。この観客の観点からは、一つの劇は幕が上がったときに始まる。しかし、役者は、突然ある瞬間に舞台の上に立ってある役を演じる=遊ぶことはできず、稽古のときに、すでに、遊び=演技は始まっていると考えられる。また観客も、劇が終わった後も、とくに、よいものであったなら、様々な場面を思い出し、繰り返しその劇を楽しむだろう。幕が下りるとともに観客の遊びが「終わる」とは言えない。これらのことは非常にあきらかである。演ずるものにとっても観客にとっても、劇が始まる前からそして終わった後も様々なしかたで存続していることが指摘できる。
私が農協のマーケットで働いているとしよう。販売されている品々は国内外の無数の人の手からなる極めて複雑で長い連鎖の中で生産され、運搬され、ここに置かれている。だが、私の仕事は、たとえば食品の安全性のチェックや、農協支部の会計処理や、本部の税金の支払い等々、このマーケットでの仕事に関係のある無数の仕事には一切関係なく、この店で客に応対するという、決まった仕事だけを行なうのである。そして、ここにある品々の生産や輸送は夜を徹して、休日にも祭日にも行なわれているだろうが、もちろん、私がこの店で働く日や時間は決まっている。だから、個々の労働者は仕事を限定された時間に、限定された範囲で行なうのである。
生活するものとしての私の一日は、すでに見たように、たとえば自由時間と職業上の労働時間に分けられ、自由時間は家事・育児などの労働、遊びなどの余暇活動の時間に分けられる。それら様々な活動は、相互に割って入ったり、他の活動を差し止めたりする。一定時間を企業のオフィスや工場などに拘束されて行なう労働ではないタイプの、たとえばパソコンを使って家庭で行なえるタイプの職業であれば、いっそう、そのことがよくわかる。
上では遊ぶ人にとって遊びは閉じていないと言ったが、遊び「自体」も決して閉じているとは言えない。テニスであれ、野球であれ、規則を構成している言葉は世界とつながっている。われわれは日常的な世界のなかでの経験と言語使用を踏まえ、その遊びの遊び方、ルールを理解する。球やラケットやネットなどの道具の意味をはっきり理解できるのは、それらが日常生活のなかで全部ではなくても、かなりの程度、何であるかが明らかであるからである。もし、動物や魚を捕獲するための「網」が存在していなければ、つまり誰も「網」を知らなかったならば、おそらく、コートの中央に「ネット」を張るテニスという遊びは「創造」されなかっただろう。
野球の規則は、打者には打ったら一塁に向かって走るよう命じ、野手には捕球し一塁手に向かって投げるように命ずる。それに似た行為動作を日常生活の中ですでにおこなっているから、規則の命令を理解することができる。「一塁に向かって走る」ことは遊びの規則が作り出した動作であるが、遊びの規則は「走る」ことを作り出すことはできず、現実の世界から借りてこなければならない。そもそも遊びの規則でさだめられている、ボールの大きさ、コートの大きさや「まっすぐなライン」や「ネットの高さ」などは感覚的世界の中に属するものである。
こうして、遊びのなかで用いられる道具、遊びの中で行うべき動作・行為を、現実世界、日常生活と無関係に、規則だけによって、「創造」することはできない。遊びの世界は、その大部分を経験的な現実世界から借用し、そのなかに、直線を引いたり、区切ったりし、特殊なしかたで行動するよう命じ、あるいはその内部と外部を区別し外部を捨象することができるだけであり、はじめからその内部で完結し、閉じているのでは決してない。
ユークリッド幾何学は、感覚的経験の抽象化や再構成の手続きを経て体系化されている。しかし、それは、土地の測量という現実世界における人間の活動から生み出されたものである。現実の地球近傍の空間を念頭に置いて作り出されたものであったからこそ、「ある直線の外の一点を通ってその直線に交わらない直線は一本だけ存在する」(あるいは「平行な二直線にほかの一直線が交わってできる同傍内角の和は2直角をなす」)ということが公理になったのであり、19世紀に生み出された非ユークリッド幾何学のように、最初から、そのような直線は「無数に存在する」ことあるいは「一本も存在しない」ことを公理とするものではなかったのである。(そして非ユークリッド幾何学はそれ以前のユークリッド幾何学を含む数学や論理学などの、“純粋ではない”学問すべてとつながっている。)幾何学における円や直線は、道具を使って描いたり測ったりでき、感覚でとらえられる「まん丸」とか「まっすぐな線」とは異なる理論的概念である。しかしそれでもやはり、現実に根を下ろしている。それと同じように、遊びの規則もまた純粋な仮構から成り立っているのではない。日常生活とは異なる特殊な規則で構成されているという遊びの世界も、現実の感覚的世界と連続しており、決して閉じられてはいないのである。
ホイジンハは祭礼儀式は日常生活から切り離された「神聖な場」で行われるのだと言っていたが、エリアスはゲームが行なわれる競技場や球場が「飛び地」だと言っていた。エリアスは、そこでは、日常生活に要求される「抑制」が緩和されるだけでなく、現実の中では生じない「模倣的経験」を観客に与え、人為的な興奮状態が作り出されると言う。だが、その興奮が原因になって「余暇を追求している人々自身あるいは他の人々のどちらかに危害がくわえられないように監視の目を彼らに注いでいる国家権力」が存在し、「今日の国家権力の規制力の効果ははなはだしく大きくなって」いることも指摘していた(第2章4節参照)。
古代社会における「神聖な場所」の非日常性については議論を保留するにしても、スポーツの「飛び地」は日常の現実生活から遊離して存在するかのように見えても、実は、現実によって支えられているのであって、「飛び地」自身の力によって宙に浮いているのではない。そして、それとまったく同様に、遊びの世界は無から自らを「創造」したのでは決してなく、現実世界のなかにその根を持っており、その無限に広がる現実とつながることによって存在しているのである。
遊びの世界が閉じているというのは、全く一面的な見方に過ぎない。あるいはある一面を誇張して捉えることにより生じた見方に過ぎない。だが、上の議論はホイジンハの議論の理論的な難点を指摘する、あるいは彼の議論に難癖をつけることが目的で行っているのではない。私は、遊び---ホイジンハの言う宗教儀礼としての遊びではなく、他の一般的な遊び----とそれ以外の活動とが人間の生の次元で同じ平面上にある、あるいは同じ重要性を持っているということを主張したいのである。
ホイジンハによれば、遊びの世界が規則によって作られ、現実世界とは切り離されてそれだけで閉じているとされるが、その仮構の世界は現実世界の上方と下方に分かれているとされる。「人は子どものように楽しみと休息を求めて、真面目な生活の水準以下で遊ぶ。しかし同時に彼はこの水準以上のところで美と神聖の遊びを遊ぶことも出来る」と言われているからである。一方で「美と神聖を求め」上方に向かう遊びは競技として「祭の一部を構成」し、「奉納される」ことに、また清めや秘儀である「祭式演戯」として行われることにより、人間をこの地上の俗世界からより高次の聖世界へと飛翔させる。この世界は儀式のきまり、競技の規則、そして特定の「場所と継続期間」によって「ありきたりの世界」から厳格に切り離され区別される必要がある。
他方「楽しみと休息を求める」「子どものような遊び」は演戯や競技の遊びと異なり、俗世界に止まる遊びである。身近な場所でまた毎日の生活の合間に行われるこの遊びもまた、真面目に営まれる物質的生活の下方に止まるようにと、遊びの規則によって指示される。(将棋盤を使い、王が詰むことによって終わるなど)場所や時間によって切り離され、現実世界と区別される。私は聖なる遊びについて語る力が全くないし、また次に見るカイヨワにしたがって、聖なるものに関わる宗教的行為は遊びではないと考えるので、「上方への切り離し」についてはふれない。俗世界の遊びについてだけ考える。
さて遊びはその規則によって日常生活ないし現実生活から切り離されているという主張は、遊びが従う規則と職業上の仕事や家事育児が従っている仕事の規則(家族の生活のために、計画的に、規則正しく、約束を守り---行動せよ)とは異なる、という単なる事実についての言表ではない。遊びの規則は仕事の規則の下位にあり、仕事の規則を妨げない範囲で守られべきものであること、つまり、遊ぶのはいいが、けじめをつけて遊ばなければならない。遊んでもそのつどきちんとけりをつけ、遊びを生活の中にまでもちこんではならない、等々のことを「遊びは閉じている」という主張は含意している。つまり、遊びは「真面目な生活の水準以下にある」ものとして現実から切り離されているということは 遊びは重要ではなく、仕事を中心とした生活に従属するものだということを含意しているのである。
しかし、私は遊びもそれ以外の活動も、それぞれ違ったルールにしたがって現実世界の中で行われ、そのどちらも、私の現実の経験として私の生を構成する。仕事も遊びもどちらも、私の一定の真面目さを要求し、喜びや悲しみ、苦しみを私に与えて、私の生の中身になる。私は仕事の中では仕事をすることによって生きる。私は遊びの中では遊ぶことの中で生きるのである。こうしたことをもう少し詳しく述べたいが、そのために、ホイジンハと同じく遊びが「仮構」だ主張する、カイヨワの議論に反論し、遊びの現実性についてもっとはっきりさせたい。その作業を次の節でおこなって、今の議論の続きをおこなうことにしたい。
だが、この結果からすれば、人間はホモ・ルーデンスだというのは現在のことではなく、過去におけることだということになる。あるいは、やはり人間はホモ・ファーベルであるということになるように思われる。
ホイジンハは、職業を中心とする「真面目な」あるいは「ありきたりの」生活が支配的な現代に批判的である。一般の職業生活は人間の生物学的な必要を満たすためのものでしかなく、精神的でより高次の人間の欲求に応えるものは遊びと結びついた文化であるはずだと考えるのである。だが、現代においては遊びと結びついている文化は音楽、詩、踊りなど芸術活動のごく狭い領域に局限されている。
かれは、19世紀以降の社会においては、遊びが真面目な生活のなかにしばしば「割って入る」と言う。以前の社会で支配者の貴族たちが遊んで暮らしていたのとは異なり、現代社会を担う「市民」は経営者も自営農民も労働者も、一日の時間の多くを労働あるいは職業活動に充てなければならず、レクリエーションや気晴らしが必要だからである。しかしホイジンハは、そうした「生物学的」欲求充足のための、個々人の「遊び」は非社会的で、文化的機能を持たないと考える。それらは子どもたちの遊びと同じ、「本物の生活と異なる」、「単なる楽しみに過ぎない」ものであり、「真面目の世界」と比較すれば「劣等」なものとかれは見なす。そして、(宗教改革によって)人々が共同体の福祉と結びついた高次の精神的欲求を充足することのできる宗教的な祭礼・儀式の機会もほとんどなくなってしまった。これがホイジンハの見る歴史的西欧社会の像である。
彼にとって現代社会は中世の遊びと祭礼に満ちた社会に比べて、味気ない、精神的な輝きを欠いた社会であり、物質的富の拡大を追求するだけの「真面目な」経済活動が支配する社会、労働者と(「いつも変わらぬ」背広やフロックコートの)資本家からなる「平等な」社会であり、混乱と無秩序の支配する社会である。(そしてヒトラー政権によって開始されつつあったヨーロッパ帝国を目指す世界戦争はその象徴である)。ホイジンハの考えは一面では、現代社会の問題点を鋭く衝いているが、他面では(注でふれたが、グルノーが指摘するように)貴族や僧侶の支配する中世の階級社会の問題点に関する視点を欠落させたものであった。彼は失われた過去を感傷的に回顧している。
上では『ホモ・ルーデンス』における叙述の順序にほぼ従って、その内容を紹介したあと、ホイジンハの論じていることのうち、規則の支配という点からはじめて、彼の考えを検討し、私の意見を述べてきた。実は同書最後で、ホイジンハが「結論」として述べていることは、まだ、紹介していない。それをここで紹介し、検討したい。
36年に第11回オリンピック大会がベルリンで開かれた。ナチ政府は競技場に〈ハーケンクロイツ(かぎ十字)〉の党旗を初めて公式の国旗として掲げるなどし、政治色の濃い大会となった。聖火リレー、聖火台など、のちにIOCで規定される式典様式はこの大会で創始されたものが多いという。IOC が記録映画をつくるようになったのもベルリン大会からであり、L. リーフェンシュタールの《民族の祭典》と《美の祭典》(ともに1938)はベネチア映画祭で金賞を受賞した。要するに、ナチスは、オリンピック大会を新たな、政治宣伝の場として作り上げ、利用した。ただし、オリンピック憲章は、創立以来の鉄則として、根本原則の第3条で、〈いかなる国または個人に対しても、人種、宗教または政治的な理由で差別することは許されない〉と規定している。この原則は第11回オリンピック・ベルリン大会のときが初めて発動され、IOC はオリンピック大会の主催権が IOC にあることを主張して、ユダヤ人排斥の宣伝物を会場周辺から撤去させるなど、極力政治的干渉に抵抗した、という。川本 信正+野々宮 徹「オリンピック」DVD-ROM平凡社世界大百科事典による。
本書『ホモ・ルーデンス』の刊行は38年とされているが、「戦争は1939年9月1日、イギリス首相チェンバレンがラジオ放送の中でギャンブル(賭け)と名づけた---」という文があるので、本書の印刷はこの後であり、この文は印刷直前か印刷中に書き加えられたのであろう。こうした状況下で本書が公刊されたことを考慮すれば、「現代文化のもつ遊びの考察」と題された最後の章で遊びとの関係で論じられているスポーツ、芸術、科学、政治、国際政治、近代戦争等はいずれも、ナチス・ドイツのファシズム、対外侵略政策を意識しながら書かれていると考えて当然であろう。
ホイジンハは「遊びの要素の不可欠性について」と言う見出しのついた「結論」のすぐ前の個所で次のように述べている。やや長いが引用しておきたい。
「われわれはゆっくりとではあったがやっと1つの結論に近づいてきた。真の文化はある程度遊びの内容をもたなくては成り立ち得ない。なぜなら文化は何らかの自己抑制と克己を前提とし、さらにその文化に特有の性向を絶対最高のものと思い込んだりしない能力をもち、しかも、自由意志で受け入れたある限界の中で閉ざされた自己を見つめる能力を前提している。文化はある意味で何時の時代でもやはり一定の規律への相互の合意に基づいて遊ばれることを欲している。真の文明はいかなる見方に立とうと常にフェア・プレーを要求する。またそのフェア・プレーとはつまり善良な誠実さを遊び言葉に言い換えたものに他ならない。遊びの協定破りは文化自体をも破壊する。文明の持つ遊びの内容が、文化創造的、あるいは文化推進的であろうとするなら、それは純粋でなければならない。それは理性や人間性や信仰によって定められた規範から迷いだしたり、それに違反したりしては成り立つはずがない。それは故意に育成された遊びの形式によって特定の目的を実現する企てを隠すための、偽りの仮面の装いであってはならない。真の遊びはあらゆる宣伝を締め出す。それはそれ自身の中に目的を持っている。その精神と情緒はこころよい恍惚境のそれであり、ヒステリックな大騒ぎのそれではない。あらゆる生活分野を一手に支配しようとしている現代の宣伝プロパガンダはヒステリックな大衆反応を巻き起こそうとし、そのための手練手管を動員して運動している。その場合、遊びの形式を借りたにしても、それは遊びの精神の近代的表現とみなされるべきではなく、ただそれにあやかった偽物であると考えるべきである」。
この文ではナチスの戦争政策に対する批判と、オリンピック・ベルリン大会を政治宣伝のために利用したことに対するする批判が行なわれている。一般的に、スポーツの国際大会がナショナリズムの高揚につながることは確かであり、そうした観点からのスポーツ研究も行われている。遊びの研究の古典としてホイジンハを読む私としてはこの問題に触れる余裕はない。もう一つのナチスの戦争政策批判として彼が述べている国際関係におけるフェアプレーの要求という、戦争を遊びあるいはスポーツのもつ「規則遵守」という面と結びつけて論ずる点について一言触れたい。
さきに、規則が遊びの世界を絶対的に支配すると言うホイジンハの主張を批判した。遊びがうまく行かない(つまり遊びの「世界」も不完全である)ことはしばしば起こりうるということ、規則は変わること、規則のない遊びも多数あることを指摘した。現実の世界もまた不完全である。その不完全さに遊びの規則を対置してみても何も得られない、と私は思う。
中世ヨーロッパの封建領主間のいくつかの戦争も、場所や日時を指定し、礼節をもって戦われる、競技として行なわれた。そのような戦争は、一人一人が平等な人間として、平等な権利を持ったものとして認め合う場の中で行われているとホイジンハは言う。
国際法は、対立する両陣営がお互いの共同体成員を「人間」と認めており、「人類」という理念による「共通の橋渡し」があることを前提にしている。「戦争は名誉と徳の厳粛な遊びであるという観念のなかから、騎士道の理念、つまり高貴な戦士の理念が形成され、騎士的義務と騎士的品位と言う観念像の結合から、---国際法の体系が」生い立ってきた。「名誉に反することは規則に反す」という意識をもつ国際法は闘技的世界に発している、と言う。
ホイジンハは戦争においても規則(法)が存在するし、それを守るべきだと説いている。実際、20世紀における二つの大戦と多くの地域紛争で起こった戦争に際して、戦争裁判が行われ、個別的な国際法違反行為が裁かれた。ナチス政権によるユダヤ人の大量虐殺の罪はあきらかなことだと思われる。日本軍が中国大陸などで行った虐殺など多くの罪もまた裁かれて当然と思われる。しかし虐殺を行った人々は、ユダヤ人、中国人、等々を「平等の権利」をもたないと見なしたがゆえに、殺して構わないと思ったのだろうか。(ナチスによるユダヤ人殺戮行為に関しては保留するが)アメリカ軍による原爆投下や、ソ連軍によるカチンの森における虐殺、等々はアメリカ人が日本人を、ロシヤ人がポーランド人を人類と見なさなかったから起こったことなのだろうか。そうではないだろう。戦争の中で敵国人はすべて殺して構わないと考えることによって、生じたのだろう。
東京裁判とニュルンベルグ裁判では戦争そのものに対する責任追及も行われた。私は連合国側が敗戦国の日独を裁くことが正しいとは思わないが、同時に、開戦を決定した日独の責任者たちが有罪であることは間違いがないと思う。
戦争を「節度ある」形で行なう、つまり国際法に違反しないように、ルールを守って行うようにすることが目標だとは考えられない。いったん、宣戦が布告され、戦争が開始されれば、自国が廃墟にされ多数の国民が犠牲になることを断じて許せないと考える指導者たち、自分が死ぬかもしれないという恐怖と闘いながら戦地で戦う兵士たちに、「フェアプレー」を守るよう強制することは不可能だと私は思う。現実の国際政治は到底その方向に向かっているとは思えないが、国際紛争を解決する手段として戦争を行なわないということ、戦争そのものをなくすことが課題であろう。
現代においては、詩、音楽と舞踊を除けばいずれの文化もすでに「遊び」の精神を失ってしまっており、スポーツですら遊びで行なわれていないことをホイジンハは指摘している。諸文化が、かつて遊びと結びついていたこと、遊びのなかで生まれたことを示すことは、人間が「ホモ・ルーデンス」であったことは示せても、ホモ・ファーベルであるとする人間観を打ち破ることにはならない。 子どもの時にはすべての活動が遊びと結びついて行われていた、いや、すべての活動が遊びであった。この頃を懐かしむことによって、毎日の労働と仕事から受ける諸個人のストレスは、多少緩和されることがあるかもしれないが、労働と産業が支配する社会は、すべての文化的社会的活動の起源が遊びのなかにあった歴史的事実を示すことによっては変わらないだろう。それよりも仕事・労働は現代においては遊びと対立するものであることをはっきりと認識し、仕事・労働を減らし、遊びを増やすことを追求すべきである。
同じように、かつての戦争が遊びとして、規則に従って行われていたことがあったにしても、そのことを指摘し、昔のように「遊びの精神」をとりもどすよう説くことによっては、現代の戦争がルールなどまったく存在しない大量虐殺を伴う総力戦である現実を変えることはできないと私は思う。
私は戦争に反対である。私が遊びについて語っていることが戦争を肯定することにつながらないことを望むし、むしろ、反戦あるいは非戦につながることを望む。しかし、反戦あるいは非戦に役立つことを語れるわけでもない。にもかかわらず、あえて遊び/スポーツと戦争との関係について一言語るべきだとすれば、前章でふれたエリアスの現代社会おける衝動規制と「慣例化」の緩和の必要という議論に糸口を求めることが可能かもしれないと思う。
国連の存在にもかかわらず、自らの力を維持拡大し、他国に対する影響力ないし支配力を強化しようとする大国間の競争は強まる一方であり、国際緊張は絶えることがない。何かのきっかけで、国家間に緊張が高まったときに、一般国民がどのような精神状態にあるのかは、重要な意味を持つであろう。もし大多数の国民が、他者の指揮・命令の下で機械的で単調な労働に長時間縛り付けられているか、あるいは同僚や顧客の考えや意向を読み取ろうとたえず神経を緊張させていなければならないような仕事を続けていれば、つまり強い「慣例化」の下で日常生活を続けているとすれば、そして、多くの国民が、労働契約を通じた上下関係、命令と服従の関係に従って行動することが、つまり「社会に自分を合わせて服従することが」得策であると信じ、権威に順応する「柔軟で強調精神に富んだタイプの」人格=「権威主義的人格」を身に付けているとすれば3)、他国との対決姿勢を強調し、武力に訴えてでも他国の力を排除しようとする政治指導者が登場したときには、その言動を支持し、攻撃的衝動を満足させようとすることに傾きやすいと考えられないだろうか。
しかし、エリアスは、文明化の過程は、それぞれの国家において、国内での暴力の行使の抑制をもたらしたが、戦争において他国民に対する暴力を減らすことにはなんらつながっていないことも指摘していた。同様に「規則に従いコントロールされた形態の戦い」であるスポーツ、あるいは自然的・感情的行動が一定の範囲で許されているスポーツに関して、国内のチーム同士の試合の場合と、国際試合とでは、選手も観衆もまたマスコミも、まったく違った振舞い方をするという事実を指摘することができる。
ホイジンハもそうであったが、一般に人間は闘争本能を持つと言い、戦いの遊びである競技はそのような本能的傾向の表れとみなされることが多い。守能信次は『国際政治とスポーツ』(プレスギムナスチカ、1982)で、スポーツを論じた多くの著書に見られる、国際関係におけるスポーツ性善説、彼のまとめによれば①人間は闘争本能を持つ、②スポーツはこの本能を平和的に満足させ、しかもその際、人間の相互理解を促す、③したがってスポーツは人間社会に平和をもたらす、という「三段論法」を強く批判し、多くの反証例をあげている。
スポーツが平和な国際関係の構築に役立つという議論の反証として、欧州ウィナーズ・カップ・トーナメント1977年大会では、フランスでの英国チームとフランスチームの試合で英仏のファン同士が乱闘を演じ30人の重軽傷者を出したのをはじめ、イタリア、アイルランド、アイスランドなどの会場でも選手同士のラフ・プレイがもとでトラブルが続発した。1964年東京オリンピック大会の予選としてリマで行われたアルゼンチン対ペルーのサッカー試合では、審判の判定に激怒したペルー人ファンがグラウンドになだれ込んで警官隊と衝突する一方、スタンドに火が放たれ、結局約300人の死者を出した。1970年ワールドカップ予選の、ホンジュラス対エルサルバドル戦で生じたトラブルから両国の外交関係は断絶。戦闘機を繰り出した戦争に発展し2,000人の死者を出したなどの事件をあげ、詳しい説明を行なえばこの種の事件だけで優に一冊の本が書けると述べている。
また、守能は、フランス国営テレビのサッカー中継アナウンスの「ナショナリズム丸出しの解説ぶり」を批判する。彼によれば、アナウンサーは、フランス選手の犯した反則については厳しすぎると審判を責め、外国選手のちょっとしたラフ・プレイにはすぐ「レッドカードを出すべきだ」と叫ぶ。一度でも耳にすればその解説ぶりには「必ずや驚かされよう」と言う。彼は欧州の統合を進めつつある政治的動きに反して、むしろスポーツがそれを妨げていると指摘する。p146.スポーツの国際試合で、たとえば日本選手が3位、4位だったと報ずるが、1位、2位の外国選手は誰であったのかを報じないこともあるような、報道の仕方などから見て、日本のマスコミの場合も大同小異である。私も、スポーツの国際試合は、諸国民の相互理解に役立つよりも、ナショナリズムの高揚や相手国への敵愾心をあおることの効果のほうが大きいと思う。
守能の指摘をまつまでもなく、スポーツは、人間がもつ闘争本能を平和的に満足させ、しかもその際、人間の相互理解を促すので、国際社会に平和をもたらす、という「三段論法」は成り立たない。
第2章で見たことだが、一国内で、激しいスポーツの闘いが、戦いたいという自然的欲求充足の代わりになり、人々の興奮が選手や観客同士の暴力沙汰の衝突に発展せずに収まっているのは、試合の興奮は競技場という飛び地のなかでだけ許されたものであることを選手もファンも十分に理解していて暴力の衝動はほとんど自制されていると同時に騒ぎが生じても警察力によっていつでも押さえ込めるからである。ところが、国際試合においては、マスコミなどによって事前に煽り立てられていた選手やファンは、国内チーム同士の戦いの場合よりも勝敗にこだわる度合いはずっと強く、ファンは自制心を失い自国チームを応援するだけでなく、興奮に駆られ相手チームを罵倒したり、相手チームに対する敵愾心をあおりたてたりする。選手も闘争心を掻き立て勝つことだけに夢中になりがちである。こうして、スポーツの国際試合が親善試合になるのは、あらかじめ、スポーツを通じた交流の目的が両国の親善にあることを選手にもまたファンにも十分に理解されている場合であって、紛争状態あるいは何らかの問題を抱えた国同士の国際試合は、両国における相互的敵愾心を煽り立てるだけになり、守能が報告しているように、時には試合場で暴動が起こったり、あるいは両国が国交を断絶し、戦争になってしまう事態も起こり得る。
2013年秋、NHKの記者が北朝鮮について、就任1年目の金総書記が自己の威信を高めるために、スポーツに力を入れている、と伝えていた。スポーツニュースをどんどん流し、選手を表彰したり、新しいスポーツ施設を次々に建設している。国際大会で優勝した選手は、高級マンションにただで入居でき、自動車を持つことができる。北朝鮮では科学者と並んでスポーツ選手になることが人々の憧れになっているとも記者は報告していた。
科学者とスポーツ選手が子供たちの憧れの的であるのは、世界中の国で同じであろう。北朝鮮はこれまでも、スポーツ選手に特別待遇を与えて来た。それは、スポーツの国際試合に勝つことは国家の対外的な威信を高めることだと考えているからであろう。だが、最近の変化は、国の指導者たちが、対外試合で自国チームが負けても、そのニュースを流すことは決して損にはならず、ナショナリズムを高めるのに有効であるということを認識した結果だと思われる。国民は、核兵器の開発を通じてばかりでなく、スポーツを通じて自国が他国と敵対関係にあることを知り、そして結束すること、愛国心をもつことになるということを本格的に認識した結果だろう。
現在行われている国際的なスポーツ大会は、実際、国と国の戦いの場になっている。個人競技でも優勝した選手が国旗を持って走り回るといった光景がときどき見られるが、オリンピックもふくめ、スポーツを国際平和の促進に役立てようとするなら、国旗の掲揚や国歌の演奏を行なうことは止め、すべて個々のアスリートの戦いに変えるべきである。ゴルフの国際試合で、日本の松山英樹がアメリカのタイガー・ウッズと闘う場合に、日本とアメリカが闘っていると考える人は皆無ではなくても少ないだろう。だが、野球やサッカーのようなチーム・スポーツの場合の戦いでは、観客の関心は、個々の選手のファインプレー(美技)を見ることよりも、自国チームが相手国チームに勝つこと、というよりも自国が相手国に勝つのを見ることにおかれてしまっている。ほんとうの戦争との違いは、それぞれの種目のルールに従う行動により勝敗が決まり、相手の選手の殺傷を目指してはいないという点にあるだけで、「ミニ戦争」だと言っても過言でないと思う。だが、クラブチームの戦いではたとえば長友のいるチーム・インテルと長谷部のいるチーム・ACミランが戦うのであって、日本の観客は日本人プレーヤーのいるチームの試合のときにより多くの関心をもって見、日本人プレーヤーを応援しながら見るかもしれないが、それはナショナリズムを煽り立てることにはほとんどならないであろう。スポーツの国際試合を、すべて個人競技に限るか、あるいはチームスポーツの場合は国ごとに結成されたチームの対抗戦とするのでなく、すべてクラブチームによる試合とすれば、ナショナリズムの形成機能をへらすことができるだろう。しかし現状では、数十年前とは違い、スポーツの国際試合が戦争にまで発展する危険は少なくなっているのかもしれない。しかし、問題を抱えた二国の間でFIFAのワールドカップの試合などが行われれば、相当に険悪な雰囲気の試合になることは明らかである。
エリアスのスポーツの「非慣例化機能」に含まれる自然的衝動の一定の充足という観点を守能の言う「三段論法」、つまりスポーツの国際試合が国際平和に役立つという単純なしかも間違った議論と結び付けて理解することはできない。スポーツの非慣例化機能が積極的に国際平和を求める人々の傾向を生み出すとは全く言えない。しかし慣例化された日常生活の中で抑圧された衝動が蓄積され、政治的エネルギーに転化し爆発することを未然に防ぐ消極的働きはするかもしれない、と考えることはできる。しかしスポーツと国際平和との間には、その程度のごく間接的で消極的な関係しか考えることができない。そして、スポーツ/遊びと戦争との関係について私が語りうることは今述べたことだけである。
2013年は、選挙における自民党の圧倒的な勝利を背景に特定秘密保護法が制定されるなど、ずっと以前から始まっていた、そして途中で少し変わるかと思われたごく短い時期をはさむ、日本政治の右へのほぼ一貫した方向転換がついに成し遂げられ、今度こそ「日本の戦後」が本当に終わってしまった、戦前が再び始まったのだという印象を強く受けた年だった。私は、戦後の平和な時期に生まれた幸運を享受しつつ生きてきた。そして、還暦のときに隠居宣言を発して、好きなだけ釣りをし、最近では釣りと遊びやスポーツについてのエッセーを書くことに人生の最後の楽しみを見いだしてきた。
私の船の名前はFriede und Freiheit(平和と自由)である。自由な暮らしを楽しむことのできる平和な時期はもう続かないのかもしれない。このことは非常に気がかりであるが、どのように現在の傾向と闘ったらいいかわからない。私は私の残されたわずかな時間を、重要だが成果のはっきりしない問題のために自分のエネルギーを注ぐことに積極的になれず、憲法第九条を守り自民党の改憲の動きに反対する意見広告、あるいは沖縄を犠牲にし、米国の手下になって戦争を遂行しようとする日米同盟推進の動きに反対する運動のための基金にお金を送るくらいのことしか思いつかない。4)
ホイジンハによれば、遊びは大きく二つに分けられた。一方は文化としてあるいは文化の基として意義をもつもので闘技や演技のような高級で社会的な遊びである。他方は単純で、非社会的、個人的な遊びとされた。彼が触れた遊びは、騎乗槍試合、演劇、音楽など、ヨーロッパ語でplayと呼ばれる活動と宗教的な儀式などであり、われわれが現代日本語でいう個人的な「遊び」は触れられなかった。釣りは単純な遊びだとは言えないが個人的な遊びである。ホイジンハは「釣り天狗」という言葉にふれただけだった。
だがすでに反論したように、社会的なあるいは文化的な活動として行なわれる時には、遊びはその本来の自由を失って、遊びではなくなってしまう。私は、個人的で、自由な遊びについて、考察を進めたい。
またホイジンハによれば、遊びは現実、あるいは日常生活の必要に対立するもので、一方では日常生活を超えて宗教的儀礼となって高まるか、あるいは本物の「真面目」な世界に対立する「仮構」、「劣等」なもの、単なる「遊びに過ぎない」もので、現実の生活や仕事の中にときどき「割って入る」ものであった。
釣り/遊びと仕事あるいは現実生活との関係について、ホイジンハ同様、遊びは仕事あるいはまじめな世界に対立し、時々後者に「割って入る」ものだという見方をする日本人が多いように思われる。幸田露伴が中年になりかかったころに書いた「遊漁の説」にもそうした見方が表れている。しかし、露伴の後半生はそれとは異なる姿勢で導かれている。露伴における「遊漁の説」と実際の彼の生きかたの違いが興味深い対照をなしている。
遊びと仕事との関係について、ホイジンハとほぼ同じ時代を生きた日本の小説家・文学者、幸田露伴がどのように考え、どのように生きたかを、かれが好んだ釣りに関して書いた文を中心に検討してみたい。釣りがどのような遊びであるのかについては第4章と第5章で書く積りだが、とりあえず遊びと仕事との関係について露伴の「遊漁の説」という文などをてがかりにして考えてみる。
露伴は1867年生まれ。1868年は明治元年なので彼の年齢と明治の年数は同じである。彼は、明治22年、22歳のときに、小説『露団々』と『風流仏』をひっさげて文学界に「擡頭」した。彼は続いて『雪紛々』、『一口剣』(23年)、『五重塔』(24年)などを次々に発表した。はじめは小説が主で、尾崎紅葉と並び称せられたこともあったが、紅葉が通俗的な人情小説作家だったのに対して、露伴は「人情小説とはまったく異なる、不可能と思える現実の困難な状況に挑戦する、主人公の強い意思とロマンティシズムを描いている。主人公の生き方を通じて自己の「理想」を語」った、といわれる(三好行雄編『日本文学全史』5.「近代」、学燈社、昭和53年)。しかし、しだいに小説から遠ざかり、30代の終わりごろにはエッセー、評論、考証、古典の校訂・解題といった仕事に比重を移した。
彼には広範な分野にわたるきわめて多数の著作があり、40数巻に及ぶ『露伴全集』(岩波書店、1980)がある。その編者・塩谷賛による、露伴の伝記『幸田露伴』(初版昭和43年、3巻;後に中公文庫、4巻、昭和52年、ともに中央公論社)があり、また<現代日本文学大系>第4巻『幸田露伴集』(筑摩書房、昭和46年初版)などもある。
塩谷賛による露伴の伝記『幸田露伴』(神田神保町の古書店、アットワンダー のブログhttp://atwonder.blog111.fc2.com/2008.5.16新着情報より転載)

彼の釣り好きは有名で、釣りに関係した小説『幻談』をはじめとして、釣りに関する随筆や釣り道具に関する論考なども多く書いていて、彼の著作、日記、手紙などから釣りに関するものをすべて集めたという開高健編『露伴の釣り』(アテネ書房、1985)という本もある。
以下で最初に引用する「遊漁の説」は明治39(1907)年6月に最初に雑誌に掲載され、その後、釣友・石井研堂の『釣遊秘術 釣師気質』の序として載った。『露伴全集』第29巻及び『露伴の釣り』には「游漁の説―石井氏釣書に題す」として収められている。
石井研堂(本名民司)は学齢館という書店の編集者で、露伴は明治26年から28年にかけてそこから発行されていた子供向けの雑誌にいくつかの物語を書いた。二人はこのときに知り合ったと思われる。露伴の日記には露伴が研堂と一緒に釣りをしたことが書かれている。また研堂宛の釣りに関する多くの手紙がある。
研堂は明治18年21歳で上京後、漢学を修め、学齢館に勤める前に、一時、小学校で教えた経歴をもち、『中村正直伝』、『西洋事物起原』などの著書がある。
沢山釣ろうとするのでなく、釣りの趣をたのしむべきである。游漁者が漁夫のやりかたをまねるなら、「これ品格ある游漁者とはいふべからざるなり」。漁夫は安価で有効な餌を使い、太くて強い竿を用い、綸〔イト=糸〕も太く丈夫なものを使って魚の取り込みを早くして、沢山魚を釣ろうとする。だが、游漁者は魚の当りを精確にキャッチできるよう、柔らかい竿、細い糸を用いて、「興を多くせんことを図るべし」。
楽しむことが目的なのだから、金を惜しまず良い道具、良い餌を使うべきで、船宿も、船子〔船を漕ぎ釣り場を案内する人〕も、親切で経験や技量の十分な者を雇うべきだ。游漁者が安い餌を用い、無趣味な釣具を用い、単に漁獲を多くしようと考えるなら、その人はすでに娯楽のために魚を釣る人ではなく、利益のために魚を釣る人となってしまって、「尊重すべき自己の職業あるを忘れて---、拙劣な一漁夫となるに等し」い。「之に反して、わずか数尾の魚を得たに過ぎないときも、游漁者たる品位を保てるものは、----内は賢く職業を忘れず、外は快く娯楽を取るの君子たりというべきなり」。
第4章で述べるが、竿釣りの場合の楽しみの中心は、「当り」つまり魚が餌をつついたりくわえたりして生じる竿先の振動や竿の曲がりを見ることと、魚が鉤(ハリ=針)に掛かってからは、逃げようと抵抗する魚の引きの手ごたえを楽しむことにある。
これが露伴の言う「興」である。職漁師の場合には、魚の種類にもよるが、当たりが出たときに、魚が単に口先で餌に触れているだけかそれとも餌が(したがって鉤が)口の中に入っているかどうかを見分け、餌を取られる前に素早く魚を掛け、強い竿と糸で魚を強引に引き寄せて船内に取り込むと、あっという間に餌を付け替えて再び仕掛けを投入する。これを手返しというが、手返しを多くすることで漁獲を多くするのである。
露伴は「遊戯娯楽」のためにおこなう游漁者の釣りは、生計のために行なうのではないのだから、効率のよさや多獲を意図するのでなく、「興を多くする」べく、竿先に出る当りを一回一回、目で十分に楽しみ、また掛けた魚の引きをじっくり楽しむべきだと言う。「漁獲の多寡と興趣の深浅とは正比をなさずして反比をなす」とさえ言う。
実は、「遊漁の説」で、彼が、魚を多く釣るためではなく「興を多くする」ためだとして述べていることの大半は多く釣るために必要なことでもある。
彼は、無粋な道具を使うべきでないといい、道具も、餌もよいものを使うべきだという。だが、高価でよい餌を使うのは、高価な餌ほど餌持ちが良く(丈夫で、魚に簡単に取られない)、魚が好み、よく釣れるからであろう。細い糸と「敏な」竿を使って当りが精確に出るようにするのは、単にその竿先が大きく揺れあるいは曲がるのを見ることが「興多い」ことだからなのではない。
初心者にありがちのことだが、当りが細かい(小さい)と、当りなのかどうか分らず、合わせ(すばやく綸=糸を引いて魚を鉤に掛けること。詳しくは第4章参照)をまったく行わないか、そのタイミングを逃すかして、結局魚にただ餌を取られてしまうことになる。細い糸、「敏な」竿は当たりを的確にキャッチするために必要なのである。漁師は丈夫で「無趣味な」竿、太い糸を使うと言うが、それは彼が当りが細かくてもそれを的確にキャッチし素早く魚を針に掛けることができるからである。游漁者でもベテランであれば漁師と同じことが言える。良い餌、敏な竿、細い糸は初心者でもできるだけ多く魚をかけることができるために必要な条件なのである。
だが、糸が細く竿も敏(細い)であれば、大物が掛かったときには(とくに初心者なら)瞬間的にハリス(針素:針を結ぶ、釣り糸の先端部分)を切られるかそうでない場合には竿が折られるか、「伸(の)されて」しまうため(これについても後の第4章を参照)結局糸を切られてしまう。したがって、游漁の釣りであっても大物を狙うベテランなら、糸も竿も釣ろうとする魚に応じて太くする。
露伴も、敏な竿と細い糸を使っていて「たまたま大魚の鉤ハリに上るにあたって竿折れ綸絶ゆるがごとき」は決して愉快なことではない、と言うが、しかしそれは、竿が細く綸が細ければ(ベテランは別として)起こりがちのことである。この点について露伴は游漁者は「不快を招くべきが如きことはすべてこれを避くるを智ありとす。この故に釣具は奢侈ならざる限り精良なるを用ふべし、決して下劣粗悪なるを用いるなかれ」と苦しい説明を行っている。
こうして、露伴が、道具選びに関して述べていることの多くは、同じ游漁者であっても初心者とプロ/ベテランの腕の違いから生ずることであるのに、「游漁者」と「漁夫」の違いから生ずることとして説明し、しかも「漁夫の真似はすべきでない」からと、結局、游漁者は金を掛けることで、漁夫とは異なる趣のある釣りを楽しむべきだと言っているのである。
「遊戯娯楽は遊戯娯楽のための遊戯娯楽にあらず、遊戯娯楽は其の人の身肢を鍛錬し心神を怡悦イエツせしめて、而して後おのづから其の人の本来の職業に対する気力を鼓舞振作し、意楽を熾盛増進し、以って其の職業上に於ける腐気を排去し、精彩を付与するにいたって、始めて遊戯娯楽の真旨に適し、妙用を果せりというべし。然らずんば、遊戯娯楽の事たる、直ちにこれ堕落の坂道ならんのみ」。「日々よく勤め、時々、よく遊び、家にあっては各自の職業を忘れず、綸を垂れては游漁者の資格を忘れず、----悠然として長く楽しまんとするものは、心に憂いなく、身に病無く、清福十分、俗にして仙たり、愚にして哲たらん」。
また「自ら処するはすべて「まめやか」なるべし、疎懶〔ソラン、他人任せ、ものぐさ〕なるべからず。---「まめやか」なれば身労して心〔は〕逸---するなり〔くつろぐ〕」と言い、「克〔よ〕く労に服せよ。船を浮かぶるは身を労するの道なり。労を厭はば須らく家に在りて布団に座すべし」と言う。
つまり、釣りの本当の目的はただ遊んで楽しむことにあるのではなく、仕事の中でたまるであろう「腐気」つまり精神的なストレスを吹き飛ばすこと、そしてそれによって、「本来の職業」に対する気力を鼓舞し、張り切って仕事に向かうことができるようにすることにある。とくに文筆家のように座業で、体を使わずに仕事をするものは体を動かすことで気分を爽快にすることができる。彼は釣りは体を使う遊びだから職業上の腐気を排去するのに適しているといっている。何事も他人任せにせず、まめに体を動かすことが精神的ストレスの解消になると言う。
こうして仕事に向かう元気・やる気を回復することが釣りの目的である。かくして「日々よく勤め、時々良く遊ぶ」事が大切だ、という我々が現代日本においてもよく耳にする、週日に仕事にはげむために、週末には適度に遊べ、という職業人の倫理を聞くことになる。この「游漁の説」において露伴は、いわば正しい游漁の仕方を説くとともに、釣りと言う遊戯娯楽と本来の職業とのあるべき関係を説いている。職業が主であり、遊びは客(従)である。
後者に関して、ついでに『釣遊秘術 釣師気質』の巻末に掲げられている「研堂釣規」を見てみよう。6ページにわたって露伴が美文を交えた「游漁の説」で述べているのとほぼ同じことを石井研堂はいくつかの標語にまとめて、もっと簡潔に述べる。
「ひとは遊ばんがために職業に勉むるにあらず、職業に勉めんがために遊ぶなり。釣遊に前後軽重の分別あるを要す。
「日曜一日の休暇はその前の6日間職業に勉めし賞与にしてその後の6日間の予備にあらず。いまだ勤苦せざるに、まず休養を名として釣遊に耽らば、身を誤り家を破るのもとい〔基〕、酒色の害と何ぞ選ばん。
「釣遊は養神〔精神を養う〕摂生のためのみ。養神摂生に害あるは釣遊の道にあらず」などという文を掲げている。
この「研堂釣規」と比べると露伴はそれほど明確に言い切ってはいないようにも見える。露伴の「日々よく勤め、時々、よく遊び、家にあっては各自の職業を忘れず」は、研堂の「日曜一日の休暇はその前の6日間職業に勉めし賞与」、「いまだ勤苦せざるに、まず休養を名として釣遊に耽らば、身を誤り家を破るのもとい、酒色の害と何ぞ選ばん」と較べると、やや「軟弱」とも感じられる。(ただし、研堂も、実際には、釣り日和の時には、会社で机に向かっていても、仕事を止め休んで釣りに行こうか、どうしようかと仕事が手につかないでいる様子を書いてもいて5)、「釣規」は建前、あるいは努力目標を述べたに過ぎないのかもしれない。)
露伴は、どこまで、仕事は仕事、遊びは遊びと割り切り、遊びとは異なるものとしての職業に打ち込もうとしたのだろうか。彼はどこまで遊びは仕事の合間になされる息抜き、休養であり、遊びは仕事に役だつ従属的な役割のものでしかないと考えていたのだろうか。
「先月より、ぢりぢり照り続きで河水の煮えて煮えてる挙句に、さきほどの夕立は何たる幸いぞ。今日さえ釣りたらば、いかなる初心の者にても、3本5本の獲物はあるべく、一年一遇の好き日なり。ことに今の空合いは---申し分なし。---すでに意外の大漁せしものも少なからざるべし。ああ、往きて釣りたし」。「今の一雨を得ては---魚類のはしゃぐこと想いやられ、餌つき〔魚が餌に食いつくこと〕何ほどかよからん。往きて釣りたし釣りたし」。「今日の新聞には干潮は2時0分とあり。中川は---3時半には必ず底る〔干潮で水位がもっと下がる〕べし。2時の退散〔退社〕を待ち、急ぎて出遊するとすれば、電車にて家に帰るに35分、---身支度して道具取り揃えるに20分、---川に---かれこれ3時40分くらいには着くべく、船を出させて---釣り始めはまず4時近くなるべし。〔潮の上げはじめがよい。〕少し後るるようなれども、日いっぱい釣るときには、2時30分間は楽しむに足れり、---しかし、わざわざこの炎暑に車〔人力車〕を煩わし、わずか2時間半では行くとすぐに帰るようで、満足できない。せめて半日釣らなければ。後日に伸ばそうか。---」
「たとい、1時間にても30分にても、釣りのために職務を休むは良心の咎め軽からずして、あえてするに忍びず。きょうばかりは世外の仙人になりたし。この復〔また〕と得がたき良き日に会いながら、悶々、中に執務せざるべからざる苦しさを思えば、むしろ浪人こそ羨ましけれ。----と、筆執れる手を頬杖にし、机によりてひたすら窓外の天色を眺めしが、胸中に往来するものは、この「往こうか往くまいか」の迷いのほか、一点の思慮もなし」。
「「執務中は断じて釣りのことを思わじ。釣りの雑慮は職務の妨げとなること少なからず。」とは幾たびか自ら誓いたることなれども、漁史〔自分を指す〕の釣りを思うは、---物に触れ事に応じて、片時も忘るる暇なく、夢想を逞しうして、神往魂飛〔精神が飛び回る、というのだろう〕禁じ得ず、終にこれを実行するに帰するが常にして、この日もまた、退散後、2時30分決行のことに思い定めぬ」と、2時半の退社後、釣りに行くことに決めた。このように、仕事をサボって、会社を早退してまで、釣りに出かけることは彼の良心が許さなかった。しかし、またとない釣り日和の到来に、彼は、「行こうか行くまいか」迷うばかりで、仕事が手につかないでいる。「浪人がうらやましい」などとさえ言っている。
研堂も擬古文で書いていて慣れるまで少々読みにくいが、釣りが失敗や事故を含めドラマチックに描かれていて、釣りの随筆・小説で私が読んだものの中では、開高健の諸著作と同様に読んで最も面白かった。
こうした職業倫理にはさまざまな思想の影響があると思われる。まず時代の一般状況に照らして、二人が徳川時代以来の「修身斉家」を中心とする儒学思想の影響を受けていたことは明らかだと思われる。
他方、二宮尊徳の門人たちによって幕末から明治前期にかけて各地で行なわれた報徳社運動が明治10年代になると、政府によって注目、称揚されるようになった。教育の場においても、明治30年代から修身の手本として顕彰されたと言われるが、報徳思想の中心は「勤倹」にあるとされている(塚谷 晃弘、大山雄三「二宮尊徳」Web版『平凡社百科事典』)。報徳思想は主に農民に向けて説かれたもので、農民ではない露伴や研堂の遊漁の説には、仕事に打ち込むこと、勤勉は重視されていても「倹約」思想は見られない。だが、露伴や研堂の「職業倫理」が、明治期日本に広く存在した勤勉を勧める儒教や報徳思想の影響を受けていることは否定できないと思われる。
また、イギリスの社会思想家 S. スマイルズの《Self‐Help》(1859)を中村正直が1871年(明治4)に翻訳出版した『西国立志編』の影響も考えられる。この本は、勤勉、忍耐、節約といった美徳を涵養して人生を切り開くことを説いているといわれる。自助努力の効用に対する楽天観があったため、没落した士族の子弟をはじめとして青少年に多大な感銘と影響を与え、総発行部数は100万部以上で、明治期をとおして広く読まれたという(坂本 多加雄「西国立志編」、小池滋「Samuel Smiles」、『DVD-ROM版平凡社世界大百科事典』)。露伴や研堂もこれを読んでいなかったとは考えられない。
先に引用した「娯楽はすべてその趣のあらんことを期すべし。その利があることを期すべからず」と言った文に続いて、露伴は、英国の紳士は銃猟を行うときに、弾の数が少なく大きい弾を使う。数が多く小さい弾のほうが命中率は高くなるが、弾が当たっても死なない鳥が増え、結局扼殺しなければならなくなる。それより、数は少なくても必ず鳥を死なせることのできる大きい弾を使うほうが、興趣を減らさずに猟を楽しめるから、そうするのだ、と言うのである。
銃を使う猟も心を楽しませるために行なうのであり、利益を得ようとするために行なうのではないから、このような「英国紳士の用意は、実に遊戯娯楽の本趣を解し、兼ねて自己の本来の職業と地位とを忘却するがごとき愚に陥らざる正確高尚なる知恵と品位の発現といふべし」と、英国の上流階級、ジェントルマンのスポーツ趣味を誉めている。
露伴がここで述べていることは、前章でみた、エリアスがキツネ狩りの「スポーツ」について、昔の狩猟と異なり実利である獲物を得るのではなく楽しむことが目的になった、と述べていることと完全に一致する。露伴は釣りを本格的にはじめる前に銃猟もやっていた。そして彼は英国の、スポーツとしての猟について書かれたものを読んでいた。こうして、彼は、沢山釣って「実利」を上げることは、漁師のようにそれを目的にしているのでなくても、「遊戯娯楽」=スポーツの本来的目的に反することだ、と言うのである。このような考え方は、職業が主で娯楽は従、遊戯娯楽は自己の職業に役だたねばならないという職業倫理とはまた別の、趣味の理念についての主張である。
露伴の「游漁の説」には趣味においては実利を得てはならないという考え方と勤勉を説く職業倫理の両方が見られる。後者にはスマイルズの著書の影響があると推測したが、ほかからも影響があるかもしれない。趣味については英国のスポーツ論の影響がみられる。当時の英国のスポーツ論、とくに釣りに関する議論は、趣味の理念に関してだけでなく、職業倫理についても、「游漁の説」で述べられている露伴の考え方に影響を及ぼしている可能性があると思われた。そこで飯田操『釣りとイギリス人』(平凡社、1995)で述べられている当時の英国で行われていた釣りに関する議論を読んでみた。
飯田によれば、著者のソーンダズは釣り師の条件として次のように述べている。「第一に商売のためにあるいは雇用されて、すなわち生活の糧を得るためにではなく、娯楽のために釣りをする人であると述べる。釣りは仕事であってはならないのである。したがって、釣り師は紳士でなければならないと言う。次に---第一の条件と密接に関係しているが、余暇のある人物であることである。家族を養う身でありながら、仕事をおろそかにし、貴重な時間を魚を釣って過ごすことは、このスポーツを不道徳なものにする---。このような場合、釣りは犯罪に等しいと述べる。さらに三番目として孤独と静謐を愛し、感情を制御できる人であることの必要を述べる」。
また、同じく飯田によれば、1803年に同国で発行された『スポーツ事典』には、「---自ら働いて生活の糧を得なければならない階層のものたちにとっては釣りは身代を潰す道楽になるものである」と「仕事を持つ者が釣りにうつつを抜かす怠惰を戒めた」文があるという。
ソーンダズの「家族を養う身でありながら仕事をおろそかにし」てはならないという戒めは、働く必要の全くない貴族や地主以外のすべての人に当てはまることのように思われるかもしれない。しかし、当時の農民や労働者は一日中働かなければならなかったのであり、「余暇のある人物」のうちには入っていないだろう。彼らはこの戒めが向けられる対象とは考えられていないはずである。
また、プロテスタントであれば、釣りであれ何であれそもそも遊ぶことは不道徳であった。だからソーンダズは、釣り人の『聖書』とも呼ばれることのある『釣魚大全』の著者ウォルトン同様、非プロテスタントであった〔ウォルトンがプロテスタントでなかったことについては、第4章第九節参照〕と推測されるが、当時、「孤独と静謐を愛し、感情を制御できる」とみなされたのは、ある程度の教養をもった、中流以上の階層の人々だけではなかったかと思われる。
露伴の「游漁の説」は他の多くの著作、とくに「評論」などと同様、文語文で書かれており、読者としては、中流以上の階級に属する、限られた数の教養ある人々が考えられており、農民や労働者、職人は読者とは考えられていなかったはずである。これらのことから彼の「游漁の説」の職業倫理は、国は異なるがソーンダズの『完全なる釣人』と同様、一定以上の階層の人々にむけて書かれていると考えることができるだろう。
飯田は、始め娯楽一般を意味していたスポーツという語が現代的な意味で使われるようになった経緯にふれながら、このソーンダズの主張が、実益と結びついて行なわれていた釣りが、次第に実益や労働と離れたレクリエーションとしてのスポーツに変わりつつある変化の現れと説明している。(ただし飯田の言うレクリエーションは労働力の回復というニュアンスは持たない、単なる楽しみ、気晴らしを意味すると思われる。)
『釣魚大全』の表題頁の図(訳書では「原著者序文」に続く訳者による「書誌」のページ入口にある)
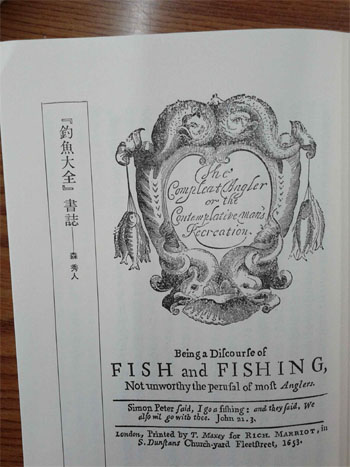
露伴の「游漁の説」は、ソーンダズの主張に極めてよく似ている。なるほど飯田の言うように、それは基本的にはウォルトンの『釣魚大全』に語られていることであり、ソーンダズの主張は「ことさら新しい考えではない」。だが、「游漁の説」の游漁者とは、漁夫、本職の漁師以外の釣り人、単に、余暇に遊びで釣る人のことなのではない。遊びで釣るという定義の限りでは、ちょっとの時間を見つけて、すぐ近くの川原や海岸などで、自分で取ったミミズを餌に使うなどして金をかけずに釣る庶民、労働者でも「游漁者」でありうる。しかし、露伴のいう游漁者は「品位」「品格」が求められ、宿に泊まったり、漕ぎ手兼ガイドのついた船を雇って釣りをすることのできる、金持ちの階層の人にのみ当てはまる釣り好き人士である。彼が銃猟について触れているところで言っているように、この游漁者は紳士、ジェントルマンなのである。
飯田によれば、英国では、当時、地主・ジェントルマンたちを主な読者とする、教養・実用書シリーズが相次いで刊行され、その一冊目は1622年発行の『完全なる紳士』というものであり、「完全なる〇〇」と言う命名は教養・実用書であることを示すのに好んで用いられたのだという。そして、ウォルトンの『釣魚大全』はそのシリーズの一冊であったというのだが、日本では『釣魚大全』(露伴の時代には「釣経」、つまり釣りの「経典」と呼ばれていた)とやや大げさな名前のつけられているこの著書の英語でのタイトルは、「The compleat angler or the contemplative man's recreation:完全なる釣り師、あるいは瞑想的な人のレクリエーション」というものである。
著者自身が庶民階層の出身であったからであろうが、「瞑想的な紳士のレクリエーション」なのではない。そして、彼の本の中では、静かな田園生活の楽しみ、釣った魚を食べる楽しみが語られる。釣り餌店などはなく自分で餌を確保するほかなかったのだから当然だが、「たいてい牛や犬の糞のなかにいる」糸ミミズの泥を吐かせ、きれいにする方法、牧場でイナゴを捕まえること、牛の糞にいるコガネムシ、カブトムシを使うことなどについても述べている。紳士とそれ以外の庶民とを区別する視点は存在しない。
「釣りは遊びだ」と言う見方は確かにウォルトンの『釣魚大全』のなかでも見られる。だが、ソーンダズと露伴に見られる、庶民とは異なる紳士の釣りという考え方は、ウォルトンとははっきりと違う。したがって、露伴の「遊戯娯楽」としての釣りに関して、英国思想の影響があるとすれば、ウォルトンの影響ではなく、ソーンダズの本が書かれた18世紀から19世紀にかけて強まる別の思想、真のスポーツはジェントルマン・アマチュアによって担われるという思想の影響だと考えられる。
イギリスでは当時のジェントルマンは、食べるための魚をミミズなどの活餌(いきえ)を使って釣りをする農民や労働者の釣りを軽蔑して、擬餌針・フライで「優美」に釣りをすることを好むようになっていた (注)。そして釣ったサケやマスを食べるのをやめ、釣りを「純粋なスポーツ」、あるいは「ゲーム」に変えつつあった。それは、ブルデューの言葉を使えば、「ディスタンクシオン」すなわち、上位の階級が下位の階級に対して自己の優越を示そうとするハビトゥス、習慣・性向の表れである。「游漁の説」においても「品格ある游漁者」とか「游漁者の品位」などという言葉が使われている。露伴が「遊漁者」の釣りについて述べていることは、近代への移行期にあった日本のプチブルのハビトゥスが行わせるディスタンクシオン追求の姿勢の現れだとみなしたくなるかもしれない。
(注)ウォルトンの親友の息子のチャールズ・コットンはウォルトンの影響で釣り好きになったが、とくにマス釣りに熱中し、フライによるマス釣り以外には「見向きもしなかった」(森「書誌」)。こうして、ウォルトンの了解も得て、『釣漁大全』は1676年の第6版からは、コットンの手になる第二部が付け加わった。飯田は「ソーンダズの釣り師の定義には金と時間に恵まれた一部の者たちのスポーツとして発展するイギリスの釣りの行方が見える」と言っているのだが、コットンによって『釣漁大全』の二部が書かれ時にすでにその「行くえが見える」と言ってもいいかもしれない。
第二部では、最後の3つの章で、マスの料理法について、またフライとは異なる底釣りと宙釣りについても触れられているが、それらは合わせて18ページにすぎず、残りの80ページ以上すべて蚊鉤=フライによるマス釣りの方法、フライの作り方等についての説明である。そして底釣りの話に入る前に指南相手の猟師に、底釣りは「蚊鉤釣りに比べればあまりいい方法ではないし、よくいわれるように風雅な釣りというわけにはいきませんが、---なにもすることがないときはこの釣りをするつもりです」と言わせてもいる。
しかし露伴はさまざまな評論において支配・被支配のある社会に反対し、公平な社会の建設の必要を主張している。彼の社会や政治に体する見方は後の「露伴の「以民為本」思想」という小見出しのもとで詳しく示すが、たとえば『修省論』(大正3年、「全集」第28巻)の「生産力及〔び〕生産者」という長文の評論では「社会は社会全部のための社会で、ある一部の種族や階級や職業や資格に属する者のための社会でないことは自明の理である」と言い、資本主義社会において「資本の威力は増進し反比例的に個人の地位は低下せしめらるること」、「資本家による職工・労働者への圧迫は強くなるばかりである」ことへの強い懸念を表明している。
露伴の場合には「品格のある釣り」は、ブルデューのいう上流階級の者のディスタンクシオン追求姿勢の表れと決め付けることはできない。
この点についての議論は再度行うことにし、その前に、彼の行なった趣味が大変幅広い多様なものであったこと、そして釣り方も、多くの小説を書いていた若いころの釣り方と「小説の筆を折って」、考証や評論などそれまでと違った幅広い領域での活動を行うようになった中年以降における釣りとでは変化が生じたことなどを見ておきたい。
青年時代の露伴

他方、彼は非常に多趣味であり、よく遊んだ。根岸党(後に「楽々会」と改称)という文士の遊びのための集まりに加わり、しばしばグループで出かける旅行を楽しんだ。また、彼は24年ごろからこのメンバーの数人と将棋を始めた。本を読むなどして研究したが、露伴の将棋への入れ込み方は並大抵ではなかった。彼は当時の名人小野五平のもとに稽古に通った。小野が露伴宅に来ることもあり親交があった(同書)。露伴は江戸時代の棋書を読むなどして書いた30ページ近い「将棋雑話」(34年、第15巻)、西洋将棋、中国将棋、日本将棋を比較して論じた40数ページに及ぶ「将棋雑考」(33年、第19巻)などの文を書いた。後の名人で当時8段の木村義雄と角落ち(4段格)で対戦するほどの腕になった。
「昭和24年版全集 月報抄」の中に木村が寄せた文があり「露伴先生の将棋は素人としては最高の水準に達していたと思う」、露伴の「研究熱心さにまったく敬服した」と書いている(「全集」の「附録」)。ただし、初めのころは腕を確かめようと誰とでも将棋を指し、勝ち負けに夢中になっていたが、結婚翌年の29年には妻の幾美子に「勝っては恨まれる種を作り」、「負けては悔しがり」「転覆反側し」て寝付かれないなんて、つまらないことだから止めてほしいと諭され、「17年間親しんだ将棋」から手を引いたという(塩谷、下巻)。その後は「実戦」はやめ主に将棋の歴史の「研究」に向かったようだ。
木村は昭和13年に14世名人となったが、彼以前は名人が次の名人を推薦する、世襲制であった。木村はこの年の第一期名人戦に勝って「実力で」名人になった。
また、すでにふれたが、彼は銃猟も行ったし、32年ごろには写真にも興味を持った。写真術はオランダ船などによって江戸末期には伝わっていたが、明治中期になると多くの写真館が作られ著名な写真師が活躍し、1889(明治22)年に榎本武揚を会長とする写真師団体・日本写真会が、1901(明治34)年には尾崎紅葉を会長とするアマチュア団体・東京写友会が創立されたという(『日本大百科全書』1986、小学館)。
露伴は相当な重量があった写真機をもって友人と出かけた。塩谷は写真機の目方が「2貫目」と書いている。2貫目は7キロ半である。昭和20年5月25日の空襲で小石川の露伴の家・蝸牛庵が焼けたときに、これを見に行った塩谷が釣竿や将棋や「露伴が作らせた大きな写真機」などが焼失したと言っている。この焼けた写真機は露伴が若いときに使ったものだろう(塩谷、同書 )。
明治40年には自転車を買い、生涯の友人の一人・遅塚(チズカ)麗水に充てた手紙で「幸い、老人、小児を傷めることなく」ようやく自転車に乗り慣れて、(向島の家から)本郷へも行かれるようになった。あまり遠くないところへご同行願いたい、と書いている(書簡番号274、全集39巻)。40歳になってからの自転車乗りでうまく乗れるまでには苦労したようだ。
日本に初めて自転車が輸入されたのは1870(明治3)年で、宮田栄助が国産第一号車を製作したのが1889(明治22)年。国内の自転車が10万台を超えるのは1906(明治39)年ごろで、自転車は当時200円くらいで、下級官僚の4~5か月分の給料に相当したという(鈴木淳『新技術の社会誌』<日本の近代>15.中央公論社、1999)から、今なら普通乗用車と同じくらいの価格ということになるが、乗る人の数が限られており、このころに自転車に乗ることは、現代の高級スポーツカーの運転に匹敵する道楽だったと言えるのではないか。
露伴が「あまり遠くないところ」に一緒に行こうと誘っているのは、日帰りのサイクリング旅行のことだろう。彼は健脚だったし、必要なら人力車を使って外出した。手紙では図書館に通うのに使うといっているが、自転車は実用のためというより、スポーツ、楽しみのために買ったことは明らかだ。
「游漁の説」では、游漁者は、生計のために「あくせく」しながら行う漁師の釣りを真似てはならず、「多獲」せず、「悠然」と「品格ある釣り」を楽しむべきだとされていた。とくに、游漁者の多獲は戒められていた。「漁獲の多寡と興趣の深浅とは反比〔例〕」するとさえ言われていた。 実は露伴の釣りは初期には「多獲」的であり「悠然」としたものではまったく無かった。だが、「游漁の説」を書いたころ、彼が40歳になりかかったころに、彼の釣りに変化が起こった。
海釣りを本格的に始めたばかりの頃の32年5月に書かれた「鼠頭魚〔キス、鱚〕釣り」(全集第14巻)では、父と弟の3人で朝の3時過ぎに家を出、1時間ほど歩いた所の船宿から出船。東京湾に出て、脚立に乗って釣る青鼠頭魚〔青ギス7)〕釣りをした。
3人とも非常によく釣れて、あわせて130匹釣ったと書いている。ほとんど休みなく釣り続けたはずだ。
Hey!Manbow (http://heymanbow.exblog.jp/)2010.4.25.「昭和の釣り、戦前の釣り」より借用した。この写真は、松崎明治『日本の釣り』(三省堂、昭和14年)に掲載された写真だというが、脚立に乗って釣るキス釣りは昭和30年代までは行なわれていた。

明治33年「かいづ釣の記」(同全集第14巻)では、カイヅ(2、3歳、大きさ20~30センチ程度までのクロダイ)釣りは初めてだったようだが、合わせ(魚が喰った瞬間に竿を立て、糸を引いて、魚を鉤に掛ける。遅れれば餌だけとられる。)のタイミングが少し難しい釣りである。最初の一匹は合わせ損ねて逃したが、それまでにほかの釣りをやっていて合わせ方の基本を十分心得ていたからでもあろうが、(船首近くにある簪カンコ と呼ばれる)横木にもたせかけておいた竿をつかんで立てるタイミングを船頭に教わるとすぐに的確に合わせることができるようになった。潮、場所もよかったと思われるが、2時間ほど、彼と船頭は「互いに劣らず」休みなく釣った。その後場所を変え、昼食をとった後、再び釣った。カイヅだけでなく大ウナギやコチの三歳魚を含め、大小さまざまな魚を次々と釣り「我を忘れ」るほどであった。
34年「雨の釣」(同14巻)では、6月30日、利根川尻でのキス釣りに出かけた。6日間根詰めて勉強した後、日曜の一日を自分の思い通りに遊び暮らすのは何よりも楽しいことだ。普通前日の宵の口から舟を出して早朝から釣る。この日は仕事が遅れ、夜中に家を出た。昨年安く買った船は嵐で壊れてしまい新しく檜造りの船をこしらえた。「チト侈オゴリの沙汰だが、平生あまり人力車クルマなどにも乗らず〔節約し〕、下らない虚飾ミエなども排斥し〔贅沢を避けてき〕た結果として」漸く最近になって造ることができた自分の船である。(漕ぐのは知り合いの船頭で、たぶん日当を払ったのだろう。)
数時間掛けて釣り場につき、握り飯の朝食を食べ、夜明けとともに釣り始めた。好釣で、すぐに魚籠の底が見えなくなるほど釣れた。「その後釣り場を変えて彼方此方を釣りめぐり、午前十時ごろになっては満足どころかほとんど望外の魚を獲た」。河岸に戻ったとき釣った魚は「大盤台〔魚屋が用いる浅くて大きい楕円形のたらい〕に山盛りになった。それを船頭に担がせて隅田の堤を家へとこころざすと、往来の人も驚いて目をそばだてて見た」。家のものもこんなに沢山釣れたんですかと驚くほどだった。
こうして初期の露伴は釣りに出かければ、しばしば「われを忘れる」ほど夢中になって釣り続け、漁師顔負けの「多獲」を行った。
また明治42年の「釣談」(全集第29巻)では、「一口に釣りといっても、種々様々で、私のするのは今は鱸釣りのみです。---鱸釣りは---酒を飲みながらでも、茶を啜りながらでも、また、詩集俳諧などを読みながらでもやれます。余裕(ゆとり)がある、一番ノンキな釣りです。半分は水の上であそんでいるようなものです。---広い景色の中に船を浮かべて、そよそよ風に吹かれながらおとなしく遊ぶ、それが面白いのです」と言い、「鱸はおおきい魚だから鮒〔フナ〕でも釣る様にそう釣れるものではない」ことをその理由にあげている。
当時、スズキ釣りは竿を使わず、手釣りで、つまり道糸を二本の指で持って当たりを待った。休むときには「脈鈴」を使う。脈鈴とは舟の縁に立てた鯨のひげの先に鈴をつけたものを言い、これに釣糸をかけておく(「書簡」225、全集第39巻)。魚が掛かると鈴がなって知らせてくれる。『幻談』のなかでクロダイ釣りの手釣りについて同様の記述がある。
友人で軍医の賀古という人に宛てた明治38年8月30日付の長文の手紙(「書簡」225、全集第39巻)では、利根川での鱸釣りについて書いていて、三尺の鱸が釣れるまでを描いた「雲消えて----秋風に小鈴ひびきて/我が針を鱸おとなふ」など4つの詩も入っている。ここで「脈鈴」の説明も与えている。
このように、スズキ釣りでは、魚を釣ることだけが目的なのではなく、自然の懐に抱かれ、のんびりと周囲の景色を楽しみながら、水の上で遊ぶのが目的だと言っている。3年前に書いた「游漁の説」では、魚をできるだけ多く釣ろうとすることは游漁者の品位に反することだと言っていた。餌をたびたび取替えたり、釣り場をあちこち移動してみたりして、滅多に釣れない大型魚のスズキを釣ろうと懸命に努めることも「あくせくする」ことであり、やはり品位に反することだと考えただろう。
だが、スズキ釣りにおいても、はじめから、沢山釣ろうとはせず、釣ることは二の次で「自然に抱かれる」ことが主目的だというような態度で行なわれていたのかというと、決してそうではなかったのである。
「夜釣の思ひ出---利根川を開いた話」(別巻下。昭和2年、62歳頃)では、 若い頃の釣りを振り返り、「鱸釣りは急流の只中に船を止めて、そこで一夜を明かさなければならない。当時は船も自分の物、船頭も東京から連れて行くという騒ぎで、大きい鱸を何十貫〔40貫なら150kgになる!〕と獲って、それを銚子籠に入れて貨車に積んで東京に運んだ」と言っている。急流のなかに船をとめる作業は船頭とともに行うのだろうが、「力仕事だった」といい、年を取ってしまった今では無理だと書いている。若い頃は、彼も本職の漁師のように、相当の労力を使って大量のスズキを釣ったのだ。
また「釣魚小話」(全集、別巻下。日記にも書かれている。)では、大正6年10月1日、洲崎の土手が津波〔台風による大波と思われる〕で切れた大荒れの日に、(船頭が漕ぐ)自分の船で向島から中川を上って利根へ出て、鱸釣りをした。土手の上の松が風に吹き折られるほどだった。家人は生きてないだろうと思っていたと書いている。このとき彼は50歳になっているがまだ気力があり、海や川が荒れている時ほどよく釣れるスズキを狙って釣りに出かけたのである。それほど彼はスズキ釣りに熱中していた。
スズキは凪つまり穏やかな天候のときには食いが悪く、当たりを待つ時間が長くなる。そのようなときには、彼は確かに、周囲の景色や野鳥の声を楽しみながら、酒を飲み、詩を作りつつ、釣り糸を垂らしていたのであろう。しかし、そのようにのんびりと待つ釣り方をするようになったのも、長年の経験で、魚が食ってこない時間帯があり、餌を取り換え仕掛けを入れなおすなどの動作を四六時中続け、糸を持つ指先に注意を集中し続けることは無駄であることを知ってからのことであろう。だから、彼の釣りは、はじめから、釣ることは二の次で「自然に抱かれる」ことが主目的というような悠然たる態度で行なわれていたのでは決してなかったのである。
44年2月の日記では、眼力〔視力〕の衰えと精力の衰えを感じ始めたと書いている。「多穫」の釣りには体力も必要だが、40代の半ばを過ぎてからは体力の方からも、「多穫」は難しくなっただろう。
このように、腕もよかったのだろうが、始めの頃は海釣りに夢中になり「多穫」することが多かった露伴は、「遊漁の説」を書くころにはスズキ釣りを始めるようになり、釣りの合間にのんびりする時間を楽しむようにもなった。だが、そのスズキ釣りにおいても、時々は、釣れそうだと考えれば危険を承知で台風時の荒天をついてでかけるなど「労働的」で、「品位」などお構いなしに釣ろうとしたこともあった。小説『幻談』8)において語り手は「大名釣り」と「労働的の釣り」の二種類を区別している。
露伴の多くの小説、物語が文語体で書かれているのに対し『幻談』は口語体で、しかも講談師のような軽妙な語り口で語る人物によって物語られる体裁をとって書かれている。文芸評論家山本健吉は「露伴独特の口演体」と呼んでいる。明治30年以後に書かれる「史伝」で多く用いられるようになったという。山本健吉『漱石・啄木・露伴』(文芸春秋社、昭和47年)。また山本健吉全集第11巻(講談社、昭和58年)。
ストーリーは、江戸時代、役についておらず閑な小旗本で釣り好きの侍が、二日続いて釣れなかった舟釣りの帰り、土左衛門(水死者)が掴んでいた上等な釣竿(全体が野布袋ノボテイ竹でできている「野布袋の丸」)を拾って帰り、翌日再度釣りに行くことになった。「釣れるは、釣れるは、むやみに調子の好い釣りに」なった。前日と同じような暮方になり、戻ってくると昨日とほぼ同じところに同じように浮いたり引っ込んだりする釣り竿が見え、「2人はなんだか訳のわからない気持ち」になり、南無阿弥陀仏と言いながら竿を海にかえしてしまう、という怪談めいた話である。
他方、語り手は、江戸末期、旗本などの侍が行なった船の黒鯛釣りは「大名釣り」と呼ぶ。この釣りでは、船頭がついており、釣り客は船の前部の茣蓙を敷いてある上座にきちんと座って前向きに竿を出し、魚を掛けたら自分で取り込まず、その竿を後に回すと、船頭が玉網に入れ魚を外して、餌を付け替えてくれる。客は少しも手を汚さずに、再び、仕掛けを振り込むことができる。彼は釣ることだけを楽しむのである。
また船には「上下箱」という茶器、酒器、食器、それにちょっとしたつまみを具えた箱があり、茶の好きな人は玉露などを入れて茶盆をそばにおき茶を飲みながら、また「潮間」(魚があまり喰わない時間帯)には酒を飲みながら、のんびりと釣りをする。「舟は上〔うわ〕だな檜で洗いたててありますれば、清潔この上なし」。舷側の最上部=「上棚」がヒノキ作りで念入りに洗ってあるというのであろう。(ただし<筑摩現代日本文学体系>4。『幸田露伴集』では振り仮名は「じょうだな」。)「客は上布の着物を着ていても釣ることができます訳で、まことに奇麗事に殿様らしく遣っていられる釣りです」という。
釣り船の船頭は魚釣りの指南番でも案内人でもない。ただ魚釣りをして遊ぶ人の相手になるだけである。人が愉快と思い不愉快と思うことをよく心得ていて客に愉快と思う時間を過ごさせることが出来れば、それが好い船頭なのである。客も、魚ばかりにこだわっているのはいわゆる二歳客(遊郭などでまだ場慣れしていない若手の客)だ。といって、釣りに出て釣らなくてもよいという理屈はないが、アコギに船頭を使って無理にでも魚を獲ろうというようなところは通り越している人である、と語り手は言う。
『幻談』に登場するクロダイの「大名釣り」は、「游漁の説」で述べられている「品格ある釣り」よりももっと上品で、粋な釣りである。
彼は、4~5日の予定で、人がまだ釣っていない仁淀川や吉野川の上流の渓谷を奥へ奥へと分け入った。愛媛あるいは徳島との「国境」(クニザカイと読むのだろう。県境のことである)をなす四国山地の中の釣り場にいくためには、バスを降りてから4時間5時間歩くのは当たり前で、時には、雨に打たれながら、4時間かけてつま先上がりの山道を岩や蔦につかまりながら急坂を上り、そのあとは逆落としの急勾配を足もとに注意しながら降りるなどした。帰路、バスに乗るべく車の通る道まで歩いたが、運悪く乗り遅れるなどし、結局、ほぼ10里、つまり40kmもの道を歩いたこともあった(「面河オモゴ行き」)。(注)
----------------------------------------------------------------------------
四万十川の上流にも出かけた。地図を見て大まかな見当をつけ、土讃線と森林軌道(これは今宇和島に通じている予土線の前身だろう)を利用し、終点でおりてしばらく川沿いに歩いた。途中から、急な山道を上り下りする「二里半」=10kmの「近道」をしたが日が暮れて真っ暗になり、岩を噛む脚下の瀬音におののきながら、足と手の感覚だけを頼りにゆれる吊り橋をわたって目的の集落に到着した(「天国地獄」)。(注)
---------------------------------------------------------------------------
(注)この釣行は昭和16年の夏である。「影地」という部落から山を越え、つり橋を渡って「松原」という部落に宿泊したという。これを確かめるには、グーグルマップ、「梼原町松原」で検索し、縮尺「200m」から「100m」で見る。雨村が越えた山とは多分、小松尾山であろう。その麓には川もある。「影地」という地名は見つからない。現在ではこの山にはトンネルが通っているようだ。
森林軌道の終点は「田野々」とされているが、現在の予土線の土佐大正駅の近くには「田野々小学校」があり、「田野々」の地名が見られる。
---------------------------------------------------------------------------
現在の釣り人には信じられないような過酷な釣りの旅が出てくる。山歩きや登山が目的ではなく、あくまでも(良型の渓流魚を)釣ることが目的なのであるが、もう若くないのに、釣りたい一心で、雨の中、危険な山道を滑ったり転んだりしながら上り下りしたり、数十キロもの道を急ぎ足で歩きとおしたりしている。
雨村のように釣りのために数十キロもの長距離を歩いたり、あるいは「近道」のために危険な山道を上り下りしたのは乗用車が普及していなかったからである。
しかし、車を使うことが当たり前の現代では、歩くことはしないだろうが、また、宿に泊まって釣りをすることもなくなった。友達と一緒に、昼釣りなら、真夜中に出かけ、釣り場に着いたら車の中で2~3時間仮眠すると払暁とともに釣り始める。夜釣りの場合には夕方出掛け、暗くなる前に釣り場に着いて磯に入ると眠らずに釣りをする。
釣れても釣れなくても予定の時間いっぱい釣りをする。今日は沢山釣れたから、あるいは大物を何匹か釣ったから、早めに竿をしまおうと考える釣り人はまずいない。夢中になって釣っているうちに帰りの時間がくるのである。そして、釣りを終わるとすぐに交代で運転して帰ることになる。渡船を利用する場合にも磯釣りでは多少なりとも危険を伴い、夜釣りは相当に危険である。こうして「労働的」で危険を伴うものである点で現代の釣りも、雨村の書いている昭和初期の釣りとさほど変わらないと言えるのである。
釣りには人を夢中にさせる要素がある。悪天候で危険であろうがなかろうが、釣りに行く時間的余裕があれば行きたくなってしまう。そして、特別の大物でなくても、魚が連続して釣れはじめると、とくに仕掛けを入れると同時に食ってくるいわゆる「入れ食い」の状態になったりすれば、ほとんどの人は我を忘れて夢中になって釣り続ける。
釣り好きの人にとって、釣りが「労働的」であることは少しも苦にならない。釣りのために必要な労苦は快楽実現のための当然のステップであるか、釣ろうとする意欲を高めるアピタイザー、ないしは釣れた場合の快をいっそう大きくしてくれる香辛料でしかない。
したがって、釣りが「労働」あるいは「労苦」、そして時には危険を伴い、釣れ始めると夢中になって釣り続けるということは、「漁夫」が釣りで生計を立てるために「あくせくする」ということとは全く別のことである。
おそらく冒険的でないふつうの漁師は、シケの日には出漁をやめるであろうし、漁をした日には明日また行わなければならない労働のために体力を残そうと、一定の目標を達成したら、そこでその日の漁を切り上げるかもしれない。
しかし、遊漁者はそうではない。露伴の時代の船頭つきの釣りの場合、船頭が今日は終わりだというまで、釣りを続けただろう。魚が釣れ続いている最中に、もう十分釣った、満足したと感じて終わりにする人は(よほどのベテラン以外には)稀であろうし、釣りで生計を立てているのではないから今日はこれでおしまいにしようなどと考える人はたぶん皆無であろう。
遊漁者の「多穫」はあらかじめ立てられた明確な目標としてあるのではなく、遊漁者はただ釣りたい一心で釣りはじめるのであって、「多穫」は運よく釣れたときの結果であるに過ぎない。「漁夫ではないのだから沢山釣る必要はない」ということはそのとおりなのだが、遊漁者ははじめから必要と無関係に釣りをするのだから、その言葉は全く意味がないのものでもある。
同じことだが、二種類の釣り(釣り方)がある。一方の釣りでは釣ることが唯一の目的で、釣り人はできるだけ沢山そしてできるだけ大きな魚を釣ろうとする。こうして、絶えず新しい餌に取替え、竿先(または指先)に注意を集中し続け、時間と体力を目いっぱい使って釣る、若者向きの釣り。この釣りでは、釣り人は行く手を阻み時には危険をもたらす荒々しい自然と闘いつつ釣り場に向かう。釣り人は「格闘的」、「労働的」で、動的な興奮の快楽を追求する。
他方の釣りは魚を釣ることにこだわらず、当たりがないときには、周囲の景色を眺めるなどのんびり時間を過ごすか、あるいは、何か他のことをして---露伴は酒を飲みながら詩を作ると言っていた---楽しむ釣り。この釣りでは静かな快楽、安らぎの快楽を追求する。ただし、たとえば詩作が主目的で釣りはどうでもいいというのでないかぎり、釣れ始めれば「他のこと」はやめ、釣りに精を出すだろうが。これはわたしような何年もの間釣りをやってきてすでにある程度釣りに満足した人間かあるいは体力を使う釣りが無理になった老人向きの釣りである。この釣り人が向かうのは「労働」や「格闘」を必要とせず「悠然」としていられる穏やかな自然である。この人は安らぎを伴う静かで落ち着いた快楽を追求する。
この二種類の釣りのうちの一方、労苦をいとわず「多獲」/「型」(つまり大型の魚)を追求する釣りは、釣りを始めて間もないが釣りに夢中になっている人なら必ずそうするだろう釣りであると思われるので、「本来的な釣り」と呼ぶことにしたい。本来的な釣りとは多数派の釣りであり、趣味上の優劣その他、価値評価は含まない。釣りにでかけたら外のことに一切関心を持たず、釣れようが釣れまいが釣ることだけに集中する釣りである。
他方は魚を釣ることにこだわらない釣りである。
ピクニックでは、野山を歩くのを楽しむとともに、食事時にはみんなでわいわいがやがや様々なことについて話をするのを楽しむ。食後には軽スポーツを楽しんだり、歌や踊りを楽しんだりする。このように、船から釣糸を垂らすが、当たりがないときには、釣りとは別のことをする、周囲の景色を楽しんだり、詩を作ったり、あるいは一杯飲んだりする、「悠然」たる釣りがある。そこでこれは水上での様々な趣を楽しむ釣り、「趣の釣り」と呼ぶことにする。中年以降の露伴が好んだ釣りである。19世紀の英国では、釣りが上流階級の社交の場になったこともあった。あるいは、多少ひろげすぎになるかもしれないが、18世紀以降英国の上流階級が行なったフライ・フィッシングのように、釣りの「様式」を強調することで他の身分との違い・ディスタンクシオンを顕示しようとした釣りをこの「趣の釣り」にいれることができるかもしれない。他の目的を、魚を釣ることと同時に追求する釣りを「趣の釣り」と呼ぶことにしたい。
ところが「游漁の説」の露伴は、一方の普通の/本来的な釣りの特徴である、さまざまに工夫し、釣れなければ場所を変えたりもして、できるだけ多く釣ろうとすることを、漁師が生計のために「あくせく」するのと同様のこととみなして退け、「多獲」せず、「悠然」と水上での「趣き」を楽しむ「品位ある釣り」行うようにと説いていた。
また「游漁の説」には、遊びである釣りと自分の「本来の職業」との関係についての議論が行なわれていた。つまり遊戯・娯楽のために行う釣りは「自分本来の職業に対する気力を鼓舞」するために行うのだという議論があった。ふつう、釣りでは、あるいは「本来の釣り」では、できるだけ沢山(そしてできるだけ大物を)釣ることが釣りの主目的であり、沢山釣れれば釣れるだけ面白く感じられる。つまり「心を娯ませ」、「職業に対する気力を鼓舞する」ことになるはずである。ところが、魚を多く釣ろうとすることは、漁夫の釣りと同じ生計への関心、生存のための身体的な関心を満たすことであり、「心神を怡悦イエツせしめる」精神的関心を満たすことではないという別の論理によって退けられ、できるだけ多くの魚を釣るという普通の釣り人の当然の関心事―そして30年代までの露伴の釣りの実際の関心事―が否定され、「悠然として」、「水雲の間に遊ぶ」、品格ある釣りが、推奨あるいは賞揚されていた。
露伴がいう「まめやか」は自分の体を使うこと、「身を労する」ことである。確かに体を動かすことは(座業がほとんどである小説家にとって)、職業上の腐気を排去することになるだろう。(エリアスがスポーツが非慣例化作用を持つと言っていたこととも重なる。)
だが、「疎懶」にせず、「まめやか」に釣ろうとすれば、仕掛けを入れたままにしてぼんやりと当たりを待つのでなく、たえず仕掛けを点検し餌を付け替え、コマセを多く撒くなどあれこれ工夫するだろう。それでも当たりがなければ場所を変える、つまり舫っていた船を動かし(当時は手で船を漕ぎ)つなぎなおすだろう。
ところが多獲をめざす漁師も同じようにするだろう。漁師の場合には一か所にとどまって魚が来るのを待つのではなく、次々と釣り場を変えながら釣ることが多い。
露伴は、漁師が「生計のために」「多獲」しようと工夫し、がんばることが「あくせく」することだと言うが、「まめやか」にすることは「休む間なくせかせかと仕事をすること」、「あくせくする」こととどう違うかを言うことは難しい。
これとは反対に、疎懶とは船の上で体を動かさず、必要な作業、行動を他人任せにすることである。別の言葉でいえばのんびりとくつろぎ、悠然としていることである。自分で船を漕ぐ/操船する手前船頭の場合には、一度船を舫ったら、釣れようが釣れまいが、そこにとどまって、釣る。当たりが出れば餌を付けなおして釣ろうとするだろうが、それまでは周囲の景色を楽しんだり、寝転んで休んだりする。『幻談』でいう「大名釣り」では、魚の取り込みも、餌の付け替えも船頭にやってもらって自分ではやらず、手も着物も少しも汚さず、釣りの合間に茶を楽しむ。これは「疎懶」なのではなかろうか。つまり「疎懶」な釣りと「悠然として」「水雲の間に遊ぶ」、品格ある釣りは区別できないのではないだろうか。
また、多くの場合「まめ」な釣り方の方が魚は多く釣れる。刺し餌は新しくたっぷりつけてあるに越したことはないしコマセも頻繁にたくさん撒けば撒くほど魚を寄せる効果が大きいことは明白である。また初心者がしばしば大物を釣る「ビギナーズラック」は、「ベテラン」なら日和り、潮、場所を理由に大した釣果は期待できないと見切って、寝てしまわないまでも餌の付け替えを怠ったりしているときに、せっせとコマセを撒き、新しい餌を付け、竿先に注意を怠らないで釣り続けることがもたらす。「まめ」は、露伴が「興趣に反比例する」という「多獲」(あるいは大物のゲット)を必ず結果するとまでは言えないにしても、多くの場合に、その必要十分条件なのである。
釣りで「まめやか」にすることあるいは「労苦」することは、獲物を得ることによって得られる釣りの快を実現する単なる手段なのではなく、それ自体に快がある。同じことだが、釣りにおいて悠然としている、あるいは疎懶でいることは、釣果が得られるかどうかを別として、それ自体釣りの快の損失なのである。
『幻談』の侍は、当たりを取って魚を掛け、魚の抵抗を交わして船べり寄せるという主要ではあるが、釣りの快楽の一部しか楽しんでいない。魚を船べりまで寄せても、そこで糸が切れたり針がはずれ逃げられることがある。魚を玉網で掬う必要があるが、それにも練習が必要で、魚を掬って船内に取り込む瞬間は魚を寄せてくるときにおとらず、釣り人が緊張し興奮する瞬間であり、上手く魚を玉網に収めた時に魚を釣ったことの快楽が強く感じられる。また魚は船の中に取り込んで初めて釣ったと言えるのであり、釣り人はそのときにこそ魚を「釣った」ことの本当の快を感じる。
そして、船の中へ入れた後、はねる魚の動きを感じながら魚を針から外し、つまり手で直に魚に触れ、「これ」を釣ったのだ思う。このように魚を船べりに寄せたあとでも、何段階もの興奮に満ちた快楽があるのだが、侍は魚を船べりに寄せた後はその扱いを船頭にゆだねてしまい、釣りの快楽の何割かを楽しまずにいる。彼は「きれいにしている」ことの「優雅さ」を楽しんでいるのだろうが、釣りの楽しみを十分に楽しんでいるとは言えない。
こうして、「游漁の説」で説かれている、游漁者の釣りと漁夫の釣りの区別、多獲をめざす釣りと「興趣」を求める釣りの区別、身を労することと悠然と水雲のあいだに遊ぶこと、まめやかと疎懶などは、一見もっともだが決して明確なものではなく、あいまいなものである。
そして、「本来の釣り」の快楽はなんであるのか、つまり釣り人が釣りに求める「興趣」とは何かについても露伴は明らかにしていない。たぶん、釣り人の取るべき態度(悠然としているかどうか)などは「興趣」とは言えないだろう。他者との関係においては、人は取るべき態度は語りうるが、釣りが一人で行うものであるとすると、どんな態度を取ろうが構わないはずである。おそらくふだんの彼のハビトゥスにもとづく態度がおのずと現れるだろうが、獲れた時には大いに喜び、釣れなければ腹立たしく思い、大物を掛けたが逃げられた時には悔しがるだろう。常に悠然としており、「君子」であることを気取る必要はないはずである。
研堂には、大型魚を掛けたあと魚が激しく抵抗して泳ぎ回り、綸(イト)が水を切って音を立てたこと、彼は「動悸しきりに催して、心も心ならず」の状態で、魚がやっと船頭の網に入ったこと、あるいは別な釣りで、魚との30分ものやり取りの後結局綸を切られてしばし呆然としたことなど、大物釣りのダイナミックさを描写した随筆がいくつかあるが、大物釣りに限らず、魚を玉網で最後に取り込むことを含めてハラハラドキドキする釣りのダイナミックな快を描いている。
露伴は鱸釣りで大型魚を逃がした時のことを日記の中で書いている。前日から小物しか掛からなかったので縒り綸(イト)を使わず、一本素(ス)の細仕掛けで釣りをしていたところ、「巨魚突として至り、綸の摩擦に指の皮を焼くに及びたり」。(手釣りでは大きい魚が突っ走ると道糸の摩擦で実際指にやけどができる。)綸が細いので時間をかける必要があると、彼は時計を開いて見、どれくらい時間をかけたら取り込めるだろうかと、「ひそかに余裕あるを得るに至りし今の我に満足しつつ、せかず慌てず心しずかにやりとりし、---ようやく二間ほどまでに引き寄せしに」、魚はスズキに特有の「水上に飛躍すること」(=えら洗い)なく、体を見せなかったが、尾びれ〔の上半分〕が見え、その大きさからひれの先の幅は7寸(21センチ)を超えると推測された。非常な大物である。彼は取り込みは無理だと思い「流石に失望の気味あり」。結局、魚の勢いは衰えることなく、最後に「手ごたえも無く〔なっ〕て逝く水の流れにす〔ハリス〕のみ浮ききたり」。時計を見ると39分経っていた。「鉤素(ハリス)を調べてみると綿のごとくになりて細り切れたり。術の力はしかけの力に及ばずと今更ながらおもひしみぬ」。仕掛けが細ければ技術があってもやはり無理だと思った、と結論を下している(「六十日記第五」、全集38)。
この日記では、「巨魚」が掛かったが、経験から、仕掛けが細すぎ、腕はあっても取り込みは無理だと冷静な判断を行いつつ、魚とやり取りをしている。ハラハラドキドキしている様子は見られない。糸が切れ魚が逃げた後も、予想通りとばかり、ほとんど悔しがっていない。露伴は、他のところで、三尺を超えるスズキも沢山釣ったと書いているが大物とのやり取りや取り込みについて描写しているのはこの日記の文だけではないか。大物が掛かったときに相当に経験があっても、ハラハラドキドキせずに釣りをする人はまれだろうと私は思うが、彼はその興奮と緊張に釣りの快楽をさほど見出さなかったようである。
釣りのハラハラドキドキする興奮の快を好み、労苦をいとわず数または型(=大型)を求めて奮闘・努力する「本来の」釣りと、獲物を得ることにはこだわらず、「悠然」と水上での「趣き」を楽しむ「品位ある釣り」の二種類があると述べ、年齢とともにまた釣りを重ねるうちに、露伴の釣りは次第に、前者から後者へと比重が変化してきたことを上で述べた。
露伴は漁夫は生計のために釣るが、游漁者の釣りは心をたのしませるための「遊戯娯楽」だという。しかし、遊戯娯楽は「遊戯娯楽のための遊戯娯楽」、つまり遊び楽しむことを目的とする自己完結的な活動なのではなく、「その人本来の職業に対する気力を鼓舞振作し」、職業上の「腐気を排去」して「始めて遊戯娯楽の真旨に適し、妙用を果たせりといふべし。---魚を釣るは手段なり、目的にはあらざるなり」と言っていた。
「游漁の説」が上流階級の人々を読者と想定して書かれていることは上で述べた。 この文の中で、遊漁者には「尊重すべき自己本来の職業」があるという。また英国紳士の銃猟の趣味について「自己本来の職業と地位を忘却」しない「知慮と品位の発現」だと書いている。 他方、一か所だけ漁業者という語もあるが生計のために釣りをするものは「漁夫」と言われており、「苦しんで生計のために齷齪(あくせく)たる漁夫」という言葉がある。これだけで彼が漁業という職業についてどのように考えていたかはわからないが、露伴が「漁夫」の仕事を単に「生計の手段」にすぎず、各自「尊重すべき」職業であると考えていなかったとすると、釣りを自己目的ではなく、職業に対する気力を鼓舞し盛んにするための手段であるとすることは、間接的には、釣りを職業・「生計」のために行う活動だとみなすことになるように思われる。『蘆聲』(昭和4年、全集第4巻)の中で「三十余年前の」思い出を書いている。そこでは、「一竿を手にして長流に対する味を覚えてから一年」たったころ「毎日のように中川べりへでかけた」と書いている。当時の中川沿いの奥戸、立石周辺は「まことに閑寂」で「黄茅白蘆コウボウハクロの洲渚シュウショ、時に水禽スイキンの影を看みるに過ぎぬ」「和易安閑ワイアンカンたる景色」であった〔振り仮名は原著のまま〕。家から立石までは約40分。彼は「然様ソウいふ中川べりに遊行したり寝転んだりして、魚を釣ったり、魚の来ぬときは拙な歌の一句半句でも釣り得てから帰って、美しい甘ウマい軽微の疲労から誘われる淡い清らかな夢に入ることが、翌朝のすがすがしい目覚めといきいきした力とになることを自然不言不語に悟らされていた。」「その日も午前から午後へかけて少し頭の疲れる難読の書を読んだ後であった」。その後、海釣りに傾倒するようになり、早朝あるいは夜中に出かけ一日中釣れるだけ多くの魚を釣った。
こうして、かれはしばしば仕事をはなれて趣味娯楽としての釣りを楽しみ、「気力を鼓舞振作」することができた。
明治39年『雑誌中学世界』に書いた「青年時代と娯楽」(全集、別巻、上)では、学生が終日一室に閉じこもって勉強ばかりしていることは心身の不健康を招くことになり、娯楽が必要だが、囲碁将棋、楽器絵画など頭脳的な娯楽は頭脳を痛め易い。青年学生には「身体的な、身体を労してする娯楽をもっとも適当と信ずる」、と言っている。ただし、他方で、娯楽はどこまでも娯楽に止まり、修学とは別のものであるからして、娯楽に重きをおくようになっては甚だ困る。学生に娯楽が必要だというのは「畢竟修学のために」必要なのであり、「その主客を転倒して勉強のほうがお留守になるやうではいけない」、とも書いている。
また明治35年の「青年の娯楽につきて」(同別巻、上)では、「自分で言うのはおかしいが小説を読むなどの娯楽は学生にとってあまりよい効果を与えまいと思う」と書いていた。理由は脳の使いすぎになるということである。ふだん頭脳労働に携わるものは身体を使うことによって「心を逸し」頭脳を休ませることができると言うのであり、ある種の「科学的」(心理学的)、理論的な説明であるといえる。
そして現実の彼の生活は頭脳を酷使するものであった。だから彼は単なる“理論”を述べているのでなく自己自身の実際の生活に即しても述べている。
ところが彼の趣味は単に「身体的」活動にはとどまっていなかった。すでに上で述べたように、彼は「青年時代と娯楽」ではよくない部類にあげていた将棋にも、ずいぶん打ち込んでいた。
また、「予が研鑽苦心の根本義」(明治42年、同別巻、上)では、中学2年まで学校で修業して以後はもっぱら家業(貸本屋)の手伝いをしていたが、読書は何よりも好きで、暇さえあれば上野の図書館に行って本を読んでいたと、書いている。彼は若いときにはとくに身体的健康を重視すべきだといっているが彼自身は、ずっと好きな本ばかり読んでいたのである。
だから、彼は、ほかの人々に向かっては、頭脳の酷使はよくない、本務・本業で頭脳を使うのであれば、娯楽においては体を動かすべきだと説いているが、彼自身はそうした“理論”に反して、頭を使う娯楽も含め、自分の好む娯楽を自由に行っていた。その点で、彼の「趣味理論」は半分しか真実でない。だが、職業/仕事が主で趣味娯楽は従(客)という職業倫理についてはほぼ忠実に実践していたと言える。
そこで、釣りにおける変化も彼の職業/仕事の在り方の変化と関連付けて考えることもできるかもしれない。彼は小説を書く仕事をしていたときにはかなり強いストレスを感じていた。頭脳の酷使というだけでなく、仕事の期限や出来栄えなどに関連した他者との関係における強い精神的ストレスを受けていた。そうした社会的・精神的ストレスが強いときには、人はワクワク、ドキドキする動的な快楽を必要とし、前の章で見たエリアスのいう「戦いの興奮」、あるいは、身体運動を伴う「興奮、緊張、そこからの解放、つまりカタルシス」を与えてくれる活動を求めるようになる。露伴の言葉でいえば、「まめやか」にし「身を労する」ことによって「心逸する」ことを求める。
釣りについて言えば普段の仕事が忙しければ忙しいほど、夢中になって魚を釣るような釣りを好む。しかし、仕事に追われるということがなく、何であれ自分のしたい事をしたい時に行う自由があるときには、人はワクワクドキドキする緊張を伴った興奮を求めることが減り、釣りに出ても齷齪と「身を労し」、あるいは「まめやか」にするよりも、のんびりとした静かな趣を楽しむことのほうを好む。
露伴の釣りの変化は年齢に伴う体力の低下とも関係があるが、それ以上に、趣味と仕事の両面を含む彼の「生」の全体のありかたが変わったことと関係があるとみることができる。
露伴は小説家という限定された(専門的な)仕事よりも、ずっと「幅広い」分野にわたる仕事を行うことに「自己をみいだした」のだ。露伴の仕事を前期と後期にわけるなら、前期の仕事は小説家としての、後期の仕事を学者としての仕事だということができる(塩谷、同書(昭和40年版)上)。後期露伴の仕事の内容からすればそれももっともである。9)
明治39年に創設された、京都帝国大学文科大学(後の京大文学部)で、露伴は吉沢義則(国文学)、内藤湖南(東洋史)、上田柳村(本名・上田敏)らとともに、教授待遇の講師として国文学を教えることになった(塩谷、中)。
明治40年には「遊仙窟」という論文を発表している。この中で露伴は日本最古の小説・竹取物語の作者とその成立年代、および竹取物語が書かれる以前に「わが邦に始めて入った外国〔中国〕の小説」・「遊仙窟」についての詳しい考証を行い、「遊仙窟」が万葉集はじめ日本の文学に与えた影響を明らかにしている。10)
露伴は同じころ、「群書類従」に収められていない演劇、歌曲などの分野に関する著作を扱う『新群書類従』編纂計画に関与するなどの仕事もしていた。彼は1911(明治44)年には「遊仙窟」に関する研究によって文学博士の学位を受けた。11)
このように彼の生活は明治40年ごろを境にして、「学者」的あるいは「学究」的活動が中心になる。では露伴の生において、娯楽と仕事との関係はどのようなものであったか。どう変化したか。
中年の露伴

また、竹取物語は延喜の前後に書かれたもので、天平から延喜まではおよそ170年あり、「始めて外国小説が我が那に入りし後、百数十年を経て、始めて我が那の小説〔が〕呱々の声を発したりと云ふ可きなり」、と言う。
「遊仙窟」の作者・張文成について、12世紀ごろの〔日本の〕「唐物語」における「奇異なる談」その他を検討して退け、その「人となりを考へ、その性情思想を測」っている。最後に「遊仙窟」(の写本)は日本に伝わってから千余年今なお存在しているが中国では早くに散逸してしまったようだ、「是も亦奇なる哉」と結んでいる。
注11)塩谷によれば、博士会の議で、議定された直接の資料は「遊仙窟」だった。なお塩谷は「遊仙窟に関してこれ以上の考証は存在しない」と最上級の賛辞を呈してる。塩谷、同書、中、p110、p27、)。
だが、その後間もなく海釣りを開始し、それに熱中する。しかも、釣るだけでなく、釣り竿、釣りえさ、鉤など、釣りに関係する事物、釣りの周辺へと彼の興味が広がった。彼はその間も多くの著作を行っており、仕事をおろそかにしているわけではないから、仕事よりも趣味の方が主になったとは言えない。だが、作家としての仕事の中で趣味の釣りに関係した著作、あるいは釣りに関係のある事柄を扱った著作が重きを占めるようになり、そして、遊びとしての釣りと仕事の境界ははっきりしないものになっていった。
彼の釣りの趣味は本来の職業とはっきり区別された遊びの領域にとどまるものではなくなった。彼は趣味娯楽であった釣りを「その人本来の職業に対する気力を鼓舞振作」するための単なる手段にとどめておくことはできなくなったのだと私は思う。工夫し経験を積むことにより釣果が違ってくる深さがあり(これと似たことは、多かれ少なかれすべての趣味に共通して言えることだろうが)、また釣り方の異なるさまざまな種類の魚を釣る、幅の広い楽しみ方もでき、そして『蘆声』や『釣談』などに書かれていたように自然に抱かれ、「四辺の光景を楽しむ」釣り方もあり、実際の釣りが多様な魅力を持っていることも確かである。しかし露伴の場合には、実際の釣りの面白さとともに、釣りの周辺、釣りに関する「詮議」あるいは「論弁思索」に対する興味が彼を釣りにいっそう傾倒させることになったのだと思われる。
『釣漁談一則』で彼は鮒(フナ)釣りに使う餌のミミズの養殖を行ったことを書いている。彼は甕(カメ)や苔を使うなど様々な工夫をし、「西洋の人」(ウォルトンだろう)のやり方も調べるなどした上で、自分のほうが優れていると主張している。独自の工夫をしながら行なったこのミミズの養殖は一種の生物学的な研究であり、それについて書いたこの随筆は「研究論文」とみなすことも可能であるが、それよりは釣りの遊びの一部とみなすほうが適当であり、さらにここでは遊びと研究/仕事を分けることはできないと考えるのがもっとも適当だと思われる。
「鉤(はり)の談」では、海外の文献も参照するなどして、釣り鉤(=釣り針)が備えるべき必要な機能と形状を20ページに渡って論じている。これも本格的な堂々たる民俗学の「研究論文」である。だが、釣り針の研究は彼の趣味の釣りの延長であることも明らかである。
「釣車考」(明治42年、全集第29巻)及び「漁父詞の作者」(大正3年、全集第15巻)はリールが中国、唐の時代に存在し、上流階級の遊びの道具として使われていたことを明らかにした論文であり、「太公望」(昭和10年、全集第17巻)は釣り人の代名詞になっている実在した春秋の時代の人物について、その伝承の信憑性を中国古代の文献を渉猟して書いた50頁に上る長い論文で、いずれも仕事としては「考証」に分類される。だがこれらの仕事も、遊びとしての釣りと密接な関連があることは明らかである。
皮陸よりも2~30年後の詩人で徐インと言う人が、釣車の仕組みや糸の出方がより詳しく分かる詩を書いている。釣車は漁夫が用いた道具であるよりは、遊漁者用のぜいたく品だったと想像される。ほかの詩文を参考にすると、全く士君子が取り扱ってもおかしくない、琴とか笛とかいうような道具の類と同じほどの品位を有していたと考えられる。
皮陸の二人より百年ほど前に張志和がいる。唐書〔唐の正史。225巻〕の121巻目に伝記が載っている。16歳で学問にぬきんでて、皇帝から非常に賞重され、その名をもらった。しかし仕官を好まず煙波釣徒と号し、一生を自由に送った、「仙人肌の大釣客」である。
書も上手で鼓を打つことも知っていれば、笛を吹くことも知っていた。漁夫詞という詩形の早期のものの一篇「西塞山前白鷺飛、桃花流水?魚肥ゆ、---」は有名。〔?は魚偏に厥でケツと読む。Hypertextediterには字がないらしい。漢和辞典によるとケツ魚は淡水魚のコチで、Web検索すると写真が載っている。〕その中に釣車の語があり、これがもっとも古い事例ではないか。「浅学寡聞の私のことですから断言はしない」。その時分は日本の奈良時代初期に当たる。中国文明は侮りがたい。唐の後、詩には見えないようだ。しかし宋の時代の名高い画家に馬遠がいて、彼が描いた寒江独釣の図がある。そのなかで釣車とおぼしきものを持って釣りをしている。
「はなはだ無益の談ではありますが釣車のお話を申し上げました。これも娯楽の余で」。
また、「鼠頭魚釣り」の中で次のように言っている。 「下手の道具詮議」という語があるがそれは正しくない。仕事でも遊びでも同じく道具選びが大切で、魚釣りにおいてはよい釣具を選ばなければならない、と言った上で、遊びの釣りであれば、よい道具を使うことがよい釣果を上げるのに役だつだけでなく、道具をあれこれ詮議〔論議〕することもまた楽しみであり、楽しみを増やすことになるからなおさらだ、と言う。
たとえば釣り竿は単なる竹竿なのではなく、原材料にする特別の種類の竹を、特定の時季に切り出し、特別な仕方で乾燥させるなどした上、すぐれた職人技によって、理想的な曲がり方をするように、また曲がっても容易に折れないように繋ぎ方が工夫された多数の部分からなるものである。こうした竿の特性を心得ておくことは確かに釣りの腕をあげることに役立つ。
しかし露伴の場合には、その特性はどのような製法や材料によって生み出されるのかという新たな知識欲を掻き立てられることになる。私ならリールが古代の中国に存在したことを知れば驚く。しかしそれで終わる。ところが露伴ではその存在を自ら資料に当たって調べ確かめようとするのである。竿の特性を知ることは腕の向上につながっても、竿の製法や原材料の知識、等々を豊富にしたからといって腕が上がるはずはないと思われるが、露伴の場合には、彼の尋常でない強い知識欲あるいは「論弁思索」を好む性向が釣り道具の研究に向かわせた。
明治40年から3年ほどの間、「欣賞会」という、珍しい本を持ち寄って紹介する、本好きの人の会が月一回ほど行われた。はじめは「珍書会」といったが後に露伴が「欣賞会」と名づけた。露伴が出品したものの中に『何羨録』と『釣客伝』があった(塩谷、中巻)。
前者は元禄初期に後者は江戸末期にかかれた釣りの書で、露伴は釣りの趣味が強まる中でこうした書物を古本屋などで見つけ、読むのを楽しみつつ、調べたのだろう。露伴は欣賞会に出品した本に関連して、釣りを始めた動機について「明治32年の春頃、その時分好きだった鉄砲〔のシーズン〕が終わりになりかけて、末の弟に付き合って、中川向こうの奥戸で鮒釣りをやった。そのときそばにいたじいさんが講釈をして釣竿を貸してくれまして、それは12本継ぎのものでそれで釣るとぼくばかりよく釣れる。どうも釣れるのは釣竿のせいだなと思って、東京一といわれる釣竿製造師たちのことを聞いたりした。そんなことから釣好きになりましたわけで」と話している(同書)。
露伴は実際に水の上に船を浮かべて釣りをするのが好きだった。だがまた、彼は足しげく釣りに通うだけでなく、魚の生態や料理法を調べたり江戸時代の釣りを調べたりした。また釣り道具の良し悪しなどの「詮議」、「論弁思索」を行ない、また、餌のミミズの養殖を試みるなど、釣りに関係のある様々なことを行なった。
では古い漢詩文を読み漁って、「釣車」や「太公望」について「調べる」ところまでは遊び、もしくはその延長であるが、文章にし雑誌に発表することは仕事であると分けられるであろうか。また、彼が実際に行なったキス釣り、クロダイ釣りについて書いた随筆はどう考えたらよいだろうか。
私の経験からすれば自分の行なった釣りについて、それがとくに大漁であったり、あるいは予想外の大物が釣れたりしたときには、後からそれを思い出して書くことは実際の釣りと同じくらいにとても楽しい。(第5章「釣りの回想の快楽―釣りについて書くことの快楽」を参照。)だから釣りについて書くことも釣りという趣味娯楽の一部だと言いうる。
露伴が雑誌に掲載した「鼠頭魚釣り」も「かいづ釣り」もあるいは「章魚〔タコ〕釣り」も大漁であるか大いに楽しんだ釣りで、露伴も書きながら釣りを思い出し、大いに楽しんだのではないか。すると彼は釣りの随筆を何篇も書いて雑誌に掲載したが、これは職業/仕事ではなく遊び、趣味娯楽と考えるべきだということになるように思われる。それらが雑誌に掲載され、原稿料を彼が受け取ったのは、彼の文筆の才がもたらした結果に過ぎない。(才能が不足していたら、彼は同人雑誌に発表していたかもしれない。)
露伴は作家、随筆家であり、材料、テーマがはっきりしている事柄を文章にするのに苦労を感じることはなかっただろう。そうだとすれば、実際に海で行なった釣りについて書くことだけでなく、自宅におけるミミズの養殖、スズキの生態についての研究、釣り針や道具類に関する調査、釣車や太公望についての考証などの結果を雑誌類に掲載できるように文章化し、(必要なら)文章を推敲するという作業も決して「労苦」ではなかっただろう。だから、私が釣り日記を書くことが実際に行なった釣りと同じくらい楽しいと感じたように、彼は、これら釣りに関する事柄を文章にするときには実際の釣りと同じくらい、あるいはそれ以上に楽しいと感じながら机に向かっていたと想像することができる。
私は釣り日記を人に読んでもらおうと思って書いていたのではないが、露伴の場合ははじめから読者を想定して書いている。彼は自分が調べた釣りに関する事柄の知識あるいは研究成果を世の人々に披露し、読者が多少でも驚き、感想や批評を述べてくれることなどを期待しつつ書いているだろう。そうだとすれば、ますます、彼は書きつつ愉快に感じていたと想像される。
露伴は一年で京大における職を辞した。その理由の一部は京大阪ではろくな釣りができないからということだった(同書)。このことに関して、塩谷は、次のように書いている。「京大で露伴としばらく交際を持ちかなり老いて後も両三度〔2、3度〕露伴の家を問うた新村出は、露伴が単に好きな釣りができないことから帰郷したのであると私〔塩谷〕に重ねて弁じた」。また露伴は京大阪では良い釣りができないとも言っているが、京大阪では陸(オカ)釣りが主で、船でする釣りは発達していない。学生を連れて疎水で綸(いと)を垂れていたら番人が出てきて大目玉を食らったことがある。「露伴の好きな釣りは京都ではできなかったのである」(同書)。
辞任した理由には露伴が博士号をほしがっているという悪口を言うものがあったことも関係があると塩谷は言っている。しかし京大を辞めたことの理由の一部にではあれ、釣りが十分できるかどうかということが含まれていたということに、彼の釣りへのこだわりの大きさがあらわれている。また逆に大学で国文学を講ずるという仕事に対してはさほどのこだわりはなかったこともわかる。遊戯娯楽は本来の職業を鼓舞するべきもの、という「遊漁の説」における言葉をそのまま受け取ることにすれば、彼は大学で俸給をもらいつつ国文学を講ずることを(遊びに対比して言われる)「本来の職業」とは見なさなかったことになる。
他方で彼は授業とは関係ないが、釣車の考証という一種の研究には力を入れている。彼は京大を辞めることによって、心置きなく釣りを楽しみながら、仕事もできる東京にもどったのである。大学で国文学を教えることも客観的に言えば、職業であり、仕事だと考えられる。すると、露伴には仕事と遊びの「主客の転倒」が起こっていると言える。
鎮西八郎が島流しにあっても自分の境遇に不満を抱かず不幸だとは考えなかったように、自分も政府に仕える官吏にはなろうと思わないというのだろう。だが、井上の好意はあえて拒むこともないであろう。しばらくは気難しく考えることはやめよう、というのだ。さらに彼は、三尺ほどの広さしかない小船を空の雲と川の水の間に浮かべ好きなだけ釣糸をたらして遊んでいれば十分である。ほしいのは釣船一艘と読書をするための一部屋だけだ、というのである。博士号を受けることを彼は少しも喜んでいない。
2月18日に中央新聞、「万朝報」から博士会に露伴のことが議題に上ったことを伝えに記者が来た。露伴は「区々〔小さなこと〕一些事に煩わしの世なる哉」と書いている。
2月21日には文部省の「出頭」要請に従い、「登省して」学位記を受け、帰りに井上宅を訪問し挨拶を述べて帰った。そして「学位の如き我唯委順する耳」と書いている。耳はのみ、委順は自然の成り行きに任せるという意味である。
彼は「学位」取得ための申請を自ら行ったわけではなく、ぜひ欲しいとも思っていなかった。そして、彼は井上哲次郎とまったく異なる思想を持っており、おそらく彼は井上に親しい感じを抱いていなかったはずだ。したがって、学位に関する井上からの手紙を喜んで受け取ったのではない。だが、露伴はあえて断ろうともしなかった。「唯委順する耳」が彼の心境である。
主に黒住真『近世日本社会と儒教』(ぺりかん社、2003)によると、井上は漢学も大いに学んでいるが、漢学科ではなく終始哲学科に属し、しかも東洋哲学を教えた。彼は最初は教育勅語の哲学的解釈者として世に現れた。《勅語衍義》(1891)で教育勅語を注釈し、《教育と宗教との衝突》(1893)でキリスト教を反国体的であると攻撃した。
清との戦い及び日本の勝利を背景に、漢字排斥論が再燃し、教育カリキュラムにおける漢文科の廃止をいう人が増加した時、井上は漢学の側に立ち、われわれは衰えた中国に代わって「東洋を背負って立つ」べきだと述べ、東洋的なものを抱き込む「大きな日本」を強調した。井上は学会誌『東洋哲学』にかかわり、「日本主義」を提唱した。日清戦争後、1900~6年に出された三部作、『日本陽明学派之哲学』、『日本古学派之哲学』、『日本朱子学派之哲学』で、彼はタイトルから「儒教」を消し、「日本」、「哲学」を標榜しつつ、日本の過去の諸思想が近代化の障害になったのではなく、それを構築する大きな意義のあるものだったと説いた。彼は「西洋に負けない東洋の道徳・形而上学やその歴史らしきものを構築することが出来た。---それは洋学を取り込みつつ、しかし東洋を強調し、さらには日本を強調するといいう意味で、明治国家の思想的要求に全面的に答えうる近代版の日本イデオロギーの条件を備えていた」と黒住はいう。
黒住は「時とともに漢学がイデオロギー化し、支那学が学術化する間で、次第に見えなくなるものがあった。それは漢学が中国文化から得てきた文学的芸術的な香りであり、また徳ある人格や政治の理想、あるいは東洋的宇宙観であった。明治末から大正頃まで、鴎外・漱石や一部の教養人たちは、それを思い起こそうとしていた」という。
私は露伴の「遊仙窟」のような仕事や、次に紹介するような露伴の文を考慮すれば、露伴はこの「一部の教養人」のなかに数えられるべきだと思う。
こういう見方をした文学はまだ無いようだから初めて聞いた人は異様に感ずるかもしれぬが、却って、旧来あまり高く評価されていた不衡平を矯正されて、いわゆる国文学者抔(など)が無上に尊重していた文明史上の真の価がほどよいほどに低下される。
鎌倉室町では、平安朝よりも民衆化され、武家や僧侶の手にも分有され、---徳川期にはじめて文学は国民共有のものとなった。明治大正になってその傾向がさらに強まっている。今後教育の普及によって教育における貧富の受ける便宜の差が減ずるにしたがって完全に国民の性情の投影と言えるようになる。
このように露伴は述べている。
大正15年「支那文学と日本文学との交渉」(全集第18巻)という論文では中国文学が日本の文学に与えた影響を古代から近世に至るまで36ページに渡り詳しく述べている。そこでは、古事記、日本書紀の成立が日本文学史上の画期を成しているが、書紀のほうがより漢文的で支那思想の影響を受けていて、支那的であり、古事記はそれほどではなく、より日本的である、という。「これが日本主義の人には紀より記の方がよろこび迎えられるに至った一原因であるが、当時の人としてはむろん書紀のほうに最高努力を払ったわけである。第一に指を屈して数えるべき国書の巨頭からして支那文学の影響を少なからず蒙っていることは、---まだ日本的なものが成り立たないで、一も二も支那を手本にしていたときのことだから已むを得ないことであった」。
記紀に次いで現われた万葉集は純文学だが、まだ漢字だけで表現していたので、多くの支那の影響を受けている。歌の序などは漢文で書かれている。また歌も音だけ借りて書いたものと、借義によって書いたものなどが混ざっている。シン紳学者(シンは手ヘンに晋(の旧字体)で、刺す、はさむの意味。シン神(シンシン)とは官吏、役人。帯をして笏をさしたから。漢和辞典による。)、留学生などいわゆるハイカラ党の輩は、シナを崇拝し、その影響を甘受したこともあろうし、自然に支那の詩文に刺激され、啓発され、これを模倣したりしたこともあろう。遊仙窟のようなはかない作り物すら相当な影響がある。支那の詩は喜んで受け入れられたのであり、模倣と言うのは少し過酷に過ぎる。
また漢詩の流行を度外視して万葉及び後の歌集を論ずるのはおろかである。奈良朝というのは仏教思想に眼がくらみ、大陸文明に腰を抜かして唐土天竺をあがめ奉ったこと、今の欧米崇拝論者が欧米をあがめるようなものであったのだ。この事情を勘定に入れないで論ずるのは、文学論でも何でも思い遣り無い非難を古人に加えることになる。
このように露伴は古代文学に対する国粋主義的な見方を退け、時代により変化してきた中国の影響を公平に見定める必要を説いている。
「一国の首都」は露伴が29歳の時に書いた最初の本格的な「評論」である(全集第27巻)。教育や警察の問題などもふくめ、首都東京の都市生活全般に関して議論を行っているが、とくに、水道水源、生活排水、塵芥糞尿の処理、道路、公園など庶民の生活にかかわる環境問題を重視した考察が行われ、そして提案がなされている。
例えば当時、公園は上野と芝の二箇所しかなかった。露伴は言う、「公園は都府の肺臓なり」。「腐を転じて鮮となす公園の霊妙なる営作」の都会に対する必要は言うまでもないことだ。「都会は---其の住民を人事の複雑なる組織中に繋定し、その天真の元気を消耗せしめるとともに、他方で「物質的に」空気の混濁甚だしき一団の不自然境を現出して、其の中に生息する人間を疲弊困屈せしむるなり。このときに際して樹木蓊茂して草竹叢生せる閑地の市中に存在するは、一方において物質的の不良の状態を救ひ、他方において精神上の抑うつを癒し、空気の変換代謝をなし、元気の振作回復をなす、その功実に測るべからず」。露伴はまた住宅の共同化と高層化(といっても二階建てにすること)により、家のそばに必ず空き地を作ることなどを提案している。山水を施した広大な武家屋敷で暮らしていた少数の政治家や金持ち階級たちが決して持つことのできなかった視点であろう。
塩谷によれば、鴎外はこの「一国の首都」を雑誌から切り取って表紙をつけて所蔵し「独りわれは露伴の詩人眼の能く大処遠処に徹して、彼カノ都府の中外その屋制を殊にすといふ論を立つること得たるを見て、喜び自ずから禁ずること能わず」と読後感を記しているという(塩谷、上)。また斎藤茂吉は「露伴先生に関する私記」(<現代日本文学大系>4.『幸田露伴集』(筑摩書房、昭和51年。原文は昭和13年)「付録」で、露伴が「道路は東京の難問題なり」として道路改良の必要性を強調している点をとくに評価しつつ、この論文の「内容の博大精緻なること」を称賛している。
私はこの評論に表れている「都府の風気習慣陋劣汚濁なれば、聖賢ならざる以上は個人の風気習慣も高尚なる能はず。之に反して都府若し善美をつくせるものならば、中以下の材〔現代的に言えば一般「庶民」〕といえども個人は幸福を享有すべし」という露伴の言葉を重視したい。
『修省論』(全集第28巻、大正3年)の「無意識の圧迫」と言う文では、人間相互間で圧迫があれば不平、反抗、闘争が生じないことはありえないという。古代インドにおけるカースト制度、源平以前の公卿の支配は武士を圧迫したであろうし、最近までの武士の支配の間は百姓町人は圧迫を受けていた。階級制度による不自然不公平な圧迫は結局闘争によって覆され新しい世界が建立される。自由民権運動も同様の圧迫に対する反抗だ。「およそ人為的の有為的の圧迫に対しては必ずその反動が惹き起こされる。---ただ意識的圧迫は軽減されるに傾いているのが今日の状態である」。
こうして諸種の圧迫が次第に軽減されていく時代になって、「無意識の圧迫」が生じてきた。その圧迫力は日に月に増進し恰も昔の暴君のように、人類の一部を圧迫する傾向が明らかになってきた。文明、器械や技術の発達は利便を生み出すが一面でそれの犠牲者を生み出している」。
ここでは露伴は「圧迫」を生み出しているのは「文明」であり、それが資本家、有力団体に利益をもたらし、無資本家、貧者、微力な個人を、傷つける。貧弱の国家を傷つけ富強の国家を利益しているというのである。だが、「文明」による「無意識の圧迫」と言う説明は不十分に感じられる。
しかし、同じ『修省論』の「生産力及〔び〕生産者」と言う24ページの長い論文では、社会ダーウィニズムと資本主義社会の批判を行っている。現代では「資本を以って王に代わる専制政治が行われている」。今の資本家は昔の王である。違いは剣の代わりに貨幣を用いるだけである。資本の力が法律を作り政治を動かし、政治・法律が資本の力を増長させる。しかし、政治の大道は「以民為本」にある。つまり人間、民をもって本としなければならない、と露伴は言う。
資本のある大国は「科学知識と結合した資本の威力を揮って、世界の土地のいたるところにその資本を植えて、---生産力を発達させ、そして資本がなくて生産者のみの居る貧国弱国を圧迫して、その産業を蹂躙し、その人民を苦境におとし、富める国の文明の華やかなる灯火のための油とし、自己らが美しき室を暖むる暖炉の燃料となすべく経営するが、以資為本〔資本をもって本となす〕の思想から言えば差し支えないのである。
しかし、社会は社会だ。世界は世界の世界だ。資本が何だ。資本と言うものは人が認めてやるからその力があるのだ。認めてやらなければ何の価値もないものだ。われわれは資本に対する思想を根底から新たにすべきときに達している。資本を中心とするか、人間を中心とするか。生産力、すなわち生産するということを大切なこととして考えるべきか、生産者すなわち生産に携わる人間を大切にして考えるべきか。---科学知識は資本と結びついて資本はいよいよ猛威を振るっている。科学知識は後退すべくもなく、人道の実現ははなはだ望みなく、世界はついに大いなる坩堝に入らざるべからざるときに臨んでいる」と言う。大正3年は1914年、(第一次)世界大戦が始まった年である。
黴菌は増殖するときには急速に発展展開するが、ある程度に達すると自己の身体から排出する物質と一族の死屍残骸に囲繞されて、ほかに新しい営生資料を得る途を見いださないときには、衰耗敗滅する。社会における個人とその事業の栄枯もこれに類似することがある。
露伴はいくつかの例を上げた後、この文の末尾で「黴菌的生滅を取るのは、個人にとっても一団の事業にとっても悦ぶべからざることである。戦争に勝利したのはよい。しかし自己が做(な)し出した軍費の継続を余儀なくされて、自己の為し出したことの為に、自己が苦しむなど感心しない。どうしても別に清新の営生資料を得るの活路をば見いださねばならぬ。一個人、一会社、一国の栄枯、その理は別に異なったことはない」(「黴菌の如き消滅」『修省論』)。
この文で露伴は、戦争により獲得した植民地の経営とそのための軍事費の増大に苦しまなければならない点を批判しているのであり、戦争により新しい「営生資料を得る」ために日本が帝国主義的政策を継続すべきこと説いているのでない。この文の次に「根本に対する培養」という題の短い文があり、「国家の経済」におけるその一切の根基となる生産力の根本は「人民」だとされ、それに続いて先に見た「生産力及〔び〕生産者」が来ている。
1917(大正6)年、第一次世界大戦の終戦直後に書いた「戦後思想界の趨勢」(全集25巻)では次のように書いている。
戦争前はどうであったか。各国共通に兵備を拡張し、凶器を猛烈にし、ばかげた軍艦や巨砲を造って、そして「平和は武装によって得られる、対抗的武装は平和を得る所以の道だ」というようなことを言って、鼬ごっこ鼠ごっこという児戯の如き軍備拡張をした。その挙句はどうだったか。曠古未曾有の愚事をあえてしているようになったではないか。
戦争には要求の衝突がある。「脛押し」という我慢比べの遊びがあるが戦争は遊戯ではない。結局自己中心を正当とする思想から起こってくる双方の国民が自己を膨張させるために、相譲らぬとすれば双狗一肉、争闘は起こらざるを得ない。双方が五分の理を主張して、うなり声を立てたり怒り毛を立てたりしている---。戦争は始まってしまい、ばかげた毒ガス弾だの火炎弾だの---この世の阿鼻焦熱の凄まじい惨劇を演じて猶已まぬ。天を測るに揣摩〔シマ、当て推量〕の心の甲斐なきことが明白になった、という。
昭和13年、文部省が出版することにした「教学叢書」に書いてくれるよう役人にしつこく依頼された(塩谷下の二)露伴は「一貫章義」(全集28巻) を書いた 。
論語第四・里仁篇にある「子曰、参乎、吾道一以貫之。曾子曰、唯。」という文で、孔子が一貫して道だと説いたことについての釈義である。老荘、仏教、また同じ儒教の思子、孟子、さらに宋学における道と孔子の道とのちがいを論じた後、露伴は次のように言う。管仲は太公望の治国の法の流れを受けて斉を一振した〔奮い立たせた〕と思われるが、管子(=管仲)は事上の用心が博くて「鹽」を説いたり「物価」を説いたり、「鉱山」を説いたりした。周公は太公よりもより多く文明的道義的礼学的に治民治世の方針を取っていた。その伝統に属する孔子は「軍陣のことなどは知らぬ」というようにみずから言い、経済のことなどは「節度」を重んじ、民力を暴使せぬことを大切とするくらいの大綱的消極的の教えに止まり、管子が行っているような事上の説は論語その他を観ても見当たらない。だからといって孔子の道が事に疎く、「実」から遠いというわけではない。太公や管子は「物」や「力」を先にし、周公や孔子は「礼」と「楽」を先にしたのである。また前者は富強を主とし、後者は文明を主としたのだ、このように露伴は説明している。
昭和13年に、論語に学ぶことを勧めつつ、その孔子が「物」や「力」や「鉱山」や「鹽」(石油と読める)あるいは「軍陣」のことよりも、礼楽を優先していたと説くことは、当時の軍国主義、戦争政策に対するはっきりした批判であったはずだ。
昭和15年正月の読売新聞に載った「愛」という文では、途中に(中略)と言う個所があった。塩谷によると、検閲で発売禁止などにならぬよう、あらかじめ記者が行った処置だという(塩谷、下の2)。
「愛」は全集第25巻にある。仁は広大で、愛は仁の片鱗末枝であるが、人の心のさまざまな働きのうちで、愛がもっとも優美で霊妙で、幽遠なものであることはいうまでもない、と冒頭で語られる。読み進んでも「中略」という個所はない。現在の全集には原文がそのまま載っているのだ。そして塩谷の書いていることと付き合わせると、新聞でカットされたのは次のような文である。
「怖るべくは科学の無忌憚応用で、これも甲国がこれをなせば乙国もなさざる能はざる事情があるから已むを得ざるには相違なかろうが、爆薬、毒薬すべて魔王の庫中にあるべきものが世に投げ出されるの情あいのことである」。(こうした一般論も、自主規制によりカットされてしまう、戦時下のマスコミ統制のすごさに驚かされる。)
そして新聞にもあったと塩谷が書いている次の文が末尾にくる。「ここに指摘する。世界の人々が愛を重んぜねばならぬことに心づく日のすでに近づけることを」。大きな戦争が近づいていることへの彼の懸念と非戦ないし反戦の気持ちが強く感じられる。
同年、婦人公論8月号に「はねつるべ」という短文が載った(全集30)。井戸の水をくみ上げるための装置・はねつるべの構造を説明し、桔槹(ケッコウ)と書くこと、古代中国の詩ではツバメの上がり下がりを頡頏(キッコウ)と表現していることなどを述べた後で、一方が上がれば他方は下がるということが国についてもあてはまるという。「いまや或る国が上がっていくのか或る国は下がっていくのか。20年前は或る国は下がって或る国は上がった。どうもしかたがない。どちらがよい作用をするのだともいえない」と言う。露伴は日本の敗戦を予感していたのではないか。少なくとも日本の戦争勝利を信じ戦争政策を支持する気持ちを述べたものでないことは明らかだ。
また、塩谷によれば、昭和15年、津田左右吉が日本古代の研究で出版社の岩波茂雄とともに不敬罪で起訴された(注)とき、露伴は「津田君のために上申書を作るのだったらおれも加わるから」と言って、第一に署名した、という(塩谷、下の二)。
(注)津田事件:1939年(昭和14年)に早大教授・津田が『日本書紀』に於ける聖徳太子関連記述についてその実在性を含めて批判的に考察したことについて、国士館専門学校教授・蓑田胸喜らが津田を「日本精神東洋文化抹殺論に帰着する悪魔的虚無主義の無比凶悪思想家」として不敬罪にあたるとして攻撃した。政府は、1940年(昭和15年)2月10日に『古事記及び日本書紀の研究』『神代史の研究』『日本上代史研究』『上代日本の社会及思想』の4冊を発売禁止の処分にした[6]。同年1月に文部省の要求で早稲田大学教授も辞職させられた。津田と出版元の岩波茂雄は同年3月に「皇室の尊厳を冒涜した」として出版法(第26条)違反で起訴され、1942年(昭和17年)5月に禁錮3ヶ月、岩波は2ヶ月、ともに執行猶予2年の判決を受けた。Wikipediaによる。
なお、伊藤整(1905-1969)『近代日本の文学史』(夏葉社、2012)によれば、太平洋戦争が始まって半年後の昭和17年5月に、日本文学報国会(注)が組織され、内閣情報局の監督を受けるようになった。無名の作家、あるいは病弱の作家を除き、芸術派たると旧プロレタリア文学派たると私小説派たるとを問わず、文士は全部この組織への加入を強いられ、表面的にしろ戦争協力の態度をとらざるを得なくなった。このときこの組織に加わることを拒否したのは「大菩薩峠」の中里介山、老大家の幸田露伴、獄中の宮本顕治―の妻の宮本百合子などの数名に過ぎなかった。谷崎潤一郎、徳田秋声、永井荷風などの作家の発表は禁圧された。---「中央公論」、「改造」などは廃刊を命ぜられ、編集者たちは弾圧を受け、検挙・投獄された。
露伴は国家の戦争政策とそのための思想統制にはっきりと非協力、不服従の態度を示した数少ない知識人の一人であった。
(注)Wikipediaによれば、日本文学報国会は「国家の要請するところに従って、国策の周知徹底、宣伝普及に挺身し、以て国策の施行実践に協力する」ことを目的とした社団法人として発足した。
幸田露伴に会長就任の打診があったが、「健康上の理由」を口実に辞退した⇒「塩谷(下の2)」。
また、宮本百合子は1943年に会の事業として女性作家作品集の企画(発行はされなかった)において掲載作品を選定しようとして、獄中(未決)の夫、宮本顕治からたしなめられるということなどもあった、といい、伊藤が宮本百合子について書いていることは誤っているかもしれない。
私は井上哲次郎の書いたものを直接に読んだことはなく、彼の国粋主義や日本主義思想については黒住の著書などから間接的にその概略を学び知った過ぎない。しかし、井上の思想についてはともかくとして、露伴は従来の「意識的圧迫」を伴う階級社会にも、また「無意識な圧迫」を伴う資本主義社会にも反対して「政治の大道」は「以民為本」にあると説く平等主義的政治思想の持ち主であったこと、また日本が古くから隣の中国から学んきた歴史的事実を十分に尊重する態度をとっており国粋主義とはまったく対極的な思想を持っていたこと、また反戦/非戦思想の持ち主で日本の軍国主義、植民地主義に反対してきたことは上で示されたと思う。
以上は、井上が学位授与の話を持ってきたことに対して露伴がとった「唯委順する耳」という態度と関連して述べたことである。露伴の仕事/職業と趣味・娯楽(遊び)との関係の問題に戻ろう。
自分がいる新聞社はまあよいところである。しかし、毎日の小説を綴るには苦しいことがある。長くなるのを詰めて書き、短くて済むのを1日分の長さにまで伸ばす、それはまだよいとして毎日毎日やまをつくれといわれるのは不可能に近いことと思う。自分はいつまでも新聞で仕事をしていくことはできないだろう(塩谷、上)と。これは露伴の実感であっただろう。
露伴も、生活していくためには何らかの仕事をして、稼ぐ必要があった。そして彼は最初、自己の天分を生かせる作家という職業を選んだ。デビューしてから明治30年代にかけて彼は小説や随筆など多くの文を書いた。また、そのための「調査・研究」にも力を入れた。しかし、作家としての仕事も、ある程度以上の収入を継続的に得ようとすれば、出版社(書店)あるいは雇主たる新聞社等との関係において、着想が湧いて書きたくなったときに(だけ)書けばよいというような自由で楽な仕事では決してなかった。毎日、何時間か書斎にこもって「頭の疲れる難読の書を読んだ」り、調べものや執筆に集中しなければならず、「職業上の腐気」、精神的ストレスや疲労と倦怠を感じることがしばしばあった。
こうして、露伴は、若いときには小説家としての仕事に打ち込んだが、また多くの趣味を持ち、職業への気力を鼓舞振作するための「手段」として、釣りをはじめとする「身を労して心を逸する」活動を好んで行なっていた。当時の釣りは仕事とははっきり区別された、「職業に対する気力を鼓舞振作」するのに役立つ遊戯・娯楽であった。露伴は、それはあくまで手段としての娯楽に止まるべきで、娯楽に重きをおくようになっては困る、そうなっては「主客の転倒」だと考えていた。
彼の経済状況は時期により異なる。趣味娯楽にもある程度は金を使ったが、浪費的では決してなかった。
明治23年から27年にかけて書かれた露伴の随筆『折々草』(全集第31巻)のなかに「債鬼の手紙」について触れた文がある。(私が債鬼という語に最初に出会ったのは開高健の『オーパ』を呼んでいたときであるが)債鬼とは借金取りのことである。
露伴は明治30年ごろまでは多くの作品を書き、かなりの報酬を受け取っていたはずである。そこで塩谷は「いくら文士が儲からない職業だった時代でも、まずは売れっ子の一人であった露伴がなぜこんなに金が足りないのか。弟成友の学費は露伴が受け持っていたが書画骨董の類には金も使っていないし「自分のためのものは本と酒ぐらい」であり「何の負債によって債鬼の急迫にあうのか」と首をひねっている(塩谷、上)。これを読むと露伴は経済観念の欠けた人だったのかと思いたくなるが、決してそうではない。(塩谷自身も他の個所では、明治20年代は印税率が低かったかのかもしれないと言い、また、原稿を出版社に渡すと出版権が一緒にわたり著者には金が入らなかったことも指摘している。)露伴は少なくとも、結婚して子供ができたころからは、自分の考えに基づいて贅沢をしない堅実な生活を送っていたと私には思われる。
露伴の日記の中には次のような文がある。 明治44年3月14日、堀内文麿(=新泉)が来て、昨今の著述家には「学乏しく才劣るものも多くは営々として利を図り富をなす。---先生のごとく怠け居たまひて貧にして晏如たるは無し」と言う。これに対し「老婆心はなはだ切なるは謝するに余りあり」などと露伴は書いている(「六十日記第二」、全集、第38巻、p68)。
3月21日堀内新泉が知り合いの杉山と話をしたことを露伴に語った。杉山が露伴先生は財豊かと尋ねたのでなんと答えようか困ったが、「長閑(のどか)気にはおはせど余りお楽には無きようなりと」答えたという。「予笑って、君の言もっともなりといふ。」
新泉は、杉山は「幸田氏いま少し山気あらば好からむを、憾むべし経済に疎し」と言った、と言う。「予聊か懌〔よろこ〕ばず。山気なしといへども水気あるあり、一竿万事足るのみ、と云へば、新泉呆れて少時語を絶したり。余曰く、君余をもて強ひて豪語すと勿れ、予また児あり、自ら快くすればすなわち足るとなすものならず、されど営々汲々たるは予の能くするところにあらず、今の欲するところ一書斎を得んとするよりほかは持竿の楽を取らんとするのみ、飲を嗜むも紅灯緑酒の郷には遊ばず、潔癖あれども精饌美衣〔精饌=精選〕を好むにもあらず、自らおもふに是の如くして年を経ば、おのづから今の苦境を脱して悠々たるを得ることを今に倍シせんとすと〔シはクサカンムリに徙(移る、移す)、倍シとは数倍になること〕。新泉黙して然りとす。--雑談猶多し」(同書 )。
前年43年4月には妻の幾美子を無くしている。同年7月12日の「六十日記第一」には次のように書いている。夕食の副食づくりは自分がやった。婢(女中)はいるものの年が若くて気が利かず、風呂を沸かすのにかかりっきりになっている。「---よろづいぶせく〔気がかりで〕物悲し。夕ぐれ蚊やりを為さざりければ蚊声かしましく、室の内取り乱されて時計は止まり火は消え居り、仏灯を点ぜんとすれば油なく、子らはただ訳もなく騒ぎ遊ぶなど、暮近き頃いささか吾が事〔仕事〕に耽りてそれぞれの指図を怠り居たりし為よろず埒無くなりたる、浅ましく口惜しかりき」(同書)。仕事をしながら子供3人の世話をするのに苦労している。44年1月30日の「六十日記第二」の書き出しには「今年は年の初めの二日より家に病者を出し、さらぬだに妻無き身の内外に手足をわずらはし、心を使ふこと多きに---昼夜に身疲れ心萎えて、日記をものする余力だに無くて今日に及べり」とある。
「紅灯緑酒」とは座敷に上がり芸者などを相手に酒を飲むことである。日々かなりのストレスがあったはずだが、彼は気分を晴らすために街へでて遊ぶということはしなかった。また彼は着る物にも金をかけなかったし、前に見たが、彼はふだん「車」(人力車)に乗らず節約し、見栄を張らないでいると書いていた。こうして、彼は浪費、贅沢をしなかった。だが、自分が足りていればよいと考えてその倹約生活を子供にも強いるということはなかった。子どもに対する配慮を忘れてはいなかった。
そして「水気はあるが山気はない」。経済的に困らない程度に「悠々たる」生活を続けられればよいと考えている。彼は著述業でもうけようとはしていない。釣りが楽しめて、読書に耽るための書斎があればそれで十分と言っている。後に『努力論』が売れて家を建て直すことになったときに彼は書斎を設けた。本が売れたときにはかなりまとまったお金が手に入ったようだ。
大正末年ごろには、発病した息子の一郎の治療費用意のために頼まれた原稿をせっせと書き、また揮毫をしたりして稼いだ。書画屋から受け取った揮毫料は高くはなかったが、それでも露伴は「まとまった金を懐にすることができた」(塩谷、下)。
しかし、大正5年、50歳のとき、釣りをしている写真を撮らせてほしいとある記者に頼まれたが、「おあしがなくて好きな釣りができないのを残念に思っているところへ、写真を撮るから釣りに出てくれといったって出られるものですか」と言い、「ことしは---周囲に病人があったりしてどこへも旅行できず、それにポケットの欠乏で掛けで買った3円の本を読んでるほかに能がなかったのです。いつも五月の半ばから釣りに出かけ、いまごろは二尺に垂(なんな)んとするような鱸を100尾ばかり釣っている頃です。今年はまだわずか10尾しか釣っていませんよ」と答えたという(同)。短期間ではあれ、収入が十分でないときには好きな釣りに行くのも控えた。
彼は、時々旅行をしたり、持ち舟で船頭付きの多少贅沢な釣りを楽しむことができる程度の稼ぎは十分にあった。しかし、彼は、たとえば、金にまったく不自由しない大店の隠居というような身分ではなく、かなり恵まれた報酬を得ることはできたかもしれないが、仕事をして稼ぐ必要があった。彼は様々な趣味娯楽を楽しむ余裕はあったが、そのためには働かざるを得なかった。
また彼は、弟子になりたいと言ってきた者をしばしば家族同様に同居させていたから「生活費」もそれなりにかかり、そのため妻の幾美子が家計のやりくりに苦心していたと(同居人の一人でもあった)塩谷は書いている(塩谷、中)。彼は弟子の面倒を見ることも含めて生計を立てるために、また趣味娯楽の出費のためにも、仕事をし、稼ぐ必要はあった。
かれは経済観念がなかったわけでもないし、金遣いが荒かったわけでもない。浪費したり派手な生活をしたりしなかっただけでなく、節約を心がけていた。そして趣味や子供の養育や弟子の面倒を見ることなど、必要を満たす程度には、彼は十分に仕事を行なって稼ぎ、臨時の支出がかさんだ時には釣りを一時的に控えたりもした。
彼は仕事に困ることはなかった。デビュー時以外、露伴の方から原稿を持ち込んで雑誌その他に掲載を依頼し、原稿料を稼ごうとする必要は全くなかったと思われる。中年以降の露伴は昔の文人たちが残した作品を好んで読み、評釈を加えた。するとその評釈は出版された。彼は興味を持った歴史上の人物について伝記を書いた。するとそれは出版された。釣りをしたり、旅行をしたりした際に日記や手帳に書き留めておいたものは、後に少し手を加えると随筆として、新聞や雑誌に掲載された。彼が書いたものはすべて「売れた」。
むしろ彼は雑誌社や新聞社などからの執筆依頼をしばしば断って、自分の自由な時間、書を読み、そのほかの、つまり読書以外の趣味を楽しむ時間を確保する必要があっただろう。「日記」を見ると雑誌社、あるいは出版社の人がかわるがわるやってきて露伴の「文を求め」ている。明治/大正/昭和にかけて、彼の書く文を読みたいと思う多くの人がいた。一言で言えば彼の博学と文筆の才が、社会に彼を放って置くことを許さなかったということになろう。
露伴はこうして、生活の心配はほとんどすることもなく、ごく短期間、釣りを我慢したことを除けば、自分の趣味を十分に楽しみつつ、自由に生きた。
彼が小説を書いていたときには、読者との関係で書き方に工夫が要求され、また締め切りなどがあり、仕事においては強制が働いた。だが、「小説の筆を折って」以降それがなくなった。史伝や評論や随筆など多方面に渡る著作活動を行うようになり、彼は自分の好むテーマ、好む分野で、自由に仕事をした。東洋史学の専門家を瞠目させた13)「釣車考」や、「太公望」、「漁夫詞の作者」などの論文は、露伴自身の趣味・娯楽である釣りの延長として生まれたものである。
また、「遊仙窟」のような高い評価を受けた専門的学問的な論文を始めとする和漢の文学史に関する諸著作も、彼の読書好きの結果であり、彼は職業として学問を行う大学の学者・研究者たちのように仕事として「研究」を行ったのではない。
大正15年、「日本文学講座」が連続刊行され、露伴は「支那文学と日本文学の交渉」などを書いたが、塩谷によると、露伴はこの講座に「日本文学研究の動機」と言う「問題」に答える一文を寄せ、「研究などと言うのは今日の流儀で、しかじかの理由これこれの動機があってではなくつまり好きだったからで、研究と言われては恐縮のようなものだと述べている」(塩谷、昭和50年版『幸田露伴』中)という。またすでに見たが、彼は社会的に高い尊敬を受けていたと思われる「帝大教授」のような職業であっても、やってみて面白いと思わなければ途中でも放棄した。自分の興味の赴くままに自由に行なうことができる仕事を彼は行なった。
このように中年以降の露伴においては、職業と趣味娯楽の区別はなくなり、趣味の延長と思われる(が他方で、社会的にあるいは学問的に十分な評価も受けた)活動を自由に展開するようになった。
私はこの第3章で、「遊びとは何か」を考えるために、遊びについて書かれた「古典」ともいうべきホイジンハの『ホモ・ルーデンス』を読むことから始めた。そして露伴の後ではカイヨワの『遊びと人間』を読む積りである。露伴についても「游漁の説」を読んだのは、釣りという「遊戯娯楽」は職業/仕事との関係においていかなるものだと彼が考えているかを知るためであった。
ところが釣りに関係のある彼の他の著作を読んでいるうちに、「游漁の説」で与えられている遊戯娯楽の従属的な位置は実際の露伴の生(人生・生活)においてそれが占めている位置と違っていることを発見した。少なくとも中年以降の彼の生においては遊戯娯楽は決して従属的なものでなく、一般に仕事あるいは職業と呼ばれる他の様々な活動と同等の活動と見なされているということに気がついた。
こうして私は、釣りという遊びを一部として含む彼の生(人生、生活)の全体を理解したいと思い始め、釣りに関係のある著作だけでなく、彼の膨大な著作のほんの一部でしかないが、泥縄式に、評論など他の諸著作や日記、手紙なども読むことになった。
山本は田辺に反論する。「雑学とは、人生に相関わらない地点で、趣味的に、無目的に知識を蒐集することで、それに反して、露伴の知識には、根底に生きるための意志が横たわっている」。「露伴にあっては、学問と言っても単にブッキッシュ〔机上の、あるいは研究室と試験管から生み出される知〕ではなく、人間の生きていく実践の領域から引き出された知識を含んでいる」。<山本健 吉全集>第11巻
そして露伴の学問が生活における実践的な知と結びついたものであり、「生きるための意志と結びついている」のは、幸田家が「有識・故実をはじめあらゆる礼儀・作法・遊芸・実務等に通暁していることが求められた」徳川幕府の表坊主衆であったことに淵源し、露伴が子供のころに、祖母から掃除、洗濯、米磨ぎ、火焚きの仕方など生活全般に関する事柄についてのきびしい訓育を受けたことと関係がある。「露伴の学問は行住坐臥に必要なあらゆる知識---を包含する」が、その根底にあるのは「生きるうえに必要な世事万般についての心得、---生活の知恵」であるという。
他方で、近代的な学問及び近代社会における日常的な知のありようについて山本は次のように言う。「今日の細かく分化した知識のそれぞれの一角を分担している専門家たちの学問においては」「自分の専門とする領域についての精密きわまる知識が、それ以外の人生の諸知識の広大な分野に対する無知によって、贖われている」。また「すでに社会の所有となった智識や技術に対して、個人としてはそれを獲得しないでも済ませていられる部分が途方もなく増大した。そのことに反比例して各個人の知識と能力はますます部分的となり断片的となってきた。そのことは自分の生活条件について、言い換えれば人生全般についての知恵がますます喪失され、矮小化してきたことを物語る。---われわれは言い換えれば相対的に愚昧になっている」。
学問の世界でも、「知識の細分化と共に知識に漂う人間味は急速に希薄化していく。露伴にあっては学問は人間の生活していくうえでの知恵の総体と関わっていた」。
山本は、露伴の学問は「人間の生きかたに関する万般を、社会の処世術に至るまでを含む。それは一方で卑近な生活上の知識を含むとともに、他方徂徠の言う歴史に行き着かざるを得ない」と言い、明治的な学問は「もっと人間味のある仕事であり、生活知につながったものであり、学者の人格に深くかかわったものであり、そのようなものとして全体的、総合的な知識、学問であった---。そのような総合的な知識の中核として歴史がある」と言う。そして「見聞広く、事実に行きわたり候を、学問と申事に候故、学問は歴史に極まり候事に候」という徂徠の言葉を何度も引用する。
黒住真『近世日本社会と儒教』からの孫引きになるが、徂徠は「学はただ博を貴ぶ、古今を通会せんこと、博学に非ずんば能わず」。「智見を広め候為、博学(ひろくまなび)候事肝要に候」と言っている。
実際和漢文学を中心にした露伴の「博学洽覧」は、徂徠が学問を行う者に求めた「歴史」を中核とする「博学」と一致するように思われる。露伴は小説を書くことをやめ、徂徠のような儒学者あるいは漢学者になろうとしたのだろうか。
「純理の思索に沈めば、理路深遠にしてヨウ焉として暗きに入るなり」。〔ヨウは穴カンムリに目、暗いの意味。ヨウ焉は奥深いの意味。〕刻苦して夜も寝ずに、自分の頭を絞り、解決しようと望む者もある。だが孔子は何も食べず、夜も寝ないで「思った」が、無益であった。「学ぶに如かざるなり」と言っている。凡庸なわれわれにあってはなおさらである。重要なことは先人に学ぶことだと言い、孔子の思ひて学ばざれば殆しという言葉について説明しながら、「一技の微といえども学ばざれば能(よく)せず。---まして---大道を知り至善に達せんとするに、---学ばずしてそもそも何となるべき」。孔夫子でさえ官職のこと、琴、礼、楽について先人を訪ね学んだ。
そして、当時の人々も「大いなる哉孔子や、博く学びて名を成すところなし」と、孔子が一つの分野で「名を成す」ことをせず、「博く道芸を学」んだことを褒め称えている。弟子の子貢は、孔子は「苟(いやしく)も識るところある者に遭えばすなはち就きて学び、なにがしという一人を師として学び足れりとはし玉わず」と言っている。
とくに弟子たちが伝えていることのなかでも、「博学篤志、切問近思」の二句が孔子の学風を余すところ無く明らかにしている、と露伴は言う。そして、この句について、難しい語を用いて露伴は一字一字説明するが、要するに、「博学篤志」とは偏らずに広く、しかも表面的でなく深く掘り下げて捉えることだと説明し、切問とは要点を鋭く正確にとらえることであるという。そして「近」の一字に「その学問記志するところのことを、文字上、儀形上、記誦の事、知識の事と、遠く身外に置き去ることなく、直ちに心裏に溶かし取り来たりて、体現身行せんとするの意の誠なるを知るべし」という。学問は「文字上」の事、単なる「知識の事」ではなく、学んだことは「体現身行」する、つまり自己の生き方と結び付け、実践されるべきだという。
学んだことを「文字上、儀形上、記誦の事、知識の事と、遠く身外に置き去る」ことと、山本の言う雑学の定義「人生に相関わらない地点で、趣味的に、無目的に知識を蒐集すること」とはほぼ同じことを指すように思われる。したがって、学んで「文字上、---知識の事と、遠く身外に置く」なら、それは雑学だということになろう。上の「博学篤志、切問近思」についての説明が孔子の学について言われているだけでなく、露伴自身の学問姿勢をも表しているとするならば―そして私はそうだと考えるが―露伴の学問は、山本の言う通り、雑学ではなかったことになろう。 露伴は徂徠と同様に博学であろうと努めた。そしてその博学は「切問近思」の姿勢によって、つまり知識を自己自身の生き方にかかわる主観的/主体的問題関心と結び付けて捉えるという姿勢によって支えられていた。
山本が露伴の学問の根底には「生きる意志」があったと言っていることと、「知識を自己の主観的問題関心とと結び付けて捉えるという姿勢」とは一面においては重なっている。そしてこの姿勢が、中年以降の露伴の活動が「学究的」あるいは「学問的な」ものであったにせよ、彼が明治の国家によって制度化されつつあった学問の担い手としての学者となることに、つまり先輩帝国大学教授たちにより審査される「博士号」の取得や、客観的・普遍的な知識を帝国大学で教授することに消極的であったことに表れている。かれは広い分野にわたる様々な知的芸術的探求・研究を行ったが、それは近代国家の制度的バックアップを受けつつ営まれる職業としての学問研究とは明らかに異なる。
職業として行われる近代的学問研究の場合には、ウェーバーが言っているように「学問上の仕事を完成したという誇りは、一人自己の専門に閉じこもることによってのみ得られる。--凡そ、隣接領域の縄張りを侵すような仕事には一種の諦めが必要である」(尾高邦雄訳『職業としての学問』(原著は1919、岩波文庫、1936)。研究は特定の専門分野の中でのみなされる。しかし露伴の博学は多くの分野を越境することによって達せられたものである。露伴の学問は、ウェーバーのいうことが正しいとすれば、職業としての学問ではないことを示していると考えられる。
また、職業的な学問研究においては、研究者は、クーンがいうパラダイムに従った「通常科学」のような研究だけを行うのではないにせよ、研究課題は大枠においてそれまでに到達されている研究地平によって客観的に限定されており、研究者はその中から自己の課題を見つけるのである。確かに研究者はその分野の研究が好きだから研究するのだし、また個別の課題を設定する際にも彼の主観的関心がそれに関与する。しかし、それはあくまでも客観的に既に存在しているその分野の研究地平を前提にしている。だが、露伴は、趣味で行った膨大な読書の中で自分が興味を感じたことなら、分野あるいは領域に関係なく、何でも自由に研究した。そして、民俗学などがまだ存在しなかった当時において「学問」の対象とみなされていなかったはずの、釣り道具や将棋の歴史などについて、彼の趣味に基づく主観的で個人的な関心に基づいて、調査や研究を行った。
露伴が旅行好きであったことも彼の知的好奇心と関係づけられるかもしれない。彼は20歳のころ北海道で電信技士として勤めていたが、途中で勝手に仕事を辞め、上京する。赴任の際は横浜から汽船で来たが、帰りは「船で直行するのは金が少し足りないし興も少ない」からと青森まで出た後、歩いたり、馬車や人力車に乗ったり、汽車に乗ったりし、時には野宿もして、1か月以上かけて、東京に戻った。塩谷は露伴という号のもととなった「里遠しいざ露と寝ん草枕」という俳句はこの旅の途中で、もしくは帰京後追懐して作られたものだと言っている(同書)。
21歳で書いた最初の小説『露団々』が売れて金が手に入ると、長野、名古屋を経て京大阪へと汽車に乗ったり、歩いたり、馬に乗ったりして旅をし、四日市から汽船に乗って横浜に帰るまで、1ヶ月にわたって旅行をし、金はすべて使い果たした(同書)。 翌23年には饗庭篁村などほかの3人とともに京阪への旅に出たが、露伴はさらに足を延ばし、四国(琴平)、広島、九州(博多、熊本、鹿児島)を回って1ヶ月あまりの旅行をした(同書)。
これらの旅行は単に金を費消し物見遊山を行うためにおこなわれたのではなく、東京育ちの露伴が自分の知らなかった地方の自然と人々の生活を目で見、知ろうとする知的な好奇心が行わせた行動だったと私は思う。もちろん旅行中に彼が観察した田舎の人々の生活や風景などは、例えば「遊行雑記」(明治30年、全集第29巻)のような紀行文や小説の中で生かされている。
露伴は思想や学問の領域においてだけでなく、東京以外の日本各地を時間をかけて旅をして回るという形でも、その自由で旺盛な知的好奇心を発揮した。釣りや将棋、銃猟、写真や自転車などの趣味も「知的好奇心」によって動機づけられている面が大きい。(とくに後の三つはいずれも当時においてまったく「新奇」なものだった)。こうした彼の行動は、子供の時に生活に必要な日常的知識を身に着けるよう祖母から訓練を受けたということによってではなく、露伴の天性の多面的な知的好奇心によって説明するほうが適切だと私には思われる。
また、山本は、露伴の「博識」、あるいは「博学洽覧」の中に、「遊仙窟」のようないわゆる学術的な研究や知識とともに、中国古代に使われた釣車や太公望という人物や江戸時代の将棋や棋士等々に関する雑学的な知識も含めるであろう。だが、私は、そうした露伴の博識、あるいは博学洽覧の根底に「生活の知恵」を支えている「生きるための意志」が存在する、と考えることにも抵抗を感じる。露伴の古今にわたる和漢の深くかつ博い学識は日常生活の中で習得されたり実際に用いられたりするものではなく、やはり古今の書を読破することによってはじめて獲得されたものであろう。そうした博学は「生きるうえに必要な世事万般についての心得、---生活の知恵 」との間には距離がありすぎると思われる。
そして、「趣味娯楽」の延長あるいはその一部として探求され獲得された知識も、それは遊びの領域に属するものとして、普通の意味での「生活の知恵」とは異なる種類の知識だと考えられる。実際、露伴においても、小説家であった30才代までは、釣りもそれに関する「詮議」(知識)も趣味・娯楽として、生きるために必要な職業とは対立するもの、「本来の職業を鼓舞振作する」のに役立つべき手段とされていた。彼は職業/仕事が主で趣味娯楽は従(客)であるとし、主客の転倒を戒める文を書いていた。一般に、趣味娯楽は、もちろん社会や時代と無関係ではないが、職業的活動/仕事とは異なり、社会的評価、他者との関係に左右されず、自分の好みだけで取捨選択し決定できる。だが、仕事を行おうとすれば他者によって定められた基準をクリアーしなければならない。「若い露伴は小説家としては成功したが、棋士を職業にしたいと考えたとしても不成功に終わったであろう」と有意味に語りうる。
「雑学とは、人生に相関わらない地点で、趣味的に、無目的に知識を蒐集すること」と山本は定義するが、では、知識が目指す「目的」とは何か。炊事、洗濯など日常生活に必要な、日常生活の中で習得される実用的・技術的な知識が一方にある。それらにおいては知識自体が重要なのではなく、それによって実現され達成される目的・結果が重要である。ひとはそれら知識とそれによって得られる結果のどちらか一方を選ぶとすれば、後者を選択することは間違いない。夫婦共働きの生活を送るなら、コインランドリーを利用し、外食あるいはデパ地下での買い物を選ぶことができる。手段としての知識は目的である結果に比べ低い価値しか持たない。
大学や研究機関において、物理化学や医学など科学技術的知が方法的、目的意識的に探求されているが、それらも直接間接に生活・生存にかかわりを持ち、日常の生活知と同様に生活に役立つ知識で「目的」を持つ知識である。
他方、露伴は遊び・趣味にかかわる歴史上の事物や人物についての「考証」や文学や芸術の歴史についての十分に「学問的な」考察を行ったが、彼はその活動が楽しいから行ったのであり、そこから得られる知識は非実用的な知識である。それら知識にはそれらが手段として役立つべき「目的」なるものは存在しない。つまりそれらは「趣味的に無目的に」蒐集されたものある。したがって、露伴の博学の多くは、それが彼の「生き方」と結びついていたという点を別とすれば、山本の定義に従う限り、単なる「雑学」的知識であることになる。
だが、私は生活の便利や豊かさを限りなく追求したいとは思わず、遊びと知的/精神的快楽をできるだけ多く享受したいと思う。「雑学」的学問、「趣味的で無目的」な知的活動は、専門的な知識を身につけ社会的に貢献すること(を楽しみかつ生活・生存を確保すること)、および炊事洗濯など日常生活にかかわる知恵と処世術を身につけることに、少しも劣らず重要なことだ、と思う。わたしは、露伴の学問、あるいは彼の知的活動の全体を雑学であると呼ぶことに反論したいとはまったく思わない。
露伴は、職業作家であった若い時にも、また多様な「学究的」活動を行った中年以降の生においても、一方で生活に必要な家事や職業としての活動を行い、他方で、趣味を楽しみ、釣りをしたり将棋を指したりした。この両方が露伴の生だとすれば、露伴の「博学」や博士号を受けるにふさわしいと判断された「遊仙窟」に関する論文も、また趣味の延長上に書かれた「太公望」や「将棋雑話」その他の文も、露伴の自由で旺盛な知的好奇心に基づく活動、すなわち露伴の「生」が生み出したものである。
「生きる」という語が衣食住の必要にかかわる日常生活ばかりでなく、趣味娯楽・遊び、知的活動、学問など「人間の生」におけるすべての活動を含むと考えることが必要だと思われる。山本が「生きる意志」と言うとき、遊ぶこと、趣味や娯楽を楽しむことを「生きる」ことの中には入れていないと断言はできないが、遊びや趣味娯楽を積極的に「生」の一部だと考えているようにも感じられない。山本は釣りや将棋に関して露伴がいろいろ調べることは「歴史研究」であり学問であると考えている。その学問の「根底」に生活の知恵を求める「生きる意志」があるというのである。私は、釣りや将棋についていろいろ調べること、「詮議」し「論弁思索」することは、彼自身が言うように趣味・娯楽の一部なのだと考える。そして、趣味や遊びもまたその人の「生」であると積極的に主張したいのである。
また山本は祖母から伝えられたことのなかに、どんな些事においても、いささかの「未熟」も「背理」もゆるさない姿勢があったといい、それが「格物致知」の儒の思想に通じているという。そして「露伴の歴史研究の中には、釣りとか将棋とか、趣味的方面においても、彼の徹底的に知り尽くそうとする態度は同じように発揮され」ている、という。
塩谷も露伴の学問と彼の生との実践的結びつきを認めている。露伴の家の古い井戸の水が減り井戸掘り職人が新しく井戸を掘ったがポンプの水が上がってこなかったときに、露伴は職人任せにしておかず、自分でポンプを動かし、水が上がってこない原因を詳しく調べ、自分の考えた通りのやり方でポンプを修理させた 。露伴は、夜中にも「しつこく考えに考えを極めた」。塩谷は「露伴が身を以ておこなった格物致知の教えとはまさにこれである」という。ただし彼は「こういう点では露伴は江戸っ子のさっぱりした気象とは異なるものを持っている」と付け加えている(塩谷、中)。
「徹底的に知り尽くそうとする態度は」、山本が幸田家の伝統に由来するという「処世術・生活上の知恵」とは一致しないと思われる。「処世術・生活上の知恵」は「拙速」、「効率」を求めるものでもある。生活上の知恵に従うなら、「格物致知」に徹するよりも、例えば、ポンプの代わりに釣瓶式にするとか、あるいは滑車を使ってくみ上げる方法に変えるとか、他の手っ取り早い方法を選ぶのではないか。「江戸っ子のさっぱりした気象」のほうが「処世」、「生活」には向いている。幸田家の伝統があったにしても、それが露伴の「格物致知」的な「知り尽くそうとする態度」を形成したとは言えない。
山本は露伴が漢学塾に通っていた時期に師の言いつけに反して「諸子百家を読破」しようとした点に露伴の「天性の自由」を見る。だが「一事に捉われないで、---諸子百家の学をも読破しようとかかっていたのだから、その自由さは天性と言ってもよかった。程朱の学を学びながら、それを否定するような思想も、同時に胸のうちに収めておこうとする。それは自由と言うより、あらゆるものを包摂する、茫洋とした露伴の学問の性質を示している」と歯切れが悪い。漢学を学んだにもかかわらず、漢学者になる道を選ばず小説家になったということも含め、若き露伴の「天性の自由」を認めるべきである。そして、同時に、趣味における「知り尽くそうとする」態度も、幸田家の伝統にその原因を求めるのではなく、露伴の「天性の自由」に基づくとみるべきである。
塩谷は、明治43年、露伴が為政編と八イツ編の注釈を受け持った『論語』(書名は『新論語』)が出たことにふれながら、次のように述べている。〔イツは一を意味する語で、文字は人偏に八+月である。〕「為政編のうち、君子不器〔君子の働きは物を入れる器のように限定されず、その徳はあらゆる場合に行われる〕の章に註して、〔露伴は〕、君子は万能を具する人であり小人は一二の能を抱くものであると説明している。それは正しいと私は思う。顧みると註者自身もまた君子の能を持つ人なのである。国漢の学は自分の本職だが必要があれば英文の書にも及び、趣味としては銃猟・写真・釣漁・将棋〔そして自転車〕を好み、能くするところは書道・数学・科学・経師〔もとは経書を教える人、のちに表具師。襖張りなどもやったというのだろう〕・掃除にわたっている。ただ文を書いて売るというだけのひとではない」(塩谷、中)。
露伴は「生」におけるきわめて多くのことに興味、関心を持ち、熱心に行った。生活に必要なこともおこなったし、趣味の活動も行ったし、超一級ともいうべき学問的な仕事もした。塩谷は露伴を、博学洽覧の学者であっただけでなく、「君子」であり、万能の人であり、何でも屋であったといっている。世の中に何でも屋と呼ぶべき人はままみられるが、露伴のように、学問においては格別としても、何事においてもすぐれた力を発揮できる人は多くいない。ゆえに君子だと塩谷は呼ぶのだろう。
昭和13年1月の新聞に「象戯余談」が載った。象戯は将棋であり、平安朝期にも将棋が行なわれていたことなどについての考証である。すでに露伴は、三十数年前に「将棋雑考」、「将棋雑話」を書いている。そのときに分からなかったがその後わかったことをこの「象戯余談」で書いている。
塩谷は付け加えて言う、「将棋は要するに遊戯である。将棋の勝敗は世界に一毫イチゴウの利益損失をも与えない。---遊戯である以上その歴史に重要な発見を加えても一の得るところはない。だからといって源を探る上の重要な発見が他の有益なものより容易に出来ると言うことはないのである。露伴にしても実に三十余年を経ている。そうするとそういう努力をするのはよほどのへそ曲がりか、しからずんば報いを求めないもっとも高級な趣味とすべきかも知れない」 (昭和50年版『幸田露伴』下、文庫版下の二)。
おそらく露伴は「努力」したということは否定するだろう。「へそ曲がり」という語には流行に左右されず権威に阿ねないという肯定的ニュアンスが感じられるので賛成する。要するに露伴は他の人々の意見や評価に左右されずに、自由に、自分が興味を感じたことを好きなように行い、或るものは途中でやめたが、或るものは何十年にわたりそれを掘り下げつつやり続けた、ただそれだけだ。
また、塩谷によると露伴は大正6年秋に「菊の賦」という文を書いた。また昭和14年1月に「餅の賦」という文が新聞に載った。〔「菊の賦」、「餅の賦」は「牛の讃」、「虎の讃」、などとともに、全集第32巻p575~665の「讃」と題された箇所に収められている。2017.3.7追加〕
塩谷が「自分は一生に一度だけでもいいからこの賦ぐらいなものが書けたら死んでも悔いないと言うと、「ああいうものは人が思うよりずっと時間がかかって損なものさ」と露伴が答えた」と書き、また、「これを作するのは露伴の後は荷風あるのみで荷風亡き後は絶えたように思われる。これに類するものを作る人もあるが平仄がはずれて14)見苦しいのもある。少ない枚数を多くの学問と芸術心と時間とを要して書き上げるこのようなものは、文を鬻ぐにはなすべくもなく、理想的に言えば、学と才と天下を蔽い後顧の憂いなく作文をあくまで趣味とする人でなくては近づかないほうが得であろう。---目に文字ある人は相ともに楽しもうではないか」と書いている(同書)。せんじ詰めて、私なりに言い換えて、要約すると、露伴は時間をかけて美しい文を書いたが、彼はたとえ売れなくても書いたであろう。それは彼にとって文を書くことが趣味であったからだ。
晩年の露伴

露伴は「業務と趣味」(大正3年、全集・別巻上)という文で次のように書いている。世人は業務については責任を持っているという感じに支配されており、ある圧迫を受けているという感じを抱いている。苦痛をも負うている。「業務であるがゆえに之に従事せねばならぬというような心理状態を持っている。---まず百人の九十五人は、役人〔も〕---商人〔も〕---、学者〔も〕---店員や労働者〔も〕、その仕事や労務が少しでも早く完了することを願っている。他方で趣味において、多くの人は、自己の愉快と真の生命を見いだしている。趣味については何の責任も圧迫も苦痛も感じていない。趣味は最大の自由の存在している最大快楽の園だと感じている」。
「だが、業務は全く責任であろうか---ちょっと考えどころがあるではないか」。「権利と責任とは一枚の紙の表裏である。業務は責任でもあろうが、しかし、見方によってはまた権利でもある。古よりの卓絶した政治家、軍人、学者、芸術家等を観察すると多くは、自己のなすことを自己の権利としてなしている。責任としていやいやながら従事しているのではない。---責任を感ずるなどと言うそういう消極的な、卑怯的な、退却姿勢をとっているようなものではない。皆活発の精神と清新の意気とをもってことに当たっている」。
「自己の業務に趣味を感ずるということが吾人の脳中にもっとも必要な一条件ではないのか。若し、自己の業務に趣味を感じたならば、自ずからにして自己の業務に清新の意気と活発なる精神をもって従事することは容易なことである」という。
露伴は業務を趣味とみなして従事することが簡単にできるかのように言っているが、私は賛成しない。中年以降の露伴が従事しているのはもはや業務ではないからである。この文で確かめておく必要がある。政治家や軍人はその地位・身分に応じてなすべきことあるいは権限の範囲が大まかに決まっている。そして学者なら自分の専門分野において自分のやりたい研究を行なう。「店員」や「労働者」はほとんど決まっているやらねばならないことを「なす」のである。いずれにしても職業であり給料をもらいながら権限を行使しつつ行なうこと、おこなわねばならないことが業務である。新聞社に籍を置き連載小説を書く職業作家であったときの露伴にとっては、小説の執筆は確かに「業務」であっただろう。また、京大に奉職していた1年の間は、学生に講義をすることは確かに「業務」であっただろう。
この文が明治30年くらいまでに書かれたものであれば、売れっ子の職業作家として仕事/業務に追われている自分を励ますことがこの文を書く動機になっていると考えることも出来る。そのころの露伴は、小説を書くことに趣味を見出し小説家になったにもかかわらず、義務と責任、圧迫の感じに支配され、「職業上の腐気を排去する必要」を感じていたはずである。
しかし、この文を書いた当時の露伴はこの意味での業務を行なう人ではない。彼は明治40年ごろには、「小説家としての筆を折り」、自分の自由な関心の赴くままに、和漢の詩文を渉猟し、考証を行い、史伝や評論を書き、そして趣味娯楽の延長である論考、随筆を書いた。これらの仕事は行わねばならぬ、行う責任のある、普通の意味での「業務」では決してない。露伴は後半生においては、退職したサラリーマン同様、「業務」を持っていないと考えるべきだ。
彼は小説を書くときには、調査・研究を徹底的に行った。たとえば、完成しないで終わった小説「八幡船」を書こうとしたときに作った海や船に関する語を集めた「水上語彙」(全集第40巻)は独立の著作として発表されたが、柳田国男が注目したほどの民俗学的意義のある仕事であった(塩谷、上)。
だが、『幻談』を書くためには何の調査研究も必要としなかった。彼は頼み込んできた編集者を前に座らせ(その脇に速記者がいる)、その編集者に向かって「胸の中で話を塩梅しながら言葉を一々吟味して話す」というやりかたで、2日間でこの小説を仕上げた(塩谷、下)。頭の中にある江戸時代の社会と人々、釣り道具などに関する知識を用いて、ストーリ組み立てつつ、「口演」したのだ。「形は同じでも講釈師が語るように記憶をそのまま口にのぼせているのではない。---ときどき話すのをやめると目を閉じて考えることもあったに違いない」と、露伴と編集者の二人から聞いた話をもとに、塩谷は書いている。書店の後の広告には露伴が「小説をしゃべった」と書かれていたという(塩谷、下の二)。
この小説は彼の趣味娯楽であった釣りの経験と知識が総合された作品であり、編集者に頼まれて「しゃべった」のだから仕事/業務であったことは確かだが、その2日間は、彼が若いときに「一室に閉じこもり、頭脳を絞って」書いていたときのように、彼の中に「排去」しなければならないと感じる「腐気」がたまったとは思われない。彼は当時はもう小説家とは認められていなかった。世間は露伴が再び小説を書いたと驚いたという。書かねばならないという責任感や圧迫感はなかったはずである。このときの彼は職業小説家として小説を書いたのではなく、彼の頭の中で浮かび自ずと口から出たものを、たまたま近くにいた人が聞き取り、書き留めたのだといってもいい。彼は「話を塩梅し、言葉を吟味した」であろうが、船の上でのんびりと鱸の当たりを待ちながら詩を作って楽しんだのと同様に「心神の怡悦イエツ」や「自己の愉快と真の生命」を感じながら「しゃべった」と思われる。
こうして『幻談』は露伴の様々な趣味・遊びの活動の典型的な産物である。しかし、『幻談』だけが露伴の遊びの成果なのではない。「太公望」、「漁夫詞の作者」、「釣車考」などの著作は学問的に重要な意義をもつ仕事である。だが、それらの仕事も、大学などに勤める専門家の普通の意味での研究業務として、趣味と区別される学問研究として行われたのでなく、露伴の趣味活動の一環として、つまり彼の個人的で主観的な生の一部として行われたことである。明治44年の彼の博士号授与に際して直接の対象となった業績は唐の時代の「遊仙窟」についての研究であった。この研究も彼が小説を書くことをやめたあとで、職業的な「責任や圧迫を感じることなく」、自由に行ったことであり、趣味とみなすことが可能である。明治40年代以降の活動はすべて同様に考えることが出来るだろう。
人間は働いてばかりいては疲れてしまうから、たまには思う存分遊びたくなるのは当然である。働くために遊ぶのだと言う人がいるが、それは「遺憾ながら僕にはそれが飾った理屈のように思える」と露伴はいう。
「遊ぶとなると何かしているのだから、やはり、それだけ勢力を費やす」。例えば酒を飲んで遊ぶ。しかし酒を飲めばくたびれる。碁や将棋の遊びは、数学の問題を解くのと同様、脳の中のあるものを消費し、脳に負担させている、と露伴は言う。様々なスポーツや遊びがある。だが、「魚釣りをして遊ぶ、鉄砲を持って遊ぶ、船を漕いで遊ぶ、いずれも身体や脳髄のいく分かを消耗せぬということはない」。遊ぶのは疲労を恢復するするためだというのは「物質学的には、まったく、説明が不可能だ」。しかし、多くの人が知っているように「遊ぶことによって心身の疲れを恢復し新しく元気を奮い起こしているということは、争うべからざる事実だ」。
遊びが心身の疲労回復に役立つのは、「人間というものは一つの物事に長く掛かっているということに耐えがたい苦悩を覚える」もので、そこからいったん離れ、ほかのことをすることが「すでに元気回復の方法になる」からであり、また「自分の快適とするところ」つまり楽しいと感じることに向かうことで「精神の暢達〔チョウタツ〕」が実現される、つまり精神が暢びやかになり、すなわち元気が恢復するからだという。
だが、「同一作業の反復から脱する」ためには必ずしも遊びは必要はない。「むしろ遊興をとらないで、元気を恢復する方法を求めたほうが、手短で、利口がっている20世紀の人々に適したことではあるまいか」。
眠れば神経の疲れは直に回復する。筋肉の疲労は休息をとり適度に食べれば恢復する。もろもろのスポーツ、そして「ボート漕ぎ、魚釣り、鳥打、そんな下らぬことはせずとも、身体は健康を保っていかれるわけだ。心細いポケットから心細い算段をし、酒を飲んだり、美人を買ったりして脳髄に余計な負担を与えるには及ばんことだ。----もし働くための遊興だというのならば、疲れた挙句に眠る睡眠ほど---経済的な遊興はあるまい。これほどの真正の無銭遊興はあるまい。賢明なる20世紀の人々はみなこの無銭遊興をとることを喜ぶに相違ない」という。
しかし、露伴は遊ぶことを否定するのではない。「利口がっている20世紀の人々」の職業倫理、「仕事のために遊ぶ」ことを否定するのである。「僕は働くために遊ぶのでなくて、遊ぶために遊びたい。こりゃ、どういうわけだか知らないが、嘘じゃない」。これが結論である。
彼がここで述べていることは「遊戯娯楽は遊戯娯楽のための遊戯娯楽にあらず」とした20年ほど前の「游漁の説」とは正反対の考え方である。露伴が小説家であったころに抱いていた職業倫理思想は今や完全に放棄されているということが明らかである。露伴はその後半生においても、仕事をし稼ぐことが不必要になったわけではないが、遊びが仕事に従属的で、生において副次的意味しかもたないものではなく、仕事と対等な意味を持つ活動だと考えるようになった。生の目的は仕事にあり、そのほかの諸活動は仕事に役立たねばならないという考えはそこにはまったく含まれない。
人は生きて様々な活動を行うであろうが、遊びは遊びで楽しむことだけを目的に自由に遊んでよい。そして、それとは別に、家族、子供との関係において責任を果たすために、かつ社会のほかの人々の評価を得(これは精神的快を与える)、報酬を得る(これは生存の苦を避けることを可能にする)べく、職業を持ち仕事をする。社会的な評価を受けるには苦労が必要である。普通の人は多くの苦労が必要だが、露伴の場合には、自分の好きな趣味の活動に、机に座りペンを動かす少しの労苦を付け加えるか、あるいは「口演」するだけで、他の人々よりもはるかに容易にそしてはるかに大きな成果を仕事から得ることができた。彼は仕事を行ったが、それは義務感や圧迫感とは無縁のものであった。彼は自分の好きなこと、したいことをすれば、それが仕事になった。
露伴は人々に「器量」の違いがあることは認める。そして人は、自己をより大きなもの、より高いものにする努力をすべきである。というのもそうすることは愉快だからである。「孔夫子曰く、学びて時に之を習(かさ)ぬ、亦説(よろこ)ばしからずやと」。学んで知識を広げることも、またそれによって自己の(実践)できる事柄が増えることも楽しい。そして彼は「日本文学と国民性」で、誰もが学問が楽しいと感じられるだけの基礎的教育を公平に受けられるようにすることを主張してもいる。人は心身ともに喜ばしい生活を送る権利を有している。人は他の人と協調しつつ自己の幸福な生を目的にして生きてよいのである。
「我を拡めるの愉快」(『快楽論』)では、自分の力の範囲、知識の及ぶ範囲、芸術を向上させること、社会上の地位や勢力を張るのも自己を広めることである。富を増したり---趣味を昨日は持っていなかったところに広めるのも自己を広めることだ。およそ、自己の外に対して自己の何物かを展開させ、拡張するのは自己を広めることだ、と言い、ここでは筋力、視力など身体能力の拡大について述べる、と言う。
船乗りははるか遠方の物を見て取る遠視能力を獲得する。庭園の仕事をする者は「地面の平不平高低を見る---視感の敏妙を有する」。大工、左官も肉眼で微妙な歪みやムラを見いだすことができる。ある呉服商人は暗夜でも指の触覚だけで織物の産地と種類を知りうる。また「釣魚の楽しみに耽れる人は指先に触れる糸のかすかな動きによって、深き水底の釣り針に来た魚の何種であり、何程の大きさであるということを知りうる」。このように感覚を鋭敏精緻なものにすることは自己を拡大することである。これら能力ははじめから持っていたのでなく、意識的あるいは無意識的に、自己の能力を少しずつ押し広げることによって、修練によって獲得されたのだ、と言う。そして終わりに、感覚能力だけでなく「我が押し広められるということは我の進歩、能力の増進」であり「何人か一種の快感を覚えなかろう」と言う。
露伴は多数の書を読み博く学問をすることで「自己の拡大」を楽しんだであろう。他方、露伴版「学問の勧め」である『悦楽』で、孔子の言う「学びて時に之を習(かさ)ぬ、亦説(よろこ)ばしからずや」の注釈行うのに先立つ箇所で、櫂や櫓を使って船を漕ぐ操船の仕方ををほぼ1ページにわたって説明している。そして「自転車に乗りて駛(はし)り得るやうになるも、遊泳を学びて水を行き得るやうになるも、其の習熟して悦を感ずる光景は皆同じ。---志を立てなば学ぶべし。学びなば---これを習熟すべし。習熟すれば悦び其中にあり」という(全集第28巻)。露伴は様々な趣味娯楽を行った。釣りをして船をこぎ、自転車に乗っただけでなく、銃猟を行い、写真を撮り、将棋を指し、またそれら趣味娯楽の道具に関する知識を広げた。これらすべては自己を「拡大」することだと考えられる。露伴は義務や圧迫感によってではなく、自己を拡大することを楽しいと感じつつすべての活動を行っていたと思われる。
彼は様々な活動を行ったが、そのほとんどは彼自身の楽しさ、快楽を追求する活動であった。結果的に彼の活動は多くのほかの人々に喜びを与えたし、学問的な貢献にもなり、また家計を支え子供たちに対する義務も果たすことができた。しかし彼は井上哲次郎のように、自己の学問を通じ日本国をアジアのリーダーにしようなどとは考えなかった。
露伴の有する様々な知識のうち、和漢の文学に関するものが専門性のある深い学識だということは間違いがないとしても、その知識の全体を近代的な意味での学問だと考える必要はまったくなく、多くは個人的な趣味にかかわる「雑学」的知識だということもまた確かだと思われる。それら雑多な知識のすべてがそれぞれの関連した分野で専門的学問的な価値をもつことはないだろう。それらは露伴自身の自由で主観的な興味によって、また興味の程度の違いに応じて異なる徹底性の程度において、多様に追求されたであろう。
人間は学問や科学技術の進歩に寄与しあるいは社会や国家に貢献することに自己の生の意味を見出すこともできる。政治に携わることも、そうした貢献の一つである。
また、他者に危害を与えない限りでもっぱら自己の主観的な興味の実現の中に生の意味を見出すこともできる。露伴の場合には自分の興味の赴くところに従って自由に活動したが、その大部分は同時に広く社会の人々に喜びを与える成果を生み出すことになった。彼はきわめて幸福な生を送ることができたと考えられる。
カイヨワは『遊びと人間』(原著の公刊は1958年、清水幾太郎・霧生和夫訳、岩波書店、初版1970)の冒頭で、ホイジンハは「文明の発達そのものにおける遊びの役割の重要性を証明した」が、彼の著作は、「遊びの研究ではなく、文化の領域における遊びの精神の創造性の研究」だと評する。カイヨワも様々な社会の文化的特徴を遊びと関係づけつつ説明しようとする。つまり彼は「遊びを出発点とする社会学の基礎を作り上げようと考えている」という。しかし、それに先立ち、ホイジンハが「自明のこととして----故意に省略した」「遊び自体の説明や分類」を真正面から取り上げ、遊びとは何であり、どんな遊びがあるかをあきらかにしようとする。その上で、遊びは人間およびその社会にとっていかなるものであるのかを解明しようという。
カイヨワ(仮)。写真は「アカデミズム底辺で生きるヘタレ神学研究者、 マイニチ・ノンデルけどサンデルとは対極のリバタリアンのアナキスト」によるEssais d'hermeneutique(http://thomas-aquinas.cocolog-nifty.com/blog/)「みんな、遊んでいるかい?」からお借りした。読む価値のある文がぎっしり詰まった素晴らしいブログだ。
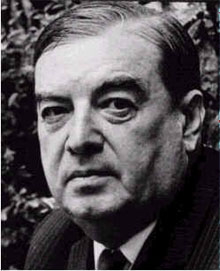
カイヨワは遊びの類型化を行なう名高い議論をホイジンハの遊びの定義の検討から始めている。 彼は、まず、ホイジンハが「遊びと秘密や神秘との間に存在する親近性を見抜いたのは、----有意義なこと」だと認める一方で、「この暗黙の協働関係を遊びの定義の中に入れることはできない」と言う。というのは「遊びの活動は、秘密を暴き、秘密を公表し、----秘密から秘密の性質そのものを奪い去ろうとする」からだ。遊びにおいては「秘密は敬われていてはならない」とカイヨワは言う。
カイヨワは第二部つまり「遊びを基礎とした社会学」のなかで、古代社会を、インカ、アッシリア、中国、ローマのように、官僚制や法律、産業、技術、都市生活の発達した「会計の社会」と、それより「原始的な」、シャーマンが重要な役を果たしていたアフリカやアメリカ、オーストラリアなどの先住民の社会、すなわち「混沌の社会」とに分けている。
ホイジンハも取り上げていた仮面を着けた祭司による宗教的行為は、最初は、模擬、物真似(ホイジンハは演ずる遊びと呼んだ)ではじまるが、それは「前座」に過ぎず、次第に興奮が高まっていき、祭司の憑依と集団的熱狂、陶酔状態に移行する。祭司は他の人々が畏怖する、超自然的で神秘的な行為を行う魔術師であるが、仮面が「恍惚を導く変身の手段」であり、仮面を着けることによって人を怖がらせることができる。そして、仮面を着けることのできる者たちは社会の権力者でもあった。「原始の混沌の社会」においてはその秘密が知られていない。実際には仮面とは単なる変装なのだが、秘密を知らないものにとっては恐ろしいものであったのだ、とカイヨワは言う。他方、後の社会で行われる、模擬や模倣の遊び、あるいは眩暈の遊び(後述)においては、「秘密」は存在しない。宗教的行為の領域と遊びの領域は異なった、別の領域である。カイヨワはホイジンハの定義のうちにある、遊びと聖なる行為との一体視をはっきりと退ける。
ホイジンハは「文化にとっては賭けは不毛だ」、つまり生産的でないと言って、遊びの中には入れなかった。しかし、カイヨワは非生産的であることは遊びの本質的特徴だと考える。「いかなる富もいかなる作品も生み出さないのが遊びというものの特徴である。この点で遊びは労働や芸術と異なる。----収穫があったわけでもなく、物が製造されたわけでもなく、傑作が生まれたわけでもなく、資本が増大したわけでもない。遊びは純粋な消費の機会である。---ボクサー、自転車競走の選手、騎手、俳優などのようなプロの場合、彼らは賞金、俸給、出演料などのことを考えねばならないから、その意味で、彼らは遊び人ではなく、あきらかに職業人である」とカイヨワは言う。
私は、前の章で、プロのスポーツマンはショーとして、職業として試合やゲームを行っているのであり、ふつうの人が休日にスポーツを楽しむ場合とはっきり区別すべきだと述べた。カイヨワのスポーツや演劇におけるプロとアマの区別には全く異議がない。
だが、釣りは魚、獲物を生み、狩猟、潮干狩り、山菜取り、家庭菜園なども獲物・収穫を不可欠の要素とする遊びである。あるいは、単に自分の楽しみのために描いていた絵画や自分で作って歌っていた歌が、後になって、世に認められたり、売れたりするということもあろう。私には、遊びにも「富を生み出す」ものがあり、またそれを意図しなかったとしても、結果的に、「傑作を生み出す」こともあるように思われる。カイヨワは芸術を遊びと区別している。当然、彼は科学を遊びから区別するだろう。だが、昆虫の観察や採集、バードウォッチングなどの「遊び」が「科学」的に重要な「発見」をもたらすことがしばしばある。
仕事が業績を必要とすることは事実である。遊びは業績を必要とはしない。しかし、何か成果を生んではいけないというわけではない。釣りと家庭菜園のように獲物や収穫があっても構わないし、日曜大工や日曜画家のように作品が生み出されても構わない。活動が楽しみのために行われるのならば、遊びである。遊んで楽しむことが目的ではなく、自分の生活の必要のために、あるいは仕事として社会的評価を受ける必要のために、獲物を獲、作品を制作することが目的になるなら遊びではなくなる。私は「非生産的であるかどうか」により遊びとそれ以外の活動とを分けることはできないのではないかと思う。これについてはまた後で述べる。
ホイジンハの「遊びは自由で任意の活動であり、喜びと楽しみの源であるという定義」には問題がないと、カイヨワはいう。「---義務として課され、あるいは単に勧められただけでも、遊びはその根本的特徴の一つを失ってしまう。すなわち、遊ぶ人が、いつでも、遊びではなく、引退、沈黙、瞑想、閑居、創造的活動のほうを選ぶ完全な自由を有しながら、しかも、自発的に、自分の意志で、そして自分の快楽のために、遊びに熱中するという事実である。---遊びが存在するのは、---気晴らしをするため、気苦労から逃れるため、つまり現実生活から逃避するために遊ぶことを欲し、そして遊ぶときだけである。さらに、とくに、遊ぶ人は、好きな時に「もうやめた」と言って立ち去る自由を持たなければならない」。
ホイジンハの場合には少し違っている。ホイジンハは祭礼における演技の遊び/playにおいては義務を伴うものになることを認めていた。祭りの儀礼を行うことを引き受けたものは「もうやめる」といって立ち去る自由は存在しない。だがホイジンハはそうした祭礼における演技はあくまでも遊びplayだとみなしていた。それは、義務を伴ってはいても、共同体の福祉という高次の目的のためにおこなわれるものであり、個人的な利害からの活動ではないということ、また祝祭行事は何かの手段として行われるのではなく祝うこと自体を目的に行われるもので自己目的的性格を有しているということなどを理由に、祭礼の演技も「遊び」の本質的特徴を持つと考えるからであった。しかし、聖と俗の世界を区別するカイヨワは祭礼における活動は遊びではないとする。カイヨワとホイジンハは、遊びは「自由に行われる活動である」ということに関して、俗の世界における遊びに限って一致している。
さらに、カイヨワはホイジンハと同じく、遊びの時間空間が持つ、特権的とも言うべき「隔離性」を主張する。「遊びは本質上、生活のほかの部分から切り離され、慎重に区別された活動であり、通常、時間および空間の厳密な限界の内部で完了する活動である。場合によって異なるが、石蹴りの図形、---競技場、リング、舞台----といった遊びの空間がある。この観念的境界の外で起こることは全く考慮されない。---時間についても同じことで、合図とともにはじまり、そして終わる。やむをえない理由もなく、放棄したり、中断したりするのは不名誉なことである」。
遊びは自由に行われる活動である。職業的な仕事の場合には、約束、契約があって、「好きなときに「もうやめた」といって立ち去る」ことは、何らかの責任を後に問われることを覚悟しなければできない。しかし、「興味によって縛り付けたものを倦怠によって解きうる」ということは遊びにばかりいえることではない。仕事は給料だけで選ぶのではなく、興味があるかどうかも重要な要素となる。その仕事に興味を失えば、転職するということは大いにありうることだ。
また、ホイジンハもそうであったが、カイヨワにおいても、子どもと退職者にとっての遊びは決して「隔離」されたものではないということが、全く忘れられている。すでに述べたが、遊びも職業も、いずれも、無限定ではなく、また完全に限定的でもない。この二人にとっても「人間」とは働くことが当然であるような存在、あるいは働き盛りの成人であるために、遊びは「隔離性」を特徴とすることになるのではないだろうか。この点に関しても後で詳しく検討し、反論を述べたい。
カイヨワは、「遊びは自由な活動であるが、しかも、それは不確実な活動である」と言う。「宝くじやルーレットなどでは、出るかも知れないし、出ないかも知れない番号に賭ける。〔運動競技を含め〕----あらゆる技の遊びは元来、遊ぶ人にとって、的を外す可能性、失敗の危険を伴うもので、それがなければ、遊びは気晴らしにはならない。----成り行きがあらかじめわかっていて、間違いや驚きの可能性もなく、避けられない結果を明白にもたらすとしたら、それは遊びの本質とは両立しない。」
カイヨワは宝くじなどの賭けの遊びを「偶然の遊び」と呼ぶ。この遊びでは、遊び手playerは彼の練習や努力、技とは無関係で「成行き」のわからない「不確実な」結果を手に入れようとする。したがって賭けの遊びはたしかに「不確実な活動」と呼ぶにふさわしい。また、私は釣りは釣果が不確かで、「不確実な活動」だと思う。
しかし、遊びが、労働(生産活動)、芸術活動とは異なる活動だという彼の考えに従うとして、では、生産活動や芸術活動は、確実で、成り行きはあらかじめ決まっていると言えるだろうか。農業などは天候により左右されるところが大であり、工業生産も運動競技における競争以上に激しい競争にさらされており、企業活動が成功するかどうかは不確実で、成り行きはわからないと考えられる。また、芸術活動が生み出す作品が常に「失敗」作ではなく、「間違いや驚きの可能性」のない「確実」な活動だ、とカイヨワがもし言うとすれば、私は到底、納得できない。
私は職業的でない藝術活動は遊びの部類にいれたいが、それは措くとして、生産活動も、政治活動も、学問研究の活動も、私には、失敗の危険がありうるし、「間違いや驚きの可能性」があり、不確実性を伴っているように思われる。私は、後の個所で大学入試と競馬をともに、一定の努力が必要でしかも偶然の要素が混じった、一種の賭けだと述べるつもりである。遊びはすべて不確実な活動だと言うことは、大学受験を含め、それ以外の活動は確実であるということを含意しているなら、賛成できない。
カイヨワは、ホイジンハの遊びの定義を検討しつつ、遊びの特徴を自由な、分離した、不確定な、非生産的な、そしてルールをもつかあるいは虚構的な活動として定義する。続いて彼は、遊ぶ人の態度の違いを基準にして遊びを4つのタイプに分類するとともに、それらタイプに分類された遊びを、意志の気ままさあるいはその反対の集中度の観点にしたがって並べる。
また、狩猟、登山、クロスワードパズル、詰め将棋などは、対抗する相手の競技者(ないしチーム)はいないが、「拡散した不断の競技」に参加することだという。つまり、その競技の参加者は一つの場所に集まって競争するのではないが、そこでは、たとえばより多くの獲物を撃ち、あるいはより難しいコースのより高い山を登頂し、あるいはより短時間にその問題を解くことを目指して、仮想の参加者と勝敗を争う戦いが行なわれているというのである。
ボフス『スポーツ史』によれば、19世紀後半、英国で娯楽のスポーツ化が進行していた頃に、世界最初の登山集団「アルパイン・クラブ」がロンドンに生まれ、4000m級の初登攀が競技会形式で実施されて、スポーツ記録のように記載されたという。これは登山が潜在的にはアゴーンであるというカイヨワの見方を支持する事実である。だが、登山と山歩きを区別することができるとすれば、山に登ること/山歩きが好きな人の大部分は、人に比べて少しでも早く、高い山に登ろうとしているとは私は思わない。登山では、途中の景観が好きだからと、同じコースを繰り返し登る人もあるだろうし、一人でなく数人で行うのがふつうだとすれば、よい仲間と楽しい一日あるいは数日を過ごすことがこのような登山の目的であろう。この場合には、潜在的にであれ、「競争」が目的の中あるとは考えにくい。
詰将棋や詰め碁ではたいてい「何分で解いて、何級程度」などと書かれている。そのために、その問題を解くことは他の人と技能の程度を比べることのように感じるかもしれない。もともと、将棋や囲碁は、他者と対戦して勝ち負けを争うゲームであるから、一人で行う詰将棋や詰め碁でも「仮想の敵」が存在する。人が「一級程度」の問題を解くことができれば、彼/彼女はそれよりも下の級であるような相手と対戦すれば、たぶん、勝つことができると予想されるだろう。だが、クロスワードパズルでは、自分の能力の程度を比べるべき基準のようなものは示されていない。その人はただ一人で頭を絞って考えるだけである。そして、そもそも、クロスワードパズルには対戦すべき相手は存在しない。彼は問題を解くだけであり、だれかに勝つことはできない。
遊びにおいては、何かに「成功」する、「やり遂げる」ことが含まれているが、何かに「成功」し、何かを「完遂」することのすべてが、他者との競争に勝利することを意味するわけでは決してない、と私は思う。釣りでは、磯や船で事故を起こさずに、できれば狙った魚を釣って無事帰宅することが「成功」であり、登山では目標の山を登りきって無事に下山することが「成功」である。これはカイヨワがルドゥスと呼んでいる遊びのタイプの概念に近い。だが、彼はルドゥスは潜在的なアゴーンだとする。この点も含め、あとで再論することにしよう。
ホイジンハはアゴーンを、文化的機能を持つ二種の「高級な遊び」のうちの一つとしていた。しかし、カイヨワは、多くの動物が生殖の相手を求めて、競い合い、激しく戦い、その戦いの「目的が相手に手傷を負わせることではなく自分の優越を示すことにあるのは全く明白」であり、アゴーンと呼んでかまわない。「人間は、これに洗練と規則の精密さを付け加えたに過ぎない」という。カイヨワの見方に従えば、人間がアゴーン・競争を好むことは、動物と区別された人間の精神性を示すものでもなんでもなく、動物の中にその根を持っていると考えるべきであるのかもしれない。
(注)しかし、補遺の二「教育学から数学まで」では、子どもの遊びについての重要な研究を行ったジャン・ピアジェと、ジャン・シャトーが偶然の遊びを無視していることについて批判しつつ、「子供は非常に早くから幸運に敏感なのだ」と言い、「本当のお金と変わらぬもの」であるビー玉を賭ける丁半遊びや、「学校の近くで、児童たちに宝くじのミニ版を売る菓子屋の繁盛」について述べている。 上の「遊びの分類」で語られていることとここで述べられていることは明らかに食い違う。理由は不明である。
この回り将棋をやった経験をもとに私の意見を言うと、子供は「行動」でばかり遊ぶわけではなく、抽象的で、知的精神的能力を使った遊びを楽しむこともある。そして、「本将棋」のルールを覚えることができない小さな子は「回り将棋」が好きである。「回り将棋」はお金をもたない子どもが喜んで遊ぶ「偶然」の遊びである。これは「偶然の遊び」である点ですごろくに似ている。
だが、すごろくのように途中の旅を楽しむというような「のどかさ」はなく、「運に頼って」、ただ、ただ、できるだけ早く前に進むだけの「競争」の「ゲーム」である。私は、ダウン症で知的障害のある息子と健常児で4歳上の娘と3人で、息子が小学校の高学年だったころから養護学校の高等部を卒業するまでの間、この「回り将棋」を何度もやった。
たとえば、角カドから2コマ手前にいるときには、振り駒では、1もまずいが、3以上の数が出るより、2が出たほうがジャンプができるので、得をする。しかし、出したい数を出すように、駒(4枚の金)を振ることはむずかしい。振ってみなければ数はわからない。うまく2が出て幸運のジャンプができることもあるし、運が悪く3以上がでて角から先の9コマを一歩一歩、あるいは数歩ずつ進まなければならないこともある。
息子は、手の中で4枚の金の向きをそろえてから振ることで、うまくいけば、4枚とも表にすることができるなど、ある程度「数」に影響を与えられることを知っていたが、必ずしもうまくゆくわけではなく、大部分は「運できまる」ことを理解していたと思う。私は、息子が、全くわけがわからないまま、3人が、ただ、かわるがわる、駒を振り、数を数え、そして持ち駒を動かすだけの空騒ぎに付き合っていたのだとは思わない。狙った数が出ないとき、運が悪いことを悔しがり、運良く振り駒が「立って」高い点数がでて相手を追い越すことができたり、ちょうどいい数が出て連続してジャンプができたりして手をたたいて喜んだ。
息子は中学生になったころからテレビゲーム、「スーパー・マリオ」などのTVゲームをやるようになった。TVゲームの場合には、指の動かし方つまり自分の力だけで、ハードルを次々にクリヤーすることを楽しむが、それとは異なり、回り将棋は、がんばってもしようがないが、しかし、試みることが楽しい、偶然の力に頼って駒をすすめるゲームである。息子はこのことを理解して、回り将棋を楽しんでいたと思う。
言語能力に障害があり、言葉の数は少なく、発音も不明瞭である。しかし、彼が比較的早い時期に覚えて、発音もはっきりしている言葉の中に「運がいい!」がある。何かいいことに偶然出会ったときに、(私の真似をして)握りこぶしでもう一方の手のひらを叩きながら「運がいい!」と言う。回り将棋をしながら覚えた言葉である。
次ぎの文は、卒業記念に学校で作製したビデオに入れるために私が提出した文「高校を卒業する大地に贈る言葉(30秒程度という条件の中で)、04・3・2」である。「大地君、付属養護学校で、よい先生や友達のおかげで、本当に楽しい6年間を過ごすことができて、よかったね。そしてその間にゆっくりと君は大人になってきました。君の口癖で、特に楽しいときに、「運がいいね」と言います。君が頑固で譲らないので、父さんもたまに怒ることがあります。でも、18年間、君と一緒に暮らしてきたことの「運のよさ」を、しばらく前から強く感じるようになっています。これからも楽しく暮らそうね」。
彼は「楽しい」とか「面白い」とかの語も知っている。「運がいい!」と彼が言うのは「偶然」が関係している状況で楽しいときであり、単に楽しい、面白いと言う時とは違う。彼が、回り将棋を繰り返しやったこと(だけ)によって「運」を理解するようになったかどうかは明らかではないが、彼は、高等部を卒業する以前に、運という語の使い方も、また偶然の遊びである回り将棋の楽しさも、知っていた。
この遊びでは、何も賭けずに行なった。お菓子くらい賭けてもよかったかもしれないが、お金を賭けることは全く考えられなかった。息子は、当時も、2016年31歳になる現在もお金の価値をほとんど全く理解していない。
現在、障害者自立支援事業を行っているNPO法人の支援を受けつつ仕事を行なっており、月2万円ほどの給料をもらう。給料日に給料を受け取ることは、「よくがんばったね」と褒められるのと同じようなことと感じているのではないかと推測する。額の大小は問題ではなく、1万円から2万円になったときには「給料日〔=給料〕アップだ」と喜んでいたが、しかし今でも、千円札を一枚ずつ数えてて10枚目で数えるのを止めてしまう。要するにお金の計算は全くできず、価値を理解していない。しかし、運というものがあり、回り将棋が運の遊びであることを知っていたことは確かである。
回り将棋のほかに、すごろくは子どもが大いに好む偶然の遊びである。カイヨワの主張にもかかわらず、一般に、幼稚園に入るくらいの年齢になれば、子どもも、運のよしあし、偶然を理解することができ、偶然の遊びを喜んで行う、と私は思う。
北九州市の「スペースワールド」(http://spaceworld-mania.blog.so-net.ne.jp/2014-09-06) が「アトラクションおすすめ」で「ベスト2」とする「ザターン」というジェットコースター。高さ65mから89度ほぼ直角に急降下して、人々を恐怖で絶叫させる。

カイヨワは「遊びをしていて本当に満ち足りた気持ちを味わうのは、その遊びが周囲の人たちをまきこむ反響を生んだ時だけである」。「遊びには共感をこめて注目してくれる観衆の存在が必要なのだ。いかなる範疇の遊びもこの法則の例外をなさない」。「遊びはすべて---孤独でなく、仲間を前提している」という。ルドゥスは個人的な技のあそびだがこの「法則」をまぬかれることはできないということになろうか。
かれが言うように、個人的な遊びが競争へと発展することがあるということは十分に理解できるし、また、技の遊びだけでなく、他のいかなる遊びをするのであれ、「注意深い共感的な同席者」、「仲間」の存在によって、より大きな「快楽と興奮」を得ることができるということも事実であろう。ルドゥスはアゴーンに発展すると、たぶん、言えるのであろう。
だが、技の遊びがアゴーンとして制度化されており、競技会が広く開催されていても、ルドゥスとして、他者と勝ち負けを争う必要なしに、また規則に従うこと、他者の評価や判定をうけることなしに遊べるがゆえに、言い換えれば、全く自分の好きなようなやりかたで、のんびりゆったりした気持ちで遊ぶことを求めるがゆえに、また、場合によっては、孤独を望むがゆえに、好んでひとりで行う人も多くいるだろうと思われる。
海釣りの場合には、遊漁船組合や渡船組合などの主催で時々釣り大会が開かれ、魚種ごとに、釣った魚の大きさに応じて賞が与えられる。だが、こうした大会に他の人と競うことによって自分の釣りの腕を上げたいと考えて参加する人はあるまい。
ほかの遊びでは他者と腕比べがしたくなり、競技会に参加するのである。だが、釣りに一定の技量は必要であるが、開催期間のあいだに大物が釣れるかどうかは運である。釣り人は、釣りの腕とは関係のない賞品目当てに釣り大会に参加するのである。釣りで一見「競技」のように見える「大会」が開かれることがあるにしても、それはルドゥスがアゴーンにおのずと発展するという事実とは無関係である.
しかし、カイヨワが言うように、遊びには「共感をこめて注目してくれる観衆の存在が必要」であり、「遊びはすべて仲間を前提している」ということが、遊びの「法則」であるなら、釣りはほとんどの場合、観衆のいないところで行なわれるし、また仲間を前提していることもない。しばしば一人で釣ることの方が好まれる。すると釣りはカイヨワの言う「遊び」でなくなってしまうことになる。
釣りに似た(獲物を得る)遊びに、素潜りで貝を取る遊び、あるいは潮干狩り、山菜取り、また家庭菜園での野菜作りなどがある。(私は狩猟も獲物を得る遊びと見なすことがもっとも適切で、そこに加えるべきだと私は考えるが、カイヨワでは狩猟はスポーツとされ、「選手たちは顔を突き合わせて対抗はしないが、空間時間的に大きく拡散した競争に参加している」と言われ、射撃の腕の競争・アゴーンに分類されている。)これら獲物を得る遊びはカイヨワの言う4つの基本範疇のどれにも属さないように思われる。カイヨワの範疇は遊びのすべてを包摂していないのではなかろうか。私は、カイヨワの遊びからは「自然の中での遊び」あるいは「自然を志向する遊び」が脱落していると考え、この点についての議論を、後の「疑問と反論」のなかで行おうと思う。
工業化以前の社会においては、労働者は職人・アルチザンとして、自己自身の主体的計画に従って自己の技量と知性を発揮しつつ物を作っていた。それを拒まれた労働者は、生産過程においてではなく、余暇に、遊びとしてのホビーのなかで、「アルチザンに戻るのだ」。彼らは、「人間には捨て去ることができないように思われる欲求―自らの持つ知識、努力、技量、知性などを無駄に〔つまり、生産のために役立たせるのでなく〕使いたいという欲求、また自己統御や苦痛、疲労、----などに抵抗する能力などを惜しみなく使いたいという欲求」を実現するのである。労働者はホビーという遊びの中で「現実への復讐」を行っているとカイヨワは言う。印象的な言葉である。「技術文明の発達を可能にする---資質」が「ホビーの発達に貢献している」にもかかわらず、この技術文明は、同じ資質が人間の労働という形で発揮されることを拒み、労働者を機械並みの存在に貶めてしまった。ホビーは「技術文明のもっとも忌むべき側面に対する対応物」であり、ホビーと工業文明は、同じ写真のネガとポジのように対応しあったものである。
カイヨワは『遊びと人間』第Ⅰ部で、遊びの類型論を展開したが、その最後の節で「遊びを基礎とした社会学」の構想を語る。第Ⅱ部の4つの章は、その「遊びを基礎とした社会学」の展開である。あるいは古代から現代にいたる諸社会の類型論もしくは比較歴史社会学の展開である。
4種の遊びを支えていた人間の欲求は、人間の根源的な欲求であり、それらは遊びという形を取った活動・行動の中に現れるだけではなく、社会のほかの領域、政治や経済や文化などの中にも現われ、その社会を特徴付ける。こうして彼は歴史の中に現れてきた様々な社会の特徴を、遊びを支える4種類の欲求及びそれらの組み合わされた欲求の元にある根本的な欲求・衝動と関係付けながら明らかにしようとする。
ところで、青柳まち子は『「遊び」の文化人類学』(講談社現代新書、1977)の第一章で、カイヨワの遊びの類型論をかなり詳しく(6~7ページにわたって)紹介し、遊びを定義したのに続く二つの章で「労働と余暇」、「遊びの伝搬と受容」について述べ、そして最後の章「遊びの型と文化の型」で、遊びの型と全体的な文化の型の相関を考察している。青柳は自分が研究したトンガの社会を含め5つの社会を取り上げ、それらを競争的、協力的など3つのタイプに分けた上で、そこにおける遊びないし余暇行動のタイプがどうであるのかを表で示している。彼女は協力型の社会では競争的ゲームがそれほど盛んでなく、反対に競争型の社会ではそれを好むという仮説はほぼ証明できた、という。
この結論について何か言おうとは思わないが、青柳はそのすぐあとの「日本人はギャンブル好きか」という小見出しついた箇所で、カイヨワの議論に触れ、次のように言う。
「カイヨワは遊びと社会の関係について論じた際に---混沌の社会、つまりオーストラリアやアフリカ、またアメリカインディアンの社会の多くでは模擬とめまい〔ミミクリーとイリンクス〕の複合型の遊びが、インカ、アッシリア、中国やローマといった計算の社会では競争とチャンス〔アゴーンとアレア〕の遊びが主流になると言う」が、「このような議論が誤りであることは今まで述べてきたところで明らかである」と述べている。
青柳は第一章で、遊びのカテゴリーを4つに分けるカイヨワのやりかたは心理的構成要素しか考えておらず不十分で、遊びにかかわってくる人間関係(個人的か集団的か、競争的か協同的か)を考慮する必要があると説いていた。それは私も否定しない。しかし、「混沌の社会」と「計算〔これは多田らの訳語で、清水らの訳では「会計」である〕の社会」とを対比したカイヨワの議論を要約した文は全くの間違いである。カイヨワはそのようなことは全く言っていない。
『遊びと人間』岩波書店刊(清水・霧生訳)には、中国など秩序の社会=「会計の社会」では、「アゴーンとアレア、すなわち、この場合は、メリットと家柄とが、社会的な遊びのもっとも重要な、しかも相補的な要素として現れる」という文がある。青柳はこの文から会計社会では競争とチャンスの遊びが主流になると、カイヨワが述べていると誤って考えたのではないだろうか。
だが、そもそもこの(訳)文は意味がはっきりしない。原始的社会ないしは混沌の社会は仮面と憑依、すなわち、ミミクリとイリンクスが支配している社会である、と述べたあとで、中国やローマなどの会計社会では「アゴーンとアレアが遊びとして、最も重要要素として現れる」と、遊び以外の領域については触れることなく、遊びについてだけ述べることはコンテクストから考えておかしい。
この文は講談社学術文庫版(多田・塚崎訳)では「これらの社会においてはアレアとアゴン、すなわち、ここでは能力と家柄とが、社会的機能(ジュ)の最重要の、ただし相補的な要素となっている」である。清水・霧生訳ではジュを遊びと取ってしまったのだろう。だが、ジュつまりjeuには遊びの意味の外に働き、機能、あるいは演技・演奏などの意味がある。この文ではjeuは機能の意味であろう。(講談社学術文庫版奥付では1990年初版となっているが、訳者後書きには1971年出版とあり、文庫でないものが講談社から71年に出版されている。青柳はこの原著第二版の翻訳を参照したはずであるが。)
つまりこの文では、会計社会では生まれと能力とが相補的要素として重要な役を果たしているということが言われているだけであり、会計社会では、遊びにおいて競争とチャンス・偶然の遊びが主流を占めていると言われているわけではない。
カイヨワは古代中国に関して「中国人は、音楽、書道、絵画と並んで、囲碁、将棋を、知識人が実践すべき四つの技芸の一つにまで高めた」。これら四技芸によって「闘争本能は鎮められ、魂は静謐と調和と可能なものを沈思する喜びとを学ぶ。疑いもなくこれは文明の特徴である」(清水・霧生訳でp117)と言っている。また「中国における弓術の競技---〔の〕判定は、結果によるよりも、むしろ、矢を射るときの正しい動作や敗者の慰めかたによる」ものだったと言い(p155)、そして、競技場の遊びは「制限とルール」のある戦いを模範として示し、「フェア・プレイと寛大との学校」になり、「文明推進の役割を果たす」と述べてはいる。
しかし、彼は古代中国における「偶然の遊び」については全く触れていないし、また二種類の「重要要素」アゴーンとアレアの遊びと異なるイリンクスやミミクリの遊びがそれら二種類の遊びと比較して多いか少ないか、どうであるのかについても当然ながらふれていない。
四つの技芸や弓術は、中国、会計社会を「アゴーンとアレア」という呼び名で特徴づけることが正当である、言い換えると会計社会が「アゴーンとアレア」を基本的原理とする文明社会であることを示す具体例に過ぎない。メリットと家柄が相補的に重要な役を果たす会計社会において、アゴーンとアレアの遊びが盛んであるということを意味するものではない。
またさらにカイヨワは混沌の社会における、ミミクリーとイリンクスの支配についてさまざまな事例をあげて説明しているが、その社会での遊びについては何も述べておらず、「模擬と眩暈が、社会の原理になっているオーストラリアやインディアンの社会で、ミミクリーとイリンクスの遊びが主流になる」とも言っていない。
彼は本書の冒頭でホイジンハの遊びについての定義を検討したときに、次のように述べていた。原始社会で行われる仮面や特別の衣装を用いて行われるさまざまな魔術的、呪術的な実践はすべて本物のトランス(何かに憑かれたような状態)や恍惚、不安や恐怖を伴ったものであり、現代社会における仮装行列等々とは異なり、遊びではない。
カイヨワは「ある文化を遊びだけで定義づけようとするのは無謀なやり方であって、おそらく、欺瞞的なものとなるであろうことはいうまでもない。実際、それぞれの文化は、同時にさまざまな種類の多くの遊びを知り、行なっている」と言い、「問題はそれぞれの社会が、競争、偶然、物真似、トランスに、それぞれどんな役割を与えているかを知ることである」。そしてそのことは「精々のところ、社会を示すための新しいラベルや種属の呼称を選択するという程度のことであろう」とさえ言い、それらカテゴリ―を用いることの限界性を十分わきまえている。遊びの型と社会の根本性格との間にはっきりした相関関係があるなどと言おうとは考えていないのである。「しかしもし、採用された呼称が、〔混沌の社会と会計の社会の〕基本的対立に一致すると認められるなら、その事実そのものから植物なら隠花植物と顕花植物、動物なら脊椎動物と無脊椎動物という区分と同じように、根本的な二大区分を打ち立てることになるであろ」。私はカイヨワの主張は十分に肯定できると思う。先に見た青柳の指摘はカイヨワの議論の誤解によるものに過ぎない。
カイヨワは混沌の社会と会計の社会という二種類の社会に類型化した。が、また彼は「補遺1「偶然の遊びの重要性」では、次のような考察も行っている。「原始的社会」の多くは長時間の緩やかな変化の過程を経て「会計の社会」に移行した。時に、仮面と憑依の組み合わせが支配していた社会が、突然、文明の発達した別の複雑な社会と接触し、それに征服され、以前とは異なる原理、アゴーンが本質的であるような諸制度を押し付けられたが、人々がそれに従って行動するだけの準備ができていないというようなケースがある。カイヨワはこれを「中間的社会」と呼んでいるが、さらに、適当な気候風土のもとにあって、衣食住のための規則的な労働をまぬかれているというような場合には、アレアが「芸術、倫理、経済、そして知識にいたるまで影響を及ぼすほどの意外な文化的意義を獲得する」ことがあるという。
彼が上げている例は「カメルーン南部およびガボン北部」の部族社会、および、革命前のキューバなどである。ここでは、人々はミミクリーとトランスの支配から突然切り離され、新しい法、競争原理に立つ、異質な社会制度を与えられ「自ら参加できない管理機構によって監督されている」。彼らは「自らを律する責務もない」。彼らは、アゴーンという新しい原理にしたがって行動すること、勤勉と禁欲の倫理に従い、自らの運命を自らで切り開くという文明社会の生き方を実践することはできない。彼らは働くことの意味を見出しえないまま、運命の決定に従う怠惰のなかにとどまることによって、「伝統につなぎとめ」られ「元の世界に連れ戻」されて、かろうじて人間性あるいは自己を失わずに生きていくことができる。彼らは「永遠の子供として、その〔新しいタイプの社会の〕外側で、細々と生きていくだけである」。こうして彼らはサイコロ遊びに熱中する。偶然の遊びが人々の「習慣、規則、第二の天性と化す」。
カメルーン、ガボンでは、天体、多くの動植物、大人や子ども、男と女、道具などの、「百科全書的豊かさ」をもった、絵や象形文字が表面に刻まれた多数のサイコロが用いられ、サイコロの製作に必要な浮彫芸術が生まれた。
キューバでは19世紀に始まりカストロの革命まで続いた「シナ文字謎」という賭けが流行した。ここでは胴元と参加者のあいだに黒人信仰についての知識を背景とした謎掛けやヒントを伴うやり取りが行われる。賭けで使われる紋章とやり取りの文句は賭け以外の生活の領域全体に影響を与えている。ハバナでかけられる額は1日に10万ドル以上であり、隣のプエルトリコでは島の予算の半分に相当する年間1億ドルが賭けに投下された。この「文字謎」は前の世紀から刑法で禁止されていたが、流行はやむことはなく、国家公認のものも含め、賭けは「明白に重大な社会問題」になっている。「個人貯蓄は壊滅し、事業は麻痺し、人々は生産労働より僥倖をあてにするようになる」とプエルトリコの委員会は知事に答申した。「文字謎」とよく似た特徴をもち、1880年頃に形が定まった、ブラジルにおける動物賭博もまた同様に、大きな道徳的、文化的、政治的、そして、経済的な影響を及ぼしているという。
現代の産業社会は「労働の価値を基礎とする」社会である。労働は、技量や知性、そして努力など個々人の能力・メリットに基づいて行われる。そして、社会の富の配分は、主として、各人の労働に基づいて行われるべきだと考えられている。労働に対する報酬は職業、社会的な地位によって異なるが、この地位は、労働能力を比較し評価する競争試験などを通じて配分される。現代社会では魔術や呪術にしたがって行動が行われるということは公的な領域に関してはもちろん、私的な領域においてもまずありえない。偶然にたよることも、できるだけ排除すべきだと考えられている。「遺産相続は出生という根本的なアレアの産物であり、時には廃止され、多くの場合重い課税の対象となって、---社会全体の利益のために使われる」。賭け事が国家により運営されているが、それは国庫を富ませ、社会に有益なしかたで還元するためである。「アゴーンだけが正当な競争---の原理であり、----価値として認められている。社会体制は全体としてこの原理に基づいている。進歩とはこれを発展させること、結局はアレアをできるだけ取り除くことである。」
こうして近代以降の社会では、人は魔術や呪術のお告げにしたがって行動するのでないとともに、運命や偶然の力に頼らず、自己の人生を自分で切り開いていくべきだと考えられており、必要なものは、額に汗して稼ぐことによって自分で手に入れなければならない、と一般に考えられている。
ところが、諸個人の有する能力は生まれや環境の偶然性に支配されている。「富、躾、教育、家庭の状況など、外的でしばしば決定的な条件のすべてが、法の中に描かれている平等を打ち消している」。また、「出生が一種の宝くじであることは誰でも知っている」。遺伝は「アレアそのもの」である。社会はこれらの点に目をつむり、「スタートの条件は万人に同じ」であり、「公正な戦い」が行なわれているとみなすことによって、試験その他の方法で社会的な地位を決め、各人の力、能力たる、労働に応じた配分を行う。
他方、「偶然の遊び」、賭け事は「金を稼ぐための正反対の手段を提供」する。そして、偶然の機会である「チャンスは、単に不公正の華々しい形態、無償で不当な幸運の姿であるだけではない。それは、労働、刻苦勉励、節倹、将来のための耐乏生活など、要するに財貨の増大を目指す世界において必要とされる一切の美徳に対する嘲弄でもある」。賭け事はアゴーン、メリット(能力)が無価値であることを声高に主張している。「賭けは労働を愚弄し、労働と競う」意味を持つ。公認された賭け事は、労働や、勤勉や努力を説く社会の欺瞞を暴露している。
とはいえ、賭け事は、たんにシニカルな意味を持つだけなのではない。それは、「忍耐と努力---辛い労働によっても---生活水準の向上さえほとんど考えられない大多数の人々にとって、---屈辱的な悲惨な条件から脱出する唯一の方法として現れる」。それは、この不公正な競争社会において「敗者を慰め、敗者に最後の希望を残してくれる」。誰もが多額の賞金を獲得し、一夜で富豪になることが可能である。「その可能性は、ほとんど幻想に近いものであるが、それにしても、目立たない人々が、そこから脱出する何らの手段もない凡庸な条件を我慢する励ましとはなる」。それは、正しいとみなされている競争に敗北し「自分の無能を責めるしかない」人々の「屈辱を埋め合わせ」、「最後の希望」を与える「不思議な力」として機能しているとカイヨワはいう。私には、賭けが与えてくれるという精神的「励まし」、幻想に近い「希望」よりも、多くの敗者が実際に賭けに負けることで「偶然」にいっそう苦しめられ、家族を路頭に迷わせ、親戚や知人からの借金を踏み倒すというような、生き地獄に陥る結果につながることさえあるという事実のほうが余計気になるが。
カイヨワは工業社会で賭けが国家によって営まれ国庫を富ませていること、また不公正な競争社会の安全弁となっていることを述べ、偶然の遊びが「社会的経済的機能」を有するとする。だが、その機能は、その社会の基本的な原理を促進し、推進する機能ではない。偶然の遊びは「怠惰と宿命論と迷信を助長する」という反論があることは彼も認める。だが、とカイヨワは付け加える。「アゴンの上に全面的に根拠を置く」はずのソ連では、「富くじはいかなる形でも不道徳とみなされている」。他方、経済成長を目的に労働者たちに貯蓄が奨励されているが、貯蓄銀行では、普通の利子を受け取る代りにくじを引くこともできる。また事実上強制的に買わせられた国債には奨励金がつけられ、宝くじで当選したものに賞金が配られた。こうしてカイヨワは結論づける。「幸運の魅惑がいかに執拗であるかは、本来幸運を最も憎む経済制度が、にもかかわらず、幸運に一つの場所―限定され、偽装され、いわば恥ずかしいこととされているのは事実だが―を与えざるを得ないと言うことでよくわかる。実際、運命の恣意的決定は、やはり、規則をもった競争にとっての必要な補足なのである。
| 社会機構の外部にある文化形態 | 社会生活に組み入れられた制度的形態 | 変質/堕落 | |
| アゴーン(競争) | スポーツ | 商業上の競争、試験、コンクール | 暴力、権力への意志、術策 |
| アレア(運) | 宝籤、カジノ、競馬場、施設賭博、 | 株式投機 | 迷信、占星術、ほか |
| ミミクリー(模擬) | カーニヴァル、演劇、映画、スター崇拝 | ユニフォーム、儀礼、芸能 | 狂気、二重人格 |
| イリンクス(眩暈) | 登山、スキー、曲乗り、スピードの陶酔 | 眩暈の克服を含む職業 | アルコール中毒と麻薬 |
「堕落」は、多田訳では「変質」である。「遊びの堕落」と題されてはいるが、この表に先立つ本文の説明で、この表の一列目に書かれているアゴーン、アレア等々は、遊びのタイプではなく、その遊びを行なおうとする欲求、衝動、本能ないし心理的態度を指していることがわかる。第二列目の、「社会機構の外部にある文化形態」とは、その欲求ないし心理的態度が実際に、しかし日常的現実の活動とは区別される周辺的活動として現れた遊びであり、第三列目の「社会生活に組み入れられた制度的形態」とは、その欲求の発現であるが、広く社会のなかで正当なものとして認められ、一定のルールのもとで働いている活動形態を指す。しかしその欲求が、遊びの特徴である「隔離性」を失って欲求・衝動が社会の中に拡散、漂流、彷徨し、「堕落」することがあるという。
そこで例えばアゴーン(競争)の欲求は遊びという文化形態をとって、競技スポーツとして行なわれ、また制度的形態をとって、商業上の競争や試験制度として行われているが、それが制限やルールを無視して野放図に追求され、勝つこと、成功以外の目的を持たない、暴力を用いた戦いになることがあり、その最悪のケースが戦争だ、という。
2行目のアレアは幸運を射止めることへの欲求であるが、その「変質・堕落」は迷信あるい占星術などを信じる行動になるという。カイヨワは迷信や占星術が当時のフランスで流行した社会現象を3ページにわたって報告している。
またイリンクス(めまいを感じたいという欲求)の「変質/堕落」が、アルコールや麻薬に依存することだというのはよくわかるが、しかしミミクリーの「変質・堕落」の形態が「狂気、二重人格」とされているのは、後者が一種の病気ないし障害(現在では多重人格は「解離性同一性障害」とされている)だとすれば、「欲求の」変質/堕落とするのはおかしいと思われる。
イリンクスについてはその文化的形態にあげられているものは、前に言われていた遊園地の機械に乗って遊ぶこととは違う欲求のの表れように思われるし、「制度的形態」で「眩暈の克服を含む職業」とされている点はおかしいと思われる。これらについては、以下の<カイヨワの議論に対する若干の疑問と反論>の1.の中であらためて触れる。
原始的社会である「混沌の社会」と文明社会である「会計/計算の社会」とはそれが基づく原理におい異なっており、両社会は根本的に異なるとカイヨワは言う。原始的社会においては、ミミクリーとイリンクスが支配する。祭における仮面の着用、演技者たちの憑依、そして集団全体の眩暈の共有が集団生活の紐帯となる。祭において喧騒と熱狂が次第に高まってゆき、集団全体が神聖な癇癪状態、痙攣状態に陥り、世界のあらゆる秩序が一時的に撤廃されてしまう。仮面を着けた者が神として、超自然的な力を持ったものとして登場し、祭りの終わりとともに世界の秩序が強化されて再び現れる。
他方文明社会ではアゴーンとアレアが支配する。古代ギリシアに見るように、ルールのある競争(遊びの祭典)とくじ引き(都市行政官の選出)に制度としての価値が与えられた。中国の官僚機構においては、下級の官職においてだけでなく次第に上級の官職へと君主の恣意や家柄や財産に左右されない、競争の仕組みが採用されるようになった。文明社会の特徴は「混沌社会」と比べて、秩序と安定を有し、数と尺度、規律と必然を重んじる精神の普及にある。
カイヨワは、ミミクリとイリンクスが支配する混沌の社会から抜け出し、能力と運の世界に移ることが「文明の誕生ということに他ならない」と言う。そして前者から後者への変遷、移行は数千年を要したが、そこには飛躍、革命があったという。
だが、この「文明社会」を支える根本原理である能力と運の結合には明確な矛盾がある。両者は人間に正反対の態度を求める。一方は外的障害に対する意志の闘争を求め、もう他方は運勢に対する意志の放棄を求める。競争は人間の能力や美徳の永続的演習、有効なトレーニングであるのに対して、宿命論は根本的怠惰である。文明社会にはこの二つの原理の相克が存在する。この相克の解決のために、この社会においては、門閥や身分などの運、「偶然の役割を犠牲にして公平の役割を増大させようという絶えざる努力が存在している。この努力を人は進歩と呼ぶ」とカイヨワは言う。
現代社会はアゴーン、つまり平等な条件の下での競争を主たる原理、価値としてはいるものの、そこには依然として出生(家族制度)という宝くじ、あるいは遺伝という能力のアレアが残存してもいる。社会はこれらの点に目をつむり、「スタートの条件は万人に同じ」であり、「公正な戦い」が行なわれているとみなすことによって、試験その他の方法で社会的な地位を決め、各人の力、能力たる労働に応じた経済的配分を行う。
社会の現実は決して公正だとは言えないとカイヨワは言い、遊びには現実社会からの脱出を求める欲求が現れている、遊びのなかに現実社会に変革が必要であることが現れているという。
遊びは、政治活動でも社会運動でもなく、社会変革をめざす活動でもない。それどころか、むしろ現実から「離脱」したり、自己を「無化」したりする代償行為でしかないが、それでも現存社会に対する批判を含んだものである。遊びは現実を変えることができない無力な多くの人の、現実をかえたいという願望、現実世界を超越しそこから脱出しようとする欲求の表れである。
カイヨワによれば、すべての遊びは現実に対して否定的な態度を取る点で共通している。そして遊びの領域においては、その社会を変えたいという欲求、現実社会から脱出したいという衝動は、いつでも実現することができる。
アゴーンは「各人が自分の価値を証明するための正確に同じ可能性を享受すべき」だという前提で設けられた条件で闘う遊びであり、アレアはこれとは正反対に、諸個人の価値、「つまり、自己の技量、筋肉、知性といった手段」、「専門的能力、規則性、訓練」を否定し、運だけに頼る遊びである。「どちらにしても、世界を作り変えることによって、世界を脱出する」。ミミクリーでは、各人は架空の世界の中で、自分とは別のものになって遊ぶ。「自分を作り変えることによって世界から脱出する」。イリンクスは「肉体的、精神的な混乱状態」、「興奮状態」を作りだし、「現実を一挙に無化する一種の痙攣、トランス、麻痺状態に入る」ことを楽しむ遊びである。
ホイジンハにおいては、遊びの、現実からの隔離あるいは遊離は、それが宗教、学問、芸術などと結びついたものでなく、単なる遊びである場合には、「低級」なものとみなされた。カイヨワにおいては、「遊びは、遊びに固有の、遊びを遊びたらしめている特有の性格により、日常生活の行為や決定と対立する、平行した独立の活動として現れる」のだ。カイヨワが取り上げている4種の遊びはほとんどすべて大人の遊びである。明確な欲求、意思を有する大人が、一方で、社会規範、基本的な価値観や倫理に従って日常・現実世界のなかで行動するとともに、他方で、この現実世界を否定し、そこから脱出することを求める。その衝動が(宗教的な行動を除けば)遊びとして表れるのだと、カイヨワは言うのである。 ----------------------------------------------------------------------------------------
労働者が模型作りによって工場労働に復讐しているとカイヨワが述べた少し後で、同じフランスの社会学者・デュマズディエは、労働者は釣りによって工業文明に復讐していると考えた。
デュマズディエは第二次大戦後の欧米を中心とした資本主義諸国における経済発展がもたらした余暇の拡大に注目し、主に労働者の時間の使い方という観点から、釣りを遊びの重要な項目として取り上げた。彼によると、1960年ごろのフランスでは「庭仕事とか釣りといったレジャー活動が特に目立って伸びてきている----。フランスの釣り人口は約350万人であるが比率からみると労働者階級に釣り人口の密度が高い」。J.デュマズディエ『余暇文明へ向かって』中島巌訳、東京創元社、昭和47年(原著の公刊は1962年でカイヨワの『遊びと人間』公刊の4年後である。)
農業、あるいは家庭菜園における労働ないし作業のリズムは工場におけるそれと違って、季節の循環という自然のリズムに従わねばならない。同様に、釣りにおいては潮時や太陽の高度という自然のリズムが支配しており、魚の当たりがなく、することもなく時間が流れるのをただ待っているだけということがしばしばある。仲村祥一は、デュマズディエの言葉を引用しつつ、「釣りには時間のむだがどうしても必要だ」と言っている。「釣魚論―時間と娯楽」仲村編『現代娯楽の構造』(昭和48年、文和書房)
自然のリズムも一種の強制であり、釣り人も、本当は、効率よく短時間で獲物を得たいのではないかと反論する人がいるかもしれない。しかし、まず、もちろん、太陽や月の運行に従うことは、資本家や工場長が決めることに従うこととは違う。
そして、工場労働の場合には、生活の必要から止むを得ず、決められた時間に従って作業を行うのだが、釣り人は遊びで釣るのであり、待たねばならず、釣れない時間帯があることを承知で出かけるのである。遊びは自由な選択によって行われるが、労働はそうではない。前に引用したカイヨワの言葉を再度引用すれば、「遊ぶ人が、いつでも、遊びではなく、引退、沈黙、瞑想、閑居、創造的活動のほうを選ぶ完全な自由を有しながら」遊びを選ぶときに、遊んでいると言える。つまり遊びが存在するのは「気晴らしをするため、気苦労から逃れるため、つまり現実生活から逃避するために遊ぶことを欲し、そして遊ぶときだけである。さらに、とくに、遊ぶ人は、好きな時に「もうやめた」と言って立ち去る自由を持たなければならない」。ベルトコンベヤーシステムに配置されている労働者は自分から欲してそこに就いたのではなく、また「もうやめた」といって立ち去る自由があるとは言えないのは明らかである。
デュマズディエに従えば、自由であるとは、時間を自分の思うがままに使うことである。仲村の言葉を借りれば、人間は「時間を無駄に使う」ことへの欲求を持つ。人間は工場労働のような、秩序だった仕方で時間を使って生きるのではなく、「無理、無駄、むら」のある、合理的でないしかたで時間を使いながら生きたい欲求をもっているということになる。
カイヨワは、人間は他者によって設定された目標に向かってではなく、自分で立てた目標に向かって進みたいし、物を作るのであれば、自分が必要と考えるもの、自分が求めるものを、自分の技量を発揮して作りたい存在なのだという。デュマズディエは、人間は、さまざまな活動を行うであろうが、時間を自由に使い、自分のペースで行動することを欲する存在だといっている。そして、産業社会は、この人間の欲求をかなえさせてくれない。カイヨワにおいてはミニアチュアの製作のような遊び、デュマズディエにおいては釣りや家庭菜園のようなレジャー活動によって、人々は、世界を変えることはできないまま、産業社会のもたらした運命に対する復讐を行っているというのである。
カイヨワによればどの遊びの根底にも現実からの脱出を求める衝動がある。釣りや家庭菜園作りで遊ぶ労働者はホビーを行う労働者と同じく過去へと脱出を図る点で共通している。しかし遊びの形は全くと言っていいほど異なる。釣りや家庭菜園づくりの遊びに対する欲求ないし衝動は模型作りに対するそれとは違うと思われるが、前者の欲求・衝動はいかなるカテゴリーに属するのか。
私の考えでは釣りや家庭菜園作りは競争、幸運、眩暈、模倣というカイヨワの4つの基本カテゴリーのいずれによっても、またそれらを組み合わせたものによっても説明されない。
デュマズディエは、余暇活動で労働者が、あるいは、大企業の支配人を含め被雇用者が、家庭で自分の利益になる家庭菜園や日曜大工的な仕事に「情熱を燃やす」のは、「自己の主体性を回復する」ことができるからであり、努力や工夫の結果としての「利益はすべて自分のものであり、そして自分は自分の主人だという感じを味わうことが出来る」からだと説明している。釣りに関しても同じことが言えるだろう。余暇に釣りをし家庭菜園づくりをする活動はデュマズディエによれば「自己の主体性を回復しようとする」欲求に基づくものである。
私は第一章で、常識的で一般的と思われる遊びの「仮の定義」を示しておいた。それは「義務や責任に拘束されて行なうのではなく、それ自体を目的に楽しみで行う活動、したがって自由な活動」というものである。この常識的な遊びの定義が認められるなら、釣りや家庭菜園づくりはカイヨワの4つのカテゴリーを用いて分類、説明することはできないが、遊びであることは明らかである。デュマズディエは、その遊びである釣りや家庭菜園づくりしようとする欲求を「自己の主体性を回復」しようとする欲求、「自分の主人でありたい」という欲求と呼ぶ。ついでながら、彼に従えば、模型作り行なう労働者の遊びも、ルドゥス、つまり特定の技量を発揮したいという欲求、従って一種の競争の欲求なのでなく、あるいはそれだけではなく、「自己の主体性を回復」しようとする欲求に基づく遊びだと考えることが可能であるように思われる。
ホイジンハは競争と演技の二つの種類の遊びだけを遊びと認めていた。賭けは遊びと認められていなかった。カイヨワは、物質的利害関心の絡む賭けは遊びではないというホイジンハの考えに反対する。
すでにみたように、アレアは、宝くじや競馬の制度として国家の財政を補い、また、文明社会の主要で正当なものとして認められている能力による競争の原理を「補足」し、生まれによる不公平を許す原理として働き、そして能力の競争に敗れた人々の最後の慰めとして機能している。賭けや偶然の遊びは「善悪はともかく、明らかに諸国民の経済と日常生活とに重要な役割を演じている」。このように社会の中で重要な働きをしているアレア(を原理とする遊び)を除外してはならないというのがカイヨワの考えである。彼は「いかなる物質的利害も、いかなる効用ももたない」というホイジンハの遊びの定義を退ける。こうして彼はアレアの遊びを、競争と演技の二つの遊びに並ぶ、第三の遊びとして付け加えた。
だが、カイヨワが賭けや偶然の遊びを遊びとみとめ、新たなカテゴリーの遊びとして遊びの仲間に加えるだけなら、ホイジンハの「いかなる物質的利害も、いかなる効用ももたない」という定義を無視するか退けるだけでもかまわなかったはずだ。ホイジンハのその定義は遊びを狭めてしまう無用な定義であるとするだけで十分だったはずだ。
しかしカイヨワは、偶然の遊びが金銭の遊びという形を取り、利害関心を伴ったものになる場合がよくあるが、それでも、偶然の遊びは遊びであり、確実に金を得るための行為ではないということを強調したかったようである。彼は偶然の遊び、幸運を得ようとする遊び(富くじや競馬)はときに大儲けを可能にすることがあるが、また極度の損失をもたらすこともあること、結局「最高の場合でも、利得の合計は、ほかの遊ぶ人の損失の合計を超えることはない」こと、そこには「所有権の移動はあるが、財貨の生産はない」等のことを述べる。
これは、富くじや競馬などの偶然の遊びが、利害関心を伴ってはいるが、結局遊びであり金もうけ行為ではないということの説明であることは確かである。しかしだからといって、すべての遊びがそうである、あるいはそうでなければならないということの説明ではない。現実に釣りや家庭菜園づくりの遊びのように収穫を生み出す遊びがあるからである。狩猟、山菜取り、素潜りで貝を取る磯遊び、潮干狩りなどは獲物を得る遊びである。カイヨワは狩猟を、射撃の腕を競うアゴーンだと言うが、とにかく獲物が得られることは事実である。
また労働者がホビーでミニアチュア模型を作り出す活動が純粋な消費であるとは思われない。彼が製作する模型は芸術作品ではないかもしれないが、作品であり、彼以外の人々の室内に飾られるかもしれない。それは「財貨」であろう。また、たとえば昆虫採集の趣味の持ち主は精密な作業によって標本を作りケースに入れて展示する。この標本箱は芸術作品ではないだろうがやはり作品であり、見る人々を驚かせ喜ばせる効用をもつだろう。同じことが、日曜画家や日曜大工の趣味について言える。
遊びの中には、物を製造し、収穫・作品を生む遊びもある。つまり、何も新しいものを生み出さず、純粋な消費でしかないということは、金銭を賭ける偶然の遊びの定義ではあっても、遊び一般の定義ではない。こう考えるのは間違いだろうか。
講談社版巻末の訳者解説で多田は、カイヨワは「様々な遊びを動機づける「本質的でほかに還元不可能の諸衝動」に照応した遊びの基本的カテゴリーを提示した」。「この4つのカテゴリーは経験と理性に照らして、こんにちまでのところ、もっとも確実と思われる」と言っている。だが、この文は「4つのカテゴリーが基本的なカテゴリーで、ほかには存在しない」、あるいは「このカテゴリーに収まらない活動は遊びではない」ということが、「理性に照らして、もっとも確実」ということなのか、「基本的なカテゴリーがほかにもあるかもしれないが、とにかくこの4つのカテゴリーはカテゴリーとして、もっとも確実だ」と言っているのか、不明である。
私は、学説のようなものを唱えようとしているわけではないが、カイヨワの遊びの説は不十分で遊びをもっと拡大したいと思う。
二つめは想像すること。
私は、広く行われていて、ミミクリ、すなわち演劇、幼児のごっこ遊びなどと似ているが、それとは別な、自由な楽しみとして絵本、漫画、小説などを読む活動があり、それらも遊びであると思う。カイヨワによれば演ずることは模倣であり、観客はヒーローやヒロインとの同一視によって劇を楽しむとされる。しかし、小説を読むことにおいては、時代背景、主人公の性別、年齢、職業、そして、テーマやストーリーによって、主人公との強い同一視が起こるものもあるが、面白く読めてしかし主人公との同一視が起こらない場合もある。
2016年3月現在、朝日新聞連載中の沢木耕太郎の「春に散る」を私は面白く読んでいるが、その登場人物のいずれについても同一視は起こらない。その前の連載、林真理子の「マイストーリー」も同様である。私の読書時の年齢と関係なく、また絵本や漫画の区別なく、思いつくままいくつか他の例を上げると、竹取物語、「西遊記」、(吉川英治の)「三国志」、「ロミオとジュリエット」、「ファウスト」、「レ・マンダラン」や「人はすべて死ぬ」などでは、さまざまな人物が登場し、様々な事件が起こる。それらにおいては、読み手は特定の登場人物に対する同一視なしに、そのストーリーの展開を楽しむ。あるいは作者の提示している問題を考える。
小説や物語を読む楽しみはミミクリの範疇でくくることはできない。読んでいて時々興奮したり、夢中になって読んだりすることもあるかもしれないが、イリンクスに分類することもできない。小説を読む楽しみとは、作者が作る、現実にありそうなしかし私の今の現実とは異なる、その意味で非現実と呼ぶことができる世界での出来事を想像力を用いて見聞きし、考えて楽しむことではないか。(演劇においても、観客が主人公との同一視によって夢中になるという場合を別として、一般的には観客は、小説を読むのと同じように楽しむのではないか。)
三つ目は自然を志向する遊びである。野や山や海に行きたくて、太陽の光、雪、風、水、波が好きでその遊びを行うような遊びである。ハイキングやヴァンデルン(野山を歩き回る活動)、山登り、スキー(競技スキーではなく滑って楽しむスキー、特に山スキー)、サーフィン、海水浴や川遊びなどがあげられる。海岸や平野など坂のきつくないところで景色を楽しみながらゆっくり走ることを楽しむサイクリングなどもここに入る。ウィンドサーフィン、ヨット、スキューバダイビング、パラグライダー、タコ上げなどは基本的に自然を志向する遊びである。釣りや山菜取りは自然志向と獲物を獲得しようとする欲求に基づく遊びである。
本栖湖のウィンドサーフィン,Wikipediaによる

『遊びと人間』「遊びの分類」の章のまとめである「遊びの配分」と題した「表1」では、タコ上げはトランプの一人占いやクロスワードパズルとともにルドゥス(したがって潜在的なアゴーン)とされる。スキー、登山は空中サーカスや、メリーゴーランド、ワルツなどとともにイリンクスに分類されている。
凧(タコ)上げは一種の技量の遊びとみなされている。凧上げは、独楽やけん玉やヨーヨーと同様「初歩的な自然法則をうまく利用する遊び」で、凧は「大気の具体的な状況をとらえ活用するところに成り立つ。凧によって、遊戯者は遠く離れたところから空をいわば聴診しているのだ」と彼は気象学や医学の言葉でタコ上げが「技量」を追求する遊びだと言う。実際、高さを競う凧上げの競技会があるようである。
だが、子どもたちの遊びとしては、独楽回し、けん玉やヨーヨーがたいてい室内で行なわれるのに対して、凧上げは広い野原や河原で行う。そして子どもたちは、一生懸命練習して技量を高めることを追求するというよりは、凧が風を受けて大空に舞うのを見て楽しむという面が強いと思う。自然の中で、風を「聴診」するのでなく、自分の全身で風、大気を感じる遊びとみることができる。
また、登山やスキーが眩暈を楽しむ遊びだというのはおかしい。登山の途中に崖状の危険なコースもあるかもしれないが、眩暈を感じたいがためにそのコースを選ぶのではないだろう。ロッククライミングなどでは目のくらむような危険な岩場を登攀する(それでも眩暈を求めるのではない)が、一般的な登山ではなるべく安全なコースを選んで、道端の植物や樹木を観察したり遠くに広がるパノラマを楽しみながら山頂を目指すのではないか。
スキーでは上級者になれば好んで急斜面を滑降するだろうが、眩暈を感じていたのでは滑ることはできない。カイヨワ自身「眩暈の作り出す状態はアゴーンを定義する条件、技、力、計算、---を破壊してしまう」と言っていた。スピードを楽しむという面はあろうが、しかしジェットコースターに乗るように、乗り物機械に身を任せて単にスピードに陶酔していることはできない。練習によって獲得した、身体をコントロールする技術を駆使することができてはじめてスピードを楽しむことができるのであり、油断すれば、たちまち大怪我をすることになる。スキーはどちらかと言えば、技量を追求する遊びであろう。
しかし、スキーは、体に風を受けて雪の上をすべることを楽しむのであり、登山とともに、自然の中で、自然を楽しむ遊びと考えることが可能である。校庭や公園でブランコなどの遊具を使って遊ぶのではなく、雪が積もっているところで走りまわったり、寝転がったりする遊びは、カイヨワならパイディアに分類するだろうが、私は雪の中で遊ぶのが楽しくて駆け回ったり転がったりするのであり、自然志向の遊びだと思う。海水浴や川遊びなども海や川の自然を楽しむのであり、単なるパイディアではない。
さて、この自然志向の遊びは、カイヨワの4種類の遊びと並んで、それらに付け加えられるべき、遊びの一つだというだけでなく、カイヨワの遊び全体に相当するものだと言いたい。というのはカイヨワの遊びはすべて社会的な遊びであり、彼においては遊びはすべて人々が寄り集まって行うもの、社会的、社交的な衝動に基づいて行うものである。
彼は遊びの定義、分類に続く「遊びの社会性」という章では、遊びが本来社会的なものだと言うことを強調していた。「遊びはたんに個人的な娯楽ではない」。「凧(タコ)、独楽(コマ)、---ヨーヨー、けん玉などの遊び道具は一人で操作して遊ぶものである。しかし競争者も観客もいなければ人はすぐに---飽いてしまう。潜在的にせよ観客が必要なのだ」。「遊びは--すべて、孤独ではなく仲間を前提としている」。遊びが、遊び場、遊ぶための施設(競馬場、カジノ、遊園地etc.)をもとめ、宝くじ、オペラ、遊びのための「発達した組織、---専任の職員を要求する」。そして制度を作り出す。こうして「遊びを基礎とする社会学」が構想された。
カイヨワにおいては社会的・社交的な遊び、孤独のなかでおこなわれるのではない遊びだけが遊びと考えられている。現実からの脱出の欲求という点では、現実の社会から脱出しようとするが脱出先は非現実の社会、例えばひと昔前の、熟練労働が支配的であった社会なのである。
ところが釣りや家庭菜園づくり、また山菜取り、登山(山歩き)などは、観衆の存在を前提とした、人間を対戦相手とする遊びでも、他の人間になろうとする試みでもなく、人々の集まる施設、ホールや競技場や遊園地から遠く離れた海や山で、あるいは自宅で、一人で楽しむことができる。しばしば近くにだれも人がいないほうが好まれる。これらは、基本的に、非社交的・非社会的な遊びである。
デュマズディエは、労働者や被雇用者が釣りや家庭菜園づくりの遊びによって「社会から離れ」て「ひきこもる」ことは昔の職人的な世界への脱出願望によるものと言う:「彼らは市民でありながら、政治的、社会的、文化的問題には関心を持たない。---彼らは社会から離れ、分業や階級闘争のなかった時代の、引きこもりがちな職人のような態度を示している」。
しかし、私見では、釣りや家庭菜園は、過去の社会へと向かう脱出であるというよりは、社会そのものからの脱出、自然的リズムに従う生活への脱出の試みでもある。あるいは現実に自然への脱出である。
そこで、自然志向の遊びはカイヨワの社会的・社交的遊びの全体と対等な地位をしめるべきものである。そこでもう少しこの遊びについて、議論を補足しておきたい。
前の幸田露伴の節でふれた飯田操『釣りとイギリス人』によれば、スポーツ発祥の地とも言うべきイギリスでは釣りが盛んに行われており、また多くの釣り文学が書かれている。釣りはイギリスでだけ行われていたわけではない。 ヨーロッパとアメリカでは釣りはほとんど川で行われており、イギリスが日本同様、島国、あるいは海洋国であることはイギリスで釣りが盛んであることとは関係がない。実際、フランスでも釣りは行われていたし、行なわれている。
デュマズディエは第二次大戦後のフランスで釣りが労働者の間で人気が高いことに触れていたが、コルバンは、19世紀のフランスでは音楽家や作家の多くが「伝統的な」(餌を使った)釣りを楽しんでいたこと、20世紀に入る頃からは、産業化と密接に結びついて、フライを使う「科学的な」「スポーツ・フィッシング」が盛んになることについて述べている。(アラン・コルバン/渡辺響子訳『レジャーの誕生<新版>』(藤原書店、2010)第10章)。
また、ボフスは『入門スポーツ史』で、19世紀末、産業主義に対する批判的思潮が強まるなかで、自然志向型のスポーツ、たとえば、ヴァンデルンWandern(徒歩旅行ないしハイキング)が流行したと書いている。日本でよく知られているワンダー・フォーゲル(Wandervogel)は元の意味は渡り鳥であるが、同じく徒歩旅行を意味していて、小学館『独和大辞典コンパクト版』によると19世紀の末にクラブが組織化された。
寒川恒夫編『図説 スポーツ史』(朝倉書店、1991)によれば同じ頃に、競技としての登山ではなく、ハイキングや観光を楽しむ登山客が増えた。また鉄道の発達により海水浴客が増大した。コルバンも同様の報告を行っている。
つまり4つのタイプに分類できない、自然志向の遊びが、19世紀末から20世紀にかけて、増大した。これら自然志向の遊びがごく少数の人々の間でしか行なわれなかったというのならば仕方がないが、かなりはっきりとした社会現象だったと思われる。
こうしたことからすれば、カイヨワやホイジンハ、とくに前者が自然志向の遊びを無視ないし軽視したのはやはりおかしなことだと言わざるを得ない。カイヨワの遊び論の欠点の一つだと私は思う。
自然志向の遊びやスポーツは一人一人がばらばらに行う活動であり、また従ってルールの存在しないものが多い。少なくともその起原においては、アゴーン(戦い)でもミミクリー(演戯)でもないし、アレアでもイリンクスでもない。しかし、それらの遊びも、人から人へと伝えられ、文化となる。社会に背を向け自然に向かうことが行われるとしても、そのこと自体社会学的関心の対象となるだろう。たとえばエリアスのように活動を余暇/「非慣例化」と非余暇/「慣例化」とに分け、遊びを「非慣例化」と関係付けて考えるなら、釣りはもちろんのこと、海辺や川の土手での日光浴や昼寝も明確な社会的意義をもつものと捉えられる。遊びが現実からの脱出とされるなら、社会的現実からの脱出としての、自然における遊びという、もうひとつのカテゴリーを考えるべきであった。
ヨーロッパで自然への関心が高まるのは産業社会化が進む18世紀半ば以降のことで比較的新しい現象だ、という反論があるかもしれない。遊びの原理に対応する「欲求」をカイヨワは本能とも言っていた。歴史の変遷のなかで新しく生まれた傾向ではなく、人間にもともと備わっている衝動だと考えているのだろう。近代社会になって始まった自然志向の遊びなるものは、歴史的偶然によって生まれたもので、人間の本能や本性に関わる「社会性」とは別のものだ。カイヨワ(やホイジンハ)は人間の本性に基づく、古代からある社会的な遊びを論じたのだ、このような反論が可能かもしれない。そこで、古代の社会においてすでに「自然志向」の欲求の表れであるような遊びがあったかどうかが問題になるかもしれない。
しかし、中国渭水湖岸で周王に見出されたという太公望(本名は呂尚)の故事を信じるなら、紀元前11世紀の中国では、すでに、釣糸を垂れて世を避ける人が存在した。また、第二節でみたが幸田露伴が示していたように、今から千年以上昔の唐の時代には「釣車」つまりリールを使って釣りをした上流階級の人々が少なからず存在したことが、彼らが残した詩によって知られる。彼らは工場で働く近代産業社会の労働者とは全く異なる条件の下で生きていた人々である。カイヨワは当時の中国の上流階級の遊びであった音楽、書道、絵画、囲碁・将棋の「四技芸」について触れていたが、これら社会的(社交的)・文化的な遊びとならんで、「寒江独釣」、自然のなかで一人で遊ぶ釣りの遊びも存在したことが知られる。
また、森三樹三郎『老子・荘子』<人類の知的遺産5>(講談社、昭和53年)によれば、前4世紀の人、荘子は宋の下級役人で漆園の管理をしていた。「秋水篇」によると、彼がぼく水(「ぼく」はサンズイに僕)という川で釣りをしていたときに、楚の王が遣わした家来が来て、荘子を宰相に迎えたいという王の意向を伝えると、荘子は竿を手にしたまま振り返りもせずに言った。「あなたの国には霊験あらたかな亀があり、死んで三千年になるが、箱に入れて祖先の廟堂に大切に保存されているそうだ。だがこの亀は死後の骨が貴ばれることを願っているか、それとも生き延びて泥の中で尾をひきずっていることを望んでいるか、どちらだと思うか」。家来が「生きて泥の中で尾をひきずっていることでしょう」と応えると、荘子は「では帰ってくれ。私も泥の中で尾を引きずって生きることにしよう」と答えた。
ジョイ・A・パルマー編/拙訳『環境の思想家たち、上、古代-近代編』(みすず書房、2004)によると、亀は生きていて宮廷に飼われていることになっている。そして荘子は「人間の手から餌をたらふく与えられて暮らす宮廷の亀のように生きるよりも「泥の中で尻尾を引きずって」自由に暮らす、普通の亀のように生きることを選ぶという理由で、王宮のより上級の役所での務めを拒んだ」とされている。ただし、こちらでは荘子の釣りについての言及はない。
森は荘子の思想に、非政治的な、個人主義ないし利己主義を見出している。『環境の思想家たち』の筆者は、荘子が、社会の慣例に従うことに批判的で、皮肉屋の利己主義者と見なされていた、と言う。以上に基づき、荘子は非社会的で、自然に向かう欲求を持ち、釣りを好んでいたと言っても間違ってはいないだろう。
そこで、露伴が周到な考証で明らかにしている唐代ばかりでなく、すでに3千年、あるいは2千数百年前の中国の古代国家において、社会に背を向け、自然のなかでの遊びを求める志向を持つ人がいた。すると、近代産業社会におけるばかりでなく、一般に、社会が発達し、人間関係が複雑化したときに、それに反発し、自然に向かう、潜在的、根源的欲求に基づく遊びをする人が増えると考えることができる、あるいはカイヨワの説を補って、遊びは大きく二つに分けることができ、一方に社会的な遊びがあるがそれと並んで自然志向の遊びがある、と考えることができるのではないだろうか。
カイヨワは「一つの役割を演ずる」ことを「あたかも自分が別の人、あるいは別のもの---であるかのごとく振舞う」ことと言い換えている。また「虚構、つまり、「あたかも----ごとく」という感情」とも書いている。だが、演ずる遊び、ミミクリーだけが虚構だというのではない。
「ルールはそれ自体として虚構を作り出す。チェス---などをする人は、それぞれのルールに従うことによって現実生活から切り離される。現実生活には、これらの遊びが忠実に再現しようとするような活動は何もないからである。----これに対して、生活を模倣するような遊びの場合は、---取られた行動がみせかけであり、単なる物真似に過ぎないという意識をともなう。この構造の根本的非現実性の意識が他の遊びを規定する恣意的なルール制定の代わりとなって、---現実生活から切り離す働きをする。---したがって、遊びは、ルールを持ち、かつ虚構的なのではない。むしろ、ルールを持つか、あるいは虚構的なのである」と言う。
カイヨワは遊びの本質を6カ条にまとめているが、その5)と6)の二つでは
5)ルールのある活動。通常の法律を停止し、その代わりに、それだけが通用する新しい法律を一時的に立てる約束に従う。
6)虚構的活動。現実生活と対立する第二の現実、あるいはまったくの非現実という特有の意識を伴う
と言っている。カイヨワは、真似をする遊びとルールのある遊びとでは「虚構性」の発生のしかたに違いがあるが、結局、遊びは虚構性を持つと言う。以下ではこの遊びの虚構性という主張が間違っていることを示そうと思う。
例えば、私が日本を離れてどこか外国で暮らすとすれば、そこでの生活は日本における現実生活の何らかの程度の「再現」であろう。他方、ルールを持つ遊びでは、その遊びのルールにしたがって行動を行うことになる。たとえば、私は将棋の指し手(指揮官)としてコマを動かし、左右にあるいは前後にまっすぐに突進して相手を撃破できる兵器を使って相手を倒すような行動を行ったり、そうするように命令したりする。しかし、このような行動は、私の現実生活のなかでは決して起こらないし、現実生活を「再現する」ものでは全くない。ほとんどの人にとってもそうであろう。こうして、ゲームを始めること、ルールのある遊びの世界に入ることは、なんら現実を「再現」しておらず、現実に全く似ていない世界に移ることである、とカイヨワは言うのであろう。
他方、演じ、真似をする遊びである劇playでは、そこで為される会話、身振り・動作、行動あるいは出来事の進行は、たとえ異なる時代、異なる世界におけるものでも、観客がよく知っている現実の世界におけるそれらに似ている。現実の再現と言ってもいいほどであることも多い。しかし、役者は常に自分以外の人物を演ずる。そして例えば本当に腹を立てているのではなく、起こっている「ふり」であり「まねで」あり、本当に相手の役者を殺すわけではなく、短剣はベニヤ板に銀紙を張ったものに過ぎない。すべては「あたかも---のごとく」という構造を持っている。そこで「取られる行動の根底にあるこの非現実の意識が、人を日常生活から引き離す」。つまり「本当ではない」という意識を持って、役者は演じ観客はそれを見て楽しむ、というのであろう。劇の世界は現実によく似てはいるが「現実生活と対立する第二の現実、あるいはまったくの非現実」だというのはそういう意味であろう。
こうして、ルールに従う将棋がなされ、また劇あるいはごっこ遊びが成立しているとき、遊び手playerは「現実の世界から切り離され」、虚構の世界に移るのだ、とカイヨワは言うのだと思われる。
ここでは主要な論点ではないが、子どもがフリをし、まねをして遊ぶ場合は大人の演ずる遊びとはかなり違っていて、子供がまねをする場合の意識は大人が演じ振りをする場合とは大きく違うということについて、まず触れておきたい。
ホイジンハは機関車ごっこをしている子ども(幼児)は、自分が機関車の「真似をしているだけ」であり「本物の機関車ではない」ことを意識していると言っていたが、カイヨワもホイジンハの文をほとんど引き写しにして「自分が本当に機関車であることを父親に思い込ませるつもりはない」と書いている。だがそれは事実あるいは真実ではない。
私は、上でホイジンハに反論して子供にとって遊びは時間的にも空間的にも「制限された」ものとしては現れないと言った。子どものにとっては遊びとそうでない活動、遊びと現実のような区別は存在しない、と言った。もう少し詳しく説明したい。幼児には店(スーパー)と幼稚園の遊戯室との違いはわかっていない。「スーパー」、「幼稚園」は知っている。その場所は知っている。そしてスーパーに行けばお菓子や野菜を売っているということは知っている。幼稚園には遊んでくれる先生がいることは知っている。しかしそれ以上のことは知らない。スーパーのなかで走ったり騒いだりすることは物理的には可能であるが、それは幼稚園の遊戯室とは異なり遊びまわるための空間ではないこと、「売り場である」ことは商品の陳列という特定の目的を持っていて、売り場の空間を外の目的のために使用してはならないこと、その目的の妨げになる行動はおこなってははならいことなどを知らない。
幼児は、あるものは(ある場所、ある施設)はあるものであるということを知っているが、それが他のものではないということを知らない。同一律「AはAである」を知っているが、矛盾律「AはAでないものではない」を知らないのである。スーパーが遊び場ではない(遊んでよい場所ではない)ことは、そこで遊んで大人たちに叱られることによって、(理由がわかってないから)部分的には知られるが、十分知っていると言えるのは、学校や、幼稚園や児童館、駅、デパート、ゲームセンター、遊園地等々の様々な施設の違いを知り、社会の仕組みを理解した時のことであろう。
同じように、より年少の子供では、機関車と人間の違いはよく分かっていないのである。テレビのアニメのなかでは機関車は同時に人間であることなども影響しているかもしれないが、小さな子が知っているのは機関車と客車の区別があること、機関車が他の客車をけん引する、あるいは一番前にあるものであること、ガッタンゴットンと走ること、等々である。「本当の電車」はずっと大きいものだということは知っている。しかし「本当」と「本当でないこと」の違い、「本当」とはどういうことかを理解できていない。ウルトラマンならビルと同じくらい大きくなったり「普通の大きさ」になったりもできる。ウルトラマンはアニメの世界にしかいないということは知らない。建物と同じくらい大きな鉄人28号が実際にある。「本当に」、大きな鉄の人がいる。そこへ行って見たことはなくても、そのことを子供は「本当のこと」を知らせている、テレビのニュースでみた、等々。小さな子は現実と虚構、本当とウソの違いを知らない。
だから人間が機関車になることは幼児にとってありえないことではない。サムは幼稚園に行き、遊び、給食を食べ、先生にサムと呼ばれて返事をしていた、サムである。どうして今はサムでなく、機関車(トーマス)なのか。さっきはさっき、今は今。さっきは給食を食べていたがそのあと歌を歌い、先生と話をした。その都度のサムがいる。人格の連続性などという難しい話は知らない。今は他の客車を引っ張ってガッタンゴットンと言っている。僕は今機関車なのだ。機関車(トーマス)であることは本当ではなく、うそっこであり、現実には人間であるサムだ、という区別は明らかではないのである。
こうして子どもにとって、遊びは「現実とは異なるフィクション」でも、「現実に似た第二の現実」なのでもなく、現実そのものであり、自分が汽車であることと機関車のまねをすることとの間に本質的な違いがあるとは感じられていない。だから彼は彼に口づけをする父親に抗議するのである。機関車である僕を人間のように扱うのはやめて!
子どもの場合には、トランプや挟み将棋でも、勝ち負けのある遊びが実際の取っ組み合いの喧嘩に発展することがしばしばある。彼らは力量、技量に差があるときに遊びだからと手加減をしてやったり、あるいは「仲良く楽しむことが目的であり、勝ち負けは二の次」などと考えたりはせず、とことん本気で、真剣に勝ち負けを争い、こうして負けたほうが悔しくて泣き出すこともある。これは、子ども達にとって、遊びが現実と感じられており、彼らは遊びと別の現実なるものがあるとは思っていないからである。
子どもの「ごっこ遊び」でも、本人は、現実には自分がそれではない汽車になり、あるいはお母さんになる「フリをしよう」としているのではない。彼/彼女は汽車に、あるいはお母さんになろうとする。そして、なったつもりでいるのである。現実と遊びの世界の区別は幼児においては存在しないか、あるいははっきりしていない。この章の最後、第七節で参照する教育学者の加用はまねをしていることの意識を「うそっこ」の意識と呼んでいるが、彼は4歳児の「うそっこ」の意識について、「ごっこに没頭中はその意識は鮮明ではなくなっており、半分以上本気であるように思わされた」と言っている。
私は、小学校生になってからかなりおそくまで、サンタクロースが「本当にいる」と思っていた。当時、我が家はかまどで薪を焚いて炊事を行っていた。かまどには煙突がついていたが、直径が10センチ程度のブリキ製の煙突である。煙突の大きさからして、サンタクロースが煙突からはいってくるということはおかしいと考える知力はあったが、実際に会って、見ようと、遅くまで目を覚まして待っていても姿をあらわさず、うとうとしたと思うと、もう枕元にプレゼントがおかれてあるのをみて、悔しがったものだ。
親が演じていることについては全く思いが及ばなかったのである。実在しないものを存在するかのように話し、それを見たことがあるようなフリをするということがあるのだということを当時の私は理解できなかった。そして、周囲の大人の言葉を信じることしかできない子どもにとっては実在するものと実在しないものを区別するのは難しいことである。
加用の言うように4歳児ばかりではなく、小学校に入る頃まで、あるいは小学校に入ってもしばらくは、実在するか実在した歴史上の出来事、事物や人と、本当には存在しない、架空の物や人との区別はそうはっきりとは行なわれてはいないし、他者に「なる」、他者の「ふり」をすることの意識、つまり「うそっこ」意識もまた、大人の場合とは違って、「実はそうではない」という意識を伴っているとは言えないと思う。(ただし、大人でも宮本武蔵と佐々木小次郎、あるいは金太郎と桃太郎が実在したのかどうかについて誰もが区別しているわけではないだろうし、さらに科学的事実とされていることについて、われわれが持っている知識の99.9%以上が伝聞の類のものであり、各人が確かな証拠なり根拠をもってそう信じているわけではないということも、事実であるが。)
自己自身についての意識を自己意識という。大人になると意識はほとんど常に同時に自己意識であり意識は行為に向っている、あるいは行為と一体であるとともに、主題的にではないが、行為しようとしている自己、あるいは行為の意識にも向っていて、二重である。子どもの場合には意識は行為と一体であり、その行為は記憶され後になって思い出されはするが、行為をしている現在の自己は意識されない。
日記の書き方にはっきりした違いがある。私の場合で言えば、小学生ごろまでは、日記には、記憶にあるその日のできごと、その日行なったことだけが、書かれることになる。中学生になれば行為とともに、その行為を行いながら自分が考えていたことが、書かれるようになる。何をしたかではなくどのように考えながらそれを行っていたかが書かれるようになり、日記はその日の出来事(自分の行ったこと)の記録ではなく、自分が考えていたこと、自己の内面の記録に重点が置かれるようになる。
自己意識が芽生えることによって、つまり意識が二重になることによって、子どもは意識によって自己の身体を制御しながら行為を行うだけでなく、あるいはその行為に埋没せず、行為をしていることを意識しながら、つまりその行為を他者が見るであろうように外から客観的にながめながら行っているかのように行うようにもなる。
自分が今行っていることが良くないことかどうか気にかけつつ行う意識が良心である。子供は教えられているとおりに正しいことをすることもあるし、欲望や恐怖などにまけて正しいと教わっていたことをできないこともある。しかし、安らかな良心とともに、あるいは、良心のやましさ(の意識)を伴ってそうするのでなく、いわば、二つの強さの異なる引力によってひきつけられて、あるいは強さの異なるエンジンによって駆り立てられてどちらかの行動するだけなのである。
自己意識が存在しない(まだ芽生えていない)ときには、子どもはしようと思うことをすることができるだけであり、ふりをする、つまり自分が本当にするつもりはないのに、外から見たらそれをしているようにみえるだろうように行動することはできない。ただし真似はできる。つまり、見えている相手の体の動きと同じように自分の体を動かすことはできる。しかしその場合には体を動かすだけであり、対象である人物の内面は真似ることはできない。
そもそも幼児の場合、相手が外面に表れているもの以外の何かをもっていることを知らず、したがって内面を含めてその存在の真似をし、それと同じものになろうとは考えない。もちろん内面を真似ることはプロの役者にも難しいであろう。だが子どもには全く見えない。内面は別だということを知りながらその人物のまねをしようとする企てがフリをし、演じることであろう。子どもは内面と外面の区別ができず、外面がすべてであるかのように考えながらその人物になろうとする。もちろん、僕とか私とか言えるようになれば、自分と他人の区別はついているだろうし、自分がお母さんではないことを知ってはいる。しかし外面以外の何が自分とお母さんを区別するのかを知らない。そこで外面だけをまね、それでお母さんになれると思う。こうしてまねをする。しかしお母さんの内面をしらず、自分がお母さんにはなれないことをはっきりとは知らないから、そうでないことを知りつつ外面だけをまねをしようとすること、つまり「ふり」をすることはできない。しかし漠然とではあれ、あるいはなぜそうなのかは分からないが、自分がお母さんとは違うことも知っている。それが「うそっこ」の意識であろう。
そうだとすると、子どもの、真似をする遊び、ごっこ遊びにおいて、その「うそっこ」意識の「根本的構造」が遊びを「現実生活から切り離す」とは言えないことになる。子どもの場合には、自分が機関車だったりお母さんだったりする遊びの世界に移行するにしても、その遊びの世界は現実の世界と連続しているからである。
問題は、劇の中の世界、あるいは劇がどのようにして虚構であるのかということではない。劇の中の世界は、小説=フィクションのなかで書かれているのと同様、虚構であり、現実とは別のものであることは(子どもでないかぎり)知られている。絵描きが絵の具を使って描く風景は本物の風景ではないが、それと同じように役者の演技で作り上げられる劇中のできごとは、本物の世界におけるできごとではない。そのことの理解は大人ならだれでもできる。
問題は、劇において、演ずるものと見るものが、その演じることにおいてあるいは見ることにおいて、どのように、あるいはどの程度「現実から切り離され」、虚構の世界の中に移るのかということであるはずである。役者は、事実・現実でないことを知りつつフリをし、演ずるが、そのことによって彼/彼女は「現実から切り離され」はしない。彼が夢中になって(虚構の世界に浸ってしまい)演技をしていることを忘れてしまうということがないかぎり、彼はまさしくある役を演ずる演技者としての現実を生きている。彼は役者としての仕事を遂行しており現実的に振舞っているのである。
ローレンス・オリヴィエが演ずる1949年の映画「ハムレット」、FC2ブログ「ニューヨーク徒然日記」
2015/08/20(http://nylife09.blog28.fc2.com/blog-entry-2857.html)より借用

観客はどの程度現実から切り離されるであろうか。演出が優れていて劇が面白ければ、舞台の上の虚構の世界に引き込まれてしまうかもしれない。しかし、舞台の上で主人公が殺害されかかったときに、それを阻止しようと舞台に駆け上がったり、ケイタイを取り出して110番に通報したりしなければ、虚構と現実を混同してはいないし、虚構の世界に移行してしまってもいない。
旅回りの一座が行う大衆演劇を見る観客が、主人公が活躍する場面で、歓声を上げたり、拍手したりすることがあるが、その客は舞台の上の出来事と日常生活を混同して、そのようなふるまいをしているのではない。その客は、そのようなふるまい方が大衆演劇を見る場合にはふさわしい、エチケットにかなった態度であるという、世間一般の常識、つまり「現実」を踏まえて、そのようにふるまうのである。彼/彼女は現実から少しも切り離されていない。
たしかに、劇を見ている間、その人のほかの領域における現実、仕事のことや家庭のことを忘れているかもしれない。しかし、彼/彼女の現実生活は仕事と家庭だけから成り立っているのでなく、たまに劇を楽しむこと、あるいはときどきウォーキングをしたり、友達とお茶を飲みながらおしゃべりをすること、あるいはデモに行くことなどなど、多くの現実から成り立っている。しかし、彼/彼女は、それらの現実の行動をおこなっているからといって、すべての他の現実のことを同時に頭におきながらそうするのでなく、多くの他のことは忘れて、いまこの行動を行う。演劇を見ている場合にも同じである。彼/彼女は今、演劇を鑑賞し、余暇を楽しむという、彼/彼女の生を構成している現実の一部を生きているのである。そして時には見ている劇のある場面ではそれに関連した仕事を思い浮かべ、何かメモを取ることがあるかもしれない。劇がそれほど大したものでなければ席をはずして仕事の電話をかけるかもしれない。
現実と虚構は全く別のものであろうが、現実を構成するもろもろの活動は別々に切り離されてはいないだろう。現実が遊びあるいは余暇活動と仕事に大きく区分されることはまちがいないが、遊んでいても仕事のことを常に考えている人もいるだろう。だがまた第2節で見た露伴の友人石井研堂のようにまだ「執務中」なのに、早退して釣りにでかけようかどうしようか迷い、仕事が手につかないでいることもあるかもしれない。遊びの中に仕事についての意識が、また逆に仕事の中に遊びの意識が入り込んでくることがある。仕事が人を遊びから完全に切り離すことはないし、また逆に遊びが人を仕事から切り離してしまうこともない。遊びと仕事の関係は虚構と現実の関係とは異なる、と考えられる。
劇を行ったり鑑賞したりすることは、釣りをしたり、野球をしたり野球の試合を観戦したりするのと同じように、遊びを楽しむ一つの方法である。遊ぶこと、余暇活動は仕事やその他の活動と同じく彼/彼女の生を構成する現実の一部である。そして、ホイジンハへの反論で述べたように、遊ぶことはどこか虚構の世界に移ってしまうことではない。釣りをしたり、野球をしたりすることは、現実の世界のなかで行われる、現実的な活動であり、彼は自己自身のまま釣りをし野球をする。劇においても、自己自身のまま、劇を演じ、あるいは劇を鑑賞する。
仮面舞踏会など大人の遊びでは、子どものごっこ遊びなどとちがい、現実と虚構のくべつがはっきりしている。だが、劇とは少し異なる。その人は仮面をかぶることにより、フリをするのではなく自分の正体を隠そうとしているのであろう。その人は自分の正体が知られないかぎりで、何者でもないものとして好きなように振舞うのであろう。そして、そのひとが、仮面舞踏会では、全く別な人になったかのように、人格が変わってしまったかのように、振舞うならば、虚構の世界に入ってしまっていると考えることができるかもしれない。
しかし現代社会で生活をしているその人は、仮面舞踏会が遊びなのだということを忘れることはできないだろうから、かつて仮面の秘密が知られていなかった社会で仮面をつけ、憑依・トランスの状態で行動した人々のようには、ふだんと全く異なる意識状態に移ってしまうことはありえない。つまりこの人は仮面を着けて普段とは全く異なる振る舞い方をするかもしれないが、法律に対する重大な侵犯となるような行為、たとえば殺人などは行わないだろうし、その一時のパーティが終わった後に待っている普通の社会生活、仕事や家庭などの現実から、完全に切り離されてしまい、虚構の世界に移ってしまうことはないだろう。
それらは「喧嘩ではない」が、それは、それら戦いが私的個人的な恨みなどが原因あるいは動機になって行われるものではなく、また相手を傷つけあるいは完全に叩きのめし、やっつけることを意図し、目的にして行われるのでもなく、 ルールにしたがって行われ、基準に従って「勝ち負け」が判定される戦いだからであり、また管理・運営する公的団体や組織によって設定される「取り組み」や「試合」として行われるからである。
だが、ゲームであり、ルールにより暴力の種類やその行使のされ方が制限されているからといって、技を伴う特定の仕方で肉体的暴力を用いて相手を圧倒することが格闘技の目的であるかぎり、格闘技が現実の戦いではなく「虚構」の世界の中にあるものだと言うことはできない。それらは相変わらず、ロープの張られた現実のリングの上で、あるいは土俵の上で、しばしば怪我や骨折を負い、運が悪いときには死ぬこともありうる、肉体と肉体が激突する、本物の戦いである。格闘技は「戦いの遊び」である、あるいは「遊びの戦い」であるとするなら、ルールのある遊びはルールによって虚構の戦いになるわけではない。
相手を技と肉体的暴力によって圧倒することを目的とするのではない格闘技以外のスポーツはどうか。サッカーの試合は、戦争における軍隊と軍隊の戦闘ではなく、ゲーム形式の遊びの一種なのであり、「本当の戦闘ではない」。だがそうだとしても、サッカーの試合は、将棋のような「虚構の戦場」における「虚構の兵士」の戦いではなく、血も肉も供えた生身の人間が、現実の時空のなかでぶつかりあう戦いである。
それが、虚構の戦いだと考えると、選手がしばしば「本物の怪我」を負うという現実のできごとがどうして起こるのかがわからなくなる。(幼児のように)遊びを本物・現実の戦いだと勘違いして、あるいは区別かつかなくなり、真剣になりすぎたのだとか、あるいはまちがった勝利至上主義にとらわれた結果だというような説明しかできないようにおもわれる。だが、選手たちの怪我は間違いや、勘違いによって生ずるのでは全くなく、体を張って行う現実の戦いの真剣さのゆえに起こるのである。試合中にトラブルが生じたことをきっかけに本当の乱闘になってしまうこともあるが、それはまた別の問題である。ルールにしたがってゲームが行われても、戦いが虚構ではなく、戦い方に一定の制限が設けられてはいるが肉体の激突を伴う本当の戦いであるからこそ、しばしば怪我が生じるのであり、ときに本当の、つまり怒りから相手を殴り倒すことを意図した乱闘に発展することも起こるのである。
テニスや水泳や陸上競技に関しても、同じことが言える。それらはラケットでボールを打つ、あるいは一定の距離のコースの中を速く泳ぎあるいは走るという方式で勝ち負けを争う本物の戦いなのである。
遊びではなく、職業あるいは仕事の領域でルールに従って行われる、現代社会における戦いを考えてみよう。多くの科学技術者が、他人の研究を盗用しないなど一定のルールの下で、発明発見の競争を行っている。無数の企業が、商法や独占禁止法などの法律で定められたルールを守りつつ、企業の生命を賭けて販売競争、経済競争を行っている。政治家は、公職選挙法で定められた規則に従って選挙戦を戦う。すべて一定のルールのもとで一定の方法で行われる、現実の戦いであり、どこにも虚構性はない。同じようにプロスポーツの選手は、それぞれの種目のスポーツの試合で、そのスポーツ特有の戦い方でルールにしたがって戦い、よい成績を上げることで、金を稼ぎまた名声を手に入れるのであり、プロ志願のアマチュアの選手も同じように試合や大会で戦い、よい成績を上げ、プロへの道を切り開くのである。
これらの「戦い」においては、科学技術者同士、企業同士、あるいは政治家同士は、そして(格闘技ではない)スポーツの選手たちは、殴りあったり、もちろん殺しあったりはせずに戦う。だからと言って、それらは「虚構の」戦いではない。一定のルールに則った、一定の方式での「本物の」戦いである。これらが「本当の戦いではない」といわれる場合があるとすれば、ルールに反した八百長の類のインチキ、事前の取引、談合などが行なわれた場合であろう。(そしてボクシングや相撲が本当の戦いだから、エリアスが言うように「楽しい興奮」を味わうために、観客が集まってくるのだ。)
また、武器を持って集まるのではなく、法で禁じられていない言論による戦いに勝利することが政治権力の打倒につながり、「ペンが剣よりも強い」と言われたこともある。これは同等の者同士が「同じ土俵」で、同じルールに基づき、同じ方法を用いて戦う「アゴーン」ではないような戦いである。しかし、この言論による戦いは統治者がさだめた法に従って行なわれたものであろう。ホイジンハは約束や規則に従って行われた「遊びとしての戦争」についてふれていた。物理的な力や武器を用いて行われるかどうかにかかわらず、何らかの規則・ルールに従う、虚構ではなく、現実の世界の中で行なわれる「本物の戦い」はいくらでも存在する。
ホイジンハは中世のヨーロッパでは、諸侯間の戦争が、軍隊同士の戦闘の代りに、しばしば、一定数の戦士による決闘で決着をつけられていたことを報告している。決闘は一定の規則に従って行われる戦いであり、ホイジンハはこれを一種の遊び、闘技とみなした。血が流れるかどうか、殺し合いになるかどうかは、遊びであることを否定する基準にはできないと言っている。エリアスによれば、実際、古代オリンピアの祭典で行われた闘技であるパンクラチオンではしばしば死者がでた。パンクラチオンが、闘技であるというのはそれが一定のルールに従って行われた競技の一つであったからであり、本当の喧嘩、闘争でないと言う意味で、一種の「遊び」、play、演技と言える。(中世ヨーロッパの約束の下での戦争や古代ギリシャのパンクラチオンは、わたしが考える楽しみのための活動としての遊びとは違っているが、それらはルールに従う戦いであり、闘技であることは確かである。) これら闘技は、暴力行使を認める程度において現代のスポーツとは格段に差があり、カイヨワの意味での遊びと完全に一致するとは言えないにせよ、一定のルールのもとで、約束や協定に従って行われる、「遊びの戦い」であった。これらの戦いが、そのルールのゆえに、「現実を再現していない」「虚構の世界の出来事」と考えることは、決してできない。 こうして、格闘技もそのほかのスポーツも、現実世界の中で、人間が自己の身体を使って運動し行動するという点で、またその運動とその勝敗の結果がその活動を行う人の精神と身体に、明確な現実的影響を及ぼすという点で、現実的活動である。ルールのある遊び、スポーツは、ルールによって非現実の、虚構になってしまうことはない。
しかし、格闘技の場合には、選手は互いに相手に暴力を行使し、しばしば負傷を負わせることがあり、運が悪ければ、死なせてしまうこともある。スポーツの正式な試合以外のところでこうしたことが行なわれれば、それらの行為は、暴行、傷害、傷害致死などの刑事罰の対象となろう。その競技のルールに従って行為している限り、それらの行為は暴行や傷害の責任を問われることはない。カイヨワが「通常の法律を停止し、その代わりに、それだけが通用する新しい法律を一時的に立てる約束に従う」と言っているのはこのようなことを指すと思われる。
格闘技ではなくても、ラグビーやサッカー、あるいは野球でも、選手がルールに違反して、危険な行為を行なうことがあり、時に選手同士の乱闘も起こる。これら行為も「通常」の生活の中では「警察沙汰」になるだろうが、試合最中の行為であれば審判により「退場処分」を受けたり、あるいはその競技の協会や組織委員会の処分を受けたりするのであって、「通常の法律」によって直接裁かれるのではない。
ただし、アマチュア・スポーツの場合、つまりカイヨワの言うアゴーンの場合には、格闘技以外には、その競技のルールの範囲内の行為であれ、ルールに違反する行為であれ、暴行や傷害が起こることは比較的少ないであろう。だが、スポーツ選手は、種目によっては、その種目のスポーツのルール「だけが通用する〔という〕新しい法律を一時的に立てる約束に従う」とカイヨワは考えるのであろう。
賭けマージャンなどにもこの定義が該当するように思われる。法律では賭博行為は禁じられている。掛け金の額があまり大きくない限り処罰されることはないようだが、法律が禁止しているということは確かである。しかし、学生でもサラリーマンでも賭けないでマージャンをすることはほとんどないと思われる。賭けマージャンは、その都度レートを決めてから行なう。したがって「通常の法律を停止し、新しい法律を一時的に立てる約束に従う」のである。
しかし、このようにルールに従うある種の遊び・スポーツが「通常の法律を停止し、新しい法律を一時的に立てる」ことになるとしても、この状態の下で行われる活動が「虚構」のものであるということにはならない。それらのルールはそれにしたがって遊ぶ人々、選手たちに、現実的な効果を及ぼし、たとえばスポーツの試合で大怪我を負ってもその相手に治療費や賠償金を要求することはできないだろうし、あるいはマージャンでは勝てば相手から金を巻き上げることができ逆に負ければ素寒貧にさせられる。
(日本の)刑法35条には「正当な業務」による行為は、たとえ刑罰法規に触れる場合であっても「違法性」が阻却され処罰されないという規定がある。例えば、人を殺すことは殺人罪の構成要件に当たるが刑務官による死刑の執行は罰せられない。他人の身体を傷つけることは傷害罪に当たるが、医師の行なう外科手術は「正当な業務」であって処罰されない。同じくプロのボクシング選手や相撲の力士の正規の試合や取り組みにおける多くの行為は、暴行罪や傷害罪の構成要件に該当するが「正当な業務」と見なされている。
だから、スポーツ選手、とくに格闘技の選手は、暴力や傷害を禁じる刑法の規定に反する、彼らの内部でだけ適用される特別のルールに従ってプレーするが、だからといって彼らは刑法自体に反する、違法行為を行うのではなく、刑法の別な規定に従って正当な行為を行うのであり、かれらは法律を停止したり廃止したりしているわけではなく、彼らが法律にしたがっているということには変わりはないのである。
こうして、規則のある遊びは、その規則によって、法律による規制を受けている現実世界とは異なる非現実、虚構の世界に移行してなされる活動ではなく、他の活動同様、法律の大枠の中でなされるものである。遊びの世界も他の諸活動と同様、法律よって規制された社会的世界の中の一つの活動領域である。
(追加 2017.5.22)
上で、カイヨワが「通常の法律を停止し、その代わりに、それだけが通用する新しい法律を一時的に立てる約束に従う」と言っていることに関して、
「格闘技ではなくても、ラグビーやサッカー、あるいは野球でも、選手がルールに違反して、危険な行為を行なうことがあり、時に選手同士の乱闘も起こる。これら行為も「通常」の生活の中では「警察沙汰」になるだろうが、試合最中の行為であれば審判により「退場処分」を受けたり、あるいはその競技の協会や組織委員会の処分を受けたりするのであって、「通常の法律」によって直接裁かれるのではない。」と書いた。また、
「アマチュア・スポーツの場合、つまりカイヨワの言うアゴーンの場合には、格闘技以外には、その競技のルールの範囲内の行為であれ、ルールに違反する行為であれ、暴行や傷害が起こることは比較的少ないであろう」と書いた。
しかし、私の上の文では、試合中の行為が、その競技で通常考えられる危険を超えたものとなる場合については考えておらず、どんな行為でも試合中の行為は「正当な業務」であるかのように受け取られるかもしれない。認識不足のところがあり、追加・修正しておきたい。
2017年5月23日朝日新聞の記事によると、地域のソフトボールの親睦大会で、捕手の女性と本塁に滑り込んだ男性走者が衝突し、捕手はひざのじん帯を断裂。裁判で男性に約100万円の損害賠償命令がなされた。一審判決で、二審について記事は触れていない。
またサッカー・アマチュアリーグの東京都社会人4部リーグに属するチーム間の試合中に、ボールをけろうとした選手が、相手チームの選手の行為(スパイクシューズの裏が接触)により脛を骨折。ファウルにはならなかった。手術などで計約1か月間入院。2015年、約690万円の損害賠償を求めて提訴。東京地裁は「退場処分が科されることも考えられる行為だった」として、相手選手に慰謝料や治療費など約250万円の支払いを命じた。被告側は控訴した。
また、関東医歯薬大学ラグビーリーグで、ジャージを掴まれて引き倒された〔これはルール上認められてない行為のようだ〕選手が地面に頭を打ち、脊髄損傷で重い後遺症を負った事例では、東京地裁は14年に「通常生じ得る範囲を超える危険までは」スポーツ選手は「引き受けていない」として、相手選手に9700万円の支払いを命じた。
これらの記事を読むと、ルールで禁じている、試合中に生じる「通常の範囲」の行為は、競技団体の内部で、その団体の規定に従って処理される。つまり、裁判に訴えられることはない。しかし、「通常の範囲を超える」場合には、試合中の接触という「正当な業務」とは認められず、法律によって直接判断されるということであろう。
(2018.6.1.追加)
2018年5月、アメリカンフットボールの試合で、日大選手による悪質なタックルで関学大選手が負傷・退場する事件が起き、マスコミで連日大きく取り上げられた。関東学生連盟は日大チームの監督とコーチが当の選手に相手選手をケガさせることを指示したと認定して、監督とコーチを「永久追放」という最も重い処分を科した。5月30日付朝日新聞などによる。
関東学生連盟は、日大選手の行為(を指示した監督、コーチらの行為)は「通常の範囲を超える」重大な違反行為だと認定したということである。被害者の告訴が警察により受理されたことも報道された。
この事件も、試合中の行為といえども「通常の範囲を超える」場合には、試合中の接触という「正当な業務」とは認められず、法律によって直接判断されるということの例である。
なお、カイヨワの「遊びのルールは通常の法律を停止する」という主張は誤りで、「規則のある遊びは、その規則によって虚構の世界に移行ししまうのではなく、他の活動同様、法律の大枠の中でなされる。遊びの世界も、法律よって規制された社会的世界の中の一つの活動領域である」という私の主張にはなんの変更の必要もない。
中村敏夫『スポーツルールの社会学」(朝日新聞社、1991)では、19世紀初頭の英国では、まだ、競走において「ところどころぬかるみがあったり砂利道であったりした道路をブーツをはいて走っていた」こと、また日本の1897(明治30)年の『野球』という本に付されているルールの解説27条には、ボールが草むらの中あるいは深い穴に落ちてすぐにとれなくなった場合にどうするかが規定されていたことなどが書かれている。
中村は言う。「少なくとも近代化が顕著に表れる以前」の社会においては、競技は「人々の日常生活の中における自然の成り行き、あるいは出来事のように行われることが多く」、レースやスポーツには「自然とか人間らしさが含みこまれていた」。しかし記録主義や勝敗主義が強まり、そして技術革新の成果の利用が進む中で、スポーツは「競技空間」と「人間」を徐々に変質せしめ、「人為性と人工性」を強めた、と。
遊び/スポーツに起こったこのような変化を文明化や進歩と見るとすれば、昔の「日常生活の中における自然の成り行き」とさほど違わない、「人為性と人工性」の少ない遊びは「十分には」遊びではなく、後に進化・発展して、始めて本格的な遊びになると考えることになるだろう。こうして、カイヨワは、彼の言葉を用いれば、「あらゆる明確な特徴の以前にある」日常生活の他の行動とさほど違わない、パイディアは「固有の名称によってその自律性を認めえない。しかし、約束、技量、用具などが現れると、そこに、特色の明らかな最初の遊びが出現する」と言う。単なる不定形の衝動が洗練され、形が整い、ルールをはじめとする人為的な工夫が加わることによって、はっきりとしたカテゴリーによって分類可能な「遊び」に進化する。つまり人為的なルールによって遊びの条件や形式が整っている完成形態にある遊びが「遊び」であり、日常生活の中で自然発生的に生まれ、そのままの状態にとどまっているような「ルール」のない「不定形」の遊びは遊びではないか、その原型でしかない。ルールはその内容が、自然から、日常的現実から離れれば離れるほど完成度が高いものだということになる。
他方、カイヨワは次のように述べている。「競争とは勝者の勝利が正確で文句のない価値を持ちうるような理想的条件の下で競争者たちが争えるように、平等のチャンスが人為的に設定された闘争である」。アレアにおいても、アゴーン・競争の場合と同様に公平の原理が求められるが、「前とは違った仕方においてであり、また、ここでも理想的な条件の下で発揮されようとする」。「アゴーンとアレアとは反対の態度、いわばシ〔ン〕メトリックな態度を表しているが、両者は同じ掟にしたがっている。すなわち、現実が人々に拒んでいる純粋に平等な条件を遊ぶ人々の間で人工的に創造する、という掟である。なぜなら、人生においては明確なものは何もないからである。---アゴーンにせよ、アレアにせよ、遊びというのは現実生活の常である混乱を完璧な状況によって置き換えようとする企てである」。こうしてアゴーンやアレアの遊びにおいては、公平の原理が、人工的に創造されたルールの形をとって、現実とは異る理想的な仕方で働くとされる。
また次のような文もある。「幕が下がり、ライトが消えれば、彼〔役者〕は現実に戻る。二つの世界の区分は、--絶対的である。同じように自転車競技やボクシングやテニスやサッカーのプロ選手にとっても、競技、試合、競走は常にルールと形式のある競争である。それが終れば---選手はまた日常の心配に戻る。彼は、自分の利益を守り、快適な将来を確保できるような方策を考え、実行しなければならない。競技場---を離れた途端に、----はるかに恐ろしい、競争が現れる。この競争のほうは、陰険で、絶えることなく、過酷で、彼の人生の全体に浸透している」。
こうして、カイヨワの説明によれば、現実は極めて無秩序、不確実で、恐ろしい。それと対比して、遊びの世界を支配する規則が目指しているのは、完全な公平、理想的な秩序を与えることである。つまり現実にはあり得ない、理想を追求するのが遊びのルールである。現実にあり得ないものは「虚構的」である。カイヨワはそのように考えてルールは虚構を作り出すと言ったのかもしれない。
私は、遊びの規則は完全ではなく、しばしば変更されるものであると、すでにホイジンハの主張に反論しつつ述べてあるが、別な例をあげてここでも一言反論しよう。実際のスポーツに全くの素人である私の知る限りでも、野球では、ストライクとボール、アウトかセーフかの判定をめぐってしばしば紛争が生じ、審判の公平性が問題になるという。ボクシングとは異なり相撲では重量別のルールがなく不公平がまかり通っている。(と言っても、舞の海のような小柄の力士が大柄で力のある力士を負かすのを見るのが楽しいというファンも多いはずで、見る「スポーツ」としては公平さがすべてではないが。)カイヨワ自身、「けれども、絶対的平等ということは、どんなに入念に設定しようとしても完全には実現できない」と言って、チェスでは先手が有利になる等々、具体的例を挙げて説明している。
そして、すべての遊びが「理想状態」で行われるのではないように、すべての「日常」、「現実」がホッブスの言ったような「万人の万人に対する闘争」状態にあり、「人は人に対してオオカミ」であるわけではない。カイヨワは遊びの世界、とくにアゴーンに、よく整ったルールと秩序が存在することを強調するために、現実の人生を「無秩序」の灰色一色に塗りつぶしているように思われる。大学の入学試験のやり方、選挙制度、商法等々の現実とスポーツのルールとを比べて、一方の現実生活が全き「混乱」であって、他方の遊びが「純粋で」「完璧」で、したがって「虚構」と呼ぶべきものだとは主張できないと思われる。
競馬では馬券を買う人と実際に走る馬とは別である。しかし、馬券を買う人は、それ以前のレースの成績を参考にして、ある馬が勝つと考えて馬券を買う。これが賭けるということである。彼/彼女が考えたとおりの成績をその馬が収めてくれれば、彼/彼女は賞金を受け取ることができる。
写真は中山競馬場。HP『馬道楽』「競馬博物館」http://umadouraku.com/museum_top.phpの「競馬場紹介」による

大学入試では、「賭ける」方法が少し違う。親が賭けるという要素も多少はあるが、主として受験生が自分に賭けるのである。彼/彼女はこれまでの自分の勉強の仕方、模擬試験での成績などから、この大学なら、確実とは言えないが、受かりそうだ、あるいは受かる可能性があると考えて、受験するのであろう。安くない受験料あるいは交通費を払って、あるいは、もしかしたら、合格の見込みがより高い、同じ日に入試が行なわれる他の大学を受けるのをやめて、この大学を受けるのであり、馬券を買うのと同様、失敗すれば、相当の犠牲を払うことを覚悟して受験するのである。
受験生の学力が大学入学試験という方法で判定され、入学を許可されるということも、馬がコースで競走して順位がきまり、当たり馬券を買った人に賞金が支払われるということも、どちらも、不確実なことに金を賭けることであり、一方だけが現実的で他方は非現実的、虚構的だというような違いがあるとは思われない。どちらも理解可能で、一定の合理性を持った行為である。
宝くじや競馬のような運の遊びを虚構的と考える理由が私には見当たらない。当たった時の賞金が本物のお金ではなく、ぴかぴか光るおもちゃの貨幣で支払われるというのなら、その賭けは純粋な遊びであり、「虚構」だということになろう。しかし、純粋な偶然で当選が決まる宝くじも、インチキが交じっているかもしれないカジノも、かなりの程度実力で稼げるパチンコや競馬も、その当たり外れ、あるいは勝ち負けの結果は全く本物の世界に属している。当ればもらった賞金で仕事を休んで贅沢ができるが、負けが込んで借金が返せなくなれば、刑務所に入らなければならなくなる。すべて現実世界に起こることである。
カイヨワはカジノや宝くじや競馬が「諸国民の経済と日常生活に重要な役割を果たしていると」言っていた。これら偶然の遊びが遊びとして虚構の世界に属するものであるとすれば、どうしてそのような役割を果たすことができようか。掛けられた金はおもちゃの紙幣でないから、国のあるいは自治体の収入になり、使途に応じて支出することが可能となるのだろう。
遊園地のジェットコースターが与えるめまいは、人為的に知覚を混乱させる仕組みによって与えられるものであるが、その眩暈は虚構ではなく、現実である。眩暈、(逆さづりの)苦痛や恐怖が大きな地震や船酔いのような自然的原因によりおこったものでなく、遊園地の機械に自分から進んで乗ることによっておこったものであるにせよ、それらは、必ずしも一部の若者のようになんの眩暈も恐怖も感じずにただ楽しいと感じられるわけではなく、(乗る前の予想を超えた)実際の眩暈、恐怖、苦痛を(三半規管の働きの衰えた)中年以上の人間には与えることがありうる。一般に人為的に作られた条件が生み出す効果はそれが人為的だという理由で「虚構」だということはできない。現代世界において自然的なものはほとんどなく、われわれは人為的に生殖に介入し、予防接種を行い、手術をし、人の死に様々な区別を設けている。人為的に室内温度や湿度を調節する。ある状態が人為的に作り出されるということを以ってその状態が「虚構」だということはできない。イリンクスの遊びのかなりの部分は、ある人々にとっては現実的な苦痛、恐怖であるようにも思われる。
また、カイヨワが遊園地の遊びと同じく「イリンクス」に分類する、登山に含まれる危険、「スキーやオートバイやスポーツ・カー」のスピードが引き起こす眩暈はどうか。ここでは障害や危険を克服し、あるいは眩暈に打ち勝つことによって、自己の技量を楽しもうとする、遊ぶ主体の態度がまずあって、それがわざとその危険や眩暈を求めさせている。その活動は、日常生活や職業の中で生じた危険や障害に対処する必要から行なわれる活動なのではなく、その「危険」はやむを得ないものとして降りかかったものではなく「人為的」である。
だが、それにもかかわらずその危険は事実である。崖や急斜面で少しでも油断したら転落して大怪我をするかもしれないということは、消防士やレスキュー隊員が職業上の必要から行なう行動における危険と同じく現実的なものである。だからそれを「虚構」と呼ぶことはできない。このように言えるとすれば、そして、仕事や生活上必要な状況のなかで行うのでない活動、つまり遊びそのものを「虚構」と定義するのでない限り、眩暈を求める遊びも眩暈を伴うような危険を克服する遊びも一般に「虚構」であるとは言えない。
ホイジンハの考えに反論しながら述べことだが、遊びの世界が時間的空間的に閉じられており、現実世界から断絶した虚構の世界であるとは言えず、両者はともに、ある点からいえばどこまでも無限定に広がり、また別な点からみれば限定されており、遊びの世界はその根を現実世界のなかに生やしており、両者は結びついている。とはいえ、両者のあいだに違いもある。というより、遊ぶ場合と、そうでない場合、つまり仕事を中心とした「現実」世界における活動を行なう場合とでは、振舞い方や態度において違いがあると人は感じる、あるいは考える。どう違うのだろうか。
ホイジンハも言っていたが、現実世界あるいは仕事の世界はまじめないし真剣さを要求するという点で、遊びをそれらの世界と区別することはできない。ふざけていたり、真剣でなかったりすれば、できない遊びもたくさんある。たとえば、遊びの一種、競技スポーツのほとんどはアマのそれにおいても、仕事と同様にか、それ以上に真剣に、まじめに行われるだろう。遊びと仕事の違いはそこにはない。
遊びは、カイヨワも認めていたことだが、行うことも行わないことも自由にきめられるという点にその本質的特徴があると私は考える。そして、仕事はいったん始めたら勝手にやめることができないのに対して、遊びはいつでも、飽きたら、あるいは他の用をたす必要が起こったら「やめて立ち去る」ことができる、と大体は言える。
もし、遊びそのものが、あるいは遊びの形式的構造が、遊ぶ人の意思に関わりなく、人を現実世界から「切り離す」、つまり現実社会への客観的、主観的関わりを断ってしまうのであるなら、ゲームをいったん始めた人は、現実社会になにが起ころうとも、そのゲームが終わるまで止めることができないであろう。だがそのようなことは普通は起こらない。ギャンブル依存症の人のようにゲーム依存症というものがあれば別だが、普通は、遊びを始めても、何か急ぎの用ができれば、途中で遊びを打ち切り、その用事を足す。それは遊びがその人の意思で始められ、したがってまたその人の意思で止めることができるからである。だから、遊びが人を「現実世界から切り離す」のではなく、遊ぼうと考える人が仕事や義務からいったん自分を切り離し、遊ぶことに決めて遊ぶのである。(そして、遊びの世界は虚構ではなく現実なのだということをすでに示した。)
カイヨワは、チェス、あるいは劇のような特定の遊びだけを念頭において、遊びに移行する際に起こる態度の変化を「現実からの切り離し」と呼んだ。だが、今私が言った意味での「現実からの切り離し」であれば、ルールの有無、遊びの種類にかかわらず、常に起こることである。そして遊びではなく単なる休息を取るのことによっても「切り離し」は起こる。
したがって、他の状態から遊びへの移行、あるいは遊びによる「現実からの切り離し」は、遊び自体、あるいは遊びの形式的構造が作り出すのではない。人々に自由を許さない拘束的なルールや義務が支配する仕事の世界、「慣例化」された社会があり、そこから人は休息や遊びによって逃れる。遊びはそれ自体何もしてくれない。遊ぶことを選び、遊びの世界に移行することを可能にするのは遊ぼうとする人の意思である。
以上が認められるなら、遊びとはルールあるいは演技により作り出される虚構であり、遊びと現実はその虚構性によって切り離されるという主張は成り立たない。遊びの活動とそれ以外の活動、「現実」との違いは、遊びがもつという「虚構性」にあるのではない。違いは、遊びが義務や必要によって行なわれる活動ではなく、自由に楽しもうとする態度によって行なわれる活動だというところにある。職場における仕事/労働と、家庭で自分で必要と感じて行う仕事/労働も異なる。そして仕事/労働と遊びも異なる。しかし、遊びをはじめることによって何か非現実の世界に突然入り込むわけではなく、「現実から切り離され」てしまうわけではない。彼は仕事/労働の現実の活動をやめ遊ぶ現実の活動を始めるだけである。
仕事における業績も遊びにおける結果もどちらも彼の生の一部である。他にやりたいことがあるのに、弁当代を稼ぐというだけのために我慢して2時間いやな仕事をやったからといって、その2時間が彼の人生を空白にするわけではないというのと同様に、2時間の遊びが彼の生を2時間空白にすることはなく、喜びを与え、時に退屈を、ときに苦痛を与え、長期的に見られた彼の生にとって、プラスをもたらしたりマイナスをもたらしたりして、快苦の総計を変え、幸福の度合いを変えるであろう。この快苦の大きさの計算は、仕事で感じる快苦と遊びで感じる快苦の評価の仕方、つまり仕事と遊びをどのように価値評価するかということで異なるであろう。
人生における遊びの意義を小さいものだと考えている人は、遊びのなかで感じた快苦をすぐに忘れるが、たとえば、金銭における損得、仕事における成否はいつまでも気にかけるだろう。仕事が人生の目的だと考えて生きている人の場合に、日々の仕事に始まりと終わりがあり、転職がなされたりしても、仕事がその人の生の主要な部分を構成するものとして退職まであるいは死ぬまでつながっていると感じるであろう。仕事は連続しており、遊びはときどき、ごく短時間、仕事の日常のなかに「割って入る」だけだと感じるだろう。
プロとして稼げるようになることを目指しているかどうかにかかわらず、若いときだけでなく、一生にわたり趣味やスポーツを継続して行っている人がいると思われる。この人々にとって、趣味・スポーツと他の日常生活が切断されているとは決して言えない。平日には生活のためにやむを得ず仕事をするが、人生は本来楽しむためにあり、休日にこそ、自分の人生があると考える人もいるであろう。そして休日だけでなく、週に何日も、仕事を終えた後の時間を好きな趣味・スポーツに当てる人もあろう。マラソンをやっている人の中にはそういう人がかなりあるようだ。そして、一定の年齢に達して、年金生活を送る退職者なら、炊事その他に必要な時間を除けばすべての時間を遊びにあてることができる。
仕事は従であると考え、遊び・趣味の活動に重点を置いて生きている人の場合には、スポーツの一回ごとのトレーニングや一つ一つの試合やゲームに始めがあり終わりはあっても、また趣味の活動の種類が変わることがあっても、その趣味やスポーツの断続的な時間は彼の生の中でつながっている。
エリアスは、「現実性」は「コミュニケーションの規律に従うすべての人間活動の属性」であり、「非現実性」は「他人に共有されないすべての個人的幻想」のことだと言い、コミュニケーションを通して行われる「すべての人間活動」は「現実的である」という。「余暇と非余暇は人々の集団によって相互に、異なった規則に従って行なわれる。余暇においては、---幻想や感情が---非余暇的生活におけるよりもより多く許されていることは明らかである。〔しかし〕それらは社会的にパターン化され、伝達された幻想であり、演劇、--フットボールの試合、---競馬、ダンス---へと結晶化した幻想である。純粋に個人的で社会化されていない幻想と対比して、それらはそこに〔複数の、他の〕人間が参加しているという点で、自由時間における子どもや妻の世話と同じく、〔また〕---〔職業〕労働と同じく、現実的である」。私はこの説明が極めて正しいと思う。
エリアスでも遊びは、遊びと区別される日常生活という「現実」に多少は似た、しかしまたそれとは異なる環境において行われ、「現実」の出来事が経験させるのとよく似た「模倣的」経験を与える。しかしエリアスはこの遊びという活動が全く「現実的」であることを強調する。一緒に遊ぶ複数の人はあるルール(仕事のそれとは異なる)を共有して遊ぶが、エリアスは仕事も一種のゲームだという。人々はさまざまな限定された生活領域、で異なる種類のルールを共有して、ゲームを行う。人々が言語、ルールを共有して行う活動は、すべて現実的だとエリアスは言うのだ。
したがって、結論的には次のように言える。演ずる遊びは現実に似せた、虚構の世界を作り出す遊びであるが、その遊びを行なう人も、見てそれに参加する人も、決して虚構世界に移ってしまうことはなく、演じ、見て楽しむというしかたで現実の生を生きるのである。将棋のような、規則のみによって成り立つように見えるある種の遊びにも部分的には虚構性が認められる。しかし将棋で遊ぶ人あるいは戦う人は、現実世界の中で、ほかのことに用いることもできる同じ時間を使い、頭脳を働かせて「格闘」し、その勝敗の結果に喜んだり悔しがったりする。
しかし、規則にしたがって行われる遊びが一般に、虚構的であるとは言えない。そして、遊びには、他の人間と一緒に演じるのではない遊び、他の人間と勝敗を争うのでも競争するのでもない多くの遊びがあり、そこでは、一般に、規則を持たず、約束や規則に従うわけではなく、現実の自然的世界のなかで現実の対象と向き合う。
ところがカイヨワは(またホイジンハも)、遊びのもつ、部分的な虚構性のゆえに、遊びはすべてフィクション・虚構だと考えてしまった。しかし、遊びがすべて虚構性を持つとみなすこと、そして遊びと、それ以外の日常生活における諸活動との違いを前者が虚構性をもつ点にあると捉えるのは間違いであった。また、遊びの虚構性という見方と関連する「ルールの理想性」あるいは遊びの「人為性」の重視は、不当にも、ルールを必要としない自然的で自然発生的な遊びを排除してしまうか、独立したカテゴリーの遊びではない、単なる原初的な、不定形の騒ぎでしかない「パイディア」の領域へと追いやることになる。
こういうわけで、自然の中で、自然物と対峙して行う、ルールのない遊び、したがって釣りは、カイヨワの4つのカテゴリーには属さず、実際、その遊び方や特徴が論じられていないだけでなく、「釣り」という名称すら登場しない。私は次の章で釣りを他のスポーツや遊びと比較し、また、釣りの面白さについて詳しく述べたいと思うが、ここで、彼の言葉や語を用いて、釣りという遊びの特徴をアトランダムに上げてみる。
私は、暖かな天気の好い時に、一人で、のんびりと釣り糸を垂らすのが好きだ。東京で始めた防波堤での釣り以来、ほとんどいつも一人で行う。好釣の時にも人に見てもらいたいとは特に思わない。釣れないよりは釣れた方がいいし、たくさん釣れればなおいい。しかし、釣技をとくに高めようとは考えない。釣りは、他のスポーツのように技を高めるために、レッスンを受けたり、実際にプレーを楽しむのとは別にトレーニングを行なったりすることはしない。釣りに通っているうちに少しずつ経験を積んで自然とうまくなる。他の人と競争するために、技量を高めようとはしない。自分で楽しめばそれで十分なのである。
釣りは、人間を相手とするゲームではなく、ルールなしに、きまった大きさのコートも一定のコースもないところで、昼でも、夜でも、好きな時間に、自分の使いたい道具を使って、魚を釣ろうとする遊びである。
釣れないで、ぼんやりと時間を過ごす時に、空想に、あるいは幻想に浸ることがある。しかし、釣りには空想的な要素は全くない。釣り、つまり魚との駆け引きや格闘は、風が吹き、太陽が照り付け、波で体が揺れる、現実の時間・空間の中で、行われる。将棋や囲碁では王が詰んだり、大石が生きたり死んだりするが、その「詰み」や「生死」は、ルールとともにすべて頭の中で起こっている「非現実」・「虚構」である。しかし釣りあげた魚が船の上でばたばた跳ねて「生きて」おり、ときにヒレの棘で釣り人を刺して復讐するが、それらには虚構性や非現実性はかけらもない。
カイヨワは遊びが自由な活動であることを強調する。そして、遊ぶ人は好きな時に「もうやめた」と言って、立ち去る自由をもっているという。しかし、アゴーンのような相手のある遊び、あるいは観衆や仲間の前で自分の技を見せるために遊ぶルドゥスでは、勝手にやめて立ち去ることはエチケットをわきまえない行為として周囲の非難を浴びるだろう。だが釣りは、いつでも好きな時にやめることができる。
自由な活動だということが遊びの最大の特徴であるとするならば、釣りこそ、あるいは釣りに似て、一人で自然を相手にして行う遊びこそ、遊びと呼ぶに最もふさわしい活動だということになりそうだ。
次に米国の社会学者チクセントミハイによって書かれた『楽しむということ』(今村浩明訳、思索社、1991)を読んでみる。原著Beyond Boredom and Anxiety(直訳すれば「退屈と不安を超えて」である)は1972年に公刊された。前節でふれたデュマズディエの『余暇文明へ向かって』の公刊の10年後である。 邦訳は2001年には『楽しみの社会学』と改題され、新思索社から出版されている。
なるほど、長時間不愉快な仕事をし、ごくわずかな時間だけ、その代償としてスポーツや遊びを行うというのは、人生の望ましいあり方では決してない。しかし、生活のすべてを楽しいものに変えるというチクセントミハイの提案は実現可能なのだろうか。自分の楽しみのために、自由に、好きなように行なうことのできる遊びやスポーツの場合と、他者に対する責任を伴い、真剣さを要求され厳しくても当然であると考えられている仕事の場合とでは本質的な違いがあるのではなかろうか。
だが、チクセントミハイによれば、そもそも、世の中の常識になっている「真剣な勉強や仕事は厳しく不愉快なものである」というのは事実なのではなく「仮定」なのだ。もし、本来的に、あるいは本質的に、仕事や勉強が厳しいものだとすれば、それを楽しいものに変えることは不可能である。しかし、決してそうではない。
米国などで「現在行われている行動の管理は、人間は外発的報酬〔ニンジン〕や外発的処罰〔ムチ〕に対する恐れによってのみ動機づけられるという暗黙の信念に基づいている。---そこで生後間もなくから、子どもたちは親の要求に適合するようにおどされ、おだてられる。学齢期になると、---成績や象徴的な奨励が利用される。---ほとんどの人が成人に達するまでに、金銭と地位という象徴的報酬によって一般的に代表される、外発的な手掛かりに反応するよう条件づけられてしまう」という。子供たちの勉強は、楽しく行うことができるような工夫がなされないまま、あるいはまた勉強は、例えば、(様々なことが自由に行えるようになる)本人の諸能力の発展成長を促す、望ましい愉快なことであるのに、そのことを子供たちに教えずに、成績が上がったら褒美がもらえ、下がれば叱るというしかたで、押し付けられてきたというのである。
「金銭や地位のような外発的報酬は人間の基本的欲求---であるということは常識的な仮説である。---しかし、物的財貨をもとめようとする努力の大部分は、一つの文化への社会化として、個人が学習する動機づけの一つにしか過ぎない---。所有欲は普遍的な特性ではない」。
チクセントミハイはさらに言う。「遊んでいる子供たちを立ち止まって眺めたことのある人は誰でも、内発的報酬がいかにして可能なのかがわかるであろう。---子どもたちはほとんどの時間を彼らの技能が行為への挑戦の機会に適合している水準での、環境との相互作用に費やしている。---彼らはその挑戦をしつくしたとき、また技能をふるいつくしたときにのみ、その行為を止める」。そして子供たちが行っていることを「遊び」とみるのは、「定型的な大人の知恵の視点から見た場合」のことにすぎない。「彼らのしていることを仕事と呼ぶこともできる」。子供には、環境に挑戦し、何であれ、できそうに思われる範囲の事に自分の有する技能を行使して対処しようとするという、内発的動機が存在するだけで、つらく厳しいものとしての仕事、そして楽しいだけの遊びという区分は存在しない。
成長とともに、自由な挑戦への機会は次第にはく奪され、「また同時に、社会的価値が、子どもの自分の行為についての解釈に影響し始める。〔社会的に見て、あるいは資本主義的工業社会から見て〕なんの具体的な成果をももたらさない努力は、時間の浪費と烙印を押され、子どもは外発的報酬をもたらす課業に精出すようにのみ奨励される」。
彼によれば、仕事/労働と遊びとの本質的絶対的な区別が存在するのではない。すべての活動は環境への挑戦であり、その結果がもたらす社会的あるいは経済的価値が大きい時に仕事と呼び、それらが(少)ないか、成果が個人的で非経済的価値しかないときに遊びと呼んでいるのだ。
そして、楽しさは遊びにおいても仕事においても見出すことができる。人間が行う活動に線を引いて二種類に分けようとするとき、その線は遊びと仕事との間に引かれるべきでなく、楽しい活動とそうでない活動の間に引くことができるし、そうすべきだ。仕事であれ遊びであれ、まず、楽しさを与える活動の構造を見出し、この特徴を指標とする「楽しさの理論モデル」を作る。このモデルに適合するように他の活動を構成し編成することができれば、遊びであれ仕事であれ、あるいはそれ以外の活動であれ、(現在の社会が採用している)分類の仕方による活動の種類によらず、活動を楽しくできるはずだ。これがチクセントミハイの考えるところである。
ムチとニンジンによって人を動かそうとする社会、外発的報酬に依存する社会は決して望ましいものではない。外発的報酬に依存する社会システムには二つの重大な問題点があるとチクセントミハイは言う。
ひとつは、すでにふれた「高度産業国の労働者に見られる根深い疎外感」である。1960年代以降はっきりしてきた「この矛盾を単に、豊かさから生ずる一時的な結末としてかたづけるわけにはいかない。」一部の論者は「労働者は仕事の心配のないときにのみ不満を抱くと考えていたようである。つまり欠乏や失業の時期には、人々はたとえ仕事が退屈で無意味なものであっても、生活のために嬉々として働くというのである。
しかし、仕事におびやかされている労働者たちは、彼らの欲求不満の捌け口を、より破壊的な方法に求めるということのほうがむしろありそうなことである。大不況のとき、ドイツの労働者たちは仕事を豊かなものにする運動を展開せず、進んで世界征服という大勝負にでたのである」。社会が重大な危機に面した際に、労働者の日常的な疎外感がどのような方向に発展するかはわからないと、チクセントミハイは心配している。
だが、彼は、もう一つの重大な問題があるという。「資源と物理的エネルギーが必要を満たすことにのみ用いられず、---空虚な仕事の補償となる象徴的報酬として用いられるとき、浪費が始まる」。「もしわれわれの営為のすべてが物的報酬を得るためになされるとすれば、われわれは地球と人間とを共に枯渇させることになるであろう」。これは1960年代末、ローマクラブの委託によるMITグループの有名な研究報告『成長の限界』などが問題にし始めていた事柄である。チクセントミハイは自分の研究「の目的は---生態学的に健康な活動の探求を始めることにある」と言う。
チクセントミハイは労働過程を楽しい(フローの得られる)ものに変えることにより、労働者の不幸感・不満を除去し、かつ地球の生態学的危機をも乗り越えようというのだ。
これまで見たところでは、彼は、人間は物を作り、働くことを本質とするホモ・ファーベルだという人間観、人間はきびしい労働に耐えて生産的活動に携わることによりりっぱな人格を形成することができるという労働倫理のようなものを説いているのではなく、人間は楽しく生きるべきだという一種の「快楽主義」に立っていることがわかる。しかし、彼は楽しさと快楽は異なるという。彼がいう「楽しさ」とはいかなるものかについて確かめておこう。
チクセントミハイは快楽pleasureと楽しさenjoymentをはっきりと区別している。彼は「快楽は楽しさと同義語ではない。基本的欲求の満足は楽しさを経験するための一つの必要条件であろう。しかし、それだけでは充足感を得るには不十分である。人は十分に機能している人間として成長し新しい技能を進歩させ、自己についての概念を維持するための新たな挑戦をすることが必要である。技能の進歩が妨げられる時、または行為への挑戦の機会が減少する時、人々は手に入れることができる唯一の意味ある経験として快楽に目を向けるようになろう」と述べるとともに「この社会では」「快楽を求める心を満足させ、物質的な安楽を得るための機会がかつてなく豊富にある」と言っている(第11章「楽しさの政治学」)。これらの文から、物質的満足を与えるもの、あるいは、生物学的な欲求を満たすものを、彼が「快楽」と考えていると推測される。だが、快楽を満たすだけでは不十分で、かれが目標にするのは人々の「充足感」である。
チクセントミハイはエピクーロスの快楽主義に対する直接的な言及は行っていないが、自分の説が「快楽主義」epicureanismとみなされることを嫌って、あえて快楽と楽しさの違いを強調したということは考えられなくもない。
エピクーロスは衣食住の基本的な欲求の充足を重視している。これは「物質的な安楽」であり、チクセントミハイが「楽しさ」と区別する「快楽」である。だがエピクーロスが究極的な幸福の条件としたのは精神的平安、「静的快楽」であり、これらは、人間の乗り越えがたい「天空の事象や死」などの恐怖・不安を哲学や自然学の継続によって解消することにより到達されると説かれていた。エピクーロスにおいては、スポーツなど身体的活動によって生み出される、興奮を伴う、積極的な楽しさではなく、悩みや苦しみのない平静な状態が快楽であった。
これと比べれば、チクセントミハイにおいては、これから見るように、ロック・ダンスなどのスポーツで得られる、動的で心身の興奮を伴う快楽が「楽しさ」の典型的な例と考えられている。重要なことは、チクセントミハイも「徳」や道徳的義務、あるいは宗教的命令などが幸福を約束する、人生の目標になるべきだとは考えず、楽しいと感じられる状態が幸福なのだと考えており、その点で、一種の快楽主義に立っているということである。
チクセントミハイとエピクーロスとの決定的な違いは、基本的欲求が満たされたとしてそのうえで必要な「楽しさ/充足感」(チクセントミハイ)あるいは「静的快楽/精神の平安」(エピクーロス)の実現方法にある。エピクーロスでは快楽(すなわち苦痛の欠如/解消)は、各人の努力、つまり十分な勘考を行い、行為選択を慎重に行うことによって達成されるべきものであった。チクセントミハイにおいては、彼の行動科学的な方法に基づいて、楽しさの、客観的で「測定可能」なモデルを作り、それに従って、ゲームにおける楽しさと同様の楽しさを得られるように、社会の全領域の活動のしかたを作り変えることが究極目標である。
かれは実際、何種類かのスポーツや遊びと「楽しく」行なわれている職業の調査によって「楽しさ」の指標を選び出し、「楽しさ」のモデルあるいは非常に楽しい経験がしばしば生むであろう「フロー」のモデルを構築した。彼は、その精緻化、改良の必要は認めるが、将来、こうしたモデルに適合するように、すべての領域の活動を作り変えるべきだというのである。
かれは、デュマズディエが肯定的に捉えた、第二次世界大戦後の先進国における傾向、つまり、労働時間を短縮し、レジャー(余暇)を増大させることに批判的である。「経験のほかの部分から孤立した「ゲーム」やフロー活動を増加させることによって、個人的社会的疎外を消去できると結論することは誤り」である。「円形競技場での競技によって民衆の不安を避けようとするローマ皇帝の試みは結局何の問題の解決にもならなかった。逆に、生活のすべてが、これらフローの特殊化された形態〔つまり、理論モデル〕によって例示される線に沿って再構造化されなければならない」という。チクセントミハイは社会全体の作り変えが必要だと言う。
以下は、「楽しさの理論モデル」構築のためにチクセントミハイが行った調査・研究の概要である。
チクセントミハイは第二章において、「自己目的的活動の報酬」が具体的にいかなるものであるかを示そうとする。彼は楽しいと感じつつ仕事に携わっている人々、作曲家、外科医、「多くの時間や努力、技能を必要とするが、金銭的地位的代償をほとんど生じない活動に深くかかわっている一群の人々」、合衆国チェス連盟によって評定されたトッププレーヤーを含む男女のチェスプレーヤー、国際的な体験をもち未登壁の初登攀の認定を受けた人などを含むロッククライマー、(パーティで踊っていた)初心者とプロを含むロック・ダンサー、ボストン地区ハイスクール・バスケットボール優勝チームの選手などに面接と質問紙によって、調査を行った。
仕事の分野でも遊びの分野でも、研究対象となった人々の多くが、程度の差はあれ、その活動を楽しんでいる。「楽しさ」は活動自体が与える「内発的報酬」である。ただし、高校のバスケットボール・チームの選手の場合は、まだ、金銭的報酬は得られないが、活動を通じて技能を獲得・向上させ、「社会的地位の上昇(プロ選手になること)」を期待できる。これは、プロが受け取る金銭的報酬と同様、一種の「外発的報酬」である。
チクセントミハイは、自分の活動を楽しんでいるロッククライマー、(プロでない)作曲家、ダンサー、チェスプレイヤー、バスケットボール選手173人に対し、「第1表」の左側に書かれている8つの項目に順位をつけさせる、というしかたで、調査した。順位1とされた項目は8点、順位8とされた項目は1点として、項目ごとに獲得した点数の総計を173で割った数字が右の欄の「平均」であろう。この表によれば、「それを経験することや技能を用いることの楽しさ」は平均して5.99点を獲得し、また「活動それ自体―活動の型、その行為、その活動が生み出す世界」は5.78を獲得した。
チクセントミハイは「それを経験することや技能を用いることの楽しさ」と「活動それ自体―活動の型、その行為、その活動が生み出す世界」の「二つの内発的理由が最も重要なものとして、---浮かび上がて」おり、予想した結果が得られた、としている。(元の表には、それぞれの項目の「平均」の標準偏差および、他の「項目」との有意差の有無、有意差の水準が書かれているが省略した。)
なお、「第2表」には、同じ「活動が楽しい理由の順位」が活動別(チェスはさらに男女別)に分けて書かれている。
第1表 「活動が楽しい理由の順位」
| 順 位 | 平 均 |
| 1.それを経験することや技能を用いることの楽しさ | 5.99 |
| 2.活動それ自体―活動の型、その行為、その活動が生み出す世界 | 5.78 |
| 3.個人的技能の発達 | 5.38 |
| 4.友情、交友 | 4.77 |
| 5.競争、他者と自分との比較 | 4.22 |
| 6.自己の理想の追求 | 3.81 |
| 7.情緒的解放 | 3.75 |
| 8.権威、尊敬、人気 | 2.49 |
チクセントミハイは、これら活動の種類、および参加者の性、年齢、社会階層などの違いにもかかわらず、「参加者のすべてが内発的報酬によって動機づけられている」ことが確かめられた、という。
また、この調査では、年長者や女性ほど、また社会経済的地位が高いほど内発的報酬を重視する傾向があることが分かった。また、チェスと作曲においてはベテランほど「競争」をより楽しいものと順位づけたが、一般的には、活動の能力と内発的満足とは結びつかないことが分かった、と言い、これらのことから、自己目的的な「活動」と、自己目的的な「パーソナリティ」、それに自己目的的な「経験」とを区別することが有効である、これら三つの概念は経験的には重複しているが、少なくとも分析レベルでは区別されるべきだ、と述べている。
彼は「自己目的的な要素の最も少ない活動を楽しむことができる人々」がいるという。このようなパーソナリティが、年齢、性別、社会階層の他にどのような要素と関係あるかを知ることは「重要」だ。「自己目的的なパーソナリティを作り出す方法を知っている社会は、外発的動機付けにのみ頼っている社会にくらべて、より幸福であり、効率的であろう」という。
彼は自己目的的活動という言葉を「参加者への直接的な内的報酬を極大化する行為の様式」と定義する。つまり、自己目的的な活動とは、その活動を行うこと自体が与える報酬が、参加者にとって、他の間接的、付髄的、あるいは結果的な報酬にくらべて最も大きいような活動のことだと、定義する。おそらく、どんな活動もその活動を行うこと自体が与える報酬以外の報酬をまったくもたらさないような活動はないと考えられるからであろう。
(「完全に外発的な仕事は存在しない」ことを示してはいないが)彼は「一つのスポーツや一つの仕事は、完全に自己目的的でもなければ完全に外発的でもない。それはむしろ内発的、外発的な様々な報酬を持っている」という。
彼は、内発的報酬に関する現象のいくつかの側面を素描したにすぎず、まだ「自己目的的な経験とは何か、それらの活動はいかにして自己目的的経験を可能にするのか」の「中心問題には触れていない」という。次の章で、彼は質問紙に対する被験者の回答に基づき「内発的報酬をもたらす活動の構造」を明らかにしようとする。
チクセントミハイは第三章で、自己目的的活動についての心理学者たちの様々な見方を紹介する。例えばビューラーらは、「機能的快楽」という考え方を提唱したが、それは有機体〔=生物〕がその身体的、感覚的な潜勢力〔能力〕に従って行動するときに経験する喜ばしい感覚のことだという。〔アリストテレースは、快楽は自己のアレテー(「器量」、能力、潜勢力)に即した活動に随伴すると述べていた。⇒第1章第三節のなかの「アリストテレースにおける哲学と幸福と快楽」参照。〕
他の人々は、刺激が(したがって活動が)楽しいものであるためには、新奇さを含んでいる必要があるという考えを提出した。
また、他の人々は、人は「自分自身で一つの行為を創出したと感ずる場合にはその活動を楽しみ、外からの強制によってそれを行ったと感ずる場合には、それを面白くない仕事として経験する」と説明している。これは哲学者たちが、自由は楽しい行為の基本をなすと考え、「参加と離脱の自由な活動」である遊びを高く評価したことと一致するという。
チクセントミハイは「これらの研究のおかげで、楽しい活動は個人の身体的、感覚的、知的な技能を伴わねばならないということ、および、行為するものに、自分の行為を統御しているという気分をあたえなければならないということを我々は知っている。しかしこれらはあまりにも抽象的、一般的に過ぎ、自己目的的活動を理解することはもとより、記述する助けにすらならない」という。
チクセントミハイは、カイヨワの遊びの類型論における、遊びは欲求の充足だとする説を、前の三説に比べより高い評価を下している。遊びは、何かその外にあるものを手に入れるための手段としての行動ではなく、その活動自体が、競争したい、自己を偶然にゆだねたい、模倣したい、眩暈を感じたいという内的欲求を充足してくれるとする考え方に立っており、「内発的報酬に対する別な説明仮説を含んでいる」というのだ。しかし、カイヨワの「優雅」な、「哲学的一貫性を」もった「体系的図式は」「研究を鼓舞するよりもむしろ締め出してしまう」という。にもかかわらず、彼は、カイヨワの遊び論から刺激を受けて研究を進めた。彼は、実際、自己目的的活動の構造を記述するための、被験者に対する質問票の項目の選択において「ある程度カイヨワのカテゴリーの影響を受けた」という。
彼は、被験者に各自の活動が何に「類似」しているかを20の項目を設けた調査票で問うた。「因子負荷が小さく」記載しなかった項目が(2つ)ある。
⇒「第3表」: 表の右側の数字は、被験者が自己の活動経験と調査者が示した左の語句との類似性に与えた順序であり、数字が低い項目ほど、よく似ていると判断されたことを示している。この調査では、たとえば、ロック・クライミングをしている30人に、左の18項目について、自分の活動に「似ている」と考える順に番号を振ってもらい、その数値を項目ごとに合計し、30で割ったものがクライマーの「自己目的的活動経験との類似性順位(平均順位)」で、クライマーたちはこうして「平均的に」、クライミングは「見知らぬ場所を探索する」ことに一番似ていると答え、「スロット・マシンで遊ぶ」ことは18番目に似ている(つまり一番似ていない)と、答えたというのであろう。〕
『楽しさの社会学』 第3表 「各自己目的的活動経験との類似性順位(平均順位)」
| 因子 | ロッククライミング30人 | 作曲22人 | ダンス30人 | チェス男30人 | チェス女22人 | バスケットボール40人 |
| 1.友情とくつろぎ | ||||||
| 性的交渉を持つ | 6 | 6.5 | 4.5 | 16.5 | 17.5 | 14 |
| 親友とともにいる | 3 | 9 | 4.5 | 9 | 14.5 | 8 |
| よい映画を見る | 15.5 | 5 | 9 | 12 | 17.5 | 6 |
| よい音楽をきく | 6 | 3 | 2 | 10 | 12.5 | 3 |
| おもしろい本を読む | 8 | 8 | 6.5 | 5 | 12.5 | 15.5 |
| 2.危険と運 | ||||||
| 思い切って遠くまで泳ぎ出る | 13 | 13.5 | 15 | 14 | 7 | 17.5 |
| 自分の理論を証明するために放射能に身をさらす | 17 | 10 | 12 | 12 | 10 | 9.5 |
| 高速で運転する | 10 | 16.5 | 12 | 12 | 10 | 6 |
| 麻薬を使用する | 10 | 13.5 | 15 | 15 | 14.5 | 9.5 |
| スロット・マシンで遊ぶ | 18 | 15 | 18 | 18 | 16 | 17.5 |
| 子どもを救うため、燃えている家の中に入る | 13 | 11 | 12 | 16.5 | 10 | 4 |
| 3.問題解決 | ||||||
| 数学の問題を解く | 4 | 2 | 9 | 1.5 | 2 | 12 |
| 装置を組み立てる | 13 | 6.5 | 17 | 7.5 | 7 | 15.5 |
| 見知らぬ場所を探索する | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 12 |
| ポーカーをする | 15.5 | 13.5 | 18 | 6 | 5 | 12 |
| 4.競争 | ||||||
| 競走をする | 6 | 16.5 | 9 | 7.5 | 7 | 2 |
| 競技スポーツをする | 10 | 13.5 | 6.5 | 1.5 | 3 | 1 |
| 5.創造 | ||||||
| 何か新しいものを設計または発見する | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 |
「性的交渉をもつ」以下、5つの項目からなる「友情とくつろぎ」と名付けられた、「第一因子」はカイヨワの模擬に、「思い切って遠くまで泳ぎ出る」以下6つの項目からなる「危険と運」と名付けられた第二因子はカイヨワの眩暈および運に相当し、第四因子「競争」はカイヨワの競争に相当する。第三の「問題解決」、および第五因子「創造」は「カイヨワの図式にはない」項目である、という。
チクセントミハイはこの調査結果に関して、バスケットボール選手を除くすべてのグループによって、創造因子と問題解決因子に高い順位が与えられた点を重視する。「活動の形式的な違いにもかかわらず、自己目的的活動の背後にある共通の類似性は、それらすべての活動が、参加者に発見、探索、問題解決――他の言葉でいえば新奇さと挑戦――の感情を与えている」という。つまり「自己目的的活動の特殊な構造がどのようなものであれ、最も基本的な必要条件は、それが明確な挑戦の方向を備えているということである」ことをチクセントミハイは強調する。
また彼は、第一因子の「人間関係に関する諸項目の相対的重要性」を強調する。彼は「明らかに他者との親密な関係から生ずる暖かい感情、または自我境界のゆるみは、少なくとも、いくつかの自己目的的活動にとって重要である」「友情と、その結果生ずる自己中心性の喪失の感覚」が自己目的的経験において重要な要素だという。
だが、彼は第3表の「順位平均値を要約」して、「すべてのグループにわたって最も高い得点を示す項目」は「新しいものの創造または発見」、「見知らぬ場所の探索」「数学の問題を解く」「競技スポーツをする」、「よい音楽をきく」であるが、これらの項目が自己目的的な経験の主要な構成要素のすべてであると結論するのは早計である。われわれの被験者の中にはギャンブル、その他の形の運に左右される遊びを楽しんでいる人々が含まれていなかった---」と、言っている。
彼はここでは、彼の調査では賭けの遊びは対象となっていないということ、つまり、彼が調査した活動は様々に異なる自己目的的活動の一部であること、したがって、そこで知られた経験の性質ないし特徴は自己目的的経験のすべてではないということ、したがってまた、それらが自己目的的経験の「主要な構成要素」であるとは言えないことを認めている。
しかし、後の章で彼は「自己目的的活動の基本的な性質を特定化した理論モデル」を提示し、そのモデルが現実場面に適用可能であると主張するが、そこで提示されているモデルは、運の関係する遊びを除外した調査に基づいて作られたものであり、欠陥がある。
わたしが思うに、運の関係する遊びはチクセントミハイが取り上げた他の自己目的的活動と大きく異なる特徴を持っている。運の遊びの有する特徴を要素として組み込んでいないモデルによって「遊びと仕事の二分法」の克服を行なおうとすることは、欠陥のあるモデルで二分法の克服が可能だと考えることである。この点については、のちの反論の中で述べたい。
チクセントミハイは、「楽しさの理論モデル」と題した第4章で次のように言う。「通常」の生活は往々にして「退屈」であり、また逆にしばしば「不安」を生み出す。これにたいしてスポーツなど自己目的的活動においては退屈も不安もない。その活動は絶えず挑戦を提供し、退屈や不安を感じる時間がなく、行為者をしばしば「没入」させる。つまり人々を夢中にさせる。
複雑な実人生においては、人がなすべく求められていることは必ずしも明らかではなくまた行為の成否、適否もしばしば不明瞭のまま終わることが多いが、自己目的的活動においては、人は「必要とする技能をフルに働かせることができ、自分の行為から明瞭なフィードバックを受け取る」。「筋の通った因果の体系にあり、そこで彼が行うことは、現実的で予想可能な結果をもたらす」。「行為は行為者の意識的な介入の必要がないかのように、内的な論理に従って次々に進んでゆく。人はそれをある瞬間から次の瞬間への統一的な流れとして経験し、その中で自分を統御しており、さらにはそこで自我と環境との間、刺激と反応との間、過去現在未来との間の差はほとんどない」。
この「特異でダイナミックな状態」、「全人的に行為に没入しているときに人が感ずる包括的感覚」をチクセントミハイは「フロー(flow)」と呼ぶ。
彼は、クライマーやチェスのプレイヤーのような、楽しみだけが目的であるような活動を行っている人々ばかりではなく、外科医や数学者にも面接した。彼らは「〔スポーツ〕プイヤーたちと、ほとんどそっくり交換可能な言葉で答えた」と言う。また、ほかの心理学者、宗教学者などの研究に基づき、「ほとんどすべての」宗教者たちについても同様のことが言えるという。
彼は、自己目的的活動から得られる経験、つまり自己目的的経験を途中からフローと呼び変える。呼び方を途中で変えるのは、フローは、活動を行うときに人々が、外発的目標や報酬があるかないかという考慮なしに、求めるものであるからだという。
たしかに、遊ぶ人は、遊びが単に楽しいと感じるから遊ぶのであり、遊びには他の目的もあるのかどうか、つまり外的報酬をともなっているかどうか(「補償」、「代償」など)といったことは、彼らにとってどうでもよいことである。遊びは遊びを楽しむということ以外の目的をもたないということ、それゆえ遊びは「自己目的的活動」であると考えるのは学者や研究者、あるいは一般に第三者である。
クライマーの観点に即して言えば、クライミングは「自己目的的経験」ではなくて、単に「楽しい経験」あるいは「フローを得られる経験」を求めて行われる活動だということになる。(チクセントミハイは「フロー」という語を使い始めたのはクライマーたちで、彼はこの語をクライマーたちから借用すると、言っている。)そして、チクセントミハイは「楽しさ」と「フロー」は同じだと考えている、あるいは両者を同じだとみな(そうと)している。こうして、彼は、遊びやスポーツ、つまり客観的に言えば「自己目的的活動」を行なっている人々の観点により忠実に彼らの経験をフローと呼び変えるのだという。
彼は続いてフロー経験の特徴を以下の6つの要素にまとめつつ説明する。
①「最も明瞭な特徴」は、「行為と意識の融合」である。「フロー状態にある人は二重の視点を持つことはない。彼は彼の行為を意識するが、そういう意識そのものをさらに意識することはない。テニス・プレイヤーはボールと相手に対して分かつことのできない注意を払っており、チェスの名人はゲームの作戦に注意の焦点を」置いている。「フローを維持しているときには、意識するということ、そのものを省みることはできない」という。質問に対する回答のなかでチェスのエキスパートはチェスのプレイにおける「注意の集中というのは呼吸のようなものです―呼吸しているかどうか考えたりすることは決してありません」言っている。
②第二の特徴は「限定された刺激領域への注意集中」であり、「邪魔になる刺激を注意の外に留めておく」ことだという。「刺激領域」とは、たとえばバスケットボールの試合中の選手にとってはコート内の双方のチームの選手の位置や動きのことである。ある選手は「コート――それだけが問題です----。」と述べている。コート外のことはすべて意識から締め出される。
③第三の特徴は「自我の喪失」「自我忘却」「自我意識の喪失」であり、「個の超越」「世界との融合」とも表現されてきた、という。
「自我の喪失」、「自我意識の喪失」は①の「意識と行為の融合」とは違う。行為は意識されており、意識は存在する。「フローにおいて通常失われるのは、個人の身体や機能に対する意識ではなく、人が刺激と反応とのあいだに介在させる、学習によって得た自我の構造」だという。
自我は、有機体の諸要求と社会的要求〔超自我〕とを調停する心的メカニズムのことである。自我の機能は個人の行為と他者の行為を統合すること、したがって社会生活に不可欠な機能である。自我の機能は、他者(の意向)への配慮、同情心、羞恥心、などにかかわる。
しかし、ロック・クライミングのチームは、会社の同僚などとは違い少しの疑いもない完全な信頼によって結ばれているであろう。「フローの出現を可能にする活動(例えばゲーム、祭祀、芸術)は通常、統合のための何らの調整も必要としない。---すべての参加者が同じルールに従う限り、役割の配分について互いに交渉しあう必要はなく、---自我を必要としない。ルールが重んじられている限り、一つのフロー状況は逸脱のない一社会体系なのである」。
前の章でふれたN.エリアスによれば現代人は社会生活において衝動的行動や感情的表現を極力抑えるよう努める。しかしチェスやバスケットボールなど、ルールに従って行われるゲームやスポーツにおいては、「対戦相手」に対する振舞い方に格別な注意は必要ではない。相手を粉砕しようとする自然的衝動のままにプレイを行うのである。チクセントミハイの被験者のチェス・プレイヤーの一人は対戦中に「暴君的な力の感覚があります。---殺したいのです!」と言っている。クライマーの一人は「ロボットのように――いやそれよりも動物のようになります。楽しいです。---岩を力強くはい上がる豹になったような感じです。」と述べている。
④もう一つの特徴は「自分の行為や環境を支配しているという」「感覚」である。「環境に適合している」という感じである。ロック・ダンス〔ストリート・ダンス、ヒップホップ・ダンスともいう〕の踊り手は、ダンスがうまくいってフロー状態にあるときには、環境を支配していながら、同時に環境に融合しているとも感じる。「私は周囲のものと一体になるのです」と言っている。
ハンドボールなどの競争的活動では、支配感は「自分自身の限界に対する勝利」と感じられている。あるハンドボールのエースは「ゲームに完全に集中している〔=フローしている〕ときには、自分の他には何もない――ボールを扱うという行為以外に何も存在しない、そんな自分にときどき気がつきます。---相手プレイヤーがそこにいるはずなんですが、彼にはかかわりがないんです。私はボールのあるべき点に完全に正しくボールを置こうとしているのであって、それは勝つとか負けるとかということとは関係ありません」と述べている。
⑤「経験が首尾一貫した矛盾のない行為を必要とし、行為に対する明瞭で明確なフィードバックを備えていること」である。実人生においては、一般に、何がよい(結果を生む)か、何が悪い(結果を生む)かは明瞭ではない。一つ一つの行動のフィードバックがあるのかないのか明らかではないということも多いだろう。だが、実人生とは異なり、ゲームやスポーツのような「人為的に単純化された現実においては、何が正しく何が間違っているかが明確にわかり、目的と手段が論理的に整理されており、現実での生活のように両立しないものごとの遂行を期待されることもない」という。
⑥最後の特徴は自己目的的な性質、それ自体のほかに目的や報酬を必要としないということである。
以上がフロー経験の特徴である。
以上のような特徴をもつフロー経験は、次に見るような、環境が行為者に与える行為への機会(「挑戦」)と行為者の有する行為能力(技能)とが釣り合っているときに、可能になる。つまり環境からの挑戦と行為者の能力とのある限定された、適切な関係において、行為者がその挑戦に対する行動を行い、「しばしの間、我を忘れ」、上の六つの要素を含む状態を経験するというのが、チクセントミハイの言う「フローの理論モデル」である。
一般に、環境が求める行為(挑戦)が人々の能力よりも大きい時に、人々は緊張し、結果的に心配や不安を感じる。逆に行為に対する要求が低すぎると人々は退屈を感じる。そして大きな技能を持ちながらそれを適用する機会を持たない人は退屈の状態を通り越し、再び不安に陥る。こうしてフロー経験が生じるような活動、つまりフロー活動とは、人々が持っている能力、技能に関して最適の挑戦を用意している活動である。
ただし、フローは環境の中にある客観的な状態、ないしは必要な技能レベルと行為者の有する技能の客観的な水準との関係だけで決まるのではない。フロー状態に入るかどうかはその人が環境からの「要求」や自己の持っている技能をどう知覚するかにかかっている。ある環境における行動がフローを生じるかどうかを予想するためには、それら「要求」や技能を過少にあるいは過大に評価するその人のパーソナリティ特性を特定化する必要がある、とチクセントミハイは付け加える。
チクセントミハイは第5章で、チェスを例にとって、自己目的的活動が与える楽しみ、およびフローはその活動の典型的な構造特性のみによって決まるのではないこと、また、チェスは単に知的な戦いのゲームであるだけではなく、いくつもの互いに独立した目標を持つ行為を含み、その楽しみ方によって異なる様々なフローが生じるということを示そうとする。
第6章では、ロック・クライマーたちがかれらの活動について述べていることを詳しく「報告」し、そのフローの構造を明らかにしようとする。ロック・クライミングは、「生命の危険を含み、これといった外発的報酬がない」ために、「まったく人間にとって非合理」であるように見える遊びで〔人間とは何なのかを考えさせるという意味でであろうか〕「深い遊び」と呼ぶ人があるといい、チクセントミハイは、ロック・クライミングで得られるフローを「深いフロー」と呼ぶ。
チェスは相手の合理的作戦の粉砕を基盤とする模擬戦争で、それは非常に競争的で知的である。チェス・プレイヤーが彼らの経験を記述するときに最も似ているとして挙げるのは「数学の問題を解く」、「競技スポーツをする」などの項目で、「第一次的には、競争的、創造的で知的な問題解決の過程として知覚されている」。⇒上で示した「第3表」を参照。
チクセントミハイは、質問票への回答の分析によって、また直接の面接を通して、チェスがプレイヤーに、困難な状況での支配の感覚を与えることによって興奮を生み出し、挑戦と技能の間の不安定なバランスの上にフロー経験があること、チェスはその用具、ルール、ゲームの構成が、通常の生活の活動とはっきりした区別を持っており、ゲームの限定された世界に注意を集中しやすく、活動への「没入」が起こりやすいこと、また一つ一つの動き〔指し手〕が明瞭なフィードバックをもっていることなどから、チェスの第一次的報酬としてのフロー経験が彼の理論モデルに一致しているという。
しかしチェスには、対戦を行う以外に、交際、娯楽、俗受けを狙うこと、一人で研究すること、あるいはこれらすべてを狙うことなど様々なやりかたで楽しむことができ、多くのチェスファンはそれぞれ異なった楽しみ方をしている。したがって、「一つの活動の中に異なった種類の内発的報酬を組み込むことができることを示唆している」。
「チェスにみられるフローの例は、本来のフロー活動以外の諸活動の中にも、フローを組み込むことの可能性をうかがわせるという意味で、意義深いものがある。チェス自体、優に千年以上の時間をかけて発展してきたのであり、この間に、チェスは多様な挑戦の様式、したがって楽しみ方の様式を獲得してきた。このことを理解することによって我々はいかにすれば仕事のなかにも、遊びと同様な楽しむ機会を作り出せるかを知ることができよう」と、彼の研究目標である「遊びと仕事の二分論の克服」にとってチェスがもつ重要性について語っている。
クライマーたちは、ロック・クライミングは公衆の面前ではなく私的な経験としておこなわれるということが一つの理由となって、人間活動のもっとも純粋な形態の一つと考えている。ロック・クライミングは、この世界に入りこむことができた者だけが、客観的難度とクライマーの芸術的手腕とを総合的に判断することができ、クライマー自身だけが何を成し遂げたか、いかに見事にやり遂げたかを知っている、そうした人間活動である、とチクセントミハイは言う。
他方、ベンサムは危険を伴う遊びを「深い遊び」と呼んだという。外的報酬がないだけではなく生命への重大な危険を含むロック・クライミングは、内的報酬を与える自己目的的活動であることは確かだとしても、その報酬は「合理的」なものに見えない。「しかしまさにそのことが人間性追求の学徒たちの関心をひく---。人々はなぜ「合理的」報酬を生まない活動に惹かれるのか」。これをチクセントミハイは「フロー・モデルを用いて解こうとするのだ」と言う。
岩場は、それを登攀するのに必要な、動きの型、力と身体支配の巧みさ、岩場の手がかりの大きさと数、形、もろさ、等々によって、客観的かつ一貫性のあるしかたで評定されている。通常2,3人で、トップをその下にいるセカンドがザイルにより(トップが落下した時に)確保するというやりかたで協力し合いつつ、尺取虫のように上る。
同じ岩場でもルートを変えることが可能である。また、無駄な動きをなくす、装備への依存を少なくする、など美的標準に焦点を絞ることもできるし、同じコースを、無装備で、あるいは単独で登攀することもある。つまり「ルールを変え」、評価基準を変えて、同じ岸壁を上りながらその都度新鮮な興味を見つけることができる。こうして、ロック・クライミングは新しい岩場あるいはより難しい岩場の登攀をめざすという「垂直的」挑戦を行うだけでなく、「水平的に」、無限の行為への挑戦の幅を持っている、という。
「深いフロー活動」としてのロック・クライミング。写真はClimbers on "Valkyrie" at The Roaches in Staffordshire, United Kingdom, in May 2002 で、English Wikipediaから転載
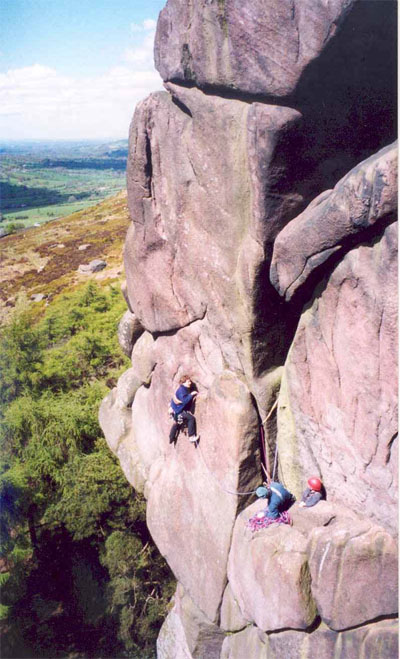
チクセントミハイは、ロック・クライミングをとくに深いフローが可能な活動、「深いフロー活動」と呼ぶ。被験者たちは、行為が「自己反応的に」流れるように連続的に行われること(行為と意識の融合)、限定された刺激領域への注意集中、「自己と環境に対する支配」の感じなど、他のスポーツやゲームにおけるのと同様のフロー経験をより明瞭に述べるとともに、他の自己目的的活動とは違った、ロック・クライミング特有のフロー経験について、報告している。
「登り始めると記憶は断ち切られたようになる」。「ものすごい集中のため、日常の世界のことは忘れてしまう」。「普通の日常的なことがらとはかかわりのない、まったく異なった世界に入る」。「注意を集中しながら登るということは、世界を閉め出すことであるが」、「その世界が再び現れるとき」世界は以前とはまったく違った新しいものとなって現れる。再び現れた世界は「その新しさのゆえに、新鮮な経験、未知のすばらしい経験」を与える。知覚の変容が起こる。
クライミングでは、身体を確保して短い休息を取る。「そのときわれわれはいつもより強い感受性をもって、自分たちの周囲にあるあらゆるものをしみじみと眺めたものです。花崗岩の結晶の一つ一つがくっきりと際立って見えました。さまざまな形をした雲を眺めて飽きることがありませんでした。岩壁一面に小さな虫がいることにわれわれは始めて気がつきました。それは小さすぎてほとんど見えないほどでした。自分を確保している15分の間、私はその一匹から眼を離さず、その動きを注視し、その鮮やかな赤い色に感じ入っていたのです。こんなにたくさんのすばらしい、見たり感じたりするものがあるのに、誰が退屈などできるでしょう。喜ばしい環境とのこの合一、この鋭く突き刺さってくる感覚が、何年もの間味わったことのない気分をわれわれに与えたのです」。
凝視、つまりクライミングという活動によって引き出された視覚とともに、物的対象は変容し、周囲の事物が、それ以前とは全く違った感情を伴う見え方をする。世界が違って見え、充実した、輝いたものとして、あるいは、もっと注意深く見つめそれをもっと吟味すべきものとして現れてくる。
この知覚の変容などについて語った登山家は宗教的経験だといっている。チクセントミハイは「恍惚の意味が常態からの「超越」だとすれば、深いフローは人を恍惚とさせる経験である」という。生まれてからこれまでの学習を通じて作られてきた「自我境界の超越」あるいは「自我の喪失」が起こっている。深いフローの経験は「新しい評価と承認の様式を生み出す。深い遊びの世界から今まで注意深く隔離されてきた日常生活の秩序は、新しい解釈と批判を受けることになる」。
深いフローは、自己目的的活動の最中に活動への強い没入状態をもたらすだけでなく、従来の自我を変容させる。登攀が終わり岩壁の頂上から地上に戻った時に、社会や世界、あるいは宇宙における人間の位置、人間存在とは何かということなど、従来、彼の日常生活の中で問われたことのなかった、形而上学的ともいうべき問題が重い意味を持った問として現れて来、彼の日常生活に対する見方・考えかたを変え、実際の生活の仕方を変えてしまうこともある。
ある被験者は言う「日常生活にはない大きな心身の投入があります。---自分の体をどんどん前進させ、体中が痛みます。そして自分がやったことを、自分への畏敬の念を持って振り返るのです。それは心を膨らませます。そしてエクスタシーへ、自己充足へと導いていきます。---これが宇宙時代の私の唯一の生きがいなのではないかと時々考えます。これなしには一週間とはもたないでしょう。---世の中は刺激が多すぎます。世の中はスモッグであり、泥沼です。下界では人々は正道を外れた考え方によって庇護された現実、偽りの安全のなかに住んでいます。---文明の中では人は現実を生きていません。人は決して宇宙のことや、その中での人間の位置を考えることはありません。---車や学校やパーティのことを考えているのです」。
何人かの被験者は「毎日山に登れるようにするために、金になる地位を山での大工仕事に変えた。---他の何人かの被験者もまた、クライミングをより身近なものにするために、ありふれた経済、教育、地位への道を放棄し」た。
チクセントミハイはこれらのうちの何人かにとってクライミングが「唯一の活動となったために「強烈な麻薬」となった」ことにも触れているが、ほとんどの者はこのフロー経験を「内面化することにあると信じて」おり、この経験を「個人がかかわりあう----あらゆる状況の中に般化させることができる。つまり「生活の他の領域で生ずる様々な状況を明確化し、それに対して決断を下すために、照合する範例としてクライミングを利用する」と何人かのクライマーは述べたという。
チクセントミハイは、ロック・クライミングのフロー経験とそれが及ぼす日常生活への影響を過大評価してはいない。彼は、クライマーであるとともに詩人でもあるギド・レイの「もしクライマーが下界においても頂上に立った理想的瞬間と同じように高潔で純粋な状態にとどまっているならば、他の人々は彼らの帰還を見て、天下った天使の一団と信じるだろう。しかし、クライマーは家に帰ると再び弱さの餌食となり、悪習を再び始め、山岳雑誌に記事を書く」という言葉を引用している。そして「ロック・クライミングが多くの人々の生活を変えてしまうなどということはない。同時にアメリカ文化の歩む道がクライミングの生み出した一握りの幻想家によって最大の影響を受けてきたということもできない」という。
ロック・クライミングのフロー経験について述べた章の冒頭では、「ロック・クライミングの分析は、フロー活動が社会変革について考える際のモデルとしていかに役立ち得るか、またそれに必要な変化へと人々を動機づける経験を、いかに豊富に備えているかを示す」と言っていた。しかし、章の「結論」では、「人は、ロック・クライミングから、内発的報酬〔つまりフローを伴う楽しさの経験〕について学び得たことのもたらすこの実際的結果は、示唆的ではあるが具体的な社会変化に適用することは困難だ」と正直に語っている。
しかしかれは、ロック・クライミングがチェスその他のフロー活動と共通している点、つまり、「行為者の能力、そしていうまでもなく、行為者の存在それ自体を確認するのに適した作業への、心身を上げての全体的参加」という点で価値があり、さらにクライミングは他のフロー活動以上に「高揚した身体的達成感、環境との調和感、クライミング仲間への信頼、そして目的の明確さを含んでいる」ために一層価値があるという。クライミングが与える深いフローは「恍惚とさせる経験」を与える。このときの「高揚した精神状態は、新しい文化形態を発展させる前提条件のひとつであるということは言えよう」と彼は言う。
こうした分析に加え、チクセントミハイは「この分析から引き出される最も一般的な結論は、大多数の人々の仕事をより楽しいものとするためには、生得的、獲得的な技能の範囲で利用することのできる、いくつにも段階づけられた活動が必要であるということ」だと言い、オルダス・ハックスリーの晩年の小説『島』のユートピア社会では、すべての若者にロック・クライミングが義務付けられていることに反対する。反対の理由は「同一の挑戦が技能の異なる人々に同じフローを生み出すことがない」からである。必要なことは「内発的報酬を備えるために、一つの活動が身体的、知的、情緒的、社会的な諸能力を含む個人の技能に関して、精密に目盛られていること」である。つまり、諸個人は特定の活動からフローを引き出すことに対する異なる能力と「存在自体」つまりパーソナリティを有している。したがって多数の人が様々な活動を十分に「楽しむ」ことができるようにするためには、人々が有する能力ないしパーソナリティに相関的に、「精密に目盛られている」多くの諸活動が提供されなければならない、というのである。
この点に関する私の考えは、のちの<疑問と意見>5.「「楽しさ」を指標とする社会全体の「再構造化」について」および、それに続く「ハックスレーの『すばらしい新世界』、仕事への労働者の配分」の中で述べることにする。
チクセントミハイの考えでは、すべての人々が十分なフローを得ることができるためにはそれぞれの人の技能とパーソナリティに合った活動・仕事を配分されねばならない。そのためには(研究により)フロー経験が正確に測定され、その経験を行った各人が感じた挑戦および各自の技能が測定されていなければならない。
彼は、第5章と第6章でチェスとロック・クライミングにおけるフロー経験がフローの理論モデルに適合することを、「印象による被験者の報告に基づ」いて確認した。第7章では、ロック・ダンスの調査・研究において、「明確に操作化されたデータ」によって、「前章までに示された質的評価を補足する量的評価」を行う。つまりこの研究で、「(a)個人が一つの活動から引き出すフロー経験の要素の数、および(b)所与の活動において、個人が知覚する挑戦に対する、技能の比率が明らかになるよう」にした、という。
チクセントミハイによると、明瞭な連続ビートを持ち、しかも大音量で流される音楽が、踊り手の「刺激領域を限定し」「注意を集中させる」。照明を暗くすることも注意の分散を減らすことに役立つ。ダンスへの没入を妨げる自我意識を低下させるためにアルコールもしばしば用いられる。相手の動作が意味しているものがただの踊りなのか、(しばしば行われる)性的な誘いなのかはあいまいで、「フィードバック」は不明瞭である。音楽が4、5分毎に途切れるときに自由に抜けることができ、曲の途中で踊りを中止することも比較的容易で、チェス、ロック・クライミング、手術などと違い「境界」は曖昧である。そこでチクセントミハイはダンスを「浅いフロー」活動に分類する。
-----------------------------------------------------
(注)
チクセントミハイは、ロック・ダンスLockdanceはロック音楽Rockmusicに合わせて、多くはペアで踊る、即興的な踊りで、多くの人は単にダンスと呼んでいる、と説明している。「演技ダンスと異なり」振り付けられたものでなく、パーティに集まった人々が自分の気分にしたがって、踊る。動作は即興的で個々の踊り手によって比較的自由に選ばれると言っている。しかし、この説明は、1960年代後半から70年代のロックダンスの様子を書いたもので、現在のものは少し違うようである。
ウィキペディアの解説やYoutubeの動画を見ると、現在では、ロックダンスはストリートダンスあるいはヒップホップ・ダンスなどとも呼ばれている。手足を非常に早く、かつ、アクロバティックに動かして踊り、Youtubeの動画を見る限り、ペアの動作は同じではないが、完全にシンクロナイズされていて、即興的なものではありえない。十分に「振付」られている。練習において身体の動かし方について様々な「挑戦」がなされるのであろうが、観衆の前で踊るときには、ほかの踊りと同様、練習中の打ち合わせによって行うことに決めた一連の動作を決めたとおりに演じていると思われる。
-----------------------------------------------------
被験者は12人で、踊っているときの表情や態度などの観察を通じて、また対話を通じて、フロー経験をしていると思われる人とそうでない人を2つのグループに分けて、6人ずつ選び出した。次に面接と質問票によって、参加者がどのようにロックダンスを経験しているかを調べた。
(「フロ」ーしていると予想された人々と、フローしていないと思われた人々とのグループ分けについては、調査者のグループ分けは3名を除いて正しかった、という。)
踊り手たちが実際にフローに入ったかどうか、またそのフローの度合いについての「測定」は次のように行われた。(1)面接に基づき、周囲の物事に対する知覚、時間の経過、直接的フィードバックの獲得、パートナーとの関係の支配など、フローモデルから引き出された14項目について、各ダンサーに自己評定させ、0から4までの数値で表す。(2)挑戦(ダンスで求められている、自我意識の払拭、型の良さ、同一動作の反復回数、動作と音楽との調和など29項目)に対する、技能(数多くのステップを身につけること、音楽の拍子に合わせること、同じ動作を何度も繰り返すこと、体をいろいろ動かせること、など11項目)の適合度合いについて、同じく自己評定させ、質問紙に回答させて、集計した。
調査の細かな点にふれることはせず、チクセントミハイが下している結論だけを引用する。
「これらの結果は---フロー・モデルが経験的に妥当であることを立証し、その理論から導き出される仮説の有効性を確証した。今後、---他の様々な条件下で、より大きな標本に対し、ここで提示された方法を用いてフロー・モデルをテストし続ける準備がいまできたのである。---我々は、例えば、なぜ何人かの人々は一つの活動でフローを経験するのに、他の活動では経験しないのか、---異なった活動をそれらが生み出す楽しさに関して比較することができるのか否か等を決定できよう」。
チクセントミハイは「仕事の楽しさ―手術」と題する次の第8章で、「自己目的的活動」ではない、つまり遊びではない外科医の手術におけるフローについての報告を行っている。彼は「手術は、職業という条件下での理想的なフロー活動の例である。外科医の仕事は明確な始めと終わりによって区切られ---る。手術は完全な集中を必要とし、直接的フィードバックを与え、正誤の明確な判断基準を持っている。手術はその構造的特性のゆえに「余暇」活動と同じく、楽しいものとして経験されると予想される」という。
「医学はわれわれの社会における地位階層のまさにトップにあり、外科医は医学の中でももっとも尊敬を受ける分野である。これに加えて経済的報酬もけっして無視できない。部外者は、人々が外科医になるべく動機づけられる理由の説明として地位と金銭を考えれば十分であると断定するであろう。しかし、外科医と話してみると、手術をするということは非常に強い内発的報酬を伴うフロー過程であることがわかる。実際に面接した外科医のすべてが、手術を「おもしろい」、「わくわくする」、「美的喜びを伴う」、「劇的でまったく申し分のない」、「催眠剤を服用するような」等と表現した。明らかに手術は、数多くの外発的、内発的報酬によって強く特徴づけられている」、とチクセントミハイは言う。
多くの外科医は「手術を行っているときに、あっという間に時間が経つ」と報告している。「熱中していて、看護婦の出入りするのもわからない、足の疲れもまったく感じない」と言っている。伝説的な話では、ある医者は屋根が落下し床の半分が破片で覆われたのに、困難な手術を続け、手術が終わって助手たちが彼の後ろに落ちている漆喰を指差すまで何が起こったかをまったく知らなかった。
まったく平凡で容易な手術ではフローがおこらず、途中で雑談したり、他の事を考えたりすることもある。しかし、容易な手術でも、あるいはときに複雑で「挑戦的」なものであっても、何をすべきかがわかっているときには、あるいは順調にいくときには、「技術的な達成感と満足感を生む」。「すべてがうまくいくことは楽しいと感じられる」。「手仕事の楽しさがある」などと答えている。
外科医の経験に関して述べている章の結論で、チクセントミハイは言う。「われわれが見てきたように、もっとも技能を要し、責任の大きな仕事の一つである外科手術は、明らかに楽しいものなのである」。
外科医の仕事は、ロック・クライミングと同様、行為者の自我の構造を変化をさせてしまうことがある。フロー経験を有する、あるベテラン開業医は夫婦で数年ぶりにとった休暇でメキシコ旅行に行った。2日間の観光のあと、彼はとてもじっとしていられなくなり、その地方の病院での奉仕を買って出、夫人を好きなようにさせておいて、残りの休暇を手術で過ごした。この外科医の場合、フローしつつ、手術の仕事を「しているときにのみ生き生きしている」が、「ほかのすべてのことが楽しくなくなる」。
「フローを経験した外科医が永久にフロー経験を奪われるとき、真に重大な問題」が起こる。「手術に数回失敗した外科医は、手術に際して常に不安を感ずるであろう。また、さまざまな理由から、外科医の仕事は、もう一つの極端、つまり退屈な日常的なものに変わりうる。いずれの場合にも手術はもはやフローを生み出さない。非常に多くの場合、その結果はアルコール中毒、家庭崩壊を生み、さらには自殺すら生み出している」。
だが、チクセントミハイは、次のように議論を続ける。「外科医に対する面接の結果は余暇活動に見られるフロー経験が外科の仕事のなかにも存在することを示唆している。したがって仕事と余暇の二分法が不必要である以上、我々はさまざまな活動を挑戦的で楽しいものに構成、あるいは再構成することができるはずである。---多くの――おそらくほとんどの――職業は、---フロー活動を生ずるように再構成されるならば、内発的報酬を生むように作り変えることができよう。---例えば---スーパーマーケットの、あるレジスター係は、レジスターのキーをリズミカルに打ち続けたり(「ピアノを弾くようになものですわ」)一人一人の客の顔を覚えたりするような、数多くのユニークな行為への挑戦機会を自分の仕事に見つけ出しており、その結果、外科医と同じように、自分の仕事への没入を感じている」。
「遊びと仕事の間の最も頑固な区別は遊びが現実の世界では真の重要性をもたない、という仮定である。遊びにおける過ちが罰せられることはない。---しかし「遊び」が、すべてがうまくいく孤絶した出来事であるということは全く間違っている」。「ダンサーのステージでの失敗や、チェスプレイヤーのトーナメントでの敗北は、彼らの自尊心を強く傷つける。賭博師はたった一勝負で持っているものすべてを失うこともある」。ロック・クライマー、自動車レースのレーサー、スカイ・ダイバー、その他多くの競技者は日常茶飯事のように自分の体を賭ける。「危険はその活動に注意を手中させ、行為者の技能へフィードバックを返す手段として役立っている。それらは楽しさを妨害するものではなくむしろフロー経験を生み出す挑戦の一部である。
彼はフローが中毒性を持ち習慣形成的なものになることの危険性を認める。しかし、そうした危険性は「内発的動機付けの持つ力を確証するに過ぎない。人は権力の亡者になったり、守銭奴になる可能性を持つと同じように、様々な形を取るフローの罠にからめとられることもありうる。---フローは危険な資源である」しかし、「その利点が外発的報酬をしのぐなら、それはわれわれにとって、無視できない資源だ」と、フローの重要性を説く。
ここで、いま述べられたことに限って、私の意見を述べる。(そのほかの論点に関しては、のちの<疑問と意見>1.から5.で述べる。)自己目的的活動、外発的でない報酬を与える活動の中に、おそらく、それが与える強いフローのゆえに、生命の危険を賭けてでも行いたくなる活動があり、そうした活動に引きつけられるパーソナリティを持った少数の人々もいる。だからといって自己目的的活動すべてがフローを生み出すのでなく、また多くの人がそうしたフロー経験を必要と感じたりぜひともやってみたいと思ったりするわけでもない。
自己目的的活動が楽しいということのなかにはしばしば挑戦の要素が含まれるだろう。それは、自己目的的活動が、生きていくことの必要を満たす活動ではなく、それがみたされていることを前提として、自分がもっている様々な能力や可能性を、自由に、努力してやってみようとする活動だからだと私は考える。それはチクセントミハイのいう環境からの挑戦に答える技能の発揮という考え方と似ている。
しかし、楽しみのために行う活動はあくまでも生きていることを前提としており、命がけで行う冒険とは異なる。楽しみのために行われる活動は生(生活)が楽しく/有意義だと感じられるためのプラス・アルファであり、何らかの理由により普通の生に満足できず、そこからの超越や恍惚によって生に代わる特別なものを手に入れようとすることではない。視野を限定するのでなく、たえず日常の生を視野の片隅において、しかし同時に楽しむ。働いて食べて眠るだけの生のなかでは実現できない、自己の拡張、自分が様々な活動を「うまくできる」ということ、成功を確かめることが目標である。
その際、目標は必ず達成できると決まってはいない。人前でダンスを踊る。上手に踊れれば楽しい。うまくいかなければ恥ずかしい/悔しい。チェスあるいは囲碁や将棋をする。勝てば楽しい。負ければ悔しい。釣りをする。良型の、狙った魚が何匹も釣れれば楽しい。坊主ならがっかりする。凧上げ。高く上がれば楽しい。上がらなければ面白くない。どんな遊びも、目標があり目標通りに行けば楽しく「報酬」が得られるが、失敗すれば負の報酬がある。
しかし、ステージでの成功不成功、対局での勝ち負け、釣果、上がった凧の高さなど「結果」だけが遊びの報酬なのでなく、その結果と関連のあるもろもろの活動の全体、ダンスの基本ステップ、定石/定跡を覚え、練習を繰り返すこと、また自作することも含め道具や用具をそろえるなどのこと、また体を動かし、あるいは頭の中で手を読むことそれ自体、などの多くのことがプラスやマイナスの報酬を与える。そしてほとんどの人は遊びが与えるこのようなさまざまな報酬の総計がプラスになると感じられるような種類の遊びを選ぶ。人が「面白い」、「楽しい」と感じる遊びとは報酬の総計がプラスだと感じられる遊びであり、「面白くない」、「楽しくない」と感じる遊びとは報酬の総計がマイナスだと感じられる遊びのことであろう。そして人は楽しくない遊びはやめ、別の遊びをするであろう。
だから「遊びはすべてうまくいく孤絶した領域の出来事ではない」というチクセントミハイの考えは半分当たっているが半分外れている。すでにホイジンハとカイヨワについての節で述べてことだが、遊びは、仕事とは別な種類の活動だが、日常生活とつながっていて、他の仕事や恋愛や子育てと同様その人の生を構成する現実的な活動であるという点で、彼は半分は正しい。
しかし、遊びは、チクセントミハイがいうように日常生活の他の諸活動と同様にあるいはそれ以上に「過ちが強く罰せられる」ような大きな負の報酬を与える活動ではない。そして、もちろん、遊びは「命がけで行う」ことではない。遊びは、何回か繰り返し行われる。いつも目標が達成されるわけではない。しかし目標が達成されなかった場合にも決定的なマイナス、罰を与えるのでなく、総計においてプラスであり楽しいと感じられるものである。
賭け事は、成果の達成には技能はほとんど必要ない。その意味でわたしがいま述べた遊びの要素である自己の能力・可能性を拡大する「挑戦」を含まない。しかしカイヨワの節で見たようにずっと昔から人間は賭け事を行ってきた。現代社会においても賭けること自体が楽しいと考える人も多く、競馬や競艇のファンが相当いることも事実である。とすれば、賭け事も(それが各自の支払い能力を超えない限りで、つまり重大な罰を与えない限りで)当然、遊びの一部門だと考えるべきだ。同じように「非挑戦的」で「問題発見的」でない、そしてフローを伴わない、楽しいだけの自己目的的活動がいくらでもある。それが遊びであろう。
クライマーが経験することのある「深いフロー」は、日常生活における経験とは「異質」で「特異な」経験であることはたしかである。しかしチクセントミハイによれば、無意識に行われる行動を含め、日常生活の中における多くの些細な行動の中にもフロー機能をもつものがある。これら些細な活動は、「最も単純な水準ではあるにしても、フロー・モデルに適合すると思われるところから、マイクロ〔小さい〕・フロー活動と呼ぶことにする」とかれは言う。かれはマイクロ・フロー活動として、白昼夢、知人との無駄話、読書しながらガムをかむこと、ひとりで口笛を吹くことなどのほか、音楽を聞く、テレビを見る、小説を読むことなどを上げる。
「たとえば、退屈な講義中に何気なく〔手元のノートに〕落書きしたり、手紙や論文を書くときの気分の集中を助けるために喫煙したり」というような「日常生活での些細な、往々にして自動的に行われる行為は、単にそれが楽しいからだけでなく、それらが時として、より構造的な活動への没入を助長するが故に重要である」。〔「構造的な活動」とは、講義を聴いたり、論文を書いたりすることをさす。〕
かれは被験者がそれらの行動を行わないようにする「剥奪実験」を行った。それによれば、48時間の実験でも行動が不活発になり、眠く、疲労し、くつろげなくなり、頭痛がするなどの影響が出、自発的な創造行為が減った。その5日後に行なった実験のあとでは、神経衰弱になるように感じた、手のやけど、膝のすりむきなどの事故を起こした、激しい眩暈のために扉に突き当たりめがねを壊したなど、急性精神分裂病の症状に似たはっきりとした悪影響が出た。つまりマイクロ・フロー活動は、それを行うことが妨げられると、日常生活にも重大な影響のある、深刻な結果が生ずる、という。
以上、私のコメント、意見を若干加えたところもあるが、チクセントミハイの述べるところを彼の章立ての順序に従い、ほぼそのまま要約し、紹介した。以下では疑問点をまとめて指摘し、私の意見を述べる。
「厳しく不愉快」と考えられている仕事を「楽しい」ものに変えることを目標に、チクセントミハイは人々が夢中になる「楽しい」活動をいくつか調査し、そこから抽出された特徴からなる「楽しさの理論モデル」を作った。彼はこの「楽しさのモデル」が有するのと同じ「楽しさ」の特徴を組み込んで、活動/仕事を構成ないし再構成すれば、分野・種類によらず、それらを楽しいものにすることができると考えている。
彼は最初の調査で、ロック・クライミング、作曲、モダン・ダンス、チェス、バスケットボールなどの活動を、金銭や名声などの外発的報酬を得るための仕事ではなく、楽しむことを目的とする自己目的的活動つまり「遊び」として行っている人々を対象として、かれらが楽しいと感じる理由を、調査者が示した8項目の中から順に選んでもらった。
その結果が第1表にまとめられているが、その「活動の経験の楽しさ」、あるいは「活動それ自体」などの内発的報酬を得られることが、高い順位を占めた。
第4章のタイトルにもなっている「楽しさの理論モデル」と言われているものは、これらの人々との面接で得られた、活動の中で彼らが行った経験についての説明を6項目にまとめたものである。しかし、その6項目は報告された諸経験の単なる要約なのではなく、それぞれの活動が有する様々な特徴、多くの要素のうち、その活動がある種のピークであるフロー状態にあるときに、その状態を構成している特徴、要素を抜き出したものである。
前にもふれたが、たとえばチェスの場合には、トーナメントでの対戦がチェスの楽しさの本質的な一部をなしているが、実際の対戦ばかりでなく、チェスに関する雑誌を購読し、国際試合などで行われた対戦を研究する、同じチェス愛好者との交友、時には家族ぐるみでの交際、社交生活を楽しむ、トーナメント参加のために旅行する、チェスの会報を編集する、クラブの企画運営を担当するなど、「チェス」には様々に異なった方法、アプローチでの楽しみかたがある、という。
しかし、チクセントミハイは、これらはチェスの「一次的な」報酬ではない。知的な戦いであることがチェスというゲームの構造との関りにおいて一次的な側面であり、友愛その他を生み出すということは二次的な問題に過ぎない」、「チェスの一次的報酬は、明らかにそのゲームへの知的挑戦から生ずるフロー経験である」とする。
トーナメントにおける対戦で相手を詰ませるために、集中して手を読み、良い手を発見しようとするときに没入、没我状態、フローが起こりやすいことは、明白である。ほかの側面に主な報酬を求めてチェスを行う人でも、対戦においてすぐに没入できるケースもあるようだ。しかし二次的側面を楽しむ多くのチェス愛好者があり、これらの人々がふだん楽しんでいる楽しみ方はハイレベルのチェスプレイヤーが楽しむのと同じような没入、没我(「天井が落ちても気がつかないでしょう」、「盤の外のできごとについての知覚は消失する。時間の感覚は停止する」)状態とは明らかに異なるはずである。
チェスでは、対戦中の(強い)フロー状態における楽しさと、雑誌を読んで研究したり、チェス仲間との交際を楽しむというような、楽しさとがあり、どちらも「楽しさ」と呼ぶことはできるが異なる状態だと考えられる。
チクセントミハイの言葉を引くと、人がフローにあるとは「しばしの間、我を忘れ、自分にまつわる問題を忘れる」状態である。「楽しさの理論モデル」の要素とされた語を使えば、「限定された刺激領域に注意を集中」しており、「行為と意識が融合」している状態である。私が愛好している釣りの経験に基づいて言えば、急に「入れ食い状態」になり、釣り人が他のことは一切忘れて魚を釣り上げることに夢中になっている状態である。
だがこれはごく短時間だけの、釣りの楽しさのピークであり、そのピークだけが「釣り」なのではない。フローになる「入れ食い状態」での釣りの楽しさは、海上で雨や風、暑さや寒さをがまんしつつ、その何倍もの時間、魚の到来をじっと待つことの「苦」、仕掛けを作り、道具の手入れをし、釣果を親戚、友人、知人に配ったり買ってもらったりする楽しみ、等々、様々な面を含む「釣り」の楽しさとは一致しない。入れ食いになった時に私はフロー状態になるが、それが釣りの活動全体の楽しさを示す状態だとは言えない。
一種類の活動の中に、様々に異なる楽しい状態があり、また様々な状態の総合されたものが楽しさである。そして「楽しい」という状態のなかには「フロー」も含まれるとは言えても、楽しいからといって、フロー状態にあるとは言えないし、フローの状態がチェスや釣りなどその活動の楽しさの全体ではない。
チクセントミハイは、フローは宗教家が経験する恍惚状態に類似しているという。そしてロック・クライミング中に経験したフローにおいて「エクスタシー」を感じたと報告しているクライマーは、知覚の変容、自我構造(つまり世界観や人生観)の変容を報告している。
だが、私は、ふつうの遊びで、それが非常に楽しく、ある時間夢中になり没入したからといって、遊びで「恍惚」となってしまったり、物の見え方が変わり世界観、人生観が変わってしまうなどということは起こらないと思う。好きな趣味や遊びを重視して、職業を変えたり住所を変えたりすることは、チクセントミハイの報告しているようなクライマーでなくてもままあることだ。しかし、そのためには、人生にしめる仕事と遊びの比重の若干の見直しが必要ではあっても、それは「自我」あるいは「自己」の比較考量のはたらきによってなされるのであり、世界観が変わったり自我が変容してしたりすることは必要ない。
何かを楽しむことができるのは、完全に没頭するのではなく、やっていることにある程度距離をとり、余裕をもって、つまり自分が楽しみながらそれをやっていることをときどき感じながら行うときであろう。人がフロー状態にあるのではなく、何かを楽しんでいるときには、自我が変容したり、自己意識が消失したりすることはない。楽しんでいるときには人は「無」になるのではなく、楽しいと感じている。行為に没入するのでなく、自分が楽しんでいることを心の片隅では意識しており、知っている。
またチクセントミハイは「人はフローをいかなる活動においても、例えば戦場、工場の流れ作業、または強制収容所などでの、およそ楽しさとは無縁と思われる活動においてすら経験しうる」言っている。私は強制収容所での作業については触れない。
工場の流れ作業におけるフローとは、動作が(例えば繰り返しボルトを締めるというような)一定範囲のものに限られおり、何も考えなくても(つまり意識と行為が分離せず)作業が規則正しくおこないうる状態を指すのだろう。彼は、工場労働者も流れ作業でフローを経験しうると言っているが、他方で高度産業国の労働者が「根深い疎外感」を抱いていると述べていた。工場労働者は生存するための必要からいわば止むを得ず働いているのであり、自分の行っている流れ作業を「楽しい」と感じながら行っているとは思われない。
また、戦場でのフローとは、兵士が敵の兵士によって殺されまいと、必死になって戦闘行為を行うときの極度に緊張した状況で、なにも考えなくても訓練で教わった通りに手足が動くというような状態のことであろう。戦場で必要なことは自分が殺されないために相手を殺すことであり、「社会的諸要求」に従って自己をコントロールする自我のはたらきなどは全く必要ない。おそらく兵士たちの自我は戦地で何らかの程度損なわれ、生きて故国に帰ったとしても、社会に適応できず苦しむことになる。
これらの場合に経験されるフローは、楽しさとは全く異なる。フローは楽しさとは無縁であるような状況や活動においても経験しうる特異な状態のことである。
ところが、チクセントミハイは第4章で「フローという語は我々が〔その前の章で〕「自己目的的経験」と呼んできたものである」と言って、フローを自己目的的活動での報酬つまり「楽しさ」と同じものだとする。
たしかに、第4章の「楽しさの理論モデル」を構成する「行為と意識の融合」以下の6項目は、チェスやロック・クライミングなどの遊びやスポーツ、つまり自己目的的活動を行っている人々の経験の報告に含まれている。
とはいえ、それらは、それら諸活動の「第一次的な」活動をおこなっていてフロー状態にあるときの経験について述べていることから抜き書きされたものである。「楽しさの理論モデル」とされているものは実際には「フローの理論モデル」なのである。だが、今見たように、「フロー」は「楽しさ」の一部をなすこともあるが、また「楽しさ」と全く無縁な状況でも経験されることのある何かであり、楽しさとは一致しないと思われる。
こうして、「フロー」のモデルであるチクセントミハイの「楽しさの理論モデル」に従って新たな活動を構成し、あるいは既存の活動を再構成したとしても、その活動は普通の意味での「楽しい」活動と一致するわけではないということは明らかであ
る。
このモデルが、遊びに見出すことができるような普通の「楽しさ」の要素から成るものではないということは、モデル作成のための調査の対象になった自己目的的活動の分野に偏りがあることからもわかる。
彼が理論モデル作成の基礎的調査の対象にした自己目的的活動は、バスケットボール、ハンドボールそれにチェスのような競技スポーツであるか、競技でないものとしては非常に大きな危険を伴う「深い遊び」であるロック・クライミングである。「作曲」はごく少数の、才能のある「エリート」にしか行いえない遊びである。
他方、彼は「釣り、ボウリング、ギャンブル」など「低い社会経済的階層」の人々により広く行われている遊びを調査の対象にはしなかった。
球技やチェスなどの競技スポーツ、また危険を伴うロック・クライミング、そして「作曲」などの「フロー活動」の場合には、「筋の通った因果の体系のなかにあり、そこでかれが行うことは、現実的で予想可能な結果を伴うことになる」。そして「行為の統御」あるいは、「技能をフルに働かせる」ことが必要である。
他方、ふつうの「遊び」の場合、カイヨワの分類でいえばパイディアであるような遊び、また「偶然の遊び」つまり運が左右する遊びや、肉体的精神的混乱状態に浸かること、つまり、眩暈を追求する遊びなどでは、そうしたことは言えない。「気ままな欲求に従う」無秩序で自由な活動や、偶然にしたがったり眩暈を求めたりする遊びの場合には、行為が「筋の通った因果の体系のなかにあり、そこでかれが行うことは、現実的で予想可能な結果を伴うことになる」とは言えず、また「行為の統御」、「技能による挑戦」が必要だとはほとんど言えない。
賭けは一種の挑戦と解釈できなくもない。しかし、チクセントミハイのいう挑戦は、カイヨワが言っているような「偶然の支配に受動的に身をゆだねる」ことではない。チクセントミハイは「挑戦には二つの型が考えられる。一つは発見、探索、問題解決へと連なる、見知らぬものへの挑戦、つまり、作曲、ダンス、クライミング、チェス等に本来備わっている挑戦であり、他はバスケのような活動にとって重要な、最も具体的な〔戦うべき敵に対する〕挑戦である」と言う。ギャンブルを一種の「挑戦」と見なすにしても、チクセントミハイが言う「挑戦」でないことは明らかである。
第11章「楽しさの政治学」では次のように書かれている。彼がフロー体験の聴き取り調査を行った、チェス、ロック・ダンス、クライミングなどの「余暇活動は全般に「エリート」の、少なくとも中流階層の文化形態に属するもの」である。「従って、これらの活動を、低い社会経済的階層特有のライフスタイルをもつ人々が広く行なう楽しさの構造にまで一般化することは困難であろう。例えば、釣り、ボウリング、ギャンブル等は、今回研究された自己目的的活動に典型的に見られる経験とは異なるものであろう」。「これらの活動では、挑戦の幅は狭いだろうし、問題発見の感覚もそれほど強くはないであろう」。
チクセントミハイはギャンブルが強い「フロー」感、つまり、夢中、熱中を生み出すことは知っている。フロー・モデル作成の1つの源泉としては役だち得たはずである。しかし、「没入」、夢中・熱中はどの自己目的的活動にも備わっている。ギャンブルは彼の構想する「フロー」ないし「楽しさの理論モデル」の作成に不可欠ではない。他方「釣りやギャンブル」は運に左右される遊びであり、「技能による挑戦の幅が狭く問題発見の感覚もそれほど強くない」。それらは、彼の考える「フロー=楽しみ」の理論モデル構築には、どちらかといえば、阻害的である。これらの遊びを調査対象から外したのは、こうした理由によると私は推測する。
こうして、彼の「楽しさの理論モデル」からは、賭けごとの楽しみ、あるいは釣りのような運の要素が大きい遊びによる楽しみや、遊園地の機械に受動的に身を任せ落下の恐怖やハイスピードの虐待にさらされることの楽しみは排除されている。彼は「自己目的的活動の、---もっとも基本的な必要条件は、それが明確な挑戦の方向を備えているということである」と言う。彼の「楽しさの理論モデル」は「挑戦や問題発見」という要素を含むようなタイプの遊びをもとにして作られた「フローの理論モデル」である。
つまり、彼が第4章で提示している「楽しさの理論モデル」とは様々に異なった特徴をもつスポーツや遊びの広範な調査を踏まえて、それらに共通する「楽しさ」の特徴の集まりとして組み立てられたものなのではない。彼が「楽しさの理論モデル」に組み込んだ諸特徴は、遊び全般が有する諸特徴ではなく、仕事が有する諸特徴と整合するような、一部の遊びがもつ諸特徴、あるいは遊びのもつ諸特徴の一部である。「楽しさの理論モデル」はたしかに遊びと仕事に共通な要素からなるモデルなのだが、仕事に打ち込むことに妨げとなる遊びの要素を始めから除外して作られた「モデル」なのである。
世界が「筋の通った因果の体系のなかにあり、そこで人が行うことは、現実的で予想可能な結果を伴うことになる」と信じること、そのような世界における「挑戦と発見」を目指すことは、ルールによってつくられた「競争」の遊び、スポーツの重要な特徴である。そしてそれはまた「仕事」において求められる基本的な態度である。「学校、事務所、工場」での勉強・仕事は運任せや眩暈に浸っているというような受動的態度とは両立しない。「遊びと仕事の二分論」が乗り越え可能であるとすれば、受動的態度は除外されなければならない。
フローとは、挑戦的であるような活動に夢中になって打ち込むときの経験である。フローの状態で仕事をすれば、嫌々行うのとは違って、あるいは仕事が自分にむいているかどうかなどと迷いつつ行う場合とは違い、「時間があっという間に経ち」、仕事は捗るであろう。だが、だからといってその仕事が楽しく行われたかどうかは別のことである。
だが「勤勉」は当然仕事上の成功を生み出したし、「禁欲」は資本の蓄積を可能にし、事業の継続的拡大につながった。こうして彼らは、仕事以外の生活を楽しみつつ、仕事も行う伝統的なやり方に頼っていた経営者たちを駆逐し、近代的な資本主義世界を生み出したのである。
チクセントミハイは次のように言う。「永遠の生命への願望は、彼らの字義通りの目的であるというよりも、むしろ人々のエネルギーを再組織するためのもっともらしい口実」である。275-7.「プロテスタントの倫理が現実に貢献したのは明瞭なフィードバック〔利益の増大〕を備えた一定のルール〔商売方法=「限定された刺激」〕を人々に与え、それによって信者が自らの生活を秩序化し〔=「首尾一貫した矛盾のない行動」を行う〕、退屈と不安とを避けることができたということである。----言葉をかえていえば、われわれはプロテスタントの倫理を----新たな「ゲーム」すなわち、フロー活動とみなすことができよう。この教条の信者が、あらゆる形態の楽しさを非難せねばならず、他方で――少なくともわれわれの解釈によれば――彼らは非常に厳しい生活の苦役を楽しんでいたに違いないということは皮肉なことである」。
チクセントミハイは、信者たちの「永遠の生命への願望」(そしてその裏にある、永遠の地獄の業火に焼かれることへの恐れ)は、「もっともらしい口実」に過ぎなかったと「解釈」する。彼は、宗教的経験は、フローの特徴、一事への専念、没入という点で、スポーツや遊びにおける夢中、熱中に似ていると言っているだけなのではない。人間の運命を自由に支配する全能の神の命令に従い、「緊張力を保ち、---恐ろしく強度な労働にも耐え、生真面目にたゆみなく綿密に徹底的に物事に打ち込んでいた」人々の活動の全体を意識的に切り捨て、彼らの経験を単なる、一事への専念、没入、あるいは集中、熱中に切り詰めることによって、フローと同じものと見なしているのである。
クライマーは自己の有する技能に適合した難度の岩壁に挑戦することによって、退屈と不安を避け得るとされていたが、「楽しさ」を求めて活動を行なう人々は、予め練習を行なうことによって技能を身につけ、各自の技能に応じた難度の機会に挑戦するのであって、スポーツや遊びで「退屈と不安」を避けることができるということは予め分かっていることである。
また、ダンスやチェスやその他のスポーツや遊びは「楽しさ」が「報酬」なのであって、プレイヤーたちは、(クライマーの場合は別としても)ゲームに負けても、見込んでいた「報酬」が得られないことによる落胆の小さなマイナスを受け取るだけであって、生命を失うことを恐れなければならないわけでは全くない。こうしてチェス・プレイヤーやスポーツマンの場合には、確かに、自由に、活動を楽しみつつ、フローを経験することができる。
しかし、宗教改革期のプロテスタントの営利活動は全く別である。経済、社会が大きく変化しつつあったこの時期、予め「練習」のできない営利活動に成功するかどうかは全くわからなかっただろう。しかも、プロテスタントは、営利活動と言うゲームに挑戦しただけなのではなく、そこには彼の永遠の生命が賭けられていた。営利活動と信仰は一体のものであった。
彼らは営利活動に打ち込むと同時に、旧教側の激しい弾圧に屈せず自分たちの信仰を守るために文字通り命がけの「宗教戦争」を闘ったが、それは永遠の生命に与りたい一心からであった。彼らは、彼らの信仰を棄てて「永遠の地獄の業火」に焼かれるくらいなら、旧教徒と戦って死ぬことも厭わなかった。だから彼らはもちろん「退屈」はしなかったであろうが、強迫神経症に似た「不安」に駆られつつ仕事に明け暮れる生活を送っていたはずで、そこには、たとえば、チクセントミハイの被験者の外科医が語っているような「おもしろい」、「わくわくする」、「すばらしい」、「他の何よりも胸が躍る」などといった、「楽しい」感じは一切存在しなかったと考えられる。
なるほど、何かに没頭、没入していたという点では、現代の外科医と、あるいはクライマーやダンサーなどスポーツや遊びに熱中している人々と、宗教改革期のプロテスタントは似ていると言えるだろう。しかし、その何かとは、当時のプロテスタントにとっては、営利活動であると同時に彼らの宗教倫理の実践であり、そしてそれはいわば生の全体に等しいもの、現世における生命・生活と引き換えにしても惜しくない何かであった。
それに対して、現代の外科医たちは、手術中は仕事に没入するとはいえ、他方で、社会的な尊敬や高額の金銭的報酬を受け取ってもいて、この世の生を大いに楽しんでもいる。外科医たちは彼らの職業を文字通り神に命ぜられた天職として、命がけで遂行しようとしているわけではない。プロテスタントの生の全体を賭けた勤勉禁欲の倫理に従う営利活動への没入が、スポーツや遊びの中で感じる、熱中、没頭とは異質なものであることは明らかである。
だが、チクセントミハイは、彼らの主観的な経験は捨象して、規則正しい生活のしかたなど、主として外面的な特徴だけで、彼らの宗教的経験が「ゲーム」におけるものと同じものだと「解釈」する。内面的に全く正反対であるような経験を行っているにも関わらず、フローにあるがゆえに、彼らは「楽しんでいる」と見なされる。
宗教改革期の歴史の解釈の適否が問題なのではない。彼は「学校、工場、事務所」などをはじめ社会における全ての活動が 彼の「フロー」モデルに従って「再構造化」されるべきだ、つまり作り変えられるべきだと考えている。「経験の他の部分から孤立した「ゲーム」やフロー活動を増加させることによって、個人的、社会的疎外を消去できると結論することは誤り」だといい、「生活のすべてが、これらフローの特殊化された形態によって例示される線に沿って再構造化されなければならない」という。彼が提出する「楽しさの理論モデル」ないしは「フロー」を構成する諸特徴を活動の中に組み込むようにすれば、活動の種類によらず(「仕事」、また「工場の流れ作業」においても)、あるいは情況の種類によらず(強制収容所でも、戦場においても)、活動を楽しいものにすることができる、と主張している。
彼は「ひとたび、この〔楽しさの〕概念が明確にされ、操作化されるならば、我々はGNPやIQ、身体的健康やカロリー摂取のような、生活の「現実的」次元を扱うのと同じやり方で楽しさの問題を扱うことができる」という。 だが、彼が提案しているのは、人々が自分のやってみたい様々な活動に自由に挑戦し、楽しいと感じられる仕事に就くことができるようにするということではない。これまで見てきた限り、「楽しさ」は各人が主観的に感じる状態なのではなく、あの6項目の特徴で「例示されて」いるもの、と考えられている。
このフロー、ないし「楽しさの理論モデル」に即して組み立てられた仕事・活動に就いた人は、その人が実際にどのように感じたかにかかわらず、「楽しい」活動を行ったと見なされることになるであろう。チクセントミハイは生活のすべての活動で楽しさを享受できる社会に作り変えるよう提案しているが、すべての仕事が「楽しく」行うことができるのであれば、仕事とは異なる領域で遊びを求める必要はなくなるように思われる。すると、逆説的だが、その社会はすべての人が勤勉禁欲の倫理にしたがって仕事に打ち込む、プロテスタントの社会に似たものになることもあるのではないだろうか。
彼は第一章で「仕事が厳しく不愉快なものだ」と感じるのは、そのように「教え込まれ」た結果であり、「仕事が厳しく不愉快なものである」というのは事実なのではなく「仮定」なのだとい言っていた。最後の章におけるプロテスタントの倫理と彼らの宗教活動の解釈を通じて、彼は、フロー状態になることができれば、つまり夢中になって仕事に打ち込めることができれば、あなたは楽しんでいるのだと、何らかのしかたで、人々に教え込むことができれば、それでもかまわないと示唆しているように思われる。
ただし、チクセントミハイは、遊びと仕事の区別は残ると考えているようである。その点については、またあとでふれる。ここでは、フロー活動を楽しい活動とみなすことは、社会のすべての活動を「楽しい」ものにはせず、逆にプロテスタント的な勤勉禁欲の倫理が支配する、仕事ばかりの日常を生み出す可能性もあるということを指摘しておく。
チクセントミハイの言う、スポーツや遊び、外科手術などにおけるフローは日常語で熱中とか夢中といわれる経験に似たものである。楽しさの度合いが大きいほど熱中や夢中の状態を生みだすだろう。だが、フローの核、熱中・夢中,没入・没我は遊びやスポーツのような特定の領域における活動から得られる経験に限らず、さまざまな状況において生み出される。プロテスタントの営利活動・仕事への傾倒はフローと見なされたが、このフローは、少なくとも信者自身の意識においては、遊びにおけるフローのような楽しさを伴うものではなかったはずである。私が触れた三昧は静かな瞑想の中で到達される「無我」の状態、「清澄」で静かな一心不乱であった。
「戦場」でのフローについて上でふれたが、この場合のフローも楽しさとは無縁である。また、事故や災害による切迫した危機に対処しようとするときには、「無我夢中」で行動がなされる。無我夢中であってもパニックに陥り、闇雲に、非合理な行動を行うとは限らず、意識を集中し自己の持てる力を最大限に発揮した合理的な行動がとられる場合もあろう。そして、そのときにもフローが経験されているといえるであろう。
こうして「楽しい」活動によって経験される「楽しい」フローもあるが、事故や災害あるいは戦争のような情況における厳しく、辛く、苦しいフローもある。フローは楽しい経験ばかりではなく、強い不安や恐怖によっても生み出される。
チクセントミハイは、歴史家の研究に依拠して「19世紀以前の織物職の親方や、各種の職人」が「自分の仕事を楽しんでいた誇り高い、独立した人々」であったと言い、現代の労働者は生産効率の観点によって編成された労働過程に縛り付けられ、かつての労働者が享受できた仕事の楽しさを奪われていると批判する。
だが、「かつての労働者」のすべてが仕事を楽しみながら行なっていたのだろうか。仕事を楽しむことができたのは少数のエリート労働者、「親方」や独立「職人」あるい「熟練労働者」に限られていたのではないか。現代においても少数の「研究者」「専門技術者」、あるいは「外科医」たちは「楽しさ」を感じながら仕事を行なっていると思われる。
これら少数の人々は、他者の直接的な指揮や監督を受けることなしに、仕事を自由に行なうことができる点で、一般的な労働者とは異なる。かつての「職人」や「熟練労働者」も、資本家の指揮・命令系統に属さず「独立」していたことによって、仕事を自由に楽しんで行なうことができたのではないか。
チクセントミハイは「楽しさの理論モデル」を提示するのに先立つ第3章では、楽しさに関する先行研究について言及しつつ、過去、哲学者たちは遊びを高く評価してきたが、それは、「自由は楽しい行為の基本的標準」であるからであり、「遊びは参加と離脱の自由な活動である」と書いている。
また、第11章では、「調査の結果、我々は、自己目的的な経験〔つまり楽しさの経験〕の中に非常に顕著に現れる、自由、技能、成長、自己超越などの諸様相を強調するようになった」と言っている。
しかし、彼が調査結果をまとめたものである、第1表、(それと同様の「楽しい理由」の順位を活動の種類ごとに分けて示した)第2表の「楽しい理由」にも、第3表の「自己目的的経験との類似性順位」の中にも、また、これらに基づいて提出された「楽しさの理論モデル」の6項目の要素の中にも、「フロー」あるいは「楽しさ」と「自由」との結びつきを意味する要素は一つも含まれていない。
自由な行為においては、行為は「自動的」に行なわれることはないし行為者はロボットではありえない。少なくとも「行為と意識の融合」、没入や没我は、いま問題にしている自由の要素ではありえない。没入していれば、そこから自由に離脱することはできないからである。
楽しさは楽しむ自己についての意識を伴っており、また遊びをやめることに結びつく様々な諸事情(天候、体の調子、仕事の都合、等々)に対する意識をも部分的には伴っている。他方、他の一切のことを忘れ、「限定された刺激領域」に没入するフロー状態においては、遊ぶ人は完全に楽しさのとりこになってしまう。
フローはしばしば(釣りの場合には突然の入れ食いによって始まるように)突然始まり、フロー状態における行為は意識的にではなく「自動的に」行われる。そして、ロック・クライミングの場合そうであるように、登頂という目標が達成された時に、自分の意志によってでなく、自動的に終わる。
(以上に関しては、次の第五節「西村清和『遊びの現象学』における遊び論」の中の、「<遊びはもっぱら現実態である>への反論、「遊びをやめる自由はない?」、「遊びは倦怠によって終わる?」の三つの項における議論を参照。)
フローはその一種であるとされる宗教的なエクスタシーの場合と同様、外から、突然、あるいは偶然に訪れることが多い。しかし、スポーツや遊びは自由に行なわれる活動であり、自分の意志で始める。そして、様々な理由によって、それを終わりにしたり、中止したりする。つまりそれらの活動を楽しむ(ために行う)かどうかは参加者、プレイヤーが自由に決められる。しかし、フローに入ったり抜け出したりすることは自由にはできない。
外科医や作曲家、研究者や専門技術者の仕事は、それぞれの人が自らの意志で仕事に着手するかどうかを決め、自らの判断で仕事の内容ややり方を決める。彼らの仕事は「楽しい」。彼らは仕事をいつ始めるかいつ止めるかを自由に決める。しかし、その仕事の最中に、いつ「フロー」に入るかを決めることはできない。フローは自らの意志で自由に出入りするというわけにはいかない状態である。
スポーツや外科手術や作曲など「楽しい活動」においては自由の度合いがはるかに大きい。従って、チクセントミハイは「楽しい活動」の特徴として、自由に行なわれるという点を強調することもできたはずである。しかし彼は「楽しさ」を考察するときに、楽しさの全体を考察せず、その自由の要素を捨象して没入、没我の瞬間であるフロー状態が楽しさだと考えてしまった。
いったん、楽しさをフローと同一視してしまうと、楽しさは自由と無関係なものになってしまう。こうしてかれは「戦場においても、工場の流れ作業においても、強制収容所でも、フローは経験し得る」と言った。彼は「楽しさ」とはなんであるかを明らかにしようとしたはずなのだが、彼は「フローはいかなる活動においても、---およそ楽しさとは無縁と思われる活動においてすら経験しうる」と述べて平然としている。
スポーツや遊びを行う人々と現代の外科医、また産業革命前の「職人」たちは活動を自由に行なっているという特徴が見られる。他方、事故・災害・戦争においては恐怖、強い不安が支配している。プロテスタントの宗教倫理に従う行動は、信者たちが旧教から決別し、一人一人、かれらの信仰を自由に選び取ったのであれば、自由の産物と言えるであろう。しかし、彼らの職業への没頭が、永遠の地獄に落とされることを避けたいという恐怖によって動機づけられていたとすれば、かれらは自由ではなかったことになろう。
フローに達するには様々な動機と様々な道がある。楽しさを追求して、自由に、楽しい活動・遊びを行うことを通じて、フローに到達することもあろう。しかしまた、神による救いを求めて、神の命じる厳しい掟(禁欲と勤勉)の実践を通じてフローに到達することもあろう。災害や戦争の中で自分の命を守るために、ありとあらゆる可能な行動をとることを通じて、フローに到達することもあろう。だからフローには、熱中・傾倒、没入・没我、無我夢中の様々なフローがあり、フローは楽しさと同じではない。
人は楽しいことには夢中になる。つまり「楽しさはフローをもたらす(ことがある)」ということは事実であろう。ところが、チクセントミハイは、“それゆえ”「フローと楽しさは同じである」あるいは「フローをもたらす活動は楽しい」と考える。「AならばB」が成り立っても、逆の「BならばA」は成り立たないことがある(「逆は必ずしも真ならず」)という基本的な真理を彼は無視する。彼はフローできるように再構造化すれば仕事は楽しくなると考えているが、それは真実ではない。
第11章「楽しさの政治学」では、チクセントミハイは、レジャー中心の文化のなかで成長する米国の青年が、「現実的な挑戦への取り組みに最善をつくす」ことのできる「確信に満ち、発展性のある自我」を形成することができないでいると指摘し、その原因は「遊びと仕事という二分法」にあるという。
そして、この「二分法」の「分裂」を克服するために青年たちに必要な第一歩は「仕事はかならずしも遊びより重要だとはかぎらないということ、および、遊びは仕事より面白いとは限らないということを、理解することである。重要であり、かつ面白いというのは、挑戦が新しい能力の発展を刺激するような状況で、自分の能力をフルに発揮して行動することである。そのような状況が、仕事であろうと遊びであろうと、生産にかかわるものであろうがレクリエーションにかかわるものであろうが問題ではない。フロー経験をうみだすならば、それらは等しく生産的といえる」と言う。
少しわかりにくい文だが、どんな活動であれ、それが「挑戦的」で、しかも、その「挑戦が新しい能力の発展を刺激する」ものならば、つまり、絶えず新たな進歩・発展を促すようなものであり、「フロー」を経験できる、つまり夢中になって打ち込めるものならば「生産的」だ、と言うのだろう。「生産的」という語もわかりにくい。しかしチクセントミハイがそのような活動を大いに「よい」ものとして肯定的な評価を与えていることは確かだ。ここでは、単に適度に挑戦的であるような一つのことを繰り返しうまく遂行することによって満足感を得ることではなく、絶えず新しいことに挑戦し続けることが「大切だ」というくらいの意味で受け取って間違いはないだろう。
これはかつて「西部開拓」(インディアンと呼ばれた先住民の人々にとっては、略奪)時代に培われたフロンティア・スピリッツと呼ばれる、アメリカ特有の人間観である。企業活動もスポーツも、必要を満たし楽しむためにあるのではなく、絶えず新たな課題に挑戦し、進歩し続けること、満たされることではなく、絶えず欲求し続けること、そのために挑戦することが人間にとって最も重要なことだという考え方である。
彼は、一面においては、人間が、特定の狭い領域のなかだけでフローを楽しみつつ「進歩・発展する」ことが必ずしも望ましいことではないとも考えている。外科医におけるフロー中毒にふれつつ、次のように言っている。 「深いフローの世界の単純な美は魅惑的に過ぎ」、「いずれのフロー活動も習慣形成的なものになりうる。---ある活動への参加者が、---特定の狭い挑戦に依存するようになり、他の全てのことが楽しくなくなることもある。チェスをしたり、ロック・クライミングをしている時にのみ生き生きしているということは、人間の適応上あまり好ましいこととは言えない。このような偏狭さは、極めて特殊化した生態学的地位(ニッチ)への適応と類似している。つまり、環境のわずかな変化も致命的なものとなる。したがって、人はいくつかの異なった領域での技能を磨くべきであろう」。彼は、フローを求めることの習慣性、そして人格の狭隘化などの問題点を指摘することを忘れてはいない。
だが、基本的に、人間はフローを経験すること、つまり夢中になって何かに打ち込むことが、幸福である。そしてフローの要件が挑戦であり、挑戦は新たな挑戦を含む。こうして人間は絶えず進歩発展することが幸福なのだと考えられている。
社会的に有意義かつ重要で、しかも楽しいと感じつつ挑戦し、結果としてフローを経験することができる、そのような仕事に誰もが自由につくことができる(そして、必ずしも、挑戦的な仕事を好まず、のんびりゆったり仕事をしたいという人の自由も尊重される)というのであれば、反対する人はいないだろう。私も大いに賛成だ。
しかし、本人の希望と関係なく役所によって「最適な」仕事が配給されたり、ハローワークに行っても、その人の登録されている技能とパーソナリティに「適した」仕事のリストしか提供されないというような社会、そして人々の幸福がフロー経験と同一視されるがゆえに、仕事に没頭せず、またのんびりした遊びあるいは運任せのゲームを好むためにフローを経験しない人々が、白い目で見られ、肩身の狭い思いをしなければならないような社会は決して望ましくない。
私の職場では定年退職の年齢は65歳であったが、私は60歳で退職することに決め、その2年程前に立てた計画に従い、事前の準備をした上で退職した。私は、定年制度により自動的に仕事の世界から遊びの世界に移ったのでも移らされたのでもない。私は自分の意思で仕事を止めた。主体的決断によって遊びを選び、遊ぶことを企てたと言えなくもない。だが、早期退職を選ぶと言うことはよくあるだろうし、また、退職後、再就職せずにのんびり遊んで暮らすことを選ぶという生き方は少しもめずらしいことではない。その際、私は当然、決して多くない年金で働かずに生活が可能かどうか、家族の分も含めて、考量した。こうした考量や選択や決定もだれでも行うことだろうし、ことさら「主体的」だとか「企てだ」とかいう語で言いたてることでもないと思う。私は、早期に退職し、老後を遊んで暮らすことに決めた。考え、選択し、そう決めた。ただそれだけのことである。
しかし、遊びは、自分から進んで、考量したり、選択したり、決断したりして行うものではないと考える人もある。これから取り上げる西村はそのように考えている。西村に言わせると、遊びは人間を取り巻くほかの現実とはまったく異なる特徴を持っている。多くのこと、たとえば、仕事は、意図して、つまり「しようと考えて」、段取りその他を考えて行う。いやな仕事もほかの事情を考えて、あえて我慢して行う。
以前の社会においては、社会的慣習やしきたりのようなものによって、人の行動はあらかじめ決められていた。人は自分の生まれた家の家業を継ぎ、親が指定した相手、あるいは家同士の話し合いで決められた相手と結婚することが当たり前で、自分で職業を選択したり、自分の考えで結婚したりするのではなかった。主体的に、自分の意思で行動することはできなかったし、する必要がなかった。近代社会になって人は自分で考え、(一定の条件はあろうが)選び、自分のしたいことを企てることができるようになったし、そうしなければならなくなった。しかし、西村によれば、それは各人に、主体的であること、イニシャティブの発揮を強いることである。だが、遊びにおいては、その必要がない。
彼の見方によれば、考え、計画して仕事中心の生活に入ることはあり得ても、そのようにして遊びの生活に入ることはあり得ないことになる。彼の見方が正しければ私の現在の生活は、仕事でも遊びでもない不可思議なものであろう。西村の遊び論が間違っているのか、私の現実生活が実は幻なのか。どっちであろうか。
西村は、「風に吹かれて揺れ動く柳の枝の遊び、ざわめき立つさざなみの遊び、さざなみに反射してきらきらと戯れる光の遊び、--」にも遊びを見出す。それらを遊びと呼ぶことは「単なるメタファー以上の意味」をもつ25。ここでは、これらを見る「私」がそれら現象の「気まぐれであてどない往還の遊動」と遊んでいるのである。私が「風景に遊ぶ」のだ。そこには、私の「と・遊ぶ」関与がある。しかし、それは、分析したり、支配したりしようとする主体の企てとは異なる関与であると西村は言う。それら風景に「誘われ、われ知らずその遊動に引き込まれるといった、ある独特の関与」である。28われわれは「風景「に・遊ぶ」」。
気がつくとポケットの中の鍵束をもてあそんでいることがある。「主体たる資格で、意図してポケットをまさぐり鍵束に手を伸ばして、これをつかみとったのではない。気がついたとき、私の掌と鍵束とは、ふれあいの同調のただなかにともにあったのである。」「「鍵束と遊ぶ」、あるいは「かぎ束で遊ぶ」とは私の掌がかぎ束「と」の相互的な同調という関係にまきこまれており、その遊隙の「場」でさまざまに生起する気分や状況「に・遊ぶ」ことを意味している。---遊びとは、ある特定の活動であるよりも、一つの関係であり、この関係にたつものの、ある独特のあり方、存在様態であり、存在状況である。それは、ものとわたしの間で、いずれが主体とも客体ともわかちがたく、つかずはなれずゆきつもどりつする遊動のパトス〔情動、情緒〕的関係である」。
西村はこのように、ホイジンハやカイヨワでは考察の対象になっていなかった、自然現象や掌とかぎ束の関係のような非意思的現象のなかにある「遊び」を分析しながら彼の議論を進める。
彼の著作のタイトルは「遊びの現象学」で、おそらく、「掌とかぎ束」の遊びや「いない・いない・ばあ」などは彼独自の現象学的な分析なのであろう。だが彼の議論はボイテンデイク、ハイデガー、ガダマーなどからの多くの引用を含み、これらの人々の議論の再構成でもある。
西村は、遊びの根本的な特徴を「遊び手と遊び相手とのあいだにおのずと生じる、主客分ちがたい関係」にあるとするのだが、彼は、ガダマーがこの関係を「遊びのもっとも根源的な意味」としての「中動相的な意味」と呼んでいることをあげて、「まことに適切な表現」だという。(中動相とは能動態と受動態の中間的な形態を指す文法用語である。)彼は第二章「遊びの祖型」の第二節に「遊びの中動相」という題をつけている。
また、ガダマーは「遊戯運動そのものはいわば基体(Substrat〔根本で支えているもの〕)をもたない。-----」と言っていること、「遊び手の意識に対する、遊びの優位」を主張していること、遊びのテーマについての研究は「いわば主体性から出発する思考方式の限界点に導かれる」と述べていることなどを引く。こうして、彼は、遊びの本質あるいは根源的特徴だとすることの多くをガダマーに依拠して述べている。
だいぶ前に、ハーバーマスとガダマーの論争が行われた頃、私はハーバーマスに魅かれており、ガダマーをほとんど読まずに嫌っていた。この機会にガダマーを読んでみようと考え、西村の依拠する『真理と方法』、および『小論集』を読んだ。そこでまず、ガダマーが『真理と方法』で述べている遊びについての議論を先に紹介、検討して、そのあとで西村の遊び論を検討しようと思う
ガダマーの論述の順序とは逆になるが、あらかじめ、「芸術」(芸術作品、そしてその経験)についての彼の考えの概略を示すことにする。
芸術作品が意味をもたない自然の美と異なるのは、それが人間、芸術家の作品であり、芸術家が、その作品に彼の語りたいことを考え入れたからであろうか。そうとも言えるし、そうでないとも言える。ガダマーは、悲劇について、言う。その制作者である「詩人がどれほど自由な創作をしている場合であっても、その創作はあくまで、すでに妥当している伝統に縛られている媒介者としての一側面に過ぎない。---詩人の自由な創作は、その詩人自身をも拘束している共通の真理の表現なのである。/これは他の芸術ジャンル、とくに造形芸術に関しても変わりない。‐-‐-素材を選択し、また選択した素材を作品に仕上げるのは、芸術家の自由気儘によることではないし、それはまた単に彼の内面の表現なのでもない。」芸術家とは、自由に創造する主体でもあるが、同時に、それ以上に、彼の置かれている伝統のなかに存在する真理・真実を観客に伝達する「媒介者」あるいは「媒体」であるに過ぎない。
他方、作品の鑑賞のために集まって来る観客は芸術家と共通の世界に属しており、彼らが芸術作品の鑑賞により引き込まれ「取り込まれている世界は、いつも彼〔ら〕自身の世界であり、-‐-その世界の内で自己をよりいっそう深く認識する」。彼らは芸術の経験において、世界そのもと再度出会い、(その作品と出会うまでは知らなかった)世界の本当のあり方を理解する。『真理と方法』
芸術作品は、個人的主観的な表現なのではなく、もっと包括的で、普遍的な意味をもつもの、歴史的社会の、ヘーゲルの言葉を使えば「時代精神」の表現だということになる。だが、そのことは、こんどは、芸術作品が、それが生み出された時代と異なる時代の観客あるいは鑑賞者に対しては、共通のものを持っていないことを意味するのではないだろうか。中世の宗教的な世界に生きていた人々と、非宗教的な産業社会に生きる現代人とでは、同じ芸術作品に対する関係は全く異なるのではなかろうか。実際ガダマーも、戯曲や音楽作品の場合には「それらの上演とか演奏は時代が異なり、機会が異なるごとに違ったものであり、違わざるをえない」といい、同じことが「彫像芸術作品についてもあてはまる-----。彫像の場合も作品は作品<それ自体>で存在していて、作用だけがそのつど異なるというのではない。芸術作品そのものが、そのつど、異なった条件のもとで異なった現れ方をするものである。今日の観察者が違った見方をするだけではなく、別のものが見えもするのである」ことを認める。
だが、芸術作品としての肖像画は写真のように当の人物をそのままそっくり再現するのではなく、その人物の本質を描くのであり、「肖像画はその人物本来の本質を作り出している」。ガダマーは芸術作品が取り上げる個々の素材、人物や出来事はすべて個性的なものであるが、作品においては「偶然性や私的な側面を払拭されて、この個性にふさわしい現われ」を与えられることによって「理想化」されると言う。芸術作品は、世界を理想化してわれわれに示す。つまり、われわれが日常性のなかで見逃してしまっている、世界の本当の姿、個別の社会や特定の時代を超えた「真理」、あるいは「存在」そのものをわれわれに示す。「作品の創造者がその時々に自らの時代の公衆のことを考えるということがあるにしても、彼の作品の本来的存在は作品が語ることのできるものであるし、このものはどのような歴史的制限性をも根本的に越え出ている。この意味で芸術作品は無時間的に現在的である16)」。『小品集』
芸術作品は、特定の時代の公衆と結びついた、限定された作者の主観的な意図を超えて、世界史的普遍性をもつのである。後の時代の演奏者、演技者が、あるいは観客、鑑賞者が、全権を持って、勝手に自由に解釈できるということはなく、彼らは決して「主体」ではありえない。優れた芸術作品の制作、上演、鑑賞においては、作者、上演するもの、鑑賞する者の「主体性」が問題ではなく、そこで生起する普遍的な芸術経験が問題なのだ。「芸術は天才の技である」ということが天才美学の結論である。『真理と方法』。この結論によれば「芸術作品を経験するということは、解釈に伴ういっさいの主観的地平を基本的に越えており、その点は、芸術家本人の地平であれ受容するものの地平であり同じである----。」第二版前書き
このように要約しうる限り、天才の創造と見なせるような、並外れて優れた作品と、天才の作とは見なせないがしかし優れた作品とを区別する基準のようなものはあるのかどうか、天才的な作品が永続的な世界の真理そのものを表現しているというその真理の内容は明確に捉えることのできるものなのかどうか、などいくつかの論点に関して保留を行うにしても、芸術に関するガダマーの説明は多くの人にとっても、ほぼ納得しうるものであろう。
西村は、ボイテンディクの説に従いつつ、物と遊び手との関係、たとえば、ポケットの中の鍵束と私あるいは私の手が遊ぶというような関係は意図的なものでなく「パトス的」つまり受動的で気分に左右されて起こるものであるといい、「遊び手と遊ぶ相手とのあいだにおのずと生じる、主・客分かちがたい関係、存在様態」なのだと言う。西村は、この「主客の分かちがたい関係」を、ガダマーが「遊びのもっとも根源的な意味としての「中動相的な意味(der mediale Sinn)」と呼」んでいると言い、「これはまことに適切な表現」だとする。こうして、遊びにおいて関係する二つの項、遊ぶ者と遊び相手のどちらか一方が「主体」で、他方が「客体」と言えないことを強調する。
西村の引用している、『真理と方法』の当該箇所において、ガダマーは、確かに「遊ぶという意識的な態度をしている主体があって、その結果遊びがおこなわれるというようなものではない。むしろ遊ぶということのもっとも根源的な意味は中間的(メディアーレ)な意味である」と言っている。ただし、この「中間的」という語は『真理と方法』のなかではここで始めて使われ、なぜ「中間的」といわれるのか、読者、少なくとも私にはその意味がわからない。ガダマーはspielenという語の用例を示すが、その用例によっても、邦訳を読む限りでは、意味は全く明らかにならない。(翻訳者も、文法語としてのmedialの意味を掴んでいないようである。)
さて、ガダマーは、この第1節、芸術作品の「存在論的解明の<手がかりとしての遊び>」の後半で、音楽や演劇の上演〔Spiel〕を「媒介」と言い換える。絵画や文学は作品が直接に観衆、読者に訴え、働きかけるが、音楽や演劇の場合には、作品の演奏者・演出(演技)者によって媒介されて始めて観客が作品を鑑賞できるのだからである。
私は、この「媒介」という語を見て、前の箇所で遊びが中間的medialと言われていたことの意味がようやく分かった。ドイツ語でmedialという形容詞は、中間物、媒体・媒介を意味するMedium (その複数がMedia)と同根であり、意味的に「中間的」と「媒介」とは結びつく。(ただし、「媒介」と訳されている語がMediumであるのか、これと同義のMittelなのか、あるいは(ヘーゲルに繰り返し登場する)Vermittelungなのかは、原著に当たっていないので分からない。)medialは言語学的には、能動態と受動態の中間に位置する「中間態」を意味する〔小学館『独和大辞典』1990〕。また、ドイツ語のMitteと同根の英語middleは文法的には「中間態」の意味を持つ。日本語の文法では「中相」としている。(<岩波講座>『日本語』6.第5章「用言」)。
そこで、medialの語が最初に登場した箇所でのSpielの用例に戻ってみると、(邦訳で)単に「なになにが---活動しているspielen」という例では、spielenという動詞が、楽器を演奏したり、役を演じたりするという場合の他動詞としては使われておらず、波が動くとか光が揺れるとかという自動詞として使われている。「何かが起こるsich abspielen」の例は、abspielenが他動詞としては「(---を)演奏する」の意味で使われるが、sichを伴った再帰動詞としては「演じられる」、「(何かが)起こる」といった、自動詞的な意味を有する。「運動中であるim Spiel sein」の例は、遊びの語が遊ぶという能動的行動を取ることよりも、遊んでいる状態を示すのに用いられている。要するに、Spielあるいはspielenが能動態と受動態の中間的な意味で使われるということ、つまり、「遊び」には主語と客語(目的語)の区別ははっきりせず、「遊ぶという意識的な態度をしている主体があって、その結果遊びが行われるというようなものではない」ということを言おうとする用例だと考えられるのである。だが、言語学的な「中間態」の知識がなければ、ドイツ語のネイティブ・スピーカーにも、読めば直ちに分かるという文章ではないと思われる。
そして、ドイツ語Spielの用例説明においては、遊びと言う語はもともと「中間的」に用いられる、つまり、主体(主語)、客体(目的語)の区別をはっきりさせずに、自動詞的に用いられると言われていた。こうして、Spiel「遊び」は再生芸術の媒介、上演の役割が有する意味と部分的に重なり合う。つまり一方の遊ぶものについても他方の演奏するものについても、かれらが能動的主体であるのか受動的客体であるのかを区別する観点は重要ではない、ということである。
つまり、私には遊びという語と遊びという現象一般の考察から芸術論が始められなければならない必然性は理解できなかった。つまり遊びの解明は、芸術の解明に役立ったようには、私には思われなかった。
さて、ガダマーにおける芸術作品の「存在論的解明」は以上のように、「手がかりとして」の「遊びSpiel」の分析から始められたのであったが、以下では、芸術論からは離れて、遊びそのものについてのガダマーの言うところを検討する。
大人の人間は仕事もしているが時に遊ぶ。遊ぶ場合には、遊ぼうと考えて、遊ぶことを意図して遊ぶ。人間が主体的に遊ぶのである。だがガダマーによれば、「言語的には遊びの本来の主体は、他のさまざまな実行行為のひとつとして遊びという行為をもしている者の主体性ではなく、遊びそのものなのである。われわれは遊びのような現象を、主体とそれがとる態度に関係付けるのに慣れ、その結果言語の本性によるこのような暗示に対して目を閉ざしているのである」。p149.「最近の人類学上の研究も遊びの問題を広く捉え、その結果、いわば主体性に基づく考察方法の限界に突き当たっている。ホイジンガ〔ホイジンハ〕は、----遊びの意識の独特のあいまいさを認識するにいたった。「未開人自身は現実と遊びを概念的に区別できない----。それゆえ祭祀行為における未開人の精神状態に近づくには---遊びを手がかりにするのが最良の方法ではないか---。ここで使われている遊びの概念のなかには、信じているのか偽っているのかの区別は存在しない。」〔とホイジンガは述べている。〕ここでは遊びが遊ぶ者の意識より重要なことが原則的に承認されて---〔いる〕」。149.
「すべての遊びは〔遊ぶ者が、反対に〕遊ばれるということである。遊びの魅力、遊びが引き起こす魅惑の本質は、遊びが遊ぶ者をその支配下においてしまうことである。----遊びの本来の主体----は、遊ぶ者ではなく、遊びそのものである。」152
このことは、緊張感をもって意識的に行われる競技という遊びにおいても妥当するという。彼によれば、「競技者自身の中には自分が遊んでいるという意識はない。しかしながら、競技によって緊張にあふれた競り合いの運動が生じ、それがやがて勝利者を生み出し、その結果全体が一つの遊びとなるのである」。151.そして「遊びは、遊んでいるものの意識や態度のなかに存在するのでなく、逆に遊んでいるものを自分の領域に引き込み、その精神で満たすのである。遊んでいる者は遊びが彼を超越した現実であることを経験するのであり、このことがいっそう妥当するのは遊び自体がそのような現実として<意図>される場合である。それは特に、遊びが観客のための表現として行われる場合である」。
彼は、競技についてほとんど分析しておらず、彼が述べていることは不正確である。彼は、個々の競技者は「緊張感」をもって、つまり意識を持って、競技を行っている。しかし、個々のプレーヤーの意識を越えたところに、「あてどないせり合い」の結果として、「全体のプロセス」である遊びが現れると言う。これは正しいだろうか。
さらに、試合の勝敗は、確かに、個々人の緊張や努力や力の発揮だけではきまらない。それは個々の競技者の主体的行為を超えたものである。しかし、また、蚊や波の無意味な遊動が生み出すような「全体」とは明らかに異なり、スポーツの試合の勝敗、あるいはせり合いそのものは、監督の十分に計算された意識的な指揮や、日ごろの訓練により培われた各人の技量と意識的チームワークによって左右される。「自然の遊び」には「遊動」はあっても「せり合い」はなく、そして「あてどがない」というのはその通りである。しかし競技においては、「せり合い」から生まれる「全体的プロセス」は、明確にその都度の「終わり」、「あてど」(ゴール)が存在する。競技の遊びは、自然に存在しないルールによってその輪郭が定まっているからである。個々の競技者もそのルールに基づいて遊ぶ、つまり競技するのだし、試合・ゲームという全体も、ルールによって競り合いの「あてど」が定まっている。
「人間の遊びの特徴は何かを遊ぶという点にある。遊ぶものははまず、自分の遊ぶという態度を遊ぼうとすることによってはっきり他の態度と区別する。しかもそのような遊ぶ用意のうちで彼は選択を行うのである」。先に見たホイジンガの未開人が祭祀行為を行う場合のように「現実と遊び」を区別しないというようなケースを除外して考えれば、(そしてカイヨワが言うように、祭祀行為は遊びではない。)人間が遊ぶ場合について言われることとして全く当然である。現代人においても、子供においてはよく見られることであり、また賭け事などに熱中して破産する人物もあるように、確かに遊びに夢中になって遊びであることを忘れてしまうということは、時にはあるだろう。
だが少なくとも、遊びをはじめるとき、ガダマーが言うように、人間はこれから遊ぶということ、職業やそのほかの労働とは異なる種類の活動を始めるということを、意識している。そしてほとんどの人は、ある限定された時間や空間において「夢中になって」遊ぶが、しかし、そうした時間や空間を、自己の全体的な生のなかに位置づけている。とすれば、遊ぶ者は、一時的には「遊ばれ」、遊びに「支配され」、「魅了され、釘付けに」されるが、そのことを知っており、限定された仕方で「遊ばれる」ことを企てつつ遊ぶのである。遊ぶ者は、限定された時間・空間において遊びに支配されようとし、意図して、その間だけ自らを遊びの支配下に置くのである。
私の退職後の生活は、仕事の生活でなく、「毎日が日曜日」であるような遊びの生活であるとしても、遊びに支配された生活ではない。私が家族や知人友人に迷惑を及ぼすような仕方で遊ぶなら、たとえば賭け事に夢中になってしまうなら、私は、遊びに支配されるのである。私は自己の生活に破綻をきたさないように考量して、遊びを楽しんでいる限り、遊ばれているのでも遊びに支配されているのでもない。
人間が何かに夢中になるということはまったくありふれたことだ。夢中になることは遊びだけの特徴ではない。そして、さまざまな遊び方がある。遊びで賭け事をやる人と本気で賭け事をやる人とは違う。本気でやる人は賭け事で財産を作ろうとして大金を賭けて、時に失敗をして、すべてを失う。しかし、遊びでやる人は、小遣いが余ったときに、小額を賭ける。勝てば儲けである。しかし、負けてもどうということはない。こうして、本気の遊び、遊びに支配されてしまう遊び方と遊びで遊ぶ余裕のある遊び方が区別できる。夢中になってしまうことが遊びの本質に属することであるとは言えないだろう。
ガダマーはざわめき立つさざなみのような現象に「光の戯れ」つまり遊びを見出した。しかし、西村は、海の波は遊んでいない、遊んでいるのはそれらを眺め、その動きに遊びを見出し、楽しんでいる、この私だという。西村では、自然現象に代わって、それらによって誘われ、あるいは「巻き込まれ同化され」て遊ぶ気分にある、人間が登場する。しかし、私はその遊動を作り出した原因でも主体でもないし、私は意図してそれに関与しているのでもない。また、私はそれが遊動であることを、思考を働かせて見出したのではないし、またそのなかに意識的に遊動を見出そうと企てわけでもない。そうではなく、私はいつのまにかそのような気分になっていたのであり、遊びへの「関与」は、能動的、主体的になされることではなく、情緒的=受動的に行われることである。人間は「自然」とは異なるが、しかし、気分によって遊びに巻き込まれるとする点で、ガダマーと同じく、西村の場合にも、遊びにおける「主体性」は否定されている。
私が、というより私の掌がポケットの中の鍵束をもてあそぶ。これは私または私の掌とかぎ束との遊びである。だが、ここでも、私は「主体たる資格で、意図してポケットをまさぐり鍵束に手を伸ばして、これをつかみとったのではない。気がついたとき、私の掌とかぎ束とは、ふれあいの同調のただなかにともにあったのである」。
西村は、ガダマーがmedialという語を用い、文法の知識を前提にして、説明せずに先に進めた議論を、日本語の動詞「遊ぶ」の用法を詳しく述べることで、遊びの本質的特徴を明らかにしようとする。「かぎ束を玩〔もてあそ〕ぶ」というが、「鍵束を遊ぶとは決して言わない」。「遊ぶは自動詞」であって、主体(主語)が客体(対象)に働きかけることを示す「他動詞」ではない。遊ぶことは主体と客体という関係を含まない、と西村は主張する。「「鬼ごっこをする、鬼ごっこをして遊ぶとはいうが、鬼ごっこを遊ぶとは言わない」。遊ぶとは行動ではなく、状態の説明なのだという。
「遊ぶとは、ある特定の行動ではなく、その行動をとりつつある私の独特の在り方、存在様態を指示する自動詞であり、とりわけて状態動詞なのである。それが決して他動詞として用いられないのも、当然である。「鍵束で遊ぶ」とは、私の掌が鍵束「と」の相互的な同調という関係に巻き込まれており、その遊隙の場「で」さまざまに生起する気分や状況「に・遊ぶ」ことを意味している」。「遊びとは、ある特定の活動であるよりも、一つの関係であり、この関係に立つものの、ある独特の在り方、存在様態であり、存在状況である。それはものと私のあいだで、いずれが主体とも客体とも分かちがたく、つかずはなれずゆきつもどりつする遊動のパトス的関係である」。
遊びにおいては、「何ものかが遊ばれるが、しかもこれはこれで遊び手と遊ぶのである」。「放り投げた鍵束が再び掌に戻らずどこかに消えてしまえば、もはや遊びは存在しない」。あえて、後で出てくる独楽を用いた遊びについて行っている西村的な説明ないし描写を付け加えると、鍵束がもとに戻ってくるのは、鍵を放り上げるときの手を振り上げる動作が、私の主体的企てによって鍵束がうまく掌の上に落ちてくるようにコントロールされている結果なのではない。鍵束が「僕がもどれるようにうまく掌を動かして!」と誘ったからであり、私がその誘いに乗って鍵束と遊ぶことに同調した結果なのである。
「このわたし〔私〕ともの〔物〕、遊び手と遊び相手との間におのずから生じる、主客分かちがたい関係、存在様態を、ガダマーは遊びのもっとも根源的な意味としての「中動相的な意味」と呼ぶ。これはまことに適切な表現と言わなければならない。活動の主体、つまりそもそもだれが、あるいはなにものが、この遊戯運動の原因となり、これを遂行するのかということは、ここではどうでもよい」32。
ガダマーは遊び一般と人間の遊びを区別していた。光や波の戯れも、それ自体、無目的な全体のプロセスとして、遊びであるとし、それを遊びと受け止める人間の存在については言及していなかった。他方、人間の遊びの場合には、遊ぶものは、遊ぶことを選び、遊びを選択すると言っていた。またかれは、遊びにおいて人間は自分の課題を果たそうとするという。それは遊びの行為の外にある目的との関係における課題なのではなく、遊びを組み立てるための、内的な課題である。しかし、遊びを遂行するという企てを持っているのである。他方、西村では、遊びは主体の企てなしに、偶然に始まる。企てる主体の非存在が遊びの本質的特徴とされる。
鍵束との遊びにおいて、「遊ぶ」は活動あるいは行動ではなく関係あるいは状態を示す動詞であり、遊びとは意図的主体的に企てられるものではなく、偶然により生起する、主客未分の二つの項の同調、往還であり、情緒的関係である、と述べられていた。さらに西村は、動物や、幼児と母親の遊びを通じて、遊びの特徴をより詳しく述べる。
「子猫はころがる毛玉につかみかかり、子犬は互いにじゃれあう。こうして動物もまた遊ぶ。幼児は、母親のわらいかける目、あやす声、愛撫する手に応えて自分も笑い、声をたて、身をよじる。----母親が目の前でならしてみせてくれたがらがらに手をのばしては、これをふりまわして遊び、あるいはベッドの外へほうりなげてよろこぶ。ゆりかごの急な動きに声を立てて笑い、ゆったりとした往還の遊動には、しずかに身をゆだねてこれを楽しむ」。ここに遊びがある。
西村は、がらがらは母親の身代わりであり、がらがらで遊ぶ幼児の行動のうちに「母親ないしその身代わりとしてのがらがらと子どもとの間にみられる独特の関係、あの「と・遊ぶ」がうちにはらんでいた独特の構図を見極める」ことができるという。
西村は「がらがら」で遊ぶ母子の行動において「デリケートな仕方で調子があわされている」という。「遊戯関係を構成する最小単位、遊び手と遊び相手という両項は、それぞれ、他の一方がどんなできごとに反応するか、何を期待し、どのように答えるかを知っている。そして、そのつど両者が同一の期待を共有し、またそれに対して平行して同一の反応を取るべく、お互いに同調しあうという意図の伝達、確認」が「お互いの笑いかけや特定の音声、身振りによってなされる」という。
母親は、がらがらが鳴り出すのに注目している子どもにむかって、わらいかけながら、「もうちょっと・もうちょっと」とはぐらかす。子どもは「早く・早く」と手を振って催促しながらも、みずからもわらいをかえすことで、母親のはぐらかしをうけいれて「いまかいまか」とまちかまえる。ここには---ひきよせてははぐらかし、追いかけては身をひく両者の呼吸の、デリケートな同調と往還の遊動がある。こうして、ついにがらがらがなったとき、母と子は「ほらね!」とばかりに声をあわせてわらうが、それは両者が、結局は、ただひとつの動き、ただひとつの期待を共有していたことを示している。両者のあいだに共有された期待---、いまだ充実されないひとつの不在がある---。--それは---いわば「宙吊り」にされた期待とそれから生じる、両者のあいだに架けられた天びんの動揺、---気をもたせてははぐらかす、つかず離れずの遊動をこそ生み出すために、仕組まれた不在である。---こうして、宙吊りの相互期待と同調という共有の関係の枠組みこそ、われわれがさがしている遊びの構造の、もっとも単純な枠組みに違いない」
「いない・いない・ばあ」は次のように行われる。最初に母子の見つめあいが起こるが、これが両者の「連携への加入」を導く。母親が顔を覆う=これは連携の「消失」である。再び顔を見せる=「再現」、これは「連携の修復」である。この連携の消失と修復が繰り返されることの「同調された遊動」が遊びの原型であり、「いない・いない・ばあ」は遊ぶものと遊ばれるものとのあいだの役割交代をもっとも単純で透明な形で見せてくれる。
西村によれば「いない・いない・ばあ」は、母と子、あるいは人と物との、主客未分化な、ふれあいの関係、他者や世界との原初の関係に根ざしたものであり、人間存在の根本様態のひとつである。
こうして第二章において、遊びとは意図的主体的に企てられる活動ないし行動ではなく、宙づりにされた期待の遊隙、同調された遊動、遊ぶものと遊ばれるものとのあいだの役割交代などからなる、主客未分の二つの項の関係であり、人間存在の根本的で、独特の存在様態である、と西村は主張する。
「浮遊と同調」と題された第3章では、ブランコとシーソーが登場する。前の章で、がらがらの遊びに関して、西村は「宙吊りの期待」、「仕組まれた不在」に言及していたが、これらは「天びんの動揺」にたとえられていた。彼によればシーソーは「同調された遊びの天びんを、そのまま見せてくれる」ものである。シーソーやブランコは西村の言う、遊びの根本的特徴である「同調された遊動」に身を任せる遊びであり、カイヨワの4つの根本カテゴリーのうちのイリンクスに属する。
西村はこの章の25ページの大部分を、カイヨワのイリンクスに関する議論に対する批判、反論にあてている。彼は、ジェットコースターなど遊園地の機械によって惹き起こされるイリンクスを描写するのにカイヨワが用いる言葉、「パニック」「虐待」、「拷問」、「恐怖の叫び」、「戦慄」などを「およそ遊びには、たんなるメタファーとしてさえ、あまりにも場違いだ」58.と言い、私とは違い、それらの表現がユーモアの精神に基づいてなされたものだとは受け取らない。「どうして人々が、---恐怖に青ざめ、吐き気にやっとたえながらも、まだ回復しないうちに、〔カイヨワが書いているとおり〕ふたたび、先を競って同じ拷問をうけようとするのか、この拷問からどうして快感がえられるのかが、全く理解できないことになる。---いったいどうして〔カイヨワが書いているように〕「他の人たちが先を争ってそういう扱いを受けようとする有様」を見るだけで、自分も同じようにこの拷問を受ける気になるのだろうか」。西村にとっては「痙攣や戦慄やパニックをひきおこす拷問にもかかわらず、ひとはなぜ、先を競ってこれを繰り返しうけようとするのか」は、「たんに感覚の問題にとどまらず、意識や、さらに人間存在のふかみに根を下ろした、難解ではあるが根本的な問題である」という。
この難問に取り組む方法は、ハイデガーにしたがい「感覚や情動をとりあつかうさいには、たんなる生理・心理状態の記述の次元と、情態性の了解の実存論的次元とを区別する」ことである。そして、「情態性(Befindlichkeit)」とはひとがある状況において、どのような情態、つまりどのような感覚、感情、気分のうちにあるか、ということについての、「根源的な自己存在了解」を示す語だという。だがその結論はいたって単純である。「遊び手とは端的に、遊びの状況、遊びの関係「に・遊ぶ」ものであり、遊びの気分の情態性に立つものである。---ここにはもっぱら、ひとびとの笑い声や快活なざわめき、楽隊の陽気な音楽などによってだれの眼にも明らかな、遊びの雰囲気が支配しており、大人も子どももそのなかでうきたつのを感じながら、自分が---遊びの情態性にあることを、十分了解している。そこに設置され、仕掛けられてあるものはすべて、拷問のためのものではなく、遊びのためのものであることが知られている」。
要するに遊園地の機械に乗る遊び手たちは遊ぶ気分にあり、遊んでいるのであり、「拷問の道具」ではないことを知っている。「ひとがこれらの刺激や感覚「に・遊ぶ」かぎり、たとえ、かれらが「こわい」とか「きゃー」とかさけぼうとも、かれらがそこに感じているのは、恐怖ではなく、正しくは「スリル」とか、あるいは---「サスペンス」などというべきだろう。ひとは、恐怖からけっして快感をえることはできない。しかしスリルやサスペンスとは元来ある種の快感の名前なのである。そしてこれらスリルや、---サスペンスの快感を提供する機械には、そもそものはじめから、その動きや刺激を、もっぱら遊動としてまた遊びの快としてうけとめられるように、---かならず遊びの隙、遊隙が仕組んである」。
彼が述べていることは、遊園地は遊ぶところで、客はみな遊び気分でやってくるということ、機械もすぐに乗り物に酔ってしまう人でなければ、楽しめるように作ってあるのであり、決して恐怖を与えるものでも人々を苦しめるものでもない、乗客は遊びかつ楽しんでいるだけだ、ということである。しかし、こうしたことは、あらためてハイデガーを引き合いに出して説明されなくても、誰もが知っていることである。どこに「人間存在の深みに根を下ろした根本問題」が述べられているのかと私は訝しく思う。
彼が述べていることの多くは、カイヨワの言葉使いが不適切だという主張と変わらない。彼は、「心地よいパニック」などの「逆説」的表現を楽しく受け取るユーモア精神を持ち合わせていないようだ。すぐ後で、彼がシーソーの遊びを分析する際に「人格の平等」等の語を用いていることに、私は、ひどく「場違いな」印象をうけたが、これはかれの諧謔精神に基づくことだと理解することにしたのだが。
この章で、彼自身が言いたいことは次の文に書かれている。「遊びの天びんをそのままみせてくれるのは、シーソーである。---ここで遊ばれる遊びとは、あるところまで上昇して反転して降下する遊動そのものであること、水平にわたされた天秤棒とそれを中点で支える支点とは、そのような往還の遊動を固定してしまうことなく、つねに宙吊りにして活性化するための遊びの骨格であり、しかけであること、天秤棒の両端に座る遊び手は、シーソーを動かす主体というよりも、その遊動を自分の身に受け止めては、これに乗り、同調することで、これに身をゆだねるもの、つまりそのような「遊びを遊ぶ」ものであることをはっきり見せてくれる。---遊び手は天びんのおもりととして、遊びの骨格を構成する一契機、遊び関係の一項にすぎず、その存在規定は、自由意志と企てと責めの基体としてのかけがえのない一個の人格ではなく、ただ相手とつりあうおもりとしての役割である。それゆえおもりとしての適正な役割を果たす限りで、かれは誰とでも交代可能である。そればかりか、おもりが適正でないときには、それをつりあわせるための仕掛けすら、天びんはもちあわせている。大きな子は天びんのより中点に近いところにすわることで、小さな子とでも一緒にシーソーを遊ぶ資格を得るのである。それは遊び手の人格の平等のためでなく、すべては遊びのためである」。私の反論は後でまとめて行う。
第4章では、かくれんぼや鬼ごっこの民俗誌的考察、精神分析的なこれらの遊びの解釈に対する批判的言及なども行われているけれども、省略し、これら遊びの根本的構造、遊びとしての本質的特徴についての彼の記述にもっぱら注目する。彼は、これらの遊びががらがらや「いない・いない・ばあ」とおなじ根本構造をもった活動であり、それらがもっている構造をより「純化」した形で示していること明らかにしようとする。とくに遊びが主体の企てによって行われるものでないことを、かくれんぼが偶然により始められるものだということを示すことで、より明確にしようとしている。
「鬼ごっこという遊び行動の本質」は「挑発してはぐらかし、追われては反転して追うという、宙吊りのスリルにこそ」ある。「鬼が子をつかまえ、ふれることによって、鬼と子の役割が交換されると言うとりきめも、---天びんが一方にかたむいては再び反転して他方に傾くという、---宙吊りの支点の設定である」。
かくれんぼは、「いない・いない・ばあ」や鬼ごっこにおける遊びの基本骨格を、「ふたつの顔、二つのまなざしのあいだ〔の〕----関係として純化した」ものであり、そもそも「いない・いない・ばあ」は「一種のかくれんぼと考えられないこともない」。
ところで、じゃれあう子犬の遊びや、がらがらや「いない・いない・ばあ」で母親と遊ぶ幼児の「自然な」遊びとは違い、かくれんぼや鬼ごっこは、一定の年齢に達した(人間の)子どもたちによって遊ばれる。子どもたちは、「遊ぼう」と考えて(西村の言葉を用いれば「意志」し、「企て」て)、「主体的に」他の子どもたちに誘いかけるのではなかろうか。そうではない、と西村は言う。むしろ、この章では、「遊びは自由な主体の企てや算定によるのではなく」、「意志や企てによってねらわれた目的ではない」ことが強調される。「鬼になるもの、子になるものも、自由な意識主体の、個としての能力や意図を勘案してわりふられるのではなく、じゃんけんや番きめ歌がもたらす偶然にゆだねられている。」「遊びは、むしろ、ことばの厳密な意味で、偶然にはじまるというべきである」。それは「ひとつの僥倖というほかはない」。
第5章では、独楽回しの遊びが、同じように、彼の言う遊びの根本構造をもつということを示そうとしている。独楽回しの遊びには、独楽を回す技量が必要であり、そのためには練習が必要である。これらのことは、独楽回しの遊びが、偶然によって始まる、独楽との単なる「同調」ではなく「企て」であること、つまり「主体」の企てにより可能となる遊びであることを示しているのではなかろうか。だが、西村は、単に練習過程だけでなく、独楽を空中に投げ上げて掌の上で回したり、綱渡りをさせたりする高度な技を含む遊びを含め、「同調」を意味する「この「と・遊ぶ」遊びの構造は、基本的にはかわらない」ことを論証しようとする。この論証が適切なものかどうか、詭弁ないしはごまかしの議論ではないかどうか、あとで十分に検討したい。
第6章では、ホイジンハやカイヨワでみられた、遊びとはフィクションだという見方に関連付けて、西村の専門である美学でしばしば論題になる「仮象論」についての議論を行っている。第7章では振りをして遊ぶ「ごっこ遊び」と俳優の演技はどう違うかの議論が行われ、遊びと芸術の違いが論じられる。第8章では、ルールが取り上げられ、遊びのルールと言語のルール、法的ルールの違いなどが論じられ、フェアプレーや賭け、スポーツなど遊びと関連する論題についての幅広い議論が行われている。それぞれのテーマに関する議論の多くは興味深く、またそこには納得のいく点も多くある。しかし、その議論の中でかれが語る遊びは、彼が本書の最初の数章で示した遊びの根本構造からはみ出している。というのは本書の後半に登場する遊びは、大人の遊びであり、子犬のじゃれあいや赤ん坊の「いない・いない・ばあ」と違い、遊びの始まりと遊びの継続、したがって遊びの「存在」は、偶然によって担われているのではなく、遊びを始めよう、継続させようとする、遊ぶ人(一人もしくは二人)の意志抜きには語りえないからである。
しかし、子犬のじゃれあいを別として、鬼ごっこはもちろん、「いない・いない・ばあ」のような赤ん坊(実は赤ん坊と母親)の遊びにおいても、遊びは偶然にではなく、遊ぶ人の意志、企てによって担われるということを私は示そうと思う。以下は西村の遊び論に対する反論である。
始まり方に注目してみよう。遊びは遊び手の意志とは関係なく、西村が言うように、偶然に始まるのだろうか。「いない・いない・ばあ」は、母親と幼児の最初の見つめあいから始まる。「そのとき母親はしばしば声を出して、子供の注意を自分の顔に向けようとする」と西村は言う(41.)が、しかし、それを母親の意図的な誘いとはみなさない。「連携への加入という一種の儀礼的行動だ」とし、鬼ごっこがはじまるときのじゃんけんぽんと同じものとみなす。鬼ごっこでは、集まってきた子供たちはすでに、遊ぶ気分になっており、鬼ごっこではいつもじゃんけんで鬼がきまるものだということを知っているから、「自由な意識主体の個としての能力や意図を勘案して」鬼と子の割り振りを決める必要はない。遊ぶ気分にない子供はそれに加わらないだけである。遊びたい子供がじゃんけんに加わる。じゃんけんぽんは「同調の端緒」である、そう言える。
だが、遊びを行う二人のうちの一方が、まだ、遊ぶ気分になっていないときには、連携への加入の誘いは「加入儀礼」とは言えないだろう。「いない・いない・ばあ」がこれから始まる直前の時点で、すでに遊ぶ気分になっているのは母親だけで、子供はまだその気分になっていない。だから、母親は、赤ん坊の顔を覗き込んだり、「しばしば声を出して子どもの注意を自分の顔に注意をむけようとする」のであり、子供が遊ぶ気分になるようにしようと努める/試みるのであろう。
つまり、あえて西村の大げさな言葉を使えば、母親が、主体的に、意識的に企てて、子供の注意を惹くことによって、初めて見つめあいが起こる。見つめ合いは偶然に起こるのでなく、子どもの注意を引こうとする母親の行為が「原因」になって起こるのだということははっきりしている。「同調の端緒」は母親の企てによって作り出されるのだ。それはすでに「加入する」気になっているものが、それを確認するだけの単なる「加入儀礼」ではない。いつもそうだというわけでなく、母親がたまたま赤ん坊のベッドの脇に来たときに、偶然に見詰め合うということが起こらないとは言えない。だが、西村が言うように母親が「声を出して、子供の注意を自分の顔に向けようとする」という場合には、それは西村の言葉を使えば母親の「主体的な企て」であろう。
また西村は、「いない・いない・ばあ」で「おたがいに見つめあったりわらいあったりする遊びの関係が、元来は、ものの消失や再現、またわらいかけてくる他者のまなざしに対して、これに応え適応しようとする子供の自然なふるまい、いわば生来の傾向を母親が利用し、これを遊びというあらたな独特の振る舞いへと構造化したものだ」と言っている。つまり「連携への加入」(むしろその「誘い」)に引き続く、「消失」、「再現」という一連の遊びの動作は、子供の「生来の傾向」についての母親の心得、計算、予測に基づいておこなわれるものである。「いない・いない・ばあ」の同調の関係は、おのずとあるいは偶然に存在しうるものでも始まるものでもなく、母親のイニシャティブ、主体的な「計量」や「勘案」、「企て」によって存在しうるものであり、これらによって、開始され、支えられている。
彼は鬼と子への役の割り振りは「個としての能力や意図を勘案して割り振られるのでなく、じゃんけんや番きめ歌がもたらす偶然に委ねられている。---結局のところ,遊びは自由な主体の企てや算定によるのでなく、ことばの厳密な意味で,偶然に始まるというべきである。それゆえ、遊びの存在,すなわち私に遊びがおとずれるかどうかはわたしの意思や企てによって狙われた目的ではない。それはボイテンディクがいうように、ひとつの僥倖というほかない」。
鬼と子の割り振り、役割分担は、確かに、偶然に依拠して、きめられた。なるほど、役割分担が決まらなければそのあとの追いかけたり逃げたりの遊び行動は始まらないが、その役割分担の方法が偶然に依拠して行われるということは、遊びが偶然に始まるということを意味していない。じゃんけんで役割が決まる前に、かくれんぼをするのだということ、そしてじゃんけんで役割を決めるということに、その場の子供たちが同意していることによって、かくれんぼは始まったはずである。この同意がこのかくれんぼの「基体」ないし原因であり、この「同意」は偶然により、つまり無原因的に、生じたものではない。
じゃんけんで役割をきめるということは、突然、その場で、偶然に発見されたものではない。鬼と子のわりふりをじゃんけんで決めるということは、かくれんぼが通常そのようにしておこなわれるものだという、子供たちの間で共有されている伝承された遊び方(ルール)の知識に基づいて行われたのであろう。そして、そもそも、集まった子供たちが鬼ごっこで遊ぶことに同意することができたのは、かれらが、偶然に、鬼ごっこという遊び(遊び方)を思いついたからではなく、その遊びを皆が予め知っていたからであろう。遊びは偶然の賜物ではなく、その社会の歴史的文化的伝承の賜物である。
しかし社会の歴史が主体で、子供たちの行動が社会の歴史によって決定されているなどと言いたいわけではない。子供たちは様々な遊びの中から主体的に選択する。いやそのまえに、少なくとも集まった子どもたちの何人かは、主体的に、まず遊ぶことを選択している。詳しく言おう。
じゃんけんが遊びの始まりとしよう。じゃんけんが行われるためには何人かの子供が集まらなければならない。そして、どこかの場所に、ある時刻に、偶然、複数の子供たちが集まるということは考えにくいことである。むしろ、たとえば、宿題を先に済ませた子供が、家で一人でテレビゲームをするのでなく、外で友達を誘って遊ぼうと考えたというように、「主体的に企てた」ことが端緒になり、彼がほかの友達を誘うことによって、子供たちが集まることになるのではないだろうか。子どもの場合に、大人のような計画や決断などのようなものはずっと少なく、ほとんどたいてい気分で決まると私は思う。
しかし、複数の子供たちが集まって何かの遊びをしようとするとき、彼ら一人一人がかくれんぼをする気になっていて、その気分が偶然に一致してかくれんぼが始まるとは言えないだろう。だれかがかくれんぼがいいと言うかもしれないが、鬼ごっこのほうがいい、三角ベース、あるいはサッカーをやろうと言う子がいるかもしれない。同意が生じないかもしれない。しかし、だからといって、すぐに皆が散るわけでもなく、取引をしたり、説得が行われたり、妥協をしたりして、合意が成立するかもしれない。そして、かくれんぼに決まった場合に、じゃんけんで割り振りが行われるのである。三角ベースとなれば二つのチームに分けなければならない。グーパーのじゃんけんで決めるかも知れず、あるいは上手なものと下手のものが適当に混ざるように勘案して、決めるかもしれない。こうして、遊びがかくれんぼに決まるにしても、そしてかくれんぼでは、通常、鬼と子のわりふりはじゃんけんの「偶然」によってなされるにしても、遊びは偶然に始まるわけでは決してないし、幸運の贈り物などでもない。子供たちは与えられた歴史的文化的状況の中で、一緒に企て、相互に調整することによって、遊びを,遊びの関係を開始する。私はこのように考える。
今述べたことは、自分の子どもの頃を振り返ってちょっと考えてみればすぐにわかることである。だが、保育に専門的に携わっている人の文を参照してみた。北條敏彰は「「遊び」とは----「遊びも子どもの仕事やでえ!」」、『発達』109号、<特集子:どもの遊びと発達>(ミネルヴァ書房、2007、winter)で次のように書いている。
「「おにごっこ」では遊び相手との関係がものをいってきます。逃げ回るより、鬼として追いかけるほうが楽しいからと言って、何時でも自由に鬼になることはできません。特に「おにごっこ」などの、子ども同士の遊びでは、子どもたちはとかく自分の思い通りにことを運びたがる特徴があります。だから子ども同士の「遊び」ではそうした「我がまま」同士が当然のことながらぶつかり合います。だからその分、自己制御をよりシビアな形で鍛えてくれます」。もちろん子どもたちは「ぶつかって」、相手の譲歩を求め、話し合い、相談し、そのなかで「自己制御」も行うのだろう。
また子どもたちは遊びかたの決まっている、<偶然に>「存在する」遊びをいつも自動的に行うわけではない。「「集団遊び」に例を取ると----「王様陣取り」でたった一人残った相手の王様が陣地から一歩も出ないことが続くと「十数えれば陣地から出なければならない」というルールを子どもたちはあみだしました。---こうした「工夫」は---なかでも他者と競い合う「遊び」には普遍的に見られるものです。」 「また、「遊び」には人数がある程度必要になりますが、この遊び相手を探すことは、他の人間(他者)に対するもっとも初歩的な能動的行動です。さらに、人数が足りない時は、他の遊びをしている子を誘わなくてはならないときもあります。当然、相手の「楽しみ」をこちらの「楽しみ」に振り向けるというより高度な働きかけすら必要となってきます。----このような「遊び」がもたらす能動性は、良い意味でも悪い意味でも、条件や他者に働きかけ、自分の都合のよいように、独力で切り拓いていく力----を育んでくれます。」
遊びは、西村の言うように、偶然の僥倖によって与えられる、「存在する」同調関係なのでなく、遊ぶものが、他者に働きかけ、能動的に作り出していくものだということがわかる。
なるほど子どもは上がり下がりを楽しむのだが、波間に浮かぶボートに揺られるように、ただ身をゆだねているのでは遊びを楽しむことはできない。二人の子どもは、意識的、意図的に、シーソーの長さで決まる周期に合わせて、交互に地面をけることなしには、この遊動の「存在」を維持し続けることはできないし、それに身をゆだねることはできない。西村は遊び手は「天びんの両端におかれたおもりとして、遊びの骨格を構成する一契機,遊び関係の一項にすぎ」ないという。
しかし二つのおもりがシーソーの両端に置かれただけでは一定のリズムの遊動は起こらない。シーソーに似た玩具がある。小さな天びんと二つのおもりで作られたヤジロベーは左右の腕が上下する(傾く)「遊動」を見て楽しむ玩具であるが、その遊動も人が指で天びんの一方を押すなどして、最初の動きを与えてやらなければ起こらない。シーソー遊びの「ルール」は「身をゆだねること」であるよりも、むしろ、「そのつど強く地面をけること」なのではないか。この遊びは決して、偶然によっては始まらず、単に受け止めて同調するだけの遊びではなく、遊び手の意志的なかかわりを必要とする。
ブランコ:『保育ジョブ』https://hoiku-job.net/「保育士さんの知恵広場」からお借りした。

ブランコも「同じように、遊動そのものに乗ってあそぶもの」だと西村は言う。どうであろうか。西村によれば、シーソーやブランコは、「揺りかごの遊びの延長線上にあることは間違いない」という。シーソーやブランコは「幼児をやさしくつつむゆりかごであり、あるいは、かれをだきかかえる母親のやわらかな腕である」。52.「かれは、いま自分の身体がうけとめているゆれが、けっして自分をおびやかす不安な動揺ではなく、また、はねあがりざま,自分の身体を,無防備なままに中空へほうりだしてしまうようなパニックでもなく、上昇しては,反転して、またかならず降下してくる遊動の往還であることを十分にわきまえている。---こうしてかれは---あがりさがりするゆりかごの動きを追いかけ、これに同調し乗ることで、この遊動「に・遊ぶ」のである」。
ブランコに乗って遊ぶことは上昇し下降する往還の遊動を楽しむことだというのはその通りである。だが、西村は,再び、「がらがら」遊び、「いない・いない・ばあ」の遊びをしていたのと同じ頃の、母親の腕による「ゆりかご」の原点へと立ち返るようにと言う。「自他の未分化な幼児」の遊びという、祖型の延長上にあるものとして、ぶらんこは揺りかごと「同じ」なのである。
しかし、シーソーと同様、ブランコも座席に座っているだけでは、自然には、動き出さない。はじめてブランコに乗った(乗せられた)小さな子は親に押して動かしてもらって、小さな揺れに「こわごわ」遊ぶ。自分でブランコを動かすには、ちょっと地面を蹴って揺らしたあと、ブランコの紐の長さで決まる周期に合わせて両足を振り上げたり、後に振ったり、体を意図的に動かさなければならない。年長の子供たちは、ブランコの振れができるだけ大きく高くなるようにブランコを漕いで遊ぶ。彼らはブランコをあたかも操縦するかのように、能動的に遊ぶ。時には最も高い位置に来た時に、前方にジャンプしたりすることもある。
ブランコは、鉄棒や雲梯など他の遊具とともに公園や校庭に置かれており、ブランコで遊ぶ子供たちは、テレビのスイッチを切って、家を飛び出し,校庭や公園を目指す。彼らは自分のからだを使って遊ぼうとしたのだ。ブランコは上下の往還を楽しむ遊びだが、その遊動は偶然により開始されるもの、「存在する」ものではなく、遊び手が意図的に,作り出すものである。
彼は第5章で「われわれは、第4章で、遊びは、ことばの厳密な意味で偶然に始まり、それゆえ、遊びの存在はねらわれるべき目的ではなく、一つの僥倖である、といった。遊びが偶然に始まったからには、私はまた、自由にこれをうちきることはできない。遊びの存在根拠が、主体の自己存在可能への企てにない以上、原理的に見て遊びには、とりわけて実存のカテゴリーである可能性も未来性も、また自由も存在しなかった。私が遊び手として、遊びのただなかに存在するとき、ちょうど船が浮きつ沈みつ、波の戯れにただようように、わたしは、遊びの往還の同調にひきわたされ、になわれていた。こうして遊びの存在が、偶然と僥倖としての、この遊動そのものにになわれてある以上、遊びはもっぱら現実態としてのみ存在する。遊び手としてのわたしが、この遊びの現実態に引き渡されている限り、私もまた、自己存在の可能性や未来性に関わることなく、常に、自己の現実態にとどまる」と書いている。
哲学用語がちりばめられた難しそうな文章であるが、内容はいたって単純である。「主体の自己存在可能への企て」とは、遊び手が自分の可能な行動を考え、決めようとすることを指している。子供たちは、公園に行き、かくれんぼをしよう、ブランコで遊ぼうと企てていたのであり、子供たちの、「自己存在可能への企て」が、かくれんぼあるいはブランコの上下動の存在の原因なのである。だが、西村は、この事実を無視し、あるいは見落とし、遊びの「存在根拠」は子ともたちの主体的企てにあるのではなく、偶然によるものだと考える。遊びが「偶然と僥倖」の産物であるならば、遊びには人間の行動を意味する「実存」の「カテゴリーである可能性も未来性も、また自由も」存在しないというのは当然である。
西村は「遊びはもっぱら現実態としてのみ存在する」という。ところで、現代科学によれば、我々の宇宙は、ビッグバンによって無から生まれたものである。この宇宙は「偶然」によりうみだされたもので、140億年前の始まりの偶然という無と、遠い未来の時点における消滅の無との間に漂うはかないものである。この宇宙に関しては、始まる前の過去がどうであったか、消滅後の未来はどうであるかについては一切問えない。(実際の宇宙論では宇宙が「振動」するか「発散」するかなど、過去と未来も問題になっているようだ。)確かなことは、この宇宙は現在あるということだけである。
西村によれば、遊びはこの宇宙のように偶然によってうまれたのである。だから、それについて語り得ることは「今ある」ということ、そして今の状態だけである。西村は、遊びは偶然に起こったものであり、遊びを始めた子供たちの過去の「自己存在可能の企て」も、遊びを中止しようという未来の企てもありえないと考える。遊びはもっぱら「今ある」ものである。「遊びの存在が、偶然と僥倖としての、この遊動そのものにになわれてある以上、遊びはもっぱら現実態としてのみ存在する」というのはそういう意味である。
そして遊び手が、その遊びに浸っており、他のことを企てない限り、かれはこの遊んでいるという現在の状態にとどまり続けるということは自明の理である。かれが「遊び手としてのわたしが、この遊びの現実態に引き渡されている限り、私もまた、自己存在の可能性や未来性に関わることなく、常に、自己の現実態にとどまる」というのはその自明なことを哲学用語を用いて述べただけの文である。自明なことというよりも一種の同語反復を行っているというべきかもしれない。
この主張の根拠も遊びが偶然にはじまるものだというところにある。しかし、仮に遊びが偶然はじまるものだとしても、始まった遊びが終わるのは「倦怠によってだけ」ということにはならないだろう。つまり飽きない限りあそびはいつまでも続くということにはならない。遊びがいつまでも続くのは、遊ぶ人が、非現実の完全な自由を有している(子どもはそう信じている)場合だけである。現実の人間---カイヨワは大人の遊びについて遊びの自由を主張している----は常にさまざまなほかの仕事や用事を抱えつつ、遊びの種類によっては天候その他自然的条件のなかで遊ぶのであって、飽きない限り倦怠を感じない限りいつまでも遊んでいられるわけではない。
飽きたからと突然やめる人もあろうが、遊び手を取り巻く諸事情、たとえば、株で遊んでいる人なら自由になる資金がまだあるかどうか、パチンコをする人なら外の車の中で子どもが熱中症にならないかどうかを考えることが遊びを終わらせる。子供でも、小学生ともなれば、食事の時間の事や宿題を考えて、どこかで遊びをやめようと考えるだろう。つまり考量がなされ、選択が行われる結果、遊びが中止される。人間が完全に自由であるのではなく、人間の生が、遊びだけではなく様々な他の用や仕事を行いながら営まれるものであれば、人はそれらの事情をいろいろと勘案しながら遊ぶのである。遊びは「倦怠によってだけ終る」のではなく、様々な事情を考量し、計画、選択を行う、完全に自由であるのではないが、主体的に企てる意志によって、終わることがほとんどである。
ただし、実際の遊びは、遊び手の倦怠と同時に、自動的に終る、あるいは存在しなくなるのではない。参加者のだれかが「もう飽きた、終わりにしようよ」と提案することによって終わるであろう。倦怠が終わらせるのでなく、倦怠を理由とする「提案」、終わらせようとする一種の「企て」と、それについての参加者の同意によって、遊びは終わるのである。もし「厳密な意味で偶然が」遊びを終わらせることがあるとすれば、遊んでいる最中に隕石が地球に衝突して、遊び手たちとともに遊びを消滅させるというような場合であろう。
また、遊び手を取り巻く諸事情が遊びの継続に差し支えがない場合であっても、遊びの同調関係は、自動的に、飽きられるまで存続するものでもない。参加者の同調が続き、遊びが存在し、その遊びに全員が没頭している限りは、「企ての合意の確認や共同作業における役割分担の計量」などは行われないであろうが、それも当たり前だ。だが、遊び手の勘違いや見込み違い、期待しすぎなどによって、同調関係にほころびが生ずることはいくらでもありうる。遊びの最中に何か問題が生じれば、いったん遊びは中止ないし停止され、話し合いか言い争いが起こるだろう。倦怠が支配していないときには、遊びを継続させるための何らかの調整、話し合いが行われるはずである
その結果、最初の合意が再確認されたり、あるいは役割分担が変更されたりして、同じ遊びが再開されるかもしれないし、合意が成立せず、その遊びは中止されるかもしれないし、別な遊びが始まるかもしれない。とにかく遊びを続けたければ何らかの調整作業、「企て」が必要だ。しかし、西村の関心は、遊びの「本質」が何であるかを示すことだけにあり、遊びがどのように始まるのかを示そうとしないのと同様、遊びの関係が解体しつつあるときに、その解体現象の分析や、遊び手たちがたぶん企てるであろう修復の努力等についても分析しない。
西村の基本姿勢は、遊びが存在するとすれば、それはどんな構造であるかということを問おうとするものである。人は「偶然」にふれた鍵束で遊ぶこともあろう。波間に浮かぶボートの揺れに身を任せて、一人遊ぶこともあろう。だが、複数の人間による遊びには、その遊ぶ人たちの「企て」や諸事情、可能性や現実性が関わりを持ち、遊びについての同意がなければほとんどの場合遊びははじまらない。しかし、西村は、いったん遊びが始まって、私がこの今の遊びを楽しんおり、他の遊びをしようとは思わずに遊んでいるときの遊びの様態を分析しようとしている。こうして、西村は、(複数の人間による)遊びがすでに始まった時点から以後の遊びの構造、「骨格」を説明するが、どのように遊ぶ者たちがその開始にあるいは終わりに到達するのかについては分析しようとはしていない。だが、遊びが始まって終わりになるまでは、遊びが「同調」、「遊動」の関係、状態であるということはいわば当然である。両項が同調、遊動の関係になければ、遊びは存在しない。同調が壊れればそこで終わる。同調は遊びという存在様態が前提される限り自明である。
そして、西村は遊び行動が、他の人間の行動とは違う、独特なものであるということを、日本語の用法に基づいて説明していた。
遊びとは、「主体としてのわれわれが、ひとつの明確な意図の下に,客体としての事物に手を伸ばし、これを手に「も〔持〕つ―もち〔用〕いる」通常の関与とはことなったかかわりかた」である。人間が、客体である事物に主体としてかかわるときには他動詞を用いる。しかし「遊ぶ」は自動詞である。遊びにおいて人は、客体である事物に、主体として関わるのではない。「遊ぶとは、ある特定の行動ではなく、その行動をとりつつある私の独特のあり方、存在様態を指示する自動詞であり、とりわけて状態動詞なのである。それが決して他動詞として用いられないのも当然である」17)。私は何ものか「と・遊ぶ」。あるいは、ある気分や状況「に・遊ぶ」。「遊びとはある特定の活動であるよりも、ひとつの関係であり、この関係に立つもののある独特のあり方、存在様態、存在状況である。---この独特の存在関係を、とくに遊戯関係と呼ぶ」と言う。
遊びは他の人間行動一般とは異なると西村は主張する。そして、遊びの独特な性格は「遊ぶ」という日本語の用法に現れていると西村は言うのであるが、そのような用法はその動詞の示す行動(活動/状態)が独特であることを示すのであろうか。遊びとは別の活動/状態を表す動詞で似たような「用法」の動詞ははないのだろうか。
ガダマーでは、動詞spielenの「中動相」的な用法が強調されていたが、spielen自体は、英語のplayと同様に、能動態でも受動態でも用いられるのである。たとえば、Tennis spielenで「テニスをする」を意味する。(小学館『独和大辞典』)自動詞であるか、他動詞であるかは、動作の特徴と必然的な関係を持たない。
ある語が使われ始めた時代には、その語は、それが指し示し表現している動作/状態と一致していただろうと思われる。そこで、ずっと昔、遊ぶと言う語が使われるようになった時代の遊びは西村が言うように動作ではなく状態だったと考えることができる。つまり、その時代の遊びとは現代に一般的であるような、大人が意識的に遊ぼうと考えて遊び方を選んで遊ぶような「構造化された」遊びではなく、幼児がいつの間にか何かに(実は母親に)遊びの状態に移行させられて楽しい気分に置かれている「いない・いない・ばあ」と似たような遊びがほとんどであった、と想像することができる。言い換えると、日本語の自動詞である遊びという語が使われだした時代には、カイヨワの語で言えば、パイディアがほとんどで、明確なゲームのような遊びは存在しなかったか、あるいはアゴーンのような戦う遊びや競争は存在したかもしれないが(たとえばその真剣さのゆえに)「遊び」とは呼ばれなかったのであり、西村が取り上げている子どもの遊びないしは赤ん坊の「いない・いない・ばあ」のような遊び(だけ)が遊びだと考えられていた、と想像できる。西村は、遊びと言う日本語の「自動詞」的性格のゆえに、遊びとは、一般に、主客未分の「状態」であり、主体的「活動」ではないと主張しているのだが、彼の主張が成り立つのは、遊びと言う語が使われ始めた遠い昔の日本においてであって、その後社会の変化とともに発展しさまざまに分化してきた現代の遊びについては、せいぜい、気分や自然的感情に左右されやすい子どもたち、つまり「自然的存在」であるかぎりの人間の遊びについてだけである、ということができるだろう。 -----------------------------
「働く」(「労働する」、「仕事をする」)を考えてみる。これらも自動詞であり、「工場で働く」、「畑を耕して働く」とは言うが、「工場を働く」、「畑を働く」とは言わない。
もし私が手作業で安全ピンを作る労働者であるなら、私は針金を一定の長さに切り、端を尖らし、曲げて---ピンをつくる。私は素材である針金とある関係を持つ。その針金を使って針金細工を作って遊ぶのではなく、働くあるいは労働する。したがって「労働とは、特定の活動であるよりは存在状況である」と、西村が「遊び」について言っているのと同じことが言える。
畑で働く。「働く」は「草引きをする」、耕す、畝を作る、施肥をするなどの特定の動作ではない。そして、「働く」は、その行動をとりつつある「私の独特なあり方」、「状態」を示している。私は、たとえば、退職後の趣味で、あるいは単なる暇つぶしで、あるいは健康保持のために、草引きをし、畑を耕しているのではない。適当な勤め口がみつからないため、自給自足のため、あるいは家族を養うために、「働いて」いるのだ。「耕す」、等々という動作ではわからない、私の存在の様態、存在状況が「働く」という語によって示される。
働くことは、一般的には、主体的に行われる企てである。だが、人はしばしば気分で働くことがある。会社人間には、オフィスで仕事が片付けられるのを待っているように感じられ、『レジャーの誕生』で描かれている19世紀フランスの勤勉な農夫には、畑の土が耕してほしいと呼びかけているように感じられたかもしれない。そしていったんはじめた仕事に夢中になることはよくあることだ。私の経験では、畑仕事は、気をつけないとやりすぎてあとで体が痛むほどやってしまう。人によっては、研究という仕事では寝食を忘れることさえある。そのようなときには、私が仕事をしているのか、仕事が私を働かせているのか、どちらとも言いがたい。どちらが主体なのかわからないと言い得る。
また、働きたいと思わなかった人、働く気分になっていなかった人(遊び人)が、ある職場で人々が和気あいあいと仕事をしているのを見ているうちにそこで働く気になるということもあろう。「働く」は、常にとはいえないがあるケースでは「遊ぶ」と同様に主体的企てではなく、気分、「パトス的」関係である。(そして、大人の遊びの多くは気分だけでは始められない、つまり遊びが気分で始まるということは、一般的には言えない。)
こうして、自動詞で、活動というよりは状態、状況を示す語は、「遊ぶ」だけではない。「遊ぶ」は、その日本語としての独特の用法によって人間存在の独特のあり方を示しているとは主張できない。
西村によれば、遊びの基本的な構造は「同調」にあるという。だが、どんな活動でも、それが複数のメンバーによってなされ、それがうまく進んでいるときには、多くの時間、同調の関係が支配するはずである。持続的な同調の関係は遊びにおいてのみ特徴的なことではなく、企業における経営者や管理者と労働者との関係、および労働者同士の関係(つまり「働く」人々の関係)、あるいは同じ政党に属する党員相互の関係の場合のように、西村が「企て」と呼ぶ、遊びがそれではないとされるありかた、「各自が有する固有の意図をもって提示した計画を、それぞれの意図、利害、能力を考慮し、相互に調整しあうことによって役割を分担し合い、引き受ける、主体的意識主体の企ての対向関係」が支配的なはずの活動形態や組織においても見出されると私は思う。とくに日本的と言われる企業においては、いったん企業に入社して働くことに決めた(そして働き続けている)人々の、なかよく仕事をしている限りの同僚や上司に対する関係については十分によく当てはまる。西村が遊びの本質と見なした同調の関係は、その骨組みについてだけなら、企業の業績をあげることに向かって協力し合う、息の合った同僚の間の仕事のキャッチボールとして、ごくふつうに見出すことができる。
たしかに、企業や政党は「企て」の「対向関係」によって生み出され、支えられているもので、入社ないし入党するかどうかは主体的決断によって決まり、遊びの仲間に加わる、あるいは「巻き込まれる」のとはだいぶ違う。しかし、それは「入る」までのことで、存在する関係の構造、「現実態」が問題である限り、そこには議論、検討、役割分担のための調整等の対向関係も存在するが、「同調」の関係が支配的だといえる。
他方、遊びにおいては、同調が支配的であることはたしかであるにしても、そこには同時に、主体的企て、考量や、調整も行われるということは、かくれんぼの始まり方に関して、すでに、触れた。ガダマーも、人間の遊びにおいては、遊び手は「遊びを組み立てるための」「内的な課題」を果たそうとすると、遊びが主体的な企てによって担われていることに触れていた。テニスや将棋など、大人の遊びの主要なものである、闘いの遊びにおいては、勝つことを意図して、「相手がどうくるか」を予期し、「それにどう応えるか」を主体的に考量する「対向」の関係が重要な要素をなしている。
このように、「遊び」としては同調の関係が基本的なものであるにせよ、対向関係や考量や決断の要素を含んでいるように、働く関係、仕事の関係においても、「企て」「対向」関係を基本的骨組みとしつつ、同調、団結の要素によって支えられていることも確かである。 組織や集団は参加者、あるいは構成員の間に存在する「同調」の関係なしには、存続し得ない。西村は、同調が遊びに固有の構造であるかのように言うが、決してそうではない。もし、「人間行動一般」のなかで、遊びがそれ以外の行動と全く異なる特徴をもつと言いたいのであれば、「同調」という存在様態に求めることはできない。
耕作においては、鍬を振り上げ、次いで振り下ろし、鍬の刃を土に打ち込み、土を掘り起こすのだが、鍬は振り上げられ、地面から離れたまま止まることはなく、また、刃が地面に突き刺さってとまったままであるのでないから「つかずはなれず、ゆきつもどりつする」という描写とよく合う。また、研究の仕事において、あることを調べてわかったとする。すると、それが、すでに分かったと思っていたほかのことについての自分の理解の浅さを知る結果になることがよくある。こうして、一つの事柄の解決が他の事柄の再検討を求め、研究が進んだり戻ったりということがよく起こる。また、西村は「がらがら」を使って遊ぶ母親と子どもの関係を分析しつつ、「いまか・いまか」「もうちょっと・もうちょっと」という、「緊張と〔その〕解消からなる遊動」が遊びの構造のもっとも単純な骨組み」だと言っているが、同じ構造は仕事のなかにいくらでもあり、緊張とその解消の間の往復が絶えず起こる。
こうして、遊びとは全く異なるはずの行動である、労働する(仕事をする、働く)ことにも、遊びに本質的とされていた「つかずはなれず、ゆきつもどりつする」「往還の遊動」という特徴が含まれている。とすれば、それらの特徴を指摘することによっては、遊びが他の人間行動一般と異なる独特の行動だということを示すことはできないのではなかろうか。
こうして、西村が遊びについて本質的特徴として述べていることは、「鍵束をもてあそぶ」場合のような、それによって積極的楽しさや満足がほとんど得られない、チクセントミハイの言う「マイクロ・フロー」の行動であるか、「二匹のじゃれあう子犬」、あるいは「いない・いない・ばあ」をする赤ん坊のように「主客の未分化」な存在、あるいはかくれんぼうで遊ぶ子どもたちのように「主体としての個的人格ではない」ような存在など、遊び手の範囲が限られた、特定の遊びを考察することによって、得られたものであり、それとは異なる、「企て」であるような多くのほかの遊びが存在する。
また、遊びの骨格をなすとされた「同調」は、「対向」と「企て」の基本的関係からなる企業などの組織における活動においても、重要な役割を果していることを私は示した。そして「往還の遊動」という特徴は「働く」という、「遊び」とは全く異なる活動にもあてはまり、遊びに特有のものではなかった。したがって、西村の『遊びの現象学』の第4章までに述べられている、「現象学的」(?)分析、あるいは、日本語の用例に基づく説明などによる遊びに関する一種の基礎論は、遊びが独特な存在性格をもつものだということを納得させてくれるものでは全くなかった。
同書第5章「玩具の存在論」では、単に「遊動に同調し、身を任せる」だけでは遊ぶことが不可能であることが明らかだと思われる、「独楽回し」という「技量」を要する遊びが登場する。
こま回し:茨城県結城市富士見幼稚園のブログ(http://blog.fujimi.jp/)から借用した。

だが独楽回しという遊びでは、幼児が、他の子供が独楽を回しているのを見て自分も回してみたい、独楽回しの遊びをしたいと思った(遊びの気分になった)としても、だからといってすぐに独楽回しの遊びを始めることはできない。彼は必要な道具(適当なひも、そして独楽)を準備しなければならず、さらに独楽を回す技量を身につけるための「練習」が必要である。相手の動きを目で追うことで遊ぶ「いない・いない・ばあ」、鬼に捕まらないように走り回って遊ぶ鬼ごっこなどの比較的簡単な遊びでも、一定の、心身の能力が必要であるが、独楽回しはそれ以上に難しい「技量」を身に付けることができてはじめて可能になる。独楽回しという遊びの理解のためには企てや努力といった、主体性(これは西村の言葉なのだが)を意味する言葉を用いる必要があるように思われる。独楽回しの遊びを「主体的企てでないもの」として描くことは果たしてできるのだろうか。ドイツ語を交えた西村の説明を聴こう。
「ドイツ語で、ふつうの独楽という呼び名のほかにも、たとえば「舞いボタン(Tanzknopf)」とか、「魔女(Dludelmadam)」----とか呼んだりするのも、そこに、自分でくるくる回ったり音をたてたりする遊び相手を認めてのことと思われる。----年長の子供たちが、この魔女と遊ぶのをみて、幼児が自分でも遊びたいと思うとき、かれの関心は、さしあたって、独楽をとりあつかう自分の手腕や、自分の思いどおりに支配する調教にあるのではない。むしろかれは、どうかして魔女を呼び出して、その跳躍や舞をもういちど見てみたい、と願うのではないか。少年が実際に自分で独楽を回して遊ぶ場合でも、この独楽「と・遊ぶ」遊びの構造は、基本的には変わらない」。
子どもは練習を始める。独楽回しを真剣に試みる子どものケースを分析しつつ、西村は言う。
「この独楽回しの練習は、曲芸師の練習と違いはないように見えるかもしれない。独楽回しをして遊ぶ少年が動員する個々の手技は、その複雑さや洗練の度合いはべつにして、基本的なところでは、曲芸師のばあいと似通っているといってよいだろう。すくなくとも、独楽を回すためには、少年は、曲芸師と同じタイミングで、腕を振り、ひもを解き放つことができなければならないだろう」。だがこの練習は曲芸師がおこなう練習とは異なる。曲芸師の場合には「曲芸の道具立てである独楽という、外的事物の抵抗を、手練によって調教し、支配し、これを手にぴったりと、隙間なく、遊びなく適合させて一体化させようとする、手の企てがある。これに対してまだ幼い子供にとっては、---魅惑は、独楽を思いのままに扱うことのできる主体の手、その支配能力にあるのではなく、その独楽の、まるでいのちをやどしたかのような自在な動きにある」。
曲芸師の場合には独楽を、手練によって調教し、完全に支配することがめざされている。曲芸師でない子どもは、「個々の手技」において曲芸師の場合と大差がなくても、支配や調教を目指してはいない。だが、「支配と調教」を目指さないとしても、そのことはただちに子どもが自ら遊びを企てるのではなく、独楽の魅惑的な踊りによって、独楽のまるで生きているかのような自在な動きによって、我知らず独楽遊びを始めてしまうということを意味してはいない。西村は、幼児と年長の子どもとを区別しているように見えるが、はっきりしない。幼児は「回す」ことに関心があるのでなく「舞い踊る」独楽に惹かれて、我知らず練習をはじめるかもしれないが、年長の子どもは、自分で独楽を「回す」こと、コマをまわす技量に関心があるかもしれない。しかし、西村はこの後者のようなケースは全く検討しようとはしない。
西村は、「子ども」、「幼児」は、独楽を支配することである技量を身に付けることを目指しているのでなく、独楽の舞い踊る自在の姿にひきつけられて、独楽回しの練習を始めるのであり、関心の様態が曲芸師の場合と全く異なるという。
いくら練習しても独楽が回らず、途中で止めてしまう子どももあるだろう。「何回やっても、独楽がまわりださないとき、独楽がもはや「もうちょっと・もうちょっと」と誘いかけることをやめたとき、遊びの関係はたちきれ、少年は独楽を投げ出す。かれはまだ、独楽と遊ぶには、遊び手として十分ではない。---」。子ども自身が「もうちょっと、もうちょっと」〔で回る〕と思って練習するのではなく、独楽が誘いかけるのだという。もうちょっとで回りそうだと考えて練習を続けるとすれば「主体的企て」であろう。しかし、遊び手が自ら遊びを企てたのではない。子どもは独楽に誘われて遊びの関係に入り、練習をしてきたのであり、途中でやめたとすれば、相手が誘うのをやめたからだと西村は言うのである。
西村は、この「期待の宙吊り」構造に力点をおいて、独楽遊びの全体を説明しようとしているが、それによってだけ遊びが成り立っているのではないという点を、ここで、あらかじめ指摘しておく。たしかに「もうちょっと・もうちょっと」という「期待の宙吊り」という関係は、「いない・いない・ばあ」、あるいは(わざとつかまりそうになってさっと逃げる)鬼ごっこなどでは、遊びの重要な骨格をなしていると私も思う。しかし、波間に浮かぶボートにゆられて遊ぶこと、あるいはブランコを漕いで前に後ろに振って遊動を楽しむことにおいては、この「期待の宙吊り」が遊びの基本的構造をなしているとは言えない。「期待の宙吊り」は遊びを構成することもあるがそうではないこともありうる。(たとえば、お人形さんごっこや、機関車ごっこも遊びであろうが、これらのあそびにおいては「もうちょっと・もうちょっと」という「期待の宙吊り」構造なるものを指摘することはできないと思われる。)
ここで何が生じたのだろうか。少年は独楽をうまく回せるようになったのだから、(少なくとも、しばらくは)繰り返し独楽を回して遊び、独楽回しを楽しむのではないだろうか。これがふつう、独楽回しの遊びといわれて思い浮かべるシーンであろう。しかし、西村はようやく迎えた独楽回しの本番の情景を描こうとはしない。彼は、この状態においては独楽は「少年の手に自在に操られる一個の道具にな」ってしまい、「遊びの同調関係は」「断ち切れ」、「主体と客体、技術と道具の支配関係」に転じてしまっている、と言う。西村は、少年がうまく独楽を回せるようになった状態はもはや遊びの状態ではないと考えているのである。不思議である。「もうちょっと・もうちょっと」という独楽の誘い、励ましに促されてのことで、「主体的」な努力とは見なされていなかったが、ともあれ、練習を行って、ようやく独楽を回せるようになった、いや、西村的に言えば、独楽が「自在に」回ってくれるようになった。なるほど、少年が「自在」に独楽を回すことができるとしても、それは独楽が「私を回してほしい」とずっと誘いかけてくれた結果であろう。独楽に誘われてうまく独楽を回すことができるようになった状態が、少年と独楽とが仲良く同調し合う状態ではなく、なぜ、主体による客体の支配関係と見なされなければならないのか、理由がわからない。独楽回しの練習を行っている場面に戻ってみよう。
しかし、西村は違う。彼は、「少年にとって、独楽を回すことがかれにとって遊びである限り、あれこれの技をためしてみることそれ自体が独楽を相手の遊びでなければならない」という。ここでいう「あれこれの技」は、すでにうまく独楽を回せる年長の子どもが持っているような技、たとえば掌の上でまわすなどのことではなく、回すことができないでいる少年の回す練習におけるあれこれの工夫のことだと思われる。そして、遊びに一定の技量が必要であれば、遊びには練習のプロセスも含まれると考えるのは間違いではないから、「あれこれ技を試してみる」ことも「遊び」だといってもよい。しかし、うまく回せるようになったときには、「遊びの同調関係は断ち切れて」しまうのであり、西村は「あれこれ技を試してみる」練習こそが、遊びなのだと主張する。
どうしてだろうか。その練習行為が「もうちょっともうちょっと」という「遊び」のもつ本質的構造と一致していると西村が考えるからだと思われる。まだうまく回すことができず、独楽が「抵抗したり、したり顔に一人で舞ったりする」ことは少年にとって、「もうちょっと・もうちょっと」と「誘いかけ」、「魅了する」ことであったが、いまやその力を失ってしまっているという。子どもが独楽をうまく回せるようになるということは、独楽が「もうちょっと」と誘わなくなること、こどもが自分で、あるいは一方的に独楽を回すこと、子どもが主体となって客体の独楽を支配するようになることであり、したがって、独楽と子供の「遊びの同調関係」は「断ち切られる」のだと西村は考えるのであろう。このとき、独楽は「もうちょっと・もうちょっと」と誘いかけるのを止めるている。この誘いかけ、ないし「期待の宙吊り」は「あれこれ技を試し」ているときにだけある。
こうして、独楽がうまく回せるようになったときには、遊びの同調関係は断ち切られ、少年と独楽の関係は遊びではないものに転じてしまう。子どもが独楽を自在に回すことができる状態はもはや遊びではない。しかし、独楽回しの遊びについての西村の分析はそれで終わるのではない。つづきがある。
西村は、独楽を回そうとあれこれ試してみるだけだった最初の練習時の「遊び」とは違い、技がレベルアップされてはいるが、ここにもやはり子どもの手と独楽との間の「遊撃」に「宙吊りにされた期待」の同調が存在する関係、つまり遊びが存在する、と言っている。子どもたちは曲芸師のように独楽を「支配」しようとしているのではなく、子どもたちは意図的に独楽と手の間に「障害を仕組む」ことにより「遊撃」を作り出 し、新たな「期待の宙吊り」という遊びの関係を作り出したのだと言われている。これが西村の描く独楽回しの遊びの全貌である。
幼児は、年長の子どもたちが独楽を回して遊んでいるのを見て自分も独楽回しを始めるのだが、「独楽を支配する」手の技を得たいとおもったからではなく、独楽の舞い踊る姿に魅せられ、「舞い踊る独楽と遊びたい」思ったからであるという。練習によって独楽がうまく回ったときに、子どもは「回った」と言って喜んで手をたたくだろう。しかし、それは独楽をうまく回せることができるようになった自分の技を得意に思う気持ちの表れなのではなく「いない・いない・ばあ」の赤ん坊の「ほらね・やっぱり」という喜びの気持ちとおなじものである。そしてうまく独楽を回すことができず、練習をやめるのは、「独楽がもはや「もうちょっと・もうちょっと」と誘いかけることをやめた」からであった。独楽は、「抵抗したり」、「したり顔に一人で舞ったり」さえするものであった。
自分が回したのであれ、友達が回したのであれ、紐をひかれて独楽が回り始め、一本足で立って回転しながらゆっくりと位置を変えて移動する(=舞う)のを見るのは楽しい。だが、ある年齢に達し一定の運動能力を有する子どもたちが、独楽回しをしようと思う(企てる)ときには、回っている独楽を眺めることにではなく、独楽を回すことの方により強い興味を感じているのではないか。私は、幼い子どもは独楽に魅せられ、独楽に「一緒に遊ぼう」と誘われていると感じているという風に描くことには反対しない。しかし彼らが自分でも独楽をまわそうと練習をはじめるときには、年長の子どもたちが独楽を回しているように、自分も回せるようになりたいのではないだろうか。そうだとすれば、練習を繰り返す子どもは、魔女=独楽に「もうちょっと・もうちょっと」と「誘われている」というよりは、独楽を回したい、回せるようになりたいという願いが「もうちょっとで叶いそうだ!」、「もうちょっとやればできるぞ!」と思っているという方が、より本当らしく、無理のない描写と思う。
したがって、少年が練習を繰り返して独楽を回せるようになり、今やっと回り始めた独楽を見る喜びは、ただ単に、自転する独楽を見る楽しさとは違うはずである。「回った!」と手をたたくときの喜びは、「いない・いない・ばあ」をしている母親が顔を覆っていた手をどけて顔をみせたときの赤ん坊の「ほらね、やっぱり」という喜びとは違うだろう。少年の喜びは何かを成し遂げたという喜びであろう。
少年は、一本足で立って回転する独楽の舞を楽しむのだが、練習の成果がこの独楽の舞のなかにはある。練習を重ねた結果独楽を回すことに成功し、今回転している独楽を見る喜びのなかには、たしかに曲芸師の場合とは違い、自分の調教が成功したという支配の喜びだけがあるのではないが、また幼児のように魔女の舞を見るだけの喜びがあるのではない。独楽が回ることと、自分が回せたこと、自分が「できた」ことの喜び、その両方があるはずだ。独楽が回ってくれたことの喜びと自分の練習の努力が実った喜びの両方が含まれているはずだ。
「練習の努力」といったが、子どもの独楽回しの遊びの練習が、仕事があともう少しで完成するから、疲れてはいるががんばろうとする大人の場合と同様の、意識的な「主体的企て」だと考えなければならないとは私は思わない。独楽を回す練習を続ける子どもは、自分の腕で回したいのだが同時に独楽とあるいは独楽で遊びたい「気分」にあるのだと言うことには反対しない。私は、企てと気分を明確に区別することはできないだろうと考えるのだ。
独楽回しの練習を始めるときの子どもの気持ち=気分は「独楽が回るのを見たい。自分で回そう」という風に描くこともできるが、「回して!と独楽に誘われた」、「独楽が誘った」と描くこともできる。うまくいかなくても独楽を投げ出さず練習を続けるときには「がんばってもう少しやってみようと考える」と描くこともできるが、独楽が「もうちょっと・もうちょっと」と誘い、励ましたと描くこともできる。独楽は「舞い、踊る」というだけでなく、「抵抗」したり、「したり顔」で踊ったりする存在でもある。
だが、西村は「主客未分」の「気分」にある状態は、主体の客体に対する一方的な働きかけの企て(さらには支配の企て)とは別物であることを強調しようとする。こうして、西村は、ふつうは、子ども(=人間)の側に見出されるであろう、“主体的”、つまり、意識的、意図的態度を見ないようにする。
西村は、子どもの側の“主体的要素”を軽視するために、独楽を擬人化する表現をとった。しかし、上の西村の一連の説明では、独楽回しの遊びが「主客未分」の「二項」の「同調」の関係であることが示されたというより、受動的な存在である人間=子どもに、擬人化された独楽が能動的積極的に働きかけることによって作り出された、逆の主客の関係が示されている。西村は、子どもから奪った主体性を物である独楽に与えてしまった。西村は遊んでいる「二項」の「主客未分」の関係を示したのではなく、人間の項は客体的で、物の項(独楽)が主体的であることを示したのである。
さて、子どもはうまくまわせるようになった。子どもが独楽をうまく回せるようになるということは、西村の描き方に従って言えば、それまで独楽に誘われ、あるいは励まされ、教え導かれる「非主体的」状態にあった子どもが、ようやく、一人前に自立し、独楽と対等な関係になったということになるだろう。とすれば、次の段階は、大人の男女が手を取り合ってダンスを踊るように、子どもは繰り返し独楽を回し、彼が回す独楽が踊るのを楽しく眺め、独楽と仲良く遊ぶ、と考えたいが、西村は「主体と客体、技術と道具の支配関係」に移行してしまった、という。
西村は、二項のうちの一方が他方を支配する対立関係か、あるいは二項の主客未分の同調(一体と言ってもいい)の関係かのどちらかしかないと考えるようである。曲芸師のように対象=モノの支配を目指す関係が一方にあり、他方で幼児のように対象=モノ(母親であれ、独楽であれ)と自分の区別のない二項の関係、欲求する自分と欲求対象であるモノとが別の存在であることを知らない主客未分の関係がある。だがその中間にそれら二種類の関係とは別の関係が存在する。つまり、二つの項が自立しており、しかも、「支配」ではなく、仲良く交わり、協力し合う、遊びという関係が存在する。だが西村には、この第三の関係は考えられないようだ。
しかし、たとえば泳ぎたい、泳げるようになりたい、あるいは、木に登りたい、木登りができるようになりたいと考えるとき、それらは水や木を支配しようとすることとは異なる。それと同様、独楽を回して遊びたい、独楽を回せるようになりたいと考えることは、主体として客体である独楽を一方的に支配しようとする企てだと見ることはできない。
何かができるということは、即、何かを支配することではない。遊びで何かを企てることと、別な目的を実現するため(利益を得るため、義務を果たすため)に何かを企てることとは異なる。後者の場合には、目的に手段が従属させられる。行為のかかわる対象のもとに立ち止まり、その存在を大切にしたり愛しんだりし、それと遊んでいる余裕はない。それを作り変えたり、利用したり、取り除いたりして、最後の目的を達成するべく前進しなければならない。
しかし、それが明確なケースとそうでなく中間的なケースがあるだろうし、遊びで身につけた木登りや、独楽回しの「技」が、支配のための行為・行動においても役立つことはあるかもしれない。子どもというより赤ん坊の遊びを、後の生活における必要行動にとっての有用性と関係付けることもできるかもしれない。そしてそのような有用性があることに遊びの意味を見出そうとする研究も行われているようだ。しかし、遊びをその外の目的と関係付けるのでなく、遊びそのものを理解しようとするとき、遊びのなかで何かできるようになることを支配と結びつけて考える必要があるとは全く思われない。木に登って遊ぶことは、いつか木に登って実を取る「支配」に役立つことがあるかもしれないが、今、遊ぶために木に登ることは支配ではない。泳いで遊ぶことは水を支配することではないし、「自在に」独楽を回す技を手に入れ、独楽を自由自在に回して遊びたいと子供が考えたからといって、それが「独楽をまわして遊ぼう」=「回る独楽と遊びたい」という最初の「主客未分」の関係ではないという理由で、その子はプロの「曲芸師」と同様、独楽を支配してしまっていると考えることは不要である。
さて、綱渡りなど難しい技に挑戦するこの新たな段階の独楽回しについて、どのように考えるべきか。難しい技に挑戦しようとしているのだが、曲芸師のように独楽を調教し、支配しようというのではない。曲芸師が目指すのは「手と独楽との一体化---手の自動化した一義的な動き」であろう。だが、子どもたちは、「手の自動化した動き」によって「自在な独楽回し」を楽しむのではなく、わざと難しい技に挑戦することに、決めたのである。西村は、子どもたちは「人工的な障害」を仕組むという。「人工的に仕組まれた障害が、手と独楽との一体化をはばみ、手の自動化した一義的な動きを解体する」。子どもたちは「手と独楽の間に、あらためて、一つの不在、一つの猶予、つまりは、遊びの隙間を仕組む」のであり、こうすることによって、子どもたちは「もうちょっと・もうちょっと」という「期待の宙吊り」構造を新たに作り出すのである。この「期待の宙吊り」構造は遊びの祖型である「いない・いない・ばあ」を構成する重要な要素であった。こうして遊びはより高い技量のレベルで継続されるというのだ。
ここで西村が説明している遊びは、カイヨワが遊びの一つのパターンとして説明しているルドゥスである。カイヨワは陽気に騒ぎ、物を壊して、喜ぶだけの活動(西村の「がらがら」遊び)であるパイディアと、また、遊ぶ人の緊張や才能が対抗心や敵対心と結びついて発揮されるアゴーンとも区別して----つまりさまざまな遊びの種類と、型があることを説明しつつ----「無償の困難の愛好」という欲求が、自分が選んだあるいは設定した「障害と戦う」ことに向けられた遊びのあり方として説明していた。遊ぶ人はここで自分の能力、技量を高めることで困難の克服を楽しもうする。
西村もカイヨワが言っているのと全くおなじことを言っている。遊び手が「仕組む」つまり自分で障害を選び設定するのだと。そして「子供たちは自分たちに実現不可能と思えるような高度な洗練を必要とする技を、遊びの障害として仕組むことはない」。子どもたちは自分ができる見込みのある、ちょっとだけ難しい「障害」を設定し、それに挑戦する。だから「もうちょっと・もうちょっと」が可能になる。子どもたちは「無償の困難を愛好」しているのだ。
だが、この独楽回しの説明においては、西村は、彼がもともと遊びの根本的特徴として述べていたこととは反対のことを主張する結果になっている。たしかにここには「いない・いない・ばあ」の場合と同様の「期待の宙吊り」構造が再現されている。しかし、この構造は、ここルドゥスにおいては、もはや母親によって与えられるものではない。また偶然に与えられるものでもない。子どもたちが乗り越えるためにわざと設定した「障害」によって、その構造は産み出されたのである。つまり子どもたちは、自らのイニシャティブにより新たな遊びを作り出そうと、企てたのである。したがって、「障害」は、子どもたちの「企て」によってはじめてその「存在可能性」を与えられた。ここには遊びをより複雑なものにし、新しくまたより強い楽しみを維持継続しようとする遊び手の明確な企てがあり、企てる主体が存在する。ここでは、以前の西村の立言に反して、遊びは「偶然と僥倖」によって始まるものではなく、子供たちが遊びつつ、遊びの発展、遊びの「存在可能」を企てるということがはっきりと示されている。
彼は前の箇所では「遊びの存在は、偶然と僥倖としての、遊動そのものにになわれてある以上、遊びはもっぱら現実態としてのみ存在する」と言っていた。ところがここでは、子どもは、ただ単に遊びに担われて遊んでいるのではなく、一つの技をマスターするとその「手と独楽との一体化」には満足せず新たな「人工的障害」を仕組むというしかたで、たえず新しく、別の遊びを作り出そうとする。そしてそのことが遊びだと西村は言っている。つまり遊びは現実態として存在しているのでなく、絶えず、こどもの主体的な挑戦によってつくりだされるものである。こどもたちはただ遊ぶのではなく、遊びを作り出そうとしている。遊ぶとは遊動の同調関係に身をゆだねて「ある」ことではなく、「期待の宙吊り」という遊びの構造を絶えず新たに作り出そうとする企てだと、西村は主張していることになる。
「無償の困難を愛好する」年長の子どもたちが行おうとするこの段階の遊びを、人であれ物であれ、遊び相手から誘われることによって生じた受動的な、あるいは主客未分の「気分」によって生じた結果とみなすことが可能だと考える人は、たぶん、つぎのようにも考えなければならないだろう。政治家の行動は、国家や社会の政治経済的な状況によって強いられ、やむを得ずなされるものであり、彼自身の責任など決して問い得ないものである。企業経営者の行動についても同じことがいえる。人間の行動はすべて、世界によって誘惑されるか強制された結果である。あるいは、人間の行動はあらかじめ運命によってすべて決定されている。
だが、もし、そのような見方ができるとすれば、世界はすべて主客未分の遊動状態ということになり、他の人間の行動や関係のありかたと異なるものとして、遊びを取り立てて論ずることは無意味になるだろう。
西村の独楽の遊びについての説明は、年長の子どもの遊びを、「遊びの祖型」とされる幼児の「いない・いない・ばあ」に無理やり還元しようとする試みに過ぎない。この「遊びの祖型」をなす基本的な骨格とは、「もうちょっと、もうちょっと」という「宙づりにされた期待」が続く状態、つかずはなれず、一定の遊隙をもつ二項が「同調関係」のなかにあり、どちらか一方が主体で他方が客体であるのではない「主客未分」な関係だとされていた。「いない・いない・ばあ」で遊んでもらっている赤ん坊が「もうちょっと・もうちょっと」という「宙吊りの期待」のうちにあると考えることには反対しない。そしてこの「遊動」状態で赤ん坊が「イニシャティブ」や「企て」や「計量」とは無関係で「主体的」に振舞ってもいない、ということも西村の言うとおりだ。(だが、西村の説明に反し、実は母親が子どもの反応についての予測をし、誘いかけるなど、主体的に働きかけていることを私は指摘したが。)
西村は遊びという活動の重要な特徴を非主体的で、主客未分の様態にあることだとする。しかし、赤ん坊が「主体的」でないのは「いない・いない・ばあ」という遊びを行っているときだけでなく、遊び以外の食べたり飲んだり、ウンチをしたりというすべての行動において「非主体的」であり、赤ん坊においては「主客未分」の状態、つまり自分と対象=モノとの区別がまだ存在していないからであろう。ところが西村は、その「いない・いない・ばあ」が特別のものだと考えた。つまりそれが「遊びの祖型」だと考えた。
「いない・いない・ばあ」においても「期待の宙吊り構造」が存在する。他の遊びにおいても、「期待の宙吊り」構造が重要な要素をなしている。そして、「祖型」において「期待の宙吊り」と「主客未分」が同居している、あるいは結びついている。こうして西村は最初に、主客未分が遊びの要素だと考えてしまったのではないか。(ガダマーは「自然」における遊びと「人間の遊び」をはっきり区別し、前者にだけ「主客未分」を認めていたのだが。
ブランコやシーソーの遊びについて、私は、その遊びの開始と継続のためには、子どもが地面を蹴るなど、自分の身体を意識的に動かす主体的関与が必要だということを示した。そこには、前後に揺れ動く体の「宙吊り」は存在したが「期待の宙吊り」は存在しない。「期待」によってはブランコの振れもシーソーの上下動も始まらず、継続もしない。自分で主体的に、ブランコは漕がなければならず、シーソーでは地面を蹴る必要がある。だから「いない・いない・ばあ」で遊ぶことを好む幼児にはまだシーソーもブランコも無理である。
また、私は、「独楽を回したい」と考えることを「独楽が遊ぼうと誘っていると感じる」と書くことはできるにしても、子どもの成長につれ、自分で回したいという主体的な動機のほうが勝るであろうことも示した。つまり練習の結果独楽がまわったときの少年の喜びは、自分が何かを達成したときの喜びであると考えるほうが自然であり、母親が顔を隠していた手をどけて顔を見せたときの赤ん坊の喜び「ほらね、やっぱり」と同じだと見なすことには無理があると指摘した。私は遊びについての別の理論を提出しようとしているのではない。遊びの「現象」をどうみるべきかを述べただけである。
しかし、西村自身、独楽遊びの最後の段階では、子どもたちが、「人工的障害を仕組む」ことによって「期待の宙吊り構造」を意図的に作り出すと述べ、遊びが主体的に作り出されると説明することになった。彼の哲学的なテーゼ、「遊びの存在根拠は主体の自己存在可能への企てにはない」、「遊びは偶然の僥倖によって始まり、現実態においてのみ存在する」は成り立たないということが、少なくとも、この技量を必要とする遊びにおいては、彼自身の説明によって、明らかになった。
以下は、ヴィゴツキー/柴田義松・森岡修一訳『児童心理学講義』(明治図書出版、1976)の一つの章「子どもの精神発達における遊びとその役割」(以下では『講義』と略す)、およびヴィゴツキー・レオンチェフ・エリコニン他/神谷栄司訳『ごっこ遊びの世界 虚構場面の創造と乳幼児の発達』(法政出版、1989)第一章「こどもの心理発達における遊びとその役割り」(以下では『世界』と略す)に基づく。
ヴィゴツキーによると乳児期(一歳まで)の子どもは遊びを求めない。彼らはただ欲求を直接的に満たそうとする(たとえば母親の乳首を吸う)だけである。幼児期前期(一歳から三歳まで)になって、それ以前とは異なる欲求・欲望、今、ここに存在しない、物を求めるようになるが、以前同様、直ちにそれを手に入れようとし、たとえばそれが実現されなければ「足をバタつかせたりしてひと騒ぎ起こす」。三歳を過ぎた子ども(幼稚園期、6,7歳まで)は、今、眼前の馬に乗りたいという個別的な欲求とは異なる、馬に乗ってみたいという、一般的な願望を持つが、これを想像の中で実現しようとすることが棒にまたがって、部屋の中を走り回る「お馬さんごっご」という遊びになる、という。「遊びの本質は願望の遂行にあるが、その願望は個別的な願望ではなく、一般化された感情を伴う願望である」(『世界』)。
また彼は「子どもは遊びの中で虚構的場面を創造する。---この想像は幼稚園期に現れてくる、視覚的世界と意味的世界の分離に基づいて可能となる」。という。
ヴィゴツキーは、幼児期前期の子どもにとってモノは誘発的性格をもつ、というレヴィンの説を参照しながら、次のように言う。「この年齢期においては、知覚は独立したモメントではなく、運動的-感情的反応のなかの始原的モメントである。つまりあらゆる知覚は、それ自身、活動への刺激である。---子どもは場面に束縛され、自分のいる世界に束縛されて行為するほかない」。ところが、幼稚園期の子どもにとって「モノはその誘発的性格を喪失する」。子どもはあるモノを見ても、それを見えるモノとは別のように取り扱うことができるようになる。「眼に見えない、思考だけによって産み出された場面での行為、想像的世界・虚構場面での行為は、子どもがその行動において」モノの直接的知覚に束縛されずに、「この場面の意味によって規定される」ことで可能となる。「幼稚園期になると、遊びのなかではじめて、意味的世界と視覚的世界の分離が生じる」。「現実に対するこどもの関係を規定するひとつの基本的な心理構造が根本的に変更されるのである」。とはいえ、こどもはまだモノから考えを分離できないのであり、別のものの支えをもたねばならない」。そして、棒は馬という役を演ずることはできるが、郵便ハガキは決して馬にならない。「遊びの中では子どもにとって、あらゆるものがあらゆるものになる―というゲーテの命題は正しくない」(注)。「学齢期になると遊びは内的過程、内言、論理的記憶、抽象的思考に移行」し、子どもは「モノから切り離された意味を操作する」ようになる。
---------------------------------------------------------------------------------------------------------後に紹介する加用にしたがえば、精神分析学派の理論も入れて、一般に20世紀の代表的な三つの発達理論においては、幼児期の遊びはごっこ遊び(ピアジェはこれを「象徴遊び」と呼び、ヴィゴツキー派のエリコニンは「役割遊びと」呼んでいる)であり、学童期に近づくにつれて社会化の進行とともに、それが次第にルールのある組織だった集団遊びに移行して行くという理解で共通している。そして、発達の段階ごとにそれに対応した特殊な遊び活動形態があって、それが発達とともに交替的に変わっていくと共通して考えられている、という。加用文男「遊びの発達的展開―発達的交替説から交差分化説へ」『発達』109号。
ルールのある遊びは、『世界』では少ししか述べられていない。以下は『講義』による。ヴィゴツキーも「虚構場面を伴う遊び」つまりごっこ遊びが、ルールのある遊びに先立つと考えている。だが、「遊びに虚構場面がある場合には、必ず、そこに、ルールがある」という。そして「最近では」ルールの遊びは虚構場面を内に含むということも証明されたという。しかし「明らかな虚構場面とかくれたルールを伴う遊びから、明らかなルールとかくされた虚構的場面を伴う遊びへの発展が、子どもの遊びの二つの極を構成すると同時に、子どもの遊びの進化ということになる」という(『講義』)。ヴィゴツキーから見て、ごっこ遊びつまり虚構の遊びが発達的には先立ち、それにルールの遊びが続くことは確かだが、それはもともと遊びがルールと結びついたものであり、発達とともに子どもがよりいっそうルールとの結びつきの強い遊びをおこなうようになるという傾向を示す証拠なのである。
ヴィゴツキーにとって、すべての遊びはルールを有するということが重要なのである。かれは言う「遊びは楽しみと結びついているから、子どもは〔目的において〕自分がいちばんしたいことをする。だが、それと同時に子どもはもっとも抵抗の大きい路線において行動することを覚える。遊びにおいてはルールを守り、直接的衝動に基づく行動を否定することが最大の満足を得る道であることから、こどもはルールを守って、したいことをやめるのである。----遊びはたえず、子どもに直接的衝動に逆らって行動すること---を要求する。ただちに走り出したい――これはまったくそうなのだが、遊びのルールは待ちなさいと命令する。-----このように遊びにおいては子どもに大きな自己制御の力が生まれる---。
子どもは遊びのなかではいつも自分の年齢よりも上になり、自分の日常の振る舞いよりも高いところにいる。遊びでは子どもは背伸びをする。---遊びと発達の関係は、教授と発達との関係に比すべきものがある」。
「遊びを目的のない活動と考えるのは間違っている。遊びは子どもの目的的活動である。スポーツには勝ち負けがあり、-‐-目的が遊びを決定する。最終的要素としての目的は、遊びに対するこどもの---態度を決定する。競走して走るとき、子どもは強く興奮し、ひどく苦しんでいる、楽しみなど少しも感じられないだろう。〔それでも、勝つことを目指して走る。〕」
かけっこ:「陸上・かけっこの家庭教師 First Sports」
http://www.taiiku-sports.com/service/primary.htmlからお借りした。

『世界』では次のようにも言っていた。「子どもにもたらされる快楽という指標によって遊びを定義することは二つの理由によって正しい定義ではない。第一に、遊びよりもはるかに大きく鋭い快楽の体験を子どもにもたらす一連の活動が存在するからである」。〔この第一の理由は不適切である。「遊びよりもはるかに大きく鋭い快楽」とは何のことかは説明がないが、おそらく、母親の乳首を吸ったり、好きな物を食べたり飲んだりすることをさすだろう。しかし乳児ではなく歩き回れる子どもにとって、眼が覚めているときに常に食べたり飲んだりしているわけにはいかないだろう。子どもは動き回り、遊ぶことを好むだろう。すると、食べたり飲んだりしている時間以外に、遊ぶ=活動する理由を快楽に求めることは可能であろう。須藤〕
「他方〔第二に〕われわれは活動の過程そのものがまだ快楽をもたらさないような遊びを知っている。---子どもにはその結果が利益になる〔と感じられる〕場合にだけ快楽を与えてくれる遊びである。それは、たとえば、いわゆるスポーツ遊びである。(---勝ち負けを伴う遊び、結果を伴う遊びである。)この遊びは、子どもに利益をもたらさずに終われば、鋭い不快感に彩られることさえよくある。このように快楽の指標による遊びの定義は、---正しいとは考えられない」(『世界』)。
『講義』に戻る。「遊びにおける発達の終わりごろになると、‐-‐目的―ルールが登場する。さらにもう一つの要素、スポーツにとってはきわめて本質的な要素が登場する。それは目的と密接にむすびついたある種の記録レコードである」。
「学童期になっても遊びはなくならない。しかし、現実との関係のなかに浸透していく。遊びは、学校教育や労働(ルールをともなう義務的活動)のなかに内的な継続をたもつ」。このようにヴィゴツキーは言う。
昨今の日本では、スポーツの勝利至上主義、記録至上主義に対する批判的意見の方が多く聞かれるが、ヴィゴツキーは、スポーツは勝つこと、記録を伸ばすことの重要性を子どもに教え込むことができる活動であり、そして仕事/労働はそのような姿勢で取り組まれなければならないということを教えることができるがゆえに、遊びの中でも最も重要なものだと考えたのである。
『講義』訳者の柴田によると、ヴィゴツキーは子どもの精神発達を常に教育との深いかかわりのなかでとらえようとした。ピアジェが「教授的干渉」をできる限り排除しようとしたのと対照的に、ヴィゴツキーは「教育は発達の尻の後にしたがうのではなく、むしろ発達を先回りし、自分の後に発達をしたがえるのでなければならないと考えた」という。
また同じく柴田によると、ヴィゴツキーの発達理論は二つの仮説に基づいていた。一つは、人間を他の動物から区別する基本的な特徴が、道具を使って自然に立ち向かう生産労働にあり、人間と自然との関係が道具を媒介とするものであるのと同様、人間の高次の精神活動はすべて、記号と言語を「精神的生産の道具」とする、道具に媒介されて起こる、というもの。人間をホモ・ファーベルと見る思想が根本にあることがわかる。第二は、人間の内面的な精神的過程は、個々の人間の内部から発生するのでなく、外部の環境、人々との共同活動、コミュニケーションを通じて与えられるというもの。子どもの精神的発達は大人の働きかけによって起きるということである。
このような基本的な考え方に立つヴィゴツキーの遊び論が、遊びは快楽を目的とするものでなく、大人になったときに、合理的に目的を達成すること、禁欲的に仕事に打ち込むことを可能にする、準備活動と見なすことになるのも当然である。
もし遊びが快楽しか与えないとすると、遊びとは別に教育や訓練を行わなければ、子どもはいつまでも精神的には子どものままにとどまることになるだろうと想像される。(身体についても同じことが言えるかもしれないが、身体は遊びだけでもかなり成長するだろう。)私、及び私と同世代の多くの人が保育園や幼稚園には行かず、「教育としての遊び」は経験していない。私たちの世代の人間は、子どもの時には、子どもたちだけで遊んできたのではないだろうか。にもかかわらず、精神的に成長し、社会化され、職業に就くことができたということからすれば、小学校入学以降の時期に、ヴィゴツキーのいうような「教育」や「教授」であるような遊び経験したということになるのだろうか。だが、私の思い出すことのできる遊びにはヴィゴツキーの言うような教育が含まれていたようには感じない。私にとっては、遊びはもっぱら快楽であったと思うが、遊びが子どもに対する教育として機能しているということもまた否定できないように思われる。しかしいくつかの点で反論したい。
ヴィゴツキーは、過程に不快なものが含まれている遊びが現実に存在する以上、遊びは快楽によっては説明されないと言うのだが、エピクーロスにしたがえば、過程の不快ないし苦と結果の快を差し引きし、快がプラスになる限り、行為は快楽を動機として行われると考えられ、したがって遊びは快を動機として行われると主張することも十分にできる。
もう一つ、ヴィゴツキーの前提していることに問題がある。彼は、遊びが物のように外に存在するものであり、外から与えられるものだと考えている。『世界』の「解説」でヴィゴツキー学派の説にたつ神谷が言っているが、子どもたちをただ自由に遊ばせておけばよいというのでなく、幼稚園教育の中に、虚構場面の創造を行う遊びを積極的に導入し、遊びの中にストーリーを導入するなど、大人の指導が必要だとされている。こうした保育実践の考え方に、遊びが外部から子どもたちに与えられるものだという考え表れている。ヴィゴツキーは、学童時期の子どもの遊びは「その結果が子どもにとって興味のある場合にのみ快楽を与える」。「これらの遊びは、結果が子どもにとってよくなかった場合、しばしば、強い不快感を与える」といっている。たとえばかけっこで一生懸命走る「過程」は苦であるが、「過程」ばかりでなく、「結果」もまた苦であり不快であるような遊びもあるということになろう。だが、そのように言うことができるのは、そのかけっこが、ヴィゴツキーの視点からみて、遊びであるからに過ぎない。いつもビリになることを知っていながら加わることを拒否しない(できない)ようなかけっこ、競走は、その子にとっては、ふつう、遊びではない。ヴィゴツキーは、遊びは物のようにどこかに客観的に存在し、それを利用して楽しんだり、それを使用するように押し付けられたりするものだと考えている。だから、遊びが楽しいことも楽しくないこともある、と言うことができるのである。
ヴィゴツキーは「競走して走るとき、子どもは強く興奮し、ひどく苦しんでいる、楽しみなど少しも感じられないだろう」言う。過程が快楽ではないということを強調するための明らかな誇張がある。なるほど、時に、子どもが、メンバーの顔ぶれから勝つ見込みが全くないもかかわらず、それゆえ、苦しみながら、苦しみに耐えて競走することもあるだろう。しかし、それは遊びとしてではなく、学校かクラブで、トレーニングかなにか課業として、命ぜられて走っているからであろう。
私が、苦しいのに我慢して走ったのは、中学のときの全員参加のマラソン大会のときが初めてであった。5キロか6キロのコースだっただろうか、ひどく苦しくて、ゴールインしたときに渡された順位のカードは後で見ると「31」と書いてあったのに、受け取ったときには「13」に見えたほどへとへとになっていたことを思い出す。 一般に、体操の時間におけるかけっこの場合には、拒むことができないから、負けることがわかっていても、楽しくなくても、走るだろう。
だが、私が小学校6年のときに経験した、「マラソン」(距離は1・5キロかそれ以下)では苦しいとは全く思わなかった。私は小学校の時には、教室で授業を受けている間、退屈でじっとしていられなかった。いつもおしゃべりで廊下に立たされた。しかし、体操の時間は楽しかった。走るのも好きだった。「マラソン」も課業として嫌々走ったのではなく、校庭から外へ出て、学校の脇を流れる川の堤防を走るのが楽しかったのだと思う。私はただ走れるだけ速く走った。私の考えでは、遊びとして、遊びのモードのなかで行われる競走は、勝つか負けるかにかかわらず、快楽を与える。
私は、また、小学校低学年の頃に、母親と一緒に歩いていたときに、突然、彼女が「競走しようか」といったので「よーし」と走ったことを思い出す。これは明らかに遊びであり、走りながら楽しいと感じていた。たしかに競争の場合には「結果に興味を持つ」。しかし、母親に勝てるかどうかについての関心だけが、このときの競走の動機なのではない。少なくともそれが主要な動機ではなかったことは極めて明白である。遊びの気分で母親と競走することが楽しいから走ったのである。たとえば外出先からの帰り道、帰宅するという目的のために、ただ黙って並んで一定のペースで歩くのでなく、「遊びのモード」に入り、たとえば、一緒にスキップしながら、あるいはかわるがわる道端の石を蹴りながら歩くのが楽しい(これも遊びであり、「結果」など問題にならない)、というのと同様に「競走しようか」と誘われたとき、私は「遊ぼう」と誘われたと感じてはっきりした遊びモードに入ったがゆえに、一緒に競走することが楽しいと感じたのだと思う。
多くの遊びは文化形態として存在しており、課業として押し付けられるという面がないとは言えないが、むしろ、遊びは遊びたいと思った者によって、そのつど作り出されるものであるということのほうがより重要だと私には思われる。つまり遊びが行われており、そこに遊びが存在するというとき、それは遊んでいる子供が(ひとつひとつの動作すべてにおいてではなくても)快を感じ、楽しんでいる限りで存在するのだし、いやになったら、快を感じられなくなったら子どもは遊ぶのをやめるだろうから、遊びはその時点で非存在となる。また、誰かが遊んでいることによって遊びが存在する場合に、まだ遊んでいない子どもにとって、それが遊びとなるのは、それが楽しそうに見え、それに加わりたいと感じてそこに加わるときである。個々の子どもから見れば、楽しくないこと、それに加わりたいと感じない活動は遊びではない。
しかし、拒むことができる場合にも、自分から進んで、苦手な遊びに加わることもあるだろう。かけっこでもいいのだが、たとえば、サッカーが下手で試合も楽しいとは思わない子どもが、集まったほかの子どもたちに誘われとき、脇で見ているか、家に帰るかするよりも、ゲームに加わり、友達と一緒に遊ぶほうが楽しいと考えたなら、そうするだろう。この場合には、サッカーのゲームそのものも、その勝ち負けの「結果」もほとんど重要ではない。仲間と一緒に運動することが楽しく、快であることを知っていれば、彼は加わって遊ぶだろう。この子は快の大きさを「考量」して、サッカーで遊ぶことに決めたのである。
私は両親の疎開先である新潟で生まれ、小学校に入るまで、父の実家である農家の土蔵で暮らしながら育ったが、周囲はほとんど畑と田んぼであった。就学前の自分の姿について思い出すことのできるのは、夏、裸になって、20~30センチの深さしかない小川(農業用水路)でバシャバシャ水を跳ね飛ばしている光景であり、大根が数本残っているだけのたぶん春先の畑で年長の子どもに交じって凧揚げをしている(見ているだけかもしれない)光景、そして雪の積もったゆるい坂路で竹で作ったスキーに乗って遊んでいる光景、そして農作業小屋の二階に積まれたわら束に埋もれながら遊んでいたことくらいである(注)。これらのシーンのなかに、私はもっぱら、快、楽しさしか見出さない。辛い競争や我慢や努力、計算のようなもの、あるいは、ルールのようなものは見出さない。
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ヴィゴツキーは、結局、ルール遊びが教育的効果を持つがゆえに重要だと考えたのであり、それに先立つごっこ遊びもルールを含んでいると考えるか、ルールのある遊びへの橋渡しを行うと考えていたようである。
私はかけっこが課業として与えられることを否定しようとは思わない。繰り返しになるが、それは遊びではなく、他の授業と同じように、課業だといいたい。幼稚園等では教育的な遊びが導入されているようである。そして、幼稚園とはそういうところなのだろうと漠然と思う。しかし、子どもたちが勝手に、つまり自由に遊ぶのと比べて、そのような「教育的遊び」が子どもたちの成長・発達にとってどのような利点があるのか、私は本を読んで調べたことがなく、わからない。子どもたちは、幼稚園ではおそらく「教育」である遊びを通じて何かを得るであろうし、必ずしも、それによって何かが失われるということもないのかもしれない。
しかし、また、子どもたちだけで勝手に、つまり自由に遊ぶことによって、彼/彼女らが何か問題を抱えた、まずい大人になり、結果的にまずい社会が出来上がるという風にも考えられない。(年の違う)子どもたちだけが集まって遊ぶことを通じて、子どもたちは、遊びに加えてもらい、一緒に遊び、仲間同士のコミュニケーションのしかた、他人との「付き合いかた」のようなもの、あるいはもっと単純なこと、たとえば裸で表を歩き回らないとか、人前でウンチをしてはならないとかいうごく基礎的な社会的ルールのようなものをなんとなく身につけるのではなかろうか。これも遊びの「教育」的機能なのかもしれないが、一般的には「社会化」と呼ばれている機能であろう。
大人が道具・手段として遊びを用いて行う意識的な「教育」とは異なる。昔のように野山を含めどこにでも遊び場があり子どもたちがいつでも自由に遊び回れるわけではないが、それでも公園や児童館で遊ぶことはできる。安全のために見守ってくれる大人がそばにいるほうがいいかもしれないが、「教育」をする人はいなくても、子どもたちは遊ぶことができるし、大人による「教育的遊び」ではないただの遊びでも、それなりに子どもは成長し、おとなになるための基礎力を身につけることはできると私は思う。
私ははっきりとした根拠に基づいて、自由、きままに遊ぶことのほうがよいと主張しようとしているわけではないが、また、ヴィゴツキーにしたがってだれか指導し教育する大人がいたほうが良いとも思わない。子どもたちだけで遊んでも楽しく遊べるし、そのことに特に問題は見いだせないと言いたいだけである。「競争しようか」と誘った母親に「教育」の視点があったとは思わない。夏休みの算数の宿題を教えるのにてこずっていたから勉強のほうでも「教育」してくれたとは思わないが、遊びにおいても、時々、バドミントンをしたり、キャッチボールをしたり、トランプをしたりして一緒に遊んでくれただけであった。
私は子ども時代の自分を振り返ると、遊びが、つまり自由にしていることが何よりも楽しく、好きであった。親に言いつけられた手伝いを拒んだことはなかったが、小学校時代を通じて、自分から進んで家で勉強をしたことはなかった。はっきり覚えているが、中学2年の2学期からようやく、「中間」と「期末」の定期試験のための勉強をやるようになった。廊下に成績の順位が掲示され、勉強の「競争」が導入されたためであった。だが、いずれは、皆、学校の定期試験のためであれ、高校受験のためであれ、必ずしも面白いと思わなくても勉強をやらざるを得なくなる。そして、大学に進学にするにせよ、高校で勉強を終えて就職するにせよ、いずれは皆、好んでではなくても、働かざるを得ない。子どもは、就学前、あるいは就学後も、遊べるときには自由に遊んだらよいのではないかと思うのである。
従来、子ども、特に幼児の遊びはすなわち、ごっこであると考えられてきており、他の種類の遊びについては描画など一部の活動を除いてほとんど研究されていない。しかし、お母さんごっこのような表象性・想像性を特徴とする遊びや鬼ごっこのようなルールのある遊びや、しりとりなどの交流遊びのような社会性を特徴とする遊びのほかに、水遊びや泥遊びあるいは竹馬など身体性を主たる特性とする遊び、相撲やじゃれあいのような社会性と身体性が合わさった肉体接触を特徴とする遊び、さらに、独楽回し、ゴム跳びなど身体技能追求的な遊びや、紙飛行機作りのような製作型の遊びなど遊びは多様だとする。
加用はこのような「①起源を別にする異種類の遊び活動が、②発達のある時点で相互に交じり合って交差し、同居しあい、未分化性を示しつつ、豊かに展開し、③それがやがてはより高度な形での活動分化へと進んでいく」という、「交差分化説」を唱えている。かれは、具体的に、ごっこ遊びとルール遊びの両面性をもった遊びの研究事例を示しながら、三歳児はまだごっこ段階であり、4歳、5歳にとなるにつれてルール遊びへと移行してゆくと見るべきでなく、3歳ぐらいではごっことルール遊びは同居しやすいが、4歳、5歳となるにつれて両者が分かれてくる、と言う。彼のこうした見方は「両方の遊びをともに保障しようとする」実践的関心と関係があると思われる。
「遊びにおける感情の耕し」『発達』122号、<特集:保育のなかの遊び>では、次のように書いている。
保育園で、おもちゃの聴診器をぶら下げて座っている男の子(4歳2ヶ月)に「あなたは何屋さんですか?」と聞くと「お医者さん」と言う。そこで筆者は「でもあなたはよっちゃんでしょ?」と言った。その子はよほど驚いたらしく、---どんぐりまなこで筆者をしばらく見つめていたが、何も言い返せず、そのまま黙った下を向いてしまったという。こうした例などから、「認知能力的にはうそっこの意識〔ホイジンハは「ただの遊び」に過ぎない、あるいは「---本物でない」ということについての「劣等感の意識」、「あほらしさ」の意識と言っていたが〕をもつことができる4歳児であっても、ごっこに没頭中はその意識は鮮明ではなくなっており、半分以上本気であるように思わされた」と言っている。幼児においては現実と非現実ないし遊びとの区別ははっきりしていないという点については木下孝司/加用文男/加藤義信編著『子どもの心的世界のゆらぎと発達』(ミネルヴァ書房)第3章でも述べられている。
私が上で「子どもは無制限に遊ぶ」という小見出しをつけ、ホイジンハの遊びについて反論しつつ述べていることは、全くの私見に過ぎないが、おそらく加用は私の見方を支持してくれるのではないかと思う。機関車である自分にキスする父親に抗議する子どもは「うそっこの意識」をうすうす感じていると思う。しかし、やはり、かれにとっては、機関車ごっこの遊びの世界こそが、より真実で大切な現実世界と感じられており、彼が機関車であることを邪魔する父親は、たとえば、中世ヨーロッパの農民に対して、お前の信じているキリスト教の教えは間違いだと告げる不信心者、あるいは無神論者のような存在に準えることができると思う。この人物は、科学的・客観的見方だけが正しく、唯一普遍妥当性を持つのだと信じ込んで、他者の世界に踏み込み他者の世界を傷つける。研究者として「でもあなたはよっちゃんでしょ?」と問い返す限りの加用もまたそうだ。だが、ホイジンハはこどもの意識を、劣等感を伴った「あほらしい」、「遊びでしかない」ものと見下しているが、加用は、「うそっ子意識」あるいは現実の意識と遊びの意識の未分化状態を脱却されるべき劣等なものと見なさず、「感情の耕し経験の宝庫」として大切にしたいと、全く異なる姿勢を示す。
仲間と一緒に遊んでいるこどもが自分ひとりではできなかったことができるようになることがある。ヴィゴツキーは遊びや学習のこうした点を重視している(前掲、柴田の解説)。だが加用はごっこ遊びなどによって「人間的感情の多様性」が「耕される」ことのなかに、「結果的に「できた」という経験がもたらす自信の獲得の側面に勝るとも劣らない意義」を見出している。
このように、加用は、遊びには感情を耕す側面があるというが、しかし、そう主張したからといって、これを目指して保育すべきであるなどという保育論を展開しようとしているわけでない、とも言う。彼は、「①遊びのなかで子どもたちが得ているものは多様であり、すべてを「学び」に解消できるものではないということ(あそびの意義を「学び」に限定して考えることは保育あるいは幼児教育全般を就学前教育にしてしまう危険性がある、)②乳幼児期に感情の耕しという性格を持っていたものが学童期になっていくにつれて美的感覚の耕しという側面へと移行していくという仮説の提示を行っているにすぎない」、という。私は、①について全く正しいと思うとともに、この②についても、スポーツばかりが子どもの世界を支配してしまうのでなく、多様な活動に開かれていることのほうが好ましいという、単純な理由で賛成である。
加用は、この文の結論で、遊び論そのものにおいて「できる・できない」論から脱却する新しい視点が求められている、という。加用が、ヴィゴツキーの遊び論から脱却することが必要だとしていることは確かである。
遊びとは何か。私は、感情に振り回されることのほうが多い発達段階を脱け出た人間、主として成人について考えている。遊びの特徴は仕事と対比することによってもっともよく明らかになるように思われる。遊びには仕事とははっきりと違うところがある。それはカイヨワが言うように、
遊びは、することもしないことも、始めることもやめることも自由にできる活動であるという点である。
仕事には、楽しい仕事、夢中になることのできる仕事もあるが、必ず行う必要があり、行わざるを得ないという面がある。仕事には、雇用契約に基づく義務や子どもの養育に対する責務が結びついている。時々やりたくないことがあってもやらなければならないという面がある。それをやらなければあとで生活に響いてくる。あるいは法的な責任を問われることもある。そして「好き」なだけでは仕事は務まらない。仕事が要求するレベルを満たさなければならない。
遊びはそうではない。遊びたいときに遊べばよい。遊びたくなければ遊ばなければよい。下手でも、弱くても構わない。「横好き」でいい。途中でも飽きたらやめればよい。もちろん、遊びも他の人とともに行う遊びであるときやチームで行う遊びであるときには、飽きた、嫌になったからと、いつでも勝手に、止めることはすべきではない。そうすることはできるが、次に一緒に遊んでもらいにくくなるだろう。(言わずもがなのことだが。)しかし、家庭の事情や勤め先の仕事との関係で、遊びを途中で抜けること、あるいは遊びの予定に遅刻することは許されるが、その逆はきわめて難しいはずである。風邪を引いて身体の具合が悪いとなれば、遊びは中止しようと相手のほうから言い出すであろうが、仕事の場合には、風邪ぐらいでなんだということになる。
一般に、遊びと仕事は価値が異なると考えられている。つまり、遊びは一般に、他の事情によってしなくてもよいもの、中止して構わないもの、重要ではないものであり、他方、仕事はさまざまな事情があっても予定通りに、優先的に行わなければならない、重要事だと見なされている。理由は、遊びは自分(の快楽)だけにかかわることであるのに対して、仕事は義務や責務をともなっている。つまり、ほかの人との関係のなかで行われることであり、他者の幸福にかかわる問題だからであろう。家事・育児は一人(子ども)または二人(子どもと互いのパートナー)の人との関係であるが、職業上の仕事となれば何十人、何百人、間接的な関係も考えればもっと多くの人との関係のなかで行われる。自分だけの都合で予定を変えることが難しい。そして仕事は、やはり関係者が多いということのゆえに、遂行、完成の時期がいつでもよいものなどまずないだろう。遅れれば「みんなが困るから」、決まった時刻に間に合うように仕事は済ませなければならない。仕事をするとはそれに関係するすべての人の要求に応えるということであり、そのなかでも、予定の日時に、一定時間内にそうするということが、良い仕事を行ったかどうかの評価に際して第一の判定基準である。
しかし、人は生きていく必要がある。障害や病気のために働くことができない人と金持ちの家に生まれた特別に運のいい人以外は、大人になれば、職業に就き何らかの仕事をしなければならない。また、未成年の子どもや年老いた親を扶養するという、自発性の程度には違いがあっても全く免れるということは不可能な、人間としての義務を果たさなければならない。好きで仕事を行う人もあるが、たいていの人の場合、仕事はそれら必要と義務に基づく活動である。「必要」と「義務」についての考え方、そして各自の「資本」により「仕事」に充当しなければならない時間には幅があるが、その仕事の時間と、睡眠と休息、食事そして入浴など、そのほかの必要生活時間を合わせて、1日24時間から差し引いた残りが、遊びの時間である。これも言わずもがなの、平明、単純な事実である。だが、人生全体を通して、遊びの時間をどのように確保するかということになると、各人のやむを得ない事情ばかりでなく、「世間の目」を気にしたり、「常識」に従うという、やめることがさほど難しくない日ごろの習慣をずるずる続けたりする“好み”ないし“自由な”選択によって、各人が確保する遊びの時間には大きな違いが生じてくる。かなりの経済的、文化的資本を有しているにもかかわらず(と私は思うのだが)、遊びにではなく仕事に極めて多くの力と時間を投入するひともある。
ホイジンハもカイヨワも遊びとは虚構の世界に移ること、現実からの脱出あるいはその試みだと考えた。私は遊びとは、現実世界において仕事と対等な地位を有する、別の種類の積極的活動であるが、仕事から意識的に脱出することによって始めて可能になる活動であると思う。私はエリアスとともに、遊びが、コミュニケーション不可能な、医者によって解釈されなければならない「非現実」の行為ではなく、他者に理解可能な行為である限り、仕事/労働に劣らず現実的だと考える。遊びは「現実からの脱出」ではなく、「仕事」からの脱出である。しかも、「偶然の僥倖」などを待っていては脱出が極めて困難な、仕事が人間の使命だという近代以降の世界を支配しているエートスの強い磁場に逆らって、意識的に企てなければ実現することの難しい脱出であると思う。
上手な息抜きをしたり、歌や音楽を聞きながらやったりするなど、辛い単調な仕事をやりきるための工夫は当然必要であろうが、仕事をしながら遊ぶこと、遊びながら仕事をすることは、そのどちらもうまく行かなくなる可能性がある。「育児」の最中にパチンコをする主婦/主夫、アルコールでイリンクスを楽しみながら店を経営する人を考えてみればわかるだろう。仕事においても遊びにおいても、人は苦を減らし快を実現しようとするのだが、長期的にその快楽計算を行う勘考・熟慮が不可欠である。遊びとは、一週間、一年間、一生における現実の活動時間の意識的で積極的な配分によって可能となる活動であり、自己のための快楽を追求し、主に他者のためである「慣例化」に従わない活動のことである。
ホイジンハ、幸田露伴、カイヨワ、チクセントミハイ、西村について詳しく見、ヴィゴツキー、加用の遊び論にも触れながら、ところどころで、思いつくままに、私の考えを述べた。
ホイジンハによれば、かつては遊びの気分がすべての人間活動を支配しており、すべての文化は遊びの中から生まれてきたのだが、現代社会においては遊びは文化との関係を失ってしまい、遊びとのつながりを残しているスポーツにおいても、遊びの精神は失われてしまったという。そして現代社会において残っている遊びは、子どもの「ごっこ遊び」の場合に典型的に見られるように、現実の世界において営まれる仕事を一時的に中断し、現実からいわば下方に脱落して、劣等感をもって、仮想の世界の中でだけ、行われる活動だとされ、そうでない場合には、宗教的儀礼と結びついて、現実を上方へと超越しつつ、遊びではない社会的文化的な機能に移行・変化しなければならないと考えられていた。
幸田露伴はについては、彼の遊びについての「考え方」というよりは、彼の人生において遊びが占めた位置・役割について明らかにした。彼は30代後半までは普通の人のように仕事を主とし遊びを従と考えていた。つまり、小説家という仕事から受ける強いストレスを解消することが「趣味娯楽」つまり遊びの役割であり、遊びは仕事を立派に行うための手段であるべきだと考えていた。しかし、後の露伴においては、趣味娯楽が彼の生の中心的位置を占めるようになる。彼は生活の必要や責任にかかわること(子供の世話、病人の介護)からは逃げなかったが、それを除けば、自分の好み、趣味を彼の全活動の出発点に据えた。
彼はきわめて多くのことに興味、関心を持ち熱心に行った。彼は自分の好奇心に従って、井戸の修理やちょっとした大工仕事など日常生活に関わること、釣りや将棋など趣味・娯楽の心身の活動とそれに関連した「論弁思索」を行い、それをまとめて著作にするとともに和漢文学に関する超一級ともいうべき学問的な仕事も行った。だが、好きでないこと、自分が面白いと思わなかったことは、社会的あるいは職業的な地位や名声にかかわることであっても、積極的に求めようとしなかったばかりか放棄さえした。
しかし、それが可能だったのは彼の博学と文才による。多くの人が彼の書く文章を読みたいと思い、露伴が自分の趣味であるいはその延長上で行った著作が、贅沢を求めなかった彼の生活の確保を可能にしてくれたからである。かれはその後半生においては、職業的な「責任や圧迫を感じることなく」、自由に「自己の愉快と真の生命を見いだす」ことのできる「趣味」に生きるという、きわめて幸福な生を生きることができた。
カイヨワでは、遊びは、実力で競争したい、偶然に任せたい、変身したい・自分以外の何かを模倣したい、眩暈・混乱状態に浸りたいという4種類の根源的衝動・欲求が、一方で政治や経済や宗教など人間社会の他の領域の活動のなかに様々な度合いで現れてそれらの活動を推進するとともに、他方でそれら社会的現実の「理想化」や「無化」あるいは「否定」の欲求をともなって、あるいは現実の「補償」、「埋め合わせ」などの機能を持つものとして、現実の世界に対抗的に出現したものである。それぞれの社会における遊び以外の諸領域において優越する原理が遊びの領域においても優越するとは限らず、基本的に遊びが現実からの脱出要求に支えられているがゆえに、むしろ、反対の関係にあることのほうが多い。こうして、遊びは、工業国における労働者の“疎外された”労働の「代償」となり、植民地化された国々で外から持ち込まれた文明社会の生き方を実践することができないでいる民衆を「元の世界につなぎとめ」、「かろうじて生き延びる」ことを可能にするものである。
私は、仕事とは、主体が意識的考量に基づき、他者と対向関係に立ち、事物・客体を支配し我が物としようとする企てだと言い切れるとは思わない。多くの人にとって、仕事は生きていく必要から、やむを得ず行うものであるが、行なおうとすれば努力や決断など、主体性が必要である。だが、また、働きたくないという気分が、働き方や働く時間の長さを左右するだろう。どの程度の贅沢あるいは人並みの生活を送りたいと考えるかで仕事に対する主体的姿勢が変わるが、生活レベルに対する欲求は気分によってきまるとも言える。しかし、企てや主体性が仕事の重要な一面であることは確かだと思う。
西村によれば、遊びは主体的企てではなく、遊ぶ二つの項のどちらが「イニシャティブ」を取るといえない、主体・客体が区別できない様態・関係であるとされる。遊びが解放だというのは、人がこの主客未分の状態に移行あるいは退行することによって、「イニシャティブ」をとる「きつさ」を免れることができる点にある。つまり、主体と対象(客体)がはっきりと分かれた「主客の対向関係」に入り、主体的に考え、行動すること、そして意識的に他のものとの関係を持つこと、つまり主体的企てあるいは自発性を課せられることの「きつさ」を免れるというところにある、と言う。
西村は、「イニシャチブ」に基づいて行動するよう求められることは「負担」だと言う。たしかに、誰もが同じようにうまく、自分に関することをすべて自分で考え、自分で決めることができるということはないだろう。そして「自分に関わること」であっても、外部の抵抗しがたい原因によって引き起こされることもある。いやその方が多いかもしれない。とすれば、自分に関わることのすべてを「自己責任」と見なされ、自分だけで、主体的に引き受け、解決しろといわれるのではかなわない。しかし、こうしたことは、友愛/連帯やセイフティネット構築の問題と考えることもでき、「主体性」あるいは「主客の関係」を好ましくないものと考えることには直結しないだろう。
仕事は、私も含めほとんどの人にとっては、生活の必要のために行わなければならないもので、人生の大きな部分をそれに充てざるを得ない。多くの仕事は、他者の意志に従い、他者との約束に拘束されて行わなければならない。ある程度の自由が可能で同時に楽しみが含まれているような仕事は、誰もが思い通りに就くことができるわけではない、限られた分野にしか存在しない。これに対して遊びは、自由に、自分の意思だけで、楽しみのために行うことのできる活動である。一人ではできず、他の人と一緒に行うことが必要な遊びもあるが、自分だけで遊ぶこともできる。遊びは、他者の価値判断に影響されずに、ただ自分の好みにしたがってだけ選べばよい、そのような特別な活動である。
ヴィゴツキーは遊びを学び/教育としてみる。つまり、彼によれば、子どもの遊びは、こどもが大人になって仕事に就き、仕事に打ち込むことができるようになるための準備活動なのである。とくに、幼稚園などで子どもに与えられる遊びはそのような機能を伴っているであろう。そして、私は、それほど明確な意図の下に考えられた遊びではなくても、人間は、子どものときに、知らないうちに、遊びを通じて、遊びの快楽にいわば釣られて、単なる動物的生から脱け出て、社会化されるのだろうと思う。幼児は遊びながら文字を覚えたり、数を数えたり、あるいは自然や社会についての知識を獲得する。就学前の子どもは鬼ごっこや石蹴りやトランプの七並べなどをして、ルールに従うことを学ぶ。そして学童期には、年齢や遊びの種類により異なるであろうが、遊びの中で、さらに、我慢すること、努力すること、約束を守ること、等々の重要性を理解し、目的合理的な行動をとり、禁欲、忍耐、等々、エリアス的に言えば内的に自己を制御する方法を身に着け、大人になると考えることができる。つまり、子どもは「遊びの詭計」List der Spielenとでもいうべきものにより、人間社会に引き入れられ、大人になり、職業労働に就く。こうして、人間はホモ・ファーベルかつ社会的動物として、人生の大半を生きるのだと思われる。
私は、戦後の平和な日本社会に生まれたという幸運に恵まれたせいもあるが、社会的動物として、ホモ・ファーベルとして生きてきたがゆえに、さほど貧困に苦しむことなく、比較的安全で、物質的にかなり快適な生を生きてくることができた。だが私は「慣例化」による外的な圧力を受けつつ自制を行う生、仕事の義務と責任、あるいは社会的存在であることから課されているように思われる責任を果たそうと努力しながら生きることは必ずしも楽なことではないとはじめから感じていたが、窮屈で不自由だという感じが次第に強まった。
古希間近の現在の私は、エピクーロスが言っているように、私の生の最後に待っている、単なる原子・分子に戻っていく過程がなめらかにいくようにする準備としても、この遊びによって引き入れられたホモ・ファーベルの社会から、再びできるだけ自然な生の世界に戻りたいと考える。私は幼児期のことはほとんど覚えていない。しかし、私はその最初の、知らないうちに辿らされた社会化の過程を、今度は、意識的に、逆に辿ろうと思う。意識的に、脱労働・脱社会であるような遊びを行いつつ、自然に帰ろうと思う。(2015年4月完。)
そして、私は、釣りこそがそのような脱労働と脱社会を可能にし、幸福な人生の終わりを迎えることを可能にする遊びだということを、次の章で書こうと思う。