




写真(ほぼ全体)
はラファエロの『アテネの学堂 The School of Athens』(1509-10、バチカン美術館所蔵)。幅7.7m、高さ5mの大作(下半分)。古代ギリシャの哲学者たちが、ラファエロと同時代の人物をモデルにして描かれているという。Wikipediaによる。
部分、左はエピクーロス(モデルは不明)、次はソークラテース(横向き)、右の中央の二人のうち、上(天上)を指しているのはイデア論を説いたプラトーンでダビンチがモデル、隣がアリストテレース(モデルは不明)だと言われる。

 カント
カント


ゴヤ「裸のマハ」

人名の表記について(メモ)
しばらく前までは、エピクーロスはエピクロス、そして、ソークラテースはソクラテス、などと表記されるのが一般的であったが、私は、確認できる限り、『キケロー選集』(岩波書店、1999~)、『セネカ哲学全集』(岩波書店、2005~)などの表記方法に従って、言語学により、古典時代のアッティカ地方で発音されていたことが分かっている発音により近いと思われる長音を入れて表記する。ただし、引用文中の人名の表記は原文どおりにしてある。
ソークラテース、キケロー、アリストテレース、アルキビアデース、デーモクリトス、プラトーン、ディオゲネース、ルクレーティウス、アントーニウス、オクターウィアーヌス、ヒッポクラテース、ピュータゴラースなど。
第一節 古代ギリシアにおける幸福論とエピクーロスの快楽主義哲学
エピクーロスの快楽主義
行動はすべて快楽の実現を目的に行われる 人は最大の快楽を実現するように行動すべきである
動的な快楽と静的な快楽
肉体的快楽と精神的快楽
肉体的快楽と精神的快楽の大きさのちがい
肉体的な苦痛の大きさについて
肉体的な快楽の限度
肉体的な快の種類、必要不可欠な快楽とそうでない快楽
快適な生活を実現する手段としての徳
魂における快と苦
カントにおける幸福と道徳
魂における快と苦の大きさについて
死に対する恐れとその解消
理論的な死と切迫した現実の死
「死は何ものでもない」とエピクーロスは言う
ルクレーティウスへの反論
(追加)幸田露伴の「快楽論」
存在しないことと死ぬこととは異なる
現実に切迫しつつある死の恐ろしさ
魂の快苦の根は肉体の快苦にある
精神の平静・平安が最大の快
第二節 A.ロング『ヘレニズム哲学』第二章エピクーロスの快楽論に対する批判とその検討
「エピクーロスは苦と快の中間状態に対する人々の「無頓着」を見落とした」?
エピクーロスは「諸原子の適切な配置=健康は喜びを与えるという想定に立っている」?
エピクーロスは快楽を「諸原子の適切な配置=健康」に関係づけて説明してはいない
ロングはプラトーンの説を援用するが
「大多数の人が、覚醒時の大半、苦痛も快楽も感じていない」ことの吟味
気候の快苦の感じ方
長期間の身体的苦痛や精神的苦しみの解消は積極的な快を与える
ロングは精神的な苦については考えていない
苦の欠如あるいは苦からの解放は「快でも苦でもない中間状態」ではなく、快である
「想念」と精神的な苦
現代社会はもろもろの苦で満ちている
快苦に関する感覚と感情の区別
「快・苦の判断」についてのカントの説明
エピクーロスにおける「感覚」と「感情」の区別
エピクーロスの「感情」とカントの「快不快の感情」はほぼ一致する
エピクーロスの快楽説に関するロングの解釈と批判が不適切であることのまとめ
感情による快苦の判断と理性による幸福についての総合判断
幸福と生の全体構想について
人により異なる全体構想
エピクーロスの教説は不道徳か、そうでないか
ロングはエピクーロスが「自己中心的」だと言う
利己主義の意味の検討
エピクーロスの「庭園」における教説の倫理性
私は、逆に、彼の倫理学以外の部門にはほとんどまったく触れることなく彼の快楽主義の倫理学説のみを扱った。
彼の倫理学
説は、歴史的背景についての考慮は必要であるにせよ、(感覚で知りうる)経験的な知を参照するだけで充分に理解可能であり、特別の背景理論ないしは形而上
学、原子論に基づく自然学や知識論にたよる必要を感じなかったからである。
もし倫理学説の難点が原子論にさかのぼることで解消されるというようなことが
あったとしても、その原子論そのものの真理性、正当性を改めて問題にすることができる。エピクーロス自身、経験的事実、感覚に現れる現象が重要であり、そ
れを説明するための「理論」にこだわることを退けている。天体の動きを地動説的に説明するか、天動説的に説明するか、あるいは、天体の光をそれ自身が発し
ているとするか他の天体の光を受けて光っているとするか等々、様々な説明が可能であるが、感覚に現れている事実に幾通りもの説明が可能であるときに、ただ
一通りの説明を押し付けようとすることは愚かだと説いている。
私は、古代哲学を専門的に研究したことは全くなく、ごく僅かな典拠はすべて邦訳で読んだにすぎない。2千年以上昔に書かれたものであるにもかかわらず、プ ラトーンやアリストテレースの場合には浩瀚な著作が残されており、古代ギリシア哲学に関心があるというだけでは読みきれないほど存在する。釣り人の間では 両手を広げた長さを単位とする「ヒロ」が使われるが、書架に並んだ何十巻というプラトンやアリストテレスの著作は「半ヒロ」近くもあり、私はどちらについ ても半分、いや三分の一も読んでいない。古代の他の哲学者たちも多くの著作をおこなったことが伝えられているが、ほとんどすべて散逸したのである。
2世紀の終わりごろから3世紀前半ごろあるいはその後に書かれたと推定されている『ギリシア哲学者列伝』の著者ディオゲネス・ラエルティオスによれば、エ
ピクーロスはとくに「たいへんな多作家で、書物の数ではすべての人を凌駕していた。というのは、彼の書物の巻数は約300にも上っているからである。しか
もそのなかには、他人の書物からの引用は1つもなく、その全部がエピクーロス自身の言葉なのである」。
彼の著作がプラトーンやアリストテレースのように保
存されて現在読めるようになっていれば、私はたぶん、このエッセーを書いていなかっただろう。主要な著作に目を通さずにその哲学者の思想を論ずることは明
らかに無謀なことだからである。幸いエピクーロスが書いたものの一部、ごく一部がこの『ギリシア哲学者列伝』の第10巻の中に収められている。そしてそれ
以外には、200年ほど後のローマ時代の思想家の著作に、彼の思想を論じたものが2,3あるだけである。こうした特殊な事情に助けられて、漁村で釣りをし
て暮らしている西洋古代哲学の門外漢が僭越にも「エピクーロスの思想」について語ることとなった。
今から2千5百年ほど昔の古代ギリシアでは、人々が抽象的で理論的な思索を進めるなかで、もともとは広く知識を求めるというくらいの意味で使われていた
フィロソフィア(動詞形ではフィロソフェイン)という語を、「世界・人生の根本原理を取り扱う学問」、日本語で「哲学」と訳している語の意味で用いるよう
になった。そして、現代世界の思想や学問のなかで重要な要素をなす西洋の思想・学問の根幹部ともいうべきものがこの紀元前6世紀から3世紀の古代ギリシア
で生まれた。
最初は自然に関する思索を行なっていたギリシアの賢人たちは、やがて人間の生き方についても哲学するようになった。
A362「ソークラテース全身像」大英博物館所蔵,amebaブログ「Gee」
「きょうの石膏像」http://ameblo.jp/sekkouya/から転載

「哲学者」ソークラテース
はエートス(=人柄と習俗)に関する学問、エーティカ=倫理学の創始者とも呼ばれる。彼はただ生きるのでなく、よく生きること、正しく生きることが人生の
目的であり、有徳な、よき魂を形成することが幸福だと考えた。
人間の一つ一つの行為はそれだけで完結しているのではなく、行為AはBのためになされ,BはCのために,CはDのために----なされる。この行為の連鎖
の最後に来る項を究極目的と呼ぶが、古代ギリシアの哲学者たちは、無数の行為の連鎖から成り立つ人生の究極目的は(それがあるとすれば)何であるか、何で
あるべきかということを思索した。
人は誰でも幸福になることを願っている。哲学者たちは幸福が究極目的であるという点では一致したが、幸福の中身、何が達成されたら幸福といえるのかについ て、さまざまに異なる考え方を提出した。ソークラテース、プラトーン、アリストテレースは、ポリスと呼ばれる都市国家=共同体を基盤に思索を行い、ポリス 共同体のよき市民であることと関係付けながら、人生の目的、幸福な生が何であるかを論じた。
人間は、他人に支配されず、自分の運命を自分で決定できるとき、幸福であるだろう。共同体についても、その内部に支配被支配の関係、ひどい差別や不平等・ 格差がなければ、同じことが言えるだろう。ヘーゲルにならって大まかに言えば、アテーナイ(アテネ)など、アリストテレースの時代までの古代ギリシアのポ リスの人々は、ポリスのあり方を自ら決め、公的な活動に加わり、ポリスの市民=ポリテースとして生きることに幸福を見出した。
ところが、アリストテレースが家庭教師を務めた、ギリシアの隣国マケドニアの王、アレクサンドロス(英語読みでアレキサンダー)は、ギリシアの諸ポリスを 征服し、さらにインド、中国に及ぶ大帝国を築いた。ヘーゲルに依拠すれば、アレクサンドロスによってポリスの政治的独立を奪われた後、ギリシア人たちは、 共同体の絆から切り離され(解き放たれ)た、ばらばらの私的個人として、あるいは世界(コスモス)の市民=コスモポリテース(英語で cosmopolitan)として生きることになった。彼らは、公的=共同体的な活動の中にではなく、個人の私生活の中に幸福を求めるか、あるいは、別な 見方をすれば、狭い民族的発想の枠組みを越えた「万人」に妥当する生き方を求めるほかなかった。1)
この時期に登場した哲学の諸学派は、プラトーン、アリストテレースの哲学とは異なって、個人の幸福をポリスとの関係において見いだすのではなく、自立的個
人の幸福と安心立命の境地を求めた。とりわけストア派とエピクーロス派がよく知られている。
ゼーノーン(前335-263ごろ)を創始者とするストア派の
哲学は「禁欲主義」と呼ばれる。ストイックStoicという語はもともとは「ストア学派の人」を意味したが、現代では欲望に振り回されず、我慢強いひとを
指す日常語として用いられている。ストア派の哲学者は「自然にしたがって生きる」ことを説いた。すべての存在は自己自身を保存することに向かう根源的な衝
動(ホルメー)を持っている。植物や動物は栄養物に向かう衝動を持つ。これが動植物の「自然・本性に従う」生き方である。人間は理性を有する。人間の場合
には、衝動をコントロールしつつ、「理性・ロゴスに従って生きること」が「自然に従って生きる」ことである。DL7巻,85-86.2)
様々な欲望・情熱(パトス)に左右されない不動の境地(アパテイア)に達し、有徳な人格を形成して、正しく生きることが人間の究極目的であり幸福だとスト
ア派は説いた。DL7巻,117.
一方、エピクーロス(前341-270)が唱えた哲学説は「快楽主義」と呼ばれる。ギリシア語で快楽はヘドネーであり、哲学説としての快楽主義は英語で hedonismという。だが、もと「エピクーロス派の人々」を意味したエピキュリアンepicureanという現代語は、酒色におぼれる「放蕩もの」を 意味している。大文字でEpicureanismなら学説としてのエピクーロス主義・快楽主義だが、小文字でepicureanismというときには享楽 主義、食道楽を指す。
エピクーロスによれば、快楽を得ることこそが人生最大の目的、最高善であり、人は快楽を得ることだけを目指して生きてよいだけでなく、快楽を最大にするよ うに生きるべきである。だが、エピクーロスは「放蕩もの」が求めるような快(つまり、飲み食いやセックスの快楽)の追求を勧めたのでは決してない。エピ クーロスは身体的な苦痛がなく(アポニアー)、精神的に動揺のない状態(アタラクシアー)が最大の快なのだと説き、実質的には、ストア派のアパテイアとよ く似た境地を、幸福と考えたのである。3)
ストア哲学においては、宇宙・自然は、キリスト教的な超越的な神によって支配・統治されているのではなく、それ自体、ロゴス(理性・論理・法則)である神 の表れとされる。あらゆる事象は必然的で、自然は運命とも呼ばれるが、同時に、それは神慮、摂理でもあった。DL7,134-139
エピクーロスは、宇宙・万有を原子の離合集散で説明する徹底的唯物論者で、死後、魂は散り散りに分散するとし、霊魂不滅を否定する(DL,10,65)。 また、彼はいかなる種類の摂理も運命も完全に否定した(同、76,77,123,124)。これは、全能の唯一神を信じ霊魂の不滅を説くキリスト教が決し て容認することのできない思想であり、エピクーロス主義は、後にヨーロッパを支配したキリスト教会により嫌われ排斥された。
他方、M.フーコーは、ヘレニズム期の、また帝政ローマ初期の哲学の特徴に関して、普遍主義的であるという点については肯定するが、「個人主義的」とする ことは不正確(「個人主義」に三つのタイプがあるという)であり、「自己の陶冶」と捉えるべきだと言う。また、彼は、ヘレニズム期以降の哲学思想の変化の 背景としてのポリスの「自立性の喪失」という見方を最近の歴史研究に依拠して否定している。ヘレニズム期以降の大君主制は地方権力〔都市国家〕を廃止した り押さえつけたり、さらに完全に再編しようとしたりするよりも、はるかにその権力に依存し、正規の租税の徴収や---軍用品の調達のために、その権力を仲 介・中継として活用しようとした、という。
フーコーは、この時期のテキスト(エピクーロス派とストア派、そしてセネカ、プルタルコスなど)の読者である地方権力の支配階層は古典期ギリシアの支配階 層とは違って、「統治する者であると同時に統治される者として」、権力を「自分がちょうつがい役をつとめている一つの網目状態の中で行使するのであり」、 特定の政策を自分の身分や地位に依拠せず、また専門技術にも依拠せず、判断力と理性に基づいて個別的に選択することが必要で、そのために自己の倫理的陶冶 が必要だったと述べている。<性の歴史>Ⅲ『自己への配慮』(田村俶訳、新潮社、1987)p113、p117-9
18世紀末にベンサムは、快楽と苦痛を原理として法、政治を論じた『道徳と立法の諸原理序説』を書いた。彼はこの主著では、快楽と苦痛の定義を与えていないが、J.R.ディンウィディ『ベンサム』(永井義雄・近藤加代子訳、日本経済評論社、1993)によれば、「ある人がその一瞬に、感じたくないと思うの でなく、感じたいと思った情感すべてを、快楽とわたしは呼ぶ。ある人が感じたいと思わなくて、感じないでおきたいと思う情感すべてを、私は苦痛と呼ぶ」と「かつて書いた」という。
痛み、苦しみ、不快、不安、恐怖、飢えや渇きなどはこの「苦痛」に入るだろう。一方、楽しさ、愉快、陽気、身体的な快感、基本的欲求の充足感、そして安らぎ、落ち着いた感じなどもこの「快楽」に入るだろう。私たちは、積極的に「気持ちがいい」と感じたいと思うが、また単に「痛くない」と「感じたい」だろう。同様に、必ずしも、積極的な楽しみ、快さ、魅力、満腹などではなくても、苦しみ、不快、不安、恐怖、飢えなどが存在しないだけの、単にそれら苦痛の欠如、解消を好ましい、望ましいと感じる。ベンサムにおいては感じたいと思われる情感が快であり、感じたくない情感が苦痛である。ベンサムにおいては苦痛の否定が快楽である。
エピクーロスも快と苦をベンサムと同じように考えている。つまり、エピクーロスの快楽は苦痛の反対の状態ではなく、否定である。つまり、ある状態は苦痛でなければ快楽なのである。中間のどちらでもない状態を認めない。これは同じ時代のほかの哲学者たちから様々な反論を招いたが、現代における、ヘレニズム哲学の専門的研究者・ロングもまた批判するところである。
少し先走りすることになるが、エピクーロスにおいては、飢えや渇きなど身体的苦痛と不安その他の精神的な苦しみをなくすることこそが快楽を実現することなのである。彼は禁欲主義者ではないから、うまい料理を食べて舌鼓を打ったり、好きな音楽を聴いたり、釣りをしたりして楽しい気分になるというような積極的な快楽を否定するわけではないが、心身の苦痛のない状態こそがすでに快楽であり、しかももっとも重要な快楽だと考えているのである。
古代の人々、とくに庶民の生活は現代先進国などと比べればはるかに不安定で衣食住の必要を充足することも決して容易ではなく、さらに死ぬこと(これは現代でも変わらないが)あるいは(当時広く信じられていた)死後の神罰などに対する恐れや不安が人々を支配しており、心身の苦痛をなくすることは決して簡単なことではなかった。
快楽の実現が幸福だというエピクーロスの教説は、快でも苦でもない状態を前提して、快楽をできるだけたくさん、あるいはできるだけ大きな快楽を実現することを説いているのではなく、現実の生活は苦に満ちていることの認識から出発し、もろもろの苦しみを遊興や放蕩によって一時的に逃れようとする代わりに、深遠で難解な学問ではなく誰もが取り組むことが可能な、「思慮」を形成することを中心とする「一生にわたる哲学」を行うことによって、苦からの解放、つまり快楽を実現しようと説いているのである。
私は、エピクーロスの説の検討に際して、ロングの『ヘレニズム哲学』におけるエピクーロスについての説明とエピクーロス哲学に対する批判は大いに参考に し、また、その批判に対する私の意見、反論も述べた。『ヘレニズム哲学』の「訳者あとがき」によると、ロング、Anthony A.Longは1983年以降カリフォルニア大学バークレー校で西洋古典学を教えている研究者で、多くの定評のある著書、論文があるが、とくに、1987 年に刊行された本書『ヘレニズム哲学』と『ヘレニズムの哲学者たち』(共著)は、「この領域における21世紀の研究の必携書とも呼びうる位置を占めてい る」という。
エピクーロスは人生の目的は快楽の実現にあると説いた。ディオゲネス・ラエルティオスによれば、彼はその「証拠として、生き物は生まれるとすぐに快楽に喜びを感ずるが、労苦(苦痛)に対しては、本性的に、そして理屈抜きに反発するのだという事実を上げている」(DL137)。
彼は「メノイケウス宛書簡」では次のように言っている。「われわれは快楽を、至福な生の始めでありまた終わり〔目的〕でもあると言っているのである。というのはわれわれは快楽を、われわれが生まれるとともに持っている第一の善と認めているからであり、そしてこの快楽を出発点にして、すべての選択と忌避を行っているし、また快楽に立ち戻りながら、その感情を基準にして、すべての善を判断しているからである」(DL128~9)。
「しかしながら」、とエピクーロスは続けて次のように言う。「快楽は第一の善であり、われわれに生まれながらにそなわっているのだからといって、そのことのゆえにまた、快楽であればどんなものでも、われわれは選び取りはしないのである。いな、それらの快楽からより多くの不愉快なことが結果としてわれわれに生ずるような場合には、そういった快楽の多くをわれわれは見送ることもあるのである。また、苦痛にしても、それを長い時間耐え忍ぶなら、その結果として、より大きな快楽がわれわれに生ずるような場合には、多くの苦痛の方が快楽よりもまさっているとわれわれはみなすのである。
それゆえ快楽はどれもすべて、われわれの本性に親近なものであるがゆえに、善いものではあるが、だからといってすべての快楽が選び取られるべきものではないのである。それはちょうど、苦痛もまた、そのすべてが悪しきものであるが、しかしすべての苦痛がつねに避けられるべき本性のものであるとは限らないのと同様である。
快楽と苦痛とを相互に測り比べて、そして利益と不利益とに目を向けることによって、これらすべての事柄を判断するのが適切なやりかたである」。DL129~30
こうしてエピクーロスは、人間はすべての行動を快楽の実現のために行っており、快楽を人生の目的にして生きているが、同時に、快楽は選択されなければならず、取捨選択を通じて、最大の快楽を実現するように努める必要があるという。
では、いかなる快楽が最も望ましい、つまり最大の快楽なのか。選択されるべき快楽は何であり、忌避されるべき快楽は何であるのか。快楽にはどのようなものがあるのか。
エピクーロスは、魂における快と身体における快、静的な快と動的な快の区別を行った。そして、飢えや渇きなど身体における苦を無くすることの重要性を強調した。また身体の苦を無くするとともに、恐怖や不安など魂における動揺の苦痛を無くして、魂に平安・平静をもたらす「静的な快楽」を最大で究極的な快楽と説いた。
こうして、欠乏状態が満たされ、あるいは癒される過程で感じられる大きさの変化する快が「動的快」であり、欠乏状態で感じられた苦痛が解消されたあとの満たされ、落ち着いた感じが「静的な快楽」である。
エピクーロスは、水を飲んでいるときに感じる動的で(「喜びや陽気さ」に似た)積極的な快とは区別して、渇きの感覚が消え苦痛がなくなった状態を「静的」快楽と呼ぶ。満ち足りたおちついた感じは「快」であることは確かだが、渇いた咽喉が潤わされるときに感じられる積極的な快とも異なるであろう。
トルクワートゥスは、動的快楽と静的快楽の区別を述べるのに先立って、次のように語っている、「苦痛が除かれると、私たちは解放それ自体とすべての不快要素の不在を喜びます。しかるに、私たちが喜ぶものはすべて快楽であり、それは私たちが嫌がるものがすべて苦痛であるのと同様です。それゆえ、あらゆる苦痛の不在が快楽と名づけられたのは当然のことでした。例えば、食べ物や飲み物によって空腹や喉の渇きが追い払われると、その不快の除去そのものが快楽という帰結をもたらしますが、何事においても、事情は同じで、苦痛の排除は常に快楽の継起をもたらします。ですから、エピクーロスは、苦痛と快楽のあいだに何か中間のものがあるという考えを拒否しました」(キケロー同書第1巻37、38節)。
私にはこの説明は十分に納得のいくものに思われる。しかし、キケローは、ご馳走を食べていて快楽の状態にある者と拷問を受けていて苦痛の状態にある者との間に、喜んでもいないし、また苦しんでもいない多くの人間がいるという事例を引き合いに出して、快楽と無苦痛(苦痛の不在)とは異なると、トルクワートゥスに反論している。
これは反論にはなっていない。拷問とご馳走は苦と快の両極端の例に過ぎない。拷問より弱い無数の苦があり、キケローはこれら比較的弱い(小さい)苦を「無苦痛」とみなしている。しかしこれらが苦であることを認めればこれらの除去は快を生むであろう。ご馳走を食べることが快の例として挙げられているが、そうした感覚を興奮させる強い(大きい)快ではない、精神的な快をキケローは快ではないと考え、実際、読書や詩の暗唱など、現代人なら明らかに楽しみで行なうことだと考える行為を快楽(ヴォルプタス)ではないと言っている(キケロー同書第1巻25節)。そこで、拷問とご馳走の両極の間に、快でも苦でもない広範な状態が存在するということになる。ヴォルプタスについては後の注13)参照。
後の第二節で見るように、ロングは、キケローと同じように、大多数の人が覚醒時に快も苦も感じずにすごしており、快楽が感覚(によって感じられるもの)だとすれば、快と苦の「中間」を認めないエピクーロスの快楽論は「全く意味をなさない」と言い、また、無苦痛を快楽とみなすエピクーロスは「快楽の概念の複雑性を把握できていない」と批判する。私は彼の批判は正しくないと思う。第三節でロングに反論する。
さて、エピクーロスは「われわれが快楽を必要とするのは、快楽が現に手元にないがゆえに苦痛を感じているときであって、苦痛を感じていないときには、われわれはもはや快楽を必要としない---」と言う(DL128)。
この文によると、人が水を飲もうと行動するのは、喉の渇きの苦を解消する必要を感じたときである。
このことは喉の渇きや空腹を解消するための行動の場合にはよく当てはまるように思われるが、すべての行動が苦痛を解消し、快楽を得るために行われるとエピクーロスが述べている点には疑問を感じる人もあるかもしれない。芸術など、何か創造的な活動を行うためには精神の充実が必要だと思われるし、朝、仕事に出かける時のように、苦痛の原因を解消するためではなく、疲れや苦痛を我慢して他の行動を行うことがあるのではないか。これらの疑問について、考えてみよう。
現代人は、原始人のように、喉が渇いたら川の水を飲み、空腹になったら木の実を取って食べるというやりかたで、必要(欠乏)とその充足という単純なサイクルにしたがうことによっては生きていけない。人はふつう社会の複雑に絡み合った分業システムによって支えられた職業/仕事につくことではじめて生きていくことができる。職業生活のなかでは、たいてい、各人の日々の仕事・活動は自分の努力だけで成果を生むものではなく、また短期的に個々の結果を得られるわけでもない。仕事の成果が得られるまでに1年2年かかるケースはざらであり、ときには完成までに10年以上かかるような長期にわたる仕事を行うこともある。
しかし、必要な義務を遂行し、努力を続ければ、たいていの場合には、安定した生活を送ることができる。社会が平和で安定していることが前提になるが、このような職業生活が基本であれば、われわれは長期的な視野に立って、貧困の苦を回避するために日々の行動を送っているということになるだろう。毎日の、ひとつひとつの行動が、具体的なひとつひとつの欠乏や苦から逃れるためのものではないことは確かだが、日々果たされる多数の行動が長年にわたって蓄積、総合され、全体として私の生が苦から免れることを可能にしているのである。
今述べたことはとくに現代人について言えることだが、すでに商工業が発達していた古代ギリシアのポリス社会にもほぼ妥当すると考えていいだろう。
芸術活動は欠乏状態の苦を解消するために行われるものでなく、創造力の充実において行われるのではないか、という当然の疑問について考えてみよう。芸術は、学問のように根気のいる長期にわたる研究によって生み出されるものではなく、天才のなせる業である。芸術家は優れた芸術家であればあるほど、神から啓示を受けたかのように、瞬間的に作品の着想を得るのではないだろうか。この着想を得たときの芸術家の精神状態は、臨月にある女性が赤ん坊を産み落とさずにはいられないのと同様の不安定な状態だと考えることができる。この芸術家は、どうして、自分の頭の中に膨れ上がった構想を吐き出し、精神の安定を得ないでいられようか。かれはたしかに、創造力に満ちてはいるが、同時に彼の中であふれそうになっている創造的な芸術のマグマを押さえつけておくことの苦に駆り立てられて、キャンヴァスにあるいは譜面に向かうのだと、考えることができる。
この説明には多少こじつけのところがある。天才的でない芸術家はどうかと言われると答えに窮する。しかし、芸術活動というものが、あるいは遊びを含めた人間のもろもろの活動が、快楽のため、喜びを得るために行われるということは明白である。エピクーロスは快楽の概念に、強い喜びや高揚感を伴う積極的な快楽ばかりでなく、苦の解消(ないし苦の欠如)をも含めている。そして彼は、(一切の)苦の欠如である、平静な状態を実現することが幸福の実現にとって最も重要なことだと考えている。だが、もちろん、すべての活動が、欲求充足など、欠乏状態の苦の解消のために行なわれるのだとは考えにくい。音楽や読書、ゲームやスポーツなど様々な活動は積極的な快楽を求めて行われる。
エピクーロスは人間はすべて快楽を求めて行動するという。そして、個々の状態は快であるか苦であるかのどちらかであり、苦でなければ快だと考える。「中間」はない。このことを認めるならば、人が芸術活動を行って快楽を実現するならば、彼はその活動を行う前には、非快楽の状態にあったのであり、非快楽は、定義により苦である。したがって、論理的にいえば、すべての快楽を追求する活動は、苦の解消を目指す活動だということになる。
普通の言い方をすれば、どんなことでも、人が何かしたいことがあれば、それをしないで(我慢して)いることは辛い(苦である)。人はしたいことをすることで、それをしないでいる苦の状態から逃れ、満足を得る。
このように考えれば、エピクーロスの快楽についての説は、不自然ではない。キケローの反論に応えてトルクワートゥスが説明していることもこれとほぼ同じである。

他方、キケロー(『トゥスクルム荘対談集』第3巻第41節)によれば、エピクーロスは「もしわたしが---朗読や歌によって感じる快楽を除外---するならば、私は善として理解しうるものを---知らない」と言っている。またディオゲネス・ラエルティオスによればエピクーロスは「もしわたしが、(食べたり飲んだりの)味覚による快楽を遠ざけたり、また性愛による快楽や(美しい)音を聴く快楽、そして(美しい)形を見る快楽を遠ざけたならば何を善いものと考えてよいかわからない」といっている。美しい音(音楽)、美しい形(絵画や彫刻)を鑑賞し楽しむことは、感覚的な、しかし、精神的な快だと考えられる。
またこの文に先立つ箇所で、当時の人々の多くが、神々や天体が人知の及ばないしかたで「怒りや好意」をもって人間の生に介入、干渉してくると恐れており、また人々は死を恐れるとともに、神々や天体が死後においてもいつまでも人々を苦しめると恐れている(DL76~81)。人々は死を「もろもろの災厄のなかでももっとも恐ろしいもの」と考えていると述べられている(同125)。
そしてエピクーロスは「肉体における快楽は、欠乏による苦痛がひとたび取り除かれたなら、もはや増大することはな〔い〕---。他方、精神における快楽の限度は、精神に最大の恐怖をもたらしていたところの、そういった事柄〔死や天空の事
象や神々〕やこれに類する事柄を、〔哲学、自然学を通じて〕よく勘考することによって達成されるのだ」(同144)と言う。こうした言葉から、肉体的快楽と精神的快楽に関するエピクーロスの区別をおおまかには知ることができるだろう。
エピクーロスは哲学や自然学を純粋な学問的な営みとは考えておらず、(プラトーンやアリストテレースのようには)哲学や自然学を行うことを純粋に知的な(その意味で精神的な)快楽とはみなさなかった。しかし、彼は死の床で排尿困難や赤痢の症状に苦しんだが、弟子に対してあてた手紙で「君とこれまでに交わした対話を思い起こすことで、魂における喜びをそれらの苦痛に対抗させている」と書いている。哲学を一緒に行ないながら弟子たちと交わした対話は楽しんでいたのだろうし、それらを想起することもまた楽しいことだったはずだが、これらは「魂における喜び」つまり精神的な快楽であったろう。
たしかに、身体的な快苦は現在存在する身体からだけ生ずる。だが、魂は現在の身体の快苦に付随する苦の感情をもつだけでなく、過去の心身の快苦を想起し、あるいは未来の快苦を予期するときにも、快と苦を感じる。魂は、知的な喜びや不安など魂特有の快苦とともに、身体の快苦を知覚、予期、想起することによって、快苦を感じる。魂は身体よりもずっと広範な事象を快苦の源泉として有する。
だが、精神的な(現在の)快苦が、過去・現在・未来の心身両面にわたる事柄から生まれるにしても、だからといって、現在の出来事からのみ生じる身体の快苦よりも大きいとは必ずしも言えないだろう。
身体に起因する苦痛は身体の苦とみなすのであろう。その痛みや痺れなどの感覚に付随して感じられる精神的な辛い想いやイライラした感じなどは、精神の苦とみなされる。精神的な苦には、それ以外のもろもろの原因による苦も存在する。しかし、大けがを負ったときに感じるような激しい苦痛は身体的な苦痛であり、それに付随して生じる精神的な苦はあってもその身体的な苦に比べてずっと小さいと考えてよいとするならば、この肉体的な苦がその時に精神が抱えているすべての悩みや苦しみ(が合わさったもの)よりも大きいということはありうる。そこで、一般に、精神が過去現在未来にわたるもろもろの「原因」からその快苦を得てくることができるという理由によっては、精神的な快苦の方が肉体的な快苦よりも大きいとは言えないと思われる。ディオゲネス・ラエルティオスの伝えるところは、われわれを納得させない。
肉体の快苦と精神の快苦についてエピクーロス自身が、述べていることを確かめてみる。エピクーロスは『主要教説』のなかで、苦痛について、次のように述べている。「肉体の中では、苦痛は絶え間なく続くことはない。いな、苦痛は、それが極度のものなら、ごく短時間しかそこにはないし、また肉体における快を越えている程度の苦痛は多くの日数の間持続することはない。さらに、長期にわたる病気は、肉体の中に、苦痛よりも快の方を多くもたらす」(DL140)。
ロングは「強い苦痛は短期間で終わり、長期の苦痛は穏やかであると言う彼の主張」は「多くの人が斥ける」だろうと言うが、私はそんなにあっさり片付けるべきではないと思う。
この二つ目以下の文は最初の文を詳しくのべたものだと考えられる。「極度の」苦痛とは、耐えることができないほどの痛みであろう。のちに見るように古代(ギリシア)の人々は、しばしば激しい肉体的暴力に遭遇した。またしばしば飢饉にも見舞われたであろう。彼らは肉体的苦痛に関して、「文明化された」現代
人に比べ、はるかに大きな苦痛を我慢せざるを得ず、実際我慢できたであろう。そこで、「苦痛は、極度のものなら、ごく短時間しかそこにはない」とは、死あるいは失神を引き起こすような苦痛について言われていると考えられる。
また「快を越えている程度の」肉体の苦痛とは日常しばしばおこる、空腹やのどの渇きなどのことか、あるいは、歩くことはできるが走れないとか、重いものが持てないとか、日常生活の妨げになるような怪我による痛みなどのことであろうと推測される。というのは、空腹でなければ人は食べ物を求めないが、その場合はエピクーロスにおいては苦ではなく、快の状態と考えられている。物を食べようとするのは、その空腹が「快を超えている」からである。そして、通常の飲食の欲求を充足させることは難しくないから、「多くの日数の間持続することはない」。また、障害が残るような重傷でなければ、怪我はたいてい短期間に治るであろう。したがって「快を超えている程度の」肉体の苦痛とは、耐えられないような強い痛みあるいは苦しみではないが、しかし、とにかく苦痛であり、それを解消することが必要だと感じる程度の苦痛だと考えられる。
トルクワートゥスはエピクーロスの教えを説明しつつ、「強靭で卓越した精神の場合はあらゆる心配や不安から解放されており、---苦痛に対しては、最大のものは死によって終息し、小さいものは休止の合間を多くもち、中間のものは私たちの支配下にあ」るとする「心構えができている」と言っており(前出『善と悪の究極について』第1巻49節)、私とほぼ同じ解釈を行っている。
三つ目の文は一見、理解しがたい。しかし、短期間で治る、発熱を伴った感冒などは、病状が治まるまで、熱による痛みや苦しさを感じる。これに対して、たとえば結核のような慢性的な病気の場合には、発病したことが分からないというし、喀血などを別として、倦怠感のようなものが主な症状で、体の痛みなどは疲労により生じるものと区別されないという。ヒポクラテスが結核につけた名前は、疲れ切った、衰弱したという意味の語の派生語だという(『日本大百科事典』小学館、1986)。
正岡子規は「肺病」と「脊髄カリエス」にかかっていたが、その痛みに我慢できず大声を上げて泣いたという。現代医学においては、肺病は肺結核のことで、脊髄カリエスは結核性脊椎炎と呼ばれている。後者は結核菌が脊椎を侵して炎症を起こした状態で、一般に、著しい運動制限、疼痛、脊椎の変形、四肢の運動麻痺 がおこるが、骨の組織が破壊されるに従い激痛に襲われるようになるという(半場道子『痛みのサイエンス』新潮選書、2004)。子規の場合には脊髄カリエスを伴っていたのでひどく苦しまざるを得なかったが、肺結核だけならば、ひどい苦しみはない。
そうだとすると、肺結核のような、全身の衰弱を主症状とする慢性の病気にかかった場合には、次第に体力と精神力の低下が起こることになるだろうが、その際、その病気の状態に慣れて、とくに苦しいと思わなくなるということがあると考えられないだろうか。
あるいは、結石を患ったモンテーニュが言っていることも、エピクーロスの言葉を説明するかもしれない。モンテーニュは疝痛(内臓の痛み)に苦しんだ。「その不快な状態に置かれて18ヶ月かそこらの間に、すでにこれと馴れ合うことを覚えてしまった。私はすでに疝痛の生活と妥協している。実を言うと、恐れていたほどには、そこに苦痛を経験しなかった」と言っている。『エッセー』第2巻37章。
エピクーロスが、モンテーニュが述べている疝痛のように、慢性的な病気の苦痛は強くなく、慣れることができるとみなしたとすれば、エピクーロスの考えでは「苦でない」ことは「快」であるから、「長期にわたる病気は、肉体の中に、苦痛よりも快の方を多くもたらす」ということがあてはまるようにも思われる。
また、病気とは違うが、大きな怪我を負って障害が残った場合にも、当時の人々は、モンテーニュ同様、その障害に「慣れ」、苦痛とは思わなかっただろう。第二章で見るが、古代ギリシアの競技大会で使用を認められていた肉体的暴力の程度は現代とは根本的に違っていた。パンクラシオンと呼ばれるレスリングに似た競技では、殺されたり、重症を負ったり、生涯不具になることがしばしばあった。そして、肉体的暴力の行使の規制が弱かったことは、暴力に対する嫌悪感が現代に比べてはるかに弱かったことともに、命をかけた戦いに屈しない肉体的強さを最高の美徳と考える価値観が関係していた。そうだとすれば、競技とは限らず 何らかの原因で障害を持ったとしても、古代の人々は苦痛とは考えなかった、と考えることもできるのである。
だが、リューマチや、関節炎などのように、長期間にわたって、断続的に、時には強い痛みを引き起こす病もあるようだ。しかし、これらにおいても、強い痛みは長くは続かないという。とすれば、これらの病気は、痛む時間とともに痛みのない時間つまり快の時間をもたらす。痛む時間に比べて痛みのない時間のほうが長ければ、これらの病気は、「肉体の中に、苦痛よりも快の方を多くもたらす」と言えなくもないように思われる。しかも、私の経験では、断続的に痛む慢性的症状の場合、そうした症状がなかったときに較べ、痛みが治まっている時には強い安らぎを、つまり快を強く感じる。
しかし、休みなく続く痛みを伴う病気に比べれば、断続的な痛みを伴う長期にわたる病気においては痛みのない時間がかなりあるということを、「苦痛より快の方を多くもたらす」と表現することに納得する人は少ないだろう。一般的には「苦痛より快の方を多くもたらす」という表現は、たとえば、味覚について言え
ば、コショウや辛子、遊びなら、重い荷物を背負って行う登山のような、進んで求められるものの場合に用いられる。病気はそうではあるまい。
私は、慢性的な痛みの経験は、後に述べるように、生に関する有意義な発見を私に与えてくれたものとして、なければよかったというより、むしろ経験してよかったと考えている。しかし、だからといって、この痛みを伴う慢性的な病気がいつまでも治らないままであることを望みはしない。したがってその言葉は、慢性的な病気では、苦痛が絶えず続くこともなく、また苦痛はあまり強くないので慣れることができ、さほど「苦にならなくなる」という意味の言葉として、ここでは理解することにする。第三節における再考「長い病いは苦痛よりも快楽を多く与える」)で再考する。
ロングの『ヘレニズム哲学』は「ヘレニズム哲学研究推進のための必携書」(同書の「訳者あとがき」)、あるいは「この時期についての概説書としてはとりわけ優れている」(内山勝利によるJ.アナス『古代哲学』―後出―の「日本の読者のために」)とされるが、ロングは、エピクーロスに対する様々な批判、反論をとりあげ、自らも容赦ない批判を行なっている。そのひとつに快楽を苦痛の解消およびその結果としての苦痛の欠如/無苦痛と同一視することに対する批判がある。ロングは言う「多くの人が、自らの経験に基づき、エピクロスの主張には何の現実的根拠もないと論じるであろう。彼らはまた、強い苦痛は短期間で終わり、長期の苦痛は穏やかであるという彼の主張も退けることであろう」。
快楽と苦痛の欠如の同一視に対する批判を含め、ロングのエピクーロスに対するほかの批判についてはまとめて後ろで述べるが、「強い苦痛が短期間で終わり、長期の苦痛は穏やかだ」という点については、今、述べたように考えれば理解できなくはないと私は思う。
さて、この文に続いて、エピクーロスは「他方、精神における快楽の限度は、精神に最大の恐怖をもたらしていたところの、そういった〔神々や死に関する〕事柄をよく勘考することによって」、恐怖の苦を取り除くことで「達成される」。だが、「肉体は、快楽の限度は果てのないものと受け取っている。---しかし、精神のほうは肉体の目的とその限度とをよく勘考することによって、またこの世を越えた(死後の)生に関する恐怖を追い払うことによって、われわれに完全な生をもたらしてくれるのだ。」という(DL145)。
エピクーロスは次のように言いたいのだと思われる。日常的な、欠乏による肉体の苦痛がひとたび取り除かれ、快が達成されたなら、その快はもはや増大することはない。にもかかわらず、人々は、それを単なる苦の欠如、ないしは快でも苦でもない状態だと考え、さらに快を増大させ、新たな快を実現しようとする。また、人々は大きな精神的な苦を抱えているが、様々な肉体的快楽を追求することで精神的な苦を一時的に忘れるようとする。(しかし、それは精神的な苦の本当の解消なのではない。)必要なことは、肉体的快の限度を認識し、また、人生における根本的な苦である、死や神罰などに対する恐怖や強い不安をなくし、精神の平静に到達することである。エピクーロスはこう言おうとしているのだと思われる。
エピクーロスは肉体的快楽に対する欲望のうち「自然〔本性〕的で必要不可欠」なものは衣食住の充足に対するもので、それ以外のものは、「自然的だが必要ではないもの」あるいは「自然的でも必要でもないもの」だとしている。(149)
「飢えないこと、渇かないこと、寒くないこと、これが肉体の要求である。これらを所有したいと望んで所有するに至れば、その人は、ゼウスとさえ競いうるであろう」(『エピクロス―教説と手紙』92p)。ゼウスはギリシアの宗教における神々の王であり、エピクーロスの表現には誇張があるだろうが、それでも、彼が衣食住の基本的な必要の充足こそが最大の肉体的快楽だと考えていたことは明らかである。
古代においては戦争や天候不順などにより、飢饉に見舞われることがしばしばあったと想像される。そして援助の仕組みなどもほとんどなかったであろう。そのような社会状況において、貴族や上層市民以外の多くの人々が、飢えず、飲み水に困らず、また寒さを防ぐに足りる住居を持つという「肉体の要求」を充たすことは容易ではなかったであろう。これら生存・生活のための必要、最低限の衣食住の必要をまず満たすことが、何よりも最大の快楽の実現であるという考えは、古代世界に生きる一般庶民の現実に即したものであり、ゼウスの名を引き合いに出した上の言葉も、決して大げさな物言いではなかったと考えられる。5)
他方、現代の日本社会においても、衣食住の心配をしなければならない人が存在する事実を否定できないが、それでも大部分の人は、雨風や寒さを防ぐだけの住居をもち、食事についてはむしろ「飽食」が問題になっている。ということは、エピクーロスの観点から言えば、日本人はすでに肉体的な快の最大値を達成しているということになる。それでも、多くの人が、喉が渇いたら、ただの水ではなく冷やしたスポーツドリンクなど清涼飲料水、あるいはジュースを飲み、しばしば、寿司やビフテキを食べ贅沢を味わう。しかし、エピクーロスによれば、それは肉体的な快楽を増大させない。単なる「多様化」だというのである。何が「贅沢」で豪華と感じられるかは文化や生育環境などによって異なるが、腹を満たすのに必要な食事の量はほぼ体の大きさつまり「自然本性」によってきまっているであろう。腹を満たすこと、飢えの苦痛を解消することは快楽であり、それは質素な食事によっても、贅沢な食事によってもおなじように実現できると考えることは、(食の)快楽の大きさは、人間にとって自然本性的に不可欠な欲求の充足をもたらすことができるかどうかにより測られる、と考えることである。
エピクーロスの言う肉体的快楽とは、食の場合には、手のかかった高級料理を味わうというような快楽のことではなく、生存・生活のために必要不可欠な、基本的な欲求の充足のことである。基本的欲求が満たされないことは苦であり、この欲求が満たされること、つまり苦の解消が快楽なのである。食事の際に付随して得られるであろう(必要を満たすこととは区別可能な)おいしい料理に舌鼓を打つ快楽、あるいは高層ホテルで夜景を眺めながら恋人と行なう楽しい食事などから得られる喜びなどは「快の多様化」ではあっても、快の大きさ(空腹が満たされることによる満足)を変えるものでない、このようにエピクーロスは考えるのだ。
肉体的な苦にも様々あり、すべてが解消されるとは考えにくい。だが、すべての肉体的な苦痛が解消され苦痛が存在しない状態・アポニアーで肉体的快は最大になり、他に何かの肉体的快を得ても、さらに快楽が増大することはないと考えられている。しかし、たとえば、何の苦痛も存在しない状態で、すばらしい香りのバラの匂いを嗅ぐというケースを考えてみれば、ロングが言うように(後出)バラの香りは快楽を増大させるのではないだろうか。基本的な欲求がほぼ充たされつつある現代社会において、多くの人が求めるであろう、バラの花やグルメや遊びや娯楽、スポーツなどが「快楽の多様化」に相当するだろう。
エピクーロスは、「自然本性的に必要な快」以外の、動的快の追求に積極的ではない。当時のギリシアにおいては、4年に1回、オリンピア競技会が開かれ、市民は、熱狂的に、その祭典、とりわけはげしい暴力の行使を含むパンクラシオンなどの観戦を楽しんでいた。しかし、エピクーロスの議論の中には、遊びや見世物や娯楽、祭典のようなものについての言及や暗示は全く存在せず、衣食住(生存)と性の、自然的な(ただし後者は必要不可欠とはされない)欲求の充足により得られる快楽(と「美しい形」を見ることなど若干の精神的楽しみ)についての言及しかない。
とはいえ、エピクーロスは、「自然〔本性〕的な」快楽以外の快楽、あるいは「多様な」快楽をすべて斥けているわけではなく、節制や禁欲に価値を認めているのではない6)。彼は、「哲学と自然学」により培われる思慮をはたらかせ、「醒めた分別」をもってすべての選択と忌避を行なうようにと説いているのであり、個々の快楽の良し悪し、あるいはその大きさは問題とされない。「いかなる快楽も、それ自体は悪いものではない」。肉体的快楽も含め「快楽はどれもすべて、われわれの本性に親近なものであるがゆえに、良いものである」。
「だからといって、すべての快楽が選び取られるものではないのである」。かれが説いているのは、「快楽と苦痛を測り比べ」、得られる快楽よりも「何倍も多くの煩いをもたらす」ような快楽を追求する短慮を犯さないということである。彼は、肉体的な快楽の限度を知ることが大切であり、「多様な」肉体的快楽を次々に追い求めることによっては、死や神罰への恐れなど生の根本的な苦しみを解消することはできず、かえって最大の快楽、精神の平静に近づく機会を失うことになると説いているのである(129、130、131、141)。
エピクーロスは、自然的で不可欠な快楽に対する欲求をできる限り少ない苦労・コストで満たし、その上で、実現の困難な永続的な精神的平安を得ることに努力すべきだと説いているのである。人々は飢えや渇きの苦痛を解消することはできても、「天空の事象や死や(肉体の)苦痛」などに対する恐怖や強い不安など、精神的な大きな苦から逃れられずにいる。
「快楽が目的であるとわれわれが言う場合、その快楽とは、---放蕩者たちの快楽や、(性的な)享楽のなかにある快楽のことではなく、身体に苦痛のないことと、魂に動揺がないことに他ならないのである。というのも、快適な生活をもたらすのは、酒宴やどんちゃん騒ぎをひっきりなしに催すことでもなければ、少年や少女たちとの(性的な)交わりを楽しむことでもなく7)、また、魚その他の贅沢な食卓が差し出す限りのものを味わうことではなくて---むしろ覚めた分別こそが快適な生活をもたらすのである。
ところでそういったことすべての出発点でありまた最大の善であるのは思慮(プロネーシス)である。それゆえ思慮は(純粋な知識としての)哲学よりもいっそう尊いものである。そしてその思慮からそれ以外のすべての徳は生まれるのである」。131-32.
(この(注)は2016.9.6.に加筆修正した。)
写真はWikipediaによる。

カントは『実践理性批判』で人間は単に幸福になることを望むのでなく、幸福に価するように道徳的に善でなければならないという。しかしこれは昔の因果応報の考えの名残だろう。私は悪い行為は罰を受けるべきだと考えるが、道徳的に積極的に善い行為を行った人でなければ「幸福になるべきではない」とは言えないと思う。
ところでカントはこの定言命法は実質的には聖書の黄金律「他人からしてもらいたいと思うように、他人に対して行え」と同じものだと言う。ルソーは『人間不平等起源論』で「できるだけ他人の不幸を少なくして、自分の幸福をはかれ」は、黄金律ほど崇高でも完全でもないが、役に立つ、自然の善についての格率だ、と言っている。私はこのルソーの考え方の方に賛成する。(ロングはエピクーロスの教説は「自己中心的」と評する(⇒第二節「ロングはエピクーロスが「自己中心的」だと言う」以下参照)が私は、エピクーロスが説く、他者に対する態度はこのルソーの言う原則に近いものであると思う。)
では精神的な快と苦の「大きさ」については、彼はどのように考えているのか。エピクーロスは、当時の人々の多くが、神々や天体が人知の及ばないしかたで「怒りにかられ」「好意にほだされ」て(139.)人間の生に介入、干渉してくると恐れており、また人々は、死を恐れるとともに、神々や天体が死後においてもいつまでも人々を苦しめると恐れている(76~81。142.143.145.)と述べている。
ロングは「人間の幸福と不幸は、神々によって配分されると言う考えは、ギリシアの民間宗教の基礎を成していた。---神話の神々に対する信仰は、おそらく、大多数の人々にとって---公的ないし私的な祭儀の問題
であったであろう。しかし、多数のギリシア人が、教育のあるギリシア人も無いギリシア人も、入信者に救済を約束する秘儀を認め、汚れや神の介入に対しては、深い恐怖を抱いていた」と言う(p63)。
社会学者のA.ギデンスは、伝統的社会において、「宗教は、通例、生きる上での潜在的な不安のまさに心理的ありかになっている」。「宗教が宗教自体に特有な恐怖感をどの程度生み出すか」は、かなり偏差があるが、「ウェーバーが「救済宗教」と称した宗教上の信念や実践の諸形態は、毎日の生活に生きる上での恐怖感を注入する傾向がきわめて強いため、罪業と死後の救済約束との間に緊張関係を実際に引き起こしている」と言っている(松尾精文ほか訳『近代とはいかなる時代か』p135.而立書房、1993)。
ロングは、エピクーロスは「神が世界を支配していると考えるところの、あらゆる信念と戦おうとした」と言い、10ページに渡ってエピクーロスの反宗教的見解についての説明を行なっているが、私は、この点に関する議論は省略する。世界には依然として宗教を持つ多くの人々が存在するし、日本にも宗教あるいは信仰を持っている人が存在する。だが、少なくとも、現代の日本社会において、日常的に神の介入や「神罰」を恐れることが大きな精神的ストレスの原因となっているような人はほとんどいないだろうと、考えるからである。(オウム真理教も「神」を信じていたのではない。)
そして、私は、それに代わる多くの、そして大きな精神的な動揺、不安を現代人は抱えているということのほうが気に掛かる。私は、哲学史の学問的研究をおこなおうとしているのではない。つまり古代の哲学者の学説を、当時の社会状況を検討しつつ客観的に研究しようとしているのではない。私は、エピクーロスの説を、自分の幸福に役立てるために考察しているのであり、私は、私が生きている現代世界における、不安や恐怖といった精神的苦しみと関連付けながら検討したい。
現代人は神罰を恐れない。諸天体は岩石の塊であるか核融合を起こしている「原子」の離合集散でしかない。しかし、人々が暮らす大地・地球は、高度に発達した科学技術をもっても予測できずまた対策も取りえないような、地震や津波、洪水や竜巻など大規模な災害を引き起こす。科学技術の発達で一定の自然災害を防ぐことができるようになった面もあるが、逆に、科学技術の産物が新たな危険をたくさん生みだし、原発のような巨大施設が自然災害以上の悲惨な結果をもたらしてもいる。
建設に際しては、わが国の科学技術とその産物は他の国と比較して断然優れており、安全性についての心配は不要だと、科学者や技術者がお墨付きを与えていたはずの原発が大規模な事故を起こすと、それは「想定外」の原因によって起こったことだという「説明」を受ける。
われわれの知の先端にいる専門の科学者や技術者だけが、きわめて複雑で高度な科学技術を理解しており、それを用いることができる。われわれ素人、一般国民が口をさしはさむ余地はない。われわれ一般人は、かれらの言うことをただ押し頂くことしかできない。古代の人々が預言者や巫女たちの言葉を恭しく承るしかなかったのと同じである。
われわれ現代人は古代の人々のように「神々」や「天空の事象」を恐れる必要はなくなったが、大きな自然災害に対する心配や不安がなくなったわけではなく、また人間自身が引き起こす地球上の不可解な恐ろしい現象、それについて科学者やテクノクラート(技術官僚)たちの解説を聞くが、納得の得られない多くの現象に、古代の人々と同様の恐怖や不安を感じている。
せいぜい20年~30年さきまでの生活の便利さや経済成長を拡大するために、また自己の利害の追求のために、長期的に見て重大な危険をもたらす可能性がある科学技術の産物を積極的に受け入れようとするテクノクラートを中心とする人々がいる一方で、科学技術の産物が引き起こした重大な事故によりふるさとを追われ職を失い家族がばらばらになる被害を蒙っている人々や、そうした施設が近くに存在し同じような事故の発生を恐れ不安を抱えている人々があり、また少数であるが、そうした危険な施設の運転や新たな建設に反対する運動に、決して好んでではないにせよ職や地位を犠牲にしてまで取り組んでいる人もある。われわれ現代人は古代ギリシアの人々と違って、気まぐれな神によるこの世の支配といった「誤った想念」にはとらわれていないが、しかし同じように、理解できず、判断のつかない科学技術の産物がもたらしうる重大事故に対する恐れや不安という苦を抱えて生きている。
「死は何ものでもない」。なぜなら、「善いことや悪いことはすべて感覚に属することであるが、死とはまさにその感覚が失われることだからである」。124.われわれは、生きているときに、快と苦を感じ、自分の状態について良いあるいは悪いと意識し考える。われわれとはわれわれの感覚であり、意識であり、思考である。こうした働きは死によって失われる。死んでいるときには(眠っているときと同様)、感覚も意識も思考も存在しない。また、エピクーロスは言う。「われわれが現に生きて存在しているときには、死はわれわれのところにはないし、死が実際にわれわれのところにやってきたときには、われわれはもはや存在していない」。したがって、「死はわれわれにとって何ものでもないのである」(DL125)。
死は時代を超えて人間を捉えて離さない普遍的な問題だと思われる。死を意識する、あるいは考えると言う場合に二つのケースがある。人間には寿命があり、いずれは自分も死ぬ、死ななければならないということについての思考。これはいわば「理論的な死」、ないしは「死の観念」である。もうひとつは現実に差し迫った死を意識し、恐怖を感じる場合である。たとえば、地底の坑道で働いている最中に落盤で閉じ込められた、あるいは、強い地震で建物が倒壊してくる、あるいはまた、後ろから津波が迫ってくるというような場合に感じる、死ぬかもしれないという、絶望もしくは激しい恐怖の意識である。
ただし、死について、これら二つのケースに区別できない場合もあろう。たとえば、臓器移植を受けた人々のように、5年生存率が○○%というようなしかたで統計数字が示されている場合には、切迫した恐怖とは違うが、具体的な死を意識せざるを得ないということがあるだろう。この場合には、たとえば70歳の人が平均余命を考え自分の「5年生存率」を「理論的に」考える場合とは違う現実的不安を感じるだろう。しかし末期がんの患者があと半年の命だと宣告された場合とはまた異なるであろう。古代の人々の場合には、戦争や疫病や飢えなどによる死者を日常、間近に見ることによって死を意識させられたであろう。とすると、彼らにとっては、死は「理論的な死」ではないが、さりとて災害に見舞われた場合のような差し迫った現実の死とも異なる、両方の性格の入り混じったものではなかったか。
しかし、一般に、人は、日々忙しく自己の務め、仕事に打ち込んでおり、このような抽象的で、観念的な死について考えることはほとんどないと思われる。仕事の合間、休日には、のんびりするか遊んだりするであろうが、やはり、死について考えるということは、ふつうはしないだろう。この「理論的な死」は、私の死
を現実にもたらすであろうできごとが存在していないときに、私が、生きるとはどういうことかを「理論的」、観念的に、頭の中だけで考えるときに出くわす死である。
しかし、地底の坑道に閉じ込められてしまった、あるいは、大きな津波が間近に迫ってきているというときには、人は誰でも死を意識するだろうし、激しい恐怖を感じるか、言い知れぬ不安・絶望に駆られるだろう。この場合には、実際に死をもたらす具体的なできごとが存在し接近しているがゆえに、われわれは現実的な死の不安・恐怖・絶望を感じる。
一方の「理論的な死」は人により反応の仕方に大きな違いがあり、私のように若い頃の一時期にしばらくの間苦しむ経験を持つ人がいる一方で、少年時代から中年にいたるまでしばしば強い絶望感を繰り返し感じるという人(たとえば森岡正博『無痛文明論』トランスビュー発行、2003、第7章参照)もあり、また、いずれは誰でも年をとって死ぬものだとまったく当たり前のことと受け止めて気にかけないか、あるいは「人類」としてつながっているのだとあたかも死は存在しないかのように言い、平然としている人もいる。だが、現実に迫った死に平然としていられるという人はいないだろう。そしてこの両者のあいだに、現実的に接近しているが、多少の時間の余裕があるような、恐怖ではないが相当に不安を感じる死があるだろう。
エピクーロスが「なんでもない」と言っている死は「理論的な死」であるか、もしくは切迫しているのではないような死のどちらかであるように思われる。彼は耐えられないような激しい苦は長くは続かないといっていた。おそらく、大きな事故や災害に巻き込まれて実際に死が差し迫っているとき、たとえば交通事故で 車に閉じ込められ身動きできないのに車が炎上したというような場合などを考えれば、その際の精神的な苦、つまり激しい恐怖に人は長い時間耐えられず気を失うか発狂するであろう。このような差し迫った現実の死が与える激しい恐怖はどうすることもできない。そのような「耐えられない」激しい苦は長くは続かない。そう考えるしかない。死が単に観念的・理論的なものであれ、現実的な原因を伴ったものであれ、苦を与えることがあり、それをなくするか減らすことが問題となるのは、とにかくしばらくの間は生が続き、その生きている間の快と苦が問題だからである。エピクーロスはそのような前提で、死について考えているに違いない。
これに対しては、私は、死んだときに私がどう感じ、どう考えるかを問題にしているのではない。私は、死ねば何も感じられなくなってしまうというそのことを、今、悲しく辛く感じるのだ(注)。私は苦しいこと、悲しいこともふくめ、世界を自分の感覚を通じて、見、聞き、味わい、臭いをかぎたいのだ、という「反論」があるかもしれない。つまり、死ねば何も感じられなくなるということ、死んでいる状態では何も感じないということは「何でもない」こと、「悪くもよくもないこと」ではなく、悪いことであり、生はよいこと、望ましいことだという反論である。
これが「正当な」反論かどうかは明らかではない。それは結局、死にたくない、生き続けたいと言っているのと同じであり、死は必ずやってくるのだから、その願望は不合理であり、今述べたことは「反論」にはならない。このように言い返されるかもしれないと思う。しかし、次のようなことは言えるのではないか。
もし、私が、明日楽しいこと、あるいは重要なことをぜひやりたいと考えているとするならば、それが実現されるように、少なくとも明日中は、生きている必要があると考える。したがって、今日私が、明日まで死にたくはないと考えるのは合理的である。
一般に、これからの人生において、なすべきこと、楽しいことがたくさんあると考えている若者はもちろん、中高年の人でもまだ元気で様々なことをやろう、やらねばならないと考えている人々が、事故や急な病に襲われるなどして死にたくない、と考えることは、単に自然的なことだというだけでなく全く合理的である。
また、完全な個人主義者あるいはエゴイストでないならば、やるべきこと、やりたいことはすべてやり遂げたと思っていたり、また逆に生に全面的に絶望していたりするにせよ、子どもや親などその人の死をひどく悲しむ人がいる限り、死にたくない、死んではならない、自殺などすべきでないと考えて生きる努力をするのも、また合理的なことである。
(注)「アトムに分解されてしまったものは感覚を持たないが、感覚のないものは、われわれにとって何ものでもない、という主張は、死の恐怖を解消してしてくれるどころか、かえって、死の恐怖にその確証を付け足してしているようなものだ---。なぜなら、まさにその点こそ、われわれの本性が恐れるところなのだから。---つまり魂が考えることも感ずることもないものに分解することを、恐れているのである。」プルタルコス『モラリア14』(戸塚七郎訳、京都大学学術出版会、1997)「エピクーロスに従っては快く生きることは不可能であること」1105参照。
この書はエピクーロスの教説に対する全面的な批判・反論の書である。ただし上流階級の人のために書かれている。次の「ルクレーティウスへの反論」への追加の(注)も参照
なるほど、早くから来ていて、もう十分にうまい酒と料理を楽しみ、満腹を感じている客なら、「安んじて」眠りにつくだろう。だが、うまい酒と料理を楽しんできたが、まだ、お腹に余裕のある人、もっと食べたいと思う客もいるだろう。彼は、満腹を感じるまで、眠りに就きたいとは思わないだろう。
また、これまでうまい酒と料理に与ることができなかった客は、酒にも料理にも興味のない人以外、さっさと眠るべきだといわれても承知しないだろう。これまで食べた料理がうまくなかったからと言って、他の料理もまたまずいとは決まっていない。他のテーブルにうまいものがないかどうか、動き回って探してみるのではないか。
私は「自然」に対して、あるいはルクレーティウスに対して、このように反論したい。ともあれ、ルクレーティウスが述べていることは、これから生きようとしている若者、まだ働き盛りだと感じている人々には、全くあてはまらない。
(注)
ルクレーティウスは、上の文に続いて次のように言う。「古いものは絶えず新しいものに押しのけられ、一つのものから別のものが生み出されなければならない---。しかし、誰も下界へ、すなわち冥府タルタルスの中へやられるわけではない。後から来る世代が成長するためには、素材が必要なのである。
---世に伝えられて、冥府アケロンに在ると言われていることは、すべてこの我々の世に在ることなのだ。物語に伝えられているような、タンタルスが悲惨にも、空中にぶら下がっている巨大な岩を恐れて空な恐怖に戦いているなどということはありはしない。
むしろ、この人生において、神々を恐れる理由のない恐怖が、死すべき人間どもを圧迫しているのであって、人々は誰に当たるかも知れない〔神罰の〕偶然の落下を恐れているに過ぎない。
---スィースビュス〔シジフォスであろう〕もまたこの世に、我々の目の前に現にいる。すなわち国民から権杖ファスケース〔権威の標章〕や残酷な斧を得ようと渇望しては、いつも得そこない、失意のうちに引きさがって行く者のことだ。なぜならば、空疎な---はなはだしい苦労を忍ぶことは、これ、取りもなおさず急な山に石を―頂上から直ぐ再び転落し---ようとする石を―営々と押し上げることに他ならないからである。---三頭怪犬ケルペルスも、また「狂暴フリアエ」も---また咽から恐ろしい火を吐くタルタルスも---全く存在し---ない。要するに愚者にとってはこの世の生活が取りも直さず冥府の生活となるのだ。〔だから、神々に対する理由のない恐怖や不安をこの世から解消することが求められているのだ。〕同書第3巻952-1023
しかし、エピクーロスが述べている「われわれが現に生きて存在しているときには、死はわれわれのところにはないし、死が実際にわれわれのところにやってきたときには、われわれはもはや存在していない」という二つ目の理由は、最初の理由と少し違う。この文は、死ぬということはわれわれが存在しなくなるということだというきわめて一般的なことを述べている。私が生きているときには、死んでおらず存在している。私が死んでしまえば私は存在しない。いずれにせよ、私は死とは全く無関係なのである。私は、私に何の関係もないことを悲しんだり、不安に感じたりする必要はないと、この文は言っていると思われる。
このように考えるべきだとすると、反論はしにくいように思われる。私は、私が存在しなかった100年前の世界について、私と無関係なものとして、(そこに どんなに興味深い事件が起こっていたにせよ)私がそこに存在しなかったことを特別に悲しく思ったり、嫌悪したりしない。100年後、私は存在しないだろ う。どうして、私は、そこに私が存在しないことを苦痛に感じなければならないことがあろう。100年前に私が存在しなかったことをなんとも思わないよう に、100年後に私が存在しないことも、私にとっては何でもないはずである。
死を恐れる必要はない、死はわれわれにとって何ものでもないとエピクーロスは言うのだが、私は彼の述べていることに納得していない。上で見たような理由によって、死は何ものでもないと言う彼の教説に納得する人はほとんどいないのではないか。私が「理論的な死」に出会った大学生のときに、死についてのエピクーロスのこの文を読んで感じたのは、いわゆる禅問答の類が与えるのと同様の印象であり、全く答えにはなっていない、というものだった。
そして、彼自身、論証は正しく、完全であると考えていたかどうかもわからない。しかし、仮にこの論証が完全に正しいとしても、それを理解することが直ちに死の不安・苦を解消することにはならないということは、彼も知っていたのではないかと思う。かれが「死はわれわれにとって何ものでもないと考えることに慣れるようにしたまえ」と言っている(DL124)ことがその理由である。
自分が死ななければならないということにはじめて本当に気がつき、その「理論的な死」をそのすべての帰結も含め十分に考えたときには、誰もが驚愕し、絶望に取り付かれる。そこから逃れるための特効薬のようなものはおそらくない。しかし、ほとんどの人は絶望して自殺するということはなく、生き続ける。そしていつかそれに慣れて気にしなくなる。
われわれは、末期がんの患者を襲うことがあるという四六時中続く激痛のような痛みをのぞけば、肉体の痛みには「限度」があり、なんとか耐えて生きることができるのだろうし、また、ひどい悲しみや恐怖や絶望という精神的な苦痛も、時間をかければ「慣れる」ことによって、苦しみではなくなると彼は考えているのだと思う。要するに、ことさらなにもしない無手勝流が一番で、といっても、時間をかける、つまり年をとる必要はあるのだが、死(の観念)の方からやがてその恐ろしい刃をおさめてくれるだろうというのが私の見方であり、エピクーロスも同じように考えているのではないかと私は推測するのである。
モンテーニュは『エッセー』の一つの章を使って、死について考察している。彼はその章の冒頭で、「キケロは、哲学するとは死に備えることに他ならない、と言った」と書いている。そして、「しっかりと足を踏まえて敵をくいとめ、これと闘うことを学ぼう。そしてまず、我々に対するその最大の強みを敵から奪うために、---この敵からその異形イギョウを取り除こう。この敵を引き寄せ、この敵に慣れ親しみ、---死をしばしば念頭に置こう。---死がどこでわれわれを待ち受けているかわからない。われわれはいたるところで死を待ちうけよう」と言う。つまり、死(の観念)と戦うもっともよい方法は、死が明日来るかもしれないと絶えず死について考え、想像し、死に慣れ親しむことだという。
だが、次のようにも書いている。彼は、仕事や、妻や子供や「何ものにも未練を残さずにこの世を去ることができるような心境になっている。といっても、生命だけは別で、これを失うのかと思うと、私の心は重くなる」という。(第20章「哲学するとは、死ぬことをまなぶことである」。)「絶えず死について考え、想像し」て、理論的な死に「慣れ親しん」だとしても、死は決して「なんともない」ものになることはない。理論的な死が人の心を重くすることに変わりはないのである。考えると心が重くなるようなこと、楽しい観念に変えることができないようなもの、つまりは苦であるようなものを、自分から進んで考え、苦を増大させることはおろかしい。私はそう考える。
エピクーロスは、どのようにして「死はなんでもないものだと考えることに慣れる」のかについては書いていない。たしかに彼は「天空の事象に関する気がかりとか---死に関する気がかりとか、そういったことがわれわれを少しも悩まさなかったのであれば」自然研究は、そしてまた哲学は必要ないと言っている。だ が、キケロー、あるいはモンテーニュのように、哲学や自然学の研究を通じて、繰り返し死の問題についての考察を行うよう勧めることはしないのではないか。
エピクーロスによれば、(理論的な)死を恐れたり絶望したりすることは、単に誤った想念によって自分を苦しめているだけである。
たとえば天候不順を理由に半年先の穀物不足が生じることを心配するという場合に、その心配とともにあらかじめ余分な食糧を手に入れておこうと「勘考」するなら、その心配は将来の苦を減らすのに役立つから有益であろうが、何もしないでただ心配するだけなら無益であり、現実に食糧不足になったときの苦に先立って余分な苦を得るというだけである。
現実的根拠があってさえも、将来について心配するだけでは、役に立たない苦を増大させるだけであり、合理的なことではない。エピクーロスもきっとこのように考えるに違いない。そうだとすると、「気がかりに」なっておらず、「悩んで」いない時に、あえて死の「理論的研究」をおこなうよりも、「気がかりに」なり、「悩んでいる」ときには、「放蕩」によってはその精神の恐怖を解消することはできないのだから、そのときには死(や神罰など)に関することがらを「哲学する」ことが有益であろう。
キケローは『善と悪の究極について』のなかで、苦を真正面から受け止めて「雄々しく」、男らしく戦うべきだと、エピクーロスを批判している。だが、エピクーロスは勇気や男らしさの徳に価値を認めない。苦を減らすことのほうを選ぶ。回復の見込みが全くない重い病の床にある場合には、死ぬことに恐怖を感じず安らかに死を迎えられることが望ましい。しかし、死を回避する方法が全くないというのでなければ、誰でも、なんとか生き延びる方法を見つけだそうと必死の努力を行うだろう。そして現実に事故に巻き込まれたり、災害が発生したりした時に恐怖に襲われるのは自然であり、われわれは「死は何でもないものだ」と泰然としているべきではなく、恐怖に駆り立てられつつ、可能な限り危険から逃れる行動をするべきなのである。この場合には「理論的な死」についての知識は、実際には、何の役にも立たない。
「理論的な死」について考えた人がどれだけいたかはわからないが、古代においては、戦争やペストなどの疫病の流行、あるいは飢饉などが身近にたびたび発生したであろうし、こうした現実に差し迫った死の恐怖、強い不安の中で多くの人が暮らしていたと思われる。差し迫った現実的な死を知った時の苦しみ、これはきわめて大きな苦である。モンテーニュの表現を借りれば、「ひとたび死が、不意に防ぎようもなく、彼ら自身の上に、彼らの妻子や友達の上に襲いかかるなら、いかなる苦悶、いかなる叫び、いかなる狂乱、いかなる絶望が彼らを押しつぶすであろう」。p71.
私は私のはじめての子どもである娘が生後2ヶ月ほどで小児がんと診断されたときにはひどいショックを受け、一週間ほどはほとんど呆然としていた。そして娘の入院後、2~3カ月にわたって、ベッドの脇で、娘がこのまま死ぬのではないかという強い不安感、言い知れぬ寂寥感にとらわれていたことを思い出す。自分ではなく自分の家族の場合であってもそうである。さまざまな精神的な悩みや苦しみがあるにせよ、自分が近いうちに死ぬのではないか、死ななければならないと考えること以上に大きな苦しみはないというのは、まちがいないであろう。
さらに、当時の人々は死の恐怖や不安だけでなく、人間の生への神の恣意的な介入や「神罰」のようなものにも強い怖れを抱かざるを得なかった。エピクーロスの教説はまさにそうした不安の苦しみを解消するために書かれたのだ。そして、彼の天体論や原子論は、たしかに、人々が天体の位置関係によって死がもたらされるとか、あるいは疫病で死ぬ人を見てそう考えたかもしれないが死はひどく苦しいものであるとか信じ、あるいはまた死後、生き残った魂が神々の恣意的な罰を受けるとか信じていた限りにおいては、死に対する不安、恐れの苦をなくすことに役立ったかもしれない。
だが、先にあげたような抽象的な、禅問答のような理由によって、死ななければならないという人間の運命を悲しく辛いことだと、現に今、感じている人を納得させることはできなかったであろうと、私は想像する。しかし、人はいつも、死の問題に取り付かれているわけではない。ほかに多くの現実的な精神的苦しみを抱えている。精神的な苦がすべて解消された状態が最大の快だとエピクーロスはいう。彼の教説をもっと先にたどることにしよう。
エピクーロスの魂は、肉体が蒙る情動をともに喜びあるいは苦しむ。肉体の必要が満たされた後の精神の快楽である平静心・アタラクシアーは、肉体と区別された純粋な部分ないし働きである「魂」の快楽なのではない。出典不明であるがエピクーロスのものであることが確実だとされる断片において、彼は「いっさいの善の始めであり根であるのは、胃袋の快楽である。知的な善も趣味的な善も、これに帰せられる」と述べている。(前掲書『エピクロス―教説と手紙』 119p。)
また、キケロー前掲書『善と悪の究極について』の中で、エピクーロス派のトルクワートゥスは、「精神の快楽や苦痛は身体の快楽や苦痛から生じるというのが私たちの立場です。---それらはいずれも身体に端を発し、身体に帰着する」と述べている(55節)。
エピクーロスによれば魂は肉体と密接に結びついたものであり、精神的な快楽は、すべての人間が必要とする衣食住、安全な生存・生活への欲求、すなわち身体の自然本性的な欲求の充足と結びついたものである。自然の研究や神についての哲学的考察9)により得られる快楽も、純粋な知的快楽なのではなく、死の不安はもちろん、自然や神によって人間にもたらされると想像された災害や天罰、つまり最終的には安全な生存、身体の快苦に関する誤った観念を解消することで得られる快である。
われわれは、日々、行動し、何らかの活動をおこなうが、すべての行動・活動は快を実現し、苦を解消するために行われる。空腹やのどの渇きが感じられなければ、飲食の行動はなされない。その場合には、少なくとも胃袋や喉など身体に関して、一時的に、人は静的な快の状態にある。空腹になれば、その苦は、食物の摂取による動的快楽の過程を通じて解消され、再び一時的な静的快の状態が回復される。こうして、食や性にかかわる肉体的な苦は、一度に永久に解消することはできず、われわれは苦―→動的快楽―→静的快楽のサイクルをくりかえさざるを得ない。しかし、それら一つ一つのあるいは毎回の苦には、欲求の満足という限度があり、多くの場合、満たすことは可能である。
他方、災害、神罰、死などに対する恐れや不安、あるいは重い病気にかかることや、年をとり、からだが不自由になってしまうことへの不安などの精神的な苦は、一時的なものでなく、何か他の活動などで紛れている間を除き、いわば四六時中、重力のように人を捉えている。それらは事故や災害に襲われた瞬間の恐怖のような動的な苦と区別される、静的なそして持続的な苦であるといえよう。人はときどき、知的な趣味やスポーツなどにより動的な快楽を得、しばらくの間、この持続的、静的な苦を忘れる。
だが、重力に逆らって運動することが重力の支配から免れることではないように、その時々の心身の動的快楽は、この災害や死などに対する恐れや不安という精神的な持続的な苦それ自体を解消してくれるものでなく、一時的な動的快楽が止めば、前からそこにあった「静かな苦」が再びわれわれを捉える。そして、これら不安や恐れをとりのぞくことは決して簡単なことではない。それら災害や死への不安の苦は、技術的なあるいは医学的な対処によって解決できるものでなく、自然学や哲学によってのみ可能なのだ。
仏教においては、諸行無常、一切皆空が説かれ、人生は、生老病死の四苦、愛別離苦、怨憎会苦(おんぞうえく)、など苦しみに満ちているとされる。そしてこの苦から解放されるために、煩悩の炎を消し(つまり、限度を知らない肉体的欲望を抑え)、瞑想において、正しく見、正しく思惟するなどの方法で、世界の真実の姿を知るべきと説かれている。
エピクーロスが、人生は、快でも苦でもない「中間状態」にあるのではなく、根本的には苦に支配されているという直観から出発し、平静心に到達して幸福な生を実現するために、(原子論など)自然学や哲学によって、天体や神々の恣意的介入への不安や死への恐れなどの苦しみを解消することを説くのは、仏教の場合とよく似ている。
原子論による死の説明は死のメカニズムの説明である。そしてそれは、死が怖くないことの説明にはなりえない。がんや結核の医学的説明を聴いて、それらに罹ることが怖くなくなるのは、治療が容易ですぐに治るという説明を受けたときであって、発病の仕組みや症状の説明を受けたときではないのと同様である。
現代においては自然は操作可能なものだと考えられており、古代において死と直結すると考えられた病の多くが治癒可能だと考えられている。しかし「人間はいつかは死ぬ」ということは変わらない。死に関しては、人間は自然に従うしかないということは、昔も今も同じである。そして現代医学においても死は「物理現象」であろう。エピクーロスに従って死を「物理現象」と理解することは、われわれを死の恐怖(あるいは嫌悪)から解放してくれることはない。
もう一つ、市野川が言うように、エピクーロスは生への執着から人を解放したか。そうとも言えない。エピクーロスは生と死を相互に不連続で無関係なものとみなし、「死はなんでもないもの」と言うが、その説明に納得し、生への執着から解放された人が多くいたと、私には思われない。人は理論によって生への執着を無くすのでなく、満足できる一定の長さの充実した生を生きることによって人は死ぬことへの準備が自然にできるようになる。それが「死はなんでもないものだという考えに慣れる」ことなのだと思う。
そして、不節制な生活をせず、健康な生を望み、病気になったときに医学の助けを借り医療を受けることは、私は不合理ではないと思う。現代医学の中には、脳死を死とすることを前提にした臓器移植など、部分的に不適切ないびつな面があるとは思うが、近代医学全体を否定しようとは思わない。
実際、ひとびとは、死は「最大の災厄」だと考えている。死ななければならないという想いは精神に強い動揺、苦しみを引き起こす。あやまった想念が原因であるとエピクーロスは言うが、そうであっても苦は苦であり、死がなんでもないものだとしても、そのことの納得は容易に得られるものではない。哲学や自然学の一生をかけた営みによってはじめて、魂の平静さ、動揺のない精神の大きな快に到達することができる。
トルクワートゥスはキケローとの対話のなかで「わたしたちは、ある種の快さによって自然〔により与えられた心身〕を動かし、ある種の喜びとともに感覚によって感知される類のものだけを追い求めているのではない---。むしろすべての苦痛が除去されたあとに感知されるものこそ最大の快楽と考えています」(『善と悪の究極について』第1巻37節)と述べているが、この「最大の快楽」は、「身体の健康(ヒュギエイア)と魂の平静さ」(128)、あるいは「身体に苦痛のないこと(アポニアー)と、魂に動揺のないこと(アタラクシアー)」(136)にある。
限度を知り、欲張らなければ、肉体の苦痛を解消し快を得ることは、日々、比較的容易に実現できる。それらと比べてはるかに強く、逃れることの困難な永続的で大きな精神的な苦から解放されるなら、われわれは本当の「静的な精神的快楽」に到達し、幸福な生を実現することができる。身体的な苦痛は同時に精神的な苦しみ、魂の動揺を生ずる。そして、死や、神罰や、天体のことなど(それらも究極的には身体にかかわることであるが)恐怖や不安によって強く精神を苦しめるもろもろの苦がある。これら心身におけるすべての苦が除去されて完全な魂の平安、精神の平静に到達するときに、人間は最大の快楽つまり幸福を実現することになる、このようにエピクーロスは説いている。
続いて彼はエピクーロスの快楽主義の「もっとも顕著な特徴は快楽と苦痛の中間に位置づけられる状態ないし感情を否定する点」にあること、つまり「快楽と苦痛は反対関係ではなく、矛盾対立関係にある」ことを指摘して、次のように言う。
「もしも快楽がすべて、ある種の感覚とみなされるなら、快楽と苦痛のこの〔中間のない、矛盾対立〕関係はまったく意味をなさない。というのも、明らかにわれわれの大多数は、苦痛も快楽も感覚することなく、覚醒時の大半を過ごしているからである。」
ロングは(相手が反論することの可能な現代の哲学者の説について彼の見解、批判を述べようとしているのではなく)古代哲学の研究者として古代の思想家・哲学者の書き残した文、苦の欠如は快である、あるいは苦と快の中間は存在しないなどの一見奇妙に思われるかもしれない文について解説しようとしているのである。一方的に自分の批判だけを行うはずはない。まず第一に、可能な限り、それらの文、そしてエピクーロスの快楽論を意味の通るものとして、説明するはずである。
そこで、この冒頭の文に続いて、読者が期待ないし予想するのは、たぶん、「しかし、エピクーロスは、快楽は感覚(されるもの)とは考えていない。彼においては、快と苦は、〇〇であり、したがって多くの人が大半の時間苦痛も快楽も感覚していないからといって、そのことはエピクーロスの快と苦の中間を認めず、苦の欠如は快であるという主張を否定する理由にはならない。というのは○○は感覚とは違い---であるからだ。実際、エピクーロスは---と言っている。」というような文ではないだろうか。
実際、次に続くロングの文は「しかし」で始まっている。しかし、そこでは彼は、エピクーロスが快苦はいかなるしかたで、つまり感覚以外のいかなるはたらきにより感受され判別されると考えている(あるいは述べている)かについては全くふれようとせず、またもや、持ち出されるのは「われわれ」の態度である。
彼は言う、「しかし、われわれが自らを省みて、自分は幸福でも不幸でもない、あるいは、何かを楽しんでいるのでも楽しんでいないのでもないと記述しうるような覚醒時の期間というのは、はるかに短いものである。快楽と苦痛の関係に関するエピクロスの見解はこの観点から解釈されるべきである」と。
ロングは、エピクーロスが「快苦」と呼んでいるものは、「省みる」ことによってとらえられるもの、つまり、自分の行為や身体の状態についての反省意識の働きに基づく、一種のあいまいな総合判断のようなものとして「解釈すべき」だと言っている。だが、こう解釈してもエピクーロスの快楽論がもっともなものだとすぐには納得できない。
人は次のように考えるかもしれない。私は、一般に自分の現在の在り方についていつもこのように「省みる」態度をとることはない。自分の現状についてはたいてい「無頓着」でいる。はっきりした、あるいは強い、快や不快を感覚して初めて、自分の状態に気が付き、それを快あるいは苦(ないしは不快)と「記述」するはずだ。ということは、エピクーロスは、通常多くの人が自分の快苦の状態について「無頓着」の態度を取っているという事実を見落としているのであり、彼の快楽説はその点で誤っているのではないか。ロングの説明を読む限り、そのように、考えたくなる。
実際、この段落におけるロングの結論は 「エピクロスの誤りは、物事に対するわれわれの気分や態度の内には、無頓着と言う語によって特徴づけられるものもある、という事実を見落とした点にある」というものである。
しかし、このように論じることは、エピクーロスの問題提起の門前払いと同じであり、不適切である。
エピクーロスは、生存に必要不可欠な欲求の充足が重要であることを強調するとともに、そうした欲求が充足された後では、(「贅沢な食事」、「少年や女との交わり」など)主として身体的な、感覚によってはっきりと感じられる刺激の強い「多様な」快楽を追求するのでなく、人生にとっての最大の苦である死の恐怖をはじめとする精神的な苦痛、魂の動揺を無くすることに努めるべきだと説いている。
身体的欲求が充足されたなら、その落ち着いた時間を大切にして、「哲学や自然学」を行い、精神的な苦痛の多くが間違った想念によるものだということを知り、精神の平静の実現に努めるべきである。身体的欲求が充足された後の状態は、精神の平静に向かうことを可能にする有意義で喜ばしい状態であることを知るべきで、快でも苦でもない、空無の状態ではなく、また多様な動的快楽の追求とそのための労苦によって埋められるべき時間ではないと言いたいのであり、その欲求充足による苦の欠如状態に対して、それがたとえ感覚にはっきりとした快苦の感じを与えないにせよに、無頓着、無関心であるべきではないと説いているのである。
また、彼は「動的快楽」と「静的快楽」という新たな概念・用語の導入によって、アリスティッポスとキュレーネー派の人々のように(DL2巻86-90)従来の感覚的で刺激的な快楽のみを快楽と考えるのでなく、苦の欠如状態は(一つの)快楽であり、他の様々な身体的感覚的な快楽よりもいっそう重要な意義を持つ快楽だとする快楽概念の変更を行おうとしている。その提案を、「人々」/「われわれ」が「静的快楽」を「感覚では感じられない」という理由で「意味をなさない」と斥けるのは、非哲学的態度ともいえる。
だから、エピクーロスが人々の苦の欠如状態に対する「無頓着」を見落としており、したがって彼の快楽論は誤りだと言うことは、そもそもエピクーロスの問題提起がなんであるかをまったく理解してないか、知っていて端から受け付けようとしないかのどちらかの態度の表れであり、門前払いと同じである。
ロングが示している「解釈」についてはどのように考えるべきか。ロングはエピクーロスがいう快楽は「省みて」判断されるもので、ある種の反省的態度を前提にしていると「解釈」するのだが、上の文では快/苦ではなく、また「楽しい/楽しくない」でもなく、「楽しんでいる/楽しんでいない」そして「幸福である/不幸である」の二者択一が例に挙げられていた。
次ぎの段落でロングは、「英語ではenjoy good healthという言い方が可能で、健康を指して喜びを与えるもの、あるいは人が享受するものと呼ぶこともできるであろう。したがって、エピクーロスが「快楽」という語によって、身体的・精神的に健やかな状態を表すのは、語法として、完全に恣意的であるわけではない」と言う。(ただし、エピクーロスが実際に快楽を健康と同一視したかどうかをロングは示していない。)
なるほど健康についてならば、身体の状態に関してなんの「感覚」がなくても、「自らを省みて」私は健康だ、私は健康を享受enjoyしている、あるいはそうではないと答えることになろう。また幸福かどうかと問われた場合にも、同じように答えるかもしれない。(しかし「幸福とも不幸とも言えない。ふつうだ」と答える人もいるだろうが。)
しかし、健康かどうか、あるいは幸福かどうかについて問われたのでなく、快適か不快か、楽しいか楽しくないか、あるいは苦しいかどうか、と問われれば、“明らかにわれわれの大多数は”ほとんどの場合、自分の現在の状態について「省み」たりせず、直ちにどうであるのかを答えると思われる。
トルクワートゥスはキケロー対して「ある苦痛がたまたまある快楽の後に続いて起こったのでないかぎり、快楽がなくなればそれによって直ちに苦しみが生起する、とは私たちは考えません。しかし、逆に、私たちはじっさい、たとえ、感覚を動かすような快楽が一切後に続かなくとも、苦痛が除かれることには喜びを感じます」(『善と悪の究極について』第1巻56節)と言っているが、私はこの説明を理解するのに何の困難も感じない。「苦の欠如は快楽である」というエピクーロスの主張を、何か特別な仕方で解釈する必要があるとは思われない。
食後の充足感、空腹が満たされて落ち着いた感じは、確かに、食べているときの舌に感じる味や食べ物が喉を通過する感じとは異なり、はっきりした感覚を与えない。だが「省み」なければ感じられないものでもないだろう。
また「苦の欠如状態は快である」は身体的な苦についてだけでなく精神的な苦(恐怖や不安)についても言える。受験生は合格発表をみてそれまでの不安がなくなったときに、「省みて」始めて、喜ばしい気持ちになるだろうか。すぐに喜びで跳びあがるのではないか。(ただし、後でもっとはっきり指摘するが、ロングは精神的苦痛についてほとんど考察していない。)
ロングのように「省みる」という観点から解釈しても、エピクーロスの「苦の欠如は快である」という主張が明らかになるとは思われない。
ロングは「快楽がすべて感覚とみなされるのが当然だ」とは書いていない。しかし、どちらかといえば彼は、そう考えているから、「われわれ大多数」が「苦痛も快楽も感覚することなく過ごしている」「事実」を持ち出し、苦の欠如は快であるとするエピクーロスの快楽論を「まったく意味をなさない」と決めつけることができるのであろう。
ふだん「われわれ大多数」は快楽と苦痛を「感覚していない」という事実からすれば、快苦どちらとも感覚されない中間状態がある。そして、当然ながら「われわれ大多数」はそのような状態に対しては関心を持たず、無頓着の態度をとっている。エピクーロスは快と苦のどちらでもない中間状態を否定し、苦の欠如は快であると「誤って」主張している。こうしてロングは「エピクーロスの誤りは、物事に対する我々の気分や態度のうちには、無頓着という語によって特徴づけられるものもあるという事実を見落とした点にある」という文でこの段落をしめくくる。
しかし、私はこうしたロングの解釈、説明に到底納得できない。
さて、ロングは、次の段落で、エピクーロスの快楽に関する「分析は、快楽は生きているものにとって自然的ないし正常な状態とは、身体的・精神的に健やかな状態であって、この状態はまさにそのこと自体によって喜びを与えるという想定に基づいている」と言う。
苦の欠如と快の同一視、苦と快の中間は存在しないという主張は、「われわれ大多数」の快楽の感じ方に照らしてみれば「意味をなさない」間違ったものだが、それでも、エピクーロスが快楽は「省みる」ことにより判断される心身の状態だと考えていたとすれば理解できなくない、とロングは考えている。つまり、エピクーロスは心身の正常な状態である健康は、それ自体快楽であり、感覚にはっきりと感じられなくても、自分が健康であるかどうかは、「省みる」ことによって知られるとエピクーロスは考えている、こうロングは言おうとする。
そこで、すでに上でふれた enjoy good health という 英語の言い回しが引き合いに出され、英語で健康を楽しむという語法があるからには、健康はenjoyされるものであり、したがって健康状態を指して、実際に喜びを「感じて」いるかどうかにかかわらず、喜びを与えるもの、つまりは快楽だと呼んでも、「語法として」は完全に恣意的であるわけではない、とロングは言う。(これはもちろん、実際にエピクーロスが、健康状態はenjoyされるものであり、したがって喜びを与えるものだとして、快楽と健康を同一視したということ、したがってまた、苦の欠如を健康状態とみなし、したがって快であると考えたということの論証ではまったくない。エピクーロスがそう考えたとしても「語法上」は問題ではない、と言っているだけである。)
ロングはルクレーティウスが『事物の本性について』で「苦痛は、〔諸原子の〕自然的な構成のかく乱である。快楽は諸原子が身体内の適切な位置に復帰するときに経験される」と書いていると(記憶に基づいて?)言い、それを、エピクーロスが健康と快楽を同一視したことの証拠とみなす。だが、ロングが参照するよう求めている同書の個所、第二巻963-968に書かれているのは「苦痛が生ずるというのは、〔肉体の〕素材の原子が何らかの力を加えられて---各自の位置において、振動を起こしているときのことであり、原子が再び元の位置に戻ってくるときが、甘い快が生ずる」(『物の本質について』岩波文庫、p103)ということである。
これは「動的快楽」についての説明だということはできる。しかし、原子が元の位置にあることが「自然で正常な状態であり、それ自体快である」という趣旨のことは全く言われておらず、「静的快楽」ないし「苦の欠如」についての原子論的説明はない。
つまりエピクーロスの快楽論は、心身の健康状態は感覚によって感じられなくても、「それ自体によって喜びを与える、という想定に基づいている」というロングの主張は成り立たない。したがって、また、前の段落で彼が提出した、エピクーロスがいう快楽は(感覚で感じられるものではなく)「省みる」ことにより、知ることのできる、自己の状態のことだ、というロングの「解釈」も正しいものだとは言えない。
だが、そもそも、快とはなんであるのかということについてエピクーロスが原子論=自然学に基づく説明を必要と考えたとは思われない。快は人々が、実際に、すべての行為に際して求めている喜ばしいものであり、しかも多くの場合、現に感じられている苦を解消することによって実現されるものである。おそらく「身体の正常」な状態である「健康」とも関係があるであろう。しかし、エピクーロスは『倫理学』のなかであるいはディオゲネス・ラエルティオスオによって伝えられている弟子たちにあてた倫理的な教えのなかで、身体の健康を原子の適正な配列によって説明する必要も、また快楽をそれに付随するものと説明する必要も感じなかったのではないか。
とにかく、メノイケウス宛の手紙と「主要教説」において、エピクーロスは、そのような説明は一切おこなっていない。
この手紙の中で、「あっさりした味のものでも、それによって欠乏による苦痛がすべて取り除かれるなら、贅沢な食事と等しいだけの快楽をもたらしてくれる」130、というように快苦はふつうに経験できることの範囲で述べられており、食事によって得られる快楽は「健康」=「正常な状態」との関連で説明されてはいない。
行為に先立ち快楽を求める働きである欲望についても、同様に、「自然的欲望」を「生物の正常な状態」あるいは「健やかな状態」と関係づける説明はない。「充足されなくても苦痛へと導くことのないものは必要(不可欠)なものではない」(148)。単なる想念によるのでない欲望が自然的欲望で、自然的欲望のなかに必要な欲望とそうでない欲望があるとされる(149)。
前に引用した、トルクワートゥスが快楽には動的快楽だけでなく静的な快楽もあると述べているところでは、前者は「ある種の喜びとともに感覚によって感知される類のもの」、後者は「すべての苦痛が除去されたあとに感知されるもの」と言っている。後者の「静的快楽」については、「感覚によって」とは言われていないが、同じく「感知される」と言っており、単に理論的=原子論的に想定される「正常な」「自然状態」だとも、反省によってはじめて肯定的(「幸福である」、あるいは「何かを楽しんでいる」)と判断される何かだともされていない。
ロングが「人々の無頓着を見落としたエピクーロスの誤り」を語ることができたのは、彼が「快楽がすべて、ある種の感覚とみなされるなら」、「明らかに、われわれの大多数は苦痛も快楽も感覚することなく、覚醒時の大半をすごしている」と考えるからである。しかし、それは間違いである。
まず、快楽と苦痛がすべてある種の感覚だ(とすれば)という想定に問題がある。身体的な快苦については、一見、感覚だと言えそうである。しかし、死や神罰に対する恐れ、衣食住に関する悩みや心配などの精神的な苦を「ある種の感覚」とみなすことは無理である。快と苦には身体的なものばかりでなく精神的なものも多く、覚醒時の大半を多くの人が苦痛も快楽も感じることなく過ごしている、とはとても言えないはずである。そしてエピクーロスは精神的な快苦の方が身体的なものよりも大きいとも言っていた。ロングは精神的な快苦について考えることを忘れている。これではエピクーロスの快楽論の適切な解釈/説明は無理である。
また、身体的な快苦に限っても、「大多数が」「覚醒時の大半を」苦痛も快楽も感覚せず(感じず)に過ごしているとは到底言えない。なるほど若くて身体が頑健である人たちは、ふだん、身体について苦を感じない。怪我をしたり、激しい運動で筋肉を酷使したりをしたりしたときには手足に痛みが起こるが、それが治れば、再び、手足は「何でもない」状態に戻る。そこで、頑健な身体をもつ人々は、ふだん、身体について「何も感じない」ことが多い。
同じように、空腹になったり喉が渇いたりした時を除けば、(健康な)人は自分の身体の状態について意識することがほとんどなく、空腹や渇きの苦が生じても、食事をし水を飲んでそれが収まれば、その後は、再び苦も快も感じない。こうして人はこの中間状態に「無頓着」の態度を取る。ここまではロングの言うとおりである。
しかし、生まれつきの障害を持っている人、あるいはまた事故などで障害を負った人、病弱な人、年を取り体力低下や体の不調などに悩んでいる人など様々な人が存在し、大多数の人が自分の身体について、ほとんどの時間、何も感じないで過ごしているとは言えない。
ある人々は無頓着で何も感じないが、他の人々にははっきり感じられるものの例として、気候についての快苦を考えてみる。
日本では、冬は寒く暖房なしで過ごせる人はほとんどいないであろうし、夏は暑く、熱中症で死者も出るほどであり、冷房も扇風機もなしで過ごせる人は少ないであろう。どちらも元気な若者を除けば、苦の季節だといえるだろう。その中間にある春と秋は暑くも寒くもなく、快適な季節だと感じられる。
冬の寒さ、夏の暑さは苦である。春と秋はきわめて快適である。では、暑さ寒さの苦を感じないが、また快適とも感じない「中間的」な時季があるだろうか。私はないと思う。寒さの苦を我慢しながら迎えた4月あるいは5月は快適に感じられる。そして5月を(さわやかで)快適と感じた人はそのあとの梅雨のじめじめした1ヶ月を苦痛に感じ、また梅雨明け後の真夏の暑さを苦痛に感じるだろう。
しかし、エネルギーに満ちていて冬の寒さ夏の暑さが平気な若者、あるいは勤め先でも家でも冷暖房完備の生活を送る人は、ほぼ一年中、暑さ寒さについては何も感じず、快でも苦でもない「中間状態」にあると感じるだろう。
また、四季がはっきりとせず、温暖で気温の変化の小さい国や地域に住んでいる人々は、ふだん気候に注意を向けることが少なく、たいてい快でも苦でもない中間状態にあると感じており、たまに異常気象などで猛暑やひどい寒波に襲われたときにだけ苦痛を感じ、その異変が過ぎ去ればまもなくその苦は忘れるのだろう。
だが、四季のはっきりしたところに住む、(若者と完全空調の生活を送る人以外の)人々は暑さ寒さの苦を感じるが、またその間の時季には苦の非存在とともにはっきりとした快を感じる(ことができる)。
こうして、気候に関しては、特定の年齢の人(つまり若者)、特定の経済的・社会的階層にある人、特定の国や地域に住む人は、年間を通して、また一日を通して、快も苦も感じず、無頓着の態度をとる可能性が大きい。しかしそうであるのはそれらの人々が様々な特定の条件の下にあるからであり、彼らがそう感じていることのゆえに、苦痛の欠如状態(春や秋)が一般に「苦でも快でもない」状態とは言えない。そして、実際に苦の除去、苦からの解放、苦の非存在が喜びであることは気候以外の様々な経験的事実からも知られる。
空腹や渇きについては、中近東における現在の戦争難民、日本の敗戦/終戦後の食糧不足時代の日本人、特に戦争孤児、また現代日本において親の虐待によって満足な食事を与えられない子供たちのように、長期間の飢え(と渇き)に苦しんだ場合には、ともかく水を十分に飲めて、ある量の食物にありつけたとすれば、それによる「動的快」も大きいが、飢えと渇きが治まった後の充足感、安堵感、精神の落ち着きは「何でもない」ものでは決してない。苦が長時間続いた場合にはそこからの解放感とともに「苦の欠如」状態の享受は強い喜びの感情を与えるはずである。
また、現代でも確かな治療法がなく、発症メカニズムも明らかでない、「神経因性疼痛」と呼ばれる一群の痛みが存在する。怪我など組織の損傷が起こす炎症から発生する痛み、「侵害受容性疼痛」と違い、消炎鎮痛薬や麻酔性鎮痛薬は効かず、長期間、強い痛み、痺れなど不快な症状が続く。11) 私の場合には一年以上続いた。デイヴィッド・B・モリス/渡辺勉、鈴木牧彦訳『痛みの文化史』(紀伊国屋書店、1998)によれば、NIH(米国国立衛生研究所)などの報告書で、 1983年に、9千万人が慢性の痛みに悩んでいる。これは人口の3分の1に相当する。また、下背部の(強い)痛みだけで500万人(人口50人に一人)の 患者がいるという。相当な数の人が、メカニズムの解明されていない「難治性」の痛みに取りつかれていると推測される。
私は、67歳になった年に、内臓疾患や頚椎の歪みのようなはっきりした原因なしに、慢性的な肩と腕の強い痛みに取りつかれ、断続的に、日夜、悩まされるよう になった。ぎっくり腰のように、体を動かすことが激痛を引き起こし、安静にしているしかないという痛みとは全く異なり、腕や肩を動かすことは自由にでき た。どちらかといえば動かすほうが気持ちがいい。打撲による痛みや疲労による筋肉痛などの場合には、その部位に触れたり、動かしたりしなければ痛みはほと んど感じず、また感じられる痛みは鈍い痛みであり、貼り薬や塗り薬がよく効く。しかし、この痛みは、焼けるようなジリジリする感じ、あるいは電気を通され ているかのようなビリビリとした感じを伴う痛さで、サロンパスなど、従来愛用していた腕や足・腰の痛みに効く市販の貼り薬や塗り薬は全く効かなかった。
筋肉痛の場合には、お風呂に入り痛む部分を揉むと、次第に痛みが取れてきて、その効果は持続する。だがこの腕と肩の痛みは、熱めのお風呂に入ったりヘ
アー・ドライアーで温風を当てると痛みが和らぐがそのときだけある。お灸も効くが、やはり痛みが止まるのはせいぜい30分か1時間くらいの間だけだった。
患部を指で押したり、手のひらでつかんで揉むと痛みが和らぐが、やはりそのときだけである。鍼灸院で小さな針の植わった貼付用チップをもらった。これは効
き目があったが、知らずにはがれ落ちることがあり、落ちているのを踏んだりしては危ないので使うことをやめた。一日中、患部を指圧したり揉んだりしている
ことはできないし、一日中風呂に入っているわけにはいかない。背中のお灸は人に頼まなければできない。市販の「お灸膏」という刺激の強い小片の貼り薬が最
も有効だと感じられた。
数ヶ月経過した頃近くの整形外科に行ったが治らない。慢性的痛みの治療法の一つにペインクリニックの専門医がおこなっている「神経ブロック」注射というも
のがあるが、新聞のある記事では、痛みが「ほぼなくなった人は3割」という。また、副作用も気になり、もう少し我慢しようと考えた。
もっとも悪い状態のときは、断続的ながら昼も夜も痛んだ。夜中に何回も目が覚め、目が覚めると同時に肩や腕の痛みを感じた。昼間起きているときよりも、就 寝し、仰向けになると、肩甲骨の周辺が体重で圧迫されるためらしいが、余計に痛みが増すようである。(枕の高さで痛み具合が違う。理髪店ではひげを剃ると きには椅子を後ろに倒すが、このとき頭はやや後ろに反るようになり、肩に椅子の背が直接当たるためであろう、痛くて我慢できず、床屋でひげを剃ってもらう のはやめた。)夜、目が覚めるのは痛みのためかもしれない。目が覚めた時にトイレに行く。この痛みにとりつかれるまでは再びすぐに眠れた。しかし半年以 上、痛みのせいでなかなか眠れなかった。転々と体の向きを変えて痛みが少なくなるように加減するが、ある姿勢がよさそうだと思ってもそのまま入眠する前に 再び痛んできて眠れない。時々、柱時計がなるのを2回聞くことがあった。つまり1時間以上布団の中で、もぞもぞと体を動かし続け、やがて、たぶん、疲れと 眠気が痛みを上回ってやっと眠ることができる。朝、目が覚めたときにも疲労感があり、眠気が残っているが、そのなかで痛みを感じる。30~40分、痛む肩 や腕の右手が届く箇所を押したり握ってみたりしてマッサージしているうちにようやく起きようかという気になる。
昼間、エアコンの冷たい風が当たると激しく痛んだ。しかし、冷気が悪いのではないようだ。真夏、町の中を自転車で走ると熱風が当たるが、この場合にも強い 痛みが起こる。そして、冬、帽子とマフラーを着けて肌の露出を少なくして走っても同じだった。船で釣りに出る。船が走り出し、風が当たると、ズキンと傷 む。外出するとたちまち腕が痛くなる。自転車に乗っているときには痛む左腕でハンドルを握り片手で運転し、右手でその腕をギュッと掴んでいると痛みが抑え られる。昼間、室内でエアコンの風に直接当たらないようにして、PCに向かって文章を書いているときにはほぼ百パーセント痛みを感じない。
24時間休みなく痛むというのではないが、生活の中で時々痛みが起こるというよりも、痛みが生活の全体を支配しており、強く痛まないときにもその影が付き まとっているように感じた。5、6年前に経験した急性の激しい腰痛(いわゆるぎっくり腰)では、ときには息をすることさえやっとで、2、3日、家の中で動くこともままならなかっ たが、そのときのように、痛みに完全に圧倒されてしまっているという状態ではない。しかし、断続的だが、繰り返し起こる、痺れと混じった痛みは、私を全く落ち着かない気分にさせ、強い不快感、苦しみを与えた。
この痛みは発症後8ヶ月くらい経った頃から軽くなり始め、あまり痛みを感じないで過ごすことのできる日が次第に増え、1年を過ぎてからは、昼間は全く痛ま ず、夜、寝ていて痛みを感ずることがたまにある程度になり、ほぼ全快したと感じた。ただし,その4ヵ月後、夏、釣りで無理をした(数日続けて、重い錨を何 度も上げ下ろしした)せいか、あるいはそれまで1カ月以上、家の中か図書館でデスクワークばかりしていたのに急に屋外に連日出ていたせいか、突然、再発し た。夜、寝ようとすると痛み、寝にくかった。ただし、痛みや痺れなど昼間の不快感の程度は、悪かった時期と比較して半分程度であり、2~3週間で治まっ た。
内臓に病気があるとき、しばしば病変のある場所から離れた皮膚に痛みを感ずることがあり、関連痛と呼ばれている。たとえば横隔膜の炎症による痛みをしばし
ば肩に感ずる。その理由は、横隔膜からの痛みを伝える神経繊維と肩の皮膚からの痛みを伝える神経繊維とが同じ高さの後根を経て脊髄に入り、その後角の同じ
ニューロンを興奮させるためである。狭心症の痛みを左側胸部、左肩、左腕の内側部などに感ずるのも同様な理由のためである、という。DVDROM平凡社、世界大百科事典。
私は、腕と肩のつよい痛みに苦しんでいた時期に、大きな病院にいき、心臓、腎臓、肝臓などの精密検査を受けたが異常は発見されなかった。私の左肩から腕にかけての痛みは、内臓の病気による関連痛ではないと思われた。
私の痛みは24時間あるいは眠っていて意識のない時間を除いておよそ16時間、ずっと続いていたのではなく、断続的であった。そして、このしつこい痛みがはじまってから間もなく、覚醒時、痛みを全く感じないでいられるのは、パソコン(ワープロ)に向かって、考えながら文章を書いているときだということに気が ついた。正確にいうと「忘れている」のではなく、その間は痛みがないのである。PCで文を書いているときにも時々は休むが、そのときに腕や肩が痛むかどう か意識をそこに向けてみても、すぐに痛みが「思い出され」、痛みを感じるということはなかったからである。
釣りをしているときには、右手で糸を持って当たり(魚信)を待つが、この場合には左の腕・肩はほとんどいつも痛んだ。痛みを「紛れ」さすために、肩をコックピットの手すりに押し付けたり、こすりつけたりした。魚が掛かって両手を使って糸を手繰るときには、たいてい痛みを「忘れる」。魚を取り込み終えて、次の仕掛けを入れて腰を下ろすと再びすぐに腕が痛むのを感じた。魚を掛けたときには、瞬間的に突っ込んだりするなど変化する魚の泳ぎ方に合わせて糸の手繰り方をすばやく加減する必要があり、その間の意識は手の動かし方に集中している。しかし、それ以外の時間、とくに当たりを待っている間は、意識の集中は全く 必要ない。
キーボードを打ち、文章を書いている時と魚を釣っている時とでは、意識の集中度が違うように思う。私はキーボードを見ずに早く打つやりかたはできず、画面 と手元を交互に見ながらしか入力できないため、指を動かすことにもかなり神経を使う。そして、文の内容、論理を考え、文章を推敲する。ときどきは休憩もし ながらこのようなPC作業を行っている昼間の間中ずっと痛みがない。だが、釣りするときには体は動かすが、ものを考えるということはほとんどない。そして 体はほぼ反射的に動く。
エピクーロスは生涯の最後の2週間を尿道結石で苦しんだ。彼はその「度を越えた苦痛」に、弟子のイドメネウスと交わした「対話を思い起こすこと---〔による〕魂における喜びを---対抗させ」ることによって耐えたと手紙に書いている。私も過去の釣りを想起しつつこのエッセーを書いている間だけ、腕と肩の
つよい痛みを全く感じないでいられた。
PCに向かって文章を書くことで痛みが消えた私の経験と弟子と交わした過去の哲学的会話を思い起こすことで痛みを抑えることができたエピクーロスの経験
が、同じメカニズムで説明できるとすれば、それは次のようなものであると思われる。恐らくエピクーロスも昔の哲学的な会話を思い起こす際には、その論理的
に進められたであろう会話の内容を想起し、たどることに意識を集中したであろうと考えられ、会話を思い出すことの「快楽」が現在の痛みと打ち消し合った、
というのではなく、痛みとは別なことに意識が向けられ、その意識の集中の度合いが強いことにより、痛みが感じられなくなった、というのが私の考えるメカニ
ズムである。
精神的な快苦については、とくに現代社会では、ロングが言うのとは反対に、むしろ、大多数の人が何らかのストレスを抱え、苦を感じていると思われる。不登校の子供はもちろん、学校に通う子供たちでも、親や教師との関係について、クラスメートとの関係について、成績について、悩みがないという子供はどれだけいるだろうか。中学生や高校生の場合には、何年も、決して楽しいとは言えない受験勉強のストレスに耐えなければならない。会社勤めをしている人々のなかで、出勤時間に遅れないようにすることや、「業績を上げる」ことや、職場の人間関係にストレスを感じないでいる人がどれだけいるであろうか。
これら精神的な原因による悩みや苦しみは年齢を問わず日常、広くみられることであり、快楽と苦痛は「ある種の感覚」という恣意的前提に基づいて、快苦から精神的なものをすべて排除するのでなければ、ロングのいうことは決して事実ではない。これらのストレスの存在に「無頓着」な態度をとっていられる人がいないとは断言できないが、いたとしてもきわめて少数であろう。
現代社会で、精神的なストレスを感じずに過ごしている人はほとんどいないということは確かだが、エピクーロスの時代にも、災害や戦争に巻き込まれたり、重い病気にかかったときのような、激しい恐怖や強い不安ばかりでなく、現代でいうストレスのようなもの、日常的な悩みや苦しみ、不安、心配のような精神的な苦は広く存在したと思われる。
当時の庶民が毎日飢えや渇きに苦しんだとは言えない(「自然本性が求める富はかぎられたものであるし、容易にえられるものである」DL144)が、水道が引かれていたわけではなく、スーパーやコンビニがあるわけでもなく、衣食住に関する日常的苦労、心身の苦労が様々にあったと考えられる。
ロングは当時の庶民の衣食住の苦労については何もふれていないが、当時の社会的歴史的状況の中で人々が「迷信や偏見やまことしやかなイデオローギー」により精神的な「不安」にさらされていたことには触れている(p100)。人々は日常的に様々な精神的な不安の中にあったと考えられる。
以上のことを踏まえれば、当時のアテーナイの人々であれ、現代の人々であれ「覚醒時の大半、苦も快も感じていない」とは言えないはずである。
したがってまた、「エピクーロスの誤りは、物事に対するわれわれの気分や態度のうちには無頓着という語によって特徴づけられるものもある、という事実を見落とした点にある」とするロングの非難も間違っている。むしろ、快楽と苦痛には身体的なものだけでなく精神的なものもあり、精神的な苦痛は古代ギリシャ世界にもまた現代世界にも存在し、多数の人が苦しみを感じたし感じている事実を見落としているロングの誤りこそが指摘されるべきである。
エピクーロスは死や神罰に対する人々の恐怖や強い不安は「誤った想念」によるものだと言っている。精神的苦は「想念や判断」によって生まれるが、その想念や判断が正しいかどうかが問題になるかもしれない。
現代人が抱く不安や恐れのすべてが、「科学的」で正しい根拠に基づくものだとは言えないと考える人もいるかもしれない。エピクーロスの時代、庶民の多くは、死後に魂が神から受けるという永劫の罰を恐れていた。これらは現代科学に基づく一般常識からすれば、あるいは当時においても鋭い知性を供えた人から見れば、誤った想念によるものである。とはいえ、その想念は、当時流布していたであろう、人間の魂や、天体や神々についての一般的な知識に基づくものであっただろう。
現代社会における不安、精神的な苦について、たとえば、2015年現在、再稼動予定の原発の敷地に存在する断層が地震を発生させる確率の高い活断層かどうかをめぐって、原発推進派の科学技術者・研究者と核の利用に慎重な科学技術者・研究者の間で意見が対立している。
そして、核施設の安全性を審査する現在の原子力規制委員会の前身というべき(旧)原子力安全委員会を構成した学者・研究者たちの多数は東京電力福島原子力発電所の建設について大地震発生と津波襲来のリスクを明らかに低く見積もっていたということは厳然たる事実であり、多数派の科学者、専門家の判断が正しいと言えないことは明白である。12)
以前とくらべれば原発の安全審査はより厳しく行われているようにみえるが、だからといって事故が起こらない保証はなく、いったん重大な事故がおきれば、発電所の近くの多数の人が生命の危険にさらされるだけでなく、そこでの生活を破壊されその土地を追われることになるということについて、人々が大きな不安を感じているのは当然なのである。
「クーンのパラダイム論はアカデミックな基礎科学研究の世界における党派的思考の特徴とその背景について述べたものである。しかし、パラダイム概念は、---技術者集団(及び、その統率者たる官庁・企業)の推進する開発路線の特徴を表現するうえでも有効な概念である。科学研究に関するクーンの議論を転用して言えば、技術開発におけるパラダイムとは、その専門分野における正統な問題と方法が何であるかを定めるものである。
たとえば高速増殖炉開発の分野では、正統な問題というのは、高速増殖炉の実用化という目標の実現のために解決すべき問題であり、また方法は、この分野で妥当性が認められている自然科学的・工学的手法である。そこではたとえば歴史家による高速増殖炉開発の批判的研究(本書のようなもの)は、問題と方法の双方において自動的にパラダイムの枠外のものとみなされる。
高速増殖炉開発集団のパラダイムの根幹にある「中心的信念」は高速増殖炉の実用化は実現可能である」という信念である。この信念の妥当性を弁護するために、有利とおぼしきあらゆる「蓋然的な根拠」が総動員される。それらの大部分は脆弱なものであるが、不確定な未来に関する言明を含んでいるためにそれに対する完璧な反証は不可能である。---それは宇宙人やUFOが存在しないことの完璧な科学的論証ができないのと同様の事情による。---〔この〕信念のもとでは「もんじゅ」のナトリウム漏洩火災事故や、欧米諸国での高速増殖炉のさまざまな事故は、高速増殖炉開発可能性の乏しさを示す決定的な出来事とはみなされない。---あらゆる不利なデータが彼らの心の中で「決定的でない」として退けられ、それらすべてが「解決すべき課題」(しかも解決可能な課題)として認識される。最悪の場合には不利なデータは改ざんされたり秘匿されたりする」と吉岡は言う。305-6p
このような「パラダイム的思考」に立つ「科学技術者」の態度は、原子炉や核関連施設を実際に設計し建設を行う技術者だけでなく、その安全性を審査する委員会、あるいは原子力政策の推進に関わるもろもろの審議会の委員である大学教授など科学技術者の大部分に支配的なものである。
また吉岡によれば「90年代半ば頃まで、原子力発電の経済性は化石エネルギーのそれを上回るといわれてきたが、90年代末現在、原子力発電はコストは高いが安定供給に優れている、というのが関係者の共通認識となっている」p315という。 70年代に建設された福島原発をはじめとする原発が「経済性」を理由として作られたとすれば、安全と防護のための設備に十分な金をかけようという意識は薄かったとしても不思議はない。こうして「科学者」からなる安全審査に関わる委員会の委員の多数は巨大地震の発生と津 波襲来のリスクを低く見積ったまま建設許可の判断を下したであろう。近代以降の社会が、中央集権的な国家とその諸制度を作り出し、科学技術や産業を発展させたことによって、それ以前の社会の人々の労苦や病苦、及び「誤った 想念」にもとづく精神的な苦痛などさまざまな苦を減らした面があることは確かだと思われる。だが、寿命が延びたとはいえ人間がまぬかれることのできない老 いと死についての「想念」は相変わらず大きな悲しみや苦しみを与える。また多くの病気が治って当たり前と感じられるようになるに連れて治りにくいがんのよ うな重い病気に罹ることは、昔の人々が結核やその他の、同じように治りにくい、重い病気に罹ったときに感じたであろうよりずっと強い不安を与える。病気も 大きな苦しみの原因であることに変わりはない。
すべての労働が、事故を起こした原発のなかで行われているような高放射線下の過酷な作業であったり、あるいは地下深いところで落盤や溢水事故に会うことを恐れつつ行なう作業のような、ひどい苦役ばかりではない。そして、誰もが労働せずに暮らしていける社会はユートピアでしかないのかもしれない。また一部のエリートだけでなく、かなりの人が仕事の中で自己実現の快を見出しているのかもしれない。
しかし、一般的には、労働がまず生活の必要から行わなければならないもので、しかも、多くの場合他人の指揮・命令にしたがって行わなければならないものであるかぎり、慢性的なストレス、精神的な苦を与えることは確かなことだと思われる。他者の指揮・命令を受けず、収入の心配をすることなく、快適な職場で自分の知的あるいは芸術的関心のおもむくままに、つまり苦痛なしに仕事に打ち込めるごく少数の人は幸いである。
また、女性の場合には(共稼ぎの家庭であっても)夫からの協力を得られずに家事、子どもの養育、老人の介護を一人で引き受けているケースが多い。仕事と
「家庭」を両立させるために女性は過大なストレスを抱え続けている。
第二章で詳しく述べるつもりだが、N.エリアスは『スポーツと文明化』において近代社会の「文明化された」、規則正しく計画的で抑制された生活様式が、自然的感情の自由な表出を許すスポーツを一種の社会的安全弁として生み出したのだという。プロ野球やプロサッカーなどを興奮しながら観戦し応援する楽しみがストレス解消に役立ち、人々の精神の安定と社会秩序の維持に役立っているというのである。
現代社会には他にも無数といっていい「多様な」快楽が存在する。人々は様々な娯楽・エンターテインメントと、アルコールやグルメやある種の薬物から得られる快楽を動員することで、自分たちが抱えているもろもろの精神的ストレスに耐えているのだ。
ロングの解釈によれば、エピクーロスにおいては快苦は直接的に感覚によって感じられるものではなく「自らを省みて」なされる一種の判断と考えられている。「省みる」ということからすれば「思考」の働きだということになるかもしれない。しかしエピクーロスは、行為選択に際して「勘考」や「思慮」が重要だとは述べているが、思考が快苦を感受し判断する働きだとはしておらず、人間は感情によって快苦を感知・判断するのだと言う。
エピクーロスにおけるこの区別を明らかにする前に、感覚と感情とは何であるか、両者の違い、両者の関係について私見を少し述べておこう。
外界からの、また身体自身の状態についての情報を欠いては生物は生存できない。それらの情報を取り入れ、(それらを整理したり、蓄積したりする魂つまり脳に)伝達する装置が感覚器官であり、そのコンテンツが「感覚」であると思われるが、生物は、単に、「客観的な」情報を獲得するだけでは生存することはできない。生物が外界と身体の情報を得るのはそれらと自己との関係を調節するためであり、危険な事物・状態は避け、有益な事物・状態は獲得したり維持したりするためである。
感覚はそのまま行動に直結するのではなく、コンテンツは加工されるべき素材として短時間「保存」あるいは「保留」され、その間に感覚とは別のもの、快苦/好悪の感情に転化される。人間が行う選択と忌避の出発点は、感覚がもたらす外界・身体についての直接的情報(コンテンツとしての感覚)を自己にとっての良いものと悪いものに分かつ(区別する)こと、つまり一種の判断にある。良し悪し、好悪、快不快の判断は価値判断である。
そして人間は一般に「身体的諸感覚がもたらす快楽や高揚の感情」など強い快苦の「感覚」を与えるものや状態について判断するだけでなく、微弱な情報しか得られない事柄や状態についても、良い/好ましい/望ましいものかどうか判断を行う。人間には対象の客観的な情報を与える感覚の働きとは別に、対象が私=主観にとって良い、好ましい、あるいは望ましいかどうかについての判断を行う働きがある。実際の行動は、こうした個別的な感情の判断だけで決定されるのではなく、さらに理性や知性によって
「勘考」がなされる必要があるが。
カントは第三批判書『判断力批判』の「序論」で、判断に、第一批判書『純粋理性批判』で扱ったような、対象の客観的な認識に関わる判断と、客観的認識ではなく、主観の快不快の感 情によって決定される(感覚・知覚を含むが概念による規定を欠いた)判断、すなわち「情感的判断」(訳語についてはこの段落の最後の個所を参照)の区別があることにふれ、さらに、第1章「美しいものの分析論」第一節~第五節 で、情感的判断を、対象の美しさに関する趣味判断、対象の快適さに関する判断、そして対象の善さに関する判断の三つに区別している。
快適さに関する判断は、対象が自分の気に入るかどうか、私がそれを好むかどうかの判断、しかもその対象の「現存」に対する「関心」、つまり、それを実現したい、実際に手に入れたいという気持ちを伴った判断である。人は各人の好みにより異なるものを、その都度の状況の中で、快適(うまい、心地よい)と感じつつ追求する。エピクーロスがいう快楽はカントの言う「快適なもの」である。
他方、趣味判断は美しさについての判断で、「たんに観照的」で、私がそれを欲しいと思うかどうかの「関心」なしに、かつ、すべての人に「賛同を要求する」、普遍妥当性を主張する判断である。
善さの判断とは、概念によって とらえられたことがらとの関係において対象が適合するかどうかについて、理性によってなされる判断で、普遍妥当性を要求する。善いものとは理性を介して概 念によって気に入る(たとえば、親切や勇気(の徳)は望ましい、あるいは好ましいなどと感じられる)ものである。何かのためによい(有用)ものと、そのも の自体よいものとがあるが、ともに、目的の概念、意欲に対する理性の連関を含んでいる、とされる。これら三種の情感的判断はいずれも対象に対する主観の 「適意」(気に入ること)により特徴づけられる。このようにカントは言う。
ところでカントは快適なものは「感覚のうちで諸感官〔感覚器官〕に満足をあたえるもの」だと言ったのに続き、すぐに感覚という言葉がもちうる二重の意味」について注意する必要がある、と言う。傾向性〔生物的・社会的欲望〕を規定する諸感官の諸印象も、意志を規定する理性の諸原則〔道徳法則〕も、あるいは判断力を規定する(時間空間の)直観のたんに規定された諸形式も、快の感情に及ぼす〔最終〕結果は同じであり、旨い料理も、正しい道徳的な行為も、美しい形も、感情においては、好ましい、うれしい、喜ばしいと言う満足感を与える。彼の考えでは、美しい形や道徳法則は感覚器官を刺激することなく、知的・精神的な満足感を与えるのである。
こうして、カントは「認識能力に属する受容性としての感官による」「感覚」と、「快不快の感情のある規定が感覚と呼ばれる場合」の感覚を区別する。そして「草原の緑色」は感覚器官によって知覚される客観的感覚で、対象の認識に役立つ要素となる。他方、「緑色の快適さは主観的感覚に属し」対象の客観的認識には役立たない。しかし、この緑色の快適さは「主観的感情に属し、対象はこの感情によって満足の客観とみなされるのである」と説明している。 第1章第三節。
カントがいう快適なもの(エピクーロス的には快楽を与えるもの)とは、感覚器官を刺激して満足感を与えるものだとされている。この点でカントは、ロングと同様に、苦の欠如、静的な快は感覚器官に(はっきりとは)感覚されないもので、快でも不快でもないものと見なすことになるかもしれない。しかし、「苦の欠如」状態は「主観的な感情」としては、快であると感じられることが可能であろう。
牧野英二訳『判断力批判 上』<カント全集>8、岩波書店、1999; 熊野純彦訳『カント 判断力批判』作品社、2015; 宇都宮芳明訳注『判断力批判』上巻(以文社、1994);原祐訳『判断力批判』<カント全集>第8巻 (理想社、昭和40年)
牧野訳「 美感的」はaesthetishの訳だが、熊野訳では「直感的」、宇都宮訳では「情感的」、原訳では「美感的」である。
牧野訳には注や解説がついており、私のような素人には助かる。熊野訳はカントの原文において言葉不足で意味の通らないところなどは語を補って訳してあり、読みやすい。宇都宮訳は原文に注釈がついており大いに役立つ。
エピクーロスの著作の中に『(真理の)基準(クリーテーリオン)について、あるいは基準論(カノーン)』という著作があり(DL27)、彼がそのなかで、真理判定の基準として、感覚〔アイステーシス〕、先取観念(プロレープシス)と感情(パトス〔情動、情念などとも訳される〕)の三つを上げ、それらについ
て論じていることを、デイオゲネス・ラエルティオスが伝えている(31-34)。また、「ヘロドトス宛の書簡」(37、38、48、51、52、53、55、62)、「主要教説」の24.などでも「真理の基準」に関して述べている。
それらによれば、感覚は、われわれの感覚器官が対象に直接に接触する〔痛覚、温覚など〕か、もしくは対象から発散・流出するその微小な粒子に接触する(視覚、嗅覚、聴覚)ことによって成立する。感覚はだからある意味で絶対的で、他の手段によって反論されない。知性・理性の判断は感覚によってその真偽が確認される、という。
「先取的観念」とは何らかの発言、主張がなされるとき、それが関連付けられている語に関して「最初に心に浮かぶもの」、「それ以上に何の説明も必要としないもの」のことだという。デイオゲネス・ラエルティオスは解説して次のように言う。「あの遠くに立っているものは馬であるか牛であるか」と問うような場合には、馬や牛は知られているものとして前提されねばならない(33)。エピクーロスの言葉では、先取観念が存在しないと、議論を積み重ねても何事も「判明にならなかったり、空しい発言をしたり」することになるという(37)。そのかぎり、先取観念とは説明を要しないものとして前提される語、あるいは事柄の観念のことだと思われる。恐らくそれも最初は「感覚」によって獲得されると考えられているのだろう。
快苦の判断の基準となる働きが感情(パトス)である。デイオゲネス・ラエルティオスによれば「彼ら(つまりエピクーロス派の人々)は、快楽と苦痛と言う、二つの感情(パトス)があると語っている。そしてこれらの感情は総ての生物に起こるものであり、その一方(の快楽)は生物に親近なものであるが、他方の(苦痛は)疎遠なものであるとしている。また、これらの感情によって、選択と忌避とは決定されるのだとしている」(34)。
「ヘロドトス宛書簡」においては「われわれは感覚にしたがって、そして---現前している直覚的な把握にしたって、すべてのことを観察するようにすべきである。同様にまた、(行為においては)われわれは現にあるところの(快・苦の)感情にしたがって何事をもなすようにしなければならない」(38)と言っている。
またすでに引用した文であるが「われわれは快楽を、われわれが生まれるとともに持っている第一の善と認めている---、そしてこの快楽を出発点にして、すべての選択と忌避を行っているし、また快楽に立ち戻りながら、この感情を基準にして、すべての善を判定している---」(129)と言っている。
ロングはエピクーロスを扱った第二章の第3節「認識論」では14ページを使って、今見た『カノン論』に関するデイオゲネス・ラエルティオスの記述と「ヘロドトス宛書簡」におけるエピクーロスの認識論について分析、解説を行っている。その中で彼は「エピクロスの認識論の基礎となるのは感覚的認識である。---〔しかし〕必ずしも諸感覚を引き起こすのは、知覚する者の外部に存在する事物である、ということにはならず、エピクロスは、空腹のような感じ(彼の用語ではpathos)には内的原因があるのを認めるであろう。〔( )内はロングの追加。〕しかし、色、音、臭いなどの感覚は、これらの属性をもつ現実のものによって引き起こされねばならないことは自明である、と彼〔エピクーロス〕は考える」と述べている。p33.
この文の中では、「現実のもの〔対象〕により引き起こされる感覚」とは別に、主観が抱く「感じ」(パトス)というものがあるとエピクーロスが考えていたことはほのめかされている。しかしパトスについてのロングのそれ以上の言及はこの「認識論」に関する節でもまた「快楽と幸福」に関する節でもみつからない。
パトスはストア派ではもっとも重要な意味をもつ語の一つである。ロングはストア派のパトスは「徳の試金石」の意味をもつものだとしている。「ストア派の知者は、あらゆる情動〔パトス〕から自由である。怒りや心配、---これに類した極端な情動はすべて、彼の品性のうちには認められない。彼は、快楽を善きものと見なすことも、苦痛を悪しきものとみなすこともない。---ストア派は、諸行為に伴う感情的な態度を、道徳的な品性を表す指標と見なした」、と言っている(p312)。
マルクス・アウレリウス、エピクテートスあるいはセネカなどローマ期のストア派においては徳を備えた知者(賢者)となること以上に、情動(感情)に動かされないこと=アパテイアが重視されている印象を受ける。そしてストア派と絶えず論争を行って覇を競ったエピクーロス(派)において、パトスは「快楽をよきものと見なし、苦痛を悪しきものと見なす」働きであった。どうしてロングがエピクーロスのパトスに触れないのか、不可解としか言いようがない。
エピクーロスは「ヘロドトス宛書簡」で真理の基準としての感覚については原子論に基づいて精しく説明しているのに対して、快苦の、したがって行為選択の判断基準というべき感情についてはごく簡単にしか触れていない。感覚について精しい説明を行っているのは、彼が、感覚は事物についての「直接的な証言」を与えるものであり、理性(推論)も「先取観念」もそうした最初の直接的証言を出発点にして初めて形成されるものであり、真理認識にとって感覚による直接的経験がもっとも重要な役割りを有しているということをぜひとも主張したいと考えたからであろう。
他方、行為の選択と忌避が快・苦の情念に基づいて行われるということは誰もが「生まれるとともに」持つ自らの経験により十分に知っていることだ、とエピクーロスは考えていたが故に、その精しい説明を行う必要があると思わなかったのではないだろうか。
ともあれ、注意すべきことは、快苦の判断は感覚ではなく感情の働きによって行われると、エピクーロスがはっきり二つの働きを区別している点である。
たとえば火に触れれば「熱い」と感じ、尖ったものが皮膚に刺されば「痛い」と感ずるが、大まかに言えば、これは客観的な感覚判断である。だが、感覚による客観的判断は必ずしも快苦の感情とは一致せず、したがって必ずしも忌避あるいは選択の指示を与えない。反射のような行動はここでは無視する。
鍼や灸による治療や指圧やマッサージを受けた経験があればわかることだが、灸なら(感覚として)熱くて我慢する必要があるが、しかし(感情として)気持ちがよいとも感じられ、鍼治療の場合なら少し痛いが気持ちがよいと感じられる。そして指圧では圧痛がそのまま気持ちいいと感じられる。感覚においてはそれらは「熱い」、あるいは
「痛い」。しかし、感情においては、感覚の証言から、また理性の判断からも独立に、快苦、好悪の判断が生じる。あるものがわれわれに快適と感じられるならば、そのものは確かに快適なものであり、好ましい。それが不快で嫌なものと感じられるならばそれは確かに不快で嫌なものである。(実際の行動を決める時に
は、知性による「勘考」や理性の判断が加わるにしても。)
今の例では身体の局所的な経験についての感覚と感情の働きかたの違いがわかる。皮膚で感じる気温や風が適度で心地よく感じられるが、足の筋肉が痛むというような、質あるいは内容の異なる複数の感覚ないし感情が同時に存在する時の、全身状態の「快苦」について考えてみる。
一方で足の痛みを感じるが、また、他方でさわやかな気分で快適であると、別々の二つの判断を行なうかもしれない。だが、多くの場合、痛みの感覚と「さわやかさ」の感覚/感情は、総合されて、わたしは「体の一部に痛みがあるが(それは何でもなく)、体全体は心地よい」、あるいは足の痛みは全く忘れて単に「体の調子はよい」という判断を下すだろう。わたしは、実際、ぐっすり眠れたとか朝の天候や気温が快適なものである時にはたいていこのように感じる。
一般に、全身状態についての感じ方、あるいは気分の快不快は、身体諸部分の局所的ないし個別的な感覚の寄せ集めによっては適切に説明できない。感情は身体の個別部位の感覚を越えて、体全体に関する総合的な快苦の判断を下すからであり、その際、判断は必ずしもロングの言うような「反省」なしに行なわれる。もちろんこうした態度や気分は、原子論あるいは現代の生理学などによる理論的な説明をなんら必要とせず、端的に感じられるものである。
おそらく、エピクーロス時代の人々にとっても、快と苦の感情(パトス)が選択と忌避に関する判断の基準だという考えは、精しい理論的説明なしで、日常的な経験を振り返ってみるだけで、十分に受け入れ可能だったのではないだろうか。エピクーロスによる精しい説明が(見いだされ)ないことについての私の推測の当否は別として、エピクーロスははっきりと感情と感覚を区別し、客観的な真理・事実に関わるのが感覚であり、主観的な快苦の判断を行うのは感情だとしているのである。ロングがどうしてこのことに触れないのか、きわめて不思議である。13)
ところがキケローは、次のようにも述べている。ギリシャ語のヘードネーとラテン語のウォルプタースは同一の内容を示す語である。しかしラテン語のウォルプ タースは「何らかの感覚が動かされて快さが感知される場合に用いる、つまり身体に用いるのが一般的な用法」で精神に用いる場合には「転用」である、と。 このキケローの説明によれば、ローマ人は、少なくとも精神的な快苦の場合と肉体的な快苦の場合とでは感受のされかたに違いがあると考えており、前者に関し ては必ずしも「感覚が動かされて感知される」とは考えていないことがわかる。『善と悪の究極について』、第2巻第4節13,14
ところがロングは身体的快苦と精神的快苦の区別にふれず、また精神的快苦についてはほとんどふれることなく、快楽と苦痛は感覚により感知されるということを当然のことであるかのように議論を行っている。
また、ついでに触れるが、キケローは、一方で、快楽と苦痛は感覚だと主張するが、他方で、パトス(感情とも訳されるが、ここでは出典の訳に従い情動としておく)についても論じており、情動・パトスを次のように説明している。 精神的な苦悩は肉体の痛みに極めて近いものである。そして、ギリシャ人は苦悩、恐怖、欲望、怒りなどを情動・パトスと呼んだと言い、さらに情動にはこれら否定的なものの他に、肯定的なものとしての喜悦などの情動もある、と言う。こうした説明に従えば、情動は精神的な快苦の感情である。
そして、情動は、人に起こるあるいは降りかかる自然・本性的な事実、できごと(たとえば病気による身体の痛み、家族の死という不幸な出来事)を核として、それに想念や判断(その出来事が将来どうなるかの予想、喜ぶべき/苦しんで当然だという考えなど---)が加わったものだと説明する。これはストア派の情動論に似ているが、ストア派は死や病気や体の痛みなどは悪ではないとし、それらを嘆き悲しんだり苦悩したりする情動はすべて誤った非理性的な想念と判断のみに起因すると説く。これに対し、キケローはそれらを悪と認める。彼は自然本性的な悪に想念と判断が加わったものが情動だというのである。『トゥスクルム荘対談』第2巻12節、第4巻27,28節
だが、ローマ人に限らず、快苦に比較的無頓着な人でも、決して心身の快苦のすべてが感覚だと考える人は少ないのではないか。 カントとほぼ同時代のベンサムは『道徳および立法の諸原理序説』で、功利主義の原理となる快苦の種類に関する詳細な説明を与えている。彼は「感情」と「感覚」を区別していない。彼は複雑な快楽も単純な快楽に分解することができるとし、「単純な快楽」の一つとして、飢えや渇きを満たす場合の快楽、味覚、嗅覚、触覚の快楽など9種類を含む「感覚の快楽」をあげているが、それ以外の単純な快楽として「富の快楽」、「名声の快楽」、「権力の快楽」、「記憶の快楽」、「想像の快楽」など13種類の快楽をあげている。また苦痛として、(飢えまたは渇きの苦痛など9種類の)「感覚の苦痛」のほかに、「不器用の苦痛」、「悪名の苦痛」、「記憶の苦痛」、「想像の苦痛」など11種類の「単純な苦痛」があるとしている。
こうしてベンサムは、「感覚」ではない「期待」や「想像」、「記憶」などから得られる知的・精神的快苦と感覚諸器官を通じて感じられる快苦とを区別し、後者を「感覚の快楽」、「感覚の苦痛」と呼んでいる。ベンサムの分類においては、快と苦の多くは知的・精神的なものであり、感覚諸器官を通じて直接感じられるものである身体的快苦は、快苦の一部をなすに過ぎない。
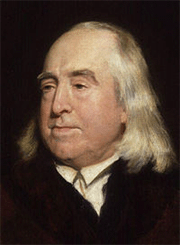 ベンサムは「感覚の快楽」の一つに「健康の快楽。すなわち、完全な健康と活力の状態、とくに適度の肉体的な運動に伴う内的な快い感情、またいわゆる精力の躍動」を挙げている。皮膚などの感覚からだけでなく身体内部からもさまざまな感覚情報が集まり、総合されて「健康と活力の状態」についての全体的判断がなされる、と考えられているのであろう。これは、エピクーロスの欲求充足後の「静的快楽」に似たものと考えることができるかもしれない。ベンサムは「感覚の快楽」としているが、これは感覚が元になって生じる「快い感情」である。『道徳および立法の諸原理序説』(山下重一訳『ベンサム J.S.ミル』<世界の名著>38、中央公論社、昭和42年)第5章
ベンサムは「感覚の快楽」の一つに「健康の快楽。すなわち、完全な健康と活力の状態、とくに適度の肉体的な運動に伴う内的な快い感情、またいわゆる精力の躍動」を挙げている。皮膚などの感覚からだけでなく身体内部からもさまざまな感覚情報が集まり、総合されて「健康と活力の状態」についての全体的判断がなされる、と考えられているのであろう。これは、エピクーロスの欲求充足後の「静的快楽」に似たものと考えることができるかもしれない。ベンサムは「感覚の快楽」としているが、これは感覚が元になって生じる「快い感情」である。『道徳および立法の諸原理序説』(山下重一訳『ベンサム J.S.ミル』<世界の名著>38、中央公論社、昭和42年)第5章
(写真はWikipedia)
結局のところロングは快楽という語をキケローが言うヴォルプタース元来の意味の肉体的な快楽の意味で考え、知的精神的快苦と考えなかったがゆえに、「感覚」と見なすことになったのではないだろうか。
ロングがエピクーロス哲学の解釈・解説の為に充てているページ数は全部でほぼ90ページである。が、エピクーロスが「最重要の事柄」と考えた「快楽と幸福」を扱う第9節には12ページが充てられているに過ぎない。
ただし最終節の最後の部分つまりこの章全体の結論部の2ページでは再び「快楽」の問題が論じられる。だがここにあるのはロングのエピクーロス哲学に対する批判=反論だけなのである。
古代哲学の研究者は幾分は哲学史家でもあるだろう。そして哲学史家の仕事は残っている資料に基づいて過去の哲学者の説の全体像を再構成して読者に提示することだけに止まるべきだとは思わない。哲学研究者としてその学説と対峙し時には反論を加えることもまた史家の仕事に含まれるだろう。しかし、エピクーロスの快楽論に関しては、ロングは説明が不十分なまま性急で不適切な反論を加えていると言わざるを得ない。
上では、エピクーロスの快楽論、とくにに苦の解消/欠如はが快である、快と苦の中間は存在しないという主張ついてのロングの解釈および批判が不適切であり、エピクーロスの主張が正当であることを、具体的な経験的事例を上げて説明してきた。簡単にまとめを行っておきたい。
ロングは彼の『ヘレニズム哲学』第二章第九節で、エピクーロスの快楽概念を分析して、次のように述べている。「もしも快楽がすべて、ある種の感覚とみなされるなら、快楽と苦痛のこの〔中間のない、矛盾対立〕関係はまったく意味をなさない。というのも、明らかにわれわれの大多数は、苦痛も快楽も感覚することなく、覚醒時の大半を過ごしているからである。」
BR>
こうした見方にロング自身も立っているためと思われるが、彼はエピクーロスの「苦の欠如は快である」を有意味な主張として解釈することをしない。あるいはできない。彼はエピクーロスのいう快楽は「自らを省みる」ことにより判断される、幸福/不幸、楽しんでいる/楽しんでいない」など自己の現状についての見方だという「解釈」を提示しているが、その根拠を何ら明らかにはしない。
また彼はエピクーロスは「自然的で正常な状態とは心身の健康状態であり、この状態はまさにそのこと自体によって喜びを与えると言う想定に立って、快楽を分析している」と言う。つまり、エピクーロスは快楽とは健康状態のことだと考えており、したがって、われわれは感覚においては快楽とも苦痛とも感じていなくても、「省みて」、健康状態を楽しんでいる、楽しんでいないかを判断し、不健康と判断されないときには健康だから、従って快楽の状態にあると判断するのだ、と考えている。
そしてこのことは物理的(自然学的)にはルクレーティウスの『事物の本性について』で外力による原子のかく乱が苦であり、そのかく乱から元の状態に戻るときに快楽が感じられるという説に表れている、このようにロングは言う。
しかし、彼はエピクーロスが健康それ自体を快楽とみなした、ということは示しておらず、またルクレーティウスも「動的快楽」についての原子論的説明を与えているだけで、「静的快楽」である苦の欠如が自然で正常な状態であり健康状態だとの説明は行っていない。
ロングが引き合いに出している「われわれの大多数は、苦痛も快楽も感覚することなく、覚醒時の大半を過ごしている」という事実も、感覚にはっきりとは感じられない状態に対して人々は「無頓着」の態度をとるものだというロングの見方も、多くの経験的事例によって反論され、苦の欠如は快であるというエピクーロスの主張を否定するものではない。また、快楽を健康と置き換え、「省みる」ことによって知られるものという解釈はロングの独断にすぎず、エピクーロスの快楽論の適切な解釈ではない。
快楽は確かに(すべて)感覚と見なすこともできないが、「省みる」というなにかあいまいな ある種の思惟によってとらえられるものと「解釈」することもできない。エピクーロスははっきりと快苦は感情によって判断されると言っているのである。
以上がこれまでの議論のまとめである。
さて、ロングが、エピクーロスの快楽の概念を解釈するに際して、(「苦の欠如」は感覚されないと考えるがゆえに)快楽を感覚と見る代わりに提出しているのは、今述べたような「感情」の観点ではなく、「自らを省みて」判断するという観点である。つまり、痛みがないときに人は普通、自分の状態には「無頓着」である。だが、あえて「自らを省み」自分の健康状態が良好であるかどうかを考えれば、人は自分が幸福であり快適な状態にあるかどうかを判断することは可能である。そうだとすれば「苦の欠如」状態についても快だと判断することは可能であろう。このように考えれば、常識に反する「矛盾対立関係」にあるエピクーロスの快楽概念を理解できなくはない。このようにロングは考えたのであろう。
しかし、エピクーロスは快楽は「生まれながら」知られるものだと言っている。理性や知性、あるいは思慮は経験や学習によって発達するはずであり、そのためにはある程度の年齢に達することが必要であろう。快苦の判断が生まれつき行われるものであるとすれば、赤ん坊や幼児に備わってはいない反省や理性・知性によって快苦の区別を説明するには無理があろう。
事物や状態ついての快不快の感情(による判断)は感覚とは区別される。だがまた快不快の感情は推論や論理的判断の働きを行う理性や知性の働きとは異なり、感覚と密接に結びついてもいる。感情による快不快や好悪の判断(区別)はなまの客観的な感覚そのものではないが、またそれとは別の働きである知性・理性に
よる反省によってなされる判断なのでもない。
感情は事物や状態についての快不快や好悪を理性・知性の介在なしに直接的に判断する。ベンサムは富、名声、権力、記憶、想像、等々の快楽を、また、敵意、悪名、記憶、想像、等々の苦痛を挙げていた(前注参照)。これらは熱さや痛さなどとは違い「感覚」されるものではない。だが、感情は記憶していること、想像されることなど、「感覚されない」精神的な事柄や状態に関しても働き、快不快、好悪、悲喜に関する判断を行う。エピクーロスの言う「誤った想念」による死や神罰に対する恐れや不安の苦も「感覚的な苦」ではない。同様に、感情は欲求が満たされた後の、感覚的にははっきりした感じのない、「苦の欠如」した心身の落ち着いた充足状態に関しても、直接、好ましい、快適であるという判断を生むことができる。
エピクーロスは、詳しい説明を与えていないが、彼が感覚と区別する感情の働きはおおよそこのようなものであろう。しかし、好悪、快苦の感情は赤ん坊ももつが、それは生育とともに環境の中で文化的に修正・育成されて、複雑なものになる。どんな味の料理を快(つまりおいしい)と感じるかは子どもと大人でははっきりと異なる。そして地域ごとに、国ごとに異なる。それ以外のことに関しても快不快の感情は生育と共に変化し、生育環境によって違ったように形成されるであろう。
たしかに蓼食う虫は好き好きであり、あるものが快であるのかそうでないのかを、一律の哲学的議論によって決定することはできない。だがロングはその格言の適用の仕方を間違えている。確かに、バラの強烈な香りを好む人がいて、「苦痛なしで強烈な喜びを与える経験」が可能な人生こそが幸福だと考える(ロングのような)人がいる一方で、必要な欲求を充足できたら「多様な」快楽の追求の必要を感じず、静かな安らぎの状態を好む人がおり、「精神の平静が最大の快楽だ」と考える(エピクーロスのような)人がいるのである。
だが、また、快苦は感情によって判定されるものではあっても、行為の選択・回避は快苦の感情に基づいてなされるわけではない。エピクーロスは、行為の選択に際しては、勘考=知性・思惟の働きによって、求める快楽が必要なものか、どうか単に空しい想いから求められていいるのではないかどうか、それを入手するのに要する労苦の大きさはどうか、「快楽と苦痛を相互に測り比べ利益と不利益に目を向ける」べきことを説いていた。長期的な視野に基いて総合的に評価・判断し、得られる快楽の総量を最大にすることにより、幸福を実現すべきだと考えられていた。そして、身体的苦痛と精神的な恐怖や不安を無くすることつまり心身の苦を無くすることによって最終的な精神の平静=苦の非存在状態に到達することが、エピクーロスの考えるところでは、総合的に最大の快楽を実現することになるのであった。
最近日本では短期的労働に就く(就かざるを得ない)人の割合が半分近くになろうとしているようだが、それでも、多くの人は就職先を選ぶときには長期にわたる勘考を行うだろう。しかし、仕事が決まった後は、せいぜい1年くらいのスパンで日々の活動における様々な選択と忌避の勘考を行うのではないだろうか。
だが幸福は生の全体についての概念であり、1年間は幸福だったとか、これからの5年間程度を幸福に暮らしたいなどとは言わないであろう。したがって幸福な人生を追求すべきだというならスパンの限られた勘考・熟慮は生の全体構想によって支えられていなければならないだろう。この生についての全体構想、つまり人生の究極目標の設定は、カントの言う意味での理性によって行われる14)。
エピクーロスではこの理性の全体構想によって設定された究極目標が「魂の平静」である。人は魂の平静を実現することによって幸福になれるとされているので
ある。全体構想なしに単に(知性による)勘考・熟慮によって個別的な快苦の選択と忌避を行なっていくだけでは、その総和としての生がどこに向かうかは分か
らず、幸福を実現できるかどうかも不確かになろう。しかし、理性の全体構想をたてさえすれば、その内容に関わらず、幸福に到達することができるのであろうか。
だが、人々の根本的な快不快の感情はみな同じだとは言えない。したがって人々が理性によって互いに異なる生の全体構想を抱き、「魂の平静」を最大の善とは考えないこと、したがってエピクーロス派の人々とは異なる生きかたを選ぶことも大いにありうる。
たとえば、人は、ストア派のように、魂の卓越性、つまり(倫理的)徳の実現をそのような根本的構想により選び、賢者となることを目指すこともありうる。
あるいは命がけの探検、冒険の生き方を選んだり、またエピクーロス的生とは正反対ともいうべき、芸能人のような華やかなあるいはきらびやかな一生、あるいはとにかく興奮に満ちたドラマチックな人生を送ろうと構想することもあるだろう。
それぞれの人はそれら「全体構想」の下で、その構想に適う「快楽」を実現すべく、長期、短期的な「勘考」に従い個別の行為の選択と忌避を行うことになろう。
人は生まれつきの、しかし成長と共に修正されていく根本的な快不快の感情にもとづき、理性により自己の生の全体構想を立てながら、勘考によって一つ一つの行為を選択しつつ、幸福ないしは最大の快楽の実現を目指す。このように考えることはエピクーロスの考えと矛盾しないと思われる。つまり、全体構想としっかりとした勘考・思慮に基づく行為の選択を行うならば、エピクーロスとは異なる究極目標を設定しても、同じように快を最大とすることはでき、幸福な生を実現することが可能である、と考えられる。明確かどうかはともかくとして人生において何らかの(究極)目標を持たない人はいないだろう。したがって、「人生の目標」に向かって、勘考と思慮に基づいて(快を生むと思われる)個々の行為を行っていけば、人は誰でも幸福になれると言えそうである。
しかし、ある時点で立てられた全体構想は後になって変わることもある。いや若いときに立てられた構想は途中で放棄され、いったんは、全体構想なしで生が模索され、経験された快とそれを手に入れるために実際に支出された苦の評価(のし直し)に基づいて、新たな全体構想が設定されるということの方が多いかもしれない。
スポーツ選手などが語る「○○を最後まであきらめずにやり続けてきてよかった」(○○はゴルフ、野球、相撲など)という言葉がマスコミを通じて聞かれるが、最初に立てた目標を決してあきらめずそれに向かって歩み続けた結果、それを実現でき、幸福な人生を手に入れることができるという人は少ないかもしれない。不適切な全体構想に固執することによって、快よりも苦が多くなり不幸な人生に終る人もあるかもしれない。
すると多くの人が、ある時点で設定された目標とは異なる目標を後になって追求することになるが、この後の目標を達成できたとしても、それは前の全体構想に照らしてみれば目標ではなかったもの、間違って達成されたものであり、幸福は短期間の生についての概念でなく、すべての期間ではなくても長期間の生に関する概念だとすれば、多くの人は幸福にはなり得ないと考えることもできそうである。
倫理的/道徳的であるとは、自分の幸福、自己の利益だけを追求するのでなく、あるいは他者を自己の利益実現の単なる手段として扱うのでなく、他者を自分と同等の人格として尊重し、他者の幸福、利益を(も)配慮することである(大庭健「道徳は効率を目指すべきか、公正をめざすべきか」『モラル・アポリア 道徳のディレンマ』ナカニシヤ出版、1998)。したがって、また、倫理的/道徳的に生きるということはそのような姿勢を柱にした生の全体構想に立って生きることである。
ところが、エピクーロスは人々が快楽を求めるということを事実として前提し、その快楽を最大にするように快楽の種類を区別し、合理的に最大の快楽を得るような勘考、熟慮、哲学を勧めただけであり、他者の人格を尊重し、他者の幸福を促進せよとは勧めていない。したがって、彼の勧めにしたがって、自己の快楽を最大にするように生きることは倫理的/道徳的に見て「正しい」あるいは「良い」生き方だとは言えないように思われる。だが、エピクーロスは、快楽を善とせず道徳的であることを唯一の目標として生きるストア派的生き方には反対したが、彼は道徳的であることは間違いだと考えているのではない。エピクーロスの教説にしたがうなら、道徳的であることは一種の快楽と見なされる。(そのことはロングの「第一の批判」への反論で述べる。)また彼は他者の利益を尊重せよとは説いていないが、逆に、利己的であって構わないと言ってはいない。
ロングはエピクーロスは「自己中心的」だと言うが、それは正しいだろうか。エピクーロスの教説は倫理的/道徳的観点からは、どのように評価されるべきであろうか。
倫理学者・大庭健によれば、倫理/道徳(的観点)からは、人間は自分の欲求〔快楽〕の実現を目指し単に「合理的に選択せよ」(十分「勘考」せよ)ということだけではなく、自分の欲求が果たして実現するに「値する」人間らしい欲求なのか、人々が置かれている社会的諸関係が、はたして維持するに「値する」人間らしい秩序なのかどうか、道徳はこうした反省を要求する。前掲論文、『モラル・アポリア』p42.
各人の行為選択が調和する保証は全くない。衝突は不可避である。だが、「自分の損得とは独立に相手を一個の人格として認めあう。---端的にかけがえなき人格として相手の尊厳を認める。これが道徳の核心である」。同書p41.
また大庭は、「人間の本質」なるものが実在することを前提して(イデア論はそういうものだと大庭は言う)人間らしい行為は一意的に定まっているという主張は退ける。当の欲求/行為だけを抜き出して「人間としての」義務/責務とかいうものさしで測ることはできず、どういう社会システムでどういう結果をもたらすかを考慮しなければならない、という「帰結」についての考慮も必要だという。同書、p42f。
私は大庭のこの説明を全面的に支持する。そしてエピクーロスは、(非エリートである)当時の人々の置かれた苦に満ちた現実に立って、苦の解消のための欲求充足及び精神の平静の実現と言う「人間らしい」目標を掲げたと思う。彼が社会的諸関係に対してどのような態度をとったかは以下でふれる。
ところが、道徳的観点に立っている人たち―大庭もそうだが、たぶん私もそうだ―が考えているような意味での「道徳」などというものは実際には存在しないという永井均のような人もいる。永井によれば、「誰もが結局自分の利益や快適さだけを目標にして生きている」。ニーチェの言葉「利己主義以外のものは存在しない」が世界に関する厳然たる事実である、と永井は考える。「道徳はほんとうにあるのか」『モラル・アポリア』p7
彼は、とりわけ、道徳的世界観に立つ人が「人生の真の価値は道徳的に生きることのうちにこそある」。「より善く、より正しく生きることこそが、人生の意義そのものである」と主張することが、彼の「個人的趣味」に合わない、と言う。彼には現実の世界は「弱肉強食」の世界であり、人々はもっぱら自己の利害を貫徹するために「金銭、言葉巧みさ、権力、など、人生を闘う様々な手段」で闘っている、したがって徳的世界観に立つ人間も同じ穴のムジナに過ぎないとしか映らない。「有徳であること、善人であることは、私有財産制のもとで金持ちが必然的に強者であることと同じことだ」。p8「あなたは強者であり、金持ちや美人がそうであるのと同様に、そして同程度には、そのことで概して有利な人生を歩めるにちがいないのだ」。p11.
永井は、すべての人は自分の利益や快適さだけを目標にして生きていると見る、反道徳的世界解釈は「究極的には、世界が中心を持つという端的な事実からの必然的な帰結だ」という。だが、彼は、説明のできないunaccountable「趣味」に基づき、むしろ、最初に反道徳的世界解釈に立っていて、その見解の根拠として彼の頭(脳)の「力技」でひねり出されたのが「世界が中心を持つ」という理論あるいは形而上学なのではないか。「世界が中心をもつ」ということが「端的な事実である」ということは、現実に距離を置いてしまっている人物の脳によって考え出された単なる理論に過ぎないのではないか。
「世界には中心があり、脳がその中心だ(そして世界は脳によって描き出されたものだ)」、と言うなら私も認める。しかし「私」(あるいは「彼」)は脳と同一ではない。「私」は身体を持った存在である。(「持つ」と言ったが所有を意味しない。⇒熊野純彦「自分の身体を自由にできるのか」『モラル・アポリア』参照。私とは脳と身体の両方だ、というくらいの意味である。)私は、他者と喧嘩したり助け合ったりしながら、他の人々とともに世界の中に存在している。そして、世界には多くの苦しんでいる人がいてその人たちが助けを求め呼びかけている、というのが「端的な事実である」と私には思われる。そのような世界は決して中心を持っていない。
私は利己主義者が世界には多くいるという事実を否定しないし、永井がたぶんその事実の確証例であることを否定しない。だが、彼の存在は「人間全ては利己主義者である」ことを証明しない。
さてエピクーロスは友を大切にすべきだということは述べているが、広く世の中の人々一般、あるいは「人間」を対象にして、その人々の人格の尊厳、自己の利 害とは独立した他者の利害の尊重を説いてはいない。友情が極めて大切だとは言うが、究極的にはそれが自己の利益になるからである。ではエピクーロスは永井 やニーチェの言うような「利己主義者」なのだろうか。
おもてに表れた実際の行動よりも隠れた動機を問題にするという点で、「世界解釈者」である永井は一種の動機主義に立っている。そして、彼は道徳の厳格主義
者と同様に、いかなる行為であれ、その動機の中に自己利益を嗅ぎつけ摘発する。しかし厳格主義者がその隠れた自己利益を非難するのとは反対に、永井は動機
の不純性を見出して喝采する。それみろ道徳は嘘だと。
私は動機主義者ではない。行為は社会的な不公正をなくし人々の苦しみを減らすのに実際に役立つのな
ら、行為者の動機によらずその結果からよい行為だと判断すべきだし(大金持ちが売名行為のために彼にとってはした金を寄付するというような場合はともか
く)、それがその人の良心に恥じない行動をとることで苦痛を回避するという自己の「快楽追求」を動機としていたところで、善い行為はよいと言えると考え
る。
他者の利益を考慮せず自分の利益だけを追求して平然としている普通の意味の「利己主義」と、道徳的に行動することで良心の安らかさという精神的快楽を「利 益」として追求する特殊な「利己主義」とは区別すべきである。動機において両者は共に自己利益を追求しているといえる。しかし、本物の利己主義者は他者の 物質的利益を損ない他者に精神的苦痛を与えながら自己の利益を実現するが、道徳的に行動する特殊な「利己主義者」の場合には他者の物質的利益を損なうことなしにあるいは他者に精神的快楽を 与えつつ、自己の利益を得るのである。
また、そもそも自己の快楽を「目標」とせずに、つまり快楽を動機とせずに「非利己的な」行為を行なう場合がいくらでもある。世の中には、様々な理由で困っており、助けを求める他者の呼びかけがある。また、正しいことが十分理解できるが自分ができないでいたことを誰かが行なっており、そして権力によって弾圧されて苦しんでいる、そのような人々から、しばしば支援の呼びかけがある。
そのような場合に、自己の生についてのはっきりとした道徳的構想を持っていなくても、(予定していた行動による)自己の利益を犠牲にしようかどうしようかという葛藤が起こる。その行動を行なったら、場合によっては、自分のそれまで考えていた人生の基本設計の変更を迫られる結果になる可能性もある。人生の方向を定めようとしている若いときには葛藤が強い。呼びかけに応えることは、呼びかけられたときの葛藤の苦痛を解消することになるが、行動の時点においては葛藤の苦の意識が支配的である。自己利益を否定することで良心の呵責を回避できるという「快楽」はその時点では得られず、“目標”にはならない。行動を行なってからもアンビヴァレントな状態は続く。私がそのように行動することにより、職を失うなどして暫くの間苦しんだにしても、選択は間違いではなく、それでよかったのだと肯定でき、精神的平静=快楽を感じられるようになるのは、かなりの時間が経ってからである。
人によっては、生活が破綻し、
いったん選んだ、他者の支援を優先する活動が継続できなくなって、活動を中止する人もある。この人は、おそらく良心の安らぎを得ることもできなかっただろ
う。私の知人、友人のなかには、数十年にわたって、自分の生活に苦労しながらも、より困っている人々を支援し、社会的な不公正と戦う、非利己的な活動を続
けている人もいる。
書物の中や教壇の上からでだけでなく、そのような人に面と向かって、君も本当は利己的なのだとか、君も「金持ちや美人がそうであるのと 同様に」「強者であり」、「有利な人生を歩んでいるのだ」と放言できる人がいると、私は信じたくない。
永井とニーチェにしたがって「すべての人間は利己主義者」だと言うとすれば、利己主義に全く異なる二つの種類があるということを認めなければならない。ひ とつは他者を単に手段と見なして、力のあるものが自己の力を利用して既存の不公正を拡大し(法律や制度を格差拡大の方向に変えつつ)、ますます自己の有利 な立場を強化しようとするような利己主義である。もうひとつは、社会を公正なものに変えようと努力し、苦しんでいる人々への援助をすることで、常に成功す るわけではないが、(良心の呵責を減らすという)快楽=自己利益を得ようとする利己主義がそうである。この二つの利己主義ははっきりと違い、区別できる し、区別すべきだ。
社会及び自分以外の人々を単に手段と考え、利己的に、つまり、単に「合法的」、「合理的」に生きようとしている人のほうが、道徳的生き方をする人よりも多 いかもしれない。社会の中で平均的かそれ以下の生活をしており、生きるのに精一杯であるような人の場合には、そうであったとしてもしかたがないと思う。し かし、平均以上の能力があって生活に余裕がある人は、自己の利益を追求するだけでなく、他者のことをも配慮すべきだ。とくに、社会に積極的なかかわりを持 ち、社会生活を営むことから積極的に利益を受けている人々はそうであるべきだ。しかしその人たちが合法的、合理的生き方で何が悪いと居直るなら、しかたが ない。
だが、私は、アリストテレースの言う「人間は社会的動物である」は正しいと考える。狩猟・採集の生活を抜け出て以降の人間は小集団、小さな団体の中でだけ生きているのではなく、(その団体の存立を可能としている)大きな社会のなかで生きているのであり、その限り、人は道徳的ないし倫理的であるべきだと思う。しかし、それは「他人からしてもらいたいと思うように、他人に対して行え」というキリスト教的、カント的原則ではなくルソー的な原則「できるだけ他人の不幸を少なくして、自分の幸福をはかれ」というものである。大雑把に言えば、エピクーロス的個人主義はこのルソーの原則と同じ姿勢に立っている。
ロング『ヘレニズム哲学』における「エピクロスとエピクロス哲学」を論じた章の第九節「快楽と幸福」における解釈と解説を検討してきた。以上の検討を踏まえて次に、その章末で行われる彼の三つの批判に順に反論を行いたい。
さて、ロングはエピクーロスの「この主張が間違っていることは明らか」と言うだけで、その理由は全く述べていないし、快楽により導かれるのではないような行為の例を示してもいない。
私は、第一節で、朝、仕事で出勤するという行動は、原始人が木の実=食べ物を取りに出かけるのとは違い、直接的に快楽を実現することにはならない。そして仕事は疲れや苦痛を我慢して行なわれることであり、一見したところでは、苦痛を解消するためにあるいは快楽を実現するために行われることではないように見えるかもしれない、という例を上げて検討した。そこでは、エピクーロスの主張に反するようにみえるかもしれない、日常的な行動について考えてみただけであった。ロングはもう少し違った「人間の行為」を念頭においているかもしれない。
ロングは『善と悪の究極について』におけるキケロのエピクーロス批判を熟知しているはずである。同書の第2巻はすべてエピクーロスの批判に充てられている。キケローは、徳こそが究極の善だという立場に立ち、対外戦争の勝利のために命がけの勇気を発揮し、あるいは内政において正義の実現に努めた執政官たちの行為をほめたたえつつ、それらは決して快楽や自己利益を目的としたものではなかったと力説し、究極善は快楽だとするトルクワートゥスに対する反論を全面展開している。第2巻34節、45節など。
キケローは、偉人たちの数多くの偉業は「たとえいかなる利益も生まないことがわかっていても、そうすることがふさわしいことであるから、正しいことであるから、高潔なことであるからというただ一つの理由」によって成し遂げられたのだと述べている。彼によれば歴史上の偉業はすべて徳の実現を目的とする行為であり、決して利益や快楽を目的とするものであったのではない。
政治家や将軍ばかりでなく、ストア派のように、哲学的知恵、勇気、節制、正義などの徳を、何らかのほかの善(快楽や利益)のためにではなく、それ自体のために実現がめざされるべき究極的な価値だと考え、実践しようとした人々もいる。このような徳に基づく行為、快苦にかかわらず徳の実現自体を目指す行為が存在することによって、エピクーロスの主張は反駁されていると考えられるかもしれない。
またローマ時代のキリスト者のような、超越的な神の命令にしたがう行動がある。彼らはあらゆる迫害に臆せず、信仰を守った。彼らの殉教もエピクーロスの主張に反するもののように思われるかもしれない。
ロングが、「すべての行為が快楽を目指して行われる」というエピクーロスの主張の「間違いは明らか」と批判するときに、その主張が妥当しない行為、つまり快楽を目指して行われているのではない行為として、具体的に思い浮かべているのは、これら徳を目指す行為や宗教的命令に従おうとする行為のことかもしれない。これらについて考えてみよう。
たとえば、自らの危険を顧みず、火事で燃えている家の中に飛び込んで人を助けるという勇敢な行動を行う人が時にはいるが、このような行動は、一見、快楽の
実現が行動の第一原理であるとするエピクーロスの主張への反駁になっているように思われるかもしれない。それは勇気や親切心・人間愛という「徳」を行動原
理にしているという風に見られるかもしれない。
だが、予想される、自らが火傷を負うことによる身体の苦痛よりも、助けを求める人を見て見ぬ振りをすることの良心の苦痛に耐えられないから、あるいは人間
として当然と考えられる徳を実行できない自己を恥じる精神的な苦から、そうするのだと見ることもできる。おなじことだが、人を助けることで感じられるであ
ろう快(ないし精神の平静)が、自分が火傷をせず無事でいることの快(または身体的な無苦痛)を上回ると感じ、考えたから、そうするのだ、と見ることがで
きる。そしてこのような見方は、この勇敢な行為を少しも貶めるものではない。
また、キリスト教徒の殉教は、不死の魂があの世での永遠の至福の生をうけることができ、不信心な人よりはるかに大きな快楽、幸福を得られると信じた結果で
ある、と見ることができる。これと同じことをベンサムがすでに述べている。
「第一に、たとえ徳が快楽を与えてくれるにしても、だからといって快楽のために徳が求められるのではない。というのは、徳は快楽を与えるのではなく、快楽をも与えてくれるのである。徳が努力するのは快楽のゆえにではなく、その努力が、たとえ求めるものは別にあっても、快楽をも与えるという結果になるからである」。そして、「徳を求めるのは何を目的としているのかと問うならば、それは間違っている。それは最高以上のものを求めることになるからである。徳から何を求めるのか、と問うのか。徳そのものである。」と言う(p136)。これは今私が上で述べたことが間違いであることを示しているだろうか。
確かに自分が信じる最高の価値に従って行動しようとするとき、その価値の実現が目的であり、それに伴って感じられるだろう快、喜びの感情が目的ではないであろう15)。 しかし、多くの場合、その価値の実現には何らかの犠牲が伴う。犠牲やコストについて考えることなしにできる簡単なこともあろうが、簡単なことなら「徳」を持ち出す必要はない。相当な自己犠牲が必要であるような場合に徳が問題になるのである。そのコストや犠牲を慎重に考えることなく、その行為に着手するのは 無鉄砲であったり、軽はずみなことであろう。
また、キケローは「徳」virtusは「男」virという言葉から派生した。「男にとって最大の徳は勇気であり、その際立った特性は、死を恐れないこと、 苦痛を恐れないことの二つである」と言う。そして、「真の誉れと栄光を求める魂の動きと渇望があれば、危険な戦闘にも立ち向かうことが出来る。強い男は戦 列においては傷の痛みを感じない」と言う。彼は、勇気の徳を目的とすることで死や苦痛をおそれず戦いに臨むことが可能になり、徳を目指す行動によって「誉 れと栄光」が手に入ると弁じている(『トゥスクルム荘対談集』第2巻、13節~27節。)モンテーニュ同様、私も、いくぶん、徳とそれが与えてくれる栄光 の喜び、つまり「快楽」とを区別することはできない場合があるのではないかと考える。
こうしてストア派の人々は、徳の実現を目的にして行動しようとするだろうが、その人は自己の身体の安全と、自己の良心に恥じない、後悔のない平静な心、いくぶんは誇らしい気持ちで生きていくことの精神的な快との間の考量を行うのである。つまり、彼/彼女に徳の行為を決断させるのは、徳を実行し不徳を避ける ことによって得られるであろう精神的な快である。
マルクス・アウレリウスは前掲『自省録』のなかで、(のちにマルクス自身も含め五賢帝の一人とされる)彼の義父アントニヌス・ピウスを称えつつ、善良さ、愛情深さ、敬虔さ、寛容などの諸徳の実践を自らに対して説いたのに続き、次のように書いている。「それは、臨終の時が至った際に、彼のごとく君もまた、良心において安らかであらんがためである」。第6巻30節
私は現在自分の旅支度に忙しく自分のことで精一杯で、倫理的な努力も怠りがちなのだが、以前はそうした生き方をしようともっと努力していた。そのころの生 きかたを振り返ってみると、前に述べたことだが、求められている(正しいと思われる)行動・行為が大きな犠牲を払うことになる可能性を含んでいるときに は、「考量」しても答えが出ず、葛藤状態に置かれてしまう。結局どちらかを私は選択する。しかし、それは、ストア派であれば感じたかもしれないような、正 しい有徳な行為を選ぶことで精神的な快を得ることができたというような状態とは全く異なる。葛藤状態の中にとどまることの苦を解消できただけだったという ほうがより真実に近い。しかしいずれにせよ自己犠牲の要素を含む行為は、徳(勇気、人間愛、義侠心、誠実etc.)それ自体を目的に行われるのではなく、 苦から逃れるために行われる。そして、エピクーロスに従えば苦を逃れることは快である。
徳の追求を快と苦に関係付けて論ずることに反対するセネカの議論に対して、このように反駁することは可能である。 だが、犠牲的行為が、すべて、徳そのものではなく徳に付随するか徳がもたらす「積極的」快楽が目的でなされると考えることには無理がある。したがって、 「快楽=積極的快楽を実現しようとする欲求により」、あるいは「喜ばしく感じられる意識状態に到達しようとする欲求により」、「人間の行為はすべて十分説 明できる」とは言えない。そして、エピクーロスはそのような主張は行なっていない。だが、その行為をなさなければ感じるであろう精神的な苦痛の回避(現代 の言葉では「良心の呵責」)が動機だという考えかたは十分に成り立つ。そして、エピクーロスにおいては苦痛の欠如は快楽なのである。
したがって、今述べた徳の実現を動機とする行為や宗教的命令に基づく行為は「人間の行為はすべて、快楽=「苦痛の欠如の状態」を実現しようとする欲求によ り、説明できる」というエピクーロスの主張を反駁するものではない。また、エピクーロスの議論の「出発点となる観察事実」、「すべての人々が快楽を追求し ているという事実」は、快楽を「苦痛の反対」ではなく「苦痛の否定」と考えるかぎり、決して間違いではない。〔ついでながらここで問題になる快と苦は感覚 的なものでないことは明らかである。周囲の人々から軽蔑されながら生きるのはいやだ、或いは自己の良心に反する行為はしたくない、また神の命令に背けば天 国にいけなくなるというのは感覚ではなく情念あるいは感情の判断である。〕
さて、ロングは、エピクーロスの「主張が間違っていることは明らかなように思われる」と言うだけで、快楽、あるいは喜ばしく感じられる意識状態に到達しよ うとする欲求により導かれるのではないような行為の例を示していないので、上では、私の推測で、その「明らかな」例になるかもしれないと考えられる、徳の 実現を動機とする行為と宗教的命令に基づく行為だけを取り上げて、反論した。ロングはこれ以外にも考えているのかもしれないが、それが何であるかは明らか ではない。彼の批判への反論としては、今のところ、十分であろう。
エピクーロスは「苦痛をこうむっていない」ことが最大の快楽で、快はそれ以上増大しないと言う。しかしその状態にバラの香りから得られる新しい満足が付け加わるなら、快楽は増大するはずだ、とロング主張している。
ロングは哲学的教説を、時代や社会を超えた人間すべてに妥当する普遍的理論だと考えているようだ。彼は他の条件に触れることなく、「苦痛が存在しない」という条件の下で、バラの香りを嗅ぐことは(バラが嫌いな人は別として)快楽であり、それは単なる意識の多様化ではなく、快楽の増大であると主張している。
私はバラの花の香りを嗅ぐと想定されている人がどのような境遇あるいは状況にあるかを具体的に考えて答えを出す必要があると考える。たとえば上でふれたような、長期間飢えと渇きに苦しんだ後で、飲食にありつくことができた人の状況を再度想像してみる。
この人はそれまでのひもじさを思い起こして、その苦が解消されたことに心の底から安らぎ、落ち着きを感じ、「静的な快楽」に浸っているだろう。この状態で、バラの強烈な香りが漂ってきたとしよう。その人が享受している安らぎと落ち着きの快楽にバラの香りの意識が加わること、意識内容の変化は「意識の多様化」であろう。しかし食事の満足感が大きなものであれば、バラの香りがそれに取って代わることはできないだろうし、食事の満足感にバラの香りが加わったものがそれ以前の快楽よりも大きくなったとその人が感じるはずだとも主張できるとも思われない。
むしろ私は、食事により飢えをまぬかれた人は、その食事が出来たことの幸せ、喜びに浸っており、バラの香りには気がつかないのではないかと思う。恐らく、彼が食後に享受したいものがまだあるとすれば、「強烈な」バラの香りやその他の物に妨げられずに静かに休息するか一眠りすることではないか、と想像する。
とにかく食事が出来て満足したという喜ばしい気分、感情がほとんど全面的にその人の「快楽」の意識を占め、暫く、たとえば、数時間か数日間か、あるいは飢え死にの危機にさらされた人なら一種のPTSDのせいで、長期間にわたって、花の香りやその他の(安定した生活の中では喜びや楽しさを感じられる)ものに対する関心は全く持てないままでいるかもしれない。したがって、このような人々の飲食の必要が満たされた状態を「苦が除去されたあかつき」と理解するなら、その状態において、バラの香りが独自な種類の快楽、新しい満足を与えるもので、快楽を増大させるはずだとは必ずしも主張できないと思う。
これは、現在の中東における戦争難民のことや、70年近く前の敗戦後の日本の食糧難のこと、あるいは現代日本において、まともな食事を与えてもらえない子供が多くいることなどを、考えてみれば、少しも極論ではない。
戦後少したってからの日本社会で食料と花について人々が感じていた快楽を、統計数字に基づいて確かめることができる。切花が日本の多くの家庭で楽しまれるようになるのは高度経済成長により、食生活が安定し、生活が豊かになって、食べることが多くの人の第一の関心事ではなくなってからであることを統計数字がはっきりと示している。16)。
人々は食生活が安定的に行うことが出来るようになるまでは花には関心を持っていなかったのである。たとえ当時一般的な家庭の貧しい食卓に偶然に花が置かれたとしても、関心のないものの色や香りには人々は無頓着であろうから、人々は食後はごろりと横になって寝てしまうかあるいは必要な家事や家業の続きを行うかするだろう。これは昭和30年代までの日本の一般家庭のありようであった。
ロングは、冷戦下の世界で最大の経済的繁栄を謳歌していた米国の上流階級の人々の生活、日本でいえば、1980年代後半以降の飽食時代の生活に基づいて、彼の主張が普遍妥当性を持つと考えているようだがそれは間違いである。
快楽の大きさは変化せず、多様化するだけだと言うことになんら問題はないはずだ。
静的快楽を享受しているときにバラの香りが加われば必然的に快楽の増大をもたらすとロングが考えるのは、静的快楽は単に苦痛がない状態だと考えるからであろう。「何の苦痛もこうむっていない状況で私がバラの香りを嗅いで快楽を得るとき」と彼は言うが、彼は「何の苦痛もこうむっていない状況」の静的快楽を快でも苦でもない中間状態と見なすがゆえに、その快苦がいわばゼロである状態にバラの香りという快が付け加われば、その分だけ快はプラスになると考えているのではないだろうか。
確かに食事は飢えの苦を解消する。それは苦つまりマイナスの快をゼロにする。しかし欲求が充足されたあとに快は存在するのであり、それが静的快楽である。食事中の動的快楽は、舌で味わいまた胃袋が満たされて行くことによって感じられる、感覚諸器官からもたらされる快であろうが、食後、感情が快と判断する静的快は、その内容である充足感のうち、感覚の情報に基づく要素はごく少なく(ロングの言う「無頓着な」人には全く感じられない程度のもので)たぶん大部分は精神的な要素が占めている快楽である。
だが、快の感情は存在し、無あるいはゼロなのではない。たまたま昼食が遅くなったサラリーマンのように、昼食が済めばもうさきほど感じた空腹のことはすっかり忘れ、再び仕事に打ち込むというケースも考えられる。しかし、長期間、飢えに苦しんできた人の場合のように、食事をすることで得られる充足感が非常に強いものであることもあろう。したがって香りによる「新しい満足感」が加わることは、快楽がゼロからプラスに変化すること、つまり快の増大を意味するのではなく、快の「多様化」なのである。
現代の英米倫理学、政治学の理論に強い影響力を及ぼし続けている、19世紀英国の倫理学・哲学者、シジウィック、Henry Sidgwick(1838-1900)を参照してみる。彼の主著は『倫理学の方法』The Method of Ehtics で、1874年に公刊されたこの本は、ベンサム、およびミル父子の古典的功利主義の伝統の頂点をなす。
シジウィック、写真はWikipediaによる。
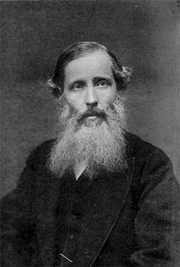 同書の邦訳はないようで、ここでの「参照」は奥野満里子『シジウィックと現代功利主義』(勁草書房、1999)に全面的に依拠した間接的なものである。
同書の邦訳はないようで、ここでの「参照」は奥野満里子『シジウィックと現代功利主義』(勁草書房、1999)に全面的に依拠した間接的なものである。しかし、ロングがエピクーロスを批判する理由はもしかしたら別なところにあるのかもしれない。というのはロングはエピクーロスの静的快楽と言う概念が、身体の自然な状態あるいは正常な状態は健康な状態で、それが静的快楽を生むと言う「想定に」基づいていると言っていたが、他の研究者によって、かつて、この健康で正常な状態を維持ないし回復するための、必要不可欠な自然的な欲求充足こそが「正しい」快楽の享受であり、それを超えたものを求めることは間違いであるかのような独断的な解釈が行われたことがあり、ロングはそれに反論する必要があると考えているのかもしれない、と思われるからである。
「静的な快楽」と訳されている原語はヘードネー・カタステーマティケーであるが、ジャン・ブランや笹谷満によれば、フランスの20世紀はじめの研究者ブロシャールは、plaisir constitutif、つまり「構成的快楽」と訳し、カタステーマ(カタステーマティケーはその形容詞形)という語は、「生命ある有機体の安定した定常的な---少なくともある持続の間は---決定的な状態を表現する。〔笹谷は「構成的な快楽とは生きている有機体の少なくとも一定の間変わらない安定した明確な状態を説明する」と訳している〕---要するにこれは生命体の様々な部分の均衡、健康---の状態を構成する均衡であり、快楽を構成する直接の条件である。快楽は身体諸器官の自然な働きによって生命体のなかで生理的な均衡が確立されるときには、自然にまたおのずから生じるものである」と述べているという。
笹谷は同様のブロシャールの文を紹介したのに続き、「有機体が一時崩壊した均衡を回復しようと努めるときに、この運動に伴う快楽がある、これは運動の快楽であるから当然苦痛を前提し、これに結びついている。この均衡が回復したときには苦痛が全く消失し、ここにありうる最大の快が生ずる。これが均衡の快楽であって決してそれ以上増大しない」と書き、また「均衡という概念は多くの反対運動の釣り合いを意味する。したがって、この状態は静止どころか、完全に積極的な、もっとも充実した状態であり、これに依存する快楽も、積極的な、充実した快楽である。---それはありうる最大のものである。したがってこれ〔均衡〕を破壊すると直ちに快楽は減少し苦痛が増大する」と書き、「以上がブロシャールが述べていることの大要だ」という。
こうしたブロシャールの説明に従うなら、静的快楽の状態である「均衡状態」を破壊する余分な快楽追求はかえって快楽を損なうとされているから、エピクーロスは静的、「構成的」快楽を維持するためにそれ以外の動的快楽あるいは「多様な」快楽を退けた、快楽は自然的で必要不可欠な欲求の充足のみに限られるべきだと考えていたことになる。
また、ブランはブロシャールに依拠することにより、「エピクロスのいう快楽は、堕落した文明の成果---としての狂態、あらゆる犠牲をいとわぬ、目先の新しさへのたえまない逃避、めまぐるしい変化などから、われわれを引き離そうとしている限りにおいては、静止の快楽である。---賢者は---変化を求めようとはしないのである」と言っている。ブランが述べていることは欲望の自由な追求、新しい種類の快楽の出現、消費と生産の絶え間ない増大を肯定する資本主義社会に対する鋭い批判であるように思われる。笹谷満前掲書p78f。ジャン・ブラン前掲書p83f
静的快楽を「構成的」快楽と訳してエピクーロスの快楽論を説明するブロシャールの説明は、ロングが言っていた、「生きているものにとって自然的ないし正常な状態とは身体的・精神的に健やかな状態であって、この状態はまさにそのこと自体によって喜びを与える」という「エピクロスの想定」をずっと詳しく述べたものである。私には、快楽の経験的心理(学)的説明と、もっともらしく聞こえるが経験的に確かめられない「自然学」的な説明との間を行ったり来たりするだけのブロシャールの(俗流唯物論的?)エピクーロス解釈が正しいとは全く思われない。
だが、ブロシャールの解釈に依拠するブランは、基本的欲求の充足による「構成的」快楽の「均衡」状態を越えて絶えず「目先の新しさ」を追い求めることは、経済格差をはじめとする社会の諸矛盾からの「逃避」に過ぎないと批判している。ブランは、ロングの言う「バラの香りを嗅ぐことによる新しい、独自な種類の満足感」、「苦痛なしで強烈な喜びを与える経験」を重視することは、結局、精神の平静さの実現を目指す努力を忘れさせ、身体的・感覚的な「多様な快楽」の積極的な追求を説くことであり、アメリカ資本主義の「堕落した文明の成果」の受け入れを勧めることに過ぎない、と言うのではないか。ロングはブロシャールやブランの批判や攻撃が、彼自身にも向けられていると感じるのではなかろうか。
エピクーロスが(多くの庶民にとって)基本的欲求の安定的な充足が何よりも重要であり、身体の快苦に関しては飢えや渇きやまともな住まいを欠いていることなどの苦が解消されれば十分で、(上流階級が楽しんでいる)さまざまなぜいたくな飲食や立派な家屋敷は必要ないと考えていることは確かである。また、彼は、人々は「限度のある」基本的欲求は満たされても、さらに、死や神罰の迷信などへの恐れや不安という、身体の苦より一層大きく、解消の困難な精神的な苦を抱えていると考えていた。そうした精神的な苦は、どんちゃん騒ぎやセックスによっては解消できない。贅沢や放蕩をエピクーロスが退けるのは、それらを享受するために余分な労苦を支払わなければならず、「哲学や自然学」を行うことが妨げられるからであった。
われわれ先進国の人間は古代ギリシャのポリスの人々に比べれば、基本的欲求に関しては充足の程度ははるかに高いといえよう。しかし、これに対して、同じくすでに述べたことだが精神的なストレスに関してはかえって強まっているとさえ考えられる。
そして、われわれの周りには、必要不可欠なものかどうかは不明だが、「独自な種類」の「新しい満足感」を与えてくれると盛んに宣伝されているものが無数にある。多くの商品が、それらを購入し消費することにより、すばらしい喜びを得、健康になり、友人をもつことができ、人々から羨ましがられ、異性にもて(結婚でき)ると、われわれに購入を迫っている。それらの商品を手に入れ、「独自な種類」の「新しい満足感」を得るために、われわれは減らすことの可能な、不必要な労苦を行っていないだろうか。
100年前と比べれば労働生産性は機械化により飛躍的に高まっているはずなのに、依然として、多くの労働者が週の内2日ほどしか休日はなく、そのほかの日は昼間のほとんどの時間は仕事に充てなければならないのは、われわれが「多様な」、余分の「動的快楽」を手に入れるために、余分の労苦を支払っているということではないだろうか。必要かどうかわからない多くのものを買うためにアルバイトやパートの仕事をしようと外に働きに出、家族と一緒に過ごす時間、家族とのコミュニケーションを減らし、親子や夫婦の間ですれ違い、心配事の種を増やしていないだろうか。
こうしたことがはっきりと否定されてからでなければ、「なんの苦痛(労苦)もない状況で、バラの香りをかぐことは独自な種類の、新しい満足感を得ることだ」というロングの主張は決して、肯定できないと私には思われるのだ。
私はブロシャールのようなエピクーロス解釈に従おうとは思わない。しかし、次に示すように、ロングのエピクーロスに対する批判には、エピクーロスの倫理思想を社会主義/全体主義的思想として捉えようとする政治的意図があるように感じられる。
ロングはエピクーロスが「精神の平静を最大の快楽と呼ぶのは言語の使用と常識に無理を加えるもの」と非難するが、この文を書くときに、彼がやはり同様にあのビッグ・ブラザーの支配する全体主義国における言語使用、「戦争は平和である」、「無知は力である」等々の「ニュースピーク」や「ダブルスィンク〔double-think〕」(『1984年』 新庄哲夫訳、早川書房、1975年)のことを思い浮かべていなかったとは考えにくい。
ロングは「言語の使用と常識に無理を加える」「そのような処置は---精神の平静には同化できない経験---を考察する道を奪ってしまう」と言っている。エピクーロスは無理な言語使用の押し付けよって、彼が最大と考える快楽以外の快楽を「考察」することさえ出来なくすることを狙っていたと、ほのめかしている。
ロングが社会主義国における共産党の一党支配と言論や思想の統制などの全体主義的性格を好ましいと思っていなかったし、資本主義=自由主義国の優位を信じていたと推測することは見当違いではないだろう。そして、ブロシャールのような解釈によるならばもちろんのこと、そうでなくても、エピクーロスの不可欠な自然的欲求充足による身体的健康を重視し、それによって得られる「静的快楽」が最大の快楽だという考えは、限りない欲望追求と消費の拡大、経済成長を望ましいと考える資本主義に対する明確な批判でもある。
実際の社会主義国は資本主義国を後から追いかけ、同じように経済成長を追求していたにしても、資本主義国と比べれば、平等を重視し医療サービをはじめとする社会保障制度の整備に力を入れていたことは明らかである。限りない欲望追求を肯定せず生物としての健康状態の確保を優先するエピクーロスの思想には、社会保障を重視する社会主義思想に近いところがある。そして単なる理論あるいは「純粋な知的探求」としての哲学の研究ではなく、生活と「生活スタイル」の共有が行われたエピクーロスの共同体は一種の「共産主義的」な団体と見ることもできる。
こうした諸々の事情を考慮に入れると、ロングのエピクーロスに対する「第二の批判」は哲学的-論理的な専門的な観点(だけ)に基づく批判なのではなく、全体主義、社会主義への(政治的)批判を暗に含んいると考えられるのである。
私自身について言えば、現在の私は少なくとも「強烈な喜び」を多く得ることが幸福の条件だとは思わないし、精神の平静状態をより多く求めている。しかし、これは年齢とも関係があると思う。若いときには誰でも冒険や新奇な事柄の経験をしたいと思うだろう。だから人の一生を通じて「精神の平静が最大の快楽だ」と主張しようとは思わない。しかし、幸福観の変化が生じるか、どのように変化するかもまた人によって異なるだろう。どのような生がもっとも幸福で望ましいものなのかは、あのことわざが言うように理性的「説明」accountにより決めることはできないと考える。
だが、苦痛がないときのバラの香りが与える快は「精神の平静」よりも大きいはずで、エピクーロスの主張は「言語に無理を加えることだ」と決めつけることができるのは、結局、ロングが、快楽の判定を直接的感覚に委ね、刺激の大小/強弱の問題に還元してしまうからである。
ロングは感覚の次元に立って、多数の人が「感覚」しない「精神の平静」という微弱な快楽よりも、感覚されている「強烈な」薔薇の香りの「快」が大きいと考えるので、前者を一種の快楽と呼ぶことは認めても最大の快楽と呼ぶことには反対し、「言語の使用と常識に無理を加える」ものだと言うのである。
しかし、快楽が感覚である、あるいは感覚によって判断される、というのはロングの独断である。彼はエピクーロスの快楽論との関連における感覚と感情の区別について何もふれておらず、また「中間状態」への多数の人々の 「無頓着」をエピクーロスが誤って「見落とした」と言うことで、快楽は感覚だと考えるべきであると示唆しているに過ぎず、快楽が感覚であることを確かな論拠に基づいて示しているわけではない。
だが、私は上でエピクーロスの著作(とそれに関するデイオゲネス・ラエルティオスの報告)に即して、彼が、感覚と感情の違いとそれぞれの役割りを説明し、快不快は感情によって判断されるとしていることを示した。またカントの説を参照しつつ、快不快は感覚ではなく感情だということ、快不快の判断は感情の働きであると考えるべきだということを説明した。
その私の説明が認められれば(私はそう信じるが)、快の大きさを公平に比較しようとするなら、元になる感覚刺激の大きさを比較するのではなく、精神の平静に関する快の感情と、薔薇の香り(感覚)に関する快(あるいは平静の快にバラの香りの快が加わったときの快)の感情とを比べなければならないはずである。また、そのときにこそロングは、「蓼食う虫も好き好き」のことわざを持ち出すべきなのである。そしてロングはバラの香りの方が(あるいはそれが付け加わった時の方が)より大きな快楽を与えると言うだろうが、エピクーロスは精神の平静こそが(あるいはそれだけの方が)大きな快楽を与えると言うであろう。
エピクーロスは、戦争や飢饉や疫病などの苦に満ちた古代世界において、全体としての生は、必ずしも、わくわくする興奮や「強烈な喜び」に満ちている必要はなく、悲しいことや苦しみや心配事がなければ満足できる、と考えた。
自然本性的で不可欠な欲求の充足ということについては、胃袋が満たされることなど客観的限度があると主張し、ふだん「水とパン」しか食べなかったにしても、時には少量のワインも飲み、友人にチーズを送ってくれるように頼んでいるし(11)、どの程度の「贅沢」なのかはあきらかではないが「久しぶりに贅沢な食事にありついた場合には、---より楽しく味わう」(131)こともあったようだ。だから欲求充足の快の大きさは変わらないと(理論的に)主張していたにしても、その充足の方法、つまり「多様化」を拒否しなかった。彼はストア派ならばそうしたであろうように節制や禁欲の徳にこだわることを斥けた。そして、当然、「多様な快楽」については、人によって好みの違いがあること、「蓼食う虫も好き好き」であることは認めたはずだ。
エピクーロスは「多様な快」の追求は、それよってその人が後になって別のより大きな苦痛や苦労に悩まされるというようなことがなければ、「何の非難すべき点も持たない」と述べているのであり、いかなる苦も伴わずに(その人が快楽と感じる)快を経験することに対してエピクーロスが反対するとは考えにくい。。
もし、精神の平静こそが最大の快楽であるからと、それだけが追求されるべきで、「多様な快楽」は精神の平静の妨げになると禁じたり抑圧したりするならば、そのときに、ロングの全体主義に対する懸念と批判が妥当することになる。しかしエピクーロスがこのような態度は取ったとは考えにくく、また彼は彼の教説を信奉する人々との共同生活を行ったが、プラトーンのように人々に「正義」を強制する力をもつ国家を構想したことも、国家の指導者になろうと考えたこともなかった。もちろん、また、エピクーロスを、強大な権力を行使して思想を統制しようとするあのビッグ・ブラザーのような人物だと考え、彼の庭園をオセアニア国だとみなす必要もない。
そして、エピクーロスの教説は贅沢や放埓を戒め、節制や禁欲を勧めることに重点があるのでは決してない。彼はストア派とは異なる。基本的欲求の充足と、当時の一般庶民が抱いていた死の恐怖をはじめとするもろもろの精神的な苦しみを解消することが幸福への道だという前提(生の全体構想)に立って、感覚的な「多様な」快楽を忙しく追求するのではなく、自己の生を省み、苦痛のないことの快の大きさを知り、迷信・俗説に振り回されずに世界を正しく認識し、最大の苦を解消し精神の平静に到達できるような生き方の探求を勧めているのである。 (精神的な)苦を抱えている人はその苦を解消するように努めるべきであり、娯楽や、消費のための消費、あるいはバラの香りを嗅ぐことや飲酒によって、その苦から目をそらせるべきでないというのである。
だが、それに先立ち、ロングが「人々の無頓着を見落とした」エピクーロスの「過ち」を指摘するときに念頭にあったはずの、「プラトーンの〔言う〕中間の
生」、快とも苦ともみなしえない「中間状態」について、その内容を確かめておきたい。ロングは苦痛の解消、欠如を快楽とみなすことは出来ないというプラ
トーンの見解を共有している。あるいは、プラトーンの説に追従している。
だが、プラトーンはその「中間状態」が、感覚的に微弱な刺激しか与えないというロングの考える理由と同じ理由に基づいてのみそう考えているのではなく、より重要な理由、その状態が価値的に無だとみなすことによって、そう考えているからである。彼は「真実の快楽」は真実在=イデアーを知ることによって得られるという。身体的な苦痛の解消で得られる快楽はそれとは全く異なる別の物であり、「本当の快楽ではない」、その意味で「苦でも快でもない」と言っているのである。
また、プラトーンを師とし、「プラトン以上にプラトン主義者」と言われることもある18) アリストテレースは、人間の魂の中の最も優れた部分である知性・理性を働かせて哲学を行うことが、人間の最高の活動であり、哲学者の生こそが幸福な生だと説いている。
ロングは「プラトンとアリストテレスにとって、幸福の基本的な構成要素は徳、すなわち「魂」の卓越性である」と言っていた。これはその通りだ。だが、私は、二人の見解は、彼らが庶民とは異なる特別に恵まれた境遇にあったことから生み出されたものであり、彼らの説に依拠することによってはエピクーロスの教説の正しさを否定することはできない、ということを示したいのである。
生物内部の調和が破れると、そのときには、自然(本来)のあり方がこわれ、同時に苦痛が生ずる。しかし、もう一度調和がととのえられ、それ自身の自然のあり方にもどるとき、快楽が生ずる。17節。 もし、崩壊も保全の回復もない「第三の状態」があれば、そこでは快や苦を感じることはない。思慮の生活においては快も苦も生じない。18節。
心身の状態の大きな変化は快苦を感じさせるが、「微小でおだやかな変化」は、快苦を感じさせない。快適の生活、苦痛の生活、どちらでもない生活の三つがある。「苦しみを感じないということは愉快を味わっているということとおなじだということは決してありえない」。26節。
疥癬の治療に摩擦を用いる場合の状態変化は何であるか。快楽か苦痛か。快苦の混合だ。飢えや渇きなどの不足が満たされるときに感じる快楽も同様である。28節。これらは快とも苦とも言えない。他方、混じりけのない快楽がある。「美しいといわれている、色、形、においの大部分などにからまるもの、そして音の響きのもっているもの、つまり不足は気づかれず、苦痛を伴うことも ないが、充足は感覚され、快を感じさせるもののすべて」が「真なる快」だ。「学識に伴う快楽」もそうである。31節。
『ピレボス』の議論は快楽が最高の善だとする人(ピレボス)への反論であるが、結論は快楽の競争相手と想定された思慮もまたそれだけでは善とは言えないとされ、人間にとってそれらの混合が必要だというものである。
『国家』では次のように言われている。
人間のうちでは「思慮ある知者」が最も優れた人だ。快楽に関してはこのような人が愛する快楽が最善の快楽である。快楽には魂の三つの部分に応じた、利得の快楽、名誉の快楽、学び知ることの快楽の三種類がある。このうち「われわれがそれによって物を学ぶところの魂の部分がもつ快楽こそが、最も快いものであり、そしてわれわれ人間のうちでは、まさにその部分が内において支配しているような人間の生活こそが、最も快い生き方である」。第9巻7節、8節、581~582.
苦痛は快楽の反対であり、それとは別の楽しみも苦しみもない状態がある。それは快と苦の中間にあって、快苦に関しては魂の静止状態というべきものである。
苦痛に悩まされている人々は「苦痛のやむことほど快いことはない」と言う。多くの人がこれに似た状態に置かれている。かれらが「もっとも快いこととして讃えるのは、苦しみがのないこと、---苦しみの止んだ静止状態なのであって、積極的な悦楽ではけっしてないのだ」。「実際にそう〔悦楽〕であるのではなく、ただそのように見えるだけなのだ」同583.
「肉体を通じて魂に届くいわゆる快楽の大多数と主要なもの」は、その苦痛の解放が快楽だとまちがえられているが、苦痛を伴わない純粋な、快楽こそが本当の快楽だ。「匂いの快楽は、苦痛が先立っていなくても、突然、非常な大きさで生じてくるし、また止んだあとも少しも苦痛を残さない」。同584.(ロングが「バラの香り」について述べていることは、ここで言われていることにそっくりである。)
こうして、快と苦は対立するもので、苦の欠如は積極的な快とは別のものであり、快でも苦でもない「中間状態」があるとされている。苦に対立する積極的な「快楽」としては、「愉快」、「悦楽」のような心身に「大きな変化」を生じさせるものが考えられている。
空腹が満たされる過程、病気の治療において感じられる状態変化は、快楽と苦痛の混合したものであるが、これに対して、苦痛の混じらない、飢餓感のない快楽がある、とプラトーンはいう。
飢えや渇きは身体における「空虚」(欠乏)であり、食事はその空虚を食物で満たすことである。無知とおろかさは魂の空虚であり、知を得ることはその空虚を満たすことだ。ところで、「純粋の存在により多く与っている」のは飲食物ではなく、真実の考え、知識や徳性などである。「不変にして不死なる存在と真理に
関連をもつもののほうがよりすぐれて存在する。---こうして、身体に奉仕する種類のものは、魂に奉仕する種類のものよりも、真理と存在に与る程度が少ない。より優れて存在するものによって満たされることはより劣ったものによって満たされるよりも、よりいっそうほんとうの意味で満たされる」ことである。
「自分の本性に適したものによって満たされることが快であるとするならば、よりほんとうの意味で満たされ、そしてよりすぐれて存在するものによって満たされるものは、より本当の意味で、またより真実の意味でわれわれに真実の快楽を楽しませるのだということになる」。同10節、585.
「思慮と徳に縁のないものたち、にぎやかな宴やそれに類する享楽に常になじんでいるものたち、彼らは<下>へと運ばれてまたふたたび<中>のところまで運ばれるというようにして、生涯を通じてそのあたりをさまよい続けるもののようだ。
彼らはけっして、その領域を超え出て真実の<上>のほうを仰ぎ見たこともなければ、実際にそこまで運び上げられたこともなく、また真の存在によってほんとうに満たされたこともなく、確実で純粋な快楽を味わったこともない。むしろ家畜たちがするように、いつも目を下に向けて地面へ、食卓へとかがみこみ、餌をあさったり交尾したりしながら身を肥やしているのだ」〔とソークラテース〕。「あなたは神託を告げるような仕方で、大多数の人間の生き方をのべられましたね」〔とグラウコン〕。「 かれらがなじんでいる様々な快楽というものは、苦痛と混じり合った快楽にすぎず、真実の快楽の幻影であ」る。同586.
以上が『国家』と『ピレボス』にある、快と苦に関する文の抜書きや要約である。それによれば、飲食によって欠乏を満たす際に感じられる快楽は本当の快楽ではなく、単に、欠乏の苦がない「中間状態」に戻るだけである。本当の快楽は、芳香を嗅ぎ、思惟によってイデアを認識するときのような、苦痛の混じらない、 純粋な快楽だという。先にみたように、ロングはこうしたプラトーンの著作にある快楽説に立ってエピクーロスを批判しているのである。
プラトーンは飢えや渇きを満たす欲求充足活動の意義を認めていなかった。欠乏や病気などの苦からの解放は苦と快とが入り混じったもので本当の快、「悦楽」ではないとされていた。飲食などの欲求の充足はむしろ「家畜」の快楽に類したものとして軽蔑されるだけで哲学の対象ではなかった。
また快と苦は運動にともなって生じるとされていた。欲求充足後には欲求充足過程におけるような運動は存在せず、快も苦も感覚されない。それは、「微小でおだやかな変化」しかない静かな状態であり、「快でも苦でもない」「中間状態」だとされた。
しかし、エピクーロスは、欲求を充足し、それによって飢えや渇きの苦痛を解消することは、身体に関して不可欠であり、欲求が充足された状態は積極的で肯定的な意味を持つと考えた。この状態は単なる「苦の欠如」状態、快でも苦でもない「中間状態」ではない。かれはこの状態を「静的快楽」と呼ぶ。
そして、身体的必要の充足、身体の静的快楽は簡単に実現できるわけではなく、苦の状態から出発して、それを解消するのに必要な労苦を支払う活動によって初めて実現でき、安定的に維持されるべき大切な状態である。この状態の実現のために、思慮、勘考、哲学が十分な役割を果たすことが求められる。
さて、プラトーンの場合には、「中間状態」で「真実在」を見る/知る活動である「愛知としての哲学」を行うことによって、魂がイデアー界に向かって上昇することが求められる。そしてこの活動こそが「真実の快楽」に与ることを可能にし、幸福な生を約束するものであった。
エピクーロスは、欲求充足により身体の苦が解消されるだけではなく、死や神罰への不安や恐れなどの精神的な苦からも解放されねばならない、と言う。したがって身体的な「静的快楽」状態に満足するのでなく、それら精神が抱えている苦を解消するための哲学と自然学を行うことが求められる。人間と世界の現実を捉えることによって魂の苦を解消することが課題であり、身体的な苦痛とともに精神的な不安・動揺の苦しみのないことが最大の快楽であり、幸福であって、そのためにこそ、自然学、哲学が行われるべきだ、というのである。
身体的な苦の解消による静的な状態への到達と、そこでの更なる哲学(エピクーロス)の努力/それと全く別な「愛知としての哲学」(プラトーン)による、より大きな精神的快楽の実現という、一種の明白な段階論が両者に共通に見られる。違いは、プラトーンが人々の現実生活を「家畜の生活」と見下し、「神託を告げる」ように語る哲学者の優位を論じ、哲学者の統治する国家の必要を説くのに対して、エピクーロスは現実の生活に苦しむ庶民の立場に立って、庶民と一緒に生活しながら、心身の苦を解消することにあくまでもこだわる、というところにある。
このように整理し両者の説を比べてみると、快楽と人間の幸福に関するエピクーロスの教説は、ロングが強調するようにプラトーンの見解と対立してもいるのだが、同時に、それと極めてよく似ており、プラトーンの説の換骨奪胎、改作だと見ることもできる。
アリストテレースは『ニコマコス倫理学』第10巻第4章で次のよう述べている。
「すべてのひとが快楽を欲するのは、すべての人が生きることを求めているからだと考えてよいだろう。生はひとつの活動である。そして、それぞれの人が活動するのは、自分のもっとも愛好することにかかわり、自分のもっとも愛好する能力を用いるときである。たとえば音楽的な人は聴覚を用いて歌曲にかかわって活動し、学問好きな人は思考を用いて観想(テオーリア)の対象にかかわって活動する。他の種類のひとのそれぞれもまた同じである。そして、快楽はそれぞれの活動を完成し、それによってひとびとの欲する生を完成する。
したがって、ひとびとが快楽を求めるのは当然である。なぜなら、快楽はそれぞれの人にとって望ましいものである生を完成するからである。快楽のために生を選ぶのか、それとも、生のために快楽を選ぶのかという問題は差し当たり論じないことにしよう。これらが組み合わされていて、切り離しえないのは明らかである。なぜなら、活動なしには快楽は生まれず、快楽はすべての活動を完成するからである」。
1175a。
だから人々が愛好する活動を行なうときには快楽が生まれる。「快楽が活動に随伴する」。あるいは快楽が「活動に加わり」、「活動を完成する」とアリストテレースは言う。1174b,1175a
第7巻では11章と12章で、快楽と苦痛に関する様々な説を逐一検討した上で、第13章で「苦痛は悪いものであり、避けるべきものである」ことはたしかなことであり、それに「相反するものは善いものである。したがって快楽は、必然に、或る善いもの〔善いもののひとつ〕でなければならない」。「獣も人間もす
べて快楽を追求するという事実は快楽が何らかの意味において最高善であるという一つの証拠」だと言う。1153b
また、第10巻第2章では「最も望ましいものとは、ほかのもののゆえにではなく選ぶもの、ほかのものを得るためにではなく選ぶものである。そしてそのようなものが快楽である」。何のために快楽を選ぶのかと問う人はいない。「快楽はそのもの自体としてみて望ましいものである」。「また、どのような種類の善い
ものであれ、これに快楽が付け加えられるとき、快楽はそれをいっそう望ましいものにする」というエウドクソスの説を紹介する。
そして、この議論が快楽がそれだけで望ましい最高の善であるということまでは「明らかに」はしていない(なぜなら、賢慮を伴った快楽の生は、快楽だけの生よりも望ましいから)、という点を除き、肯定する。1172〔「賢慮」はフロネーシスの訳で、エピクーロスの場合には「思慮」と訳されていた。〕
アリストテレースは、快楽は器量・アレテーに基づく活動に随伴するもの、活動を完成させるものだという。第7巻12章では
快楽とは「自然の本性にかなった性能の活動」〔から生まれるもの〕とされている。1153a.「性能」はヘクシスの訳である。ヘクシスとは習慣で、後天的に形成される性向である。特定の活動に対する愛好はその人の性向に含まれているし、「好きこそ物の上手なれ」というように器量もその性向によって形成されるところが大であろう。そして、何かを愛し好む性向は、行為がその人に快楽を与えるがゆえに形成されるか、あるいは快楽により形成を促進されるであろう。たとえば、不正義に怒りを感じたり弱いものを助けたいと感じる性向は、それらを動機とする行動が周囲の人々により褒められることにより子供の中に育成されるのであろうし、親切心や正義感などの倫理的徳(器量)はそうした性向によって形成されるであろう。
したがって、快楽はアレテー・器量に基づく活動から生まれるもの、あるいはそれに付随するものだといっても、アレテーの形成過程でもはじめから、快楽と結びついているのものであり、快楽とは別個のものとしての器量があって、その器量による活動に、あとで何か別の原因によって快楽が付け加わるというのではない。例えば、好きではないことを我慢して行い、賃金をもらって、旨いものを食べるという場合には、活動が結果として快楽を生むが、この場合には快楽が活動に付随するとは言えない。アレテーに基づく活動と快楽とは一体のものである。
ストア派的な倫理的な徳を目指す活動について、それが相当大きな自己犠牲を必要とするような活動の場合(ただし、生命や健康さえもどうでもよいもので、徳のみが善だとする考えはとらないとする)であっても、不徳の存在となることの意識から生ずる不快・精神的苦を避けようとすることが動機であり、したがって快(精神の平静、静的快)を目的とするものだと言えることを、上のロング「第一の批判」への反論の中で、セネカの議論に対する反論として述べた。アリストテレースによれば徳に基づく行為こそ快楽と結びついている。
1174aでアリストテレースは「たとえ、そこから何の快楽も生まれないとしても、われわれは多くのことに熱中しうる。見ること、記憶すること、知ること、器量を備える〔徳を身につける〕ことがその一例である。たとえ、これらのことには快楽が必然的に随伴するとしても何もかわりない。というのは、そこから快楽が生まれてこないとしても、われわれは同じようにこれらを選ぶであろうからである」と述べている。
しかし、この文では、徳に基づく行為の場合に、そこから快楽が生まれなくても選択がなされうるということの例が示されているのではない。彼は「学習の快楽」、見ること、聞くこと、記憶が快楽であると直前のページで述べている。これらはいずれも、何らかの意味で人間の「器量・アレテー」に基づく活動なのであり、快楽を必然的に伴うものである。すべての活動は快をもとめ、不快を避けようとすることと分かちがたく結びついている。
一般に、「快楽のために生を選ぶのか、それとも、生のために快楽を選ぶのかという問題」は次のような問題であろう。
「快楽のために生を選ぶ」場合とはエピクーロスが説くように、「快楽を最大とすることを生の目的と考え、生の諸活動を快楽の観点から取捨選択しようとする」生き方で、こちらでは、徳は快を実現するための手段と考えられている。ただし、その都度の、一つ一つの活動の快不快は問題ではなく、長期的に、総合されたときに、快楽の大きさ、したがって幸福であるかどうかが判断される。
これにたいして「生のために快楽を選ぶ」というのは善き生の実現のために快楽を適切に取捨選択しながら生きることである。アリストテレースは万物が快楽を追求すると言うことは認めるが、同時にすべての快楽が善であるわけではなく、劣悪な快楽があると言う。不適切に、劣悪な快を選べば、劣悪な(不幸な)生になってしまう、と言う。
こうして、アリストテレースに従えば、エピクーロス的に生における快の最大を実現しようとする生き方には問題があることになるだろう。劣悪な行為から生じる快、劣悪な快が存在するが、そのような快を回避し、優れた善い快を選択するという条件があれば、人は「快のために生を選ぶ」のでも、「生のために快を選ぶ」のであっても、同じく、優れた善い活動を追求して生きることになる。ここでは、しばらくアリストテレースの考えにしたがうことにする。問題はいかなる活動が「優れた善い」活動であるの
かということになる。
アリストテレースによれば、人間の「器量」は三種類にわけられる。テオーリア、必然的なものを観想(思惟、認識)すること、プラークシス、行動によって自己の善さをあらわすこと、そしてポイエーシス、(芸術作品を含む)物を作ることである。第6巻第1~第5章
しかし、彼はそうは言っていないが、人間はそれら以外に、自然や人間と交わりつつ「楽しむ」=「遊ぶ」能力・働きをもっていることも確かである。遊びの活動は、人間の理性・精神に備わっているもう一つの能力・働き、アリストテレースの言葉で言えば、性向と器量による活動である。
そして、アリストテレースが学問がもっとも優れているとみなすのは、それが「役に立つ」からではなく、「役に立たない」からであり、もっぱら自己充足的な自己目的的活動だからである。現代社会においては、学問が「役に立たない」という点は疑わしいし、各自の生活の必要と無関係に学問が行われているわけでもない。自己目的的性と言う観点からは遊びのほうがより優れた「最高の」活動だということになるのではないだろうか。
「遊ぶために辛い仕事をするのはおかしい」とアリストテレースがいうのは、彼が、遊びを辛い仕事に対する休息とみなしており、労苦がなければ、休息つまり遊びも必要がないと考えるからである。だが、遊びは単に(労苦の後の)休息でなく積極的な楽しい活動であり、仕事は遊びという究極目的を行うための手段と
しての活動だと考えれば、遊ぶために仕事をすることは少しもおかしくない。
アリストテレースは仕事の詳しい定義を与えていないが、「真面目にすること」であると述べている。その代表例が最高の器量(観想)による最も優れた活動である学問である。彼は家事・育児の労働はもちろんのこと、生活費を稼ぐために他者に雇用されて行う労働は「仕事」だとは考えていないだろう。そして、仕事
は成人が自分の一生を構成するものとして行う活動で、その時々に行われるような遊びと対立する何かと考えている。
仕事にも、アリストテレースにしたがっていえば、立派な仕事と劣悪な仕事(たとえば金儲け)があるだろうし、「真面目に」とは「真剣に」とほぼ同じだと思われるが、すべての仕事が真面目に、真剣に行われるとは言えないであろう。他方、たぶんアリストテレースの念頭にあるような単純な、短時間の気晴らしは別 として、遊びにおいても、真面目さや真剣さを必要とし、そして辛いことや場合によっては危険すらもふくむ遊びがいくらでもある。
奴隷制の上に立つ古代ギリシャ・アテーナイの「市民」と違い、われわれ現代人のほとんどは、仕事をせずに遊ぶことはできない。一生を通して考えれば、普通の人は、ある時期までは仕事を中心にした生活を送ら ざるを得ない。そこでは、遊びは休息として行われるという面が強いであろう。しかし、或る年齢に達すれば、年金生活に入り、何かのためでない、つまり仕事のための休息ではないような遊びの活動、快楽を目的とする遊びを、それ自体として行うことができる。一生を通して考えるとき、一定の条件の下で、人間は幸 福な生を実現するために、究極的な目的である遊びの生を実現するために、ある時期まで、仕事をするのだと考えることができる。
アリストテレースにとっては、純粋な思惟の活動である哲学は生活の必要を満たすための活動ではなく、生活の苦労と切り離されたところで営まれる、自己の器 量を発揮する活動である。したがって、哲学は快楽を与えるが、快と苦が入り混じった快楽ではなく、純粋に知的な快楽だということになる。「智慧にしたがっ て生まれる活動は、万人の認めるとおり、器量によって生まれる活動のなかでもっとも快い---。とにかく、智慧の愛求〔フィロソフィアー〕はその純粋性と 確固性において驚嘆すべき快さをそなえている---」。1177a20.彼は、彼の師であったプラトーンと同様、哲学によって得られる快楽は、苦の混じっ ていない、「高尚な」、人間にとって「最高の」快楽であり、純粋な「真の快楽」だと考えたのである。
たぶん、歴史的に知られたほとんどすべての社会において、生活における労苦の必要度が異なる様々な人がいた。アテーナイの場合、奴隷によって主要な産業が担われていた。だが、何らかの仕事(農業、商業、教師、---)をして収入を得る必要のある市民もかなりいた。他方、プラトーン19)の ように貴族の家系に生まれるなどして、生活の心配をする必要の全くない人もいた。彼は身体の健康にも十分恵まれていた。アリストテレースも父はマケドニア王の侍医であったというのだから、恵まれた家庭の出であったことは確かだ。一つの社会のなかで、技術知や、実業に関する知識、つまり生存の必要を満たし、苦を解消するのに役立つ知識ではなく、純粋な知的好奇心を満たすことに向かうことが可能であったのは、生活の必要を免れた、恵まれた少数の人々であったと考えることができる。
これらの人々は、物質的には不自由のない、安全の確保された平穏な生活を享受することができた。彼らにとって、この状態が当たり前のものであり、「快でも 苦でもない中間状態」と見なされるだろう。そして彼らは、「快と苦の入り混じ」っていない、純粋で高級な快を与えてくれる「哲学」に向かう。特に、生物の 研究に時間とエネルギーの多くを注いだアリストテレースの場合、純粋な知的好奇心のおもむくままに自然学、哲学の研究に向かったとみることができる。
プラトーンは衣食住の心配の必要はなかっただろう。しかしソークラテースのような高潔な人物を死刑にしてしまう現実の国家・社会のあり方にかれは満足でき なかった。彼の哲学は、現実の人間世界との関連を欠いた、たとえば、数学、あるいは生物学のような、純粋に理論的学問であったのでも、知的好奇心のみに よって行われる活動だったのでもなく、正義と不正義、権力と支配をめぐる争いが行なわれる現実の世界を変えようとする強い実践的な動機にも支えられてい た。
死後「神のごとき人」と称えられ(DL第3巻43節)、2千数百年にわたるヨーロッパの思想家たちの書いたものはプラトーンの著作への単なる「脚注」に過 ぎないと、ホワイトヘッドに言わせたほどのプラトーンの哲学が、心的な外傷により蒙ったストレスによって生み出されたなどと言いたいわけではない。ソーク ラテースの死によって強いショックを受けた人はたくさんいたであろうが、プラトーンの哲学はプラトーンの天才によってしか生み出されなかったことは言うま でもない。だが、彼は、ソークラテースの死をきっかけにして、ポリスについての哲学的思索に向かい、『ポリテイア(国家)』を書き、政治的行動もおこなっ た。
彼は、シキリア(シシリー)島への3回の旅行(40歳ころに第一回目、3回目は27年後)を行い、哲人政治の実現を目指し、シュラークーサエの僭主との交 わりも持った。彼が関係者にあてた「第七書簡」では「本当の意味で真実に哲学している人々の種族が支配者の地位に就くか、あるいは、国々で権力の座にある 人たちが、なにか神的な摂理によって、真実に哲学するようになるまでは、人類にとって、不幸は止むときはないことでしょう」と述べられている。前出シャト レ「プラトン」から引用。斎藤忍随『プラトン』<人類の知的遺産>7(講談社、1982)も参照。
彼の哲学が、快と苦に全く関係のない自由な思索活動、純粋な知的好奇心によって生み出されたのではなく、ソークラテースの死が与えたショックが彼の思索の エネルギーになり、また思索の方向にも一定の影響を及ぼしたことは確かである。彼は、彼を苦しませた現実世界からその原因を取り除こうとした。その意味で 彼の活動は快=「苦の欠如」を実現しようとするものだったと言えないことはないだろう。 しかし、彼の哲学は理想の「哲人国家」の実現のために善のイデアの探求に向かう。このイデアを見る/知ることが与える快は、空腹や痒みなどの身体の苦とは 関係のない、純粋の快、本当の快である。苦痛の欠如/解消と快とは同じではない。この快に関する見解は、エピクーロスの見解と真っ向から対立している。
しかし、アリストテレースのように純粋な学究生活を送ることの可能な人はほんの一握りである。彼の説に従えば、哲学者、あるいはもう少し範囲を拡げても、 学者・研究者以外は、つまり、人間の99.9%は幸福にはなりえないということになる。だが、人間は皆幸福になることを欲する。そして人間の置かれた境遇 は様々である。望ましいのは社会がすべての人が幸福になれるように条件を整えることである。そして、これが難しい現実においては、特別な境遇の少数者だけ が幸福になりうるというのではなく、平凡な多くの人々が置かれている共通した条件あるいは状況においても幸福になることが可能だという教説こそが多くの人 の承認を得ることができるのではないか。 エピクーロスの観点から言えば、アリストテレースは、大多数の人間が生活の労苦の中にあることを問題にせず、生活において何一つ不自由がなく、平穏な生存 を享受している(つまり、アポニアーとアタラクシアーをほぼ達成している)「中間」状態を前提して、その生活の上に可能なアレテー(徳・すぐれた能力)に 基づく活動だけを考えている。
当時のアテーナイの上層市民は、戦時は別として、基本的に生活の心配、労苦は免れていた。病弱な者は赤ん坊の時に遺棄されたから20)、 成人は皆、健康で丈夫な身体をもっていた。おまけに、日常的に行われた軍事訓練としての体育で鍛えられてもいた。プラトーンの「立派な体格」については上 でふれた。こうして、アテーナイ上層市民は、一日に数回の空腹やのどの渇きなど、すぐに充足される短時間の小さな苦を除いて、エピクーロスのいうアポニアーとさほどちがわない「快でも苦でもない中間状態」にあると考えることができたであろう。(たただし、栄誉や富を得ようとする競争心が強く、権力闘争が 絶えず起こったから「平静心」にあったとは到底認めがたい。)こうした状況から知的に洗練された哲学論議に快を見出すものが多数輩出した。彼らはこの活動の中で快の増大を感じることができる。彼らはロングが「バラの香りに」について言っているのと同様「何の苦痛もこうむっていない状況で」「何か独自の種類 の---新しい満足感」を哲学のなかで感ずることができたのである。
私もこうした慢性の痛みを経験する以前であれば、ロングの言うような中間状態の一般的な存在を認めたかもしれない。中間状態を否定するとしても、ロングの
「第一の批判」への反論においてそうであったように、行為の説明(とくに徳を目的とする行為)における論理的な首尾一貫性を維持するために、「苦の欠如は
快である」と考えることが都合がよいということがその主な理由であっただろう。
しかし、私は慢性的な身体の痛みを実際に経験することで、人がふだんの平穏
な状態を苦ではないにせよ快でもなく、幸福と呼ぶに価するとは感じていないことがたとえ事実であっても、この平穏な状態は常に存在し続けるのではなく、失
われ得るということ、そして、それが失われたときには、その状態が実は快適で幸福な状態であったことに気がつく、ということをたしかな事実として発見し
た。
また、慢性的な痛みの経験は私に、人間は一般に壮健で、ふだんは快でも苦でもない中間状態にあり、そのどちらでもない健康な状態でさまざまな快楽を味わうことが
できる存在なのではない、という事実を発見することを可能にしてくれた。私はこの事実を発見することにより、体力も、記憶力や思考力など知的・精神的能力
も低下していく老後の生が不満足で不幸なものだと考えないで済むことができるようになった。
心身に何も障害がなく痛みも苦しみもないという状態は、誰もが一生にわたって享受できるものではなく、むしろ、最も体力のある一時期にのみ、それも運の良
い少数の人だけが享受できる状態なのである。身体に関してだけ見ても、生まれつきの障害をもっている人、事故その他のために障害を負った人々、あるいは何
らかの重い病気や怪我で長期にわたって入院生活を送らねばならない人々、ある年齢以上の大部分の老人たち、そして原因不明の「難治性」の痺れや痛みを抱え
た人など、何らかの持続的な苦の状態にある人の方が多数だと推測されるのだ。とくに原因の特定されない痛みは病院に行っても治してもらえない(診察料や薬
代は取られる)ために、患者は苦しみながら黙って我慢している。
人間が一般にいつも壮健でありそれが当たり前のことだと信じていると、静かな安らぎの時間を持つことは快でも苦でもない単なる中間状態、空白で退屈な時間 をすごすことであると考えることになり、また、スリルや興奮に満ちたスポーツ、賭け事などの遊び、セックス、グルメ、飲酒などから得られる、そのつどの 「動的な」快楽を味わい続けることが、「快楽を増大させる」ことであり、人を幸福にするのだと考えることにつながる。
娯楽や遊び、飲酒など「動的快」は現代人特有の精神的ストレスを軽減してくれる限りで必要だが、身体の痛みや病いの原因を取り除いてくれるものではない。 そして、そのような「多様な」動的快楽を忙しく次々と追い続けることは、いつ失われるかわからない、今ここにある静的な快楽、落ち着きと安らぎの時間を十 分に享受し、そこから可能な最大の快楽を汲み出すことを妨げてしまう。人により感じ方が異なることは確かだろうが、多様な動的快を追求することが、長期的 にみて、最大の快を与え自己の生に対する満足感と幸福感を与えるとは決して言えない。
そして、私は「苦の解消/欠如は快である」と言うエピクーロスとともに、(いつまで続くかは分からない)身体の大きな苦のない現在の私の状態を快楽だと感 じているというだけでなく、退職後10年になる自己の生活の全体---詳しくは第4章と第5章で述べようと思うが、概括すれば、時々は魚を釣る興奮も楽し んだが、大抵は多くの時間、魚の当たりを待って小さな船内で仏像のようにただじっと坐っているだけであるような「静的」な楽しみを享受することで過ごして きたこと---を十分な満足感を持って振り返ることができている。私は、身体の苦がなければ、そして、魚の当たりを待っているのであってすることがなく退 屈するわけではないという条件があるにはあるが、釣れなくても、あるいは釣れないが故にただ静かに坐って時間の流れに身を任せるだけの生が、大いに満足の いくものであることを発見した。
文学者・哲学者ルソー(1712-1778)は、若い時に社交界で華々しい生活を送り、のちに孤独な隠遁生活を送った。かれは1765年、53歳のとき、 隠れて住んでいたモティエで迫害を受け、ビエンヌ湖のサン・ピエール島というところに、逃れ住んだ。彼は言う。 「魂が十分強固な地盤を見出しそこにすっかり安住し、そこに自らの全存在を集中して、過去を呼び起こす必要もなく未来を思い煩う必要もないような状態、時 間は魂に取って何の意義も持たないような状態、いつまでも現在が続き、しかもその持続を感じさせず、継起のあとかたもなく、欠乏や享有の、快楽や苦痛の、 願望や恐怖のいかなる感情もなく、ただ私たちが現存するという感情だけがあってこの感情だけで魂の全体を満たすことができる、こういう状態があるとするな らば、この状態が続く限りそこにある人は幸福な人と呼ぶことができる。それは---充実した完全無欠な幸福である。---こうした状態こそ、私がサンピ エール島において---孤独な夢想にふけりながら、しばしば経験した状態だった」。
ルソーの肖像画。Wikipediaによる。

この 「継起のあとかたもなく、欠乏や享有の、快楽や苦痛の、願望や恐怖のいかなる感情もなく、ただ私たちが 現存するという感情だけがあ」る、という箇 所は誇張されている。これでは植物状態一歩手前で、身動きもせず、ただ自分が生きているというぼんやりした感情、意識だけがあるような状態に聞こえるが、 実際には、彼は生活し、過去を思い起こし、考え、動き、したいことをしていたからである。
サンピエール島でルソーが一生の中で最高に幸福であったと感じた生活とは、具体的には孤独な散歩、植物採集、湖水が穏やかなときにそこに浮かべた舟のなかに寝そべって、何時間も夢想にふけるという生活だった。 「この隠れ家を永久の牢獄として一生の間ここに閉じ込めてもらえたら、--対岸との交通をいっさい禁止してもらい、世間で起こることは何も知らず、世間の存在を忘れ、世間からもまた私という者の存在を忘れてもらえたら、とどんなに願っていたことだろう」。 彼は植物採集に熱中した。「もう骨の折れる仕事はしたくなくなった私には、自分の気に入った、そして怠け者でも嫌にならない程度のほねおりしか必要としない、楽しみとなる仕事が必要だった。」
「長い生涯の間の移り変わりの内に、私はこの上もなく甘美な享楽と強烈な歓喜の時期の思い出が意外にも、私をひきつけ強く心に触れるものではないことを 知った。激しい情念に取り付かれたそれらの短い時期は、どんなに生気に満ちたものであろうとも、その激しさのゆえにこそ、生の直線上にまばらに散らばった 点にすぎない。それはごくまれに起こり、すみやかに消え去るのであって一つの状態を構成することはできないし、私の心が愛惜する幸福とは、たちまちに過ぎ 去る瞬間から成り立っているのではなく、一つの単純な変わらない状態なのであって、---その持続は魅力を増大させ、やがてそこに至高の幸福を見出すにい たるのである」。佐々木康之訳『孤独な散歩者の夢想』(白水社<ルソー全集>第二巻、1987年)
ルソーはヴァラン夫人をはじめとするかつて出会った女性たちとの恋愛の中で「この上もなく甘美な享楽と強烈な歓喜」を何度も経験した。エピクーロス的に言 えば「多様な」、「動的な快」であり、ロングの言葉では「高揚の感情」「積極的な快楽」である。そして、それらは「この上もなく甘美で、強烈」だったのだ から、彼は最大の快楽を実現したはずである。
当時の貴族界では夫のある女性が別の男性と恋愛関係をもつことは、現在不倫という語が意味している関係のように良心の咎めのようなものをともなう関係では なかったようだが、それでも独身の男女間の恋愛のように結婚がゴールインになるような幸福なゴールは存在せず、そのつどの逢引としてしか成立し得ず、はじ めから別れが約束されたものだった。それゆえに「甘美な享楽と強烈な喜び」を与えるものであっただろうが、また、その強烈な「快楽」はその都度「速やかに 消え去」ったという。
飲食の動的快楽が飲み、食べている間にだけ感じられ、食事が終わるとともに消えてしまうのと同様、情熱的でロマンチックな行動が与える興奮に満ちた快楽は結局「瞬間的に吹き過ぎる」もので、持続しなかった。エピクーロス派のトルクワートゥスによれば、食事後の充足においては食事中の動的快楽とは異なる安定した「静的快楽」が存在する。
恋愛においてもそれに相当するものが存在するのだろうか。食事の満足の後で達せられる静的快楽については、後の「静的快楽」再考で、私の解釈を述べるが、それとの類推で言えば、おそらく恋愛において実現される「静的快楽」は、自己自身と同じように全面的に受け入れ愛することの出来る存在であるような相手との安定した相互関係についての(一定の)確信ではないだろうか。
恋愛においてこうした境地に到達できることはたぶん簡単ではないだろう。ルソーは実際その境地には到達できなかった。彼は何人もの女性との恋愛において、短期間の親しい関係もしくはそのつどの逢引きが終わるたびに、その快楽が「速やかに消え去」る経験しかできなかった、と思われる。
彼はこうした経験を経、晩年になって動的快楽を多く経験することが快を増大させることではなく、幸福を構成する経験としての快楽は持続するものでなければならないということを発見した。そして彼は孤独な散歩、植物採集、穏やかな湖に浮かべた船に寝そべって何時間も夢想にふける生活のなかに、幸福を構成する 持続的な快楽、精神の平静を与えてくれる快楽を見いだしたのだった。そしてサン・ピエール島の生活における「孤独な散歩と夢想」という「静的快楽」が持続的で「充実した完全無欠な幸福」を感じさせるがゆえに、最大の快楽と感じた。
だが、次のよう反論があるかもしれない。ルソーが、興奮と強い喜びに満ちた生活よりも、孤独で誰にも妨げられない静かな生活のほうが「充実した完全無欠 な」幸福だと感じたのは、それ以前の経験があったからである。彼は、以前、とにかくしばらくの間、激しい恋愛に跳び込んで行った。当時の彼にとってはそれ が大きな快楽であり喜びであった。それが最大の快楽でも、本当の幸福でもないと気がつくのは、後になってからである。彼が、激しい恋愛を経験したことがな く、最初から、サン・ピエール島で、気ままで、孤独で、静かな生活を送っていて、この穏やかな幸福の生活に満足を感じていたと仮定して、そこにヴァラン夫 人のような女性が現れたとしたら、彼はやはり、激しい恋におちいるのではないか。そうだとすれば持続的な、きままで孤独な静かな生活から得られる快楽のほ うが、激しい恋愛から得られる快楽よりも大きいとは言えないのではないか。
彼がその孤独で静かな生活を棄てて、激しい恋愛に陥ると仮定してみよう。しかし、やはり、同じ結果になるのではなかろうか。ルソーは、しばらくの間、興奮 と強い喜びに満ちた生活を送るだろう。しかし、かれは、このような生活は本当の幸福ではない。以前に送っていた穏やかな生活こそがずっと幸福であったと気 がつく、と私は思う。
人はだれでも、とくに若いときには、恋愛のような、激しい喜び、強い快楽をもとめて行動するかもしれない。きっとそうするであろう。しかし、「自然的で」 「必要不可欠」な欲求の充足とは異なり、「高揚の感情」や「積極的な快楽」は時々は求められても、たえずそれを追求することは不可能なのではなかろうか。 ドン・フアンのように次から次へと新しい恋愛の快楽「高揚の感情」、「積極的な快楽」を追い続けることに、おそらく、人間の精神は耐え切れず、心を病むこ とにならざるを得ない。「自然的で」「不可欠な」欲求の充足、そこには身体的な苦痛の欠如ということも含まれるだろうが、それらが満たされたあとには、 (日々のストレスをためないようにする若干の楽しみと)持続的な精神の平静さこそが最大の幸福を与える、そのように私には思われる。
ルソーは「バラの香り」のような興奮と喜びにみちた生活と、孤独な散歩の、静かな生活の両方を経験した。彼は、他者に、また面倒な仕事に、煩わされること なく、自己自身のこれまでの生と現在の生をみつめ、現在の穏やかな生活こそが完全無欠な、つまり最大の喜び=快楽であり、幸福であることを発見したのであ る。エピクーロスはふつうの生活の中で、誰もが簡単に、自ずと、この平静の精神、アタラクシアーの大きな快楽、幸福を見出せるとは言っていない。彼はアタ ラクシアーに到達するためには、一生の哲学が必要だといっている。ルソーは情熱的な、行動の人でもあったがまた思想家であり、彼は一生に渡り、社会につい ての思索と自己省察を続けた。そして晩年になってこの境地に到達することが出来た。
私は、上の文を書いたその一年後にM.フーコー他『自己のテクノロジー』所収、ハック・グットマン「ルソーの『告白』―自己のテクノロジー」を読んだ。
グットマンによれば、ルソーは感情生活への価値付与によって、当時の理性を過大評価したヨーロッパ世界から自己を区別し、感情的生活を基盤として自己を個
体化する『告白』作業を通じて、みずからを主体化したという。(グットマンのいう主体化とは、フーコーのそれと同様、社会を覆っている権力の網の目のなか
で社会的諸力によってに貫かれながらそれを強めようとしたり逆に抵抗したりしている、服従する者であるような主体のことである。)
だがグットマンは「ルソーの自伝的で告白的な著作の大いなるアイロニー・反語のひとつは著作の中心戦略、つまり自己を自己ならざるものから分離すること、その結果起こる自己の探求と賛美が結局最後には否定されるという事態だ」と言う。
「ルソーの個体化された自己は、結局は、役立たずだとわかり、そのために起こる必然的に起こる喪失はその自己が生み出す代償的な満足に結局のところまさり、そしてルソーは、自分の告白的な数々の著作が無理やり定めようとつとめる、自己の境界そのものを最後には無に帰す―もしくは無に帰したいと思う―のである」と言う。
そして彼は「ルソーは積極的な自己を捨去り、自己と自己ならざるものとの境界を消し去って、そして自己と自己ならざるも
のへの分割に先立つあの統一性の写しであると思われる全体性に身を委ねる」と言って、私が引用した文とは異なるが同じ『孤独な散歩者の夢想』からその一節
を引く。全部をそのまま引用しよう。(a)、(a')などは後の便利の為に私が入れたものである。
(a)夕方になると、島の頂を下りて、このんで湖の岸辺に出て、砂地のどこか隠れた休み場所にいって坐る。そこでは波の響きと揺れ動く水面がわたしの官能
を捉え、心から他のいっさいの動揺を追い払って、甘美な夢想に引き入れ、しばしば夜がやってくるのも気がつかないでいる。寄せては返す水面の波、単調な、
しかし時をおいて大きくなるその響きは、休みなく私の耳と目にふれて、夢想に消えた内面の運動に変わり、考える努力をしないで、十分にわたしというものの
存在を喜ばしく感じさせてくれる。時々、この世のことのはかなさについての漠然とした短い間の反省が浮かんできて湖水の面に世の姿を示してくれる。しか
し、やがてそれらの淡い印象は私を揺すぶっている一様な連続運動のなかへ消え去る。この運動は心の積極的な協力を全然必要としないで、しかもわたしを強く
惹きつけ、時刻と合図にうながされてそこから立ち上がるにも努力を必要とするくらいだった(a')。---
(中略:グットマン)---
(b)そのような境地にある人はいったい何を楽しむのか? それは自己の外部にあるなにものでもなく、自分自身と自分の存在以外のなにものでもない。この
状態が続くかぎり、人はあたかも神のように、自ら充足した状態にある(b')。(c)他のあらゆる情念をふりすてた存在感はそれ自体、満足と安らいの貴重
な感情なのであって、この世でわたしたちの心をたえずこの感情からそらして、その楽しみをかき乱そうとするあらゆる官能的な、地上的な印象を自分から遠ざ
けることができる人には、その感情だけで十分にこの存在は愛すべき快いものとなる。しかしたえず情念に悩まされている大多数の人々は、そういう状態を知ら
ないし、あるいはほんのみじかいあいだしか、また不完全にしか味わったことがないので、それについてはあいまいで乱れた観念しか持つことができず、その魅
力を感じとることもできない(c')」。
この文に関しグットマンは次のように言う「わたしどもがこれらの文章に見るのは、びっくりするほどの一点集中である。夢想と想像に完全に没頭することによって、想像する自己は無となり、しかも自己と自然は分化されず、分割されない統一の中に吸収される。フロイトはこの状態の、一種の宗教的体験としての遍在的な現われに言及しつつ、この状態を、---「海洋的感情」と呼んだのだが、この感情を彼は、自我の喪失に対する、宇宙の中への自我の分化されない没入に対する代償的要求であると考える」と。
だが、私は、宗教的体験とは、現実をはるかに超え出た、そして感激と興奮に満ちた、そしてごく稀にしか出会うことのできないような体験のことだと想像する。
ところが、上のルソーの文の中に、私は「一点集中」、「自己が無となり、分割されない統一の中に吸収されて」しまっている状態を見いださない。そこで述べられているのは、強い緊張から解放されゆったりとした気分に浸っているときにはだれでも経験できる状態で、決して超現実的でも、まれにしか起こらないことでもない。したがって、グットマン(あるいはフロイト)が言うような「宗教体験」を見て取ることが全くできない。
またグットマンは、ルソーのこうした「宗教的体験」を根拠に、他者との区別、社会からの分離によって自己を個体化、主体化しようとしたルソーの企ては挫折したのだと主張しているが、私はこの主張も肯定できない。
確かに(b)~(b')には「神のように充足した状態」と言う言葉があるが、グットマンはその言葉にひかれて、ルソーの散歩中の体験、心の状態が神との関係において説明するのがふさわしい体験つまり「宗教的体験」だと考えてしまったのではないか。しかしルソーの文を吟味してみると、散歩中の彼の心の状態
(a)~(a')と、(c)~(c')には「宗教的」と呼ばれるような、そう呼ぶことがもっともふさわしいような内容は皆無と言ってよい。
(a)~(a')で書かれていることは、岸辺に坐っている時に周囲の景色や音が「考えようとする努力なしに」耳や目から、自ずと入ってきて私の心を占めてしまうということと、その状態が大変心地よくいつまでもそこにとどまっていたいと感じられたということの、ほぼ「客観的な報告」である。
しかし、その後の(b)~(b')で述べられていることは「そのような境地にある人は何を楽しむのか」という文から分かるように、散歩から戻ったルソーが、このサン・ピエール島でそのような境地にある自己を(外部から眺め)どのような人物として描きどのような人物として読者に提示しようかを考えながら書いたものである。
(c)~(c')では(a)~(a')で述べた「充足状態」を、情念に駆られて行動をしていた時の経験に比べてはるかに好ましく快いものであり、情念にとらわれている人々は知らないだろうと述べているが、これは、すでに激しい恋愛が幸福を構成するものではないという考えを見てきたわれわれには、十分に理解できることである。
したがって(a)~(a')と(c)~(c')に関して言えば、それらは異常な、神秘的体験では全くなく、比較的よくある日常的な経験に照らしてみても、十分に理解可能なことである。われわれが研究か何かのために特定の事柄を観察しようとしているのはなく、浜辺や木陰に寝転んでぼんやりしているのであれば、周囲の景色や物音が「考えようとする努力なしに」、耳や目から自ずと入ってきて私の心がそれらで満たされてしまうということは、ごくありふれたことである。
しかし、ルソーはその充足状態を、通常経験することのできない、神秘的な状態だと感じたから「神のような充足状態」と書いたのではないかとグットマンは反論するだろうか。答えはノーである。というのはこのように書いているときにはルソーはその「充足状態」の中でそう感じているのではなく、それを後で、振り返って眺め、考察し、それを言い表す適切な言葉を探しているのである。
彼はこの「神のような充足」と言う言葉を、グットマンが言うように、自己を独自で普通の人々とは異なるものとして理解し、またそのような存在として他者に提示することが「役立たず」であったことを知って、そのような企てを放棄し、「経験の分割に先立つ、あの統一性の写しである全体性〔神のことだろう〕に身を委ねる」行為、あるいはそうしたいと願う行為として発しているのではなく、全く逆に、自分を過去とは異なり、日々の孤独な散歩の中で、この上ない、言ってみれば、神のような充足を感じることができている、やはり独自な、他者と異なる人間として描き、読者に提示しているのである。
なるほど岸辺に坐ったルソーは外部からやってくる音や形に対して、あるいは自己の想像や夢想に対して、「分離分別」という分析的で観察者的態度をとってい
ないことは明らかだが、だからといって外部の自然と自己の区別が消失してしまい、また睡眠中のように無意識のなかで様々な想像・夢想に支配されてしまって
いるというのでもないことは上の文から明らかだ。
だが、このような感情は、なにか特定の対象あるいは人間にたいして油断なく身構え、忙しくまた意識的になにかを行おとしたり行っていたりするのではなく、とくにやらなければならないことがなくのんびりしていて構わないとき、とたとえば上でわたしが引用した文にあったような小船の中に寝転んで、波の上下動に身を任せてぼんやりと空想に浸っているときにはいくらでも起こりうることだと私は思う。このような経験を彼はサンピエール島での生活において繰り返し行っていたはずである。こうした状態を即、宗教的境地にあるとみなすことには無理がある。
ルソーが「代償的欲求」を感じているのだとすれば、彼は一種の欲求不満の状態にあることになる。しかし彼は今の状態に幸福を、満足を感じているのである。これを、全体の中に部分的な自我を溶け込ませたいという欲求、あるいはそれがかなえられないことの代償的欲求を感じている状態だと解釈するのは、何ヶ月間 かあるいは何年間か自然の中でのんびりと過ごすことの楽しさを知らないせいではないだろうか。若いときから絶えず強い精神的緊張を保ちながら仕事を続けていてそれが当たり前だと感じている人は、自然の中で長期間のんびり過ごすことがどのようなことかを想像できなくなり、それがあたかも普通の意識的生活も何 も一切を放棄して「全体」に自己を委ねてしまうような異常なことだと考え違いをしてしまうのではないか。
たとえば、一流の証券会社に勤めていた腕利き証券マンが何か失敗をしでかして、あるいはバブル経済の余波を食らって会社がつぶれて、山村の実家に戻って暮らしているというような例を考えてみよう。証券マンでなくてもよい。大病院の外科医でも、あるいは理系大学あるいは研究所の研究者(ピペ奴などという言葉
さえある)であってもよい。
業績を上げるための激しい競争にさらされて(あるいは自分からそれを求めて)緊張に満ちた極端に忙しい日々を送った経験のある人ならだれでもよい。
今彼/彼女はたまに家事の手伝いを求められるくらいでとくにしなければならない仕事はない。彼/彼女はしばしば裏山に登り山菜や茸をとるのが楽しみである。彼/彼女は歩き疲れたら木の根元に寝転んで、木の葉の間から透かして見える空を見るともなく見上げ、木の枝をゆする風の音を聴くともなくぼんやりと聴いている。
かつての業績争いのほかに職場内での恋愛や不倫も含め、仕事に就いていたときにとらわれていた情念から完全に解放されることは難しいだろうが、それらが感傷に変化し、あるいはルソーも書いているような「この世のことのはかなさについての漠然としたみじかい間の反省」として「浮かんでくる」状態になることは十分ありうることだし、そうであれば、風の音や揺れ動く木の葉や木漏れ日が「私の官能をとらえ、---甘美な夢想に引き入れる」と表現し、あるいは「考える努力をしないでも十分にわたしというものの存在を喜ばしく感じさせてくれる」と表現できるような状態は、われわれ普通の人間にも十分に想像できる。そしてこのような「経験」は現実の日本社会において十分に考えられることであり、なんら「宗教的」と呼ぶ必要はない。
そしてわれわれは、何か特別の厳しい修行を行ったり、導師と称するひとにすがったりすることをしなくても、サンピエール島におけるルソーのような隠遁生活 を行い、仕事は「怠け者でも嫌にならない程度のほねおりしか必要としない、楽しみとなる仕事」に限定し、のんびりと過ごすことができるなら、情念の大部分 から解放されことができよう。われわれ普通人も、生き方の転換を図ることで、自分の力で情念による支配を減らすことができる。
ルソーはピエール島での生活においてそれまでの情念に満ちたロマンチックな生とは違った生きかたに幸福を見いだした。彼は社会(社交)のなかで個別的で絶
えず消えてゆく感覚的官能的快楽を追求することによっては幸福を見いだすことはできず、ゆったりと流れる時間の中で自然(水や風、樹々、植物)と交わるこ
とを楽しむ、穏やかな生活に快楽を見いだした。このようなしかたで彼はエピクーロスの言うように、精神の平静こそが「神的な充足状態」と表現したくなるほ
ど大きな快楽であり、幸福であると感じたのである。(エピクーロスには精神の平静が自然を媒介とするものだという考えは見られない。だが現在の論点との関
係においてはその点についての考察は必要ないだろう。)
ルソーは自己を何か全体的なものに委ね、主体であることを放棄することによって幸福を見いだしたのではない。エピクーロスによれば、わたしたちは、何もの
にも拘束されることなく完全に自由に決定し行為することができるわけではない。「未来のことはわれわれのものではない---、かといって、全くわれわれの
ものでなくもない」(DL127)。だが「あるものはわれわれの力の範囲内にあるのだ」(DL133)。人は、自らのつまり主体的な勘考・思慮に基づい
て、自らの力の及ぶ範囲にあることがらの選択と忌避を行うことを通じて、幸福を実現すべきである。つまり何か全体的なものに帰依し、自己と他者(そして自
己と自然)の区別を廃するのではなく、意識的に他者との(そして自然との)関係を作っていくことを通じて、精神の平静に到達すべきである。ルソーの晩年に
到達した境地は、エピクーロスの説く「精神の平静」が最大の快楽だという考えがもっともなものであることを示す確かな例である。
エピクーロスにとって、哲学は、裕福な生活を送る一部のエリートが純粋な知的興奮を得たり、知的冒険を楽しんだりするために行なうものなのでなく、人間以 外の動物とは異なり精神を持っているが、生活に苦労をしている全ての庶民が、老いも若きも、精神的な安らぎを得、「魂の健康」を得るために行うべき、知的 精神的な活動であった。
エピクーロスは、事物の究極的な成り立ちや、天体の発光の原因等々、経験的に確めようのない仮説的理論にこだわることは無益だと述べているが、さらに、生 存、生活に苦しんでいる人々の苦しみを解消するのに役立ちえない知的活動、哲学や自然学の探求は必要ないと考えた。エピクーロスが二種類の「静的快楽」を主題的にはっきりとした区別を行っていないということは確かである。しかし彼がロングの言うように「異なるも の」を区別しなかったということも事実ではない。エピクーロスが述べたことの中で二種類の異なる状態が区別されていることは確かである。
すでに述べたが、個別の欲求充足活動によってあるいは軽い怪我や病気が治ることによって苦が解消されたあとで感じられる、主として身体に関する快が「静 的快」と呼ばれている。ここには解決がさほど困難ではない細かな問題についての心配、気づかいなど小さな精神的な苦が解決されるたびに得られる快も含まれ るであろう。
他方、「メノイケウスへの手紙」の中で、エピクーロスは、「魂の健康を手に入れ」「幸福になろう」とするなら若いときにも年老いてからも 哲学が必要だと述べ、哲学によって、正しい知識を獲得し、誤った想念をなくし、神について、死について、あるいは未来は決定されているのかどうか等についての不安や恐れのような大きな精神的な苦を解消する努力が大切だとしていた。
「なぜなら、そういったことについての迷うことのない考察こそが、すべての選択と忌避とを身体の健康と魂の平静さに関連付けることを可能にするからである。---けだし、---ひとたびそういった状態がわれわれに生じるなら、魂の嵐はすっかり静まるのである」。ここでは、思慮ある生活の実践を続けるとともに、哲学や自然学による正しい知識を獲得することを通じて、「魂の嵐がすっかり静ま」った状態としての、そして「すべての選択と忌避」がそれに結び付けられているようなその人の生を支える根本姿勢のようなものとしての「静的快楽」が語られている。
だから、別々の名で呼ばれてはいないが、エピクーロスには、そのつどの個別の欲求の充足にすぐ続いて起こる「静的快楽」のほかに、それらを包括し生の全体を貫き生を支えている、もう一つの精神的な「静的快楽」という概念がある。
感覚は基本的に身体が置かれている現在の状況についての情報であり、快の感覚はその原因が存在しなくなれば直ちに消滅する。したがって食後の満足感・満腹感は食べたものが消化されればやがてなくなる。しかしそうだとすれば食後の充足感は「静的快楽」ではなく、次の食事時になるまで次第に小さくなる動的な快楽であることになろう。だからトルクワートスがいう、欲求を満足させることに続いておこ快楽が「静的快楽」であるとすれば、それは感覚で感じられる快楽とは違う。
これまで述べてきたように快楽は、感覚及び知性・理性と共同して働く「快不快の感情」によって生み出される判断である。これら三つの能力あるいは働きが結びついて、個別の対象(行為)の快不快や望ましさの判断を行う場合に関しても、また幸福追求の長期的観点に立って行為の是非を考え取捨選択を行う場合に関しても、判断が行われるのだとエピクーロスは考えている。
したがって、食事は充足の快の感じを生むだけでなく、経験にもとづき、たとえば、しばらくは食事をするために動き回る必要はないということ、数時間は、(エピクーロスに忠実に言えば)
他の「苦を解消するための行動」、たとえば仕事上の義務を果すための行動、あるいは、長期的に幸福な生を実現するのに必要な他の行動を行うことができるということなどの判断を生む。満腹後の静的快楽は、自由な活動が可能だということの判断を伴った、そしてそれを空腹で無力の状態よりも好ましいと感じる快の感情であると言える。
これは、精神的なしかたで、たとえば、談話を楽しいと感じたり、神罰は存在しないと確信するなどのしかたで得られる純粋に精神的な快とは異なる。食事の満足が与える静的な快とは、身体的な必要が充足されることによって生み出される、自己が活動可能な状態にあることについての自信と行動への意欲である。しかし、結局、魂の静的快楽を生む。
この欲求充足後の静的快楽もいつまでも「持続」はしない。それはしかし時間がたち空腹になり再度食事をしたくなるということとは別のことである。その「静的快楽」の中身である充足感は、自己の活動能力についての判断を生み、それに基づく実際の行動となってそのつど実現されて、好ましい経験として記憶され、全体的静的快楽の中に吸収される。あるいは全体的な静的快楽に組み込まれ、それを構成する。
病気から回復したときに感じる「静的快楽」については同じことがもっと明確に言える。回復直後は食後の満腹感に似た「感覚」が多く混じった「充実感」が感じられる。しかし、単なる「充実感」ではなく、自分がやりたい仕事や活動を思い通り自由に行なうことができる状態にあるということについての判断、自分の生のありかたについて、自己の友人や家族との関係を含む自分の活動の可能性についての判断をともなった、その状態をうれしく喜ばしく感じる感情である。
ロングが言う病気回復直後に感じる快楽とは、ベンサムの言う「健康の快楽」に似たものであろう。前の注13)におけるベンサムの「健康の快楽」を参照。これは一種の感覚とされるいわゆる「体感」によって、直接に感じられる心地よさ、精力充実感である。だが、この心地よさ、精力充実感は、病気から回復した直後だけでなく、「健康と活力の状態」が「感じられる」限り、存続すると考えられる。
しかし、ロングにとって、基本的に快と苦は「感覚で感じられる」ものである。だから病気回復後の快はしばらくの間しか続かない。しばらくたつと快の感覚は微弱なものになり、苦でもない中間状態に移行する。
私が1年以上の強い痛みが収まったときに感じたのは、強い痛みがないことは大きな喜びであり、大きな快楽だということだった。また私は快不快についての以前とは全く異なる異なる考え方、「感情」を持つようになった。私は痛みがない状態にあることをきわめて快適で幸福だと感じているが、この痛みの非存在は快であるという感じ方/思いは持続的なものである。そしてここには一般に快と苦は生においてどのような意味をもつかということについての考え、あるいはこれからの生において快と苦に対してどのような態度をとるかということも含まれている。そしてこれらの考えも持続性をもつ。
私はだから、この痛みが治ってから2年以上経った現在だけでなく、10年経っても「痛みから解放されてうれしいでしょう」という言葉はきわめてリアルで有意味なものとして受け止めることができるだろうと、強い確信をもって言うことができる。〔2012年にこの文は書かれた。ホームページ化作業を行っている16年春において、この確信はまったく変わらない。〕
そして、重い病気にかかり、死ぬかもしれないという不安に取りつかれた経験を持つ人は、その病気が完全に治って退院し、再び家族一緒に生活をすることができるようになった後、私の想像では、5年でも10年でも、健康でいられることの喜びを日々の生活の中で感じつつ生きていくであろう。
病気の種類や重さによって、また人によって違うかもしれない。慢性の強い痛みを経験した人の中にも、痛みがなくなって一年もしないうちに、治った直後にはうれしかったが、今は、快でも苦でもない中間状態にあり、うれしくもなんともないと言う人もあるかもしれない。たぶんロングもそう言うのであろう。しかし、一般的に、静的な快楽はいずれ消滅し感じられなくなるとは言えない。私は快苦についての感じ方は人によって大きく異なると思う。
贅沢とも言える飲食物に慣れた現代日本人の飲食の欲求であっても、たとえば大きな災害で食料や水を手に入れることができず充足にひどく苦労したというような、その欲求が充足されたときの状況によって、またその人のさまざまなハビトゥス、生育環境によって形成された思考と実践の傾向によって、あるいは「思想」によって、経験がもたらす「静的快楽」の受け止められ方は異なり、個別的な静的快楽が一生持続することも大いにあり得ると思う。
そこで、二種類の静的快楽があって個々の静的快楽はそのつどいずれ消滅するものであり、他方に不変の「精神の平衡」のようなものがあって、両者は全く別のものだと主張することはできない。そして、一般に個々の快楽の受け止め方がそのひとの全体的な静的快楽を構成するのだから、個別の静的快楽を全体的な静的快楽と全く別なものと考えることは正しくない。
ロングは、病気回復直後の「静的快楽」と、それとは「全く異なる」「精神の平衡状態」という別な「静的快楽」が存在するとし、エピクーロスはその2種類の「静的快楽」を一緒くたにしていると批判した。しかし、今見たように、病気回復直後の快楽を「感覚的」快楽と考えるのであれば、エピクーロスはそれを「静的快楽」とは考えていない。静的快楽は、単に感覚的なものではなく、思惟・判断を伴う「感情」であり、また、自由に活動しうることの確信、自己が好ましい状態にあることについての判断を含むものであり、また思惟・内省によって幸福を構成するものとして見出されるからである。こうして個別の静的快楽は、全体としての静的快楽の一部をなすものであり、前者と後者は持続時間によって区別されるものではない。以上の議論により、ロングのエピクーロスに対する「第三の批判」は退けられた。
寺田寅彦(1878-1935)が、昭和10年、寝たきりになった。露伴より10歳下である。露伴が塩谷と一緒に見舞いに行くと、病状を説明して、痛みが 方々を廻るので体中を一回りしなくては収まりがつかないのかもしれないが、それでもいまはいくらか訓れてきたから、右足に来つつあるのも左足のときほど痛 まなくても済むんじゃなかろうか、と言ったあとで、「痛いところをじいっと見つめるように考えています。痛むのはどこにあるのかと突き止めてそれに神経を 集中しています」と言葉を継いだ。
すると露伴は「や、それはいけません」と反対して非常に真面目な顔つきになった。「痛むときにはよそのことを考えたほうが楽ですよ。痛みに対して心を向け
ては苦しみを増すようなもので利口なやりかたじゃない。こういうことを考えて御覧なさい。自分の股のあいだに谷があると考えて、気を鎮めてその谷を上のほ
うから眺め始め、それから下のほうへだんだんに目をやり、心をやる。そうすると痛みを忘れることができるといいます。これは古くから伝わった方法でし
て」。
ゴヤ(1746~1828)の「裸のマハ」。写真はWikipediaによる。
 露伴は、痛むときにはほかの事を考えたほうが楽になる、<楽しいこと>を思い浮かべることが痛みを忘れる秘訣だと言っている。これは、エピクーロスが言っ
ていることと同じである。しかし、寺田は「こんな痛い目にあうくらいなら死んでしまったほうがましだと思う」と言っているように、心身ともに弱ってしまっ
ていた。そしてその年の内に亡くなった。死の床でひどい痛みに苦しんでいる老人にとって「谷間」=女性の身体を想像する余裕はなかったのではないだろう
か。閑話休題。
露伴は、痛むときにはほかの事を考えたほうが楽になる、<楽しいこと>を思い浮かべることが痛みを忘れる秘訣だと言っている。これは、エピクーロスが言っ
ていることと同じである。しかし、寺田は「こんな痛い目にあうくらいなら死んでしまったほうがましだと思う」と言っているように、心身ともに弱ってしまっ
ていた。そしてその年の内に亡くなった。死の床でひどい痛みに苦しんでいる老人にとって「谷間」=女性の身体を想像する余裕はなかったのではないだろう
か。閑話休題。
通常の人間生活においては、飢えや渇きの他に病気や災害や事故による怪我などがもたらす主として肉体的な痛みや苦しみが存在する。他方、自分のあるいは家族の病気に対する不安、災害や事故などに対する不安や恐れ、そして、仕事やそのほかの人間関係における義務や責任、あるいはトラブルなどから生じるストレス等の精神的不安や苦しみもある。また、当時の庶民はもろもろの神がこの世でもまた死後においても、恣意的に恐ろしい罰をくわえて来ることを恐れなければならなかった。
エピクーロスははっきりとは述べていないが、われわれ---というのは、幸運に恵まれたごく少数の人々を除いた大多数のふつうの人という意味だが---の生は普遍的な苦しみのなかにあると考えていたことは間違いないと思われる。そして彼の「庭園」で彼と生活を共にしつつ彼の教説を学んだ人々の多くが属していた階層においては、実際にそうであったと考えられる。彼が、心身の苦痛を解消することそれ自体が快であり、苦を解消することで持続的な精神の平安を実現することが幸福な生だと説くのは、まず、われわれの生が心身の苦痛の中にあって、それを解消することなしには、幸福ではありえないという根本的な直観に立つからだと思われるのである。
エピクーロスのいう「動的な快楽」は日々繰り返し起こる飢えや渇きをそのつど解消してくれるものとして、必要不可欠である。しかし、必ずしも必要不可欠と言えないとエピクーロスが考えた「多様な」快楽も全く不必要だというわけではない。彼の挙げている例に即して言えば、「美しい音」(音楽)を聴き「美しい形」(絵画や踊りなど)を見ることは魂に快楽を与えるし、たまに「ワインとチーズ」が手に入ったときには贅沢を味わうことができる。これらはエピクーロスにとっては特別の苦労をしないで享受できた「多様な」快楽であったろう。これら個別的快楽ないし「苦痛の欠如」と究極的な精神の平静・平安が快楽である。動的快楽は持続せず、蓄積され得ず、それだけでは永続的な平安を構成することはできない。
生の全体構想の下で、個別の「静的快楽」において満足を得るとともに、現在歩みつつある生の方向性についての十分な確信が持て、さらに、生の限界とも言うべき死についての恐れや不安も存在しないとするならばその人は「最大の」精神の平静、平衡を実現しつつあり、幸福な生を歩みつつあるといえるだろう。
エピクーロスは、日常生活の中で、必要を超える「多様な」快の追求を減らし、できるだけ「静的な快楽」状態を実現し、その中で、人間の自然・本性を研究し、行為の取捨選択に関する判断力・勘考と思慮の徳を身につけるための、哲学を行なうことによって究極の平安=幸福の実現を目指すべきであることを説いた。以上がエピクーロスの倫理(学)的教説の要約であると言っていいだろう。
上では、ロングによるエピクーロスの快楽論の解釈と批判に対して反論しつつ、エピクーロスの快楽論を擁護したが、「思想運動」や「政治的対立」とは何の関係もないものであり、客観的で公正な論述を行うよう最大限務めた。
だが、また、エピグラフの文でも掲げたように、このエピクーロスの哲学の考察は純粋な学問研のために行っているのではなく、私が生きることに役立たせようとして行っているのであり、実際私はエピクーロス哲学から大いに学ぶことができたと思う。
そして、私は「すべての人は快楽の実現を目的に生きる。そして人は快楽を最大にするよう生きるべきである」というエピクーロスの根本テーゼは真理であると思う。(ただし、この主張は苦労し努力してまた犠牲を払って何かを達成しようとする生き方も、その達成が与えるであろう喜び・快楽とそのために支払う労苦・犠牲とを比較考量し、達成により得られる快の方が大きいと判断して選択を行うのだ、という考えを含む。)
私は60歳で退職して以後、体を使った遊びである釣りを中心にした生活を送って来た。そして以下のいくつかの章では遊びやスポーツについて考察しようと思う。わたしが、遊びやスポーツについて考えるのは、それらが生きるために必要な仕事を行うことに劣らず重要だと考えているからである。
しかしエピクーロスは、身体に苦痛がなく精神が平静・平安であることが幸福の必要十分条件だと説いており、そして生存のために必要不可欠な欲求を最小限の労苦で満たした後での「多様な」欲求の追求については、全面的に否定しないまでもはっきりと消極的な姿勢を取っている
私がエピクーロスの哲学を根本において正しいと考えているからといって、われわれ現代人は、当時の彼の信奉者のように、彼の教説に従って生きるべきだと考えているわけではない。では、現代人は快楽を最大にし、幸福を実現するために、必要不可欠な衣食住の欲求の充足という条件を満たしたあとでどのような快楽を追求すべきなのか。
私は、苦の非存在が快楽であるということは真実だと思う。とくに、大きな苦しみの中にある人々にとっては、その苦を取り除くこと、その苦から解放されることこそが、他のどんな(いわゆる)積極的な快楽も比べものにならないほど必要なことと感じられ、実際にその苦が解消され、その状態が持続するときには、その以後の生活がたとえ「平凡」なものでしかないにしても極めて幸福だと感じられるということは間違いないと上でも述べた。そして実際、現代社会においては、例えば大きな災害や事故などに遭って家を失ったり家族を失ったりして苦しんでいる多くの人があり、学校や職場で「いじめ」に合ってひどく苦しんでいる多くのサラリーマンや生徒たちがいる。
エピクーロスは、当時、多くの庶民が、死後、神々の審判や永劫の罰に苦しまねばならないという宗教を源泉とする恐怖・不安を大きな精神的な苦として抱えていることを指摘していた。このような苦については現代人はまぬかれていると思われる。
エピクーロスは、彼が当時の人々の(もう一つの)大きな苦だと言う、「死への不安・恐れ」は誤った思念に起因するものであり「死はなんでもないもの」だと説いていたが、他方で「なんでもないと考えることに慣れるようにしたまえ」とも言っており、その言葉からは、死が何でもないものだということは論理的なしかたで納得できるものではなく、「いずれ時が解決してくれる」ということを認めていると推測された。
こうして、エピクーロスの生きた時代と現代とを比較すると、心身の大きな苦しみを除去することが最大の快楽であるということは同じように言えるにしても、現代における「大きな苦しみ」はエピクーロスが指摘していたものとは異なっており、また苦しみの種類が多様化していると思われる。
現代人はすでに、宗教的な原因による強い不安や恐怖からはまぬかれている。しかし、地震などの大きな自然災害だけでなく、社会の複雑化(第三章で考察するが、エリアスのいう「文明化」)に伴う人間関係から生じる諸問題、自動車から原発まで安全を欠いた科学技術の利用が引き起こす災害、先端技術を駆使した兵器による徹底的な破壊と殺戮が行われる戦争での被害など、無数の不安、苦しみを抱えている。
そして、生活を送ることが不可能であるようなひどく強い不安や苦しみからはまぬかれてはいても、エピクーロスの言葉を用いると「快楽である状態を超えている程度の苦痛」つまり日々の生活はなんとか続けているが様々な精神的なストレスにさらされて安らぐことのない人がほとんどであると推測される。
様々な遊びやスポーツはエピクーロスがいう「動的快楽」である。つまりその快楽はその活動を行っているときにのみ得られるもので、その活動が終わればたちまち消えてしまう。「哲学や自然学」(あるいはさらに文学や芸術)の場合には読んだり考えたり鑑賞したりする活動の後に「静的快楽」を与えてくれると思われるのに対して、遊びやスポーツの場合には、人々が日常的に抱えている精神的な苦痛やストレスを、その都度、忘れさせ、精神を活性化させてくれるが、持続的な「精神の平静」、安らぎを与えてくれはしない。
では、人間は「活動」あるいは「運動」によって、「静的快楽」を得ることができないからと言って、「幸福」になるためには皆が「哲学や自然学」、あるいは文学や芸術に向かうべきなのだろうか。(私は、そのことがたとえ論証されたとしても、しかし、好みは各人にゆだねられるべきだと最後には主張するつもりなのだが。)
アリストテレースは、快楽は各存在のアレテー(その存在に特有の機能・能力)を発揮するような活動に伴って生じ、その活動を完成させるものだと述べていた。つまりすべての存在は、それぞれのアレテーに基づく活動を行なう時には、本性的に快楽を感ずるのだというである。
このアリストテレースの見解に従えば、考えたり、工作したり、遊んだりする動物であるわれわれ人間は、それぞれ異なる自己のアレテーを発揮する時に大きな快を感ずることになるが、また、植物とは異なり動物である限りは、「動くこと」、「運動すること」をアレテーとして有しているのだから、人間は、本性的に、体を使い運動するときには、ある程度の快を感ずるはずだと考えられる。実際、アリストテレースは「すべてのひとが快楽を欲するのは、すべての人が生きることを求めているからだと考えてよいだろう。生はひとつの活動である」とも述べている。(ただし、彼自身は、身体的な運動とは正反対の哲学的思索活動の中で最大の快を見出したのであったが。)
他方、エピクーロスによれば、人間は苦痛を解消し快楽を実現するためにすべての行動を行う。欠乏は苦痛であり、欠乏の充足は快楽である。したがって、もし、人間が、体を動かすこと、運動することを本性的で不可欠な欲求として有するならば、人間は運動をしないでいることを苦痛と感ずるだろうし、運動不足の苦を解消すること、「運動の欠乏」を充足することは快楽だと感じるであろう。
ところがエピクーロスにおいては、体を動かすこと、運動することが本性的な快楽であると彼が考えていたことを示す言葉は全く見当たらない。しかし、(必要不可欠な欲求は満たされているとして)誰かが運動を快楽だと主張し、実際に運動を行なうとすれば、エピクーロスは様々な快楽を追求すること自体を否定してはいないから、その運動を行うために何か特別な苦労や犠牲を払う必要がないならば、反対はしないであろう。
そして、エピクーロスは、衣食住の必要不可欠な欲求が充足されたあとでは、精神の平静・平安が実現されるべきだと考えている。だが、彼の説く「最大の快楽」である持続的な「精神の平静・平安」の境地に実際に到達するためには、特別深遠な知的洞察や宗教的悟りのようなものではないにしても、それでも「若いときから」の一生にわたる「哲学」が必要だとされていたように、私は、現代社会に生きるわれわれ一般人にとって、その境地の実現は決して簡単ではないと思う。
繰り返しになるが、現代世界の先進国では、自然本性的で必要不可欠な衣食住の手段の充足に関しては古代社会よりも明らかに容易になっている一方で、社会の複雑化に伴う多種多様な精神的ストレスが増大している。
われわれは、できればエピクーロスが勧めるように、必要な欲求を満たしたあとで、「自然学や哲学」によって人間にとっての究極的で最大の苦を克服することに向かうべきなのだろうが、それができないでいる。いわば煩瑣な、だがわれわれの忙しい社会生活の中で絶えずわれわれを悩ませ精神を動揺させる無数の精神的ストレス=苦にとりつかれ、躓いており、「平安」に向かう次ぎの段階へと進めないでいる。古代の人々にとっては衣食住の問題が生存の問題であったとすれば、われわれにとっては、職場や家庭など、社会的な生活のなかで生じる主として精神的な諸問題が生ていく上での中心的な問題になっている。
古代の人々にとって、まず、生存のために、日々、できるだけ余計な苦労をすることなしに、衣食住の欲求を充足することが重要であったとするなら、われわれにとっては、一歩でも精神の平静に近づくために、社会的な諸関係のなかで生じる精神的なストレスを減らし、できるだけ少ない苦労で最大の快楽を得る工夫が求められている、と言ってもいい。
職場での活動、あるいは市民運動やボランティア活動によって、われわれを苦しめる問題を解決し、あるいは減らすように、可能な努力を行うべきだろう。私も20代の半ばから50代後半に至る時期、自分の利益だけを追求するのでなく、ボランティア的に労働問題や環境問題などにかなりの時間を割き、様々な形で取り組んだ。しかし、それら活動の成果はなかなか得られないばかりか、それらの活動が新たなストレスを与えることさえある。
誰でも、自分が抱えている苦を、できれば、今すぐに減らしたいと考えるであろう。そして一般的に言えば、晩酌やテレビのドラマの観賞、あるいは、休日の遊びや趣味・娯楽、スポーツなどが実際にそのような役割を果たしている。これらの楽しみはストレスを一時的にしか解消してくれない。空腹や喉の渇きと同様、一時的に充足されても、時間が経てば再びその必要が感じられてくる。しかし、現代人は、ストレスをためすぎないように、つまり、精神の平静の欠乏が大きくなり過ぎないように、日々、少しずつ、ストレスの解消を図る必要がある。
そして、年をとって働く必要がなくなったとき、そして残された生がわずかなものとなったときには、一日の大部分を遊び、楽しんで過ごすことにより、それまでの仕事中心の生活において、休日の気晴らしによっては解消されずに残っているであろう「疲れ」をゆっくり解きほぐし、安らかな眠りにつく準備をするのがいい。このように私は考える。
エピクーロスの快楽説について考えたこの章に先立つ第三部の「序文」に掲げた中国の古諺に見るように、老後の遊び、楽しみにも様々あろう。仕事をもっていたときには、車の運転をするのであれ、人に会うのであれ、とにかく仕事に差し支えないようにとお酒は控えていたであろう。だが、老後にはお酒を飲んで、一日を陶然として過ごすこともできる。子どもはすでに大きくなっているだろうから、1人で街へ出て、自由に、恋愛を追求するということもできるだろう。そして、歯の健康を維持できている人は、グルメを追求することもできる。だが、私は、釣りが残された人生を楽しく幸福に生きていくために最も役立つと考えるのである。
再度私はモンテーニュから、現在の私の暮らし方と考え方を擁護してくれているように思われる文を引きたい。
「いまこそ世間との結びつきをほどくときだ---もはや、なにも寄与することなどできないのだから。貸すことのできない人は、借りることも差し控えなくてはいけない。---。
「若者は教養を身につけなくてはいけない。大人は、りっぱなふるまいを実践しなくてはいけない。そして老人は、市民としての仕事や軍務から、きっぱりと身を引いて、いかなる務めにも拘束されることなく、自分の自由な裁量で生きていくべきだ」とソクラテスは語っている。
そしてこのような引退の教えに対してほかの人々よりも適した気質の人間が存在する。理解力が弱く、弛緩していて、感情や意志がもろく、それでいて、容易に人に服従したり人に使われたりすることがない人間がそれだ。実はわたしも---そのひとりなのだ---。
こうした引退生活者のためには、辛くもなく、退屈もしない仕事を選ばなくてはいけない。さもないと、休息を求めてそこにやってきたことが無駄になってしまう。なにを選ぶかは、各人の好み次第だ。---。
たしかに書物は楽しい。とはいえ、それに付き合うことで、結局はわれわれにとってもっとも大事な、快活さと健康を失うというのなら、そんなものとはおさらばしようではないか。
---ふつうの生活に飽きて、---そこから身を引いた人間は、---あらゆるたぐいの労苦とは別れを告げていなくてはいけない。そして心身の静けさの妨げとなる、様々な情念は、とくにこれを避けて、自分の気質にもっとも合った道を選ばなくてはいけない。
〔エピクーロスは友人の〕イドメネウスに、---公務を扱い、お偉方を相手にすることをやめて、孤独の中に引きこもるべきだとして、こう書いている。「きみは今日まで、泳いだり、浮かんだりして、生きてきた。そろそろ死ぬために、港に入ったらどうだろうか。人生の大半を光に与えたのだから、こちらの部分は、影に与えるがいい。---」」第38章「孤独について」
このようなモンテーニュの言葉に励まされつつ、私は、自分に最大の「安楽」と感じる釣りを選んだ。そして釣りの合間にその安楽の一部として「釣りのエッセー」を書きはじめた。能力のないものにとって、学問は骨である。学問は私の気質に向いていない。私にとってあまり苦しくなく、退屈でない「仕事」の一つとして、エッセーを書くことにした。「毎日が釣り」の生活だから当然、釣り(魚種や季節に応じたさまざまな釣り方など)と、漁村での生活がテーマになった。
しかし、3~4年かかって「第一部、釣り」、第二部「漁村での暮らし、半島の自然」がほぼできあがったと思った頃、私は、退職後どうして、以前からの趣味であった釣りを続けようと思っただけでなく以前よりももっとやりたくなったのか、そして釣り三昧の生活を始めてから4~5年経っていたが、どうしてこれからもずっと続けたいと考えているのか、一言で言えば釣りはどうして面白いのかを考えるようになった。
最初は、他の遊びやスポーツと釣りを比較して考えた。そのうちに遊びとスポーツの共通点と違いが問題になり始めた。こうして、数年間好きなだけ釣りをすることができ、退職前に感じていた釣りへの“飢餓感”が薄らいだためか、60代半ばを過ぎたことによる明らかな体力低下のせいか、あるいはまたこの数年の夏の猛烈な暑さにせよ冬の寒波の厳しさにせよ記録尽くめの異常気象により出漁不可能な日が増えたせいか、釣りに出ている時間が減り、考えたり読んだり書いたりする時間が増えた。
スポーツと遊び、釣りについて書いた後、最後に、できるだけ労苦を少なくして楽しんで生きることが幸福な生だと説く、エピクーロスの哲学について書くことにした。在職中には――私は大学で倫理学・哲学と思想史を教えていた――仕事としての授業の中で古代ギリシャの哲学に関して「概論」としてふれたことがなんどかあった。今回は遊びとして、モンテーニュの言う「安楽な仕事」として行ったことであったが、この一つの章を書き上げるには、考えるエネルギーと時間を相当に投入したと思う。だが、私にとっての“本業”は釣りであり、釣りが「私の職業、私の技術」である。スポーツと遊びについて書いた、以下の章も第一章におとらず骨であったが、同様に安楽に役立てるためのものであり、釣りという安楽仕事を自分にとって明らかにするために、書いたものである。「私がここに書いていることは、私の学説ではなく、私の〔生のための、私的な〕研究である。他人のための教えではなく、自分自身のための教えである」。