|
2016年12月25日: クリスマスに因んで H.A. (岩見沢の哲学者、Ab兄から伝蔵荘日誌に投稿がありました。Ab兄は瑞鳳寮の大先輩で、小生がドイツ語の試験で危うく教養部をドッペリそうになったとき、助けて頂いた大恩人です。このレスキューの顛末を2007年9月21日の日誌に書いていますので、ついでにお読み下さい。 T.G.) 
日脚がもっとも短くなる12月13日、陽の光を待ち望む思い切なる北欧では「聖ルチア祭」が寿がれる。ナポリ民謡に歌われるあのサンタルチアに因んだ祭りである。ルチアはラテン語の光、すなわちLuxに由来する。ルチアとは4世紀初頭殉教した乙女である。彼女が殉教したことは事実のようだが、その経緯などはよくわからない。伝説によればその発端は母親の病気平癒のための巡礼先で見た夢だった。シシリー島の西海岸シラクサで裕福な家庭に生まれ育ったルチアの巡礼地は、そこから海沿いに50キロほどエトナ山よりのカタニアだった。そこは50年ほど前に起こったデキウス帝による最初の本格的なキリスト教徒弾圧で、アガタなる女性が殉教したところだった。そこでアガタの夢告を受け、ルチアはキリストの花嫁になることを決意したと言われる。 彼女にはそのとき不本意ながら母親が薦める異教徒の婚約者がいた。しかしそれ以前から熱心なクリスチャンであった彼女の決意は固く、翻意を促す声にも耳を貸そうとしなかった。結婚を断られた男の恨みを買ったルチアは、クリスチャンであるという密告を受けたのである。時代はキリスト教の拡大に手を焼くデイオクレチアヌス帝が、空前のキリスト教徒弾圧に乗り出した304年のことだった。後に残された絵画や彫像は、ルチアが両眼を抉り取られて惨殺されたことを物語っている。キリスト教徒への異教徒のおぞましい憎悪の激しさの表れだった。 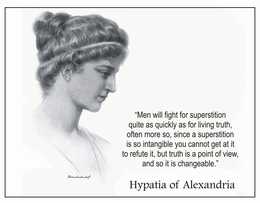
このルチアに触れたとき、論者(松田)の脳裏をアレキサンドリアのヒュパテイアのことがよぎったに違いない。狂信的なキリスト教徒によって惨殺されたギリシャ哲学者だった。ヒュパテイアの惨劇が起こったのはそれからおよそ一世紀後、ホノリウス帝治下の415年のことである。キリスト教がコンスタンテイヌス帝による公認を経て、ローマの国教となって17年後である。国教となったとは言えキリスト教は内部にペラギウス派などさまざまな異端を抱え、外部にはマニ教をはじめ多くの異教からの攻勢に晒されていた。教父時代の最高の神学者となる、ヒュパテイアと同時代に活躍したアウグスチヌスは、『告白』でローマでの異教・異端との厳しい論争を余儀なくされたことをつぶさに記述している。カトリックに入信するまでもっとも多感だった青年期、10年以上にわたってアウグスチヌスを虜にしたのはほかでもないマニ教だった。 ヒュパテイアが活躍したアレキサンドリアもご他聞にもれなかった。70万冊(点)というローマ圏随一の蔵書類を誇る図書館を擁するアレキサンドリアは、諸学問が華を競う研究・学問の一大拠点だった。宗教・思想でもユダヤ教からギリシャ哲学、さらにペルシャ・インドの思想までもがキリスト教に伍して互いに覇を争った。なかでももっとも活況を呈していたのはギリシャ哲学で、後々までその知性と美貌が語り草となったアテーナーの申し子のような学頭ヒュパテイアは、百華斉放の華の都でも一際瞠目された大輪の華だった。 
ところが異教・異端で辣腕を振るったキュリロスが、アレキサンドリアの大司教になったのを機に形勢に変化が起こった。マリアの神性を否定したネストリウスを異端として烙印を押し、その一派をペルシャから唐の長安まで追い詰めたのもそのキュリロスだった。奈良時代唐から渡来したと文献に散見される景教徒はその一派だった。ギリシャ哲学は危険視され、その頭目と目されたヒュパテイアが標的となったのである。彼女がどのようなことを講じていたのかは詳らかでない。語り伝えられるところによれば、ロゴスの命じること以外に従うべきものなしとしたプラトンの美しい遺風を継いだ彼女は、当時ほとんどの宗教や思想深くに根を下ろしていた牢固たる迷信や異言の類は一切受け付けない、徹底的に知的な女性だったという。アレキサンドリア図書館の最後の館長(キリスト教徒による相次ぐ襲撃を受けて壊滅)で、天文学や数学で高名だった父テオンの資質を受け継いでいたのかもしれない。ユステイニアヌス帝によって閉鎖されることになったアカデメイア最後の学頭ダマスキオスは、ヒュパテイアをキリスト教徒の反知性主義的暴力が生んだ最初の犠牲者と呼んでその死を悼んだ。 この点で注目されるのは、ヒュパテイアが心酔したのがプロチノスを祖とする新プラトン主義だったということである。プロチノスが活躍したのは3世紀後半であったが、弟子ポルフェリオスによって編集されたプロチノスの著『エンネアデス』は広く読まれていて、ヒュパテイアと同時代のアウグスチヌスもプロチノスを読んでいる。新プラトニストのヒュパテイアが、プロチノスはいわばバイブルのようなものであったであろう。キリスト教、ミトラ教、マニ教・・・と諸宗教が入り乱れてローマ権で覇権を争ったヘレニズム期に、プラトンを奉じ、ギリシャ哲学を以ってそれらに対峙しようとしたプロチノスはキリスト教にとって手強い論敵であった。 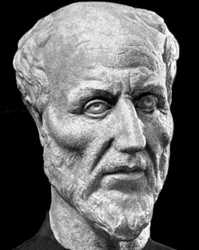
間違いなくヒュパテイアも手にしたはずの、のちに異端と宣告されたキリスト教一派グノーシスへの論駁書によれば、プロチノスは当時にあっては極めて合理的なひとで、病の原因を悪霊の仕業と説くグノーシス派に対し、単なる体への気遣いの欠如のせいとし、彼らが死後約束されていると豪語する天国なるものは一体どこにあるのか、オデュッセウスよろしく船にでも乗ってゆけるところにでもあるのかと揶揄している。そこが「ここ」とか「あそこ」といったどこかにあるのでないことは、ルカ伝(17章)の記しているところである。 だが不幸にしてプロチノスが接したグノーシス主義の天国観は、耐え難いほど雑駁なものであった。プロチノス流に天国があるとしたら、それを約束するのは祈りでも救済でもなく、己の内部から聞こえてくる内なる声への聴従でしかなかった。それはこの世界から離れた異郷などではなく、われわれが己が内奥に沈潜するなかで顕現する、まさにこの世界そのものの最も秘められた相貌以外のなにものでもなかった。プロチノスはプラトン同様、知性には「超えた」神秘のあることを知悉していた。鉱脈深くに手付かずの黄金が眠っているように、神秘はこの世界そのもののなかに深く秘匿されているものだった。知性の限界を認め、それを越えなくてはならないとはしたが、少なくとも知性に「反する」ことはプロチノスが断固として認めるところでなかった。プロチノスには、原罪や救済、恩寵といったキリスト教の核心ともいうべきものを受け入れる余地はまったくなかったのである。 
ローマ皇帝ガリエヌスの厚遇を忝くしたプロチノスが、主観的にはともかく客観的にはローマ帝国の対キリスト教対策を後押しするイデオオーグの役割を果たしたことは間違いない。筋金入りの新プラトニスト・ヒュパテイアは、キュリロスにとって放置できない存在だった。事件は復活祭に先立つ四旬節に起こった。馬車で通りがかったヒュパテイアが、数人の修道士に襲われ惨殺されたのである。その殺害は書き記すこともはばかれるほどに惨たらしいものであった。襲撃がキュリロスの使唆によるものだということは公然の秘密だった。ルチアの穢れなき目を抉った異教徒の狂気が、今度はアレキサンドリアの華を一瞬にして散らす偏狭なキリスト教徒の狂信となって噴き出したのである。 論者(松田)が扱った遥か古代ギリシャを席巻した狂えるバッコスから、論者が知らずに逝ったISにいたるまで、目を背けたくなる得体の知れないおぞましい血に飢えた蛮行は僅かな裂け目を狙っては噴出する。だが耳を聾せんばかりの叫喚にかき消されそうになりながらも、絶えず清らかな歌声が聞こえてくるのもまた事実である。ヒュパテイアに哲学を学び、キュレネやペンタポリスの司教となったシュネシオスは、最後まで師ヒュパテイアを称え、キュリロスに同じなかった。ヒュパテイアの事件を書き残した高名な教会史家ソクラテス・スコラテイコスは、後にレオ13世によって「教会博士」の称号を授けられるキュリロスを、大胆にもキリスト者として許しがたいと断じ、キリストの山上の垂訓からはもっとも逸脱した者と指弾してヒュパテイアの死を悼んでいる。 |