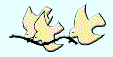 |
 |
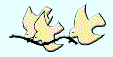 |
 |
開廷前に、「安井原爆訴訟連絡会」の八木靖彦副会長らが担当書記官に署名7588筆(2月17日現在集約分)を手渡しました。
法廷では、厚生省が反論の準備書面を提出し、被爆と前立腺ガンとの因果関係はなく医療認定ができない、と主張しました。それに対して原告側は次回(5月22日)法廷で反論することになりました。法廷後、高教組センターで報告集会が開かれました。
【原告弁護団代表の高崎暢弁護士】
今日の法廷で提出された厚生省側の反論の準備書面では、「原爆と疾病の起因性として統計上、前立腺ガンと被爆の因果関係はない。またDS86認定基準に照らしても原告の被爆距離2kmでは被ばく線量は15ラドしかならず、医療認定はできない。」と説明しています。
しかし、安井さんは原爆手帳を申請したときは被爆距離2kmとしたが、その後1昨年12月に判決が出た京都訴訟の原告と同じ通信隊の建物で被爆したことが判明しました。京都訴訟では被爆距離1.8kmですが、安井さんは謙虚に1.87kmと訂正し北海道に認められています。なお被爆地点を立証する資料を京都訴訟に照会中です。
函館の59歳の女性の(乳ガン・肝機能障害・卵巣腫瘍・胃ガン)行政手続きは却下されましたが、昨年12月に異議申し立てをし2月には札幌で口頭陳述を行いました。彼女は被爆地点1.8kmを1.6kmに訂正し、北海道は認めているにもかかわらず、国=厚生省は訂正を認めたことに対して北海道にクレームをつけています。
弁護団は被爆距離で判断する現在の原爆行政には反対の立場をとっています。放射線量についても、国のDS86認定基準はつくった人も誤差を認めていますし、当時は現在のような大型コンピュータもありません。さらにアメリカから提供された資料に基づいているのですが、それは被爆者救済の観点での資料ではありません。DS86認定基準は近い所は過小評価されていて、基準そのものの見直しも必要です。
次回の法廷までに、物理学者等専門家の協力も得て、安井さんの被爆後の時間の経過と位置を明らかにして残留被ばく量も明らかにしていきたい。また放射線降下物として黒い雨は一般的ですが、安井さんは黒いすすをあびたと話しています。このことにも注目していきたいと思います。
最近の松谷、京都、石田訴訟と一連の原爆裁判の判決の傾向としては、原告側にハードルの低い基準となってきています。2月5日に全国原爆訴訟交流会が東京で開かれましたが、原告・弁護団・日本被団協から25人以上が参加しました。国側の対応として、最初の裁判を何処でやるかということだけで国側は東京を主張し、松谷訴訟など何年も費やしました。安井訴訟は札幌地裁で法廷を開くことになりましたが、その後の広島訴訟ではまた東京地裁となり、後戻りした形になっていることにも注意したいと思います。安井原爆訴訟のたたかいは、全国の原爆訴訟に連動しています。書面・証拠書類を日本被団協に提出して全国で力を合わせてたたかっていくことを確認しました。次回の交流会は8月の予定です。
今日の法廷は、傍聴者の方から「裁判官の声が小さい」「内容が面白くない」「と言われました。次回からは反論のやり取りもあり、傍聴人に見える形の裁判にしていくようにします。裁判に勝つには弁護団だけではなく、皆さんの支援がぜひ必要です。松谷訴訟など全国の経験を生かして早期に解決していきたいので、ご協力よろしくお願いします。
【原告安井晃一さんのあいさつ】
裁判では裁判官が署名の数と傍聴人の数にとても神経質になっています。このことからも運動に結びつけて勝利することが大事なことです。
「松谷訴訟」は13年目のたたかいとなっています。自分がそれだけ生きられるかわからないのに、なぜ提訴の決意をしたのか。全国30万人の被爆者の救済。それに自分の前立腺ガンは潜伏期間が40〜50年と長いため、データが少ない。全国の原爆訴訟でも、ガンが発症してからの提訴は初めてです。
「被爆者は絶対ガンになって死ぬだろう。だけどガンで死ぬな。」これは広島で被爆した肥田舜太郎医師がよく言う言葉ですが、「ガンで死ぬな」とは負けるなと励ましているのです。原爆手帳を持っているのに、なぜ認定しないのか。一般の戦争被災者とは違って、被爆者は特別の被害を被っているのです。どうしてもこの行政を変えたい、被爆者に冷たい国の逆立ちした行政を直したい、私はそう決意しています。
【支援連絡会八木靖彦副会長のあいさつ】
今日は先ほどご紹介されました、皆さんの支援の署名7588筆を札幌地裁に提出しました。支援連絡会事務局会議では、2月17日現在、団体会員34を今年中に100団体、個人会員305人を1000人にする目標を決めました。なんとしても勝利するために、皆さんのご協力をお願いします。本日は本当にありがとうございました。
→安井訴訟を掲載しているページへPeace Wave from Obihiro Hokkaido Japan
2月5日、東京で第1回原爆裁判交流会が開催されました。この交流会は(1)国側の主張に対抗するため、法律家・科学者・医師などの専門家の協力を得ること、(2)それぞれの裁判の現状や問題点を出し合い、今後の支援運動の交流を図ることを目的にひらかれたものです。長崎からは中村尚達弁護士と支援する会の山田事務局長、大塚事務局員の3名が出席しました。
松谷さんは「ながさき女性国際平和会議」参加のため出席できませんでしたが、京都訴訟のAさん、東京訴訟の東数男さん、札幌訴訟の安井晃一さんの3人の原告が顔をそろえました。その他の出席者は、4つの訴訟の弁護団と支援者、そして、沢田昭二先生(名古屋大学名誉教授)、肥田舜太郎・斎藤紀医師など総勢25名でした。
まず最初に各裁判の現状についての報告がありました。
◆京都原爆訴訟の現状と問題点(尾藤廣喜弁護士)
争点は、Aさんの個別症状と原爆起因性である。裁判所はAさんの病状の関係で審理を急ぐべきと明言しており、国側の準備書面を3月末までに提出させることを約束させた。次々回までには結審できる見通し。
運動が最大の弱点である。裁判の傍聴者は、回を重ねるごとに増えている。昨年12月18日に判決1周年の集いを開催し、近く正式に支援する会が発足する予定。
◆東京原爆訴訟(内藤雅義弁護士、山本英典東友会事務局次長)
立証課題として、被爆実態・診療経過・DS86批判・肝機能障害と被爆・他の事例、などを考えている。
東数男さんを東京の被爆者があまり知らない。当面、3月15日に決起集会を開く(150名規模)以降、支援する会を検討する。
◆札幌原爆訴訟
疾病の被爆起因性・被爆による治癒能力低下を主張。アメリカ科学アカデミーの「前立腺ガンの発病率も、平均より高い」との調査結果を入手し翻訳中。
支援連絡会を昨年11月1日に結成、個人会員229名、団体会員21、連絡会ニュース4回発行。弁護士28人、署名到達3404筆。
会議では沢田先生が『DS86とその見直しの現状』と題して講演、DS86とは何か、DS86以後の広島・長崎の原爆放射線量評価の研究状況などを報告しました。続いて、斎藤医師が『原爆放射線障害と肝障害、前立腺ガン』について報告し、肝機能障害と放射線との関係についての見解が年とともに変化していること、放射線影響研究所のデータをもとにした研究発表の一部を国・厚生省が認定却下のよりどころにしていることを明らかにしました。
討論の中で今後の問題として指摘されたのは、最高裁で勝利させることを前提に「認定制度を変える取り組み」でした。そして裁判にかかわる資料を日本被団協に集中すること、また、年に2回交流会を開く(次回は8月28日東京での開催)ことなどを確認しました。
第4分科会に松谷さんがゲストスピーカーで出席

「第1回ながさき女性国際平和会議」は、長崎市が昨年9月、「男女平等参画宣言都市」となったことを受け、市の奨励事業として開催されました。企画運営は公募で集まった市民と女性行政室で官民一体となった会議となりました。
初めて開かれるこの会議のテーマは「女性の人権」。その人権を「戦争と平和」から考えましょうということで、支援する会からも企画運営委員に応募することになり、牧山次長を送りだしました。
牧山次長は企画運営委員会の常任委員となり、分科会のひとつの企画に「平和の継承・ナガサキの少年、少女たち」と題する原爆問題を設定しました。ここに松谷さんはじめ中村照美弁護士、被爆者の下平作江さんやハーグ市民平和会議参加の高校生、平和大使として二ューヨークの国連へ行った高校生を招き、それぞれの立場で語り合うことになりました。会議宣伝のため、広報ながさきにも掲載され松谷さんのアピールもできました。
2月5日の会議には全体として1200名の参加がありました。そのうち、第4分科会は「平和への継承、ナガサキの少年少女たち」をテーマに被爆の実相を若い世代に伝えようと下平作江さんとともに松谷さんは被爆者として、また、原告として「多くの被爆者の思いを(国に)わかってもらう日までたたかう」と語りました。また、松谷訴訟弁護団の一人である中村照美弁護士も同じ分科会で訴えられました。その後、国連へ平和大使として行った高校生、ハーグ市民平和会議へ参加した高校生らが自らの体験を基に平和を継承する思いを語りました。分科会への参加者は90名でした。
長崎の女性達による手作りの「女性の人権と平和」を考え、行動する集会となり、マスコミにも大きく報道される催しとなりました。
松谷さんも企画運営委員の女性達に大変励まされました。

分科会参加者の感想を紹介します。
京都原爆訴訟、大阪高裁第5回口頭弁論ひらかれる
2月1日大阪高裁で第5回口頭弁論が開かれました。
弁護士6名、傍聴者14名で長崎から2名が参加しました。裁判長は国側に対し、今後の予定や期間をただし、国側が「2ヶ月程度」と答えると「まだ、そんなにかかるのか」と言いたげな態度を示し、弁護団も「結審まじか」を確信していました。次回の口頭弁論は、4月13日です。