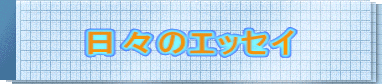
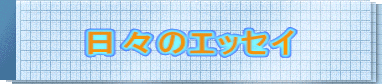
秋のバラが実家の庭に咲いていました。今年は、大きくて綺麗な色です。
薔薇という漢字を初めて何も見ないで書けた時、大人になったなぁと
思ったものです。中学のはじめ頃でしょうか。あと、『憂鬱』なんて字も、
画数が多くて複雑ゆえ、使うたびアカデミックな気分にひたれて。
「ばら」と平仮名で書くと、可愛くやわらかな花、「バラ」とカタカナで書くと、
凛としてスマートな花のイメージ。そして、「薔薇」と漢字で書くと、
なんとなく耽美的な雰囲気に。
漢字で表記された薔薇の物語を、二冊、読みました。
中井英夫さんの『幻想博物館』は、
流薔園という名前の精神病院が舞台です。
短編集で、その一つ一つが、患者さんの
夢のようなエピソードになっています。
「薔薇の夜を旅するとき」というお話には、
薔薇になって、薔薇の内部の感覚を
身を持って知りたいと願う車椅子の男が、
皮膚に薔薇を植え、恋人とともに、肌を
緑化させ、長い年月の後、閉鎖が決まった
病院の庭で、二人で一本の白い見事な
薔薇になったーーーという幻想的な物語。
静謐な文章が美しくて、作られた世界に
浸れます。
もう一冊は、皆川博子さんの『薔薇密室』。
こちらは、かなりの長編。第一次世界大戦
期のドイツとポーランドの国境あたりに、
怪しげな僧院があり、そこに住む博士が、
傷ついた兵士を連れてきて、人間と薔薇を
融合させる実験を行っています。
戦乱の中、ドイツの娘に化けて僧院に
やってきたポーランド人の少女の、現実に
流れる日々の様子と、それとは対照的な
僧院の悪夢めいた時間が交差し、
なにが本当でなにが作り事なのか、混乱して
くる物語です。 中でも、黄色い薔薇になった、年老いた男娼の
語りが、虚無感たっぷりでいながら、人間味があり、一番信じられる
ような。
八十二才の皆川さんは、今年『本格ミステリ大賞』を受賞されました。
文章の緻密さと、バイタリティーは見習いたいですね。
杉並(東京都)の細道を歩いていたら、美容院の店先に、なぜか
チェロが・・・。 秋は、弦楽器が似合うと思ってしまうのは、
学生の時に上田敏の訳詩を諳んじたせいでしょうか?
秋の日の ヴィオロンの ためいきの、
身にしみて ひたぶるに うら悲し
ヴェルレーヌがハタチの時に作った、『落葉』という有名な詩。
いろいろな人が訳してますが、やっぱり上田敏の選んだ言葉が
一番似合います。 バイオリン、じゃなく、ヴィオロンというのが
耳に優しいです。古い時代の言葉って、素敵なものが多いですね。
その、ヴィオロンを作っているお店が、実家の近く(代々木駅付近)に
あります。ショーウィンドウに、こんなふうに飾ってありました。
完成形しか知らない私には、面白い眺めでした。
秋は落ち葉の季節でもあります。枯葉ではないけれど、葉っぱの
形が良いなと思って、秋になると出番が多くなるお皿です。
枯葉に似せた黄色とか赤色とかがあれば、一緒に使いたいところ
ですが、売っていたのは、この一色。 でも、何でも合います。
今月は、今年末に出る予定の長編の、最終調整を情熱をこめて
やっています。 夜が舞台のお話です。 私は昔から、だんぜん、
昼より夜が好き。 とくに皮膚炎になったこの一年半は、ほとんど
夜しか活動しないドラキュラ生活でした。(今はやっと治ったので、
朝も昼も楽しみ始めていますが)
だから、夜を描いた物語を読むのも好きです。
大石真さんの『眠れない子』は、大切にしている本の一つ。
タイトルどおり、眠れなくなった子が、真夜中の町をさまよい、
不思議な灯りのともる家を見つけ、そこに集う人たちに出会い・・・。
眠れないという体験を意識した最初は、小学校四年くらいの頃でした。
以来、睡眠は短いほう。すっきり眠ったと思える日は、ほとんど無い
けれど、もはや、それがベストな状態で、気になりません。
眠れない、という主人公には共感を持ってしまいます。
作者の大石真さんとは、新宿の児童文学学校に通っていた時、
一度だけ、講師としてお話をしてくださり、授業の終わった後に、
みんなで飲みに行きました。
お作品そのものの、やさしく、あたたかな感じの先生でした。
その後、『びわの実学校』という、大石先生が編集長をやっていらした
雑誌に、私の作品が掲載され、お礼状を出したところ、先生から
丸いきれいな文字のお葉書をいただき、励ましの言葉に感激した
ものです。 もう二十年以上も前の話ですが、文面を今も覚えて
います。
今月末は、ハロウィンですね。 かぼちゃの飾りが町を彩っています。
寒くなってきたので、風邪など召しませんように。
2012年 10月
トップページへ
前回のエッセイへ
次回のエッセイへ