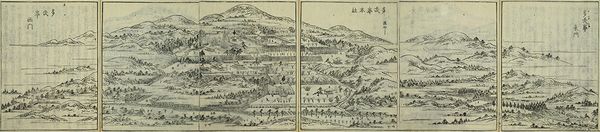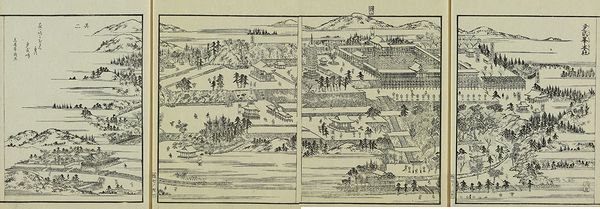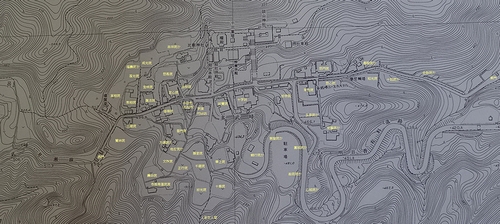|
�����������y���\�O�d���F�d��
�V���V�c�V�N�i678�j���b�������j��b��������̋A�����A���̕��ےÈ��Ђ̒n�����a�̂��̒n�Ɉڂ��A�\�O�d���������̂�������̑��n�ł���B
���u���ɂ����闼�E��䶗���Ԃ̓W�J�v�@���F
�@�����R�N(1173)�������O�k�̏Ă������ŏĎ��B
�@�������N(1185)�ċ��B
�����������\�T�N�i1532�j�Č��B�B��̖ؑ��\�O�d���̈�\�B�����P�R�D�Q���B���ւ͎��ցB�S���͂Q�w�~�܂�B
�{�������F�͓P������A���݂͓��~�������u�Ɖ]���B���͒k�R�_�А_�_�Ə̂���B
���u��a�̌Ó��v�@���F
��d������ӂQ�W�ځA�����Q�ځA�㐬��ӂP�X�ڂQ���A�����Q�ځA�T����ӂP�R�ڂX���A�����P�ڂR��
�@�@���d�S�R�ԂX�ڂT���R���A�����ԂR�ڂX���P���A���e�ԂQ�ڂW���P��
�@�@��d�S�R�ԂW�ڂS���S���A�����ԂR�ڂR���S���A���e�ԂQ�ڂT���T��
�@�@�O�d�S�R�ԂW�ڂV���U���A�����ԂR�ڂQ���U���A���e�ԂQ�ڂS���T��
�@�@�l�d�S�R�ԂV�ڂS���S���A�����ԂR�ڂP���W���A���e�ԂQ�ڂR���T��
�@�@�d�S�R�ԂV�ڂU���P���A�����ԂR�ڂP���P���A���e�ԂQ�ڂQ���T��
�@�@�Z�d�S�R�ԂV�ڂR���R���A�����ԂR�ڂO���R���A���e�ԂQ�ڂP���T��
�@�@���d�S�R�ԂV�ڂO���T���A�����ԂQ�ڂX���T���A���e�ԂQ�ڂO���T��
�@�@���d�S�R�ԂU�ڂV���W���A�����ԂQ�ڂW���X���A���e�ԂP�ڂX���T��
�@�@��d�S�R�ԂU�ڂT���O���A�����ԂQ�ڂW���O���A���e�ԂP�ڂW���T��
�@�@�\�d�S�R�ԂU�ڂQ���Q���A�����ԂQ�ڂV���Q���A���e�ԂP�ڂV���T��
�@�\��d�S�R�ԂT�ڂX���S���A�����ԂQ�ڂU���S���A���e�ԂP�ڂU���T��
�@�\��d�S�R�ԂT�ڂU���V���A�����ԂQ�ڂT���V���A���e�ԂP�ڂT���T��
�@�\�O�d�S�R�ԂT�ڂR���X���A�����ԂQ�ڂR���X���A���e�ԂP�ڂS���T���A
�@���֒��P�Q�ڂP���A�S���T�R�ڂR���T��
2007/09/25�lj��F
���u�k�R�_�Џ\�O�d���v�֖��i�u���z�G���v��Q�R�P���A�����R�X�N�@�����j�@���
���̓��̍Č��N��͋L�^���q�̓`�ӂ���̂Ȃ����A��̎��������ꂽ���D�ɂ���āA���\�T�N�i1532�j�ƒm���B
�e�d���R�Ԏl�ʒ��A�����ԂP�Ԃ͔ˁA���d�e�Ԃ͘A�q���A����ɂ͑g�҂�p�����A�o���ɂ���Ċی����x������B���͓�d�ɐ��A�����w�畘�A�O���؍ނ͎�h�A�،��ɂ͉��y��h��A���ؒ[�͓t���̕�������A�����͑f�̂܂܁B
�����R�U�N����R�W�N�ɉ�̏C���B���̎��A���i�P�W�N�̓��D���B
�@�@�\�O�d�����i�P�W�N���D�S��
2020/06/28�lj��F
���u�֗]�E�������̓��v
�����͓y��̏�ɏ���A�S���͓�w�Ŏ~�܂�B�l�V���̎O�ʂ�͂��Ƃ��A���ʂɐ_����u���Ƃ����B���ւ͎��ւł���B
2020/11/19�lj��F
���u�d�v�������k�R�_�Г��k(�\�O�d��)�C���H�����v�ޗnj��������ۑ��������ҁA�ޗnj�����ψ���A1966.3�@���
�{���ɑ�����̉��v�A���k�i�\�O�d���j�̉��v�A���k�̍\���`������ї��ʐ}�E���ʐ}�Ȃǂ̐}�ł̌f�ڂ�����B
�i�]�ڂ͂��Ȃ��̂ŁA�{���ɓ�����ׂ��B�j
��������\�O�d��
2002/03/28�B�e�F
2020/05/07/�B�e�F
���Q�l�F�����゠�邢�͈�\�̎c��ؑ��\�O�d��
�ȉ��̎��@�ɑ��݂������Ƃ��m����B
�@���R��}�u���E��s�������l���@�E���q�Ɋy���E�R�鍂�R���E�R����������E��a���J���E��a���R����E���O������
�����������y���̊T�v
�������N�G��
���{���F�B���݂ł́A�\�Z���I�����ȑO�̐������Ɖ]���Ă���B
���u���������N�G���v�k�R�_�ЁA������q�A2016�@���
���̊G���ł͓��������̐��U�i�剻�̉��V�Ƃ������͓����Ȃǁj�A���j��b�ɂ�銙���_���E�\�O�d���E�u���E�{�a�̑n���A�����l�̎��сA��j��̗쌱杂Ȃǂ��`�����B
�{�y�[�W�ł͒�b�ɂ��\�O�d�������ɂ��Ď��グ��B

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����N�G���F��}�g��}�F�T�C�Y�F2.88M
���R�Ȃ���A�G���͌������ĉE���獶�Ɉړ�����B
�����ɕ\����Ă��邱�Ƃ̐^�U�͕s���ł��邪�A���y�����邢�͖��y���\�O�d���̑n��杂ł���B
��b�A���ɍ݂�Ƃ������݂�B�H�A�g�͍��R�Ƃ��Ēk�̕��ɋ���B�����ŕ������������ĉ]���B�፡�V�ɏ������B���͂��̒n�Ɏ��������āA����ȋƂ��C�߂�B��͂킪�_������̕��ɓV�~���Ďq����i�삵�A���@�𐢂ɍL�߂悤���@��
��b�͓��k�������̕���̏�Ɍ��Ă悤�Ƃ��A�����R�ɓo�����A���r�@�\�O�d�����ڂ����A��i�I�Ƃ����j�ꊔ���Ȃ��ē��̗p�ނƈׂ����Ƃ���B
��b�͏\�O�d���̗p�ށE���ȂǂB���A�A���̓r�ɏA�����A��D�����D�������A�����̈�d���̗p�ނ������Ɏc�����ƂƂȂ�B
��b�͋A�����A�E��b�s�䓙�ɑ�E��������͂ǂ����Ɛq�˂�ƁA���Ú������S���ЎR�Ȃ�Ɠ�����B
��b�͐��O�A��E���Ƃ̖�����ƌ��B���Ō���������ڍׂɘb���B
��b�͂Q�T�l���������Ĉ��ЎR�̕�ɎQ��A��[������@��o����ɂ����A���܂��Ă����B��͓V�ݖL���V�c�i�F���V�c�j�̑��Ȃ���O������̈����ɂ�蓩���i�����j�̑��ƂȂ�@�ƁB
�܂��A�l�ɓy��S�����Ƃ��ɒk���ɓo������B
��b�͒k���ɓo�����A�⍜�����A���̏�ɓ������Ă�B�ޖE�����s�����A�\��d�ōH���͒��f����B
�锼���d���̑�J�啗��������A�����͓V���A�������グ��ƍޖE�����ςݏd�Ȃ�\�O�d���ƂȂ�B�\�O�d�ڂ̉����͓��̍�����������Ƃ�m��B
�o�N�̌�A���̓�ɎO�Ԏl�ʓ������āA���َ��ƍ����B����͒�b�̌��Ă����̂ō��̍u���Ȃ�B���ꂪ���������̑��n�Ȃ�B�E
�u��������̕ӂ�Ɉٌ������X�����B��b�͂��̂Ƃ���ɕ��O��̌�a�i���˓a�̑��n�Ȃ�j�c���A�������ˑ������u����B
���t�͋ߍ]�����j�ۂȂ�B
�����������y���{�a�E����
2020/06/28�lj��F
���u�������k�R�_�Ж{�a�v�O�Y���K�i�u���{���z�w��v��n�_���W
��355���v���a�U�O�N�X���@�����j�@���
�@���������y���{�a�͗�̏��Ȃ��O�ԎЏt�����ł���A���̕��ʂ͈�Ԏl�ʂ̌`���ł���A�_�Ж{�a�Ƃ��Ē��������̂ł���B�܂���w�̎l���ɔ݂����炷�A���邢�͔݂ɗނ����Ԃ�݂���Ƃ������̂ł���B
�@�u���������L�v�ɂ��ƁA�Ր_�ł��铡�������͓V�q�V�c�W�N�i669�j�ɖv���A�ےÍ������S���ЎR�ɑ���ꂽ���A���̒��q��d�a���������A������Ƒ�����ɉ������ĕ��ɏ\�O�d����n�����A�o�N�̌�ɂ͎O�Ԏl�ʂ̍u���𓃓�Ɍ������Ė��y���ƍ������Ƃ����B�܂��A�����̌�e�������u���邽�߂Ɂu���O���a�v���n�������Ƃ����B���̖��y����������̖{�̂ł���C���O���a�����ˉ@�̑O�g�ł���B
�������ɓ���A����ɂďo�Ǝ������������������̍���ƂȂ�A�V��P�O�N�i956�j�ɂ͉���̖����ƂȂ�B
���̂��Ƃ͓�s�������Ƃ̊W���������A���ɂ͋������O�k�̏P�����邱�ƂƂȂ�B
�@���� �C
�i�ی��N�i1081�j�O���A�V�m���N�i1108�j�㌎�A�����O�N�i1173�j�Z���A������N�i1208�j�i����͋���R�O�k�ɂ��j�A���匳�N�i1227�j�����A����N�l���ɂ��ꂼ��đł�����A���̂��������O�N�ɂ͂قڑS�Ă���B
�܂��C�����Z�N�i1351�j�\�ꌎ�ɂ͎��ɂ��S�Ă���B
�������ɂ͑�a�𒆐S�Ƃ����z�q���ⓛ�䎁�Ȃǂ̍R���Ɋ������܂�A�i���\�N�i1438�j�����Ɖi���O�N�i1506�j�㌎�ɂ͕��ɜ�
���ďĎ�����B�܂����̊Ԃ̉��m�O�N�i1469�j�ɂ͓����ɂ���ďĎ�����B�L�b�G������a�S�R��ɓ��{����ƁA�V���\�Z�N�i1588�j�l���ɌS�R��ɎГa��V�����Đ_�̂ł��銙���̌�e����J�������A���\���N�\�ɂ͑�����ɋA������B
�����ېV�̐_�������ɂ��A���y���̍��͔p����A�_�ЂƂ���A���݂Ɏ���B
�@�{�a�́A�]�ˊ��ɂ͌\�N�قǂɈ�x�̑��ւ����{�ɔF�߂��Ă���A���݂̖{�a�͉Éi���N�i1848�j�ɖ؍�n�A���O�N�ɏ㓏�������̂ł���B
���ʂ͈�Ԏl�ʂ̎剮�ɎO�Ԃ̌��q��t�����`���ƂȂ�A�O�ς͎O�ԎЏt�����i���ؓ���j�ƂȂ��Ă���B
�@����A�]�ˊ��ɂ�����ŏ��̖{�a���c�͌��a�ܔN�i1619�j�ł���A����Ȍ�A�������N�i1668�j�A���ۏ\��N�i1734�j�A�������N�i1796�j�A�Éi�O�N�ɑ��ւ���Ă���
�B
���ւɂ��s�p�ƂȂ������{�a�́A
�@�������{�蓰�i���a�x�j�A
�@�������y�Ж{�a�i�����x�j�A
�@��a�S�ώ��{���i���ۓx�j�A
�@���厛����@�������i�����x�j
�Ƃ����ꂼ��ڌ����ꌻ������B
�]�ˊ��ɑ��ւ��ꂽ�����̖{�a�́A�ڌ����ɉ����������̂����邪�A��������ƁA���ʂ�t�����̌`���͓���ł���A���ւɍۂ��ċ��K�P���Ă��邱�Ƃ��m�F�ł���B
2020/09/15�lj��F
�@��a�S�Z���{���ɂ��ẮA��a�S�Z���̃y�[�W���Q�ƁA�ʐ^�f�ځB
���ۑ��֎��̖{�a���������֎��ɑ����������ł�������a�S�Z���Ɉڌ��i�A���A��x�]�p�̌�A�S�ώ��Ɉڌ��̉\��������j�Ƃ����B
�{�a�͎O�ԎЏt�����ł��邪�A�S�Z���{���͓��ꉮ���ɉ����������A���ʋK�͂͑������{�a�̕��ʋK�͂ƈ�v����Ƃ����B
��������T�v
2022/10/01�lj��F
���u�R�x���@�����̉ۑ�v�]�J���i�u�����l�Êw�W���[�i��(426)�v1998.1�@�����j
���y���̉����z�u�͋����̒����ɐΊK������A�����ɓ����B���ɂ͖��y�����ˉ@�q�a�E�{�a�Ȃǂ�����A���ɂ͓V��@���@���z����鉾���ł������B
�\�O�d���𒆉��ɂ��āA�����ɂ͖@�ؓ��Ղ�����A�����ɏ�s���A���ɂ͖@�ؓ���z������̂ł������B
�\�O�d���̈�i���ɂ́A�u���𐼂ɁA�����𓌂ɔz�����b�R����i�����j�ɗގ����鉾���ł������B�i�����͋����Ձj
�@���������������y������
���������ɓV��@�ɓ]���b�R���ƂȂ�A���̂��߁A�x�X��s�i�������j����Ă����������B
�]�ˊ��ɂ����Ă��A���̂R�O�O�O�A�S�Q�V�𐔂����Ɖ]���B
�����ېV�̐_�������ŁA��R�͎��@�h�Ɛ_�Дh�Ɋ��ꂽ���A�_�ЂƂ��đ������邱�ƂɌ����A�k�R�_�ЂƉ�������B
��v�����͐_�ЂƂ��đ����������A�����̖V�ɂ͔p��A���Ȃ������̉@�V�Ղ����邱�Ƃ��o����B�܂����̎��A�����̕����E������p�����B
�@���_�������̏��u�Ŏ�v�����͈ȉ��̂悤�ɉ�₂����B�i�������A���Ԃ����@�ł���A�_�Ђ̎����������������߂Ǝv����B�j
�c�����铰���F�����A����@�i�{�a�E�d���j�A�썑�@�i�q�a�E�d���j�A�O��i�d���j�A�u���i�_�_�q���E�d���j�A��s�O�����i���a�E�d���j�A���Ж{�a�i�d���j�A���Дq�a�i�d���j�A������Ɂi��������d���j�A�{�蓰�i���a�E�d���j�A��b�_�Ёi�d���j�A�ω����A���ꓰ�B
���u���������L�v�u�������N�W�v�F
�V�q�V�c�W�N�������������A�ŏ��͎��q�s�䓙�ɂ��ےÈ��ЎR�ɑ�����B
���P�V�N�A���q��d�A���A���̒n�ɉ������A�_���Ƃ��Ă��̏\�O�d�����������A������쎝���邽�߂ɖ��y����n������B
�u�����������L�v�F�\�O�d���̂ق��ɁA���y���ɂ͂����đ��E�O�d�������݂���B
���k�R���y���썑���ƍ�����B�������ł͓��k�͒�b�a���̑��n�ŁA���y���̍��{�Ƃ����B
�n��ɑ�D���i�����j�̈⍜�����߂��Ƃ����B�{���͕����F�B�Y��Ƃ����������O�d�������i����j�Ȃǂ�L����B
2007/09/25�lj��F
���u���������y���̓W�J�v�H�i���F�i�u���䒬�j�@���v����s�����A���a�R�Q�N�@�����j
�@�@�Ȃ��A���_���́w�u�����M�v(���O�@���j�p��:��23��)������C�ҁA�Y�R�t�A�����R�N�x�ɂ����^�����B
�����ېV�܂ł́A�����E���������y���E�k�R�����E�썑�@�ȂǂƏ̂��ꂽ�B
�u���������L�v�i���v�W�N��1197���̐����ŁA���q���ȑO�̖��y����m�肤��B��̎����Ɖ]����B�j�ł�
�V�q�V�c�W�N�i669�j�������������A�ŏ��͎��q�s�䓙�ɂ��ےÈ��ЎR�ɑ�����B
���P�V�N�A���q��d�A���A���̒n�ɉ������A�_���Ƃ��ď\�O�d�����������A������쎝���邽�߂ɖ��y����n������B
���̌㓰���͍r�p������A���������A����i��ɉ����j���r�p��J���A���y�������A���㌟�Z�ƂȂ�B
�@�����쎮�E���˕��̋L�ڂɁu��������@��������b����ʒW�C���������b�A�ݑ�a���\�s�S�E�E�E�E�v�Ƃ���A
�@�ʏ�A�W�C���Ƃ͊������q�s�䓙���w���A���̂��Ƃ���A������ɂ͊����ł͂Ȃ��s�䓙������ꂽ�Ƃ���������z�����i���Ă���j�B
�@���̐��́A�u���������L�v�̋L�ڂȂǂŐM�����Ă������Ƃ��ے肳�����ł͂���B
�@�������A�W�C�Ƃ͖��炩�Ɋ������w���Ǝv���镶�����U������A���쎮�ʼn]���W�C�Ƃ͊������w���Ɖ��߂��Ă��s���ł͂Ȃ��A
�@�×�����̐M�Ɩ���������̂ł͂Ȃ��B
����P�X�N�i919�j�����m�s�A��������S�㌟�Z��������B�����͍����ȉ���C�s�m�ŁA����ɓV��N�i947�j���������ƂȂ�B
�ȍ~�����l������ɁA��������l�����Z�ɂ���K�����n�܂�A������͎�������b�R�̖����ƂȂ�B�i�b�R�������ɂ��Ăِ͈�������B�i�u���̕���v�j
���a�R�N�i963�j�b�R�w�m�E�����l��������ɓo��A���n�ő����̒�q�ɓV�䋳�w���u䭂���B�ȍ~�V�䋳�w�����łɑ�����ɍ��邱�ƂƂȂ�B
���������̈�R�̓��k�E���F�ɂ��Ă͈ȉ��Ɠ`������B�i�u���������L�v�j
���k
�@�\�O�d���F������A��d�̌����A��d�������R��r�@�����ڂ��Ɠ`����A���邢�͌I�̈ꊔ�ō��ꂽ�Ɖ]���B
�@�����F�������N�i1025�j���Z�����̑����B
�@�O�d���F�m���i1167�j�����A���a�֔�������b��[�̌��B
����
�@�u���F�\�O�d����A�R�Ԏl�ʓ��A�����y���A��d���P�P�P�N�����B
�@�����F�u�����A��d�����A���Ӌ������C���B
�@�@�@���F�V��W�N�i954�j���������B
�@�@�؎O�����F�N�ی��N�i964�j����V�c�@�ؓ������A�����l�ڏC�O���������B
�@��s�O�����F�V�\���N�i970�j�ې������ɛ���s�������A�o�@�T�t��ɑ����u�A���ۂQ�N�����\�땶���V�B
�@��䶗����F�V�\���N�i970�j�����ɛ������B
�@���哰�F�匳���N�i976�j�~�Z�V�c�����B
�@�擿���F�É����N�i1169�j�r��@�t���i���������B
�@�H���F�����T�N�i935�j����^���A�����X�ԂQ�ʂ̐H�������B
�@�����F���P���B
�@���O�F���P���A���������N���������V�A�V�c�T�N�i942�j�����E�^�������B
����@�F�w�畘�R�Ԏl�ʁA��E���������u�B
���ЁF�w�畘�A�����S�N�i926�j�͂��߂đ��Ђ�B
�ʉ@
�@���@���A��@���A��y�@�A��y�@�o���A�����@�A�����@�o���A���y�@�A��ω@�A�ܑ哰�A���A���I�����A�~�쎛
�������F�����̖��������邪�A�����Ȏ��@���U�������B�i�����Ȗ����͈ȉ��̒ʂ�ł���B�j
�@���Ύ��i�@���P�@���j�F�y�s�S���H�R���ɂ���B
�@��c���i�@���������j�F���s�S�앣�A�ƍ쒹�̌����Ɖ]���B
�@�R�c���i�@���،����j�F�h��q�R�c�ΐ얃�C�̌���
�@�v���F���s�S�v��
�@�������F�_���V�c�ˈ悩�疾�������ɑ�E���ՂɈړ]�������@�Ǝv����B�@�@�Ȃ�
������͓������n�c�����̕揊�ł��邪�A�b�R���ɂȂ������߁A����������璆���ɂ����āA�������̎����������Ƃ̊ԂŐ������̑������䂫�N�������B���̑����́A��{�I�ɂ͋������Ɖ���Ƃ̑��������邽�тɁA�b�R��������͋������̏P�����A���������ɑ����̑��Q���o���Ƃ����\�}�ł������B
�呹�Q���o���������ȑ����i�퓬�j�ɂ͈ȉ�������A
�V�m�Q�N�i1108�j��y�@�����V�A�R���̑��X�A�H���E�o���E�y�ЁE�剷���E���E���E�ܑ哰�E��y�����Ă����B
�����R�N�i1173�j��y�@�E��@�E�����@���n�ߍu���E�����E��s���E�\�O�d���E�@�ؓ��E����@�E�E���O�E�y�ЁE��䶗����E�O�d���E�擿���E�H���E�剷���E��y���E�ܑ哰�ȂǎR���E�����E���������Ď�����B
���̑��̍R���E���i�E�Њd�Ȃǂ͖����ɂ��Ƃ܂��Ȃ��B
�@��k���������U�N�i1351�j���ɂ��A��R�����Ď��A�������ܗ��N����ċ��ɒ��肷��B
�i�����N�i1429�j��a�i���̗��Ɋ������܂�A�u���ЖV�ɕ��n����v��R�قڏĎ��B
��a�i���̗���͈�R�̊m���i�w���Ɠ����j���R�����ĂсA�����Γ����V�ɂ��Ă��B
�@���Ⴆ�Ή��m�R�N�i1469�j��@�ƕ����@���������A����������߁A��R�w�ǏĖS����B
�i���R�N�i1503�j��a���y���̍R���ŁA��R�Ď��A�܂��Ȃ������B
�V���P�R�N�i1585�j�L�b�G����a���{�A������̋|�E�ȁE�S�C�E��E�b�h�E�����ȂLj��v���A�����ɒ����I�O�k�i�m���j�͉��R����ł����B
�V���P�U�N�G���͑�D���̌S�R�J���𖽂���B
�V���P�W�N�S�R���A�R�A�R�Q�V�������A�c���T�N�ɂ͂S�Q�V�B
�ߐ��ɂ͋����@�ȉ��Бm�S�Q�V�A�G���U�V�A���V�͉��@�̕��q�@�ȉ��S�V�A���@�@�E�{�{�V�E�w���|�іV�Ȃǂō\�����ꂽ�B
2006/11/05�lj��F
���u�_�������̓����v���
�{���͑�E�����������ŏ\�O�d���𒆐S�ɓ������̗����ƂƂ��ɔɉh���ɂ߂�B����䂦�A���̌����͑��̎��А��͂Ɠ��l�ɂ߂Đ����I�ł��������B�V��̎x�z���ɂ���A���̐_�E�͑��݂����A�o�c�E�s���E��ɂ͑S�Ă͑m�����s���Ă�������ł́A���@�ł��������A�{���͒k�R�����A�k�R���_�ł���A���̓_�ł͐_�����s�v�c�ɏK�����Ă����Ƃ��v����B
�����ɉ����Ă��q�@�R�R�V�Ə��d�i���ɁE�����Ǘ��E�G���j�V�U�V���������B���̂͂U�O�O�O�B
�_�������߂ɂ���āA���y���͖{��������_�i�������̂ɁA���̖{������邽�߂ɕ����E�_���邩�A���@�ł��邱�Ƃ��т����R���邩�̑I���𔗂��邱�ƂɂȂ�B��R�͕����h�Ǝ��@�h�Ƃő��������A���ǂ́i�����炭�͌o�ϓI���R�Łj�R�𗣂��͍̂���ŁA��R�����E�_���邱�ƂɌ�����B
�������āi�_�ЂƂ��Ă̎��̂̂Ȃ����y����_�ЂƂ��ĕ������邽�߂Ɂj
����@�͖{�a�A�썑�@�͔q�a�A�\�O�d���͐_�_�A�u���͔q���A��s�O�����͌��a�A�얀�����P�a�E�E�E�Ȃǂ̖����ꒃ�ȓ]�p���Ȃ��ꌻ�݂Ɏ���B����܂ł͖{���Ȃǂł������������u�̕����E����E����Ȃǂ́u���v�̂悤�Ɉ����A��ӏ��ɏW�߂��A�ǂ�ǂ���Ă������B�u���{���߉ޟ��ϑ��͂Q�T�K�A����Q�T�����ꊇ���ĂQ�T�K�ł������B
�i�O���Ś삵���Y���p���ꂽ�Ɖ]���B�j
���������܂ł͑m���ł��������̂ǂ��̎�ɂ���Ăł���B
�����S�N��n�߂Ŏ��́E�З̂��v���A���������y���͍������ɂ߁A��R����E���U�Ƃ��������ɂȂ�B
2020/06/24�lj��F
���u���ȂƋF�]�@�`���[�̖�v�W�H�@�u�A�d�q�o�ŎЃn�b�J�h���b�v�X�A2014�@���
�@�i�������ł���B���̒��̈�߂��f�ڂ���B���҂ɂ��Ă͏�Ȃ��A�s�ځB�j
�@�u������͌ÐF��тсA�w�i�m�ł��낤�j�k�������C�s�̂��߂ɏZ�މ����ł������B�ꎞ�A������͖��������̐_�������̉e���Ŏ��@�̖ʉe���c���Ȃ���������ς���̖����̒k�R�_�ЂƂ��đ��݂��Ă����B�������{���͑����Ƃ��������ł������B����Z�c�q�Ɠ������������V�̖��k���s�����Ƃ����邱�̎��ɁA�����̎q�̒�d�ƕs�䓙���ؑ��\�O�d�̓������������̂��͂��܂�Ƃ��ꂽ�B���{�Ō�������B��̖ؑ��\�O�d�̓��ł���A�w�畘���������c�ɘA�˂������P�V���ɂ��y�ԓ��ł������B������͍ĎO�̉ЂƖ��������̐_�������ɂ��A���݁A���̗��j��H��͕̂s�\�ɋ߂��B�����È��́u���������L�v�i1197�j��x�i�����j�厜���́u������Ǝ����|�����@���̈�ʁ|�v���̌����ɂ���Ă��̑S�e�����炩�ɂȂ�n�߂Ă����B�v
2020/10/30�lj��F
���u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j�@���
�@�@�@���u������̐_�ŕ����v�͑吳�P�T�N�����I���B
�C�j���v
�@�V�q�V�c�W�N�����������I�����A����𝐒Ó����S���ЎR�ɑ�����A�V���V�c�U�N�����̎q��d�a����������A�����A�X�ɂ�����a�\�s�S�q��R�ɉ������A���̏�ɏ\�O�d�����c�݁A�㐔�N�ɂ��Ă��̓�ɎO�Ԏl�ʂ̓������āT���y���ƍ�����B���ꂪ������̑��n�ł���Ɠ`������B���̓��͌�̍u���ł���A���݂̎Ж����ł���B
�܂��A��d�͓��̓��ɕ��O��̌�a��A����Ɋ����̑������u����B���ꂪ�����̏�������a�i��a�E�{�a�j�ł���B
�@�������ĐF�X�ȓ��ɂ��Q���o�c�����A���߂͖@���@�ł��������A�����l�ċ��ȗ��V��@�ƂȂ�A�������̔ɉh�Ƌ��ɁA��R���v�X�����ƂȂ�A�L��ȏ��̂Ƒ����̏O�k��i���āA��s�̏����E�ߗׂ̕��ƂƑ����A�ƁX���ɜ��B�������A���̓s�x�������ʂ����A���ς�ۂB
�V���P�R�N������͖L�b�G�g�̖��ɂďG�������̏鉺�S�R�ɑJ�������ށB��R�͑�����̖{���Ɏc����̂ƌS�R�̐V���ɑJ����̂Ƃɕ��A���̂U�O�O�O�͐V���ɂR�O�O�O��^���A�c��R�O�O�O�͖v�����ꂽ�悤�ł���B
�P�U�N��D���S�R�ɑJ���A�{���̓��������͈�F���c�����j��A�O�k�͗��U����B
�P�W�N�����̎Ў��̋F���̌����Ȃ��A���炵�Ă����G���̕a��͎v�킵���Ȃ��A����������͑�D���̐_���̒v���Ƃ���ł���Ƃ̉\�����z���A��D���̓{�����߂邽�ߑ�����͋A�����邱�ƂƂȂ�B����́A�S�R�V���̂R�O�O�O�͖{���Ɉ��������ƂƂȂ�B�������A�V���͂Ȃ����S�R�ɗ��܂�y���������悤�ł���B
�c���T�N�i1600�j�ƍN�ɂ��u���̍Č������A���̍u���̍Č��ɂ�葽����͂قڋ��ςɕ�����B
�ȍ~�ߐ��͂��悻�T�O�N���̖{�Б��ւ�����A������͂قډ����̈ێ����}���A���̂܂ܖ����ېV���}����B
�i���j�����E����
�@�ߐ��̑������}�ɂ��Ă͌c���T�N�i1600�j�A���ۂQ�N�i1645�j�A���ۂV�N�i1722�j�A���̑���㉚����c��B
���ۑ�����㉚��F���������A�U�ڂR���~�T�ڂW��
�@���ۑ�����㉚��F���y����������юR���q�@�̑S�e���`�����B
���ۑ�����㉚��F�����@�i�������j���A�T�ڂS���~�X��
�@���ۑ�����㉚�
�@���ۑ�����㉚��E���������F�ߐ��O���̑��������y�������̑S�e��������B
�@���������y�������͎��̂悤�ł������B
����̒��[���瑽�����ڎw���Ƌ����֊|�낤�Ƃ���Ƃ��낪������ł���B�i�s�������̑�A�j�s�����A�n�����U���Ȃǂ�����B�j
�@��������J��ɋ��i�勴�E���`���j���˂���A���̋���n��Ƌ����ł���B
���̐�A���a��i�ނƐ�������A���̍��[�Ɂu���l���]���ܒ��v�ƍ��ޕW������B���̏��l���͍��͂Ȃ��B
����n��ƕ\��i����E�����j�ł���B�����ɉ�������B
��������R���A���̍��ɐΑ����p���i����֓��j������A����͈�̒������牾�����P�����ƂɌ��Ă��ΕW�̏I�_�ł���B���̐Γ��͐_�������̎��A�y���ɖ��߂�����A�����Q�T�N�@��o���A���n�Ɍ��Ă����̂ł���B
����֓����班���o���č��ɓ���Ə��������R�n������B�����ɕ����Ƃ��̔w��ɒn�������������B
�@���ɖ߂��Ă���ɐi�ƁA���Ă̒҂ɏo��B���̒҂����ɓo��ƍr�_�ЂƔ��R�ЂƂ��̂Q�Ђ̔q�a���������B
���Ă̒҂ɖ߂�Ƃ����ɂ͓�ʂ��钹���i��̒����j������B���̒����͈�̒����Ɠ����ł��邪�A�{�a�i����a�j�̒����ł���A�\�O�d����u���������y���Ƃ͉��̊W���Ȃ����Ƃɗ��ӂ��ׂ��ł���B
�@�Q�����̓����ɂ͘O��i�R�ԁ~�Q�ԂP�ځA���͔p��j�̘O�傪�������B�i���͂Ȃ��j
�O������ƁA���ɓ��ʂ��Č䋟��������B�i���̋{�i��ł���B�j���ې}�ɂ͂��̌䋟���̏��ɐ��̌얀��������A����ɉ��ɐH��������B�܂��ʐ}�ɂ͂��̐H���̏��ɐ��̌얀��������A���݂��P�a�͂��̕ʐ}�̐��얀���ł���B
�@�Q��������ŁA���̓��Ɍ얀�����������B���̓����̌얀���͑����p�����炵���A�ېV�����ɂ͐��얀���Ղ䋟�����o���A���̌얀���Ղɂ֑͗�������A���̗֑��̓��ɂ͋��ې}�ł͟������������A���̟��͈ېV�O�ɂ͖{�蓰�̓��ֈڂ��Ă����B
�@�Q���E�ΊK��k�ɓo��ƁA�ΊK���r����Ɍ�{�n�u��������B�u���͌��ݎЖ����Ƃ��ĕۑ�����A�{��d�����Ȃǂ͓P������A�����O�ɂ��ގO���������u����Ă����Ƃ������Ƃł���B
�@���̍u���̓�Ɍ��đ����ĕ��䂪����A���̐��ɂ͐H���֒ʂ��钆�傪����B�܂��u�����ɂ͏�d���������������A����E����ƂƂ��Ɍ������Ȃ��B��d�����̓��ɂ͋��ې}�ɂ͏��O�����������B�܂����O���̓��E�Q�q���̐ΊK�����Ăę����V�Ђ��������B
�@�ΊK��o��l�߂�ƁA���ې}�ɂ͉����ʂɑJ�a������A���̉E�ɋ{�d���Ƒ�ʎᏊ���������B�����đJ�a�̂܂��ɂ͔q���Ƃ��̑O�������ɞى������������A�����͈ېV�O�ɂ͎����Ă����B
�@�ΊK��o��l�߂������E�ɂ͌�a�i����a�j������B��D���̐_�����J��A�Éi���̑��c�ł���B���̑O�͌썑�@�i���ɂ�������~�E���̔q���j�����B��a���ɂ͋{�d���A���̓�͓��L�Ō썑�@�ɒʂ���B��a���ɂ͌o��������A���̓�͓��L���A�Ȃ�A���E������a�ƌ썑�@�Ƃ̊Ԃ̐Ώ������ł���B
�܂��썑�@�Ɛ����L�Ƃ̊ԂɘO�傪����A��a�O�̍L��ɏo�邱�Ƃ��ł���B
�����Č썑�@�̓��i�Ⴋ�ꏊ�ɓ������Q������B�i�����͑ޓ]�j
�@�����̓����R�n�ɖ{�蓰�i��d���j������A���݂ł͐ێГ��a�Ə̂��A�s�䓙�����l�i��d�j���J��B�c�����ɂ͑�����Ƃ���B
��d���̓��ɂ͒���������A�ω����ł������炵���A���������͟��ł������B�ω����̖{���@�ӗ֊ω��͖{�蓰�Ɉ��u����Ă������炵���B
���̂܂����Ɏቤ�q�ЂƐ��R�_�Ƃ��̗��Ђ̔q�a�����������A�����̏��Ђ͔�b�_�ЁE��ЁE���R�ЂȂǂ̏��ЂƂȂ�A��s���̐����ɂ���B�����Ă��̖k�ɂ͎O�V�_�i�������_�E���s�n���P�_�E�E�F�ꍰ�_�j�Ɣq�a������B
�܂���a�����Ă̓��ɂ������āA����ɂ�����A���̓�ɂ͏t���ЁA���ɂ͔H�X����������B
�c�����ɂ͂����Ɍ얀���Ƒ������������ƂɂȂ��Ă���B
�@�@���ߐ������ɂ͖��y���ɑ����������悤�ł��邪�A����ȏ�̏��͂Ȃ��A�ڍׂ͕s���ł���B
�@��a�����L�̐��ɂ͐�������B���ې}�E�c�����E���ۚ��ɂ͂����ɖ@�ؓ������������ƂɂȂ��Ă���B
�����琼�Ɉ�i���������Ƃ���ɏ\�O�d���i�����_���j������A�����F�������u���Ă����B���̓��̑O�ɂ͔q�a���������B
�@���̓��̐��͏�s�O�������ł���B�{���͈���ɔ@���ł����������͓P���������A�{��d�͍��Ȃ𑶂��A�����ł͌��a�Ƃ����B�Ȃ��A�{��d�̌������ɂ́u�������s�O�������a�ܖ����������g���v�Ƃ���B
�@�O�����̌�ɂ͗����Ђ��������B�����Ђ͑����}�_�Ђŗ��_�������u���A���̖T��ɗN�o���門��@��Ə̂��鐴��̎��_�ł���B���̗��͕����ȑO�܂ł͖����_�O��脉��ɋ������Ƃ������Ƃł���B�i������脉��䂩�j
����ɏ�s���̐��ɂ͖��ӓ��ƌ�@�P�_�ЂƔ����Ђ��������B
�@��s�O�����̑O���ɐΊK���~��ƉE���ɓ��ʂ���y�Ђ̔q�a�Ɩ{�a������B�����̖{�a�͉Éi�ɐ���@�̐��a��J�������̂ł���Ƃ����B�����đy�Ђ͌Â��͒k�R�����Ə̂����Ƃ����B
�@���̑y�Ђ̑O�������ɐ��ʂ��Č얀��������B���̌얀���͎Q�q���̗����ɂ����������̌얀�����z���ꂽ��Ɍ��Ă�ꂽ���̂ł��낤�A�����P�a�Ə̂�����A�Ȃ��{��d�𑶂��A�V�䓙���������Ă���B
����Ɉ�i����ƉE���ɋ��ۚ��ł͌䋟�������邯��ǂ��A�����ȑO�Ɍ䋟���͎Q�q�������̍����ɑJ���Ă����悤�ł���B
�@��������і����ɂ��Ă͎��̕���������B
���u�{����������v�V���R�N�i1783�j�D�������������D�����͌��ʎ�@�Ǝv����B��
�@�@�a�B�\�s�S������썑�@�V��@���y��
����@�@���R�O�O�O��
�@���@�P�O�O�O�i�N���s�����E���ЏC�����j
�@�@�@�@�Q�O�O�i���@�@���Ռ䎛���́j
�@�@�@�@�R�O�O�i�w���V�́j
�@�@�@�P�Q�O�O�i�S�Q�V�̎��m�́j
�@�@�@�@�Q�O�O�i�y�����j
�Г�
�@�{�Б�D���喾�_��q�a��
�@��������S�]�_
�@�R����
�@��@�P�_�{
�@�ቤ�q�{
�@���Ёi���J���j
�@�i��J���j
�@�{�Ќ䋟��
����
�@�\�O�d��
�@�u��
�@��s��
�@��
�@�{�蓰
�@�֑�
�@�얀��
�@���O��
�R�ы���
�@�i���j
������O�O�����Ɛ��V�O���]
�������ʉ@���������̂ݗ��A�K�v�ɉ������ׂ����o����
�@�V��@�@������
�@�V��@�@���ى@�i�ޓ]�j
����������
�@�O�u�A�@�V��@�@���W��
�@�@�����l�˓�
�@�@�߉ޓ�
�@�@�V���@�U�����A���ÂP�R�V
�@���@�@�V��@�@���W���i�ޓ]�j
�@���ΎR�@�V��@�@���@��
�@�쉀�R�@�V��@�@���ю�
�@�@�ȏ㑽�����ɔV�L
�@�a�B�L���S�S�Z���@�S�Z���@����a�S�Z��
�@�a�B���s�S���䑺�@�핟���@����a���䒬�핟���i�t�����_�j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�ȏ�
�@�@�@�@�@�@�@������@���s��
�@�@�@�V���R�N�i1783�j�S��
2020/11/07�lj��F���㍀�̑���
�E�_�Ђ̝s���ƏO�k�̊ґ�
�@������͂܂������Ƃ��đn�������B���̌�������Ƃ��č��J�����B�����ېV�܂Ő_�E�͑��݂��Ȃ������̂ł���B
�Ƃ��낪�A�����ېV�̐_�������̗߂ŁA���������y���͐_�ЂƂ���A�O�k�͊ґ��𖽂����A���́E����y�ѕ����W�̏����͏����𖽂�����B
���̐_�������̗߂ɑ��A�����̓�F�������ꂽ���Ƃ͑z���ɓ�͂Ȃ��B�����̎O�_��ł���������@�E�����@�E���o�@�͖��߂̏�����咣���邪�A�����@�E���@�@�E�q���@�Ȃǂ͖��y����O�u�A�Ɍ��Ă邱�Ƃ��咣����B�ꎞ�͔O�u�A�ɕ�������h���D���ł��������A�Ⴂ�A���͑Q���ґ��h�ɌX���A�������̋���ł����������̎R�����V���̔��ɑ����A�O�u�A�ɕ�������Ă͓ڍ�����B�A���A�O�_��E�Ⴂ�A���Ɏv�z�I�w�i����������ł͂Ȃ��B����͑�����ɂ����č��w�͈���ɍs��ꂸ�A�ނ��늿�w�������ł������Ƃ����B
�����Q�N�Q���A�������āA�O�k�͕����ґ����A�Бm�͐_���A�O�j�͐_��ƂȂ�A���͎ЉƂƏ̂��A���d�͐_���ƂȂ�B
�E�������̏���
�@�����V�N�����@�@���{�G�����ޗnj����ɒ�o�����R���L�ɂ�����̋L�ڂ�����B
����a�͖{�ЁA�썑�@�͔q�a�ƂȂ�B
�\�O�d���k�͐_�_�A�u���͐_�_�q���A��s���͘�a�A�얀�����P�a�ƂȂ�A�ȏ�ɕt�����铰�F�͎c������B
�����{�蓰�͊J�R��d�a�������u������A���ɒk�C������������B
�������͏����Ɉ��u�̕���F�������̓��ɉ��ɓ����B�i���͎����ƁX�������A���Ƃ͂Ȃ��j�ꂽ�Ƃ����B�j
���O�͖����V�N���܂ł͊m���ɑ��������A���̚ʂ��ꂽ�͖̂����P�T�N����Ɖ]���Ă���B
�֑��͈��S�����̑����@�̖^���i������͒�����y�^�@��y���Ɣ������Ă���j�֖����P�V�A�W�N���ړ]����ꂽ�Ƃ����B
�Ȃ��A�Бm���d�̎q�@�V�ɂ͂��̂܂ЉƐ_���֗^��������A�������Q�A�R�@�͍r�p�ɋA�����Ƃ������Ƃł���B
�E���̕���̏���
�@�����̕��̂͂�������o�����ɏW�ߒu���A�q�@�̕��͊e�q�@�ɏ����������B���̕��̂́A������ɍ䌧���珈���𖽂��Ă���̂ŁA���{�̕���@�ɂ���Ă��܂��B����@�ł͐��[�ꕧ�낤�Ƃ������A���A�����A�l�V���E���R�n�������_�͐��m�l�ɔ��p�Ƃ����B
�u���ޟ��ϑ��͎���@�������ɉ������ꂽ���A�����ɂ������Ƃ���Q�T�K�̒l�i�ł������̂ŁA�������ю��Ɋ�t����B
�Ȃ��A�e���̂������Βn���͂������菜���B
�@�q�@�ł�����ɕ��̂���������B
����@�i�䎁��̊ω����́u�i�䎁����t�F�m���T�ɓn��A�t�F�m���T���������鎺�����قɈڂ�B�t�F�m���T�ւ̔��p�̎��A�t�F�m���T���ƕ����̂ŁA�T���̂���łT�{�̎w���o�������A�t�F�m���T�͂T�O���Ɖ��߂��A�T�O���Ŕ������v�i�i�䎁�k�j�Ƃ̂��Ƃł���B����͖����Q�Q�A�R�N�̂��Ƃł���B
�����@���������̒n����䶗��͓ޗǂ̑���͂��P�O���Ŕ������Ƃ����B�؏�@�Z�����́u������͂���Ő����ׂ����v�ƌ����Ă����Ƃ����B
�܂��������̒k�ł́u�������`�͂Q�T�{�ňꊇ���Q�T�K�łǂ�ǂ�o�����B�v�Ƃ����Ƃ����B�ꏊ�͏�Z�@�̋q�a�Ŏ�ɉF�ɂ̌Õ����������A����͖����V�W�N�̍��Ƃ����B
����ނ��܂����������B�֑��̈�،o�͋��s������}���ɔ��p�����Ƃ����B���̌o�̔��͔ʎ�@�M���@�Ɏc��Ƃ����B
����͈��ł���B
����Y��̑S�����U�킵���̂ł͂Ȃ��A���_�Ђ̏��L�ƂȂ�A�����̕��`�E�o�T�ނ��c��B����͖{��85-90�y�[�W�ɋL�ڂ����B�i�k�R�_�ЏY��ژ^���̔����j
�ȏ�̂ق��A����̌��{���F��Г��������E�I�����I�Ղ�����B
�Ȃ��A����@���������ɂ͌��̂܂܂Ɏ������E�œa�E���́E����c��Ƃ����B
2020/11/07�lj��F
���u���䒬�j�@���v���䒬�j�Ҏ[�ψ���A1957
�{���̋ߐ��́u�������R�̑g�D�Ǝ��́v�̋L�ڂ́A
�����ނˁA�O�q�́u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j�P����B
�����āA�㑱�́u����s�j�@�㊪�v����s�j�Ҏ[�ψ���A1979�@�Ɉ����p�����B
�@�ېV�O�ɉ�����q�@�̖��̂Ƃ��̔z�u�}�F�M��������
2020/11/07�lj��F
���u����s�j�@�㊪�v����s�j�Ҏ[�ψ���A1979�@���
���ߐ��̑�����
�@�����̍��̋L�q�́A�O�q�́u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j
�y�ѓ������O�q�́u���䒬�j�@���v���䒬�j�Ҏ[�ψ���A1957�@�����~���ɂ��Ă�����́B
�P�j�S�R�J���ƈ�R�̑g�D�E����
�퍑���A��a�̓���͓��䏇�c�̎�Ŏ���ɐi�߂��A�V���P�O�N�i1582�j�ɂ͖L�b�G�g�̖��ɕ����邱�ƂƂȂ�B
�����ɂ͑m�������҈Ђ�U������������R���G�g�ɂ���đ�e������B
�V���P�R�N�i1585�j��R�̋|�E�S�C�Ȃǂ͎c�炸�v���i��a�ɂ����铁��̎n��j�A�O�k�͑ގU�A��R�Ɏc��̂͘V�O�E�s�l�̈ꕔ�݂̂ŁA�̓��̖ʉe�͑S���n�ɗ�����B
���N�A��a�S�R���L�b�G���͑�����̌S�R�J������}���A���s����B
�V���P�S�N�i1586�j�S�R�ɒn���A���P�T�N�Гa���c�A�X�ɗ��P�U�N�S�R��̒���Ƃ��ČS�R�鐼�k���ɑJ������B�Ƃ��낪�A�G���͝������A�����Ί�ď�ԂƂȂ�B
�V���P�W�N�i1590�j�S�R�钆�Ɋ���ȏo�������������A�G�g�̌�������G�����A��D�����M�����A������ւ̋A�R���������ƂƂȂ�B
�������A�S�R�J���̎��A�S�R�ɐV�����V��A�ݏ��Ɉ����Ă����V�傪�����킯�ŁA����ɂ܂��A�R�Ƃ������ƂɂȂ�A���Q�W�̒���������A�ꕔ�̐V���͌S�R�ɋ��c�邱�ƂƂȂ�B���̌�P�O�N�قǁA�S�R�V���ƋA�R���������̑����͑������ƂƂȂ�B
�c���T�N�i1600�j����ƍN�ْ̍�ŁA�S�R�̏@�k���A�R���A�����͎��E����B
�����Ɩ���
�c���T�N�ɍċ����ꂽ������̑S�e�͐��ۂQ�N�i1645�j��㉚��ɂ���đS�e��m�邱�Ƃ��ł���B�����ۑ�����㉚��F��Ɍf�ځ�
�@���ۂV�N������㉚�
�@�ېV�O�̑�����q�@�z�u�}�F�M������������㉚��ɂ��
�ߐ��ɂ����āA�Đ�������R�̐M�̒��S�͏\�O�d���i��d�n���̓��������揊�j�A��{�n�u���i���y���j�A����a�i��D���̐_�������u�A�k�R�����E�k�R���_�j�̎O���ł��邪�A����͈�̐M�ɋA�ꂷ��B�����i��D���j�̐_�Ёi��j��R�̖��A�_���̔j��j�ւ̐M�ł���B
�ʉ@�E�����ɂ��Ď��̂悤�ȏł������B
�匴�̓������͊����̐��a�n�Ƃ��ċ��������̕ʉ@�ł���B���y�@���ʉ@�ł��邪���łɑޓ]�B
�@���������F�������A�����ېV�Ŕp���A���݂͍k��n�ƂȂ�A���n�ɂ͒���ł������匴�Ёi�Ր_�͔����_�j�̂ݎc��B
�O�u�A�̎��W���A���H�̋��@���A�����̐��ю��A���ɑޓ]���Ă������W���͑������ɂ��閖���ł���B
�������̕S�Z���̕S�Z���A���s�S���䑺�̏핟����������̖����ł������B
�@�@�i���@����a�S�Z���A�@����a���䒬�핟���i�t�����_�j�j
�q�@
�V���P�W�N�i1590�j�S�R����A�R�������͂R�Q�V�A�c���T�N�i1600�j�ƍN���ċ��������́A�w���P�O�V��V������藧�āA�S�Q�V�ƂȂ�B
�����ېV�̎��͂R�R�V�Ɍ����Ă���B
�@���S�Q�V�i�q�@�j�̊T�v�E�E���ɂ��Ă͉��Ɍf�ڂ́u���������y���X���ꗗ�v���Q�ƁB
�������S�}�i���ۂV�N�ʁj�F�M����������㉚��ɂ��B
�ېV�O��
������
�c���W�N���얋�{�ɂ���āA����܂ł̎��̂R�O�O�O�����g�����B�ƍN����ɂ͍L���S�R�O�O�O�ƍ��킹�u����O�����ߕӎR�ђ|�v����i�����B
�Ȃ��L���S�R�O�O�O�Ƃ͕S�Z���P�V�R�S�]�A�L�����V�U�U�]�A���X���S�S�Q�]�ł���B�܂���O���͖����E���łł��邪�A���Ɉ�R�̌��p�E�G�p�ɏo�d�����B
�����T�N�i1665�j�̂R�O�O�O�̔z��
�@�a�B������L���S���X�L���S�Z�ԕ��l�������O��Δz���ژ^
�@�@���Q�O�O�@�@�@�@�@�@�@��Վ�����
�@�@���R�O�O�@�@�@�@�@�w����
�@�@���P�T�O�O�@�@�@�@���m��
�@�@���P�T�T�@�@�@�@�@�䋟���
�@�@���P�S�O�@�@�@�@�@�N���s����
�@�@���Q�S�T�@�@�@�@�@����l�������ד��p
�@�@���S�U�O�@�@�@�@�@�C�����@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�s���R�O�O�O��
2025/10/19�lj��F
�Z�u�w���������L�x�È��{���ڂ̍��������N�ɂ��āv���u�c�{�٘_�p�v�R�R���T���A2000�������@���
���������L�F
�@�u���������L�v�͑��������y�����A��������Q���ŁA���v�W�N��ƂȂ��Ă��邪�A�È��{�͓Y��̕M���{����A�E�R�������B
�@�i�ϖ{�͋L��������߂ďڍׂŎj���I���l�������Ƃ����B
������̎l��q�@�F
�@���Z�E�בP�̌���������y�@�́A�㐢�ɕ����@�E��@�E������@�Ƌ��ɁA�R���̎l�吨�͂́\�ł������B
������̖����F
�@������̖������L�����j���͓V���R�N�i1783�j�́u�{���������v�����m���邪�A�����ɂ͋����̖����Ƃ��Ď��W���E���W���E���@���E���ю����A���O�̂���Ƃ��čL���S�S�ώ��A���s�S����핟���������Ă��邪�A�������̎����͂Ȃ��B�������Ƒ�����̖����Ƃ���m���Ȏj���͂Ȃ��悤�ł���B
�������G�}
���u��a���������v�����R�N�i1791�j���@���F
�@����������E�{�ЁE�����F���}�g��}�F�T�C�Y�e��4.8M�F2020/06/24�摜����
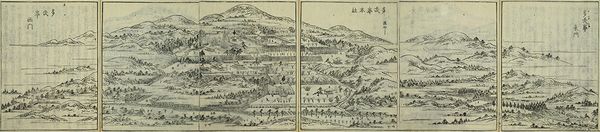
�@�@�@�@�@�@�@�i�Q�l�F�@������\�O�d���i�����}�j �@�@�@�@�@�������S�}�E�E�E�i��������֑O�摜�j�j
2020/06/24�lj��F
���u�����O�\�O��������㉁v�Éi�U�N�i1853�j���@���F
�������{�ЁE���̓��F���}�g��}�F�T�C�Y�e��4.0M
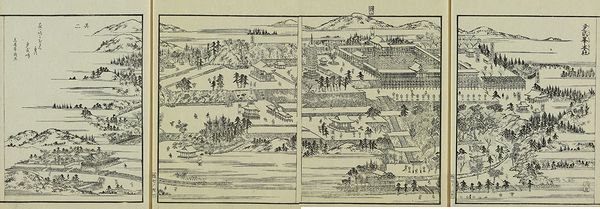
�k�R���y���F�T�C�Y�e��2.0M�@�@�@�@�@�i�k�R�j�����@�@�@�@�@�����l��E���W��
2006/04/07�lj��F
�������t�ōցE��u�������V���v
���u�c���`�m�}���ُ����]�ˎ���̎��Ћ����G�}�v�@���
�@2020/06/24�lj��F�摜����ցi3.9M)�A�{�}�́u�����t�ōցv��ł���B
�@�����t�ōւ͕����U�N(1823)�Ɏ����ł��邩��A�����̐_�������ȑO�́u���������v�ł���B
�@�A���A�}���Ɍf�ڂ̊G�}�̏�Ԃ������̂ŁA���Ɏ����u��������}���فv�ł̎Q�Ƃ��肤�B
�@�@�������V���F�]�ˌ��
2020/06/24�lj��F
�@2020/10/11�lj��E�X�V�B2020/11/07�lj��E�X�V�B
�������t�ōցE��u�������V���v
���I�[�N�V�����o�i�������V��
�@�������V���Q�F�^�I�[�N�V�����ɏo�i����A���ɗ��D�ς݂ƂȂ��Ă������i�i�ʐ^�j�ł���B
���u��������}���فv�ő������V��
�@�������V���R�F�e��3.4M�A��}�Ɠ����u�����t�ōցv��ł���B
�{�}�ɂ��A�]�˖����̑�����̎����i�q�@�j�̑S�e��������̂ŁA���̕\���쐬����B
�@�����Ɍf�ڂ́u���������y���X���ꗗ�v�Ɏ����������i�q�@�j���̂́A���ɒ��߂̂Ȃ����̂́A�{�}�u�������V���v���璊�o�������̂ł���B
2020/06/24�lj��F
�������t�ō���A�l���t���ĉ�u�������V���v�F�ޗnj����}���ّ�
�@�l���t���ĉ�u�������V���v�F�̑����t�ō���A�l���t���ĉ�A���ʓ������ɂ�铺�ł̒k�R�_�Ћ����}�ł���B
�t���َ͖R�̍�������A�����Q�X�N�i1896�N�j��63�Ŏ����B��m�����O�̋��̕W���Ɂu�ʊe�����k�R�_�Ёv�Ƃ���̂ŁA�����V�N12��22���ȍ~�̏o�łł��邱�Ƃ�������B
2020/06/24�lj��F
�����T���^���u�������V���v�F�k�R�_�Б�
�@���T���^���u�������V���v�G�@����T���^���Ƃ���B���T���̖��m�ȗ����͕s�ڂł���B
�A���A�{�}�̌���́u�����t�ōցv�ł���A����͖����ېV�O�ł��낤���A���ʂ̎����͂悭������Ȃ��B
�@��s_minaga�̎茳�ɂ͖{�}�����邪�A�����ǂ��œ��肵���̂��A�S�����A�s���ł���B
2025/09/14�lj��F
���u���������y���@�{�V�v���������y���ҏW�i�O�֎R���������j�A2021�@�ɋL��
�@�����������y���S�i�}�F�{�}�̑f�����悭������Ȃ��B�������ĉE���Ɂu�R�����v�u�����v�����邪�A���Ǐo���Ȃ��B
��������ɁA���ʂ̖��y���ċ��ɍ��킹�A�ߐ����̑������V�}��V���ɖ͎ʂ����u�V��v�ł���̂����m��Ȃ��B
��������
2002/03/28�B�e�F
�@�������O��
�@�������{�a�@�@�@�@�@�������{�a�Q�@�@�@�@�@�������{�a�R�@�@�@�@�@�������{�a�S 2007/08/23�lj��F
���u���{�����ʐ^�}�������v�����F���ЁA�����R�S�N�@���
�@�@�������]���P�@�@
�@�@�@�������]���\�O�d��
���u�ߋE�����v���؏G���Y�A�_�ˁF���ʐ^���ň���A���R�U�N�@���
�@�@������\�O�d���R�P
���u���{�������z�ʐ^���v�֓������Y�ҁA�����F�M�F���A�����S�P�N�@���
�@�@������\�O�d���R�Q
���u�������v�@���
�@�@������\�O�d���R�R
2017/01/11�lj��F
���G�t���Fs_minaga���F�ʐM���̌r�����R���̂P�ł���A���u�����͕֗X�v�Ƃ���̂ŁA����40�N4��〜�吳7�N�i1918�j3���܂ł̂��̂ł��낤�B
�@�k�R�_�Џ\�O�d�V���G�t��
2020/06/28�lj��F
�������2020/05/07�B�e�A�����2020/11/19�lj��u����s�j�@�㊪�v���A�����2021/03/15�B�e�F
�@�V��@���y���͖{���������A�{�����ˉ@�{�a�Ƃ��A�V��̑厛�ɑ��������������\���A���@�g�D�͐@�@��ՁE�w���|�іV�̎x�z�ł���A�����̎����̑m�����njo�E�_���Ă����B���A�����̐_�����R�̗߂ɑ��āA�R���̑Ή��͎��@�Ƃ��đ������邩�A�_�ЂƂ��ĐV���{�ɋ������邩�Ŋ������A���ǂ͖V��ł��邱�Ƃ������Ȃǂ͌��X�Ȃ������ƌ����āA�_�ЂƂ��Đ������т邱�Ƃ�I������B
�������āA�V��͊ґ��E�_���A���y���͔p���E�k�R�_�ЂƂȂ�B
�ܘ_�A�_�����R�̏��u�͌��O�ł͌������A���̖V��ǂ��͌Ќ��𗽂����߁A�����E���`�E����Ȃǂ�O���ŏ��������B�������A���y���ɉ����Ă͎��Ԃ����S�Ɏ��@�ł��������߁A��������菜���A�_�ЂƂ��Ă̊�i�����j�������Ȃ邽�߁A�����͈ꕔ�̂��́i���E���O�E���U�E�얀���j�������A�_�Ђ̎Гa�Ƃ��đ�������Ƃ��ƂƂȂ�B
����͍K�^�Ȃ��Ƃł������B
���Ȃ��A�V��@���y���̉����͐_�������̏��u���o�Ă��A�قڂ��̂܂܌��݂Ɏc���Ă���̂ł���B
�@�����`��
�@�����y�����`���Q�@�@�@�@�@�����y�����`���R�@�@�@�@�@�����y�����P
�@�����y�����Q�@�@�@�@�@�@�@�����l���W�E����
���������y�������F���y���썑�@�̑y��ł���B�J�̓������؍ōǂ��A���̂��k���ɍ����Ɛ��˂�������������\����B
�K�͍͂����̊Ԍ��S�D�U�T���A�����U�D�Q�T���Ŗ؍̗��[�̒������P�X���ɂȂ�B�����N��͕s���ł��邪�A���ϐ��ɋ��a�R�N(1803)�̖n��������Ƃ����B
�u���̓���������ē��v�吳�P�P�N�F���`����n��A�،��e�E�����e�ŁA�e���甼������ŕ\��̎�O�ɐ�������B���̍��T�Ɂu���l���]���ܒ��v�ƍ������W������B
�Ƃ�����A�e�E�W�Ȃǂ͖����B
�@���������y�������P�@�@�@�@�@���������y�������Q�@�@�@�@�@���������y�������R
�@�����y�������S�@�@�@�@�@�����y�������T�@�@�@�@�@�����y�������U�@�@�@�@�@�����y�������V
�@����剺����F�����@�e���i�����V�c��T�c�q�j�M�Ƃ����B�����ɂ��������������B�w��̐Ί_�͋����@�Ղł��낤�B
�@�����y������Q�@�@�@�@�@�����y������R
�@���O���̓��e�ɁA�u���l�����v�ƒ���ꂽ�Δ肪�����Ă���Ƃ����B
�@���l���F���݂͑ޓ]�Ƃ����B
�@�@������Îʐ^
�@�@�@�F�����͏��a�S�S�N�ɔ���̏C���A�����Q�U�N�ɕۑ��C�����s���B
�@�@�@�@�u���̓���������ē��v�吳�P�P�N�@���F�k�R�_�Г����
�@�@�@�@�o���s���G�t���F��a�����������@�@�@�@�@�@�@�����������
�@
�@���y������֓��F�d���F����3.15���A�ԛ���B�����Q�N�i1303�j���N�I������B�����ېV�̎��A�����̈╨�Ƃ��ēy���ɖ��߂��Ă������A���a�S�O�N�キ�炢�ł��낤���A�@��N�����A���n�Ɍ��Ă��Ƃ����B�T��ɋ�������B
�@���y�������F�����F�����͋��̂���ł��������A����͒��̈�ł���B���͖����B
�@�����y������֓��E����
����傩�琼���Ɏ��鑽�����J�ɂ͎Q�����ʂ�A�Q����k�ɂ͖��y�������Ƒ����̖V�ɐՂ̐Ί_�E���R�n���c��A�ꕔ�ɂ͖V�ɂ̈�\���c������B
���̖V�ɐՋy�ш�\�͉��Ɍf�ڂ���u�����X���v�̕\���Ɍf�ڂ���̂ŁA�Q�Ƃ���B
�@���Ă̒ҐΓ��ĂP�@�@�@�@�@���Ă̒ҐΓ��ĂQ�F���ˉ@�Ɏ���ΊK�̍ʼn��i�ɑ����̐Γ��U�����ԁB
�@�����U�̒ҐΓ��U�R
�@����V�c��i�Γ����F�d���F�����R�N�i1331�j�̔N�I�����ނƂ����B���Ă̒҂ɂ���B
���y�����̓��F
�X�C���i�����s�䓙�j�\�O�d�Γ��Ɠ`����B�ߔN�܂ŕ��U�����Ă������A���̌㕜������A�Q�������������B
��d����ւ̒���܂Ŗ�4.79���A���`��̍����T�U�����A���X�Q�����ŁA��ɂ́u�i�m�U�N�i1298�j�v�u��H��s���v�ƍ�����B
�@�����y�����̓��P�@�@�@�@�@�����y�����̓��Q�@�@�@�@�@�����y�����̓��R�@�@�@�@�@�����y�����̓��S
�@�����y�����̓��T�@�@�@�@�@�����y�����̓��U
�@���ˉ@�ΊK�P�@�@�@�@�@���ˉ@�ΊK�Q�F�����낵���ΊK�A�ʂ钹���͓�̒����ł���B
�@�����y����̒���
���y���֑�
�֑��͌��������A���̐Ւn�݂̂��c���B
�������Ȃ���A���̏����̂ŒNjL����B�i2021/02/23�j
�u�֑��͐_�������̏��u�ŁA�����s������y���{���Ƃ��āA�ړ]�E���z���ꌻ������B�v
�@�@�@���{�y�[�W�̉��i�u����̌��z��\���R�j�����̐_�������̏��u�ɂ��֑���\�v�̍��ɋL�ڂ���B
�@�@�@�@�@�i�uCtrl�v�L�[+�uF�v�L�[�Ō����𐿂��j
�@�@�@��2025/09/1�S�lj��F���@�������֑��F������y���{���@�Ɍf�ڂ���B
�@���y�����U���F�����ɓy�d�l�̈�\���ʂ邪�A���U�ՂƎv����B�i���m�F�j
�@�����y���֑��ՂQ�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂR�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂS�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂT�@�@�@�@�@�����y���֑��ՂU
�@�����y���֑��ՂV
�@�]�֑��̎��i���S�b�j�F
�@�@���֑����S�b�P�@�@�@�@�@���֑����S�b�Q�@�@�@�@�@���֑����S�b�R
�@�u�ޗnj����S���v�F�����̐_�������̏��u�Ŏ�蕥����B���͑s��Ȃ錚���ŁA��،o��[�ߕ��������u���B
�@���͗B�b�̂ݑ�����B����Ǐ�ɂ͉��O���̖��c����Ƃǂނ�E�E�E�@�Ƃ���B
�����͓����̕~�n���m�ۂ��邽�߁A��̒J����k�̎R��ɋ���オ��`�ŐΊ_��z���A���R�n���m�ۂ���B
�@���y�������Ί_�P�@�@�@�@�@���y�������Ί_�Q�@�@�@�@�@���y�������Ί_�R�@�@�@�@�@���y�������Ί_�S
���ˉ@
�@�����y���{�ЎГa���ʐ}
���y�����ˉ@�i���{�a�j�F�d���F��N�i701�j�̑n���A���݂̓��͉Éi�R�N�i1850�j�̑��ցA�O�ԎЋ��ؓ��t�����A�����w�畘�B
�@���y�����ˉ@�{�a�P�P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�Q�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�R�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�S
�@���y�����ˉ@�{�a�P�T�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�U�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�V�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�P�W
�@���y�����ˉ@�{�a�P�X�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�Q�O�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�{�a�Q�P
�@�����y������a�{�ЂR�P�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�Q�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�R�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�S
�@�����y������a�{�ЂR�T�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�U�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�V�@�@�@�@�����y������a�{�ЂR�W
�@�����y������a�{�ЂR�X�@�@�@�@�����y������a�{�ЂS�O
���y�����ˉ@�q�a�E�O��E���L
���y�����ˉ@�q�a�F�d���F�i���P�V�N�i1520�j�̑��c�A�����i���s�P�ԁE���ԂR�ԁj�A��d�A���ꉮ���E�ȓ��A�O�㌬���j���t�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���E�ˏo���i���s�T�ԁE���ԂR�ԁj�A��d�A���[���ꉮ���A������������w�畘�B
�@���y�����ˉ@�q�a�P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�Q�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�R�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�S
�@���y�����ˉ@�q�a�T�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�q�a�U�@�@�@�@�@���ˉ@�q�a�V��P�@�@�@�@�@�@���ˉ@�q�a�V��Q
�@���ˉ@�q�a�������@�@�@�@�@�@���ˉ@�q�a�O�Γ��U
�@�����y������a�q�a�P�P�@�@�@�@�����y������a�q�a�P�Q�@�@�@�@�����y������a�q�a富��@�@�@�@�����y������a�q�a�V��
���y�����ˉ@�O��F�d���F�i���P�V�N�i1520�j�����A�O�Ԉ�˘O��A���ꉮ���A�����w�畘�B
�@���y�����ˉ@�O��P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�O��Q�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�O��R�@�@�@�@�@���y�����ˉ@�O��S
�@�����y������a�O��P�P�@�@�@�@�����y������a�O��P�Q�@�@�@�@�����y������a�O��P�R�@�@�@�@�����y������a�O��P�S
�@�����y������a�O��P�T�@�@�@�@�����y������a�O��P�U
���y�����ˉ@���L�F�d���F�i���P�V�N�i1520�j�����A���s�S�ԁE���ԂR�ԁA��d�A���ʓ��j�����A���ʓ��ꉮ���A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��ʐ܋Ȃ蕔�͌��s�T�ԁE���ԂQ�ԁA��d�A�������A������������w�畘�B
�@���y�����ˉ@���L�P�@�@�@�@�@���y�����ˉ@���L�Q
�@�����y������a�����P�P�@�@�@�@�����y������a�����P�Q�@�@�@�@�����y������a�����P�R�@�@�@�@�����y������a�����P�S
���y����s�O�����i�����a�j�F�d���F�������i�i���N�ԁj�ɍČ��A�T�ԁ~�T�ԁA���ꉮ���A�ȓ���A�����w�畘�B
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�V�\���N�i970�j�A�n���A�ې��E��b�����ɛ��i���ꂽ���j�̔���ɂ��B����@�S������ɑ������u�B
�����y����s�O�������ʐ}
�@���y����s�O�����P�@�@�@�@�@���y����s�O�����Q�@�@�@�@�@���y����s�O�����R�@�@�@�@�@���y����s�O�����S
�@���y����s�O�����T�@�@�@�@�@���y����s�O�����U�@�@�@�@�@���y����s�O�����V�@�@�@�@�@���y����s�O�����W
�@���y����s�O�����X
�@�����y����s�O�����P�P�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�Q�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�R�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�S
�@�����y����s�O�����P�T�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�U�@�@�@�@�@�����y����s�O�����P�V
���y���u���i���V�_�q���j�F�d���F���P�W�N�i679�j��d���������������{�̂��߂ɑn���A���y���̍u���ł���B
�@�@�@�@�@�@�@�����W�N�i1668�j�Č��B�T�ԁ~�H�ԁA���ꉮ���A�����w�畘�B
�����y���u�����ʐ}�F�Ȃ��{���͌��݈��{�̕���@�{���Ɉڂ���Ă���B
�@���y���u���P�@�@�@�@�@���y���u���Q�@�@�@�@�@���y���u���R�@�@�@�@�@���y���u���S�@�@�@�@�@���y���u���T
�@���y���u���U
�@�����y���u���P�P�@�@�@�@�@�����y���u���P�Q�@�@�@�@�@�����y���u���P�R�@�@�@�@�@�����y���u���P�S
�Ȃ��A
�u���{����Z�ގO�����͖����̐_�������ŁA���{����@�ɑJ����A��������B
�����́A�{�y�[�W�̉��Ɍf�ڂ���B
�@�@�@���@���@���y���u���{���߉ގO�����^�n����F�O�����@��
���y���{�蓰�i�����a�E��{�j�F�d���F���a���ւ��̐��ˉ@�{�a�������W�N�i1868�j�Ɉڒz�������̂ł���B�O�ԎЏt�����A�����w�畘�B
�@�@�@�@�Ȃ��A�{�蓰�̓��ɂ͟��A��ɂ͏��O���������i�G�}�j���A�����͐_�������őޓ]���H�B
�@���y���{�蓰�P�P�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�Q�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�R�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�S�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�T
�@���y���{�蓰�P�U�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�V�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�W�@�@�@�@�@���y���{�蓰�P�X�@�@�@�@�@���y���{�蓰�Q�O
�@�����y���{�蓰�Q�P�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�Q�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�R�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�S�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�T
�@�����y���{�蓰�Q�U�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�V�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�W�@�@�@�@�����y���{�蓰�Q�X�@�@�@�@�����y���{�蓰�R�O
���y������ɁF�d���F���a5�N�i1619�j���c�A�Z�q��
�@���y������ɂP�@�@�@�@�@���y������ɂQ�@�@�@�@�@������ɂR
�@�����y������ɂS
�@�i���y���j�ω����F�ڍוs��
�@2020/11/19�lj��F�u����s�j�㊪�v�F
�@�{���ؑ��@�ӗ֊ω������i������U�P�����j���J�������ʂ��鑽����ω������ŋߗL�u�ɂ���ē��a�̓����ɐV�z�����B
�@���i���y���j�ω����Q
�O�V���
�F��_�A�V���V�_�i�������^�j�A�s�n���P�i�ٍ��V�j���J��B�ω��������炳���250�����ɓ��������ɂ���B
�R���͕�����Ȃ����A�O�V�ЂƂ��ď\�O�d���̔w��ɒ������Ă������A���������Ɍ��ݒn�Ɉړ]�Ƃ����B
�@�������t�ō���A�l���t���ĉ�u�������V���v�F�ޗnj����}���ّ��@�@�ł͏\�O�d���̔w��Ɂu�O�V�Ёv���`����Ă���B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�����y���O�V��ׂP�@�@�@�@�@�����y���O�V��ׂQ
���y������ɁF�d���F���a5�N�i1619�j���c�A�Z�q��
�@���y������ɂP�@�@�@�@�@���y������ɂQ�@�@�@�@�@���y������ɂR
�@�����y������ɂS�@�@�@�@�����y������ɂT
���y������R�������F�d���F��ԎЗ����A�璹�j���y�ь����j���t�݁A�����O�畘�A���i�S�N�i1627�j�����A�̑匴�ɂ������匴�{���ڒz�Ƃ����B�Ȃ��A�匴�Ƃ͊������a�̒n�Ƃ�����Ƃ���ŁA���݂��匴�_�Ђ�����B�匴�{�Ƃ͂����炭���̒n�ł��낤�B
�@���y���R�������P�@�@�@�@�@���y���R�������Q�@�@�@�@�@���y���R�������R�@�@�@�@�@���y���R�������S
�@���y���R�������T�@�@�@�@�@���y���R�������U
�@�����y���R�������P�P�@�@�@�@�����y���R�������P�Q�@�@�@�@�����y���R�������P�R�@�@�@�@�����y���R�������P�S
���y��脉��䉮�F�d���F���a�T�N�i1619�j�̌����A����杮���B
�@���y��脉��䉮�P�@�@�@�@�@���y��脉��䉮�Q�@�@�@�@�@���y��脉��䉮�R
�@�����y��脉���S
���y���y�Ж{�a�F�d���F�n���͉����S�N�i926�j�̊����ɂ����̂Ƃ����B���݂̖{�a�͊����W�N�i1668�j���ւ̐��ˉ@�{�a�����ۂQ�N�i1742�j�Ɉڒz�������̂ł���B
�@���y���y�Ж{�a�P�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�Q�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�R�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�S
�@���y���y�Ж{�a�T�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�U�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�V�@�@�@�@�@���y���y�Ж{�a�W
�@�����y�����Ж{�a�P�P�@�@�@�@�����y�����Ж{�a�P�Q�@�@�@�@�����y�����Ж{�a�P�R
���y���y�Дq�a�F�d���F�����W�N�i1668�j�̌����A���ˉ@�q�a���k�����ȗ��������l���ł���A���ʁE�w�ʂƂ��ɓ��j�������B
�@���y���y�Дq�a�P�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�Q�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�R�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�S
�@���y���y�Дq�a�T�@�@�@�@�@���y���y�Дq�a�U
�@�����y�����Дq�a�P�P�@�@�@�@�����y�����Дq�a�P�Q�@�@�@�@�����y�����Дq�a�P�R
���y���얀���F�_��������̊G�}�ł́u�P�a�v�ƋL����Ă��邪�A�������Ȃ��B
�r�_�R�F�{�Ђƌk�������ĂđΛ����A���̒����͒��]��i�Ȃ�B�ېV�O�܂ł͍r�_�̎Ђ��������B
���Ă̖T�����ɓo�邱�ƂQ���]�ɂ��ė�ɒB����B
�@�������j��R�P�@�@�@�@�@�������j��R�Q�@�@�@�@�@�������j��R�R
��j��R���ɕ����P�U�N�Ɍ������ꂽ�u��v�̓����Ƒ�ڌܗΓ�������B
�@��j��R�����ƌܗ֓��P�F���ʁF�{�唪�i�^��ځ^��s���`�@�ƍ��݁A�ԗ��ɂ͓����Ƃƍ��ށB
�@��j��R�����ƌܗ֓��Q�F�����ʁF�ד����Ɛ�c��X�ǑP���V��ʁ@�ƍ��ށB
�@�@�E���ʁF����������^������������^�����s�䓙��^����������@�̎l���̐��������ށA���������Ƃ͕s���B
�@�@�w�ʁF�����@���āi�ԉ��j�@�����P�U�N�P�O���g�������^�{��@�����j���@�������q�i�����j�E�E�E�����������@�̐��͕s�m���B
�@�������ƂƂ��芙���Ȃǂ��˂��J��Ǝv����̂ŁA������J�R�ł��铡�����ꑰ���J��̂ł��낤�B
�@�����炭�����@���Ă������������̂Ǝv���邪�A�����@���ĂƂ͕s���A�{�唪�i�Ƃ���̂Ŗ{�嗬�̑m���ł��낤�B
�@���ɂ��铡���ƂƂ����͓̂������̖{���Ȃ̂ł��낤���A��j��R�Ƃ͐��n�ł��낤���A�Ȃ����̐��n�̈��ɋ��{���̌�����
�@�������̂ł��낤���A�������Ȃ��A�@�؏@�{�嗬�i�����嗬�E���i�h�j�Ǝv���鋟�{���Ȃ̂ł��낤���A��͑����B
�@�������k�R�F�i�����炢��܁j�F�����Ȃǂ��A�d������ꏊ�Ƃ����B
���ꓰ�ՁF�����@���ɂ���B�]�ˊ��̊G�}�ɂ͑��ꓰ�̋L�ڂ͂Ȃ��̂ŁA���Ƃ�肱���ɂ������̂��ǂ����͕�����Ȃ��B
�u�֗]�E�������̓��v�ł͎��̂悤�ɉ]���B
���ꓰ�ɂ͑����l���Ɠ������u����B�����l���͑����S�T�����j�͍]�ˊ��̍�ŁA�͂��ߔO�x���̔O�����ɂ��������A���䗈�}���Ɉڂ�A���̌�]�X�Ƃ��Ă������A�L�u�̐l�X�ɂ���Ė����R�U�N�����ċ�����A�����Ɉ��u�����B
���ꓰ���u�̖�t�@�������͍]�ˊ��̉���ł���A�ʎ�@���J���B
���ꓰ�{������ɔ@�������i�����T�Q�����j�͖����R�U�N���ꓰ�Č��ɍۂ��A�����@���J���B
���̌����ɂ͌Ï���݂邷�B����͂��ƔO�u�A�̌o���ɂ��������̂ŁA�����R�N�i1323�j�����̗z��������A���i�Q�R�N�i1416�j���A���i�ǖ��j������Ƃ����B
�A���A���ݑ��ꓰ�͑ޓ]���O���̍s���͕s���B�i�����l�����͒k�R�_�Б��Ƃ����B�j
���u�ޗnj����S���v�吳�S�N�F���O�u�A�Ȃ�o���ɑ����l���͂��肵���A���͈ڂ�č��䗈�}���̈ʔv���ƂȂ�i���͗��}���ʔv���͑ޓ]�j�ؑ��͓]���Ĉꎞ���l�̎�ɂ��肵���A�����R�U�N�L�u�҂����̓����������ĕ��A������Ȃ�B
���a52�N���ł́u�֗]�E������̓��v�ɑ��ꓰ�̎ʐ^������̂ŁA���ɓ]�ڂ���B
�@�@�@���݂肵���̑��ꓰ
�@���ꓰ�ՂP�@�@�@�@�@���ꓰ�ՂQ�@�@�@�@�@���ꓰ�ՂR�F���ꓰ�O�ɂ��邪�A���Ǐo�����B
�@�����y�����ꓰ�ՂS�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂT�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂU�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂV�@�@�@�@�����y�����ꓰ�ՂW
������
�@���������y�������P�@�@�@�@�@�@���������y�������Q�@�@�@�@�@���������y�������R
�@���y������剺����F�����@�e���i�����V�c��T�c�q�j�M�Ƃ����B�����ɂ��������������B
�@���ӐΑ��F�����Ղɂ���A���i�R�N�i1266�j��������B�@�@�@�@�@�����ՐΓ��U
�@����受�l���Β��F��������ߐ��A������ł͏��l�̗���������ւ��Ă����A���̌Ð��������Β��ł���B
���O�u�A
2020/06/24�lj��F
���u�����O�\�O��������㉁v�Éi�U�N�i1853�j���@���F
�@�����l��E���W���F���W���ɂ͎R��E���O�E��s����������A�w��ɂ͑����l�_������B
�@���W��/�����l���ܗ֓��F���W���̎R��ɂ��菬���̓��Ɍܗւ̐Γ�����@�Ƃ���B
�@�ܗΓ��ɂ́u��E���E���E��E��l�v�ƍ��݁A���ۂQ�N�U���X���̏�l�̎�������ށB
�@���ɏq�ׂ�悤�ɁA���̌ܗ֓��͌��ݒn�ւ̂�������B�_���͑ޓ]�����݂͂Ȃ��B
�@�O�u�A�̐Ί_�P
�@�O�u�A�̐Ί_�Q�F���W���֎��铹�̘e�ɋ���ȐΊ_���Q������A������O�u�A�̖V�ɐՂł��낤���B
�@�O�u�A���W���ՂP�F�����E�̐Δ�́u�吼�njc�a�����a�n�V�n�v�̐Δ�ł���A
�@�a���͑�����ɐ��܂�A���̒n�ɂ͑吼�Ƃ̕悪����ȂǂƋL���B
�@�O�u�A���W���ՂQ�@�@�@�@�@�O�u�A���W���ՂR�F�n���Ε��͍O���S�N�i1558)�A����ɐΕ��͓V���P�P�N�i1583)�̍���������B
�@�����l������F���W���Ղɂ��̔肪���B
�����l���F�ΊK�͂P�T�O�i�A���`�Q�d�̐Βd�̏�ɍX�ɂQ�d�ɐςݏグ��ꂽ�̉~�˂Łv����B���i�̌a�͂S���A�����P�D�P���A��i�̌a�Q�D�R���A�����V�V�����B���͂ɐΑg������A�S�D�Q�S���l���̕��������������̂Ǝv����B�u���������L�v�ɂ͌ܗ֓������Ƃ���B���݂͌ܗ֓��̒n�ւ݂̂�����Ɏc��B�n�ւɎc��N�I�̒��ۂT�N�i1003�j�͏�l�̎�N�A�c���V�N�i1602�j�͐ΒˁE�ܗ֓���V���ɑ��������ł��낤�B���W���͑����l�̗�_�ł������Ƃ����B
�@�����l���ΊK�P�@�@�@�@�@�����l���ΊK�Q�@�@�@�@�@�����l���ΊK�R
�@�����l���P�@�@�@�@�@�@�@�@�����l���Q�@�@�@�@�@�@�@�@�����l���R
�@�����a���ܔ����F�����P�O�N�i1798�j�̔N�I������B�@�����A�n���@�W���̌����B
�@�O�u�A���Q�P�@�@�@�@�@�O�u�A���Q�P
�@�O�u�A���{�ƕ���F�������ĉE�ɐ��{�ƂƂ���̂ŁA���@�@�̕揊�Ɛ��肳���B
�@�瑠�@��X�ƕ���F���U�@�͊ґ����A��X���ƂȂ����Ɛ��肳���B
�@�����@�ق������P�@�@�@�@�@�����@�ق������Q�@�@�@�@�@�����@�ق������R
�@�������@�̕揊�Ǝv����B����@�Ƃ͕s�ځB
2020/06/28�lj��F
���ޗǐV���F2009.04.23�L���F�u���ɂ݂鑽�������� - �k�R�_�Ђő��������v�@���
�y�T�v�͈ȉ��̒ʂ�z
�@������Ɏc��m���̕��Q������s����ψ�����������A�蕶��傫���������ׂ��B
�@��b�R���疭�y���ɉ����������l(����P�V�N/917�\���ۂT�N/1003)�̒˂𒆐S�ɖ�800��̕�肪�W���A�O�u���ƌĂ�Ă���B
�@�s���ς͍�N10���ɒ������J�n�B���܂ꂽ���O�▽���A�������V�[�g�ɋL�����A�`���P�Q��ނɕ��ނ����B
�ł��Â��͓̂V���N��(1532�\1554�N)�ŁA�P�V���I��̕悪���������B�����ōō��ʂ̌��Z�E�̕������A�L�^�ƑΏƂ��邱�ƂŁA�����̋߂���Ƃ����B
�@�O�u���ɂ͊ҍ��ȍ~�̕�肪�����A����ȑO�̕��͘e�ɂ悯��Ȃǂ��Đ�������Ă����B
�@�]�ˎ���ɂ͈�R�̓����҂Ƃ��Ċw���E���u���ꂽ���A�u�w���v�ƍ��܂ꂽ���͊m�F����Ȃ������B
�@�����l�̒�(���5.8���[�g��)�����ӂ@�����A3�����v�����s�������A�z�����������ł��鎑���͌�����Ȃ������B
�����������y������
�����������y���X���ꗗ
|
������ |
���@�@�l |
|
���ߐ��̐E���i�h�A�i�j
�����i�@�@��Ռ��сE���Z�j�@�\�@�w���i�Z�V�͒|�іV�E���Z�j�@�\�@���s��i���~�͏�Z�@�A�Q�������ԂŋΖ��j�@�\�@���Z�i�����j�@�\�@�O�j�@�\�@���m�i�Бm�j
�@�����Z�͒����ł͍���Ɏ����A�������R�̎x�z�҂ł��������A�c���̍ċ��ȍ~�E�ߐ��ł͎��s��̉��ɑ����A���@���ɂ͓��t�A�_���ɂ͐_��ƂȂ�B
�@���O�j�F���Z�̉��ɂ���A�@���E�_����S������B�q�@���̈����E�����E�O�����₳���B
���_��������̗뗎�i�h�G�u������̐_�ŕ����v�@���j
�@�@���u������̐_�ŕ����v�͑吳�P�T�N�����I���B
�����Q�N�Q�������ґ��ƂƂ��ɎБm�͐_��E�ЉƂɕ₹���A���d�͐_���ɔC�����A�З̂̔z�����A�]�T�̂��鐶�������Ă����B
�����S�N�V���_�И\�������A�З̖̂v���i��n�j����������B
�ڍׂȌo�܂͎������Ȃ��A�s���ł��邪�A��n�̌�A�����A�ЉƁE�_���͍����Ɋׂ�B�����T�N�̑�����В��A���́u�Q�菑�v�Ɏ������ʂ�ł���B
���̊ԕ��́E����̑��̍��Y�̔��p�ō����𗽂������Ƃ��A�z�����B�S�Q�V�̎Бm�X�V�̏��d�͕�������ɂQ�A�R�͑ޓ]���A�����P�T�N���ɂ͂��̑唼�͖����Ȃ�A�S�R�E����ɏo�čs�����Ƃ������Ƃł���B�ދ��̐l�X�����V�ɂp���ċ��������Ƃ͌���ւ��Ȃ��B
�������āA���ݎR��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B
�����Ď����@�i�R�c�j�A�����@�i����j�A��S�@�i���{�j�̂R�Ƃ͔p��Ƃ����B�Ȃ��A�����̏Z�@�E��Z�@�͌��݊w�Z�̕~�n�ƂȂ�B
�@�������Ĉ�R�͕����̉e��f������A�B�ꑝ�ꓰ���ċ������o�������ŋ��I�L���̂�����̂ł������B
���ꓰ�{���͑����l���͖����P�S�A�T�N���R���o�āA�s�����s���ł��������A����̌Õ����̋��ɂ��邱�Ƃ��������A�����R�U�A�V�N����������Ԃ��A���ꓰ���Č����A�����l�������u����B |
|
| ��������E�葤�i�k���j�̖V�� |
|
|
|
�i����j |
|
|
| |
�����@ |
�e
�h�F�M���������u������㉚��v�ɂ͋L�ڂ���A�����ȑO�ɑޓ]�� |
|
| |
����@�i�����j |
A�F�������A�h�h
�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł���A�_�������̏�����咣����B
B�F2019�N�������u�o�^�L�`�������v�ւ̓o�^
����@�q�a�y�ьɗ��F�������Z��
����@�q�a�y�ьɗ��i�������Z��j�͍]�˒����̌��݂Ɠ`���B�����Q�N�̐_�������̔j��ŏZ�E�͊ґ��ЉƂƂȂ�B�؍ȑ��V�����A���̌ɗ��𗎂����Ƃ��l���ɉ������B���@�̏�lj�i�l���ɂ킽���ĕ`����Ă��鉦�G�G�j�́A���a�S�X�N�ɏd�v�������Ɏw�肳��A
�ޗǍ��������قɊ������Ă���B
�h�F����@���������ɂ͌��̂܂܂Ɏ������E�œa�E���́E����c��Ƃ����B
�h�F�u���ޟ��ϑ��͎���@�������ɉ������ꂽ���A�����ɂ������Ƃ���Q�T�K�̒l�i�ł������̂ŁA�������ю��Ɋ�t����B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B
�i�F��lj�R�V�ʁi�d���A���{���F�j�͕��N�i1751�j���@�Ő��삳���B
�i�F�]�ˑO���̒뉀���c��B
�@����@���@
|
|
| |
�P���@�i�����j |
�h�h |
|
| |
�i�����j |
|
|
| ���傩��̎Q���쑤�̖V�� |
|
|
| |
�q���@�i�吼�j |
A�F�������E�������̑吼�njc�̕��̏o�g���@�A�h�h
�h�F����@�E���@�@�E�q���@�����ېV���������ɔ����A�O�u�A�ɕʗ����邱�Ƃ��咣����B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |
|
| |
�i����֓��j |
|
|
| |
�\�@�@ |
�h�F�M���������u������㉚��v�ɂ͋L�ڂ���A�����ȑO�ɑޓ]�� |
|
| |
���S�@�i�K�c�j |
�h�h |
|
| |
���{�@���������� |
���{�@�������{����ɍ����͍���s���a�Ɋy���ɑJ������������B�i�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv�j
�h�FJ�F�������ł���A�s�������̍s��ꂽ�Ƃ���ŁA�n���̔z���͂Ȃ��B |
|
|
��Z�@�������� |
A
C�F����s���w�蕶�����i�s�w��j
�����y���q�@�@��Z�@�̕\��i������j�A�k�R�_�ЁA������478-1
�@���������w�Z������Ƃ����L��������̂ŁA��Z�@�͏��w�Z�ɓ]�p���ꂽ���̂Ǝv����B
�d�F�����͎��s�㉮�~�Ƃ��A��Z�@�ՂƂ����B���݁A���c�����[�X�z�X�e�����J�݂���Ă���B
���F�i���j��쎛�Ќ��z���H�����с����̑��̖ؑ����z�����������w�Z������
�@����s���L�B���s�܊ԁA���ԓ�ԁA���ꉮ����{�����B2011�N�C�U�H���B
���Ɩ��y���̎q�@�A�퉝�@�̒�����B�����ȍ~�ɑ����w�Z�̕\��Ƃ���Ă����B�S���ɖ��a�S�N(1967)�̖�������B
J�F�����̏Z�@�ŁA��ʂ̎q�@�̂悤�Ɏt�푊���ł͂Ȃ�����A�n���i���́j�̔z���͂Ȃ��B
�i���s�㉮�~�ƌĂ��j�Ƃ̂��ƁB���s��͊w���ɑ���Ĉ�R�̓����ɂ�����B����Q�l�łS�Q�̎q�@����I���ɂ���đI���B��R�̐����E�o�ρE�O���̎��ۂɓ�����B���s��͌��Ԍ��Ŏ�������B
�i��Z�@�͈����ŁA���s�㉮�~�ł���A���s�オ�l�߂Ă����̂ł��낤�B�j
�h�F�吳�����ɂ������B
|
|
|
�ʐ�@�i�R�{�j |
�h�h
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |
|
| |
���@�@�i�c���j |
�h�h
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |
|
| |
�S��@�i�����j |
�h�h
�h�F�����Q�N�́u�l�ʌ�����ʁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��i���Z���j |
|
| |
�����@�i���ҁj |
�h�h |
|
| |
�ύs�@�i�����j |
�h�h |
|
| |
�ʎ�@�i�D���j |
�h�h
�d�F���ꓰ���u�̖�t�@�������͍]�ˊ��̉���ł���A�ʎ�@���J���B�A���A���ݑ��ꓰ�͑ޓ]�������̍s���͕s���B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |
|
| |
�����@�i�i��j |
�h�h
�h�F����@�i�䎁��̊ω����́u�i�䎁����t�F�m���T�ɓn��A�t�F�m���T���������鎺�����قɈڂ�B�t�F�m���T�ւ̔��p�̎��A�t�F�m���T���ƕ����̂ŁA�T���̂���łT�{�̎w���o�������A�t�F�m���T�͂T�O���Ɖ��߂��A�T�O���Ŕ������v�i�i�䎁�k�j�Ƃ̂��Ƃł���B����͖����Q�Q�A�R�N�̂��Ƃł���B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |
|
|
�i�r�_�Ёj |
|
|
| ���y�����������琼��ɂ����Ă̓쑤�V�� |
|
|
|
�\���V�i�g���j |
A�A�h�h
D�F����@�Ɍ����Ă��鑽����ό��z�e���̖����������u�`�o��v�ŁA���̗R�������������̂��H��ɓY�����Ă����B�i���̓`���ɂ��āj�A��Œ��ׂ���w��ȋ��x�ɍڂ��Ă��鎖���킩�����B�����Ƃ���@�̏\���V�������A�`�o��̂悤�Ɍ�ނ̓��i���،{�����j�ł��ĂȂ����Ƃ͂�������Ă��Ȃ��B
�@�u��ȋ��v�������N�i1185�j�\�ꌎ������h�N
�g��R�[�_�@���B���B������@�����B��ਁ@�F�@����D����e�@�]�X�B
�����V���ҁA��@�������A���V��@�\���V�g���B�V���m��B�㘬�B�A�܁A�]�X�B
�@����@���������\���V�ƍ��������Ƃ�������B |
|
|
���o�@�i����j |
A�A�h�h
�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł���A�_�������̏�����咣����B
�A���A�����R�N�_�劋��r���͐������A��C�ɎO���@���^�����₹����B |
|
| |
�w���E�|�щ@ |
�e
G�F�E����A�V��@�@�@��Ղ��b�R�����������y�������錚�O�ł��������A���ۂ͈�R�̊w���̏�ɗ��w������R���x�z�����B�����Ċw���̉��ɎO�j�������B
���u�ޗnj����S���v�F�䗷���i���N�S���P�U���̎��ՂŐ_�`�̎���|�j�͊w���|�іV�̈�Ձi�w�����~�j�Ȃ�B
J�F�ƍN�̖��œV�C�̍��팫���̊J��A��X�b�R���猓�Z�A��ɂ͓��b�R����̗֔Ԃł������B
�w���͎����̉��ɂ��邪�A������͈�R�̓����҂ł���B�P�X�㎜��͋v�\�R���c����]����B�����ېV�܂Ŋw���E�͂Q�U�㑱���B�A���A�w���͏�Z�ł͂Ȃ��B
|
|
| |
�����@ |
���Ɍf�ڂ́u���̑��̉@�v�̍����Q�ƁA�܂���L�̏\���V���Q�ƁB |
|
| |
����@�i����j |
�h�h |
|
| |
�������i�����j |
|
|
| |
���ω@�i���j |
�h�h |
|
| |
�O�U�@�i���j |
�h�h
�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł��������A�����R�N�_�劋��r���͐������A��C�ɎO���@���^�����₹����B |
|
|
�S�։@�i�g�c�j |
�h�h
�h�F�����Q�N�́u�l�ʌ�����ʁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��i���Z���j |
|
| ����̂���ɓ쑤�ɂ���V�� |
|
|
| |
�؏�@�i�Z���j |
�h�h
�����������؏�@���A�u�S�Z�����N�v�V�ۂP�Q�N���B��a�S�Z���͖��y�������ł������B
�h�F�����@���������̒n����䶗��͓ޗǂ̑���͂��P�O���Ŕ������Ƃ����B�؏�@�Z�����́u������͂���Ő����ׂ����v�ƌ����Ă����Ƃ����B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B |
|
| |
�\��@�i���сj |
�h�h |
|
| |
�����@���������� |
�h�FJ�F�������ł���A�s�������̍s��ꂽ�Ƃ���ŁA�n���̔z���͂Ȃ��B |
|
| |
���U�@�i��X�j |
�h�h
�O�u�A�ɕ�肠��B |
|
| |
���s�@�i�匴�j |
�h�h |
|
| |
�n���@�i���Ɂj |
�h�h
�d�F�@�����A�n���@�W���͊����P�O�N�i1798�j�����a���ܔ����������B���@�͊Y�������s�ځB |
|
| |
�ݑ��@�i���Áj |
�h�h
�i�F�{���ؑ��@�ӗ֊ω������i������U�P�����j���J�������ʂ��鑽����ω������ŋߗL�u�ɂ���ē��a�̓����ɐV�z�����B |
|
| |
�����E�@�@�{ |
�e
G�F�E����A�V��@�@�@��Ղ��b�R�����������y�������錚�O�ł������B
I:���y���{�V�B�����͈�R������ō��@�ւŐ@�@��Ղ̌��тł������B
�c��5�N�ƍN�̎����ő����@�e�������т����̂��n�܂�ł���B�J�{�̓��t�A���J�{�̒��g���t�A���ʏ��i�E��C�A�g���E�V��̂��Ƃ��E���ł���B�A���A��R�d�u�E���@�x�E�|�E��ځE���@�ړ]�E�Ж�D�d�E���̔z���Ȃǂ͓�����Վx�z�ł������B |
|
|
����@�i�~���j |
�h�h |
|
| |
�ꖽ�@ |
|
|
| ���y�����������琼��ɂ����Ă̖k���V�� |
|
|
|
�@���@�i���c�j |
�h�h |
|
|
�����@�i��c�j |
�h�h |
|
|
�����@�i�x�j |
�h�h |
|
|
��S�@�i���{�j |
�h�h |
|
|
���@ |
�h�F�M���������u������㉚��v�ɂ͋L�ڂ���A�����ȑO�ɑޓ]�� |
|
|
�@���@ |
|
|
|
����@�i����j |
�h�h
�h�F�����Q�N�́u�l�ʌ�����ʁv�ɂ͋L�ڂ��Ȃ��i���Z���j
�h�F����@�E���@�@�E�q���@�����ېV���������ɔ����A�O�u�A�ɕʗ����邱�Ƃ��咣����B |
|
|
���@�@�i���{�j |
A�A�h�h
B�F2019�N�������u�o�^�L�`�������v�ւ̓o�^
�^�@�@�F���{���Z��
�^�@�@�q�a�y�ьɗ��F�Éi�R�N(1850) �z
�^�@�@�\��F�Éi�Q�N(1849)�z/���a�U�O�N�����C
�^�@�@���d��F�Éi�R�N(1850)�z/���a�U�O�N�����C
�����Q�N�̐_�������̔j��ŏZ�E�͊ґ��ЉƂƂȂ�B�剮�̓��q���͂��ƕ��ԂŁA�{���~�q�͏������ɐ����Ă���A�����ɔq�Ɠ`���B
�\��͓���ŁA�ؕ������A�ꌬ�a���̐[�����͗͊�����O�ς����B���d��͓y���ɊJ���r�ؖ�ŁA�w�畘���̌��t�����c���A�y���Ȉ�ۂ̖�B
�h�F����@�E���@�@�E�q���@�����ېV���������ɔ����A�O�u�A�ɕʗ����邱�Ƃ��咣����B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B
�i�F�\��A���A����A���@�A�뉀�Ȃǂ��c���B
|
|
|
�����@�i�V���j |
�h�h
�O�u�A |
|
| |
�����@�i�����j |
A�A�h�h
�d�F���ꓰ�{������ɔ@�������i�����T�Q�����j�͖����R�U�N���ꓰ�Č��ɍۂ��A�����@���J���B�A���A���ݑ��ꓰ�͑ޓ]�������̍s���͕s���B
�h�F�������N����@�E�����@�E���o�����O�_��ł���A�_�������̏�����咣����B
�h�F�����@���������̒n����䶗��͓ޗǂ̑���͂��P�O���Ŕ������Ƃ����B�؏�@�Z�����́u������͂���Ő����ׂ����v�ƌ����Ă����Ƃ����B
�h�F�吳�������A�R��ɋ��Z����Бm�̉Ƃ͚���@�i�i��j�A���@�@�i���{�j�A����@�i�����j�A���@�@�i�c���j�A�ʎ�@�i�M���j�A�����@�i�����j�A�؏�@�i�Z���j�A�ʐ�@�i�R�{�j�A�q���@�i�吼�A�A�����ɏZ���A�ʑ���V�ɐՂɐV�z�A��s�������ǎ�吼�njc�͂��̉Ƃ̏o�ł���B�j�̂X�Ƃɂ����Ȃ��B
|
|
| |
�܌��@�i����j |
�h�h |
|
| |
|
|
|
| |
�g�ˉ@ |
��L�́u���y�����������琼��ɂ����Ă̖k���V�Ɂv���痣��ĕ`����邪�A����͕`���̕ό`�ŁA����㉚��ł͉����@���߂ɕ`�����̂œ�@�ɑ�����̂ł��낤 |
|
| |
|
|
|
| ���d�i�h�A�i�j |
J�F�q�@�̑��X�@�������Ƃ����A���������ɂ���đ���������A�����Q�N�i1790�j�̐l�ʉ��ł�
�⎺�A�|���A�����A�~���A���ܑ�@�̂T�@���������B |
|
| |
|
|
|
| ���̑��̉@�i�h�A�i�j |
J�F���̓��̒��ŁE�x�@�Ɍg���B�����V�A�����@�A�����Ȃǂ��������B
������A�݉ƂŁA�G�������̂��ߎ��ɕ�������B
��L�̎q�@���Ɂu�����@�v�����邪�A����͍݉Ƃ̓������o�Ƃ��q�@�ɏ��i�����̂��m��Ȃ��B |
|
| |
|
|
|
| |
|
|
|
�q�@���̂̎��́i�j���͖����̐_��������̊ґ����F�Ⴆ���܌��@�i����j�̓��삪�ґ����B�@�@�E�{�{�V�E�w���|�іV�ƎБm�S�Q�V�i���L�R�@�V�͊ܗL����Ȃ��H�j�A�G���U�V�ō\������A����ɉ��̉@���W���ɂ͕��q�@�ȉ��S�V�̑��������������ƒm���B�Ȃ��A�{�{�V�Ƃ͕s�ځB
A�F�T�C�g�F�u�_�a��ρv���u������v�@���
�a�F2019�N���������\�u�����R�c��̓��\�i�o�^�L�`�������i�������j�̓o�^�j�ɂ����v�@���
�b�F����s���w�蕶�����i�s�w��j�@���
�c�F�T�C�g�F�������k�R�_�Ёi���y���j�@���
�d�F�u�֗]�E�������̓��v���{����E�����فE���a�T�Q�N�@���
�e�F�u���������y���̓W�J�v�H�i���F�i�u���䒬�j�@���v����s�����A���a�R�Q�N�@�����j�@���
G�F�u�_�������̓����v�@���
�g�F��@���邢�͓��@�Ƃ����@�����U�������B
�Ⴆ�A
�u����s�j, �j���� �㊪ ���n��v�ł�
�@��������@�ՏƉ@���c�����@�V��13�N����3��22���@�i���o�l�j����@��@�ՏƉ@�i��@�����@�T�N���C���q��l�Y
�u��ȋ��v�������N�i1185�j�\�ꌎ������h�N�i��q�j�@�ł�
�@�����V���ҁA��@�������A���V��@�\���V�g���B
�Ƃ����B
���̗p�@����A��@�Ƃ͖��y�������̓쑤�Ɉʒu����V�ɂ𑍂��ē�@�Ƃ�̂ł͂Ȃ����B�H�A��@�ՏƉ@�A��@�������i�@�j�B
�ȏ�̐������������Ƃ���A���@�Ƃ́A���傩�疭�y�������Ɏ���J�̖V�ɂ𓌉@�Ƃ�̂ł͂Ȃ����Ɛ�������B
�h�F�u������̐_�ŕ����v�ґP�V���E��������i�u�����ېV�_�ŕ����j���@�����v���a�S�N�@�����j�@���
�@�c���ȑO�̎q�@�͕s���A�V���P�W�N�S�R����A�R�������͂R�Q�V�A�c���T�N�ƍN���ċ����w���P�O�V���旧�S�Q�V�ƂȂ�B
�@�����ېV���ɂ͂R�R�V�Ɍ������Ă����B
�@�h�h�F����10�N�u�q�@�z���\���撲���v�ɋL�ڂ̂R�R�V�A
�@�����͂R�O�E�������͂Q�O�������ςł���A�Z�m�͐��m�ł���A��q�͂P���������������A��}�P�l�������̂���ʓI�ł���A
�@�q�@�̐����͗T���ł������Ɖ]����ł��낤�B
J�F�u����s�j�@�㊪�v1979�@���
���������i�q�@�E�V�Ɂj�����}
�����������}�i���j
�{�}��
�@����������2500���y��{�}�F�k�� 2500�A���ʔN 1971(��46)�F�i�e��2.5G�j
��}�̏��a�S�U�N���ʂ́u2500���y��{�}�v�ɏ�q���������V���R�A�u���䒬�j�@���v���ېV�O�ɉ�����q�@�̖��̂Ƃ��̔z�u�}�A
�u����s�j�@�㊪�v���ېV�O�̑�����q�@�z�u�}�Ȃǂ��Q�l�ɁA�������𐄒肵�A�}��ɕ����������̂ł���B
���n�ł̒n�������A�����W�Ȃǂ��s�\���ŁA�܂��ԓ��J�ʂɂ��n�`�j��Ȃǂ�����A�m����ʒu�̓��肪�o���Ȃ��������U������A����̂Ɂi���j�}�Ƃ���B
2021/03/15������q�@�̕�������}�ƌ��n�Ƃ̏ƍ����s���A���̂悤�Ȍ��ʂ��̂ŁA����B
�����2020/05/07�B�e�A�����2021/03/15�B�e�F
�����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@��������@�Չ��Ί_�@�@�@�@�@��������@�ՂP�@�@�@�@�@��������@�ՂQ�@�@�@�@�@��������@�ՂR�@�@�@�@�@��������@�ՂS
�@��������@�Տ�Ί_
�m���@�i�q���@�j�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B���Ɉʒu����Ƒz�肳���\�@�@�Ղ͕s���B
�@����m���@�ՂP�@�@�@�@�@����m���@�ՂQ
�P���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B�㉺�̂Q�c�̐Ί_�����邠�邪�A�����Ƃ��Ȃ̂��ǂ��炩������������Ւn�Ȃ̂��͕�����Ȃ��B
�@����P���@���F�㉺�Q�c�̐Ί_
�@����P���@�Չ��P�@�@�@�@�@����P���@�Չ��Q�@�@�@�@�@����P���@�Տ�P�@�@�@�@�@����P���@�Տ�Q
����@��
�@������@�R��P�@�@�@������@�R��Q
�@����@�ՂP�P�@�@�@�@�@����@�ՂP�Q�@�@�@�@�@����@�ՂP�R�@�@�@�@�@����@�ՂP�S�@�@�@�@�@����@�ՂP�T
�@����@�ՂP�U�@�@�@�@�@����@�ՂP�V�@�@�@�@�@����@�ՂP�W�@�@�@�@�@����@�ՂP�X�@�@�@�@�@����@�ՂQ�O
���S�@�ՁE����@�ՁF��O�͎��S�@�ՁE���͎���@��
�@���S�@�ՁE����@�ՂP�@�@�@�@�@���S�@�ՁE����@�ՂQ
���S�@��
�@���S�@�ՂP�@�@�@�@�@���S�@�ՂQ�@�@�@�@�@���S�@�ՂR
���{�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@������{�@�ՂP�@�@�@�@�@������{�@�ՂQ�@�@�@�@�@������{�@�ՂR
��Z�@��
�@����Z�@�\��
�@��Z�@�ՂP�@�@�@�@�@��Z�@�ՂQ�@�@�@�@�@��Z�@�ՂR�@�@�@�@�@��Z�@�ՂS�@�@�@�@�@��Z�@�ՂT�@�@�@�@�@��Z�@�ՂU�@�@�@�@�@��Z�@�ՂV
�ʐ�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@����ʐ�@��
�ʐ�@�ՁE�ʎ�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B���̐Ί_���ʎ�@��
�@�ʐ�@�ՁE�ʎ�@��
�ʎ�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@����ʎ�@��
�~��@�A�S��@�A���s�@�A�ύs�@�͓��H�E���ԏ�ɑ������ꉝ���̖ʉe���c���Ȃ��B
���@�@�A�\���V�A���o�@�Ղ͎Q�������̗��فE�y�Y�X�ɕϖe���Ă���B
�w���|�іV��
�@���w���|�іV�ՂP�@�@�@���w���|�іV�ՂQ
�@�w���|�іV�ՂP�@�@�@�@�@�w���|�іV�ՂQ�@�@�@�@�@�w���|�іV�ՂR
�����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@���蓡���@�ՂP�@�@�@�@�@���蓡���@�ՂQ
�؏�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@����؏�@��
���U�@�A���s�@�A����@�Ղ͓��H�Ȃǂɓ]�p����A�s�ځB
�����@�E�\��@�ՁF���ݐՋ��͎c��Ǝv�킦����A�m�͂Ȃ��B
�@���薭���@�ՂP�@�@�@�@�@���薭���@�ՂQ
����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@���蕁��@�ՂP�@�@�@�@�@���蕁��@�ՂQ�F��O�E�Ί_������@�ՁA�㒆���Ί_���n���@�ՁA�������Ί_�������@�ՂƐ��肳���B
�n���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@����n���@�ՂP�F�����Ί_���n���@�ՁA��O�E�Ί_������@�ՁA�������Ί_�������@�ՂƐ��肳���B
�@����n���@�ՂQ�@�@�@�@�@����n���@�ՂR�@�@�@�@�@����n���@�ՂS�@�@�@�@�@����n���@�ՂT
�施�@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��A���ݍċ����ꂽ���y������������Ă���n�Ɛ��肳���B
�@����施�@�ՂP�@�@�@�@�@����施�@�ՂQ
�@����施�@�ՂR�F��O�̓��H�����U�@�A���s�@�A����@�Ղ��т��Ɛ��肳���B
�ċ����������y��
���u���y���̍ċ��v�O�֎R�������E�Z�E�F�ێq�F�@�@���
�n���͓����������q��d�������̈�[�����̒n�ɖ������A�\�O�d�̋��{���������������ƂɎn�܂�B
���̌�A�����E��s�O�����E����@�����������B
����P�X�N�i919�j��b�R��������S�㌟�Z�ɏA���A�@���@����]���A�b�R�����ƂȂ�B
�����ŁA�b�R�̎G�ꂪ������ɉB������B
�������N�i1025�j���Z�������������B
�m���N���i1167�j������[�A�O�d�������B
�@���T�@�̕����͊�����
�������N�A�_���������ɂ�薭�y���͔p���B
2021�N���y���͑����@���y���Ƃ��čċ������B
�@�����������y���́A��150�N�Ԃ�ɁA�O�֎R�������Z�E�̔���E�z���ōċ����ꂽ���̂Ɛ��肳���B
�@�ċ����y���P�@�@�@�@�@�ċ����y���Q�@�@�@�@�@�ċ����y���R�@�@�@�@�@�ċ����y���S
�@�ܘ_�A���y���͌��݂̒k�R�_�ЂƂ��Ďc�鐹��a�A���k�A��s�O�����A�u���Ȃǂ̏������\������A�����ېV�Ŕp���ƂȂ�B
�@���̖��Ղ���������@�Ղɑh�����Ƃ����Ӗ��ł���B
�@��2021/12/25�lj��F
�@2021/12/23�t�u�����V���@�[���v�Ɂu�V�����������ꂽ���y���v�Ɋւ���L�����f�ڂ����B
�@�@�������́�2021/12/23�t�u�����V���@�[���@�L�������Q�ƁB
�@�@�{�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��A�施�@�Ղɐڂ����̕��ʂ����̐Ւn�Ǝv����B
�@���萴�@�@�{��
��S�@��
�@����S�@��
�@��S�@��
�����@��
�@�����@��
�g�ˉ@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@����g�ˉ@���F���̕t�߂Ɛ��肳�����A�s�m���ł���B
���ω@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ�
�@���荁�ω@�ՂP�@�@�@�@�@���荁�ω@�ՂQ�@�@�@�@�@���荁�ω@�ՂR�@�@�@�@�@���荁�ω@�ՂS
���@�@��
�@�����@�@��\�P�@�@�@�@�����@�@��\�Q�@�@�@�@�����@�@��\�R
�@���@�@�ՂP�P�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�Q�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�R�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�S�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�T�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�U
�@���@�@�ՂP�V�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�W�@�@�@�@�@���@�@�ՂP�X�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�O�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�P�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�Q
�@���@�@�ՂQ�R�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�S�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�T�@�@�@�@�@���@�@�ՂQ�U
�����@��
�@�������@�ՂP�@�@�@�@�������@�ՂQ�@�@�@�@�������@�ՂR�@�@�@�@�������@�ՂS
�@�����@�ՂP�P�@�@�@�@�@�����@�ՂP�Q�@�@�@�@�@�����@�ՂP�R�@�@�@�@�@�����@�ՂP�S�@�@�@�@�@�����@�ՂP�T�@�@�@�@�@�����@�ՂP�U
�@�����@�ՂP�V�@�@�@�@�@�����@�ՂP�W�@�@�@�@�@�����@�ՂP�X�@�@�@�@�@�����@�ՂQ�O�@�@�@�@�@�����@�ՂQ�P�@�@�@�@�@�����@�ՂQ�Q
�@�����@�ՂQ�R
���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@������@��
�����@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@��������@�ՂP�@�@�@�@�@��������@�ՂQ
�܌��@�F�A���A�m�͂Ȃ��B
�@�����܌��@�P�@�@�@�@�@�����܌��@�Q
�O���@�ՁF�A���A�m�͂Ȃ��B
�@����O���@�ՂP�@�@�@�@�@����O���@�ՂQ�@�@�@�@�@����O���@�ՂR
�S�щ@��
�@�S�щ@�ՂP�@�@�@�@�@�S�щ@�ՂQ
2025/09/23�lj��F
���������Ȃǂ̒n�А}�ɂ���
������s�������u�������n�А}�v
�@�n�А}�i�����}�j�ɂ͋��Ƃ��̒n�Ԃ��\������邾���ŁA���y���X���̖��̂�������Ă�����̂ł͂Ȃ��B
�@�]���āA�n�А}���疭�y���X��������o�����Ƃ͍���ł���B
�����s��w�l�����}���ّ��u�\�s�S�����������S�}�v
�@���L
:�u���ʃj�g�p�Z�V��B �n���g�ē� �t���X�}�R���p�c�v�L�ڂ���.
�@�{�}�ɂ��Ă��A���Ƃ��̒n�Ԃ��\������邾���ŁA���y���X���̖��̂�������Ă�����̂ł͂Ȃ��B
�@�]���āA�n�А}���疭�y���X��������o�����Ƃ͍���ł���B
�Ȃ��A�{�}�ɂ��Ă͉{���͉\�ł��邪�A���ʂ͕s�ł���B
�������A�}���ِE���̍D�ӂŁA�E�������}���ʐ^�B�e���A������p�\�R���Ɏ�荞�݁A�v�����^�ŏo�͂������̂̒���B
�A���A��L���@�̃v�����g�ł͑����ɕs�N���ł���B
------------------------
�����������y���{�V�̍ċ�
�@2021�N�@�@�{�Ւn�ɑ��������y���{�V�Ə̂��铰�F���ċ��Ə̂��Č��������B
�ċ������͎̂O�֖��_���������O�֖��_�ɍċ����������@�ċ��������Z�E�ێq�F�@�ł���B
��2021/12/25�lj��F
��2021/12/23�t�u�����V���@�[���@�L����
���u�����y���@�ڂ̑O�ɂ����y���H�v
������ɖ��y�����ċ������B����͈�F�̓��i���s��P�R���A���Ԗ�V���j�ł���B
�����ɂ́A�u���������y���@�{�V�@�@�{�Ձv�Ȃǂ̐V�����Δ�����B
�@���������y���Δ�Ȃ��F2021/03/15�B�e�F�k�R�_�Ђƍċ����y���Ƃ��a瀂̌����ƂȂ����Δ�E�G�z
�ċ������̂͑����@�O�֎R�������Z�E�ێq�F�@�t�ł���A���̓��͕������̏o�����Ƃ��Č����Ƃ����B�v�H��2021/05���B
�ċ����ꂽ�n�́u�{�V�@�@�{�v�̐Ւn�ŁA500���l�̒n���҂���w������B
�@���ێq�F�@�t�͂��̒n���@�@�ՂƂ��邪�A���n�̒n�`����A�@�@�Ղł͂Ȃ����̖k���̋��ł���施�@�Ղł��낤�B�A���A�施�@�͑ޓ]�����Ƃ��̉������̗��R�Ő@�@�{���n���҂ƂȂ��Ă����̂����m��Ȃ��B
�ێq�Z�E�͑����@�̑m���ŁA�������O�_�{���Ŗ����ېV�̐_�������Ŕp���ꂽ���������ċ�����B�����͑�ŋM�̂��艾�����ċ�����B
�����@�J�c�����̑c���͓�����[�ł���A��[�͖��y���ɎO�d������i�����Ɠ`����B�܂��{�R�i�����̑�Q���lj_�����i�������ƍ��t�j�A��R���O�ʋ`��A��S���`���͑��������y���ŏC�s�����Ƃ����B���������o�܂���ێq�Z�E�͖��y���̍ċ�����}�����Ƃ����B
���������́u�lj_�����T�t�����y���Ŋw�̂ŁA������������铰�������������v�Ƃ̎�|�ł������̂ŁA���̊�}�ɂّ͈��͂Ȃ������Ƃ����B
�Ƃ��낪�A������Ɂu���y���v�̎����肪��������A����ɂ��Ă͑��������Ƃ̊Ԃ��a瀂������Ă���B���y���̗R�����c�߂��Ă���A���邢�͗��j�F���Ɍ����������Ƃ̗��R�Łu���y���v�̏���Ȏ�����͍���Ƃ����B���������͖��y���̍��̕ύX���邢�͔�̓P�������߂�\���Ƃ����B
�Ȃ��A���y�������̎q���ł��鈤�m����勳�����{�G�I���_�����i���{�Ñ�j�j���R�����e�[�^�Ƃ��ċL���ɓo�ꂷ�邪�A���@�@�i���{�j�̌���ł��낤�Ǝv����B
�@�����ʂ̖��y���ċ��ɂ��đ�����i�k�R�_�Ёj���́u���j�I�ɂ����y���͒k�R�_�Ђ̂��ƁB���̊�̑O�ɂ��������āA����ɖ��y���𖼏����Ɨ��j���c�߂���v�Ƃ����B
�܂��A���y���m���̎q���ł��鈤�m����吼�{���_�����́u���j�I�ɖ��y���𖼏���̂͒k�R�_�Ђ����Ȃ��B�_�Ђ̎��ߋ����ł���Ȃ��������Ă���Ό�������v�Ƙb���Ƃ����B
�@�������A���̘_�͋��Ⴄ�ł��낤�B
�k�R�_�ЂƂ͖��y���Ɠ��`�ł���A����ɖ��y���𖼏��̂͗��j���c�߂��邠�邢�͌���������Ƃ����̂ł���A�k�R�_�Ђ����y���ɕ����A�{�@�͐���@�A�q�a�͌썑�@�A�_�_�͏\�O�d���A�_�_�q���͍u���A���a�͏�s�O�����Ȃǂƕ�������̂��ł��낤�B
���Ă̖��y���������ېV�̐_�������̑[�u�Œk�R�_�ЂƉ�₂��ꂽ�Ƃ��Ǝ��̂����j���c�߂�ꂽ���Ƃ��邢�͌�����������Ԃ���u���Ă���Ƃ������Ƃł��낤�B
���ʂ̖��y���ƍ����铰�̍ċ��ŁA�k�R�_�Ђƕ������Ƃ̊Ԃ��a瀂��������Ƃ���Ȃ�A�������������{���I�ȉ������@�͖����ېV�̐_�������Ŗ��y�����p����k�R�_�ЂȂ鎗��Ȃ�̍��ɂȂ������Ƃ����߂邱�Ƃł��낤�B
�[�I�ɉ]���B
�k�R�_�Ђ͐_�����̂āA�V��@���y���ɕ�����ׂ��ł���B�����̐_�������̏��u�ƑS���t�Ȃ��Ƃ����邾���ł���B
����ȓ��ł��邪�A���ꂪ���j�̘c�݂����̔�����h�~����B��̓��ł���B
��2025/09/11�lj��F
���u���������y���@�{�V�v���������y���ҏW�i�O�֎R���������j�A2021�@���
�@�i����@�������������q�@��d�a���@�J�R�@�苁�a���̎��@�����E�@�@�{�Ձj
�@�������A�F�O�֎R�������@�ێq�F�@
�@������̗R������钆�Ɏ��̈ꕶ������B�i�v��j
�m���N���i1167�j����������[�i�����T�t�̑c���j���O�d������i����B
���q��������[�\�E�i�}�O�̎Y�A�����i�j�̑��Ƃ����j���y���ɂđT�@�B���@���J���B
�\�E���A��q�S�傪�@�����p���A�S��̂��Ɖ��ӁE�����E�`��E�`���炪�C�s�A��ɉ��ӈȉ���傪�����ɉ��@���A�����̑����@�̑b�ƂȂ�B
�@���a�S�U�N�����O�֖��_���c�������ċ��̂��߂̊��i����n�߂�������A���������y���̍ċ���S�ɍ���ł����B
���̌��ʁA���̓x���������y����150�N�Ԃ�ɍċ��̉^�тƂȂ�B
�@�����ݍċ��������͑����@�ł��邪�A������͗h�Պ��̑T�@�Ɗւ�肪����������m��B
�@��������ċ��͑��N�̔ߊ�ł��������Ƃ��m��B
�E�ȉ��ɐ}�ł�]�ڂ���B
�@�����������y���S�i�}�F�{�}�̑f�����悭������Ȃ��B�������ĉE���Ɂu�R�����v�u�����v�����邪�A���Ǐo���Ȃ��B
��������ɁA���ʂ̖��y���ċ��ɍ��킹�A�ߐ����̑������V�}��V���ɖ͎ʂ����u�V��v�ł���̂����m��Ȃ��B
�@�V����w���E�������V�}�F�V����w���Ƃ���B�@�@�{�E�w���E�|�щ@�t�߂̕����}���B
�@�ċ����y�����ʐ}
------------------------
�@�������e�@�h�c�t��
�@����[�\�E�ƒB���@
�@�B���@�͓V��̊w�m����[�\�E���������T�̈�h�ł���B
�ےÎO�E���������y���ŕz���������n�߂�B����������[�\�E�̖��t�̑T�͎t�q������`���Ƃ���T��łْ͈[�Ƃ����B
�\�E���A��q�S�傪�@�����p���A�S��̂��Ɖ��ӁE�����i�i�����Q��j�E�`��i�i�����R��j�E�`���i�i�����S��j�炪�C�s�A��̉���3�N�i1241�j���ӈȉ���傪�����ɉ��@���A�����̑����@�̑b�ƂȂ�B
��2022�N�u���������既�v��Q�Q���@���i�v��j
�@�E�E�E�E�E���̓x�̖��y����@�̍Č��́A50�N���̔O��ł���B
��������s���Ŕp���ʎ߂ɂ��p���ƂȂ����̂́A�������Ɩ��y��������B
�E�E�E�E�E�A���y���͉i�����J�R�E�����T�t�̑c���E������[���O�d������i�����ŁA�i�������lj_�����T�t�A�O��`��T�t�A�l��`���T�t���C�s�������ł���A�E�E�E�E�E�E�B
�@�i���̓x�̖��y����@�̍ċ��ɂ�����j�����ɑ��������y���{�V�̐Ւn���������̕��ɂ����肢�����������Ǝv�O����B
�E�E�E�E�E������̋k�ΗY���ɖ��y���{�V�E�@�@�{�Ւn500�����n���Ē����^�тƂȂ�B
�@���ċ����y���̎��n�͒n���ҁE�k�ΗY��������n���ꂽ���Ƃ�m��B
������u��a���������O�d�������v�F���k�R�_�Б�
������ɍ���u��a���������O�d�������v���`���B
�a���W�N�i715�j�Ɋ����������������̌��������`������̂ł���B
�@����a�����������Ɏʐ^�E��{���f�ځB
2025/09/23�lj��F
���u�ޗǍ��������يJ��130�N�L�O���ʓW�@���@����[�F��̂����₫�[�v�ޗǍ��������فA2025�@���
�@��a���������O�d�������@�@�@�@�@��a���������O�d�����������@�@�@�@�@��a���������O�d����������
��ӂ́A�����V�c�i��`��������{���V���V�c�j�̌��A���b���b�哈�����Ǎc�q�i������F���{�j�̖������F���Ĕ��肵�����̂ŁA�哈�̖v��͔��̒��b�z�c�����Ƃ��p�����A�\�ߔN�i�����V�c8�N/694�j����a���W�N�i715�j�܂łQ�Q�N�̍Ό����₵��Z�̎߉ޑ����J������y�юO�d����A�Ƃ������̂ł���B
�����̍Ō�́A���Ǎc�q�E�哈�̕����F��蕶�ł���B
--------------------------------
��������̌��z��\
�P�j��a�S�ώ��{���F���ۓx���ւɂ��{�a��\�F
�@�@���@��a�S�ώ��{���i���ۓx�j
�Q�j��a���厛����@�������F�����x���ւɂ��{�a��\�F
�@�@���@���厛����@�������i�����x�j
�R�j��a������y���{���F�֑���\�F
�@���@���������y���֑��F������y���{���i���Ɍf�ځj�F��a������y���{���Ƃ��ďC���ڌ�
�S�j��a�����J�R���F���������y���얀���F������ڒz
���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v��y������������A���s�F��y���h�Ƒy��F�吼�r��A2024�@���
�@�J�R���͖{���̐����Ɍ��B�J�R���͓��ꉮ���ȓ��̎O�ԓ��A���̌��z�͑��������y���얀���ł���A�����X�N�i1797�j�̌��z�Ƃ����B�����S�N�ɉ����̈ڒz����A�ߔN���C�����Ƃ����B
���T�C�g�F��̌䎛�@�����@���
�J�R���i�[���E������j
�{���̐����Ɍ���ڂ��Č��ȓ���O�ԓ��B����ɎO�������u�B
���������y�����ڒz����A���͌얀���ł������Ɠ`���B�ڒz�̍ہA�����O��Ԃ����犢�����ɕύX�����B
2004�`06�N��̏C�������{�A�����͞w�畘���ɕ�����B
���̉�̏C���ł͌����N��Ǝv����u�����X�N�v�̖n������������A�܂��ڒz�����̓��D����������A�����S�N�ɓ����Ɉڒz���ꂽ���Ƃ����炩�ɂȂ�B
2008/01/08�B�e�F
�@�����J�R���P�@�@�@�@�@�����J�R���Q
�������܂������� > �ޗnj� > �������� > ����
�@2009�N10��25���B�e�F
�@�����J�R���R
���y�[�W�F��a�O��ω� ���������L�y�����z�Aby �Ђ��@���
�@�����J�R���S�F�����J�R���T�i�E�Ɍf�ځj�̏k���摜�@�@�@�@�@�����J�R���T�F�e��1.91MB
�T�j���|�c���O������
�Z�u�����s�j �{�� /�����v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���
�@�����O��
�^�@�����h�A��͑��������y���ɂ��������̂ŁA�����P�Q�N�Ɍ��n�Ɍ�������Ă���B
��GoogleMap�@���
�@���|�c���O���X��P�@�@�@�@�@���|�c���O���X��Q
�U�j�c����厛��
�Z�u�����s�j �{��/�����v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���
�@����R��
��y�^�@�A��͖����X�N�ɑ��������y���q�@�̖������Ĉڒz����B
��GoogleMap�@���
�@�c����R���X��
--------------------------------
�����������y���֑��F������y���{��
2020/02/23�lj��F
�@���y���֑��͎�蕥����Ƃ������A�u�����s�j�v�ɂ��A�����s������y���Ɉڒz����A�����z����A�{���Ƃ��Ďc������Ƃ����B
���̂��Ƃ̔��[��
�����s�������~�d�z��������E�吼�l���A������y���{���͑�����̈�\�ł���]�X�Ƃ̃��[���Ղ������Ƃł���B
�@�����A�v�����T�C�g�Ō�������A�u�����s�j�v�ɍs��������B
�ȉ��u�����s�j�v���A�]�ڂ���B
�P�j�u�����s�j�@�㊪�v�����s�����A���a�U�Q�N
�@https://www.city.kashihara.nara.jp/material/files/group/7/5c34c21af1a7f00f31b18fb6.pdf�@���́@p.581�ɂ�
�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ����B
�@�����̏�y���{���͑�����֑����ڒz�A�����z���Đ^�@�{���ɂ��Ă����̂ł���B�k�R�_�Ћ��{�a�̓��厛�{�V�������A�L�˒��̕S�ώ��{���ƂƂ��ɁA������̈�\�Ƃ��Ă��d�v�ł���B
�@���Q�ƁF��a�S�ώ��{���i���ۓx�j�A���厛����@�������i�����x�j
�Q�j�u�����s�j�@�����v�����s�����A���a�U�Q�N
�@https://www.city.kashihara.nara.jp/material/files/group/7/5c34c221f1a7f00f31b18fc0.pdf�@���́@p.653�ɂ�
�ȉ��̂悤�ɋL�ڂ����B
�@��y���@������
��y�^�@�{�莛�h
��E�{���E�ɗ�������A��O�ɐׂ������āA��i�l�N(1524)�ݖ��̎߉ޔ������̐Ε�������B��̋S���Ɋ��ۓ�N(1742)�̍�����������B
�{���͓��ꉮ���{�����Ō��s�O��A���s�l��A���ʂɈꕷ�̌��q������B
���̓��͂��Ƒ������̗֑����ڂ������̂Ɠ`�����A���Ȃ��������Ă��邪�A���̐^�@���@�ɂ͌����Ȃ����F���铰�ł���B�]�ˎ��㒆���̌����ƍl������B
���ʓ����ɕ���t�̉ޗː����̗z�����̒������ڂɂ��B���w�����ɂ͓�A�̉ԓ��������Ă���B�k�R���y���̗֑��͎Гa�̉����ɂ��������A�ېV�̐_�������ɂ���ė֑����s�v�ɂȂ�A���n�Ɉڂ��ꂽ���̂ł���B�ڒz�ɓ����ē��w������t���ĉ����������̂ŁA���w�����͗��e���Ԃ��L���Ȃ�A���̕����͗��s�܊ԂɂȂ��Ă���B
�������̗֑���m��d�v�Ȏ����ł���B
�@���w�����{��d�ɖ{������ɔ@���������J��A�����ĉE�d�Ɍ��^��t�A�{�@��l�A�����m�̉摜���J��A���e�d�ɐ������q�摜���������A�ʔv�Ȃǂ����u���Ă���B
��y���̉��v�ɂ��Ă͎������Ȃ��̂Ŗ��炩�ɂ��邱�Ƃ͂ł��Ȃ����A���Ƃ͖@���@�ł������Ƃ����Ă���B
�Ȃ��A
��L�̃~�d�z������ЁE�吼�l���ʐ^�̂������̂ŁA�f�ڂ������Ē����B
�吼�l���摜�F�������s������y���{��
�@���y���֑���\�P�@�@�@�@�@���y���֑���\�Q�@�@�@�@�@���y���֑���\�R
���q�тƂ��̑g���A�{�����l�g���y�щޗː����̗��ԂȂǂɑ������֑��̈ӏ��̕З��c����̂Ǝv����B
�@���ޗ˕p���F�ł��������������Ƃ���钹�@�Ƃ����B
2021/03/15�B�e�F
�@���y�����U�ɂ��ẮA�w�Ǐ�Ȃ��B
�]���āA�ÊG�}�ɂ��Ċm�F���悤�B
���ۑ�����㉚��i���ۑ�����㉚��E���������j�ł͗��U�͌�������Ȃ��̂ŁA���U�͍]�˒����ȍ~�̑n���ł��낤�B
�]�ˌ����
�u��a���������v�i����������E�{�ЁE�����j�A�u�����O�\�O��������㉁v�i�������{�ЁE���̓��j�A
�u�����t�ōցv��i�������V���R�j�A���T���^���u�������V���v�@�Ȃǂł�
��`���̗��U�i���ʌ��q�t�݁A�����炭�����j���`�����B���Ԃ͕K���������m�ł͂Ȃ��Ǝv���邪�A�R�Ԏl���Ɛ��肳���B
�@��������o���i���U�j�����Ă݂悤�B
�ߍ]���鎛�i�O�䎛�j�����h�������o������ڌ����ꂽ�������̂��̂ł͂��邪�A�o��������B
���@�o���R�F���ʂR�ԁi�����Ԃ͍L���A���e�Ԃ̔{���炢�̊Ԍ��ł���j�A���ʂ͕ό`�̂S�Ԃł���B�A�����ʂɂ͌��q�͕t�݂��Ȃ��B
�@����A
��Ɏ������u�����s�j�@�����v�ł�
�@�u�i��y���j�{���͓��ꉮ���{�����Ō��s�O��A���s�l��A���ʂɈꕷ�̌��q������B
���̓��͂��Ƒ������̗֑����ڂ������̂Ɠ`�����A���Ȃ��������Ă��邪�E�E�E�E�]�ˎ��㒆���̌����ƍl������B
�E�E�E�E�E�k�R���y���̗֑��͎Гa�̉����ɂ��������A�ېV�̐_�������ɂ���ė֑����s�v�ɂȂ�A���n�Ɉڂ��ꂽ���̂ł���B�ڒz�ɓ����ē��w������t���ĉ����������̂ŁA���w�����͗��e���Ԃ��L���Ȃ�A���̕����͗��s�܊ԂɂȂ��Ă���B
�������̗֑���m��d�v�Ȏ����ł���B�v
�Ƃ���B
�@�ܘ_�A�ڌ��ɓ������āA��������Ă͂��邪�A���ʋK�͂Ƃ��ẮA���s�R�ԁE���ԂS�ԁE���ʂP�Ԃ̌��q�̋K�͂ł������Ɛ���ł���B
����ɁA���݂̓��w�����͕t���E��������A���e���ԂÂÍL���i�Ӗ����ǂ�������Ȃ��j�Ȃ�A���̕����͗��ԂT�ԂɂȂ��Ă���B
�@�ł͎��ۂ̏�y���{�������Ă݂悤�B
���̑O�ɁA���Ԃ�����A���n���U�Ղ̊�d�y�я�y���{���K�͂̌v����ӂ�A���҂̕��ʋK�͂̔�r���ł��Ȃ��̂��c�O�ł���B
��y���{���i���y�����U��\�j�͓��ʂ���B
�@���U��\���ʂP
�@���U��\���ʂQ�F�����Ԃ��ɒ[�ɍL���i�e�Ԃ̔{�قǂ̊Ԍ��j�R�ԂŁA���q��t�݁B���Ƃ̗֑��̕��ʂ��c���Ǝv����B�A���A���͓y�Ԃł������Ǝv���邪�A�т�ʂ�����A��y�^�@�̖{���̋@�\���ʂ����悤�ɉ����������̂Ǝv����B
�@���U��\���ʂR�F�{�����ʂ��������B�e�A�����Ԃ��ɒ[�ɍL���R�Ԃł��邱�Ƃ�������B
�@���U��\����F�{�����ʁi���s�E��ʁj���������B�e�A�ʂ�̂͊O�w�ŁA�������ĉE�̉��̉��͓��w�ł���B���ʂ̒����Ԃ��e�Ԃɔ�ɒ[�ɍL���A���y���֑��̑��ʂ����ʂƓ����������Ԃ��ɒ[�ɍL�����ʂł������v����B
�@�Ȃ��A�u�����s�j�@�����v�ł́u���s�l��v�Ƃ���̂ŁA�����̘e�Ԃ͂Q�ԁi�e�Ԃ�����ɔ��Ԃɕ����j�Ƃ��A���ʂS�Ԃł������Ǝv����B
�����ɂ��ẮA���X��`���ł��������A�ǂ̂悤�ɏ����g�����������̂��͕s���ł��邪�A�{���炵�����ꉮ���ɉ�������Ă���B
�ו��ɂ��ẮA�֑��ł���A�T�@�l�̗l����p�������̂Ǝv����B�܂�������̌��z�ɑ������������u����t�̉ޗː����̗z�����̒����v��₩��富҂Ȃǂ��p�����Ǝv����B
�@���U��\�l���P�@�@�@�@�@���U��\�l���Q�@�@�@�@�@���U��\�l���R
�@�{�����ʂ̑嗓�ԁF
�@�@�ޗː����̗z�����P�@�@�@�@�@�ޗː����̗z�����Q
���w�ɂ��Ă͗ǂ�������Ȃ����A�O�w�E���w�̎d���ݒu���A�{��d�╧�d�ݒu�̂��߁A���ԉ��ɕ��ʂ��L�����`�Ղ͔F�߂���B
�@���U��\���w�P�@�@�@�@�@���U��\���w�Q�@�@�@�@�@���U��\���w�R�@�@�@�@�@���U��\���w�S
2025/09/14�lj��F
���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v��y������������A���s�F��y���h�Ƒy��F�吼�r��A2024�@���
�@���{���̊T�v�́u�}���v�̃y�[�W���Q�Ɖ������B
�@���G�F����y���{���Α��@�������F���̂́u��y���v�����A���݂́u��y���v�����A
�@����̒������@�ɖ�O�̐�꜂���A�����ɑJ����Ă���悤�ł���B
�@2024/10/26�B�e�F
�@�@��y���Α��߉ޔ@������
�����������i���E�~���s�j��y���{���F���������y���֑��ނɂČ���
����y�����j
�@���݂̐^�@��y���͖@���@��y���i��y������y���j�ƍl������B
�u���@���撲���v�i�����Q�S�N�j�̏�y���̍��ł�
�厚�\�s�Ɂu����̉����v���������Ƃ��A�����̖k���̋v�ې쌴�̎Œn�i�X���̓y�n�F1.8���l���j���O�g�����̈�ւ��Ƃ��Ă��āA�ØV�����̌���ɂ����̎��͖@���@��h�R��y���ƌĂ�Ă����Ƃ����B����́u���ג��t���Y���v�̒��Ɂu���̒��ɏ�̎����L������́v����Ƃ����L�ڂɕ���������̂Ǝv����B
�@�܂��A����̒����ŁA��y���Α��߉ޔ@�������̌������č�������u��y���v�̖��������o����Ă���B
�����āA���̐Α��̔N��͂P�U���I�O���i��������j�Ɛ��肳��A����ɂ��̐Ε��͏�y���̖{���ł��������낤�Ɛ��肳��Ă���B
�@���@��y�����������Ȃ�����ċ����ꂽ�̂́A�Ε��̔N�㊴���炷��Ύ�������̂��ƂŁA���ꂪ���̍����A�����炭�ߐ��ɒ����̏W���̒��Ɉړ����A�^�@����Ƃ��Ă̐M���W�߂Ă������̂ł͂����낤���B
���̌�A��y���̌���ł��낤�^�@����́A���U�N�i1756�j�{�R���玛���F�i���U�N�u�����F��v�j������A�u��y���v�ƌ��̂���B
����y���Α��߉ޔ@������
�@�u�����s�j�v���u���@�v�ł͖{���ɂ��āu��O�ɕ�꜂�����A��i�S�N�i1524�j�ݖ��̎߉ނ̔������̐Ε�������v�ƋL�q������B
�������A����̒����ł́A�����͑��̍��E�ɒ���ꂽ���̈ȊO�͌��o���ꂸ�A�N�I���͑��݂��Ȃ����Ƃ����炩�ƂȂ�B
����������
�@��y���߉ސΕ�������e�F�̑�E���V�T�F�Ƃ���@�@�@�@�@�@��y���߉ސΕ������d�q��e
�̒ʂ�A���̍��ɂ́u�{�_�v�A�E�ɂ́u��y���v�̖������������o�����B
�@�{�_�F���܂��͊J�ᓱ�t�Ǝv���邪�s�ځA��y���F��y���̑O�g�E�@���@��y���Ɛ��肳���B
����������
�@�u���@���撲���v�i�����Q�S�N�j�ɂ͏�y���R���Ƃ��āA�����̖k���̋v�ې쌴�̎Œn�i�X���̓y�n�F1.8���l���j�ɂ��Ė@���@��h�R��y���Ƃ������@������A���̎��@�������R�N�i1472�j�E���������Ɍ��ݒn�Ɉړ����A��y�^�@��y���ƂȂ����|�̋L�ڂ�����B
����ɁA�����̏K���Ƃ��ċ���Q���P�T���Ɏ߉ސΑ��O�ɂāu���ω�v���s���邪�A�u�������ɐ₦���͉��É����ɂğ��ω�Ɏ��s�����́X�̈╗�Ȃ肵�Ƃ����v�Ƃ���B
�܂艝�É����Ƃ͗�h�R��y���̂��ƂŁA�߉ސΑ��O�ɂāu���ω�v�͏�y���̂�������p���s���Ɠ`������B
�@�u�y�M�d�i�䒠�v�i�吳���N�j�ɂ́u�吹�߉ސ����v�i�Ε��̂��Ɓj�͌���Ƃ��āu��y���Ɉ��u����Ă����v�Ƃ���L�ڂ�����B�R���u��h�R�v�̎����悤�ɖ@���@��y���͎߉ނ�{���Ƃ��Ă����W�R���������A�܂��Ε��̕ۑ���Ԃ��ɂ߂ėǍD�ł��邱�Ƃ���A�������J���Ă����\���������B
�@�A���A���̑O�g���@�E��y���̈�ւ͋�襂ȎŒn�i�X���̓y�n�F1.8���l���j�ł���A�Ε���[�߂邾���̏��F�ł����Ȃ������悤�ł���B���u�����̂����J�̉e�����₷�����F�̌̂ɖ{���͐Ε��ł������̂����m��Ȃ��B
�@�Ȃ��A�u���@���撲���v�t���́u�Y�햾�ג��v�ɂ́u�W�����̒��ɏ�̎����L���A����ɉ��@�̍ۏ�̎������ߏ�y���Ƃ��A�E�E�E�E�����ނ̏��a�̈╨�Ȃ�v�Ƃ���B
���Ε��̗ޗᒲ��
����������Ƃ����ȉ��̐Ε��������ΏۂƂȂ�B�i�ڍׂ͏ȗ��j
�@��s�܍��@�n���Ε��Q��@�@��s�̖����n���Ε��R��@�@��c��c���n���Ε�
�ȏ�U��͓�s�̎�������̍��Ƃ����Ε��ł��邪�A��y���Α��ƒ����Z�@��l���Ȃǂŋ��ʍ��������ƌ��_�Â�����B
���߉ޔ@���̗ޗ�F�߉ޔ@���̈��͋ɂ߂ď����ł���A��������������̍��͌�������Ȃ��B���̍��͕����Ɓ`���q���̂��̂ł���B
�@�����n���J�@���Ε��@�@���J�Ε��@�@��s�O�ϐ@�@��s�\�։@�ΌA�߉ސΑ��@�@�R��a�����R��
�c�O�Ȃ���A��������̍�i�͏�y���̐Ε��݂̂ł���B
����y���{���̌��z
�@��q�̂悤�ɕ��U�N�i1756�j��y���͖@���@��y���̎�����F����A��y�^�@�̓]����B
���n�͒����̂قڒ����ɂ���A��ɂ͓��H������Łu���_�Ёv���ڂ���B
�V���S�N�i1784�j���{���̑O�g�ł���{�����Č������B
�����P�T�N���������y���̗֑����w�����A������厲�Ƃ��Ă��̑��̌Íނ����킹�Č������ꂽ�̂����݂̖{���ł���B
�u�{���Č�����蒠��J�v�i�吼�Ƒ��j�Ȃǂ���A�����P�T�N�������֑��̌Íނ��w���A�����Q�O�N�ɏv�H��������������B
�@��������͌��݂̌o�H�Ŗ�P�R�����A�W������R�T�O���邪�A������[�����Ԃ�唪�ԂƏM�^�ŁA���x�����������Ǝv����B
�ے��P�Q�{�A���̑b�ՂƑb�P�Q��A枓栱�ށA�n����т̉��ˍށA�֑��ȊO�̉�̂��ꂽ�V���ˁE����A�������ށA���A�A�Ȃǂ�l�͂ʼn^�������̂ł��낤�B�u�{���Č�����蒠��J�v����͑�������n�ߑ����̐l�X�̎ӗ��������Ȃ���^�����Ă������Ƃ�������B
���y�������̑m���͑������ߗׂ̑���l�w�o�g�ł��邩��A�o�Ƃ�����������Ƃ̊W�͑����Ă������̂Ǝv����B
�@�Č����ꂽ�{���͓��ꉮ���A�����V�����A���s�R�ԗ��ԂS�ԁA���ʂɂ͂P�Ԃ̌��q��t�݁A�����͊O�w�E���w���敪����B
���֑��͕�`���A���R�Ԃ̌��z�ł���̂ŁA�{���͒P�Ȃ�ڒz�ł͂Ȃ��A���炽�ɗ֑��Ȃǂ̕��ނ�V�����f�U�C���ŐV�����A�Z���u�������V�����{���Ƃ�����ł��낤�B
�ے��E�b�E�b�Ղ̔z�u�A枓栱�≡�ˍނ̎g�p�A�e�풌�ԑ��u�̔z�u�A���Ԃ̈����A�V���˂̎g�p�Ȃǂ̓��F����A�Z���u���ɂ��ẮA����ɂȂ�̂ŏȗ����邪�A����͖{���ɂ���Ė��炩�ɂ���Ă���̂ŁA�Q�Ƃ𐿂��B
�ꌾ�ł����A���R�Ԃ̋��֑��ƑO�{���y�їR���s���̕��ނ����ꂼ��Ɏv�������[�����Ďg�p���A���ʓI�ɂ͗��z�̐^�@�w�{���`����ڎw���v�悵���z�������Ƃ��悭�����錚�z�ƕ]���ł���̂ł͂Ȃ����B
�@��y���{�����ʐ}�@�@�@�@�@�@��y���{����b��}
�@�Ȃ��A��y������͖��������̌��z�Ǝv������A�u��y������͋����y���q�@�̖�ł���v�Ƒ�����̏Z�l���畷�����ꂽ�Ƃ������`�Ȃǂ�����A�T�d�Ȓ����Ȃǂ�v����B
2024/10/26�B�e�F
�@������y���R��P�@�@�@�@�@������y���R��Q
�@��y���R�剡����F�������ĉE�s꜂ɐΑ��߉ޔ@�����������u����Ă�����꜂ł���B
�@�{���O�w�̐��ʂƑ��ʂɂ͐�ڞ�����炷�B�i���R�A�֑��ɂ͑��݂��Ȃ��j
�@�@�����͌a��30�����̊ے���ɑ�ւ���炵�A�e����ɓ��іؕ@�Ƒ�֖ؕ@������B�g���͏o�O�l�I�ؕt��p����B
�@�@�ے��͍��v�P�Q�{���m�F����A�������֑��͕��R�Ԃ̌��z�Ǝv����̂ŁA�֑��̒��P�Q�{���]�p���ꂽ�Ɛ��肳���B
�@�@�Ȃ��ے��ȊO�̒��͑S�Ċp���ł���B
�@�@�i���w�ɂ��Ă͏ȗ��j
�@�{���̓��F�̏o�F�͐��ʂɁu�嗓�ԁv���������Ƃł��낤�B
�@�@�����炭���̑嗓�Ԃ̐��@�ɍ��킹�āA���ʂ̒��Ԃ����߂�ꂽ���̂Ǝv����B���������̑嗓�Ԃ̏o���E�R���͖��𖾂ł���B
�@�@�@�����̑嗓�Ԃ̎ʐ^�͍���͎B�e���Ă��Ȃ��B
�@�@�@�������A��Ɍf�ڂ��Ă���@2021/03/15�B�e�́u����t�̉ޗː����̗z�����̒����v�����̑嗓�Ԃł���B
�@�@�@�@���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v���R�����u��y���̌��z�ӏ��ɂ��āv��
�@�@�@�@�@�ʐ^�i�\�Ɨ��j�Ǝ����}�y�щ��
�@�@�@�@�Z�@�u���@��v�����ʊ�e�u��y���̌��z�������猩������́v��
�@�@�@�@�@�ʐ^�y�щ��������B
�@���q���{���g�ɐ��ʂƓ��������X�����������B
�@������y���{���P�@�@�@�@�@������y���{���Q
�@��y���{�������P�@�@�@�@�@��y���{�������Q�@�@�@�@�@��y���{�������R�@�@�@�@�@��y���{�������S
�@�{��富ҁF
�@�@���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v�@���
�@�@�{������富ҁF�{�����ʂɂS�ʂ�富҂��t�����A���̗����͕s���ł���B
�@�@�@�S�ʂƂ��{富ҁi������富ҁj�ł���A�ӏ��́A�O���������č�����~�E���E���O�E�e�ł���B
�@�@�{�����q富ҁF��ʂ���A�Ƃ��ə���т��̖{富҂ł���B���͗���ŁA���ʂ́E�_�E�Ή��E���g�A���ʂ͉_�E���g�ł���B
�@�@�@�@�{������富҈ӏ��@�@�@�@�@�@�{�����q富҈ӏ�
�@�{������富ҁE�e
�@�{�����q�ӏ��P�@�@�@�@�@�{�����q�ӏ��Q�@�@�@�@�@�{�����q�ӏ��R�@�@�@�@�@�{�����q�ӏ��S
�@�{�����q富ҁE�E�̕\�@�@�@�@�@�{�����q富ҁE���̕\�@�@�@�@�@�{�����q富ҁE���̗�
�@�{���O�w�����E枓栱�P
�@�{���O�w�����E���ԑ��u�P�@�@�@�@�@�@�{���O�w�����E���ԑ��u�Q
�@�{���O�w�����E���ԂP�@�@�@�@�@�{���O�w�����E���ԂQ�@�@�@�@�@�@�{���O�w�����E���ԂR
�@�{���O�w�����E���ԂS�@�@�@�@�@�{���O�w�����E���ԂT
�@�{���O�w�����E枓栱�Q�@�@�@�@�@�{���O�w�����E枓栱�R
�@�{���O�w�����E����
�@���ɂ͉~�����̒f�ЂƖؕ@���c��B�ے��͖{���ċ��ɂ�����A����葵�������̒f�Ђł��낤�Ɛ��������B
�@�ؕ@�ɂ��Ă͏[�����鏊��������������ł��낤�B
�@�֑��ے��f���F�オ���̉��[�@�@�@�@�@�{���ؕ@���̂P�@�@�@�@�@�{���ؕ@���̂Q
2020/10/11�lj��F
�����������y�������̍s��
���u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv���q���q�A����ސV���A2020�@���
�@�����ېV�́u�_�������v�ŁA�������R�̑m���͑S�Ċґ��A���y���͔p���ƂȂ�A�A�y�������͉�₂���A�k�R�_�Ђ��ł����グ����B�����Ȃǂ��S�~���l�ɏ����������A����������̂��̂͋ߗׂ̎��@�ɑJ�����A��������B
���݁A���������������Ă��閭�y�������͎��̂悤�ł���B
�����y���u���{������ɎO�����F
�@���{����@�ɑJ�����A���݂͕���@�{���������ĉE�̎߉ޓ��Ɉ��u�����B
�A���A�u���{���͈���ɎO���ł��������A����@�ł��ގO���Ƃ����J����A�Ȃ��ގO���Ƃ��ꂽ�̂��͕s�ڂł���B
�����̑ٓ��ɂ͊����W�E�X�N�i1668�E69�j�̏C������������A�ٓ���舢��Ɍo���������ꂽ�Ƃ����B
�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv���q���q�@���
�@���y���u���{������ɎO���P�@�@�@�@�@���y���u���{������ɎO���Q�@�@�@�@�@���y���u���{������ɎO���R
�Ȃ��{���ł́w�����̌��w������[�Ɂu�\�O�d���v�������A���炩�ɖ��y���\�O�d����\���x�Ƃ��邪�A����͂ǂ����Ă��P�Ȃ�u�v�Łu�\�O�d���v�Ƃ͌����Ȃ��B������ƁA�M�̊��肷���ł��낤�B
2021/03/15�B�e�F
���{����@�߉ޓ����u
�@���y������ɎO�����P�@�@�@�@�@���y������ɎO�����Q�@�@�@�@�@���y������ɎO�����R�@�@�@�@�@���y������ɎO�����S
�@���y������ɎO�����T�@�@�@�@�@���y������ɎO�����U�@�@�@�@�@���y������ɎO�����V�@�@�@�@�@���y������ɎO�����W
�����y���n����F�O�����F
�@���{����@�{�����Ɉ��u�A���y������J���Ƃ����B�i�ǂ̓��F�Ɉ��u����J������Ƃ����L�ڂ��Ȃ��̂ŁA�s���Ȃ̂ł��낤�B�j
�O�����͍]�ˊ��̍�Ƃ���邪�A���������̒n����F�Ɨ��e���̎�͑S���Ⴄ�B�i�����炭�A�����Ƙe���͌����ʂ̂��̂ł������̂��B�j
�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv���q���q�@���
�@���y���n����F�O�����F�ʐ^�͒����ŗ��e���͎ʂ��Ă��Ȃ��B
�����P�U�N�i�ޗnj����䌧�ɕғ��̔N�j�䌧�m���̖��y��������{����@�ւ̈ڐ�����̂ŁA���̔N�ɕ����͑J���������̂Ǝv����B
2021/03/15�B�e�F
���{����@�{���Ǝ߉ޓ��Ԃ̌q�����Ɉ��u�����B
�u�p���̂ݕ������́A���v�Ŗ��y������J���Ƃ��ďЉ�����A���y���̂ǂ̓��F����J���ꂽ�͕̂s���A���y������J�������Ƃ̍������s���ł���B�܂��{���͍]�ˊ��̍�i�Ƃ����B
�@���y���n����F�O���P�@�@�@�@�@���y���n����F�O���Q
����������{�@����ɔ@�������F
�@����s���a�Ɋy�����A������U�O�����B
�Ɋy���͏�y�@�A�����Q�T�N�ɗ��ցA�������i���d���J�镧�̈ӂ��j�ł��鈢��ɔ@���������C������B���̎��A�w�Ɂu�V�䎜�o��t���E��a����������{�@�v�ƁA���������ɂ��u��a����������{�@�������{����Ɏ��o��t��]�X�v�̖n������������A�{������������{�@�̕����ł������Ƃ���������B
�A���A�{���������ېV�̔p���ʎ߂ŗ��o�����̂��A����ȑO�̑�����̏Ď����ɗ��o�����̂��́A�s���Ƃ����B
�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv���q���q�@���
�@��������{�@����ɔ@�������P�@�@�@�@�@��������{�@����ɔ@�������Q
���������n����F�����F
�@����s�R�c�P�s�����A�ؑ��E������S�O�����A������܂ލ����͂U�T�����B
�P�s���͏�y�^�@�B
�{�����ڂ������͕��U�P�����A�����P�W�����̞w����Ղł���B�A���A��Ղ͌��X�m���������ɂ��o���グ�鎞�ɍ����̂��Ƃł���B
���̗�Ղ̓V���ʂɁu���������y�������V��݁v�u��i�ܔN�i1525�j�Z���g���v�̖n��������B�n����F��������̂��̂��ǂ����͕s���ł��邪�A�Q�c�����Ɉڂ��Ă����Ƃ�������A�{�������y���̈╨�Ɖ]����B
�@���A���A���������V�Ƃ͌��݊m�F���ł��Ȃ��A�s���ł���B
�@�����ېV�̔p���H�߂̎��A���y�����畧���E�����a�����ė~�����Ƃ̈˗�������A���̎R�c�̒n�ɂ���R�����Ŏ�������Ƃ����B
�P�s���ɂ͏�L�̕����Ɨ�ՁA���O���ɔ����|���A�R�c���ɑ�t����a�����Ƃ������A�P�s���ȊO�͍s���m�ꂸ�ł���Ƃ����B
�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv���q���q�@���
�@�������n����F�����@�@�@�@�@����������@�@�@�@�@��������Ֆn��
�����y�������{������ɔ@�������F
�u�p���̂ݕ������́A���@�ޗnj������ҁv���q���q�@���
�@�Z�ʔO���@�̑厛�ł�����䗈�}����
�Z�E�̒k�ł́u�ؒ�����ɔ@�������̘@��ɖ��y�������̖{���ł���ƋL����������ǂ��Ƃ�����B�v�Ƃ̂��Ƃł���B
��ɂ͈������▭�y���̑b���u�����Ƃ������B
���̑��������`���̕�������֎��̋[���P���K�i�̎萠�������Ă���Ƃ����B
2024/09/19�lj��F
���������`���̉��G�u�Ԓ��}�v�F�������̉��G
�Z�u2024/09/18�����V���[���L���v�@���
�������{�z�{�u�Ԓ��}�v�Ƒ�p�����ٖ{�u�Ԓ��}�v�͈�A�̉��G�ł���Ɣ������A����͑�a������̉��G�Ɠ`�������B
�@���[���L���̃^�C�g���́u�X�̂ӂ��܊G�@���_�͉p���Ɂv�ł��邪�A��a�������R���̓`�������邱�Ƃ��M�d�ȏ��ł���B
�@�������炭�͑��������y���̂����ꂩ�̎��V�ɓ`��������G�ł��낤�Ǝv����B
�P�V���X������������ψ���\�F
�@�P�D�������̍��_�ł������{�z�Ƃ̗���u�������i���ނ���j�v�ɁA���G�u�Ԓ��}�v������B�@�ʂ͖�170�~110�����̂S���g�ł���B
�R���͋{�z�ƂX��ڋ{�z�������吳�P�P�N�������Ŕ���o����Ă����{���G���w�������Ƃ����B
�@�{���G�́A���R�����]�ˏ����Ɏ��h�̊G�t�̎�ɐ�����̂ŁA�����k�Ƌ�𗬒����ł������Ƃ����������y���Ɋ�i�������̂Ɠ`���B
�@�Q�D�{���G�̊Ӓ�𓇔��V���i���w�K�@�勳���j�Ɉ˗��A�������͎R���P�玁(�������������E���h�����Ɓj�ɉ摜��]���B�R�����͊������������A�u��p�����ِ}�^�v���甎���ُ����̉��G�u�Ԓ��}�v�����o���B���́u�Ԓ��}�v�͏��a�P�O�`�P�P�N���ّ��i�ƂȂ����Ƃ����B
�@�{�z�Ə����̉��G�͏t�ƉĂ̐}���ł��邪�A�����ُ����̊G�͏H�Ɠ~�̂��̂ł������B
���G�Ƃ������̎g�p�ł͂Ȃ��A����̍��q���{���Z�@�ł��邱�ƁA�@�ʂ��قړ����ł��邱�Ɓi�ʐ^�ł̓Y��������A�@�ʂ��قړ������ǂ����͕s���j�A�{�z�Ɩ{�̉Ă̕��ɕ`���ꂽ�����͑�p�����ٖ{�̏H�̕��̐��ӂɂȂ����Ă���悤�Ɍ����邱�ƁA�u����i����j�v���O�b�œ����ł��邱�Ƃ���A�R�����͗��҂���A�̉��G�ƌ��_�Â���B
�������A�{�z�{�̍�҂͎��R�y�Ɠ`������A���̒f��͍��͂ł��Ȃ��Ƃ̗���ł���B
�@�B��a���������y�����G
�W���̉�����Ȃ�A�W���Ŏl�G��`���B
�������ĉE�̂S�����{�z�Ɩ{�̂S���ŁA�E����t�E�Ă�`���B
���S������p�����ٖ{�ŁB�E����H�E�~��`���B
2026/01/14�lj��F
��2026/01/07�����V���L���@���]��
�@�u��p�����ٓ��{���p�R���N�V�����v�W�������s���p�ًy�ё�㒆�V�����p�قɂĎ��{�����B
���̓W���̒��ł̒��ڂ́A��p�����ق́u�H�~�Ԓ��}���v�i���������y�������j�ƈ�A�̉��G�Ɣ��������X�������{�z�Ƒ��u�t�i�Ԓ��}���v�i���������y�������j����P�T�O�N�Ԃ�Ɉꓰ�ɉ�W�������Ƃ������Ƃ���������B
�@�܂��A��p�����ق̔��Α��ɕ`����Ă����A�����J�E�V�A�g�����p�ق́u�Պ������l�}���v�i���������y�������j�����A�莋�W�������Ƃ����B�i�Պ��͂��j
�@�ܘ_�A���̎O�_�͖����̐_�����R�߂ɂ���Ĕ��p���ꂽ���̂̈ꕔ�ł���B
�����s���p�فF2025/07/25�`10/18�A���V�����p�فF2025/10/31�`2027/01/31�J��
�@�H�~�Ԓ��}���E�t�i�Ԓ��}���F�B��a���������y�����G�F�������č��S�ʂ��H�~�Ԓ��}���A�E�S�ʂ��t�i�Ԓ��}��
�@�Պ������l�}���F���p�蒠�T�C�g����]�ځF�A�����J�E�V�A�g�����p�ّ�
���Q�l����
����a�����t�����_�i���E���_�Ёj
��a���\�s�S�����ɏ��݂���B
��q�̒�����y���̓�ɗאڂ���B
�܂��A�����Ɋω������c���A�_�������ȑO�̎Ђ̎p�����݂ɓ`����B
��Y���ɒ�������u�V��ː_�Ёv�Ƌ��Ɏ����Ёu���_�Ёv�̘_�ЂƂ����B
���Ђ̑n���E�R���͏ڂ炩�Ȃ炸�B�i�Ƃ������o�L�ڂ��ɂ܂�Ƃ������Ƃł��낤�j
�Z�u�����s�j �{�� /�㊪�v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���
���_��
�@[�a�B�܌S�_�А_�����嗪����]�i�u�܌S�_�ЋL�v�A�������j
�@���]�A�\�s�S���_�Ј���A���ݐ_�ˋ����R��R��A���]�T�≮�B�T�g�`���鏴�]�A�V���R���_�ЎҋT�Ô��̖���A���_�a�B�ΌA���߉]�X�A�T�g�`�m�����m�X�A�L�Iɕ��W�A
�@��l�l�āA�T�≮�A���]�V�ΌA�r����A�����Ή��ӎY����A���]���R����A���t����t�A�����t���t�唖�A���]�_�y���p���R�K�e�ؗt����
�@[��a�u]
�@���_�Ё@���i�u�H�v�̉��Ɂu���v�̊����j�x�Z�ݒ������̏t��
�@[��a��������]
�@���_�Ё@�i�����ɂ���A���A�t���Ə̂��j
�@�@�@��a���������E�L��
�Z�u�����s�j �{�� /�����v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���
�@�i����Ӂj
�@�Ր_�@���P�Ɛ_
�@�n���E���v�Ȃǖ��炩�łȂ��B�u��a�u�v�i���ۂQ�P�N�j�܂��u��a���������v�i�����R�N�j�ł͏t���Ə̂��Ă����Ƃ����B
�u�_�Ў撲���v�i�����V�N�j�A�u�_�Ж��ג��v�i�����P�Q�N�E�䌧�j�A�u���ג��v�i�����Q�S�N�j�A�u�@���@�l�@�ɂ��͏o���v�i���a�Q�V�N�j�����l�ł���B
�Ր_�ɂ��ẮA�ڂȂ炸�E�V���������E�t���l�_�E���P�Ɛ_�Ɨl�X�ł��邪�A�u�܌S�_�ЋL�v��u��a�u�v�̂悤�ɁA��Y�̓V�≮�_�Ђ���ː_�ЂƂ�����̂�����B
�@�i�_�ˋ����R��[�ɂ���A���ɋT�≮�Ƃ����B�j
�����F�Γ��Ă͖����Q�S�N��[�A�Ѝ���͏��a�P�U�N�����A�Β����͖����R�S�N�̕�[�A�L��̓쑤�ɂ͌��̎Ж����Ɗω���������B���ʍ����͈����Q�N�̖��A���̐Γ��Ăɂ͓V�ۂQ�N�̖�������B
�q�a�͂R�ԁ~�Q�Ԃ̐؍ȑ��łQ�O�N���̉��z�ł���B�{�a�O�̐Β����͈��i�X�N�ƕ����R�N���̈�ł���B
�{�a�͑f�̈�ԎЗ����i57�~89�����̕��ʂŌ��q�̏o60�����j���������A�S�O�N���̑��ւŌ��݂̉����͏��a�T�V�N�̕��ւł���B
����269�B
�ω����͂Q�ԂS�ʖ{�����ŁA�~�q���ɂ͖{���\��ʊω��i����50�����j�����u����B���݂��ω��u�P�P�˂���B
�]�Ԃ̈ʔv�ɂ͒勝��N�i1685�j��������B
�u�@���@�l�@�ɂ��͏o���v�̕ʋL�ɂ́u�]�O�͎Бm���Ǘ��A�_��������_���������đ��ЂƂȂ�v�Ƃ���B
-------------------
�ȏオ�u�����s�j �{�ҁv�̋L�ڂł��邪�A���̑��̃T�C�g�ł́A
�@�u�T�m�`���鏴�v�ɂ��A�Ր_�͋T�Ô䔄���Ƃ����B�_�a�͖����A������A������݂̂Ƃ���B
�u��a�u�v�i�]�˒����j�͎����Ёu���_�Ёv�𒆑��u�t�����_�v�i���݂̍��_�Ёj�ɔ�肷��B
�A���A����A�u��a�u���v�i�吳�R�N�j�ł́A�����Ёu���_�Ёv���Y���ɒ�������u�V��ː_�Ёv�ɔ�肵�Ă���B
�ȂǂƂ����B
�@���ڂ�����������C�͖ѓ��Ȃ����A
�@������ɂ��掮���Ёu���_�Ёv���������ł���������Ђɔ�肵�悤�Ƃ��鎖���̂ɖ���������B
�@��������ɁA�Ñ�̎����Ђ��S�ċߐ��E�ߑ�ɓ`�����Ă���Ƃ����O��ɖ���������A
�@�����̎����Ђ͔p�₵�Ă���ƍl����̂����R�ł��낤�B
�@�Ñ㎛�@�̑啔�͒����E�ߐ��E�ߑ�ɔp�₵�A������啔�����̔푒�҂̖��͌㐢�ɓ`����ꂸ�A
�@�_�ЂȂǂƂ�������ڂ��{�݂ł́A�Ȃ������O�ł͂��肦�Ȃ����낤�B
�@�����Ђ�����ɓ`���ƍl����͍̂��w�҂╜�Ð_���Ƃ̖��z��֑�ϑz�⋳����`�ł����Ȃ��B
�@�������āA���݁A�����̏t�����_�͎Ѝ������_�ЂƏ̂��Ă���Ƃ������Ƃ́A�����▾���ېV�̂���A�m���鍪���Ȃ��ɁA
�@�����Ђɔ�肳�ꂽ�Ƃ������ƁA�܂�t��ꂽ�Ƃ����C���`�L�ł������Ƃ������Ƃł��낤�B
���u�ޗnj��j�i�_�Ёj�v�ł͎��̂悤�ɂ���Ƃ̂v���������B
�Ր_�F�����݂��Â��i���P�Ɓj
�u��a�u�v�Ɏ����ЂƂ��āu�ݒ������̏t���v�Ƃ���Ĉȗ��u���쎮�v�_�����o�ڂ̏\�s�S���ɂ��Ă��Ă���B
�����̖��ג��ł́A�t���l�a���Ր_�Ƃ��Ă��邪�A���a�Q�V�N�u�@���@�l�ɂ��͏o���v�ɂ́A���P�Ɛ_��a�Ƃ��Ă���̂ł���ɏ]���B
�u��a�u�v�i���ۂQ�P�N(1736)�j�ł͏t���_�ЂƏ̂��A�u��a�����}�G�v�i�����R�N�i1791�j�j���t���_�ЂƂ��Ă���B
�@����a���������F���Z�F�\�s�S�@�ł͊��Ɂu���_�ЁF�����ɂ��荡�t���̂��v�Ƃ���̂ŁA�ߐ������ɂ͏t���Ə̂�������_�Ђɔ�肳��Ă���Ǝv����B
�u�܌S�_�ЋL�v�̂悤�ɓ�Y�̊�ː_�ЂЂɏ[�Ă悤�Ƃ���ِ�������B
��Ղ͏\���\���B�����ɓ�Ԏl�ʂ̊ω���������A����50�����̏\��ʊω������u����B
�]�Ԃ̈ʔv�ɒ勝��N�i1685�j��������B�����ȑO�͎Бm���_�Ђ��Ǘ�������s�����Ɠ`����B
���u�ޗnj������s�@��y���@�����������v��y������������A���s�F��y���h�Ƒy��F�吼�r��A2024�@���
�@���_�ЁF�Ր_�͕��P�Ɩ�
�u��a�u�v�i���ۂQ�P�N���j�ł͎������ЂƂ��u�t���v�Ƃ��̂���Ă����B�^�@��y���Ƃ͓��H�����ݓ쑤�ɗאڂ���B
�{�a�͏t������ԎЂł���B
�����ɓ�Ԏl�ʂ̊ω���������A���Ă͏\��ʊω����������u����Ă������A����ɑ������݂͍s���s���ł���B
�]�Ԃɒ勝�Q�N�i1685�j���̈ʔv������A���̓��̋N�����]�ˏ����ɑk��\��������B
���a�Q�V�N�u�@���@�l�ɂ��͏o���v�ɂ́u�]���͎Бm���Ǘ��A�_��������_�����������ЂƂȂ�v�Ƃ̋L�ڂ�����B
2024/10/26�B�e�F
�@���Ђ������Ђł��邩�ǂ������A�ߐ��ł͕����ƎЂ��A�_�����������Ă������Ƃ��d�v�Ȃ��Ƃł���B
�����āA���̋��������w�╜�Ð_���������ɐ_�������Ƃ������̖��߂ŁA�_���̍�������}�������Ƃ͌��͂̕|�����������̂ł��낤�B
�ߗׂ̒����ȎO�֖��_�⑽�������y�������ł͂Ȃ��A�����������̎Ђ�H�T���K�Ɏ���܂ŁA���ƌ��͖͂\�Ђ�U������Ƃ�����̗�Ƃ��Ď��グ��B
�����Ƃ��A���ЂɁA���ݕ����╧�����c���Ă���Ƃ������Ƃ́A���͂̎v�f�ʂ�ɐi�܂Ȃ������Ƃ������Ƃł��낤�B
�@�����t�����_�ω����P�@�@�@�@�@�����t�����_�ω����Q
�@�t�����_�ω��������F�����̎�ނ͔��f�o�����A�A����q�̂悤�Ɂu�����s�j�v�Ȃǂł͏\��ʊω��Ƃ��邪�A���̂悤�Ɍ����Ȃ����A
�@����ɑ������݂��s���Ƃ����̂ŁA�ʂ̕��������u����Ă���̂ł��낤���H
�@�����t�����_�q�a�@�@�@�@�@�����t�����_�{�a
����a���|�c������i���E�|�c�_�Ёj
�@�����̐_�������̏��u�̌�A������͒|�c�_�Ђ̒��̐_����������̎c��̂悤�Ȉ����ł��邪�A���Ȃ��Ƃ��ߐ��ł͑�������|�c�_�Ђ��Ǘ����Ă����̂����ԂƎv����B
�@�]���āA�y�[�W�͋ɗ͑��������̂Ƃ��ċL�q����B
�Z�u�����s�j �{�� /�㊪�v���������s�j�Ҏ[�ψ���
�ҁA1987.3.�@���
�@���|�c�����
�@�\���`���F�R�ԁ~�R�ԁA��d�A��`���E�����{�����A���ʋy�ёO�[�Ԕݕt�A
�����Ɣ݂ɂ͑g����p���Ȃ��B���ʂ͒��Q�{�̔ݒ�����o�������������Ē����Ԃ̉���������ɕ������낵�Č��q���̈����Ƃ���B
�w�ʋy�ё��ʌ���Q�Ԃ͌�������i���˂�`���Ƃ��Ĕ݂̉�����艺����B
�@�R���E���v�͖��炩�łȂ��B
�����͔w�ʌ���ɉ~�������ĕ��d���\����B���d�͐~�q�Ƃ��đ���@�������u����B
�~���Ԃɂ͊G�͗l���{����������n���A����ɘg�g�̉ԕI��u���āA���̏�ɑ�ւ�������قȍ\���ł���B
�S���Ɂu��i�O������i1708�j�v�̍���������A�����炭���̎���̌����E����ƌ��Ă悢�B
�@���|�c�_��
�@[�a�B�܌S�_�А_�����嗪����]�i�u�܌S�_�ЋL�v�A�������j
�@�|�c�_�ЁA�͕݉Ӌ��|�c���͕�
�ЉƎ҉͕ӘA���]�A�|�c�_�ЎғV�ƍ��ƕF�Ζ�����A���ЕӗL�Y����A����ݑ����Α�|�A���ĉ]�|�c�A�y���m���V�c�䐢�A�j�����c�����F�Ζ����������������Ė����j��@�Ȍ���|�씢����V����A�����V�c�ߏܔ��A�َ��|�c��ӘA
�@[��a�u]
�|�c�_�Ё@���|�c�����̎O�\���Ёy�����z
�@[��a��������]
�|�c�_�Ё@�i���|�c���ɂ���B���O�\���Ёy�����z�Ə̂��B�u�_�����v�ɏo�Áj
�@�@�@��a���������E�L��
�@[������������]
�|�c�_�Ё@�i�E�����ɂ���B���O�\���Ёy�����z�Ə̂��B�_�����ɏo�Áj
�Z�u�����s�j �{��
/�����v���������s�j�Ҏ[�ψ��� �ҁA1987.3.�@���
�@���|�c�_��
�Վ��F�V���v�R��
�Ր_�ɂ��Ă�
�u�_�Ж��ג��v�i�����Q�U�N�j�ł͓��b���A�u�@���@�l�@�ɓ͏o���v�i���a�Q�V�N�j�ł͓V���v�R���A�u��a�u���v�ł͒|�c���̑c�E�Ζ����i�V���v�R���j�������Ƃ���B
�@�������F�|�c���̑c�E�Ζ����i�V���v�R���j�ɂ��Ắu�����^�v�ɏڂ����B�������A�_�b�ł���A�j���ł͂Ȃ��B
�@�u�����^�v�̑�ӂ͉��̌f�ڂ�
�@�@�Z�T�C�g�F�_�Џ��V�^���|�c�_�Ђ̊T�v�@�ɂ���̂ŁA�Q�Ƃ𐿂��B
�����Џ��Ђɔ�肳��Ă���B
�u��a�u�v�ł́u���̎O�\���Ёv�y�����z�Ƃ���B
�@�����������ɕ��v�R�N���̈�̏�铔�A
�@�@�@�@�@�@�@�@�@���̍����̐��Ղɂ́u�O�\���Б�����@���ۏ\�l�N�сi1719�j�\�ꌎ�g���v�̖�������B
�����{�݂͎��̒ʂ�ł���B
���ʂ̐Β����͖����R�X�N�̕�[�ł���B
�������匠���i�Δ�E�����U�N���j�A���̑O�ɂ͕��v�R�N��[�̐Γ��Ă�����B
�Ж����������ق͂V�ԁ~�R�ԁA�s�ғ��͗����E�����������ŁA�����s�ґ��i����53�����j���J��A���E�ɐ����̑O�S�E��S���T����B
�@���Ж����������ق͋��ɗ��Ƃ���T�C�g������A�W���쌩�ł��낤�A�ߑ�ł͑����x���̐_�Ђ͐_���ł͂Ȃ��Бm���Ǘ��ɗ^��A�m�����풓���Ă����Ǝv���A���Ƃ���A�ɗ��Ə̂���̂��Ó��ł��낤�B
�u�@����ʁv�ƍ�����ԛ���̐Γ������B
����ɐ��̐Γ��Ďc�����U������B
���̍��ɕ�⸈������A���ʂɁu��⸈@�ێ������Z�сi1741�j�O���\�ܓ��A���֖���V���n�v�v�̖������ށB
�@���_�{��������͕�`�������{�������A�S�ԁ~�R�D�T�ԁA�S���Ɂu�a���\�s�S���|�c�W������v�Ȃǂ̖�������B
���ʘk���i�a20�����j�ɂ́u�{�哖�W�^���Y�@�������\�i1824�j�v�Ƃ���B
�{���͑���@���i�����W�W�����j�B�E�ɔ@�ӗ֊ω����A���ɍO�@��t�������u�B
�L�됳�ʈ�̐Γ��Ă͊����Q�N�i1749�j�̖�������B�q�a�͊��q�a�ŁA���a�T�X�N���z�A�؍ȑ������V�������A���ʂR�ԁ~�Q�Ԃł���B
�q�a���͓���Œ���Ɩ{�a���j���ɂŌq���B
�{�a�͈�ԎЏt�����i83�~62�����̕��ʁA���q�̏o62�����j�����w�畘���B�������ĉE�̏t�����̎Гa�͌����_�Ёi74.5�~109�����Ō��q�̏o53.5�����j�ł���B
��ړ��i�u�얳���@�@�،o�^�J�^�^�@����v�j������u�������S�@�����ܐ\�g���v�Ƃ���B
�@�@�������ł���A���Ԃ͕s�ځB
���̖k���ɐʋ����肪�����A�V���U�N�i1786�j�̖��ł���B
�����R�X�O�B
�@���i������j
�|�c�_�Ђɗאڂ��đ�����̓�������A����͂��Ƃ͒|�c�_�Ђ̐_�{���ł������B
������͂R�ԁ~�R�Ԃ̕�`���ŁA���w�ɑ���@�������𒆉��ɁA�n�����摜�E�O�@��t���Ȃǂ��J����B
���̖�t�@������������������ɑ����A���̂܂܂ł���B�A���~�q�͎c��A��i�U�N�i1709�j�̔N�I�Ȃǂ�����B
�{������@�����͖ؑ��f�n�ʊ�̒h�������A������100�����ł���B������͓����̂܂܂ł���B
�܂��A���ɂ͖n����������B�O�����N�i1555�j�ɓ�s�h�@���t������̍�ɂȂ�B
���a�T�S�N��t�@���ƂƂ��ɓ���ɑ������A���̑��͖����ɖ߂��Ă���B
������̌��������ł��邪�A�S���Ɋ��i�R�N�i1626�j�̍���������A�����ו��̗l���ƃ}�b�`����̂ŁA���̍��̌����Ƃ݂Ă悢���낤�B
�@���|�c������@�@�@�@�@�@��������ʐ}�@�@�@�@�@�@������{������@������
�@���ؑ�����@������
������{���ŁA�����E�A���g�̍����ł���B
�w�̊�ؑ��A�f�n�A�ʊ�Ɠ��B����100�����B
�����ɖ�������A���̑S�e�͎��̒ʂ�ł���B
�@���������@�������ٓ���
�O�����N�����A���l�Y�ȂǏh�@���t�����삵�A�J��͋�ɕ��ƕ�����B
�Z�T�C�g�F�_�Џ��V�^�@���
�|�c�_�Ђ̊T�v�F
�@���Ђ̑n���ɂ��āA�w�V����^�x�����_�ʂɉΖ����̎q���ł���Ƃ����u�|�c��ӘA�v���L�ڂ����B
�@�w�V����^�x�i��Ӂj
�m���V�c�̌��A��a���\�s�S�̌Y���̕ӂ�ɒ|�c�_�Ђ�����B��������_�Ƃ��A���̒n�ɏZ��ł���B�Β|���傫�������������̂Ŕ��|�Ƃ��Č��サ���Ƃ���A����ɂ���Ē|�c��ӘA�̐����������B
�@���ꂪ���̂܂ܓ��Ђ̗R���ƂȂ��Ă���B
����A
�@�V����^�x�ɂ͑��ɂ������Ƃ��ē����������_�ʂɉΖ����̌ܐ����A�����Ė��̌���ł���u����|�c�A�v���L�ڂ����B
�@�w�V����^�x�i��Ӂj
�@�q�͒|�c�ܖ��ł���B�i�s�V�c�̌��A�c�������c�A�������悤�Ƃ����Ƃ���A��̊Ԃɂ��̓c�ɋہi�^�P
/ �����̂��j���������B�V�c�͂�����ۓc�A�̐����������B��ɉ��߂ē���|�c�A�Ƃ����B
�@����ɂ��u�|�c�v�Ƃ͖{���́u�ۓc�v�̈ӂ������悤�ł���B
�@����u����v�Ƃ͍c�q�̗{��ɂ�����E���ł���ƍl�����A����|�c�������������E���ɏ]���������Ƃ��M����B
�@����ɑ���|�c��ӎ��͂����Ȃ�E���ɏ]���������͕s���Ȃ���A�|�̔������サ�����Ƃ���{��̒�����z�V���i��V�v�i������Łj�ł��������Ƃ����������B
���̗����͉Ζ�����c�Ƃ�������n�����ł���A�����̔����n�������{��̒�����c�q�̗{��Ȃǂ�E���Ƃ��Ă��邱�Ƃ��狰�炭����������P�����̂ł��傤�B
�@�܂����Ђ͓c���{�����ɒ�������u�����\�u���s��Ð_�Ёv�̔H�X���v���ܔN�i1149�j�ɒ�o�����w���_�{���i��x�ɂ����y������A���Ђ̎�{�ł��邱�ƁA��Ր_�́u�V�����ƉΖ����v�ł���|����_���Ƃ��Ă��邱�Ƃ��L����Ă���B
�@���݂͂ǂ��ł��邩�͕s���Ȃ���A���������ɂ͒|����_���Ƃ��Ă����Ƃ����A�܂��Ɂw�V����^�x�̋L���Ɋ�Â��|�����ˑ�Ƃ��Ă݂̂Ȃ炸�ꑰ�̏ے��Ƃ��Đ_�����������̂ł��낤�B
�@���̈���œ��Ђ��u�����\�u���s��Ð_�Ёv�̎�{�������Ƃ̂͂ǂ̂悤�Ȏ���������̂��s���ł��B
�@�܂��哯�O�N�i808�j�ɐ���������w���w�哯���ڕ��x�ɂ͓��Ђɓ`����Ƃ��āu��T���i�J�n�m�w�j��v�u���v���i�^�P�^�j��v�u�^����i�\���J���j��v�Ƃ����O��ނ��̖o�ڂ���Ă���B
���u��a�E�I�Ɂ@���@�_�Ў��T�v�@���
�|�c�_��
�@�����݂ɒ����B�����ЁB�Â��͎O�\�����ЂƏ̂������A�u���쎮�v�_�����\�s�S�́u�|�c�_�Ёv�Ɏ���i��a�u�j�B
�u�V����^�v�����_�ʉ��Ɂu�|�c��ӘA�A�����i�Ζ��j�ܐ��V���A�m���V�c�䐢�A��a���\�s�S�Y���V�ӗL�|�c�_�ЁA���Ȉ��_�A�����Z���A�Β|����A���䔢�|�A��䢎��|
�c��ӘA�v�Ƃ���A�|�c��ӘA�̎��_�ŁA�Ζ������J��Ɛ��肳���B
�|�c��ӘA�͒|�c�_�Ђ̏j���ŁA�u��T����v�u���v����v�u�^�����v�Ȃǂ̖����`���Ă����i�哯���ڕ��j�B
�����ɂ͂��Ɛ_�{���̑����������A�O�����N�i1555�j�ɏh�@�i���ޗǎs�j���t�����E���l�Y���q�ɂ���č��ꂽ����@���������u�B
-----------
���y�����z
���O�\����
���䏊�s�ό��z�[���y�[�W���ό��K�C�h���_�Е��t���O�\�����@���
�@�@��20���N�ԁAHP���^�c���Ă������A20���N�ɂ��ď��߂Đ_�Ђ̉���Łu�܂Ƃ��ȁv�y�[�W�ɑ�������B
�@�@���݁A�_�ЂƏ̂�����̂́A�قڑS�āA�����̐_�����R�߁i�_�������߁j�ł��̗R���E�Ր_�E�Ѝ��Ȃǂ����w�╜�Ð_���Ȃǂ�
�@�@��₁E�t���Ă���Ǝv���Ă悢�B�ɐ���n�z��Ёi���݂͏o�_��Ёj�Ƃŗ�O�ł͂Ȃ��A���̐_�Ђǂ͉����Ēm��ׂ��ł��낤�B
�@�@����āA���̌����ȉ���Ɍh�ӂ��A���Ɍf�ڂ���B
��R���E�����
�@�w�O�\���Ёx�Ɩ��̂��_�Ђ͊��E�l���n���𒆐S�ɏ\���Ђ��邪�A���̌�R���A��Ր_�͂��ꂼ����ł���A�_�Ж����w�O�\�����_�Ёx�w�O�\���_�Ёx�w�O�\���_�Ёx�Ȃǂ��܂��܂ŁA�ǂݕ����w���イ�͂��x��w�݂���x�ȂǁA��������ł���B
�@�����A���̔�������1�ł���A��q�̗��R�Ō�R���A��Ր_�����ꂼ��̎ЂňقȂ�悤�ɂȂ����Ǝv����B
�@�e�n�́w�O�\���x�Ɩ��̂��_�Ђ̋N���͋g��̋����R�ɋ��߂邱�Ƃ��ł���B
�@���q����ɏ����ꂽ�w�����R�閧�`�x�̊���w�O�\�����{�n��瑃m���x�ɂ́A
�@�w�E�E�E�s�Ґ_�R�j���e���{�����m�O�\�����m��_�������A���n���F�����胒���V�e�A������Ώt���F�쓙�������e�{�������X�A���j�썑�m�v������B�����O�\���_���V�e�ꏊ�j���k�B�{�n�n�����A��瑃n��g�����c���g�g�׃��E�E�E�x
�Ƃ���A���s�ҁi�����p�j���������A�t���A�F��Ƃ��������{�̖�������_�A�O�\���_�������R�Ɋ������A�J�����Ƃ���Ă���B���ꂪ�O�\���_�Ђ̂͂��܂�ł���Ǝv����B
�@�����A�w�O�\���x�Ɩ��̂��_�Ђ͎��̕~�n���Ɍ��Ă��Ă�����A���Ɩ��ڂȊW�����_�Ђ̐ێЁE���ЂƂ��Č������ꂽ���̂������B
�@����䂦�A��������ɓ���_���������O�ꂳ��Ă����ƁA�_�ВP�Ƃł̌�R���A��Ր_�̐������K�v�ƂȂ�A�����̐_�ЂŁA�����F�̋����A���s�҂����������Ƃ����O�\���_�Ƃ͕ʂ̌�Ր_���f����悤�ɂȂ����ƍl������B���̌n���������A�w�O�\���x�́w�O�x�ɒ��ڂ��ĎO������Ր_�Ƃ���p�^�[���A���ۂɎO�\���_���[�Ă�p�^�[���ɑ�ʂ����B
�@�O�҂̗�Ƃ��Ă͓ޗǂ̏t����Ћ����ɂ���w�O�\�����_�Ёx�ŁA�����͐_���V�c�ƈɎדߊ�A�Ɏדߔ��̎O�����J���Ă���B��҂̗�Ƃ��Ă͓��Ђ����s�啟�ɂ���w�O�\�����_�Ёx�ŁA�{���_�i����ōՂ���_�j�O�\�Z�_�ƈɎדߊ�A�Ɏדߔ��̎O�\�������J���Ă���B
�@�n���̕��̂��b���
���T�C�g�F�y�����̖��t�̔菄��z�@���]��
�@�������ړ��F�h�����đ�ڂ������ǂł��邪�A�����s�j�ɂ��u�얳���@�@�،o�^�J�^�^�@����v�j������u�������S�@�����ܐ\�g���v�ƍ��ޑ�ړ��Ǝv����B
2024/10/26�B�e�F
�@���|�c������P�@�@�@�@�@�@���|�c������Q�@�@�@�@�@�������⸈�
�@�������⸈����F���m�ɔ��ǂł��Ȃ����A�����s�j�ɂ��u��⸈@�ێ������Z�сi1741�j�O���\�ܓ��A���֖���V���n�v�v�ƍ����Ƃ����B�u���֖���v�̈ӂ��͂����肵�Ȃ����A���Ȃ�i�S�ցE���ցj�̔@���̋��ł͌��ѕt���Ƃ������Ӗ��ł��낤���B
�@��⸈E�s�ғ��@�@�@�@�@�s�ғ������s��
�@�O�\���Дq�a�@�@�@�@�@�@�O�\���Ж{�a�F�{�a�͈�ԎЏt�����A�������ĉE�������Ђł��낤�B
2006�N�ȑO�쐬�F2025/09/23�X�V�F�z�[���y�[�W�A���{�̓��k
�@
|