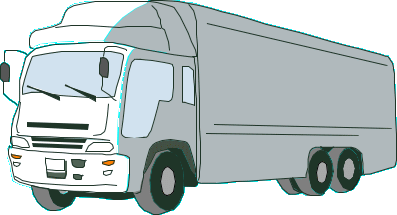
違法駐停車していた運転者の責任
違法駐停車車両に事故責任を問えるか、という問題は、人身事故と物損事故とに分けて考える必要があると思います。
人身事故については、自動車損害賠償保障法3条が「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によって他人の生命又は身体を害したときは、これによって生じた損害を賠償する責に任ずる」と規定しているところから、「運行」のなかに駐停車も含むと解する有力説に従えば、比較的容易に違法駐停車車両の責任を追及することが可能ということになります。
物損事故における違法駐停車車両の責任追及は、民法709条の問題に他ならないわけです。
民法709条により、他人に発生した損害を賠償しなければならない義務が生じるのは、一般的に次の要件を満たすときといわれています。
①責任能力ある者が
②故意または過失により
③他人の権利もしくは利益を違法に侵害した行為によって
④損害が発生したこと
つまり、違法駐停車した運転者の行為が不法行為といえるためには、違法駐停車によって事故が発生したといえるか、ということです。
お前さんが、そもそもこの場所に駐停車しなかったらこの事故は発生しなかった。こう主張できるとき、たしかに、原因・結果の関係(因果関係)はありそうですから、違法駐停車した運転手の不法行為責任を問えそうですね。
平たく言えば、因果関係とは、Aという事実によって(原因)、Bという事実が発生した(結果)という関係をいうんですね。
因果関係の例としてよく知られているのが「風が吹けば桶屋が儲かる」の話です。
①風が吹けば埃が舞う。
②埃が舞えば埃が目に入る。
③目に埃が入れば目を悪くし、めくらになる人が出てくる。
④めくらが増えると三味線が売れる。(昔は盲人が三味線を弾いて生活の糧を稼いだ)
⑤(三味線の音響部分の皮は猫の皮を使っているから)三味線が売れれば猫が減る。
⑥猫が減ればネズミが増える。
⑦ネズミが増えれば桶をかじるネズミも増える。
⑧桶をかじられれば、桶を買う人が増えて桶屋が儲かる。
⑨桶屋が儲かれば…
このように、風と桶屋という、一見全く関係のないもののように思われる二つのものが、原因、結果という名のもとにつながっていく。因果関係というものは、このように理屈をこねれば限りなく広がっていってしまうというたとえ話です。
ところで、保険実務における実際の事故において、保険会社は、違法駐停車車両に一方的に契約者が追突した事故においては、基本的には、契約者がわの一方的責任事故として扱っています。何故でしょうか。
たしかに、違法駐停車と事故発生という両者の関係は、客観的な事実的見地から判断すれば、原因・結果の関係にある。しかし、それはあくまでも事実的因果関係が存在したことにすぎ、その存在をもって即法律的見地からの因果関係も存在したことにはならない。こう保険実務が判断しているからです。
別の言葉で表現すれば、法律上の損害賠償義務が発生すると認められる原因・結果の関係(相当因果関係)が存在しないから、不法行為責任は追及できないとしているからです。
この保険実務の考え方は正しいと思います。なぜなら、違法駐停車車両に一方的に追突・接触した事故においては、事故発生原因は、追突した側の一方的不注意によるものと判断されるケ-スが一般的だからです。
では、どのような場合に、違法駐停車と発生事故との間に法的因果関係(相当因果関係)を認めることになるのでしょうか。
道交法上、駐停車車両の運転者には、つぎのような義務が課されています。
①「車両は、駐車するときは、道路の左側端に沿い、かつ、他の交通の妨害とならないようにしなければならない」(47条2項)
②「車両等は、夜間、道路にあるときは、政令で定めるところにより、前照灯、車幅灯、尾灯その他の灯火をつけなければならない」(52条1項)
保険会社の資料によると、これらの規定に違反し、後続車両に対する危険を増大させた場合には、駐停車車両にも責任が発生するとしています。
つまり、事故発生に対する法律上の因果関係を認めて、駐停車車両側の不法行為責任が肯定されるとするわけですね。
そして、この資料によれば、駐停車側の過失を認定した二つの判例を紹介していますので、これをみていくことにしましょう。
まず、第一の事例として次の判例を紹介している。
霧がかかって前方の見通しが悪く、路面が凍結していた国道において、A車にB車(普通貨物自動車)が追突。両者話し合いのためにその場に車を止めた際、B車が尾灯を点灯させないまま停車していたために、後方からきたC車(大型貨物自動車)がB車に気づくのが遅れて追突した、という事故につき、岡山地裁は、つぎのように判示して、B車の過失20%とした。
「B車は第一の事故の発生後、後続車両に対して、自己運転車両が停車中であることを示す措置(尾灯の点灯)を怠ったことが、本件第二の事故を引き起こす一因となった」(昭和58.5.30判決)。
第二の事例として、次の判例を紹介している。
交通整理の行われていない交差点でのA車(普通乗用車)とB車(自転車)との衝突事故で、C車(普通貨物自動車)が、その交差点直前部分(A車から見て右側、B車から見て左側)の駐停車禁止区域に駐車していたという事案につき、千葉地裁は、つぎのように判示して、C車に対し20%の過失責任を認めた。
「事故の主たる原因はA車、B車双方の過失によるものであるが、C車の駐車と本件事故との間には相当因果関係がある。その過失割合は本件事故の損害額の20%にあたる」(平成6.1.18判決)。
そして、この保険会社発行資料は、これらの判例から判断して、駐停車車両に不法行為責任が問われる要件としては、駐停車の場所が不適切であること等により、当該道路の交通の危険が著しく増大したことをあげている。
そして、その判断は、以下の諸事情を詳細に調査し、総合的に考慮して決定するとしている。
①当該道路の広狭
②事故当時の交通の状況
③夜間か昼間か
④後方から進行してくる車両からの見通し
⑤駐停車の方法
⑥駐停車により他の交通に生じた支障の程度
⑦駐停車の際に必要とされる措置を運転者が講じていたか否か…
以上述べてきたように、そもそも、駐停車車両の過失責任を問えるかどうかは、当該駐停車車両と事故発生との間に法律上の損害賠償を科すことが相当と認められる原因、結果の関係(相当因果関係)が肯定されるかどうかということであり、肯定されれば、違法駐停車した車両の過失責任を問えるということです。
しかし、現実の保険実務においてはどうでしょうか。違法駐停車車両の不法行為責任を厳格に追及するようになれば、保険金の支払いはかなり複雑なものとなるでしょうし、なによりも、保険金の迅速な支払いという面において種々の問題が生じてくるのではないでしょうか。
(平成18年5月15日)