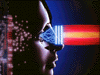



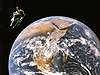
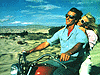
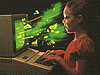
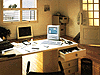
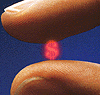
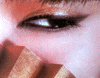

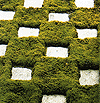
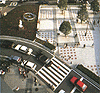


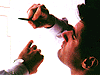

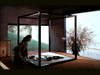
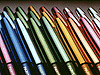
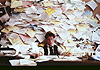
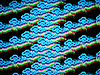
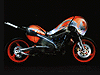

デザインの歴史は、第2次世界大戦以降の飛躍的に伸びたものづくりの歴史と呼応しています。
東京でオリンピックが開かれた1964年までを最初の10年として、今日までの10年ごとの様子を見てみましょう。
デザインは生産合理性を踏まえながらも簡潔な美しさをもたらす手法として驚きをもって迎えられました。ただ残念なことに、デザインは見違えるほど印象を変える魔法だと単純に認識されてしまいます。しかし幸いだったのは「デザインものは売れる!」というジンクスが企業人達にささやかれ、デザインの価値が定着しはじめたことでした。
通商産業省は一早くデザインの力を見抜き、加工製品輸出貿易に頼らざるを得ない日本の国情にデザインは欠かせないと判断して、デザイン啓蒙のためにデザイナーの海外派遣制度を作り尽力をそそぎはじめます。
我が社の設立者達も西ドイツや米国に留学するチャンスを得て学んだ経験を持ちかえりました。GKが会社としての設立したのは1957年ですが、ここに見られるプロダクト製品のデザインや提案がその成果に相当するものです。
これらは高く評価され、新聞紙上をにぎわす新鮮で効果的な欧米化現象としてもてはやされました。 しょう油卓上びん、オルガン、ユニットコア−計画や公共施設計画などです。
1973年のオイルショックまでの10年間を次なる第2段階とします。日本は高度経済成長を遂げ、デザインは生活の広範囲なモノに活用されるようになりました。豊かな性能を大胆なパワ−感に表現したり、洗練された流麗な美しさの表現にしのぎが削られました。デザインがさまざまなものに応用できることが理解されはじめたときでした。
エナ−ジクライシス後の10年間を次なる第3段階とします。これまでの路線が大きく修正される時を迎えます。例えば車のデザインはそれまでのパワ−、スピ−ドの追求から一転して、経済効率と安全で人にやさしい道具へと大きな変身をとげはじめます。デザインは初めて厳粛に時代が抱える社会性と正面から対峠する時を迎えます。
東京大学の社会学者木村教はそれを評して「体が喜ぶことを求める商品づくりの時代は終わりを告げた。これからは頭の喜ぶ商品がもてはやされる時代になるだろう。」と未来予測をしています。その例として示されたのは、前者は高性能車に乗ってクルージングする時のワクワクするドライブ感覚を代表例に。そして、後者の代表例にはファミコンが画面いっぱいに繰り広げる目くるめくゲ−ム世界に引き込まれてしまう楽しさでした。
そして80年代後半に入り第4段階を迎えます。頭が知的に納得し喜ぶという心の豊かさが求められはじめます。社会性と正面から取り組むことへの反動として自分をもっと大切にしたいという個性化が一挙に花開きます。世をあげて多様性が求められ、さまざまにデザインされたモノが自己を主張する市場はこれまでにない活況を呈しました。
当時、評判を呼んだ腕時計のブランド名を借り、スウォッチイズムという言葉が製品デザインの差別化を細かく行なうという革命的な手法を表わす代名詞になりました。人にやさしいインタ−フェ−スが重要視され、非物質性のためのデザインが脚光を浴びはじめます。
デザインには個性や独自性が求められ、あれもこれもと生みだしても尽きることがないという稀有な状況におかれています。今、日本のデザイナ−は手の休まる暇もないという史上初の大変忙しい時代を迎えています。その割には儲からないというのはまた別のことですが…。そして問題もおきてきました。
選択するのに困るほどに市場に溢れるモノ。モノ相互の関係が取りにくくなってきました。こうなるとモノを選ぶがわの見識なしではどうしようもありません。暮らしは豊かになったけど、さまざまに主張するモノがあふれ、便利さと引き換えに心やすらかな調和のとれた暮らしは遠ざかってしまいました。
最近もてはやされるようになったコ−ディネ−タ−やスタイリストの出現はこの混沌とした暮らしからの救いにあると思われます。
こうした中で今、このままではいけないという反省が始まり、新たな解決の模索がはじまっています。 元来、日本文化の中に培ってきた個と全体との調和の精神に立ち戻ろうとする兆しも見えはじめました。もちろん、そのことを論じることができるだけのゆとりがやっと生まれたからだとも言えましょう。
さまざまな人の心を満たす個性化と、個々の質の追及には一応目度がたち、それらが集まりあった時にかたちづくる風景に目が向けられはじめたといえましょう。 暮らしを整える環境としての調和づくりがこれからのデザインの課題です。
最近、都市のインフラストラクチャ−である公共施設の整備の立ち遅れに対して非難の声が高まっています。暮らしは豊かになってきたものの、心やすらかに街を楽しみ、なごめる環境としてのしつらえがまだまだ整っていない。たしかに大変な勢いで、力いっぱいモノ作りにはげんできたが、ふと気がつけば、これまでないがしろにされてきた街は汚れ、自然はキズついてしまっていた。
おりしも今は、政治経済面では貿易立国をめざし、世界に通用する製品づくりをデザイン面からも後押しした通産省のデザイン政策が、40年以上かけての効果を納め、今度は国際世論も受け、内需拡大政策の推進とからめて国内を良くすることに力が注がれる時代に。ちなみに、日本ではこの一年間をデザインイヤ−と宣言し、史上初の世界デザイン博覧会が開かれています。そこには文化国家としての将来像をデザインを軸に確立したいとするもくろみがこめられています。
国内を良くしようという声は、都市レベルでの環境整備問題にとどまりません。もっと小さなレベルの、例えば、個人の部屋、家、学校、職場環境から、町なみ、駅、公園、広場・・・とあらゆる環境にあてはまります。
私たちはこの一連の環境を“風景”という視点からとらえることを提唱しています。「かたちが作り出す新風景」。この言葉は目に美しく快適な心象風景を、日々の暮らしのあらゆる風景に実現しようというものです。人の生みだしたさまざまなモノ、道具、施設相互のバランス良い共生をはかることが次なる課題だと考えます。
このことは企業の生み出す製品についても例外ではありません。単に良いモノやサ−ビスを提供することのみに専念するという域を越え、いかにそれが周囲のモノと調和し“快適な暮らしの風景としてなくてはならない要素の一つとすることができるか”というマクロな視点に立つモノづくりが必要です。新たな要求を満たす、新たな思想にもとづいたデザイン。
大量生産品を扱うデザインにとって社会性が問われることは宿命とも言えましょう。“デザイン会社のサ−ビスを使う”というクライアントの立場に立てば、デザインは、客観的な視点から苦行の社会的役割を見定めてくれる貴重な存在でもあるわけです。つまり、それぞれの時代や地域が求める企業の社会的役割を見定めながらデザインを意味づけることがデザイン会社のサ−ビスなのです。


Think Visually, Act Graphically!