不安だ。
いつものことだが、たまらなくイヤな予感がする。
オレが何にそんな不安を感じているのかというと、今の自分のおかれた状況にである。
今、オレがいるのは大道寺邸の一室だ。
一般の家庭ではまずありえない、とても広い部屋である。
置かれた家具類もまた一流のものばかりだ。あの壷一つとっても、並みのサラリーマンの年収は軽く超えているだろう。
それに上品でもある。
そこらのにわか成金がやたらと派手な物を置きまくっているというのとは違う。
一見なんでもないが、見るものが見ればそれとわかる歴史と気品を感じさせる逸品ぞろいである。
かすかに漂う香水の匂いも品のよさを感じさせる。
言っておくけど、別に部屋の高級さに気圧されてるわけじゃないからな。
たしかに見事な部屋だけど、オレの実家にだってこれに負けないくらいの部屋はあった。
他のヤツならともかく、オレはこの程度で驚いたりはしないぞ。
オレが不安に思っているのは、そんな部屋にオレ一人しかいないということにだ。
そもそもなんでオレが大道寺の家にいるかというと、大道寺にクリスマスパーティに呼ばれたからである。
ハッキリ言って来たくなかったんだが。
他のやつらも呼んでるならともかく、今日のパーティに呼ばれてるのはオレとさくらだけなのだ。
この時点ですでにいや〜〜な予感を感じてしまうのは仕方ないだろう。
何かよからぬことを企んでるに決まってる。
行きたくない。
「悪いけどクリスマスの予定はもう決まってるんだ」
そう言って断りたかった。
それなのに。
「知世ちゃんの家でクリスマスパーティ? うわ〜〜楽しそうだね、小狼くん!」
オレより先にさくらがあっさり了承の返事を口にしてしまったのだ。
さくらにそう言われたらオレに断れるわけないじゃないか。
あぁ、さくら。
お前には学習能力というものが無いのか。
これまで、同じパターンでどんな目にあわされたか覚えてないのか。
お願いだから、もう少しだけ人を疑う心というものを持ってくれないか。
特にこの“大道寺知世”という超危険人物を疑う心を。
・・・無理か。さくらだもんな。
そんなわけで今、オレは大道寺の家の一室にいる。
だけど、いくら待っても今日のホストの大道寺は姿を見せない。
先に来ているはずのさくらも現れない。
オレの不安は高まるばかりだ。
そして。
そんなオレの不安をさらに高めているのが、目の前のテーブルに盛られた“料理”の存在だ。
正確には“料理と思われるもの”と言うべきか。
低めの丸テーブルの上に料理と思しきものが置かれている。
なんで料理と断言できないかというと、それが銀の丸い蓋で覆われているからだ。
高級レストランでボーイが料理を運んでくるときに被せているやつだ。
あれと同じもので覆われている。
オレが部屋に入ってしばらくしたら、大道寺のボディガードの黒服達が運び込んできたものだ。
「なんですか、それ」
と聞いたら、ニヤリと笑いながら
「知世お嬢様特製の“肉料理”です」
と言われたもんだ。
あの笑い方・・・大道寺の笑い方にそっくりだったな。
類は友を呼ぶのか、それともああいうタイプの人間を選りすぐっているのか。
この邸の人間はみんな、大道寺と同じ雰囲気を漂わせてる。
淫靡な香りというやつだ。
ま、それはともかく。
オレがこの“料理”を気にしてるのは別に銀蓋が被されてるからじゃあない。
もう一度言うけど、この程度のものに驚くようなオレじゃないんだ。
こんなものは香港のレストランで見飽きている。
皿の方もなかなかの高級品みたいだけど、そんなのもどうでもいい。
オレの不安を掻き立てるもの・・・それは銀蓋の大きさだ。
デカイ。
いや、でか過ぎる。
クリスマスパーティであの蓋が出てきたら、たいがいのやつは七面鳥の丸焼きを連想するだろう。
だけど、目の前の蓋は七面鳥を隠すにしてはあまりにもデカイ。
中身が豚の丸焼きだったとしてもまだ大きすぎる。
それほどにデカイ。
というか、ぶっちゃけた話、
女の子一人くらいなら覆えるほどに
デカイのだ。
気になるのはそれだけではない。
銀蓋の中から何か音が聞こえる。
いや、今さら言葉を濁してもしょうがないな。
銀蓋の中から何か声が聞こえてくるのだ。
それも普通の声ではない。
「ふぅーっ、うむぅーっ・・・」
という女の子の呻き声が聞こえてくるのである。
まるで、何かを無理やり口に押し込まれてうまく声が出せない、という感じの声だ・・・
―――――――――――――――――――――――――――――――――
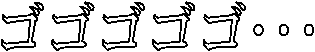
いつまで経っても姿を見せないさくら。
人を隠せそうなほどに大きな銀蓋。
その中から聞こえてくる呻き声。
これらから連想される“料理”の正体は一つしかない。
まさか、そんな?
そう言うヤツは大道寺知世という人間を知らないのだ。
この日本でそんな無体な真似が許されるはずがない?
残念ながらここは日本じゃない。
この敷地の中は大道寺一族の“王国”。
ここではアイツが法なのだ。
アイツが望めばどんな無法もまかり通るのだ。
ああ、もう帰りたい。
帰ってベッドにもぐりこんで布団を被って全てを忘れて寝てしまいたい。
だが、そんなことが許されるはずがない。
アイツが大人しく帰してくれるわけがないからだ。
それに、何よりもこの“料理”をほうって帰るわけには行かない。
しかたがない。
何度目かの逡巡の後、腹を括ったオレは銀蓋を開けた。
「うぅ〜〜っ、むむぅ〜〜っ」
蓋の下から現れた“料理”について今さら説明する必要はあるまい。
予想通り皿の上に置かれていたのは、手足を縛られた全裸のさくらだった・・・
NEXT・・・