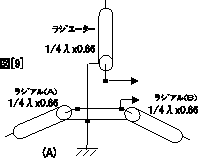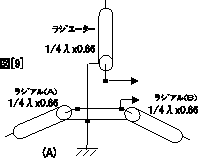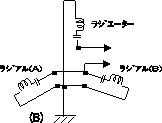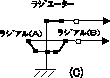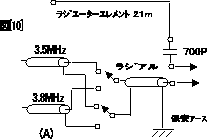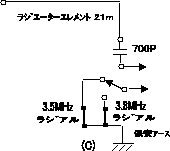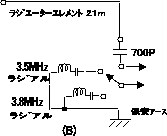No5
図9は冒頭の図1と同じものです。
測定結果を踏まえてアンテナシステムとして動作可能か検討してみます。
図9(A)の其々の同軸ケーブルエレメントはある周波数で1/4λで共振しています。
これを直列共振回路として書き換えれば図9(B)になります。
直列共振回路は高周波的に短絡状態ですからさらに書き換えると図9(C)になり給電部をラジエーターとラジアルの共振回路で高周波的に短絡状態でアンテナシステムとしては動作不可能ではないでしょうか。
図10(A)は同じくCQ誌に出ていた記事です。
ラジエーターエレメントは21mで直列に700pのコンデンサーが接続されており、ラジアルは3.5/3.8MHzで長さを切り替えて同軸ケーブルを1/4λで共振させ保安アースで接地されているとのことです。
このアンテナシステムもラジアルエレメントを書き換えると図10(B)になりさらに書き換えると図10(C)となります。これは3.5/3.8MHzの共振回路を通して保安アースで接地している接地型アンテナと考えられます。
記事中にもラジアルの同軸ケーブルの配置を換えてもマッチングに影響しないと書かれていますが、普通ラジアルはアンテナの片側で輻射があり曲げたりすれば影響は出るはずです、しかしラジアルの同軸ケーブルは1/4λの共振回路でこの共振も同軸ケーブルの中心導体と外側導体(シールド)の内側での動作であるため外部への輻射は無く、長さが変わらなければどんなに曲げても影響しないことはとうぜんです。
直接保安アースに接地した方が共振回路のロス分が接地抵抗に加わらず効率の低下は防げると思われます。
同軸ケーブルをアンテナエレメントやラジアルエレメントに使用できるか
同軸ケーブルの大きな短縮率はケーブル内部でのみ適用され、高周波の伝送でなく外部への輻射を伴うアンテナエレメントやラジアルエレメントとして使用する場合は中心導体は殆ど無関係になり、外側導体を内部が詰まった太い導体で短縮率K=0.91程度としてしか使用できない。
大きな短縮率を生かした同軸ケーブルをエレメントとしたアンテナは実現できないと言い切ってもよいのではないでしょうか。