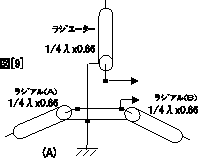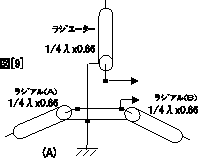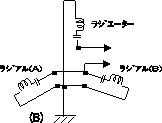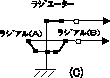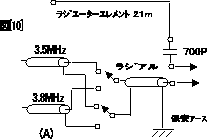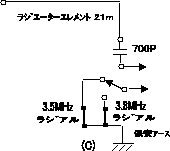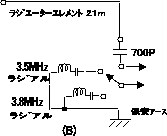幚尡寢壥偺峫嶡
埲忋偺應掕寢壥傛傝
嘆1/4兩偱嫟怳偟偰偄傞摨幉働乕僽儖偼捈楍嫟怳夞楬偲摍壙偱丄愭抂僆乕僾儞偱偼崅廃攇揑偵僔儑乕僩忬懺偵側傞丄媡偵愭抂僔儑乕僩忬懺偱偼暲楍嫟怳夞楬偲摍壙偱僀儞僺乕僟儞僗嵟戝偱僆乕僾儞忬懺偲摍壙偵側傞丅
嘇摨幉働乕僽儖杮棃偺抁弅棪偑揔梡偝傟傞偺偼拞怱摫懱偲奜懁摫懱偺撪懁偺傒偱揹棳偼屳偄偵媡岦偒偺帪偺傒偱偁傞丅
嘊傾儞僥僫僄儗儊儞僩傗儔僕傾儖僄儗儊儞僩偲偟偰巊梡偡傞応崌偼揹棳偑摨憡偲側傝杮棃偺抁弅棪偼揔梡偱偒側偄丄傑偨奜懁摫懱偺傒偑僄儗儊儞僩偲偟偰摦嶌偟抁弅棪俲亖0.9偰偄偳偵側傞丅
偑妋擣偱偒傑偟偨丅
師偼恾侾偺傾儞僥僫傪幚嵺偵摦嶌偡傞偐専摙偟傑偡丅
摨偠傕偺傪恾俋乮俙乯偵傕偆堦搙帵偟傑偡丅偙偺傾儞僥僫偼偡傋偰挿偝1/4兩偱愭抂僆乕僾儞偺慻傒崌傢偣偵側偭偰偄傑偡丅偙傟偼恾俉乮俛乯偺傛偆偵捈楍嫟怳忬懺偱偁傞偨傔媼揹晹懁偼僀儞僺乕僟儞僗嵟彫偱僔儑乕僩偠傚偆偨偄偱偡丅恾俉乮俠乯偺傛偆偵彂偒姺偊偱偒傑偡丄柍慄婡懁偐傜尒傟偽僔儑乕僩忬懺偱俽倂俼偼柍尷戝偵側傝巊梡偱偒傑偣傫丅媡偵愭抂傪僔儑乕僩偡傞偲媼揹晹懁僀儞僺乕僟儞僗偼嵟戝偵側傝柍慄婡懁偐傜偼僆乕僾儞忬懺偲摨偠偱偙傟傕俽倂俼偼柍尷戝偵側傝巊梡偱偒傑偣傫丅
恾10乮俙乯偼埲慜俠俻帍偵弌偰偄偨儔僕傾儖偵摨幉働乕僽儖傪巊梡偟偨3.5乛3.8俵俫倸懷傾儞僥僫偺婰帠偱偡偑丄儔僕傾儖偲偟偰3.5俵俫倸懷丄3.8俵俫倸懷偵偦傟偧傟偵嫟怳偟偨愭抂僆乕僾儞偺1/4兩摨幉働乕僽儖傪俽倂偱愗傝懼偊偰偄傑偡丅偟偐偟1/4兩摨幉働乕僽儖偼愭抂僆乕僾儞偺応崌恾侾侽乮俛乯偺傛偆偵捈楍嫟怳忬懺偱媼揹晹懁傪僔儑乕僩偟偰偄傞偙偲偵側傝傑偡丅偙傟傪彂偒姺偊傞偲恾侾侽乮俠乯偲側傝摨幉働乕僽儖偼儔僕傾儖偲偟偰偺摦嶌偼慡偔側偔曐埨傾乕僗偱壗偲偐愙抧宆傾儞僥僫偲偟偰惉傝棫偭偰偄傞偲巚傢傟傑偡丅摨婰帠拞曐埨傾乕僗偺堷偒夞偟曽偱儅僢僠儞僌忬懺偑曄傢傞偲偺撪梕偑偁傝傑偡偑偙傟傕擺摼偱偒傑偡丅
寢榑偲偟偰
嘆摨幉働乕僽儖傪傾儞僥僫僄儗儊儞僩傗儔僕傾儖僄儗儊儞僩偵巊梡偡傞帪偼丄抁弅棪俲亖0.9偰偄偳偺扨側傞揹慄偲偟偰奜懁摫懱偺傒巊梡偱偒傞丅拞怱摫懱偼奜懁摫懱偵愙懕偟偰傕偟側偔偰傕塭嬁偼側偄丅
嘇倀/倁俫俥偱摨幉僐乕儕僯傾傾儞僥僫傪嶌傞応崌偼抁弅棪俲亖0.9掱搙偺摨幉働乕僽儖偱側偄偲惢嶌偱偒側偄丅
嬻婥傪愨墢懱偲偟偨摨幉働乕僽儖偑偁傟偽壜擻偱摨幉僐乕儕僯傾偱偼側偔摨幉僞僀僾僐乕儕僯傾傾儞僥僫偵側傝傑偡丅
嘊僟僽儖僶僘乕僇傾儞僥僫偼1/4兩偺摨幉働乕僽儖偲愭抂偵揹慄傪偮側偓慡懱偲偟偰丄1/2兩僟僀億乕儖傾儞僥僫偲偟偨傕偺偱丄1/4兩摨幉働乕僽儖偺愭抂偼僔儑乕僩偟偰偄傑偡丅偟偐偟媼揹晹懁偐傜尒傟偽1/4兩摨幉働乕僽儖偼愭抂僔儑乕僩偺応崌偼暲楍嫟怳帪偲摍壙偱僀儞僺乕僟儞僗嵟戝偵側傝傑偡丅偙偺帪柍慄婡懁偐傜尒傟偽僆乕僾儞忬懺偲摨偠偱偡丅嫟怳廃攇悢偱偼僴僀僀儞僺乕僟儞僗偺偨傔愙懕偝傟偰側偄偺偲摨偠偙偲偱傾儞僥僫偲偟偰偺摦嶌偼摨幉働乕僽儖偺奜懁摫懱偲揹慄偲偑僄儗儊儞僩偲偟偰摦嶌偟偰偄傞偲憐憸偱偒傑偡丅
嵟弶僟僽儖僶僘僇乕傾儞僥僫傪峫偊偨恖偼丄1/4兩傛傝抁偄摨幉働乕僽儖偲揹慄偺慻傒崌傢偣偨僄儗儊儞僩偱惢嶌偟偨偺偱偼側偄偱偟傚偆偐丠
1/4兩傛傝抁偄摨幉働乕僽儖偼梕検惈儕傾僋僞儞僗偱偁傞偨傔僐儞僨儞僒偲偟偰媼揹晹偵暲楍偵愙懕偝傟偨偙偲偵側傝嫟怳廃攇悢偑壓偑傞偺偱僄儗儊儞僩偺挿偝偑抁弅偱偒傞偙偲偵側傝傑偡丅偨偩媼揹晹偺僀儞僺乕僟儞僗傕掅壓偡傞偨傔壗傜偐偺曗惓偑昁梫偵側傝傑偡偑丅偙傟偑偄偮偺娫偵偐摨幉働乕僽儖晹暘偺摥偒偑棟夝偝傟側偄傑傑1/4兩偺挿偝偵曄壔偟偨偺偱偼側偄偐偲憐憸偟傑偡丅
嬤擔拞偵捛帋偟偰傒傞梊掕偱偡丅
偍撉傒捀偁傝偑偲偆偛偞偄傑偟偨丅杮婰帠偼俫俙俵丂俰倧倳倰値倎倢俶倧113偺撪梕傪堦晹曄峏偟偨傕偺偱偡丅