氷期の森と縄文の森 その4
縄文の森をめぐって
![]()
氷期の森と縄文の森 その4
縄文の森をめぐって
![]()
| 八千代市周辺の極相林は、シイやカシの仲間からなる照葉樹林であると言われています。事実、市内にはかつて薪炭林として使われていたイヌシデとコナラの斜面林をよく見かけますが、そんな林の中にはいると、林床にはアカガシやスダジイなどの幼木が生えています。しかしイヌシデやコナラの幼木はありません。このまま放置すれば、やがてアカガシやスダジイが大きく育って、イヌシデやコナラと交代するであろうことは明らかです。 | ||
 |
||
| 林床に常緑広葉樹の育ったイヌシテ゛とコナラの林(八千代市桑納) | ||
 |
 |
 |
| アオキの実生 | スタ゛シ゛イの幼木 | シロタ゛モの実生とヤフ゛コウシ゛ |
| しかし花粉分析の結果を見ると、現在よりも人口が少なく、気候も温暖であった縄文時代においてさえ、新川流域に照葉樹林が発達したことは一度もありません。照葉樹の仲間は、コナラ亜属を主とする、落葉広葉樹林の一部を占めるにすぎないのです。このような傾向は、関東平野、特にその内陸部や北部では、一般的な現象です。その理由については十分に明らかになっていませんが、現在考えられていることを二つあげておきましょう。 平戸の花粉ダイアグラムにおいて、照葉樹林が拡大の傾向を見せるのは、Hd-IIIC亜帯の後半から、Hd-IVA亜帯にかけてのことです。アカガシ亜属の出現率がしばしば10%を越え、同じ照葉樹林要素の、ヤマモモ属やツバキ属を安定して伴います。この時、一緒に増加し始めるのは、ニレ―ケヤキ属、クマシデ属、クルミ―サワグルミ属、それにスギなどです。クマシデ属を除けば、これらはどれも、暖温帯から冷温帯の、谷沿いなど、地下水の豊富な場所を生育の場としていますから、気候の湿潤化を示す現象と考えられます。つまり、照葉樹林の拡大傾向は、気候の湿潤化に伴って起きた現象と見ることができそうです。八千代市周辺の台地には、4〜5mもの厚さの関東ローム層が積もっており、このため台地上は、かなり乾燥した土壌条件の下にあります。このことが、照葉樹林の拡大を阻んだ、原因の一つではないでしょうか。関東平野は照葉樹林分布域の北の外れですから、降水量や土壌条件などのわずかな違いが、その分布に大きな影響を与えることは、十分考えられることです。この時、冬季に気温の低下する、内陸部や北部ほど、受ける影響は、シビアなものになることでしょう。 辻誠一郎さんは、1985年に書かれた論文で、関東平野において、照葉樹林の拡大の場は台地斜面に限られ、台地上には落葉広葉樹林が卓越していたとし、その原因に、台地上の土地的乾燥をあげています。しかし同時にまた、縄文時代以降、台地面が、活発な人間活動の場となったことの影響も、無視できないとも述べています。そしてその後、各地で行われた縄文遺跡の発掘成果をふまえて、関東におけるコナラ亜属主体の落葉広葉樹林は、縄文時代以降人為的に維持されたものであるとして、その維持システムのもとに成立した生態系を、「縄文里山」と呼びました(辻,1997)。 平戸の花粉分析結果には、このことを裏付けるデータはありません。しかし、上流の勝田川低地では、縄文時代後・晩期、約3000年前のソバの栽培とマツ二次林の拡大、それに低地における稲作の実施が知られています(稲田ほか,2004)。この時代のマツ属花粉の増大は、伊勢原市栗窪(清永,1993)・横浜市金井(清永,1990)・千葉市辺田(米林,1995)・四街道市亀崎(内山,1994)など、関東平野のいくつかの場所でも見られ、そのうち、千葉と四街道のデータでは、ソバ属の花粉を伴っています。辻さんの「縄文里山」の維持システムの存続は、この時代になって、マツ二次林の拡大を招くまでに至ったと見ることも、可能かもしれません。 |
||
![]()
 |
 |
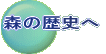 |
 |