亭主の寸話41 『豆乳に第2の発展期か?』
豆腐は奈良時代に唐から入ってきたとされていますが、豆乳がいつごろ日本に入ってきたかは定かではない。しかし、鎌倉時代の書物(庭訓往来)によると、禅宗の精進料理として僧侶はもちろんのこと、武士、町人の間にまで豆乳が広まったとされている。当時は豆乳とは呼ばれずに「豆腐羹(とうふこう)」といわれていた。羹とはスープのことを言い、羊羹(ようかん)というのも元々は羊のスープを指して言っていたようです。しかしこの豆腐羹も、その後の広がり方は、同じ大豆食品である豆腐、納豆、味噌、醤油に比べて、まるで火が消えたような有様です。その理由はおそらく豆乳の独特のいやな臭いにあったのではないかと想像される。大豆は水で膨潤させて磨り潰すと瞬時に自分の命を守るためか、大豆の中にひそんでいた酵素であるリポキシゲナーゼが働いていやな臭いを出す仕組みになっているのです。豆腐はこの豆乳ににがりを加えて凝固させて閉じ込めてしまうのでいやな臭いを感じないが、豆腐のように固める前の状態の豆乳ではこの臭いが直接鼻を突くことになる。だから豆乳技術とはこの臭いとの戦いだったとも言えるだろう。
ところが現在ではその豆乳の人気がすごい。最近は大豆の臭いを抑える豆乳製造技術が格段に向上しており、なんの抵抗感もなしに無調整豆乳が飲めるようになっている。無調整豆乳は大豆から豆乳を絞ったままの状態であり、まさに大豆そのものといえる。なんといってもこの豆乳の脱臭技術の向上が豆乳飲料の伸びの最も大きな要因であろう。もうひとつの要因は消費者に浸透した大豆に対する健康機能の認識であり、さらには自然志向へのうねりも加わっているかもしれない。大豆の持つ健康機能はそのまま豆乳の中に移動しており、豆乳はまさに「飲む大豆」と言える。大豆のもつ健康機能や豆乳については私の別のコラムを見ていただくとして、今回は豆乳の第2の発展段階ともいえる現在の豆乳の様子についてお話したいと思います。
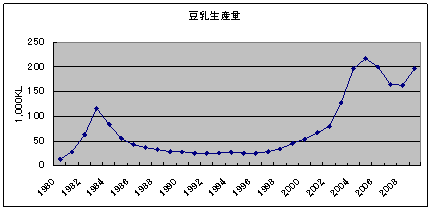 一般に豆乳と言われるものには大きく分けて豆乳(無調整豆乳)と、豆乳に生産段階で甘味料や香料、植物油脂などを加えて飲みやすくした調整豆乳、さらには果汁など他の飲料と組み合わせた豆乳飲料の3つに分けられる。これらの豆乳のどれにも大豆の持つ健康機能は期待できるが、より自然に近い形で大豆を取り入れようとする人にとっては無調整豆乳に人気がある。日本豆乳協会の調べによると、平成21年度の豆乳生産量は、無調整豆乳2万6千キロリットル、調整豆乳11万8千キロリットル、豆乳飲料5万キロリットル、その他の用途も含めて合計19万7千キロリットルと予想されている。この生産量が多いのかどうかは過去の生産量推移を見ていただければ発展の様子が想像できますが、近所の食料品店の棚に並ぶ豆乳の勢いで実感しているのではないだろうか。だが、2005年の統計として農水省がまとめた世界の豆乳消費量から見ると、日本の一人当たり年間2リットルに比べると、タイの5リットル、マレーシア4リットル、韓国3.5リットル、オーストラリア3.1リットル、カナダ2.3リットルと、わが国は相撲でいえばやっと幕内に上がってきたところである。大豆との付き合いの長い日本にしては出だしの遅い食品であり、これから発展していく余地を感じさせるレベルでもあるともいえる。
一般に豆乳と言われるものには大きく分けて豆乳(無調整豆乳)と、豆乳に生産段階で甘味料や香料、植物油脂などを加えて飲みやすくした調整豆乳、さらには果汁など他の飲料と組み合わせた豆乳飲料の3つに分けられる。これらの豆乳のどれにも大豆の持つ健康機能は期待できるが、より自然に近い形で大豆を取り入れようとする人にとっては無調整豆乳に人気がある。日本豆乳協会の調べによると、平成21年度の豆乳生産量は、無調整豆乳2万6千キロリットル、調整豆乳11万8千キロリットル、豆乳飲料5万キロリットル、その他の用途も含めて合計19万7千キロリットルと予想されている。この生産量が多いのかどうかは過去の生産量推移を見ていただければ発展の様子が想像できますが、近所の食料品店の棚に並ぶ豆乳の勢いで実感しているのではないだろうか。だが、2005年の統計として農水省がまとめた世界の豆乳消費量から見ると、日本の一人当たり年間2リットルに比べると、タイの5リットル、マレーシア4リットル、韓国3.5リットル、オーストラリア3.1リットル、カナダ2.3リットルと、わが国は相撲でいえばやっと幕内に上がってきたところである。大豆との付き合いの長い日本にしては出だしの遅い食品であり、これから発展していく余地を感じさせるレベルでもあるともいえる。
豆乳の歴史を見ると最初のブームが1983年頃に起こっている。この頃は私も現役で仕事をしており、このときに豆乳の製造企画に携わったことがある。この頃はいかにいやな大豆の臭いが少ない豆乳を製造するかに各社の力点が置かれていた時代であった。この頃に名乗りを上げていた豆乳メーカーの多くは大豆の加工業者や豆腐製造業者が中心であった。彼らは豆乳を大きな潜在市場と期待をして名乗りを上げていったが、彼らの多くは顧客の支持が得られずに姿を消していった。このときに生き残った企業はそれ以降も引き続き、いかに飲みやすい豆乳を製造するかに多くの努力を割いた。この長い苦節の時代があったればこそ、21世紀になって豆乳第2の発展期を迎えることが出来た、といえよう。豆乳の第2発展期になると各種飲料メーカーが他の飲料で蓄積したマーケットノウハウを駆使して市場開拓に乗り込んできた。彼らのマーケティング戦略は多岐にわたっている。豆乳の製造は専門業者に委託して、自らは消費者に対するマーケティング展開に注力するという動きも多く見られる。このことによって豆乳の品揃え、消費者に対する訴求の仕方が近代的され、このことが現在の豆乳市場の成長を支えている大きな原動力になっているものと思われる。まさにマーケティングの時代へと突入してきた感がある。
彼らの商品の流通ルートは従来の食品ルートにこだわらずインターネットを駆使した通販など幅広いチャンネルを展開しているのが特徴である。インターネットでの豆乳製品のバラエティの豊富さは先輩牛乳とはまったく様相を異にしている。これら豆乳の消費拡大はどこに食い入っているのだろうか。といっても豆乳の消費量はまだ牛乳の0.5%にも届いていないので先輩飲料を駆逐しているとはとても言える段階ではないが、飲用牛乳の下降線とあるいは無関係でないのかもしれない。
飲用牛乳の消費量は1994年の一人1日114グラムをピークに下降線をたどり始め、直近の2006年データーには98.1グラムと100グラムの大台を割り込んでいる。この飲用牛乳の下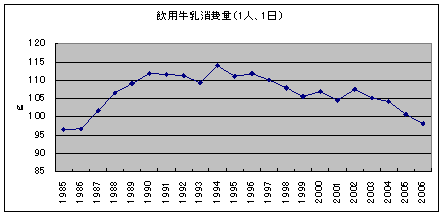 降トレンドは今後も続いていくのかどうか、しばらく様子を見ないと判断は出来ないが、牛乳万能との見方が薄れてしまっていることは否めない。しかし、現在の牛乳の消費は飲用部分をはるかにしのぐ量がパン、ケーキ、麺などへの練りこみ用として用いられており、私たちは知らない間に飲用牛乳をはるかにしのぐ150g/日もの牛乳をこれらの食べ物を通じて摂取していることになっている。これら私たちが年間に摂取している牛乳は1,200万トンに達しており、お米の消費量900万トンをはるかにしのぐところまでに達している。これだけ牛乳を摂っても骨粗鬆症の改善にはつながっていないとすれば、牛乳の摂取=骨粗鬆症の改善、という幻想に問題ありと考えざるを得ない。
降トレンドは今後も続いていくのかどうか、しばらく様子を見ないと判断は出来ないが、牛乳万能との見方が薄れてしまっていることは否めない。しかし、現在の牛乳の消費は飲用部分をはるかにしのぐ量がパン、ケーキ、麺などへの練りこみ用として用いられており、私たちは知らない間に飲用牛乳をはるかにしのぐ150g/日もの牛乳をこれらの食べ物を通じて摂取していることになっている。これら私たちが年間に摂取している牛乳は1,200万トンに達しており、お米の消費量900万トンをはるかにしのぐところまでに達している。これだけ牛乳を摂っても骨粗鬆症の改善にはつながっていないとすれば、牛乳の摂取=骨粗鬆症の改善、という幻想に問題ありと考えざるを得ない。
ところで豆乳が大豆の健康機能にたいする期待から消費が伸びているとすれば、大豆製品の大御所である豆腐の消費はさぞ伸びていることであろうと思うのだが、そう単純な図式にはなっていないようである。グラフに示したように総務省の家計調査によると、1世帯当り年間の豆腐購入量は73丁ほどとやや下降傾向になっている。これは別に豆腐の価格が高くなったわけでもない。同じく家計調査によると、平成5年から10年までの豆腐1丁当りの価格が99.85円であったのに比べて平成15年から19年の5年間の豆腐の値段が89.07円であったことからも想像できる。ではこの豆腐離れはどこから来ているのか、単純に食の洋風化とも言い切れないのではないだろうか。我々が食べている大豆の半分は豆腐・油揚として食べているのである。農水省の平成20年の予測によると1年間に日本人が食べる大豆104万トンの内、豆腐・油揚として食べる大豆は約半分の50万トン、次いで味噌14万トン、納豆13万トンなどとなっている。このことは豆腐の消費減は即大豆の摂取減ということにつながることを意味している。
明らかに消費者は健康とは別の次元で新しい食のあり方を求めているのではないだろうか。豆腐の食べ方には新しい食べ方が浮かんできていないのに気がつく。相変わらず豆腐の味噌汁と冷奴に頼る食べ方には今の若者をひきつける魅力に欠けている。色のバラエティ、香りの楽しみ、味の変化、どれをとっても豆腐は保守的過ぎる。豆腐が健康にいいことは誰でも知っている。豆腐業界はそこにアグラをかいてしまっていたのではないだろうか。そこに同じ健康という切り口で変化を見せたのが近頃の豆乳飲料といえる。インターネットで豆乳を検索すると、そのバラエティの豊かさに驚かされる。コーヒー味の豆乳、果汁味の豆乳などその種類の豊富さは見ているだけで楽しくなる。
ざっと目に付いたものを羅列しても次の通りである。豆乳チョコレート、豆乳ココア、豆乳紅茶、豆乳バナナ、豆乳イチゴ、豆乳抹茶、豆乳フルーツミックス、豆乳麦芽コーヒー、豆乳黒ゴマ、豆乳黒みつ、GABA豆乳、杏仁豆乳、黄な粉風味豆乳、豆乳ぜんざい、豆乳アイス、豆乳プリン、豆乳チョコ餅、豆乳クッキー、豆乳カステラ、豆乳おかき、豆乳ヨーグルト、豆乳ドレッシング、豆乳ホイップ、豆乳スープ、豆乳コロッケ、豆乳麺、豆乳パン、豆乳鍋、さらには豆乳ローション、豆乳石鹸まで登場しており、まさに群雄割拠の時代に入ってきたと思われる。
冬場のスーパーマーケットには豆乳鍋の素がずらりと並んでいた。これからの夏場で豆乳がどんな展開をしていくのか、大いに注目をしている。その拡大の勢いによっては豆乳が豆腐の王座を脅かす時代の幕開けを迎えたと言えるのかもしれない。
茶話会の目次に戻る
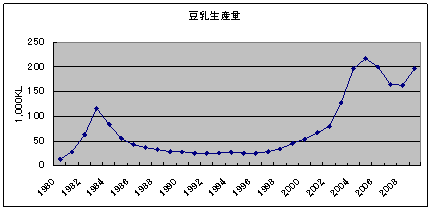 一般に豆乳と言われるものには大きく分けて豆乳(無調整豆乳)と、豆乳に生産段階で甘味料や香料、植物油脂などを加えて飲みやすくした調整豆乳、さらには果汁など他の飲料と組み合わせた豆乳飲料の3つに分けられる。これらの豆乳のどれにも大豆の持つ健康機能は期待できるが、より自然に近い形で大豆を取り入れようとする人にとっては無調整豆乳に人気がある。日本豆乳協会の調べによると、平成21年度の豆乳生産量は、無調整豆乳2万6千キロリットル、調整豆乳11万8千キロリットル、豆乳飲料5万キロリットル、その他の用途も含めて合計19万7千キロリットルと予想されている。この生産量が多いのかどうかは過去の生産量推移を見ていただければ発展の様子が想像できますが、近所の食料品店の棚に並ぶ豆乳の勢いで実感しているのではないだろうか。だが、2005年の統計として農水省がまとめた世界の豆乳消費量から見ると、日本の一人当たり年間2リットルに比べると、タイの5リットル、マレーシア4リットル、韓国3.5リットル、オーストラリア3.1リットル、カナダ2.3リットルと、わが国は相撲でいえばやっと幕内に上がってきたところである。大豆との付き合いの長い日本にしては出だしの遅い食品であり、これから発展していく余地を感じさせるレベルでもあるともいえる。
一般に豆乳と言われるものには大きく分けて豆乳(無調整豆乳)と、豆乳に生産段階で甘味料や香料、植物油脂などを加えて飲みやすくした調整豆乳、さらには果汁など他の飲料と組み合わせた豆乳飲料の3つに分けられる。これらの豆乳のどれにも大豆の持つ健康機能は期待できるが、より自然に近い形で大豆を取り入れようとする人にとっては無調整豆乳に人気がある。日本豆乳協会の調べによると、平成21年度の豆乳生産量は、無調整豆乳2万6千キロリットル、調整豆乳11万8千キロリットル、豆乳飲料5万キロリットル、その他の用途も含めて合計19万7千キロリットルと予想されている。この生産量が多いのかどうかは過去の生産量推移を見ていただければ発展の様子が想像できますが、近所の食料品店の棚に並ぶ豆乳の勢いで実感しているのではないだろうか。だが、2005年の統計として農水省がまとめた世界の豆乳消費量から見ると、日本の一人当たり年間2リットルに比べると、タイの5リットル、マレーシア4リットル、韓国3.5リットル、オーストラリア3.1リットル、カナダ2.3リットルと、わが国は相撲でいえばやっと幕内に上がってきたところである。大豆との付き合いの長い日本にしては出だしの遅い食品であり、これから発展していく余地を感じさせるレベルでもあるともいえる。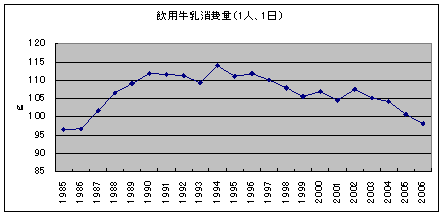 降トレンドは今後も続いていくのかどうか、しばらく様子を見ないと判断は出来ないが、牛乳万能との見方が薄れてしまっていることは否めない。しかし、現在の牛乳の消費は飲用部分をはるかにしのぐ量がパン、ケーキ、麺などへの練りこみ用として用いられており、私たちは知らない間に飲用牛乳をはるかにしのぐ
降トレンドは今後も続いていくのかどうか、しばらく様子を見ないと判断は出来ないが、牛乳万能との見方が薄れてしまっていることは否めない。しかし、現在の牛乳の消費は飲用部分をはるかにしのぐ量がパン、ケーキ、麺などへの練りこみ用として用いられており、私たちは知らない間に飲用牛乳をはるかにしのぐ