| e d u c a t i o n p r a c t i c a l s t u d y |
|---|
| 北門児童センターにおける『造形ボランティア/造形広場』 |
|---|
【『造形ボランティア2004 手引き』より抜粋】
1.児童センターの位置とボランティアとしての関わりかた
(1)母体である児童健全育成推進財団について
地域社会において,児童の健全育成に尽力している児童館・児童センターが全国におよそ4600館ある。それぞれの児童館は,地域との共同により,その特色を生かしつつ健全育成活動を進めている。このような各地の児童館活動が一層発展し,わが国のすべての児童が心身共に健やかに成長し発達することを願い,全国の児童館・児童センターがひとつになって,その目的を達成させるための連絡・調整・推進機関として「財団法人児童健全育成推
進財団」が設立されている。(参考:児童健全育成推進財団のホームページ)
(2)児童館とは
児童館(児童センターを含む)は,児童福祉法第40条による児童福祉施設である。屋内型の児童厚生施設(他に屋外型の児童遊園あり)であり,子どもに健全な遊びを提供し,その心身の健康を増進し情操を豊かにすることを目的としている。
児童館は屋内型の福祉施設であるが活動は建物内にとどまらない。地域児童の健全な発達を支援するための屋内外の地域活動をはじめ遠隔地でのキャンプなど,必要な活動の一切を含んでいる。
児童館は,子どもたちに遊びを保障する。遊びは,子どもの人格の発達を促す上で欠かすことのできない要素であり,遊びのもつ教育効果は他で補うことができない。子どもたちは遊びを通して考え,決断し,行動し,責任をもつという独自性・自主性・社会性を身につける。換言すれば,今の教育に最も欠けている自立教育プログラムが,遊びの要素に含まれているのである。
児童館では,子ども一人ひとりの状態を観察し,個々のペースに応じて自立していくことができるよう,専門職員(児童厚生員)が支援している。
また,子どもの生活が安定する環境が整備されるためには大人の理解と協力が不可欠であり,親のグループやジュニアボランティアを育成するとともに,諸機関や団体との連携を図る中で,子どもにやさしい総合的な福祉の町づくりを目指している。
共働き家庭の子どもたちが安定した放課後を過ごせるように,登録制で毎日学校から直接来館する児童クラブ事業や,育児不安に陥りがちな子育て中の母親を支援する午前中の幼児クラブ活動などは,まさに児童のデイサービス事業と言えるだろう。
以上のように子どもにとって児童館は,現代社会の「オアシス」であり,「駆け込み寺」であり,「松下村塾」といえるのではなかろうか。(参考:児童健全育成推進財団のホームページ)
(3)ボランティアとしてのスタンス
上記の位置付けを有する児童センターにボランティアとして参画する際,その前提として次のようなスタンスが必要である。
①「児童福祉施設」であるので,子どもに遊びを強制するのではなく,「提供」する存在であること。(義務教育の小中学校とは異なる・子どもが自主的に選択する)
② 様々な子どもを対象にすること。(年齢・発達・家庭環境・気分…)
③ 学校外ではあるが,教育活動であること。一人の社会人として振舞うこと。
④ 自分が楽しもうとしなければ,子どもも楽しくないこと。
2.北門児童センターについて
略
3.前期の活動日 ~『ぞうけいひろば』~
略
4.活動当日の時程 (基本的な流れなので,状況によって変化する)
1時45分:3コマ目の授業のない人のみ366教室(図工教室)集合
・準備の確認
2時:大学出発
・センターにて設定・準備
2時30分:『ぞうけいひろば』の活動
・3コマ目の授業受講者の合流
4時50分:片付け・清掃
・帰校
5時:366教室にて片付け
・反省会(①自己反省 ②協議 ③大泉から)
・次回の分担の確認
・道具・材料の準備(参考作品制作や看板やポスター製作,及び材料の下ごしらえも含む)
それ以降~別日:題材のネタ収集
・材料の収集
*3コマ目の授業後に参加する者は,授業終了後,すぐに駆けつけること。
5.企画・活動にあたって
[企画の段階]・[活動中]・[活動後の反省] において,以下の5つの視点から,絶えず自分の企画・活動を検討することが必要である。
[A]教材開発の視点
・想定する対象児童に適しているか?
・魅力があり,モンクなく楽しいものであるか?
[B]指導方法の視点
・異年齢集団にどう対応するか?
・指導の分担は?
・言葉使いは?
[C]子ども理解の視点
・投げかけ・声かけの内容と方法は?
・共感的受容的態度は?
[D]安全管理の視点
・道具の扱いに対する留意点は?
・けがへの対処方法は?
[E]指導評価の視点
・子どもの活動の様子は?(子ども評価)
・次回へ生かせる反省点は?(指導評価)
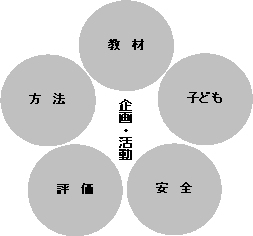
(1)企画にあたってのポイント
① 子どもが自由参加であることが前提である。来館した子が誰も参加しないかもしれないし,多くの子が参加するかもしれない。そこで基本的には,やりたい子が自主的に取り組めるような企画が望まれる。つまり,ひと目でつくってみたくなり,ひと目でつくり方が理解できるようなものがよい。
② ターゲットを小学校中学年あたりにして,低学年の子には個別支援を,高学年・中学生には活動を発展させられるようにするのがよい。
③「つくったものを○○する」ことまで考えに入れ,持ち帰りにくいもの,保護者に誤解されるようなものなどは避ける。
④ 材料・道具の入手方法,時間的条件を考慮する。
(センターでお借りできるもの)
○壁面 ○机・椅子 ○はさみ ○のり ○セロハンテープ ○カッター
○カラーペン ○掃除機 ○雑巾 ○ブルーシート ○新聞紙
(こちらで用意するもの)
基本的には,上記を除いたすべてを用意する。特に消費するものは,こちらが持ち込む。
⑤ 無理のない範囲で複数の題材を用意し,子どもに選択させるようにするとよい。
⑥ 企画をより魅力的に見せるためのPR方法を工夫する。当日掲示する看板や見本などが考えられる。
⑦ 企画を事前にPRするには,以下の方法がある。
・『ほくもんセンターだより』で紹介してもらう。(7月分は,6月中旬までに依頼)
・児童センターにポスターを掲示させてもらう。(最終1週間前まで)
・管轄の小中学校に,チラシやポスターを配布する。(早めに伊藤先生に相談)
・市の広報誌で紹介してもらう。(前期は無理。2ヶ月前に依頼)
⑧ 片付けまでを視野に入れて構想すること。
⑨ 9月に行われる「センターまつり」に企画や展示などで出店することも可能である。例年,多くの来館者が訪れる。
(2)活動にあたってのポイント
① 一緒に楽しむのが基本であるが,常に指導者としての立場を忘れないこと。(1ページの「1.児童センターの位置とボランティアとしての関わりかた」を参照のこと)
② 「子どもは大人の背中を見ている」ことを自覚する。(挨拶・礼儀・言葉使い・服装・掃除)
③ 不特定の子どもが来館する児童センターにおいては,挨拶は基本である。自ら名乗り,子どもたちと心を通わせるように心がけること。(名札を着用するとよい)
④ 基本的に,子どもが自主的に活動するのを助ける。あまり手を出し過ぎず,見守ることが大切。「何とかしてあげたい」と思っても,ひと呼吸待ってみたり,「やってごらん」と促したりすることも時には必要。
⑤ 安全に留意し,けがをした場合は,センターの先生に伝えた上で自分のできる処置を取る。
⑥ いけないことをしたり,人を傷つけたりする行為には毅然と対応し,センターの先生に報告。
⑦ なるべく散らかしたり,汚したりしないよう心がけて指導する。
⑧ 個々の子どもの「よい所見つけ」をし,子どもにフィードバックしてやるよう心がける。
6.その他
・学校から一歩出たら,一人の社会人であり,旭川校の看板でもあります。自覚ある行動を望みます。
・当日参加できなくなったときは,必ず事前に大泉まで連絡を取ってください。(学外での活動,しかもボランティアであることに注意する)
・写真記録を行いたい場合は,センターの先生に承諾を得ること。(「写真を使用するときは,必ずご一報いたします」)
・アンケートを実施するときも同様。集計結果は,必ずセンターの先生にも伝えるようにする。
・センターの先生方に対する礼儀を重んじるべきです。挨拶をはきはきとする。「こんにちは」「よろしくお願いします」「ありがとうございました」「さようなら」は基本です。
・教育大の複数のサークルが,北門児童センターで活動しています。それらサークルと,自分たちはどんな部分で差異化できるのか?またはどんな部分で共同できるかも考えてみよう。
・貴重な現場経験です。やりっ放しでなく,何かしら記録しておくことを勧めます。大泉も「造形ボランティア日記」を記しています。(自分なりのテーマをもって取り組むことは,大歓迎!)
・題材企画に関する相談は,逐一受け付けます。メールにて在籍確認の上,研究室へどうぞ。
・参考になるHP
「じどうかんネット」http://www.jidoukan.ne.jp/net/net.php
・・・全国にある児童館の紹介のほか,様々な遊びの紹介,掲示板など,充実しています。