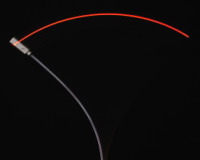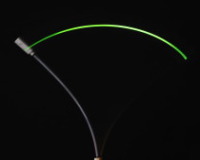| 直流/交流比較実験器 A(電流の向きの変化) |
| 直流/交流比較実験器 B C |
| 直流と交流の特徴を比較する実験の中に、電流の流れる向きが、直流ではいつも同じ向きと、交流では交互に変わることを確かめる実験がある。直流と交流を比較する観点は、①電流の向き、②電圧の変化、③直流・交流と、他の電気部品との関連 などである。 |
|
| 1 電流の向きを確かめる実験の問題と工夫 |
|
① |
電流が流れる向きが違うことを調べる実験で、子供一番わかりやすいのは、モーターの回転の向きが変わることである。しかし、残念ながら、モーターの回転の向きが、交流の周波数についていけないので、この方法は、普通の電源ではできない。 |
|
② |
そこで、ほとんどの教科書では、LED2つを逆向きに並列につなぎ、電流を流している。 |
| |
|
直流では、並列の片方だけがつくが、交流では、両方つくことを見せる。そして、実は、交流の場合、交互にLEDが点滅していることを、実験器を左右に振ることで確かめている。 |
| |
|
この場合、LEDの性質(極性があること)を、子供は、よく理解していないとならない。 |
| |
③ |
市販されている②の実験器は、硬い棒か、板にLEDがついているので、振るのが大変で、きれいな点滅が見られない。そこで弾力のあるばね棒を使う。 |
| |
④ |
商用電源は、周波数が50か60ヘルツで、変化が速いので、任意に周波数が変えられる自転車用発電機を利用する。これを使うと①のモーターの実験も可能である。 |
|
|
|
| 2 直流/交流LED点滅実験器(ヤガミで市販されている) |
| |
◆材料 |
 |
 |
|
| LED 3φ 赤1 緑1 |
2 |
| ステンレスばね棒 2.5φ 長さ30cm |
1 |
| アクリル板(黒) 厚さ2mm、60×20mm |
1 |
| プラスチックパイプ 20mmφ 長さ20cm |
1 |
| 押し切りスイッチ 赤1 緑1 |
2 |
| 定電流ダイオード |
1 |
| 抵抗(33Ω、50Ω) |
各1 |
| 導線、ゴム栓 |
|
|
|
◆つくり方 |
 |
|
① |
黒のアクリル板に、LEDをつける穴を2つ(間隔40mm)をあける。 |
|
② |
赤と緑のLEDをはめ込み、2つを極性を反対して並列に配置し、導線3本をスイッチまで配線できるようにする。 |
| |
|
途中に、LED保護として、定電流ダイオードと抵抗を入れる。 |
|
③ |
ゴム栓に穴をあけ、ステンレス棒を差し込み、グリップのパイプにはめ込むみ。 |
| |
|
ゴム栓には、3本の栓が通るように側面に溝を切っておく。 |
|
④ |
赤のスイッチには、緑のLED、緑のスイッチには、赤のLEDをつなぎ、点灯状態になるように配線する。 |
|
|
グリップで、赤のボタンを押せば緑色のLED、緑のボタンを押せば赤色のLEDが消えるよう配線する。 |
|
◆活用法(弾力があるので、振るに楽で、きれいな線が見える) |
| |
|
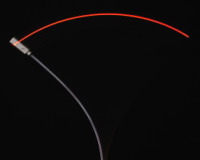 |
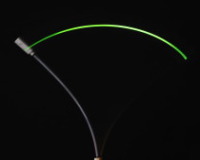 |
 |
| |
|
直流/赤側が+ |
直流/緑側が+ |
交流 |
| |
|
|
|
|
| 3 直流/交流の比較のための電源装置 |
|
◆材料 |
 |
|
| 自転車用発電機(交流) |
1 |
| ゴムタイヤ |
|
| 木板(台用)、10mmφボルトとナット、ねじ など |
|
| 整流ブリッジ(200V2A) 導線、ターミナル |
|
|
| |
◆つくり方 |
|
① |
タイヤを回転させやすいように、ハンドルをつける。 |
|
② |
タイヤをまわす台をつくり、中心にボルトを通し、タイヤをはめ込む。 |
|
③ |
自転車用発電機を台に固定する。このとき、発電機の回転部がタイヤに当たってまわるようにする。 |
| |
④ |
交流は、そのまま出力し、ブリッジ整流した直流の端子もつくっておくと便利である。 |
 |
|
◆活用法 |
| |
① |
タイヤをまわして発電する。回転数で周波数が変化するので、便利である。 |
| |
② |
羽根(3枚羽根がよい)をつけたモーターを回してみると羽根が往復する様子が見られる。(交流) |
| |
|
直流にすると、一方向にいきおいよく回転する。 |
|
| |
③ |
逆向きにし、並列につないだLEDは、ゆっくりな交流なので、交互に点滅するのがよくわかる。 |
| |
|
|
|