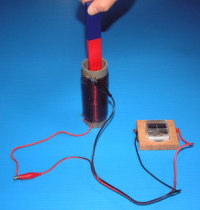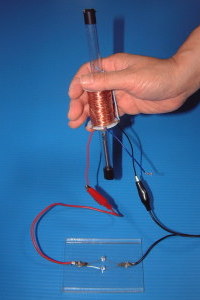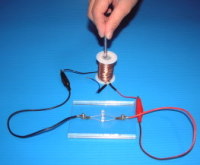| 電磁誘導用コイル(個人実験用) |
| |
|
|
|
| 電磁誘導の実験では、コイルと検流計が不足していて、子供一人一人が実験できない。そこで、次のように工夫してみた。 |
|
| 1 工夫したところ |
|
|
① |
普通の棒磁石の出し入れが楽なコイル(大型コイル) |
|
② |
磁石の出し入れで、LEDが点灯し、個人実験可能な小型コイル |
|
③ |
磁石の往復がすばやくできる小型コイル |
|
※小型コイルには小型アルニコ磁石を使用。1500円ぐらいで普通の鋼製より安い |
|
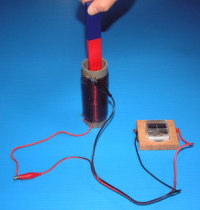 |
| 2 材 料 |
|
| 大型コイル用 エナメル線 0.4mmφ |
約300g |
小型コイル用
エナメル線 0.2mmφ と 0.26mmφ() |
各100g |
大型コイル用 巻きわく 塩ビパイプ
長さ13cm 内径35mm 外径42mm |
1 |
| 小型コイル用 巻きわく 市販コイル用ボビン |
2 |
| 配線用ビニール線 |
少々 |
| 透明塩ビパイプ 長さ20cm 外径12mm |
1 |
| アルニコ磁石、LED(赤)、簡易検流計(電流計) など |
|
|
|
|
| 3 作り方 |
 |
|
◆ |
大型コイル |
| |
① |
長さ13cm 外径42mmの塩ビパイプに、0.4mmφエナメル線を約800回巻いていく。
|
|
|
※学校で使用している棒磁石の大きさに合わせる。 |
|
② |
200回ぐらいで、途中端子を出す。 |
|
③ |
右巻きと左巻きをつくり、何か区別する工夫をする。(導線の色を変えるなど) |
|
|
|
|
|
◆ |
小型コイル Ⅰ (0.26mmφエナメル線使用) |
 |
|
④ |
長さ45mm 内径13mmのボビンに、0.26mmφエナメル線を約3600回巻いていくく。 |
|
⑤ |
1200回で、途中端子を出す。 |
|
|
|
|
◆ |
小型コイル Ⅱ (0.20mmφエナメル線使用) |
|
⑥ |
長さ45mm 内径13mmのボビンに、0.20mmφエナメル線を約4000回巻いていくく。 |
|
⑦ |
2000回と3000回で、途中端子を出す。 |
|
|
|
|
| 4 使い方 |
|
◆ |
大型コイル(普通の棒磁石を使用) |
|
|
① |
右上の写真のように、簡易検流計(別ページ参照)を接続し、棒磁石を出し入れすれば、誘導電流が観察できる。 |
|
② |
巻き数の違いによる電流の強さ、、右巻き・左巻きの違いによる電流の方向などが観察できる。 |
|
③ |
しかし、LEDを点灯させることはできない。 |
|
|
|
|
|
◆ |
小型コイル Ⅰ・Ⅱ (長さ50mm、太さ5mmφのアルニコ磁石を使用) |
|
④ |
巻き数が多いので、アルニコ磁石を出し入れすると、簡易検流計の針の振れが大きいので、注意を要する。電流計でも確認できる。 |
|
⑤ |
LEDは、3000回以上で、アルニコ磁石を出し入れすると、点灯する。(写真下) |
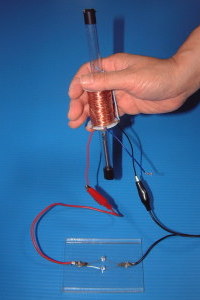 |
|
|
※磁石をコイルに入れるときの方が点灯しにくいが、4000回だとはっきり点灯する。 |
|
⑥ |
右の写真のように、コイルに塩ビパイプを通し、その中をアルニコ磁石を行き来させる(振る)と、LEDはが、明るくはっきり点灯する。 |
|
|
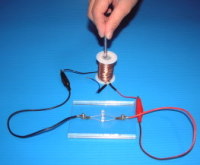 |