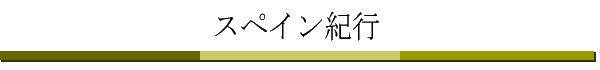
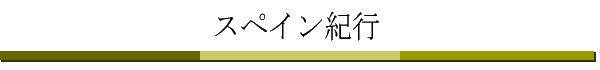
|
3日目(3/21) ブラド美術館とコルドバ 朝、出発前に現地ガイドの近藤さんにこんな質問をしてみました。 「2月11日のアトーチャ駅の列車爆破事件でバスク過激派犯行説が報道されましたが、バスクにはかなり大きな自治権が認められているのに何故彼らが過激な行動をするのですか。」 「何故彼らが過激な行動に走るのか、本当は良く分からないのです。フランコの時代には彼らの話すバスク語の使用は禁止されていましたが、今は公用語として認められています。彼らは自分たちの組織(ETA)を続ける資金稼ぎために行動をしているのでイデオロギーも何も持っていません。彼らを支持する人もほとんどいないのです。」 「バスクの人たちはピレーネ山脈の麓の谷あいにひっそりと暮らしてきた民族ではないのでしょうか。ザビエルもバスク人だと思いますが」 「司馬遼太郎さんはそのように書いていますがバスク人はそのような民族ではありません。フランシスコ・ザビエルも純粋なバスク人とはいえないと思います。」 私のバスクの知識はもちろん、司馬遼太郎さんの「街道を行く・南蛮へのみちⅠ・Ⅱ」によるものです。近藤さんはそのことを察して答えてくれたものです。純粋なバスク人ではないといった事は少し解釈が難しい。バスク人はこれまで国家というものを持ちませんでしたし、彼らのアイデンティティは系統不明のなぞの言葉、バスク語を話すことでしょう。ザビエルの父はアラゴン王国に使えていました。それが何故今独立運動なのか不思議です。 スペインが誇るブラド美術館(Museo del Prado) プラド美術館は1819年11月19日「王立絵画彫刻美術館」として開館しました。元は王立科学博物館として建てられた建物でした。開館後も何度も改築が重ねられて現在の姿になりましたがなお新しい施設の計画があるそうです。 美術館に入るには飛行場と同じように手荷物検査を受けなせればなりません。大きな荷物、リックサック、大きめなバック、ナイフ、はさみ、液体類などは持ち込み禁止です。フラッシュをたいての撮影とビデオ撮影は禁止されています。
エル・グレコとはギリシャ人という意味ですからもちろん本名ではありません。本名はドメニコス・テオトコプロスといいます。グレコはクレタ島の出身でトレドに住み天上世界を描き続けた人です。ベラスケスはフェリペ4世の宮廷画家、ゴヤはカルロス4世の宮廷画家でした。またルーベンスはバロックの大御所といわれる大画家ですし、なんとも不可思議な絵を描くボッスはフェリペ2世のお気に入りの画家です。その他、私の好きな絵であるベラスケスの「バルタサール・カルロス皇太子騎馬像」や彼の絶筆となった「マルガリータ王女」、フラ・アンジェリコ作「聖告(受胎告知)」などを見て回りました。たっぷりの2時間といわれましたがとてもとても2時間ではゆっくり見ることもできませんでした。 ラス・ベンタス闘牛場(Plaza de Toros de Las Ventas) スペイン3大闘牛場の一つ、威風堂々の建物です。前の広場で闘牛の話を聞きました。闘牛士には3種類あり馬に乗って槍で牛の首筋をつく役のピカドール、飾りの付いた派手な銛を付きたてる役のバンデリリェーロ、そして最後が手負いの牛を迎え撃ち、とどめを刺すマタドールです。もちろん花形はマタドールですばらしい演技には牛の耳が与えられます。さらに最高の演技をしたときは牛の尻尾が与えられ、ファンに肩車されて正面の門から出てくるのだそうです。最近は医学の進歩で牛の角にやられても死ぬ人は少なくなったのだそうですが、かつては有名な闘牛士も何人も死んだのです。広場のモニュメントには若い闘牛士が召されて天使が生まれたと書かれた彫刻がありました。 スペインの日曜日 デパート、スーパー、お店は日曜日には全部しまっています。これは法律で決められているので勝手に日曜日に営業してはいけません。行楽地の売店などは許可を取って営業しているのです。これは本来、家庭の主婦を家事から解放することを目的にしています。昔はどの家も大家族であったので主婦の家事も大変だったのです。いまはそれほど家族も多くはありませんが休日は家族で郊外に出かけるそんな生活がごく普通なのだそうです。休日も満足にとれずに働いている日本人は異常なのかもしれません。 昼食は「Museo del Jamon」というアトーチャ駅の近くにある生ハムの店でした。ジャガイモの入ったスペイン風オムレツと生ハムを食べました。生ハムはもちろんスペインの名物ですがほかのハム・ソーセージ類も大変おいしく感じました。店の壁に一面につるされた生ハムは壮観です。 AVEにてコルドバ(Cordoba)へ 昼食後はアトーチャ駅へ向かいました。駅前には2月11日のテロによって亡くなった202名の慰霊を弔う花束やローソクがあり、多くの人が集まっていました。ハイジャック防止のシステムの検査を受けて車両に乗り込みました。AVEは出発の14:00になると発車のベルもなく静 かにすべるように走り出しました。駆動車両が先頭車両と後尾車両だけで、日本の新幹線とは構造が異なります。揺れも少なく大変静かでした。 はじめの1時間ほどは平らな風景が広がります。麦畑、オリーブ畑が延々と地平線まで続いています。1時間半ほど走ったところで車窓の風景が変わってきました。AVEは山の中を走るようになります。山といってもそれほど高い山ではなく、山羊の放牧が見えました。トンネルが続き、13個目のトンネルを抜けたところがコルドバ駅でした。さすがスペインが誇る新幹線で定刻の15:41ぴったりの到着でした。
そして柱の高さや形はそれぞれバラバラ、これは以前あった建物の材料を再利用したものであるからです。使われている材料も大理石、花崗岩、雪花石膏など時代や場所によって様々でした。しかし天井や壁の飾り彫刻は実に緻密で美しい。特にミヒラブと呼ばれる祈りの場のアーチ装飾、モザイクは見事でした。 1236年聖フェルナンドによって再征服されるとこの建物はキリスト教会として改装されることになったのです。1523年工事は開始され200~300本の柱が抜かれメスキータの中に教会が作られることになったのです。この工事を認めた国王カルロス5世は後にここを訪れてこう言ったといいます。「私は、このようなものだとは知らなかった。知っていれば決して手をつけるようなことはさせなかったであろうに。なぜなら、その方達はどこにでも造れるものを建てているのだ。そのために、世界に1つしかないものを破壊してしまった」と。トレドでも見ましたがここの主祭壇も大変見事なものです。聖歌隊席はキューバのマホガニーで作られています。パイプオルガンは18・19世紀に作られたものです。 メスキータの北西すぐ近くに旧ユダヤ人街があり、その一角に花の小径といわれる小さな路地があります。窓や壁に飾られたゼラニュームの赤い花が可愛らしい所でした。 見学を終えてバスは一路、セビリアの街を目指します。距離は約137Km、時間にして2時間というところです。スペイン南部はアンダルシアといわれる地域ですがここにはスペインのイメージが凝縮しています。情熱の国、太陽の国、闘牛士とカルメン、ひまわり畑、オリーブとオレンジこれらはみなアンダルシアの文化です。アンダルシアの人たちは黒髪、黒い瞳で陽気で明るい。人生を楽しむために働く。明るい太陽の下で祭りに明け暮れていると今日を楽しくという気になるのでしょう。
今宵の宿はセビリアの西20Kmのところにあるサンルカールラマヨールのソルカールというホテルでした。 |