2017.11.21
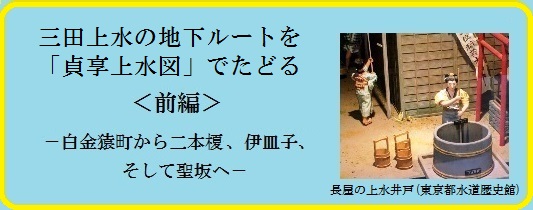
はじめに
三田上水は、江戸幕府が寛文4年(1664)に玉川上水・下北沢村から三田・芝まで開いた全長約12㎞の上水です。下北沢村、代々木村、中渋谷村、目黒村、白金村を通って白金猿町(大崎猿町)まで地表を流れ、そこから樋管(木樋や石樋)で地中に入り、高輪町、三田町、松本町、西應寺町まで届きました。後には北品川の八ツ山下へも伸びていました。流れが地中に入った白金猿町は、現在の高輪台交差点の辺りです。当時の幕府は江戸市中に水を配るために神田上水、玉川上水を始めとする六つの上水の開発を進めていましたが、そうした中で三田上水は、古川(渋谷川)より南にある大名屋敷や町屋に水を届けることを目的としていました。玉川上水の羽村水門が幅5間(9m)・高さ3尺(90㎝)に対し、三田上水の下北沢村の取水口は3尺四方(90㎝)でしたから、取水口を全開にすれば玉川上水の約1割の水を引くことができました。その大きさは時の老中松平信綱が自らの川越藩に引いた野火止用水に次ぐもので、幕府の力の入れぐあいが分かります。
しかし時は変わり、三田上水は享保7年(1722)に幕府の命で突然廃止されて58年の歴史を終えました。(注1)。その後三田上水の余水を灌漑に用いていた14カ村から請願があり、享保9年(1724)に下北沢村から白金猿町までのルートが村民に払い下げられました。名前も「三田用水」と改め、流れは昭和50年まで約250年にわたって続きました。しかし白金猿町から三田、芝、品川までの地中のルートが復活することはありませんでした。三田上水は三田用水と違って史料が少なく、遺跡や遺物もほとんどありませんが、「三田用水」の生みの親とも言うべき存在です。今回はそうした三田上水の流れの中で、これまであまり取り上げられることがなかった白金猿町以降の地中のルートを探ります。
<前編>
1.「貞享上水図」と三田上水
2.高輪台地・三田台地を流れる三田上水
(1)白金猿町から二本榎へ
(2)伊皿子の細川屋敷と老増町
(3)三田台町を通って聖坂へ
<後編>
3.三田・芝、そして品川を流れる三田上水
(4)三田通りに入って阿波横丁、松本町へ
(5)西應寺町とその周りの町
(6)東海道を歩いて品川の八ツ山下へ
<「貞享上水図」とは>
今回のお散歩のガイドは、貞享の頃(1685-1688)の江戸の上水ルートを描いた「貞享上水図」です。この絵図は東京市役所『東京市史稿』上水篇の付図(大正10年)で、貞享年間に描かれた神田上水と玉川上水の絵図を合体して作成しています(注2)。上の図はその部分で、下の方に描かれている二本の横線の下の線が三田上水です。原図はカラーですが、国会図書館から白黒のデータでの公開許可を頂きました。図の左端にある太い縦線が玉川上水です。三田上水(図には芝三田参候水道と表記)は、玉川上水・下北沢村から取水し、白金猿町を経由して東の西應寺町まで流れていました。南の品川に向かう流れは途中で終わっていました。「貞享上水図」には、地中の樋管(木樋、石樋)のルートと枡の他に、大名屋敷や寺社、町屋などが記されていますが、三田上水はルートと枡以外はあまり書かれていません。このため、同じ時代に作られた古地図(注3)や幕府が編纂した『上水記』(注4)や『御府内備考』(注5)などを参考にして、上水の流れや当時の町の様子をさぐることにしました。
ところで、「貞享上水図」で三田上水のすぐ上を流れているのが細川上水(細川越中守殿参候水道)です。熊本藩主・細川越中守が伊皿子の私邸に引いた上水で、三田上水の7年前の明暦3年(1667)に開かれました。細川上水は三田上水より三町(約330m)下流の場所で取水されたと伝えられ、その後は三田上水と並ぶ形で細川屋敷の前まで掛っていました。面白いことに、二つの上水は途中で2回交差しています。細川上水は三田上水と同じ年に廃止され、その一部は後の「三田用水」の水路にも使われたようです。三田上水の流れは途中までは細川上水とよく似ていますが、その目的や上水の仕組みを考えると、江戸の地中に上水網を張り巡らしていた玉川上水の方とより多く共通点があります。
<今回のお散歩ルート>
左の図は「貞享上水図」の三田上水のルートをGoogleマップに赤の線で書き込んだものです。歩いた道は黒い線です。三田上水はルートと桝以外は情報が少ないため、武家屋敷や寺社、町屋については同時代に描かれた幾つかの古地図を用いました。その中でメインに選んだのが延宝七年刊「江戸大絵図」(1679)で、この図は『東京市史稿』産業篇第7巻(1960刊行)附図です。延宝7年は貞享年間(1684~87)の数年前であるため、「貞享上水図」が描かれた頃の町の様子を知る手掛かりになります。また方角や面積も同時代の地図の中では比較的正確です。
Googleマップに三田上水の想定ルートと歩く道を書き入れた手順ですが、白金猿町から西應寺町までの樋管(地中の木樋や石樋)は道路に沿って埋設されていたため、まず「貞享上水図」の中で三田上水が掛っていた道を「江戸大絵図」で探し、その道の時代的な変化を江戸末期や明治以降の地図の中で確かめ、それを現代のGoogleマップに反映させました。そこで感じたのは、貞享と現代では約300年も離れているのに、道の方向や形が実によく似ていたことです。大きく変わったのは芝の薩摩屋敷の周りぐらいでしょうか。もちろん道幅や傾斜はかなり変わっているはずですが、実際に現地を歩いてみて、その思いをさらに深くしました。歴史が色濃く残っている土地なのです。こうした地域を歩く時間ですが、白金猿町(高輪台)からのメインのルートは半日で十分でした。しかし史料で明らかになった支管のルートは何回かに分けて歩きました。台地と麓の町の間には20m前後の高度差があり、夏の暑い最中ということもあって急坂を往復するのが大変だったからです。以下では、左の図の緑の①~④枠にしたがって、三田上水の流れを順にたどります。
2.高輪台地・三田台地を流れる三田上水
(1)白金猿町から二本榎へ
左の図は先の全体図の①部分で、赤い線が三田上水のルート、黒い線が歩いた道です。右はこれに対応した「江戸大絵図」で、三田上水のルートと桝を書き込みました。三田上水が地中に入ったとされる白金猿町(現在の高輪台交差点の辺り)は、三田上水が開かれる13年前の慶安4年(1651)に起立した商人町屋で、「江戸大絵図」で見ると左下の細川丹後のすぐ下に記されている「町」がそれです。文政年間(1818-1830)に幕府が町の名主に提出させた「町方書上」には、道を挟んで南北に89軒の町屋が並んでいたとあります(注6)。「貞享上水図」が描かれた頃は起立して三十数年が経っており、町は賑わいをみせていたのでしょう。
<白金猿町の桝の役割>
今回のお散歩の出発点は高輪台交差点(桜田通り)の少し手前で、目印は白洋舎のお店です。この場所の標高は国土地理院の地図によると28.7mで、三田上水はこの地から標高2.4メートルの西應寺町へと流れていました。『上水記』には、「下北沢の取水口から地表を開渠で流れてきた三田上水は、白金猿町(大崎猿町)があった交差点の辺りから地中に入った」と書かれています。ところで「貞享上水図」を見ると、白金猿町に入る手前に連続して二つの桝があります。「江戸大絵図」で細川丹後守屋敷の右の角に記した二つの赤い四角です。現在の白金児童公園(猿町公園)と高輪台交差点の間でしょうか。桝は当時、土中にあるものと地上にあるものがあり、流れを分けたり、水勢や汚れの具合を調べたり、水を引き上げたり降ろしたりと、様々な目的に使われていました。江戸は火事が多かったため、消火の水にも使われました。「貞享上水図」に描かれた三田上水の桝の数を数えると23カ所ありました (注7)。
ところで、玉川上水の四谷大木戸には水番所と水門があり、そこで水量の調節やゴミさらいをして(芥留め)、余水は渋谷川に流していました(水吐き)。三田上水についても同じことで、白金猿町から地中に潜る前に水量を加減し、石や砂、ゴミなどを取り除き、余水を目黒川に流していたことが考えられます。そうした作業をしなければ、これから何キロも続く三田上水の地中の流れを正常に保つことはできないでしょう。白金猿町の手前の二つの桝は水番所に代わるような重要な役割を担っていたはずです。
<二本榎通りを伊皿子坂に向かう>
高輪台の長い信号を渡って100m余りまっすぐ進むと、二本榎通りのT字路に突き当たりました。ここを左に折れると三田・芝へ、右に折れると北品川の八ツ山下へ向かいます。この日は三田・芝に行くことにしました。一日に両方はむりですね。二本榎通りは昔からある街道で、徳川家康が天正18年(1590)に江戸に入って東海道の道幅を広げるまでは奥州に抜ける幹線でした。街道は高輪台地と三田台地の尾根を伝わって北に向かっており、道の右側(東)は海岸、左側(西)は渋谷川沿いの低地になっています。街道から両側に降りる天神坂、魚籃坂、伊皿子坂などはいずれも急傾斜ですが、それは、これらの台地が7000年ぐらい前の縄文海進期(海面が今より数メートル高かった時代)に波の浸食を受けたためです。台地から三田の低地に下りる聖坂も、品川に下りる柘榴坂もかなりの傾斜です。
「貞享上水図」には二本榎通りの入口に桝がありましたが、この桝を使って上水を三田・芝と北品川に分けていたと考えられます。三田上水の桝の配置を調べると、ここから2㎞先の聖坂の下まで一つもありませんが、特急電車のようにただ素通りしていたわけではありません。『上水記』や『御府内備考』を読むと、老増町や車町のようなルートから外れた町にも三田上水が届いていたことが分かります。三田・芝の低地部に入ると、そのような町がたくさんありました
(注8)。「貞享上水図」の時代から三田上水が廃止されるまでの約40年間に、新たなルートが開かれたり、桝が設けられたと考えた方が良さそうです。
<二本榎の由来>
二本榎通りを歩いているとお寺が目に付きます。この土地にお寺が多いのは、明暦の大火の後、幕府が防火のために寺社を江戸の周辺に移したためです。江戸時代の古地図を見ると、この地域には今以上にお寺が多く、とくに伊皿子を超えるともうお寺の団地という感じでした。各お寺の前には必ずと言っていいほど門前町屋が置かれており、昔の人は何かとお寺を訪れていたようです。
高野山東京別院(右側)の大きな門の前を越えると、高輪警察署と高輪消防署(二本榎出張所)がある交差点に出ました。信号の左角に緑の街路樹が茂ったモダンな公園がありました。この公園一帯はかつて上行寺と門前町屋の敷地で、二本榎と呼ばれており、二本榎通りの名の元になりました。二本榎とは上行寺の表門に古くからあった高さ三丈(9m)余りの2本の榎で、一里塚として旅人の目印になっていました。榎は何回も火事で焼けましたが、地元の人に植え継がれて今日に至っています。公園には榎の歴史を記した石碑があり、後ろには壮年期と思しき元気な榎が立っていました。『上水記』や『御府内備考』には二本榎に三田上水が掛っていたことが記されています。二本榎通りを歩いてきた旅人は、榎の下のお茶屋で疲れを休め、上水で喉を潤していたのでしょう。
<樋管、枡の形やサイズ>
ところで、地中を通っていた樋管(木樋など)や桝はどのような形をしていたのでしょうか。元東京都水道局の堀越正雄氏は、玉川上水(西銀座)の木樋の発掘に立ち会った時の様子を述べています。「地下3メートルぐらいのところに(中略)、30センチほどの真四角な木樋が、2メートルぐらいの長さでつなぎ合わされて、100メートル以上も真一文字に延びているのがわかった。そしてある部分では、木樋の側壁に小さな穴がえぐられていて、そこからさらに、いちだんと細くした四角い木樋が直角にのびているのが見えた。たぶん本管から分岐した支管のようなものであろう」(注9)。後の「三田用水」の時代ですが、目黒川に余水を流すために白金猿町の地下を通した埋め樋は巾1尺(30㎝)でした(注10)。最近は神田上水や玉川上水の発掘調査が進んでいますが、地中から発掘された樋管や枡を見ると太さ、形、材質は様々です。(注11)。
下の図はそうした樋管や桝と、屋敷や町屋に設けられた上水井戸を繋いだモデルです。図の下の方に描かれた樋管(木樋、竹樋)を上水が右から左へ流れており、桝(埋桝、桶枡)の所で流れの向きを変えたり、上水井戸に水を溜めたりしています。上水井戸の底には「泥溜」があり、ここに泥や砂を沈めて取り除いています。このような仕組みの上水網が江戸市中にびっしりと張り巡らされ、人々の毎日の暮らしを支えていたわけです。
上水の使い方ですが、本管から木樋や竹樋で引いた水を上水井戸にいったん溜めてから使いました。大名や武家は上水を専用管で敷地内に引き入れ、上水井戸に溜めて飲み水に使ったり、庭の泉水やお堀に流し込んでいました。町人については、豊かな商家などは家々に上水の井戸を持っていましたが、長屋の住人は上水井戸(溜桝)を共同で管理し、もっぱら飲み水に使い、洗濯や水浴びは雨水か浅い井戸水で済ませていました。井戸の底に桶を降ろしてツルベで汲み上げるため、女性や子供には重労働だったようです。水道橋の東京都水道歴史館(東京都文京区本郷二丁目7-1)には都心で発掘された木樋や桝が展示されており、長屋で上水井戸を使う様子などが時代劇のセットのように精巧に復元されています(タイトルの写真)。ぜひ訪れてみて下さい。
<三田上水の支管の継手を発掘>
話はお散歩に戻ります。高輪消防署の前を過ぎて少し歩くと、右に折れて品川へ下る道がありました。この道は延宝や元禄の地図にもあり、俗に但馬横丁と呼ばれていた古道です。弘化3年(1846)の「御府内場末沿革図集」を見ると、沿道にお寺と門前町が並んでいました。今は静かな一角ですが、当時は人通りの多い道だったのでしょう。二本榎通りから一時離れて、この道に入って数十メートル進むと、左側に高輪台小学校の校庭がありました。三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』によると、昭和50年頃にこの校庭から三田上水の遺物が発掘されました(注12)。ひどく腐食していたそうですが、原形は留めていて、中央に上水が通る四角い穴がえぐられていました。二本榎通りには三田上水の本管が通っており、部品が小ぶりなことなどから、著者の植松慶太氏は地中の木樋を繋ぐ「継手」ではないかと推測していました。私も現物が見たくて学校に連絡したのですが、そのような話は聞いていないし、遺物も保管していないというご返事でガッカリ。写真が残っているだけでも良かったです。実は植松氏はもう一つ大きな発見をしています。港区立芝小学校の工事現場で発掘された木樋なのですが、現場が三田上水のルートにちょうど当たっているため、その一部であった可能性があります。これについては
“特ダネ”があり、<後編>でご紹介します。
(2)伊皿子の細川屋敷と老増町
<細川上水と細川屋敷>
話を二本榎通りに戻します。但馬横丁の角を過ぎて北に歩くと、道路が少しずつ右に曲がり始めました。やがて右側に東海大学高輪キャンパスが、左側に都営高輪一丁目アパートの高い建物が見えてきました。東海大キャンパスの奥には「忠臣蔵」で名高い泉岳寺があり、斜め向かいの都営アパートと旧高松宮邸には、その四十七士を温かく迎えた細川越中守の下屋敷がありました。細川屋敷は、志士たちが討ち入後から切腹までのひと時を過ごした場所なのですが、その話はテレビドラマで有名なので省きます。当主の細川綱利は、初めにも書きましたが、三田上水より7年前の明暦3年(1657)に、玉川上水からこの屋敷まで細川上水を引いた殿様です。彼が上水を用いて庭に豪勢な池と滝を作ったところが、公儀を慮った家老が諫めて全て取り壊してしまったという人気の逸話が残っています。脚色抜きで言えば、幕府が細川家に伊皿子の下屋敷を与え、飲み水や泉水に使う玉川上水の分水を許したところが、殿様が豪快にやり過ぎたということでしょう。細川上水は私邸の上水であるためか、工事の請負人や建設費、土木技術、工事期間などの記録がありません。幕府が編纂した『上水記』にも書いてありません。幕府が仕切っていた玉川上水を分水したのに公式の記録にないのは不思議です。いずれにしても、細川家のような大藩になると、全長10㎞の上水路を一気に作ってしまうぐらいの政治力と財力を持ち合わせていたのでしょう。
<細川上水の終点>
高輪一丁目アパートの手前には江戸時代の商家のような虎屋の店がありました。この店を扇の要として、二本の道がV字形に北の方まで伸びていました。左は目黒不動に向かう天神坂の道、右は上の写真にある細川屋敷の裏道です。「貞享上水図」のルートをみると、屋敷の手前に二つの桝があり、細川上水はここで流れを終えていました。最後の桝は私邸に上水を引くためのものでしょう。屋敷の地形はほぼ平らですが、奥は北に向かって大きく下がっており、今は区立高松中学校の敷地になっています。標高差を見ると、細川屋敷が24~26mに対し高松中学校は10~15mで、とくに屋敷の北西の角が崖のように急に落ち込んでいました。殿様がもしこの高低差を使って滝を作れば江戸名物になっていたかもしれません。家老の気持ちは分かりますが、豪勢な池と滝を残しておいてほしかった気もします。
<三田村鳶魚『江戸の実話』から>
細川屋敷の地形に端を発した江戸の逸話がまだあります。三田村鳶魚『江戸の実話』には、細川上水が廃止されて25年後の延享4年(1747)に、旗本の板倉修理が細川綱利の孫の宗孝を殿中で切り付けた話が載っています。幕府が真相を明らかにしなかったため、町の人々が色々と噂をしました。その噂の一つなのですが、高い土地にあった細川家の庭には滝を作るために昔引いた水道が残っていて、大雨になると雨水が水道に入って溢れ出し、低地にあった板倉家の屋敷に流れ込んでいました。このため板倉氏が細川家に再三かけあったのですが埒があかず、とうとう怒って殿中で宗孝を襲ったというものです。宝永5年(1708)「分間江戸大絵図」を調べると二人の屋敷は確かに背中合わせでした。実際に屋敷の境に行ってみたのですが、高松中学校の敷地の南側で、細川屋敷の土地が切りたった崖のように前に迫っていました。腐った水道管がなくても、この地形ならば雨になると水が流れてきそうです。この事件は板倉氏の人違いという説もありますが、さて本当のところは…。
<老増町まで伸びていた三田上水>
話は三田上水の流れに戻りますが、旧細川屋敷の奥は谷のように下っており、降り切った所に桜田通りがあります。桜田通りのさらに北に老増町という面白い名の町がありました。老増とは町を起立した老沼庄助と増島惣左衛門の頭文字で、今でも当時の三角の町の形を残しています(白金一丁目28)。『御府内備考』にはこの町から「上水が掛っていた」という報告が出ていました(注13)。どこから取水したかは分かりませんが、辺りの地形や道を考えると、二本榎通りの本管に桝を設け、天神坂から木樋を降ろして町まで繋いでいたと考えられます。老増町は、農民に払い下げられた「三田用水」についても「町内の裏通りより新堀川へ流れていた」と報告しています。この流れは白金村から玉名池を経由して渋谷川の五ノ橋に注いでいた久留島上分水です。
日を改めて老増町へ出かけました。高輪台駅から二本榎通りに入って虎屋の左の天神坂を降りると、桜田通りの信号「清正公前」に出ました。幅広い道路の向こうに加藤清正を祀った覚林寺が見えました。交差点を渡って桜田通りを右に200mほど進むと、左側に斜めに入る道があり、そこを200mぐらい進むと立行寺の赤い門の前に出ました。このお寺を角にした三角形の土地が老増町です。試しに土地を歩測してみると、各辺が約50m×140m×150mありました。桜田通りに面した一角のトイレの壁に「老増町公衆便所」とありましたので記念に写真を撮っていたところ、タバコを吸っている方に睨まれました。町の標高は8.3mで、天神坂の上とは20m近い差がありますから、昔から水の通り道になっていたようです。
<単独で流れ始めた三田上水>
細川家屋敷に着くと細川上水と三田上水との並走が終わり、三田上水は単独で流れ始めました。旧高松宮邸(表通りはマンション)の前を通り過ぎると、もうすぐ伊皿子坂です。道路の右側を見ると、お寺の参道や建物の間の私道が南(海側)に向かって下がっていました。昔は建物の間から海の風が吹いてきたことでしょう。上の写真は道に面した保安寺の石門です。石段で作られた坂道がとてもきれいでした。
二本榎通りは伊皿子交差点の手前に来ると緩やかに下り、交差点を超えるとまた上がり始めました。交差点と高い所の標高差は4mぐらいありますが、この窪んだ所を三田上水はどのように超えたのでしょうか。先の「分間江戸大絵図」を見ていて気付いたのですが、江戸時代は現在のように魚籃坂と伊皿子坂がつながっていませんでした。中央を斜めに走る道の中ほどに「イサラゴ」という文字がありますが、その上の交差点はT字路です。幕末や明治時代の地図も同じ形でした。この辺りの地形は現在とかなり違っていたようです。
(3)三田台町を通って聖坂へ
<三田上水が掛かっていた牛町>
伊皿子交差点を越えて三田台町に入る前に、伊皿子坂周辺の三田上水の様子を述べます。『御府内備考』は、伊皿子坂の上にある伊皿子台町に三田上水が掛っていたと記していました。また、この坂を東海道まで下った所にある車町に三田上水が掛かっていたとありました(注14)。「貞享上水図」のルートには桝がありませんが、その後に本管に桝を設けて分水したのでしょう。車町は海岸に沿って南北に伸びていた細長い大きな町で、町名の「車」とは牛車のことです。当時、貴重な重機であった牛と牛持ち人足を増上寺の大工事のために京都から呼び寄せ、工事が終わった後でこの地に住まわせていました。車町には品川港に着いた荷物などを運ぶ牛車がたくさん行き来していっため、俗に牛町と呼ばれました。
上の絵は歌川広重「たかなわ牛町」です。大きな牛車の車輪がシンボリックに描かれ、その陰に食べカスを漁る子犬がいます。昼間は牛車と人波で騒がしい町ですが、東の海が赤く輝いている様子から、静かな明方の景色でしょう。大きな牛車と小さな犬、美しい港と浜辺のゴミというコントラストが面白いです。『御府内備考』には、明暦3年の江戸大火の後に牛車大工の八左衛門が人力による荷車を造ったとありました(注15)。牛町なのに牛を描いていないということは、この車輪も牛車ではなく新発明の「大八車」でしょうか。
後日に車町まで足を伸ばしてみました。伊皿子交差点から伊皿子坂を150mぐらい下ると、左に折れる細い急坂の道がありました。これが昔の伊皿子坂で、幕末までは階段があり、その脇を三田上水の支管が流れていたようです。坂を降りて行くと国道一号線(旧東海道)に出て、交差点の信号機に「高輪大木戸跡」とありました。その少し南に東海道の高輪大木戸があり、そこから車町が海岸沿いに南に続いていました。町の中は人と牛でいつもごったがえしていたようで、『御府内備考』には牛の数が142匹とありましたが、1000頭とか数千と書いてある本もあり、いずれにしても喧噪な町だったのでしょう。旅人を迎える掛茶屋も軒を連ねていたそうで、水の需要が大きかったと思います。
<月の岬から海原の月を眺める>
話は伊皿子坂の上に戻ります。伊皿子交差点を過ぎると道路が緩やかに上り、右手に三田台公園、亀塚公園が現れました。日曜日のため家族ずれの人々がたくさん遊んでいました。三田台公園の奥には伊皿子貝塚遺跡の調査で発見された縄文時代の住居跡があり、貝層の大きな断面が復元されていました。縄文時代は海進期に当たり、今より海面が数メートル高いところにありました。この辺りは小高い日当たりの良い丘で、海もすぐそばなので、縄文人が住むのに適していたのでしょう。『御府内備考』によると三田台町1丁目に三田上水が掛っていました(注16)。台町と名前が付くだけあって土地がとくに高いため、月を眺める絶好のスポットでした。「月之見崎(月の岬)」とも呼ばれ、歌川広重の有名な絵が残っています(この絵の場所は北品川の八ツ山との説もあります)。亀塚公園の辺りは船が安全に航行するための大事な目印にもなっていました。二本榎通りを挟んで両側に武家屋敷やお寺、門前町屋がぎっしりと並んでおり、この土地も上水の需要は大きかったでしょう。
<聖坂を一気に下る三田上水>
亀塚公園を過ぎると「聖坂」と書いた木の標柱が立っており、区立三田中学校(左側)の辺りから道が下がり始めました。かなりの急坂です。ここから坂下の三田3丁目交差点まで約400mありますが、亀塚公園の標高が28.0m、途中の汐見坂の前が11.1m、三田3丁目交差点が6.0mですから、100m当たり5mぐらい下がる見当です。急な坂道では地中の上水の流れも速かったことでしょう。左側にはクウェート大使館、亀塚稲荷、阿含宗別院などが続いていました。この土地は功運寺の大きな敷地で、道に面して門前町屋が幾つも並んでおり、功運寺門前から「三田上水跡」の報告が出ていました(注17)。お寺の門前から三田上水に関する書上げが出たのはここだけです。「貞享上水図」には聖坂の右側(海側)に久留島佐渡守の屋敷がありましたが、屋敷名を記したということは、ここに給水していたのでしょう。
聖坂をほぼ降りた所に左に上る坂道がありました。海がよく見えたと伝えられる「汐見坂」です。高輪台の交差点以来、上る脇道は初めてですが、それだけ下まで降りてきたということです。案内板に誘われて登ってみたところが、上は見晴らしの良い高台でした。今は大きなビルが並んでいますが、埋め立てる前は海岸に沿って田町の民家が並び、その向こうに広い海と房総の山々が開けていたのでしょう。「貞享上水図」では、汐見坂の少し先に桝がありました。二本榎通り入口にあった桝から約2㎞ぶりの桝ですから、水位をチェックしたり、石砂や泥、ゴミを取り除くなど色々な役割を担っていたと考えられます。聖坂の下には町屋が集まっていましたから、ここにも水を届けていたでしょう。高輪台地と三田台地を流れた三田上水の話はこれで終わります。次回は低地部の三田・芝、そして新たにルートが伸びた北品川の流れを探ります。お楽しみに。(前編・終わり)
<注釈>
(注1)幕府は享保7年(1722)に神田上水、玉川上水を除く四上水(青山上水、本所上水、三田上水、千川上水)を突然廃止しました。その理由として儒学者の室鳩巣(直清)の非科学的な建議があったとされていますが、他にも水道の維持が財政的に難しくなったこと、堀り井戸の技術が発達したこと、武蔵野の新田開発のために灌漑用水が必要になったことなどがあります。
(注2)「東京市史稿上水編付図解説」(大正10年発行)によると、原図は旧幕府から東京府に引き継いだもので、「神田上水大絵図」と「玉川上水大絵図」を合わせて1図にし、仮に「貞享上水図」としました。原図の表題肩書には「貞享之頃」とあり、神田上水と玉川上水がほぼ完成した貞享年間の様子を知ることができます。
(注3)「明暦三年の絵図」『東京市史稿 變災篇 第4付図』。三田図書館「延宝年間図」『港区近代沿革図集』別冊、昭和54年。延宝七年刊「増補
江戸大絵図 繪入」『東京市史稿』産業編第2巻付図、1960年。元禄六年刊「江戸圖正方鑑」。寶永五年「改正 分間江戸大絵図」『東京市史稿』産業編第9巻付図、1964年。享保元年頃「分道江戸大絵図 乾」。享保7-8年「享保年中江戸繪図」『東京市史稿 水道篇付図』、大正8年など。他に港区立三田図書館『近代沿革図集』や内務省地図等を参考にしました。
(注4)『上水記』は江戸幕府の普請奉行石野広通が天明8年から寛政3年にかけて編集した水道事業の報告書で、玉川上水と神田上水の歴史、運営、水路、技術などを記してあります。三田上水が掛っていた地名として、北沢むら・代々木村・中渋谷村・三田村・上目黒村・中目黒村・白金村・大崎村・大崎猿町・二本榎・伊皿子通り・聖坂・三田町・松本町・新馬場・同朋町・西応寺町、他に八ツ山辺・高輪・浮簀・芝田町筋・新網町・増上寺新門前辺・大芝町・芝金杉辺などを挙げています。詳細は「三田上水の事」『上水記』東京都水道局、平成18年、285-286頁。
(注5)江戸幕府が『御府内風土記』を編纂するために集めた江戸市中の地誌の記録で、町名主に町の由来や市街の状況などを書上げさせたものです。完成は文政12年(1829)頃。『御府内風土記』は明治5年の皇居火災で焼失しましたが、編纂時に集めていた資料を後にまとめて『御府内備考』としました。それによると江戸市中の26の町(各丁目)から「三田上水跡」や「上水跡」の書上げが出ており、これらの町に三田上水が懸っていたことが分かります。詳細は蘆田伊人編集校訂『御府内備考』第4・5巻、雄山閣、昭和45年、312、315頁。
(注6)長谷川正次『江戸町方書上』(二)芝篇下巻、395-397頁
(注7) 「貞享上水図」に描かれた三田上水の桝の数は合計23カ所、白金猿町以降は20カ所です。細川上水は合計9カ所、白金猿町以降は3カ所です。神吉和夫『玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する研究』によると玉川上水の桝は四谷大木戸より下流で408カ所あります。
(注8) 三田上水が掛っていたことが『上水記』や『御府内備考』に記されている町で、「貞享上水図」のルートにはない町があります。『上水記』では八ツ山辺、浮簀、芝田町筋、大芝町、芝金杉辺など。『御府内備考』では金杉通、金杉裏、本芝、六軒町、老増町、車町など。「貞享上水図」が記録を省いたか、貞享年間より後の時代にルートが伸びたことが考えられます。
(注9)堀越正雄『日本の上水』、新人物往来社、144頁。
(注10)蘆田伊人編集校訂『御府内備考』第4巻、雄山閣、357頁
(注11)神吉和夫『玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する研究』では、樋管の内法は3寸(30cm)四方が多く、桝は内径が3尺(約90㎝)四方、高さが5尺(150㎝)の直方体が多いとしています。材質は石、木(ヒノキ、松)、竹、陶器など。上水井戸は箱型が多く、高さは約13~16尺(4~5m)、直径は約2.5尺(76㎝)です。他に樽を使った丸い桶桝もあります。詳しくは同論文の6-15頁、63-70頁。
(注12)三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』同組合発行、昭和59年、45-47頁。
(注13)前掲『御府内備考』第4巻、336頁。
(注14)前掲303、315頁。
(注15)前掲295頁。
(注16)前掲324頁。
(注17)前掲339頁。
<参考文献>
東京市役所『東京市史稿』上水篇第1、大正8年
東京市芝区役所『芝区誌 全』、昭和13年
東京都港区役所『新修港区史』、昭和45年
蘆田伊人編集校訂『御府内備考』第4・5巻、雄山閣、昭和45年
堀越正雄『日本の上水』新人物往来社 昭和45年
東京都港区立三田図書館『近代沿革図集』全巻、昭和47年
間宮士信他編『新編武蔵風土記稿・東京都区部編』第1・3巻、春秋社、昭和57年
三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』同組合発行、昭和59年
神吉和夫『玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する研究』とうきゅう環境浄化財団、1994年
伊東好一『江戸上水道の歴史』吉川弘文館 平成8年
江戸遺跡研究会編『江戸の上水道と下水道』吉川弘文館、2011年
野中和夫編『江戸の水道』同成社、2012年
2017.11.21

3.三田・芝、そして品川を流れる三田上水
上の図は「貞享上水図」に描かれた三田上水のルートで、<前編>の初めに載せたものと同じです。<後編>にも「貞享上水図」のルートや桝の話がよく出てきますので参考にして下さい。
(4)三田通りに入って阿波横丁、松本町へ
左の図は全体図(「前編」を参照)の③部分で、赤い線が三田上水の想定ルート、黒い線が今回歩いた道です。右図はこれに対応した「江戸大繪図」で、赤い線が三田上水、四角は上水の桝です。聖坂の急スロープを降りた三田上水は、三ツ俣(三田3丁目交差点)を左に折れて北の赤羽橋に向かい、その途中で3つのルートに分かれました。仮に名前を付けると、いちばん手前が「阿波横丁ルート(芝税務署)」、その次が「西應寺町ルート」、北の赤羽橋に向かうのが「松本町ルート」です。これらのルートの町角には桝があり、上水の水勢を調べたり、流れを分けたり、底に溜まったゴミを浚ったりしていました。また木樋から支管を出して、大名屋敷、武家・同朋衆(お城の坊主方)の町屋敷、町屋(商家や長屋)に水を届けていました。余った水は屋敷のお堀や下水、また古川や入間川に捨てられました。それでは順に見ていきましょう。
<海辺の田町に懸っていた三田上水>
聖坂を下がり切って少し右に曲がると、広い三田通りの三田3丁目交差点に出ました。道路の両側にはお店が並び、たくさんの車が走り、人通りが増えて急に賑やかになりました。「貞享上水図」ではこの信号の所(三ッ俣)に桝がありましたが、ここは聖坂の最終点であり、また低地部の給水エリアの出発点でしたから、おそらく頑丈で大きな枡が設けられ、水位や水質のチェックが行われていたのでしょう。
「貞享上水図」によると、三田上水のルートはここから北に向かいましたが、『上水記』や『御府内備考』には、反対の南にある田町(芝田町)にも懸っていたことが記されています。もしそうならば、この桝で流れを南北に分けていたことになります。当時の田町は、東海道に沿って高輪大木戸まで続く細長い町で、海岸に沿って1丁目から9丁目までありました。陸側には町屋が、海側には大名の浜屋敷が並び、人通りが多かったことがうかがわれます。各丁目の名主から幕府に提出された「書上げ」に三田上水のことが記されていないため、流れのルートははっきりしませんが、樋管が三田通りに沿って埋設されていたとすると、三ツ俣の桝から田町四丁目の「札ノ辻」(幕府の高札があった所)の辺りに届いた後、海岸に沿って両側に伸びていたと考えられます。
<上水の仕組みについて>
ところで、三田通りは坂の下にありますが、水の流れの勢いによって木樋や桝が破損したり、増水した時に上水井戸の井桁から水が溢れ出すようなことはなかったのでしょうか。このような疑問について、神吉和夫氏が示唆に富んだ説明をしていました(注18)。それによると、日本の上水は高低差を用いて自然に流しているため、水理学的には低地の上水井戸などから水が溢れ出す危険があるので、常に適切な排水が必要で、その役割を大名屋敷の泉水や堀、下水などが果たしていたというのです。つまり大名屋敷の泉水が無ければ、三田上水は水理学的に成り立たなかったということです。飲み水の視点から上水の機能を捉えるだけではなく、全体的な仕組みから考えなければならないとも述べていました。高い所から落ちてくる水の勢いや量を心配していたのですが、そうしたことよりも上水の水理学的な構造が問題なんですね。庭園の泉水やお堀の水は大名の贅沢だと思っていましたが、そうとばかり言えないことが分かりました。この論文を読んでいて、以前に金沢を旅行した時に見た兼六園の噴水のことを思い出したので、写真を載せておきます。噴水は逆サイホンの原理によって、水源の池とほとんど同じ高さまで上がっていました。
それともう一つ、三田通りに入って思ったのですが、このようなほとんど平らな土地にどうやって水を流したのかということです。傾斜を付ければ水は低い方に流れますが、先に行くほど木樋をどんどん深く埋めなければなりません。こうした疑問について、肥留間博氏の『玉川上水-親と子の歴史散歩-』の中に分かりやすい説明がありました(注19)。平らな土地の地中に木樋と桝を埋める場合、まず木樋に傾きをつけて次の桝の低い所に差し込み、その桝の高いところから次の木樋を出してまた次の桝の低い所に差し込むというように、水を低い所に入れて高い所から出すという形で次々と繋いでいくそうです。ここで木樋に水が詰まっていれば、水の性質上、一度下がってもまた元の高さに戻るので、先に行くほど地面を深く掘る必要はないという訳です。江戸の職人たちは、このような技(わざ)を経験的に覚えて木樋の高さを保っていたのです。
<阿波横丁のルート>
話は三田3丁目の交差点に戻ります。この信号を渡ってから左(北)に曲がり、三田通りを赤羽橋の方へ歩き始めました。慶応義塾大学・三田キャンパスの手前で国道一号と合流して道路の名が「桜田通り」に変わりますが、ここでは赤羽橋まで「三田通り」としておきます。三田上水の初めの「阿波横丁ルート」に入る角はどこなのか、Googleマップと古地図を見比べながら約200mほど歩いていたところ、ラーメン店の角に右(東)に入る道があり、その奥に目印となるクランク型の道筋が見えました。この辺りには松平阿波守の中屋敷があったため、この道は「阿波横丁」と呼ばれていました。途中のクランク型の道筋は、右上の「江戸大絵図」だけでなく、もっと古い明暦3年の絵地図(1657年)にも出てきます(次節で紹介します)。これが昔の道の名残りならば、約360年も続いていることになりますが、地図上のアナロジーでしょうか。
この道を東に歩いていくと、左側に芝税務署の建物が現れました。「貞享上水図」によると、三田上水の樋管は松平讃岐守の屋敷を通り過ぎた角で終わっていましたが、ちょうど税務署の辺りのようです。流れの終点には枡がありませんでしたが、おそらく周りの武家屋敷に給水した後に、余水を脇の下水か屋敷のお堀に流したのでしょう。ここでお昼の時間になったので、芝税務署前の「小諸そば」に入って一休み。安くて早くて美味しくて、これで儲けが出るのか心配になりました。
<三田上水の原点「三田通り」>
食事を終えて三田通りに戻り、再び北に歩き始めました。江戸時代は赤羽橋から南の一帯を俗に四国町と呼んでいました。道の東側に松平阿波守、松平土佐守、西側に松平主殿頭、松平隠岐守の四国の大名屋敷があったためです。明治から昭和39年まで三田通りの東側だけが三田四国町と名乗っていましたが、現在は芝3~5丁目です。以前にこの辺りの裏道を歩いていた時、「北四国町会」(芝3丁目32)という町内会の掲示板がありました。前編の老増町もそうでしたが、昔の町名を見つけると妙に懐かしいものです。
この通りを約300m歩くと、左手に「綱の手引坂」が降りている信号が見えました。その先の左側の三田国際ビルや済生会中央病院の敷地は有馬中務の御屋敷でした。三田1丁目の信号を超えて少し先を右に折れると「西應寺町ルート」に入りますが、ここは最後に行くことにして、さらに北に進みました。この辺りは昔の三田一丁目で、『御府内備考』では「三田上水跡」について詳しい報告があった町です(注20)。三田二丁目、三丁目、四丁目からは「委細は三田一丁目より申上候通りに御座候」とありましたが、最後の「そうろう・どうりに・ござそうろう」という言い回しが丁寧すぎてユーモラスですね。それはともかく、『御府内備考』の中の「書上」げを読んでいて、この三田町が三田上水の名前の原点であり、給水の最大の目的地であったことを改めて感じました。
上の図は明暦3年(1657)の三田通りで、『東京市史稿』変災篇第4付図の部分です。地図の方向や距離は正確ではありませんが、三田上水が開かれる数年前の三田の特徴をよく捉えています。図の左上から右下に斜めに走る道が三田通りで、その両側の土地のほとんどが武家屋敷に割り当てられていました。図の中ほどに先ほどの阿波横丁の角の道とクランクの角がちゃんとありますね。増上寺の土地が古川を超えて南岸に広がっており、その東南には楕円形の馬場がありました。現代の競馬場と形がよく似ていますね。馬場は享保14年(1729)に一之橋に移り、その跡は薩摩藩邸に併合されました。当時の幕府から見ると、三田は大名たちに屋敷を給地するための大切な土地だったのでしょう。玉川上水の四谷大木戸からの水をこの土地に配る余裕がなかったため、新たに三田上水を開いて、下北沢村から高輪経由で給水したと考えられます。
<三田上水を何に使っていたのか?>
ところで、最近は江戸考古学と言われる分野で神田上水や玉川上水の発掘調査が進み、その成果が発表されています。それによると、大名屋敷に作られた水道網には、玉川上水などの樋管から引いたものと、自前の堀り井戸を使ったものとの二系統がありました。以下は神田上水の例ですが、飯田橋の讃岐高松藩の上屋敷を発掘したところ、上水道の木樋の多くが木栓などをして止められており、屋敷内の堀り井戸から汲み上げた水を主に使っていました。また彦根藩の上屋敷では、給水された上水の15%未満しか生活に使われず、残りは泉水を経て下水に捨てられていました(注21)。大名たちは、幕府から屋敷地を給付された頃は上水を使っていましたが、次第に水質や水量が安定した井戸水に切替えたようです。とくに地下30~40mの砂礫層(東京礫層)まで掘り下げる「掘抜き井戸」の技術が進んだことにより、本水(ほんみず)と呼ばれる上質の水がいつも得られるようになり、大名や豊かな商人の間で自前の井戸を設ける人が増えました。幕府が享保7年(1722)に四上水を突然廃止した時に江戸市中がパニックにならなかったのも、こうした技術革新があったためと思われます。
<三田上水の松本町ルート>
東京タワーを見ながら桜田通りをそのまま200mほど北に進み、赤羽橋南の信号のところに出ました。左側は済生会病院です。「貞享上水図」を見ると、三田上水のルートは、信号の手前100m辺りから大きな弧を描くように右に曲がり、古川の川岸に沿って東に200mぐらい進んだ所で終わっていました。現在の芝公園ファーストビル(右側)の角です。この辺りは昔の松本町で、寛文7年(1667)に起立した町ですが、貞享の頃は町の形がまだ整っていませんでした。しかし周りには桝が5つ設けられ、そのうちの4つが河原に沿って並んでいました。なぜ出来て間もない町に上水が引かれ、しかも多くの桝が設けられていたのでしょう。ヒントとなる情報の一つが『芝区誌』の「街史」にありました。それによると、松本町は道路を隔てて古川に臨み、その河岸は船が運んでくる炭薪(すみまき)の物揚場となり、炭薪商が軒を列ねていたとありました(注22)。上水や多くの桝はこうした港の仕事と関わりがありそうです。もう一つは堀越正雄『井戸と水道の話』に出てきた話ですが、当時は「水船」という商売があり、川に捨てる余水を排水口(吐口)で仕入れて船に汲み入れ、井戸が使えない本所や深川に運んで売っていました(注23)。これは想像ですが、古川の脇に「水船」が接岸し、これらの桝の吐口から川に流される余水を買っていたのかもしれません。
(5)西應寺町とその周りの町
<西應寺町ルートを探す>
松本町のルートを確かめた後、先ほど通り過ぎた桜田通りの「西應寺町ルート」の入口に戻りました。これから歩く地域は三田上水のルートがはっきりしない区間があります。三田上水が流れていた道の一部が薩摩屋敷の拡張で敷地に併合され、無くなってしまったからです。「江戸大絵図」では図の中ほど、中川、加藤、松平薩摩の屋敷の上の道、あるいは明暦3年の絵図では「馬場」の下の道です。このため、この区間で推定される上水ルートを赤い点線(右上の図)で示しました。
さて、三田一丁目の信号から40mぐらい北の角を左(東)に曲がって200mぐらい歩くと、先の芝公園ファーストビルの裏側の十字路に出ました。貞享の頃は、ここを右(南)に曲がって数十メートル進んだ所に左(東)に曲がる道があり(中川、加藤、松平薩摩の上を通る道)、その道が西應寺町の方まで続いていました。三田上水もこれに沿って流れていたと思われます。しかしこの道は薩摩屋敷の拡張で消えてしまったため、さらに数十メートル進み、芝パークタワーの角を左(東)に曲がって西應寺町に向かいました。
<名物「七曲り」の道>
芝パークタワーの角から70mぐらい歩くと、「芝さつま通り」と交差するT字路に出ました。この交差点は前が広場で通り抜けられるため、そのまま真っ直ぐに進み、セレスティンホテルの横を歩いて日比谷通りに向かいました。この辺りは広大な薩摩屋敷の跡地で、広場には屋敷図や港区の古地図などが展示されていて見応えがありました。日比谷通りに出ると、通りの反対側のやや左に戸板女子短大があり、その脇に芝小学校の下をくぐるトンネルの小道が見えました。信号を渡ってその小道に入ってトンネルを抜けると、そこは十字路になっており、正面が「七曲り」の道の入口でした。後に述べますが、貞享の頃は西應寺町を四方から取り囲む道があり、三田上水はその道に沿って町の四辺を流れていました。そして、西側の一辺がトンネルを抜けた所の十字路を通って国道130号に繋がっていました。なお、芝小学校の敷地内から上水の木樋が出土しており、これについては後に述べます。
有名な「七曲り」の道ですが、「貞享上水図」や同時代の古地図には描かれていません。薩摩屋敷が敷地を拡張した享保の終わりごろに西應寺町との境に作られたのでしょう。城内に侵入した敵を討ち取る迷路ではないかと密かに期待したのですが、予想は大いに外れ、教習所のクランクのような明るい空間でした。『芝区誌』には昔は大名の御用商人などが軒を並べていたとありますから、当時は話題のショッピングモールだったのでしょう。「七曲り」の道の出口は、古川の将監橋から来る道との交差点でした。
さて三田上水のルートですが、「七曲り」の土地の北の縁を東に真っ直ぐに進み、将監橋から来る道を右(南)に曲がって国道130号に向かったと考えられます。このルートに従い、「七曲り」の出口の交差点を右に曲がって約200m歩くと、国道130号(旧海岸通り)の広い道路に出ました。この道は昔の入間川を埋め立てたもので、江戸時代は細長い入江でした。『新編武蔵風土記稿』によると、古は渋谷川の河口の一つであったと伝えられています(注24)。国道に出る少し手前の右側には、町名の元になった西應寺の参道がありました(現在は芝2丁目)。西應寺は初代オランダ公使の宿舎があり、幕末の薩摩藩邸襲撃事件の際には兵火で全焼するなど歴史の荒波を潜り抜けました。中を見学させていただきましたが、宿舎の跡は今は幼稚園になっていて、お寺全体が町の中に静かに溶け込んでいる感じでした。
<三田上水のお宝発見か>
「貞享上水図」を見ると、先に述べたように三田上水は西應寺町の四方を流れていました。その形は横長の台形に描かれていますが、他の古地図では正方形に近かったようです。ところで三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』には、この土地から木樋が発掘された話が出てきます(注25)。芝小学校が昭和38年にプールを作った際に校庭の地下から出土したもので、同校の社会科教諭の談話によると、「その土木工事の際、1メートル余の地下から、昔の上水の埋没木樋の一部が発掘された。長さ4メートルぐらい。それを分与してもらいたいと申し出た向きがあったので、鋸で二分し、短い方を同校の標本室に保存することになった」とありました。著者の植松慶太氏は「(中略)現物を実測してみると、全長106センチメートル、全高23センチメートル、全巾23.5センチメートル、内径11.6センチメートルとなっている。(中略)内径の小さいところから推定すれば、水道の末端部分のものである。そして、このあたりに来ていた上水は、三田上水と推定するのが妥当ではないか」と述べていました。しかし本書には木樋の写真が収録されていなかったため、具体的なイメージが湧きませんでした。
今回のお散歩の準備で芝小学校に連絡をとったところ、快く見学を許可して下さいました。当日、菊原副校長先生に案内していただいて資料室に入ると、左奥の壁際に1メートルぐらいのこげ茶色の木樋が置いてありました。これが見たかったのです! 形は直方体ですが、片方が細くなっているのは木樋か桝に差し込むためでしょう。木樋を持ち上げると意外に軽く、素材は松かヒノキのようです。触ると外はザラザラしていましたが、水が流れる内側はすべすべしていました。木樋の寸法は植松氏の計測とほぼ同じでした。問題はこの木樋が三田上水のものかどうかです。傷みが少ないので幕末か明治初期のものかもしれませんが、低地部は土中の水分が多いので遺物の保存状態が良いと聞いたことがあります。これ以上のことは専門家でないと分かりませんが、西應寺町を取り巻く流れの西側の一辺の周辺から発掘されたことは、三田上水の木樋の可能性も十分考えられます。もしそうだとすると、三田上水としては初めての遺物ということになりますが。ご多忙の中お時間を割いていただいた副校長先生と事務職の方、そして木樋を長く大切に保存して下さった芝小学校の関係者の方々に心から感謝いたします。
<三田上水は周りの町にも流れていた>
流れのルートの話に戻ります。西應寺町に届いた上水はこの土地でどのように流れていたのでしょうか。「貞享上水図」によると、三田上水は西應寺町の周りを流れた後、余水は入間川に注いでいました。こうして玉川上水・下北沢村からの長い旅を終えたことになります。しかし史料を調べると、ここが終点ではなかったようです。『御府内備考』には、西應寺町から周りの多くの町(各丁目)に支管が伸びていたことが記されています(注26)。例えば西應寺町の隣の金杉通一丁目ですが、「(略)三田上水が掛っており、(略)三田台町の聖坂通りで樋筋の普請をした節の出銀の請取書が有った」とありました。詳しいことは分かりませんが、当時は金杉通りに水道組合のようなものがあり、聖坂の樋管の工事をした際に支払ったお金の受取書が残っていたということでしょう。この他にも入間川の南の芝町などから三田上水が掛っていたという報告が出ていました。三田上水は西應寺町で全ての流れを終えたのではなく、そこから周りの町に支管を伸ばしていったのです(注27)。
西應寺町の商店街が国道130号に出る所に、「芝」と太い白字で書いたゲートがありました。なかなかモダンなデザインだったので、国道の反対側に渡って記念写真を撮りました。この広い国道が昔は入間川と呼ばれた細長い入江で、このゲートの前には「廻り橋」が架かっていました。この橋を人々が往来し、多くの漁船が橋の下を行き来して魚を荷揚していたと思うと、時代の移り変わりをつくづく感じました。三田上水の「西應寺ルート」はこれで終わります。次は品川の「八ツ山下ルート」です。
(6)東海道を歩いて品川の八ツ山下へ
話はお散歩の出発点となった白金猿町(高輪台交差点)に戻ります。さて、日を改めて「貞享上水図」にある品川方面のルートを歩きました。左上の図は、「貞享上水図」の三田上水のルート(赤の線)と今回歩いた道(黒い線)を現代のGoogleマップに記したものです。線を書き入れた手順については、本ホームページ<前編>の「1.貞享上水図と三田上水」の中の<今回のお散歩ルート>」をご覧下さい。右図は、左のGoogleマップに対応する港区三田図書館作成「延宝年間図」の部分です。これまで用いてきた「江戸大繪図」が北品川宿をカバーしていないため、代わってこの地図にしました。三田図書館の資料調査員の方々が昔の史料を元にして手書きで作られたそうで、江戸の絵師も顔負けですね。延宝年間は1673~1680年ですから、三田上水が開かれて10年後ぐらいの様子です。なお訪問地の名称ですが、史料によって「八ツ山辺(八ツ山の辺り)」と「八ツ山下」がありますが、場所はどちらも北品川宿の入口ですので、浮世絵や錦絵によく出てくる八ツ山下にしました。
「貞享上水図」では、白金猿町から地中に入った三田上水は、二本榎通りを右に曲がり、さらに左(品川方面)に曲がって下り坂(現在の柘榴坂)の途中で終わっていました。しかし貞享より約30年後の正徳年間(1711~1716年)に描かれた「正徳末頃の上水図」(『東京市史稿上水編第一』付録、大正8年)では、図の右下に「此上水品川宿迄(この上水は品川宿まで)」とあるように、この坂道をさらに東海道まで降りて右に曲がり、南の品川宿の方へ向かっていました。貞享以降に上水のルートが伸びたのでしょう。本管は宿場の入口の八ツ山下までだったようですが、支管は本陣まで届いていたのかもしれません。
<寄り道して東禅寺参道脇の浮簀(うきす)へ>
八つ山下までの出発点は、<前編>と同じく高輪台交差点の白洋舎のお店です。高輪台交差点を渡り100m位真っ直ぐに歩くと、二本榎通りのT字路に来ました。今回は三田・芝方面とは逆の右に曲がり、プリンスホテルの土塀に沿って300mほど進み、道なりに左に曲がって柘榴坂を下りました。この坂を降り切った所が第一京浜国道(東海道)の品川駅です。「貞享上水図」の三田上水のルートは、この坂の途中の有馬玄蕃守屋敷前で途切れていました。終点に枡がないということは、余水は周囲の屋敷の泉水か下水に流されたのでしょう。ここからは先の「延宝年間図」を手掛かりに歩くことにしました。
柘榴坂を下って品川駅前に出ました。坂の上が高度25.0m、品川駅が5.1mですから、聖坂と同じように急坂です。昔の東海道はちょうど駅前を通っており、ここを右に曲がれば北品川宿まで約1㎞です。しかし、その前に道草することにしました。三田上水が浮簀(うきす)に掛かっていたという記述が『上水記』や『御府内備考』にあったからです。浮簀は町名でないため正確な場所は分かりませんが、『御府内備考』には、高輪北町の本田伊予守屋敷の南に「有喜寿(うきす)之社」があって、ここは柊の大木や雑木が生い茂り、海から浮洲のように見えたとの記述がありました(注28)。「うきす」の漢字の書き方は色々とあるようですが、いずれにしても場所は東禅寺参道の北側の海寄りの土地です。
ところで、浮簀に三田上水が届いていたとすると、どこから分水したのでしょうか。二本榎通りの高台を走る本管から東海道まで支管を降ろしたことが考えられるため、この二つの街道を結ぶ坂道を歩いてみたのですが、道筋が曲がりくねっていて、また人通りが少ない印象もあり、上水を埋設するには適していない感じがしました。これに対し柘榴坂を経由して東海道を北上するルートは、道がまっすぐで人通りも多く、こちらの方が可能性が高いと判断しました。当時の東海道は町屋がびっしりと並んでおり、水の需要も大きかったと思われます。
第一京浜国道(旧東海道)を品川駅から田町駅に向かって400mほど歩くと、左側に東禅寺山門に至る参道がありました。浮簀は参道の北側と思われますが、この辺りはマンションやオフィスビルが並んでおり、昔の上水を思い起こさせるものはありませんでした。参道の入り口には「歴史と文化の散歩道」という石柱と案内板があって、この土地の歴史を感じさせました。東禅寺は幕末に英国公使館が置かれ、R.オールコックの『大君の都』で紹介されたお寺として有名です。幕末には芝の西應寺と同じく政治の荒波にもまれました。当時の欧米の船舶は品川沖に停泊していましたから、地勢学的にも重要だったのでしょう。東禅寺を見学したところ、その堂々たる山門と三重塔、本堂に圧倒されました。
<乗船場があった八ツ山下>
さて、今回のお散歩の最後の訪問地、北品川宿の八ツ山下です。上の図は「延宝年間図」の八ツ山下のフォーカスです。海岸を縦に走る広い道が東海道、その中ほどの赤い枠が八ツ山下、そこから南に伸びる灰色の町屋が北品川宿です。八ツ山下は八ツ山の麓の土地の呼び名で、北品川宿の入口に当たり、北の高輪町との境には傍示杭が立ち、海岸には波風を防ぐ護岸の石垣が築かれていました。町ではないせいか「延宝年間図」に区画や名前はありません。海路を旅する人のための「乗船場」がありましたが、これは上の地図に描かれています。八ツ山下に接した北品川宿の南側の発展が著しく、後の享保7年(1722)には歩行(かち)新宿として独立し、品川宿は歩行新宿、北品川宿、南品川宿の3つの宿場を擁して栄えました。
東禅寺を拝観した後、品川駅に戻り、第1京浜国道に沿って南に歩きました。緩やかな坂を上っていくため、左側のJRの線路がだんだん下がって見えました。しばらく行くと「八ツ山橋」と記した信号がありました。昔はこの辺りに八ツ山がありましたが、海の石垣や目黒川の護岸のために切り崩されて平らになったと伝えられます。それでも信号付近はなだらかに盛り上がっていて昔の山の面影を感じさせました。この信号の手前を左に入る道が旧東海道で、JRの幅広い線路を東南の方向に斜めに横切って海の方に向かっていました。明治5年には線路を作るための切通し工事が行われて陸橋となりましたが(注29)、江戸時代は地続きで海岸まで伸びていました。現在の品川駅の高度は5.2m、八ツ山橋の入口は9.8mで、品川駅より5m近く高いですが、当時もこの辺りは海に面した小高い崖になっており、その上を東海道が通っていました。
50mほど歩いて陸橋を渡り切ると、右側に駅のターミナルのような形をした広場があり、その下を「八ツ山アンダーパス」という立体交差の道路が通っていました。埋立地と道路の上に作られた人工の広場です。広場の先には京浜急行の踏切があり、それを渡った所が南に向かう東海道の入口でした。三田上水の樋管は、陸橋のやや右を斜めに通って広場のある土地にに入っていたと考えられます。広場の奥には東屋風の休憩所と案内板があり、東海道にハイキングに行くらしい人たちが集まっていました。古地図と現代図を見比べると、この広場の辺り一帯が八ツ山下のようです。八ツ山橋の一部(線路上)が含まれるかもしれません。広場の高度は10.0m、京急踏切を渡った先の東海道入口は9.1mで、ここから目黒川・品川橋の2.7mまで緩やかに下っていました。
上の浮世絵は文久3年(1863)に刊行された歌川国貞の「東海道名所之内品川八ツ山下」です。海岸には何層にも石垣が積まれており、石段の上にある小道を登った所に東海道があります。街道と海面の間にかなりの高低差を感じます。街道の向こうには八ツ山の崖と柵が、高台には林が見えます。東海道はちょうど大名行列が通るところで、道の両側に町屋が並び(海側は屋根のみが見えます)、この土地を往来する人々の姿をシンボリックに描いています。この絵の見どころは舟遊びをしている女の人や着物の色柄のはずですが、どうしても地形に目がいってしまいますね。
海岸をよく見ると、石段の下に小さな船が浮かんでいます。目をこらして数えたところ五艘でした。『新編武蔵風土記稿』によると、八ツ山下の海岸には長さ10間(18m)、幅2間(3.6m)の「船繋場」があり、常に船を繋いで旅客の往来に用いていたとありました(注30)。江戸幕府は、宿場を保護するために「旅人は陸路、物資は海路」とする政策をとっていましたが、八ツ山下と江戸の間だけは海路を認めていました。このため八ツ山下は江戸を行き来する人々の海路の大切な中継点でした。また、当時は旅人を品川まで見送ったり出迎えたりする習慣があったため、この辺りにはお茶屋が並び、いつもたくさんの人で賑わっていました。三田上水は、こうしたバイタリティーあふれる八ツ山下と北品川宿の人々の暮らしを裏方から支えていたのでしょう。
(おわりに)
今回のお散歩では、三田上水の地中の流れを「貞享上水図」をガイドにして歩きました。下調べを始めた頃は、295年も前に廃止された三田上水をどこまで探すことができるのか、とても不安でした。地上に残った流れの跡もなければ、その姿を見た人もいません。これまで調べてきた渋谷川や「三田用水」とこの点がまったく違いました。また「三田用水」は多少なりとも遺跡や発掘物があるのですが、その前身である三田上水についてはほとんど何もありません。しかし「貞享上水図」や同時代の古地図をながめ、『上水記』や『御府内備考』などの史料を参考にすることで、三田上水の姿がだんだんはっきりしてきて、お散歩も何とか終点までたどり着くことができました。歩いた道筋にはお寺や武家屋敷の跡がたくさんあり、港区の案内板もあちこちに立っていて、歴史散歩としても楽しいものでした。江戸の町が大きく発展した寛文から元禄、享保の時代に、60年余りにわたって人々のライフラインであった三田上水を、かなり身近なものとして頭の中に焼きつけることができました。あとは今回歩いた道の地中から、ある日三田上水の木樋や枡が発掘されて、その歴史的な役割が広く世に知られることを望むばかりです。長い文章をお読みいただき、ありがとうございました。
(注18)神吉和夫「玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する基礎的研究」『土木史研究』第13号、1993年。
(注19)肥留間博『玉川上水-親と子の歴史散歩-』たましん地域文化財団、1992年、73-75頁。
(注20)蘆田伊人編集校訂『御府内備考』第4巻、312、315頁。
(注21)江戸遺跡研究会編『江戸の上水道と下水道』吉川弘文館、2011年、34-37頁。
(注22)東京市芝区役所『芝区誌 全』、昭和13年、1717頁。
(注23)堀越正雄『井戸と水道の話』論創社 1981年、127-129頁。
(注24)間宮士信他編『新編武蔵風土記稿・東京都区部編』第1巻、千秋社、昭和57年、26-27頁。
(注25)三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』同組合発行、昭和59年、19頁。
(注26)前掲『御府内備考』によると、金杉通一丁目から「三田上水跡」について「書上げ」があった他、金杉通二丁目、三丁目、金杉裏、金杉同朋町、金杉片町、金杉濱町、築地同朋町など11の町(各丁目)で「金杉一丁目より申上げた通り」との記載がありました。海岸部の本芝一丁目、二丁目、三丁目、四丁目、六軒町の5つの町からも同様の報告がありました。
(注27)「貞享上水図」をみると、三田上水の他にも、玉川上水が古川を超えて沿岸の松平伯耆守(相模守)の屋敷や金杉通、金杉裏の一部に給水していました。古川が川幅を拡張した宝永3年(1675)よりも後のことなので、金杉橋の下に木樋を沿わせて川を渡らせたり、逆サイホンの原理で川底を潜らせるなど、当時の最先端の技術が用いられたのでしょう。
(注28)前掲『御府内備考』第5巻、14-15頁。
(注29)「明治維新後の品川 第14回」、品川区ホームページ。
(注30)前掲『新編武蔵風土記稿』第3巻、426頁。
<参考文献>
東京市役所『東京市史稿』水道篇第1、大正8年
東京市芝区役所『芝区誌 全』、昭和13年
東京都港区役所『新修港区史』、昭和45年
蘆田伊人編集校訂『御府内備考』第4・5巻、大日本地誌体系4・5、雄山閣、昭和45年
堀越正雄『日本の上水』新人物往来社 昭和45年
東京都港区立三田図書館『近代沿革図集』全巻、昭和47年
間宮士信他編『新編武蔵風土記稿・東京都区部編』第1・3巻、春秋社、昭和57年
三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』同組合発行、昭和59年
神吉和夫『玉川上水の江戸市中における構造と機能に関する研究』とうきゅう環境浄化財団、1994年
伊東好一『江戸上水道の歴史』吉川弘文館 平成8年
江戸遺跡研究会編『江戸の上水道と下水道』吉川弘文館、2011年
野中和夫編『江戸の水道』同成社、2012年
(終り)
(頁トップへ)
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2017.4.1

以下は2019年1月21日に、表参道の東京ユニオンチャーチ(TUC)「おにぎりフェロウシップランチョン」で行った講演「三田上水と三田用水」に加筆したものです。当日は終了後も来場者と川の話で盛り上がりました。企画と運営をして下さったTUCの樋口様に厚くお礼申し上げます。
玉川上水の話
三田上水は今から350年以上前、江戸時代の寛文4年(1664)に作られた長さ約12㎞の人工の川で、有名な玉川上水の分水です。三田上水は後に三田用水と名を改め、恵比寿や目黒、白金の人々の暮らしや産業を長く支えてきました。その存在を抜きにしてこの地域の歴史を語ることができないほどです。実際にどのような川だったのでしょうか。
上の図は江戸時代に描かれた「正徳の上水図」(1711-1714)です。多摩川から江戸城まで流れる玉川上水と分水網を記しています。多くの流れを見やすく配列するため川の方向や長さを適当に変えており、地図としては正確ではありません。しかし江戸時代の上水がどうなっていたかを一目で見るにはとても便利です。図の上を流れている太い線が多摩川で、その真ん中から江戸城に向かって真下(東)に流れているのが玉川上水です。
玉川上水の右(北)と左(南)には何本もの分水が延びていますが、図の中ほどから左斜め下(東南)に向かっている薄い色の長く伸びた線が細川上水と三田上水です。2本線になっています。細川上水は三田上水に先立つ7年前の明暦3年(1657)に開かれた上水です。細川上水と三田上水は享保7年(1722)に幕府の命で廃止されましたが、その2年後の享保9年(1724)に、流域にあった村々の請願によって三田上水が払い下げられ、名前も三田用水と改めて復活しました。この三田上水と三田用水が今日の話の中心で、昭和50年(1975)に廃止されるまで実に300年以上も流れていました。
三田上水と三田用水の水源となった玉川上水について説明します。玉川上水は多摩川が流れている羽村から四谷大木戸まで全長43㎞に及ぶ水道です。江戸幕府が成立して約50年後の承応2年(1653)に開かれました。当時の江戸は飲み水に適した湧き水がほとんどなく、井戸を掘っても泥水や塩水ばかりだったようです。江戸の町が大きくなるにつれて、人々の暮らしを支える大量の水が必要になったため、幕府の命で開かれました。実は江戸城を始め、武家屋敷や寺社の庭園に池の水を引くことも大きな目的でした。玉川上水を開くときに玉川兄弟が様々な苦労をした話は昔の教科書などに載っていますので、ここでは省きます。
上の図と写真は多摩川の羽村取水堰の様子です。左は幕末の絵図で、多摩川は向かって右から左に流れており、手前の左側に玉川上水が見えます。右は現代の写真です。多摩川は今でも水道原水の一つで、正面奥から流れてくる多摩川を堰止めて、手前右側の玉川上水に水を導いています。多摩川にかかる堰は丸太や木の枝でできていて、川の水が増えると堰をそのまま流せるようになっているため、大雨で多摩川の水嵩が増しても、濁流や土砂が玉川上水に流れ込むことはありません。素朴ですが実に巧みなやり方で、江戸時代も今も基本的には同じ方式を用いています。
玉川上水は取水口の羽村から終点の四谷大木戸まで地上を流れていました。大木戸の水番屋でゴミや汚れを取り除いた後に地中に入り、石樋や木樋を通って江戸城や武家屋敷、町屋に流れていました。初期の江戸の暮らしはこうして地下に張り巡らされた水道によって支えられていたのです。享保の頃になると井戸を掘る技術が発達し、江戸の地下の水質も良くなり、これが享保の時代に細川上水や三田上水を廃止した理由の一つであると言われています。玉川上水の話はこれぐらいにして、次に細川上水、三田上水、そして三田用水の話に入ります。
三田上水と三田用水の誕生
上の絵図は国会図書館が所蔵する「貞享上水図」の部分図のコピーです。江戸の貞享年間(1684-1687年)に描かれたもので、原図はカラーです。初めにご紹介した「正徳の上水図」の細川上水と三田上水がより詳しく描かれています。この二つの流れをこれほど正確に描写した絵図は他にないでしょう。コピーは白黒のみですが、しばらく前までは手書きで写すしか手立てがありませんでしたので、コピーが認められた時はちょっと興奮しました。図の左側の縦の黒い太い線が玉川上水で、その根元の下北沢村から細川上水と三田上水が斜め下(南の方角)に出ています。2本の上水は2カ所で交差しています。流れに沿って進むと、両岸に幾つかの大名屋敷がありますが、西側(図の下側)にある中川佐渡守と松平主殿頭の屋敷の庭が有名なので後でご説明します。下目黒村の辺りで東に大きく曲がり(現在の目黒駅付近)、再び南に曲がって進むと白金猿町(今の高輪台)に着きます。白金猿町には大名屋敷や辻番屋(交番)、町屋などがたくさんあって賑やかでした。この町を過ぎてから北(図の上側)に直角に曲がって道なりに東に進むと伊皿子の細川越中守の中屋敷に至ります。細川上水はここまでです。その後は三田上水だけが地下を流れ、三田や芝の武家屋敷、寺社、町屋に給水しながら西應寺の門前町である西應寺町に行き、そこから渋谷川(新堀川)傍流の入間川(いりあいがわ)に注いでいました。
ところで細川上水を開いたのは熊本54万石藩主の細川越中守綱利です。現在の港区高輪の伊皿子に大きな屋敷を構えていました。なぜ彼は自分の屋敷まで上水を引いたのでしょうか。三田村鳶魚『江戸の実話』によると豪勢な庭が欲しかったからです。上水が完成するとさっそく池を掘って大きな滝をこしらえました。滝の工事にはさぞお金がかかったでしょう。ところで、これを聞きつけた熊本の国家老がすぐさま江戸に飛んできて、家中や百姓が困窮の折に「かく奢侈超過とあっては公儀への聞こえ宜しからず」と綱利を諌め、せっかく作った滝はもちろん立石泉水までも取り壊し、関係者を皆処分して国にサッサッと帰ったそうです。我儘な綱利と彼を心の底で思いやる国家老の立ち合いがお芝居みたいで面白いですね。当時の大名は飲み水が足りなくても庭園や池は立派に作ったそうで、大名同士の見栄もあったのでしょう。
次に作られたのが三田上水で、幕府の命を受けた請負人が開削しました。上水図にあるように細川上水と場所もルートもそっくりです。細川上水がうまくいったのを見て、厄介な測量などの仕事を省いて近くに水路を作ったという見方があるようですが、細川氏から何らかの協力を得て作ったと見る方が自然な感じもします。いずれにしてもこの2本の上水が地域の水道の大元になり、周辺の土地に庭園の文化や衛生的な生活環境をもたらしました。さらに上水の余り水が農民の灌漑用水に使われることによって米の生産を促しました。こうした状況があったからこそ、三田上水が廃止された時に農民が払下げを請願し、三田用水が誕生したのです。三田上水は幕府の請負人が管理していましたが、三田用水になると流域14ヵ村の地主が水利組合を作って管理するようになり、この仕組みは昭和の戦後まで続きました。
江戸絵図に描かれた三田用水-北沢5丁目から鎗ヶ崎まで-
これまでは三田上水や三田用水が誕生するまでの経緯を「正徳の上水図」や「貞享上水図」を通して見てきました。次に、これらの川が流れていた水路に沿って順にエピソードを紹介したいと思います。上の図は三田上水と三田用水の水路をグーグルマップに書き入れたものです。三田上水も三田用水も現在の北沢5丁目の取水口から始まって南に向かい、三角橋、駒場、東大裏、青葉台、代官山、恵比寿などを通って目黒へと流れていきました。そして現在のJR目黒駅で東にほぼ直角に曲がり、教育植物園の南側の高台を東に進み、白金台を右に大きく回って高輪台に至りました。自然の川は低い方に向かって流れますが、三田上水や三田用水は渋谷川と目黒川に挟まれた高台の尾根を通り、精巧に設計された勾配を保ちながら長い道のりを高輪台まで流れていました。高輪台からのルートは三田上水と後の三田用水では全く異なります。三田上水は高輪台を過ぎると地中を北に進み、三田の聖坂を下って芝・金杉の平らな土地に流れました。三田用水はその逆に南に向かい、北品川を一気に下って目黒川の小関橋、森永橋近くに流れました。なお三田上水と三田用水は北沢5丁目から高輪台までルートが同じなので、この間の流れを説明する際には、歴史が長かった三田用水で代表することにします。
この地図は三田用水が流れ出した地域の様子です。地図の一番上を横切る道は甲州街道、その下の大きく曲がって流れている川が玉川上水です。取水口の北沢5丁目は京王線の笹塚駅のすぐ近くで、玉川上水の羽村取水口からは約36㎞の地点にあります。
左の写真は昭和30年、右は現在の三田用水の出発点の様子です。玉川上水は手前から奥に流れていました。昭和30年の写真では流れの先に大小の二つの水門が見えます。左側の大きい方が本流の玉川上水で、右側が三田用水の取水口です。現在の写真を見ると、玉川上水には緑の草が一面に生えており、右奥の階段のような所が三田用水の取水口です。三田用水はここから北品川の目黒川まで約12㎞を流れていました。
取水口から始まった三田用水は、北沢5丁目商店街の傍を通って駒場4丁目に抜けていました。上の左の写真は今も残る暗渠の道で、幅は1間ほどです。右は駒場東大裏の塀際にある嵩上げした水路です。この辺りの地形は窪んでいるため、サイフォンの原理を用いて水の流れを良くしたのでしょう。昭和の初めになると取水口から恵比寿の日本麦酒まで水路が木製からヒューム管(鉄筋コンクリート製)に替わり、地下に埋設されました。
この東大キャンパスの辺りは「駒場原」と呼ばれる御鷹場で、8代将軍吉宗は盛大に鷹狩を催したと伝えらます。上は「目黒筋御場絵図」の部分図で、将軍の御鷹場があった駒場原の周りの様子です。三田上水が駒場原の北側をカーブを描きながら流れているのが分かります。右は広重の「駒場野」で、この御鷹場で狩りをする勇猛な鷹をモチーフにしています。鷹匠の手に停まっている鷹の姿も見事ですが、気になるのは羽の下から垣間見える水色の川で、三田用水でしょうか、地元の小川でしょうか。ところで渋谷区教育委員会が発行した『渋谷の湧水地』には、「渋谷の田子免池で白鳥を飼うことになり御用地になった」という『野崎家史料』が引用されています。田子免池は現在の東2丁目にあった池で、幕府の『上水記』によると三田上水を「御用水」に使っていました。白鳥は観賞用に飼われていたと思いたいのですが、当時は将軍の狩りの獲物として白鳥、鶴、カモなどが使われたようで、ここで飼育されていたのでしょう。
左は目黒区の青葉台付近の地形図です。ここには三田上水の時代から中川佐渡守の屋敷があり、庭園には上水(後に用水)を使った池と滝がありました。明治になると西郷従道が兄の隆盛のためにこの屋敷を購入しましたが、西南の役で敗れた隆盛が住むことはありませんでした。屋敷の周りの地形を見ると、旧山手通りを流れる三田用水の高度は36m位、西郷邸の庭の高度は15m位で、その差は20mもあります。自然の崖を巧みに用いた滝はさぞ素晴らしかったでしょう。目黒区がこの庭園を復活して下さって菅刈公園として開園しています。旧山手通りから階段をひたすら降りていくと公園の池に着きます。名物の滝はありませんが、池の周りの斜面に目をやって当時の滝がどこに落ちていたのかと想像するのも楽しいです。
三田用水は旧山手通りに沿って南に流れ、恵比寿から来る駒沢通りと鎗ヶ崎で交わっていました。上の写真はその交差点に架かっていた水路橋です。歩道橋ではありません。駒沢通りは昭和の初めに崖を切り崩して作られましたが、その崖の上を三田用水が流れていたため水路橋を建設したのです。当時は日本麦酒や海軍技術研究所が三田用水を大量に使っており、このような工事を行って大切な水源を確保したのでしょう。
時代はさかのぼりますが、江戸時代に鎗ヶ崎から中目黒村の一帯を眺めた絵図があります。江戸末期に描かれた歌川國長の「鑓崎富士山眺望之図」です。これについては目黒区めぐろ歴史資料館学芸員の横山先生から色々と教えていただきました。「鑓崎富士山眺望之図」の左側の丘にある茶色い山は文政2年(1819)に築造された「目黒新富士」です。江戸時代は富士講が盛んでしたが、富士山に登るにはお金も体力も必要で、しかも女性は許されていませんでした。そこで年寄りや女性、子供など富士山に行けない人のために富士塚が作られ、ここをお参りすると実際に行ったのと同じぐらい御利益があるとされていました。「目黒新富士」は、当時の富士講の一つである山正廣講が景色が良いこの土地を選んで作ったもので、択捉(えとろふ)探検で有名な近藤重蔵の別邸内に建てることで幕府の許可を得ました。富士塚は一般的に富士山から黒ボクの溶岩を持ってきて作られましたが、この「目黒新富士」は形がすべらかで赤土の色をしています。1991年の新富士遺跡の発掘調査で、御神体や祠などを含む地下式の胎内洞穴が発見され、「新富士」はそこから掘り上げた関東ローム層の赤土を盛土にして作られたと考えられます。全国でも例がない胎内洞穴の遺構は型取り保存され、現在は目黒区めぐろ歴史資料館に再生展示されています。
ところで、本ホームページでは当初、新富士の奥に三田用水が流れていると述べましたが、その後に横山先生から「これは新富士の奥にあった大池(おおいけ)と思われます」とのご指摘がありましたので訂正します。三田用水は新富士の手前の崖の上を流れていますが、林に隠れて見えません。しかしその林から三田用水の分水が滝となって流れ出て、真下の田んぼに勢いよく落ちています。鎗ヶ崎の目の前に見える分水といえば別所坂の「別所上分水」でしょう。当時の絵は感じたままに描くところがあり、分水の流れというよりは大きな滝ですね。三田用水が村々の灌漑用水として使われていたことがこの絵図からもよく分かります。余談ですが、図の右奥に見える白い小さな山が富士山です。横山先生は「この場所に見える筈がないんですが」とおっしゃっていました。現代地図で富士山の場所を確かめたところ、この絵から右にかなりはみ出したところにありました。
先の歌川國長は北から南に向かって風景を描いていますが、上の歌川広重は東から西に向かって「目黒新富士」という絵を描いています。この絵のテーマも左に描かれた大きな富士塚です。今度は深い緑色で、山腹や山頂に人がいますね。この絵では富士塚の麓の桜と三田用水の流れも重要なモチーフになっています。流れの岸辺を見ると手前が崖のような斜面になっています。奥に僅かに見える川の岸辺の先も崖になっており、木立の先には田んぼや民家が遠く霞んで見えます。三田用水が、田畑を見降ろすような高い尾根を伝って流れていることが分かります。右奥に本物の富士山が堂々と描かれていますが、先生によればこれは正しい位置だそうです。山の上に人がいることについては、「富士山も富士塚も山開きは6月1日だが、桜のシーズンに「新富士」だけ特別に上ることができたのか、それとも広重の脚色なのか分からない」とのお話でした。「鑓崎富士山眺望之図」と「目黒新富士」は共に絵師のイメージで描かれていますが、三田用水の地形的な特色はしっかり押さえられていますね。横山先生にはたくさんの貴重なお話をありがとうございました。
明治の近代化と三田用水-恵比寿から目黒まで-
江戸の後期になると三田用水は灌漑用水の他にも精米・製粉を行う水車の動力として使われるようになり、手作業による精米は姿を消していきました。上の写真は渋谷の鍋島松濤公園に復元された水車小屋です。三田用水には17の分水があり(明治は19)、渋谷川と目黒川に向かって勢いよく流れ込んでいました。土地の傾斜を巧みに使った水車が次々と生まれ、最盛期には49軒という記録が残っています。大正時代になると電力が普及して急速になくなりました。ところで、明治時代になると綿工業や製薬などの近代産業が次々と起こり、製造に使う工業用水が求められるようになりました。とくに三田用水を必要としたのが明治13年(1880)に設立された目黒火薬製造所(後の海軍技術研究所)と、明治21年(1888)に創業した日本麦酒(現在のサッポロビール)です。
目黒火薬製造所の歴史は、江戸幕府が目黒三田村に設立した火薬製造所にさかのぼります。この工場は4万坪の敷地を持ち、三田用水を使った水車を用いて火薬を作りました。当時は浦賀にペリーの黒船が来航し、幕府は大砲や鉄砲に使う火薬を大量に作ることを迫られていました。この地に危険な火薬工場が設けられた理由は、人口が少なかったことに加えて、三田用水が流れる高台から目黒川に下る広い急な傾斜地が水車による火薬製造に適していたからです。工場は幕末にいったん閉鎖されましたが、新政府によって再び始められ、海軍が玉川上水から独自に取水し、三田用水の道城口(火薬庫口)と田道口から水を引いて火薬の製造を始めました。火薬を作るのに適した鉄製の頑丈な水車でした。その後海軍は勝手に分水口を改造したり水路を変えたりしたため、地元の農民との間で紛争が起きて、解決まで時間がかかりました。昭和になって火薬製造所が移転すると、その跡に海軍技術研究所が入り、巨大な実験用貯水池を作って艦船の航海実験を始めました。戦艦大和の実験も行われたそうです。三田用水の用途はどんどん広がり、求められる水量も増えました。
次に日本麦酒ですが、明治21年(1888)恵比寿に創業した日本麦酒は、三田用水の田道口と銭瓶口の分水から供給を受けてビール生産を始めました。工場内には二つの貯水池がありましたが、今の恵比寿三越の辺りに造られた第二貯水池は1辺が100m、深さが最大9mもありました。よくこんなに大きな池を一杯にできたものです(詳しくは本HPバックナンバー1「9月10日 真っ青な貯水池のミニチュアが」を参照)。日本麦酒も地元の農民と水争いになりましたが、最終的に契約を交わし、日本麦酒が三田用水をヒューム管にするなど改良し、管理を主に行うようになりました。
昭和になると三田用水の周りは田畑から住宅や工場に変わり、農業用水の需要はほとんどなくなりました。その後、敗戦により海軍技術研究所は占領軍に接収され、返還後は防衛庁技術研究所になりました。時代は流れ、昭和27年に水路を管理していた三田用水普通組合の法的な解散が決まりました。その後、水路の権利を巡って組合と国・都の間で長い係争になりましたが、法律的な問題ですので説明は省きます。昭和49年(1974)には恵比寿のサッポロビールが、昭和50年(1975)には防衛庁技術研究所が用水を水道に切り替え、三田用水は三田上水の開削以来311年の歴史を終えました。技術研究所のプールは防衛省艦艇装備研究所に引き継がれて今日に至っています。
さて上の写真はガーデンプレイスのタワービル39階から写した防衛省艦艇装備研究所の全景です。真ん中に細長い緑の屋根の建物があり、その中に長さ250mの巨大な実験用貯水池があると伝えられています。防衛省の周りの道を歩いている時は横に長い建物があるなということぐらいしか分かりませんでした。高層階から眼下に広がる景色を眺めていた時に、この建物があったので写真を撮りました。後に玉川上水の展示会(本HPの「三田上水と三田用水・展示パネルの紹介」参照)でこの写真を掲載したところが、写真のプロの方から「このアングルをいただきます」と褒められましたが、偶然の賜物です。
ravel h
ところで防衛省構内の三田用水の跡がどうなっているかは、入口近くにある図書室(現在は市谷に移転)以外は立ち入ることができないため、全く分かりませんでした。しかし昨年12月17日、NHK『ブラタモリ』が三田用水を取り上げ、敷地内の三田用水の遺構や巨大貯水池の様子を放映しました。もう私たち三田用水に関心がある者にとってはびっくり仰天です。録画した番組の画面を何回も何回も止めて敷地内の様子を観察しました。以前に『ブラタモリ』が港区麻布のマンション敷地内にある「ガマ池」を放映した時も驚きましたが、今回は歴史的な価値が違います。関心のある方はNHKオンデマンドでご覧ください。
先ず左の写真ですが、タモリ一行が敷地内をぶらぶら歩いていて見つけた三田用水の水路橋の残骸です。そして右の写真はNHKが十八番のCGを用いて水路橋を復元させたものです。残された橋の一部が道の反対側にまで伸びて堂々とした水路橋になりました。三田用水は、敷地内の低い所を流れる時にこうやって高さを保っていたのですね。その後、研究所の案内の方が「三田用水の水がまだ残っているので、これからそこに案内します」と言いました。タモリは信じていない様子です。昭和50年に使わなくなった三田用水の水が、どうして今も残っているのでしょう。
艦艇装備研究所の建物に入ると、遥か先の方まで延びている細長いプールがありました。あの緑の屋根の建物の中はこうなっていたのです。プールが収容する1.8万トンの水のうち、約4割が昔の三田用水の水であるという説明がありました。研究所の方によると、艦船実験の条件を一定にするために水をなるべく入れ替えず、藻や汚れが発生しないように光を遮断して今日まで来たそうです。要するに昔の水が新しい水とブレンドされて残っていたという訳です。納得!
今回の『ブラタモリ』には感動しましたが、それだけで終わらないのが三田用水のファンというものです。ここで『東京時層地図』を引っ張り出してこの辺りの昔の地形を調べてみました。左は「明治のおわり(明治39-42年)」の地図なのですが、構内を横に走る実線が三田用水の水路です。その真ん中あたりを道路(二本の点線)が横切っており、道の両側が高台になっています。そして道路と交わる所の水路が白い長方形のマークになっています。右は『ブラタモリ』で紹介された水路橋の場所ですが、左の『東京時層地図』の場所と一致しています。この白い長方形のマークが構内にもう一カ所ありました。「明治のおわり」の地図の左上ですが、高台の谷間を通る水路にこのマークが付いています(地図の赤丸部分)。これは新しい発見ですね。大正以降の地図を見るとマークは消えています。水路が鉄管になり、道や低地を跨ぐ橋は要らなくなったとも考えられます。
防衛省の構内の話はこれぐらいにします。さて敷地から出た三田用水は茶屋坂の上を通り、さらに南へ流れてJR目黒駅の方に向かいました。上の左の写真は『ブラタモリ』でも紹介された新茶屋坂の水路橋です。鎗ヶ崎の水路橋と同じように、この場所の崖を切り崩して都道が作られた時に隧道になりました。隧道の上部の様子を示したのが目黒区からお借りした右のカラー写真です。真ん中を三田用水が流れており、水路はコンクリートの蓋で覆われています。両側は水色に塗られています。平成15年(2003)には都道が拡張され隧道が撤去されました。下の左の写真は昔の茶屋坂の近くに建てられた「三田用水跡と茶屋坂隧道跡」の記念碑です。
三田用水は茶屋坂を過ぎて恵比寿ガーデンプレイスの西側にある日の丸自動車の土地に流れ込みました。日の丸自動車ビルの側面に張り付いている巨大な赤い半球体をご存知の方もおられると思います。地元の方のお話では、この辺りには三田用水の流れの跡が残っていて保存運動も起きましたが、当時は開発が優先されたそうです。右の写真は練習所のフェンスの脇に建てられた記念碑で、下にある丸い石は三田用水の木樋(木の管)を支えていた礎石です。
再び江戸時代の有名な絵図を紹介します。日の丸自動車から目黒駅にかけての広大な斜面の土地に松平主殿頭(とのものかみ)の屋敷がありました。庭園には三田用水から水を引いた池と滝があり、景色のあまりの美しさから「絶景観」と呼ばれていました。歌川広重の「目黒千代が池」にはこの土地の自然の崖を巧みに用いた五段の滝が描かれています。明治以降は元勲の三條実美の屋敷などになりましたが、残念ながら千代が池は残っていません。今では目黒川に下る斜面にホテルプリンセス・ガーデンを始めたくさんのマンションが建ち並んでいます。三田上水が農民に払い下げられて三田用水となった後も、大名たちは用水を庭に引いて池や滝を楽しみました。しかし用水は池に貯まっただけではなく、その余水が近隣の農村に流れて灌漑や生活用水に使われました。当時の人は水を大切にしており、地域に循環させることで最後まで使い切ったのです。
三田用水の遺構の保存-白金台から高輪台まで-
JR目黒駅の西側に流れてきた三田用水は、ここで東に直角に曲がりました。そして首都高目黒線を越えてから尾根伝いに右に大きく回り、白金台を通って高輪台(当時の白金猿町)に至りました。この辺りの水路跡を歩いていると流れの右側が深い谷になっていて、三田用水が白金台の稜線を辿りながら徐々に高度を下げていったことが分かります。
三田用水の流れに沿って白金台の小道を南に歩いて来ると、突然突然土地の高度が変わり、それまで緩やかに降りてきた道が階段に変わります。階段の脇には「導堤遺構」と港区教育委員会の看板があります。この場所で水路を崖に沿って下げると高輪台まで流れの勾配が保てなくなるため、人工の堤を築いて水路を嵩上げしたのです。三田用水の導堤はこの辺りが住宅地になる時に取り壊されましたが、港区関係者のご尽力によって水路の断面が保存され、この場所に展示されました。今では三田用水を愛する人の聖地になっています。
ところで三田用水は都心を流れていたため、それが廃止された後は水路の跡地が住宅やビルとなってしまい、遺構のようなものはこの白金台と東大裏ぐらいにしか残っていません。その白金台に4年後に新しい道路(環状4号線)が建設されることが発表されました。工事が進むと白金台3丁目の「導堤遺構」も取り壊されてしまうかもしれません。近くには三田用水に架かっていた今里橋の欄干(左上の写真)があり、三田用水の水路が埋まっていると思われる古い道路や宅地もあります。こうした歴史的な遺産を後世に伝えることが大切な課題になっています。
初めに申し上げたように三田用水は玉川上水の分水の一つですが、いま玉川上水とその分水網を保全し活用していこうという動きがあります。市民団体の玉川上水ネットが進めている「玉川上水・分水網の保全活用プロジェクト」です。その目的は玉川上水に水を流して都心の外堀を浄化し、災害時にはその水を防災用水として使うと共に、分水網をきちんと保存して水と緑、そして歴史を後世に伝えていく取り組みです。昨年12月21日、この取り組みが日本ユネスコ協会の「プロジェクト未来遺産2016」に登録されました。この活動の一環として三田用水の遺構の保存をいま港区にお願いしています。大事な三田用水の遺構ですからぜひ実現したいですね。
三田用水の流末-西應寺ルートと小関畑ルート―
三田用水の流末に話を進めますが、その前に流れの全体の様子をまとめておきます。上の図は国土地理院の『地理院地図(電子国土Web)』 を用いて三田用水が流れていた地形の勾配を調べたものです。縦軸が標高、横軸が距離で、三田用水の流れた土地を1㎞おきに区切って勾配を示しています。取水口の北沢5丁目の標高は約40m、中継点である8.5㎞先の高輪台の標高は約28mですから、その差は12mで、勾配は100mにつき約13.5㎝です。玉川上水の羽村取水口から終点の四谷大木戸までの勾配は100mにつき21.4㎝ですから、三田用水の勾配はかなり緩やかですね。傾斜の少ない地形に水を滞らせずに流すためには、あちこちで土木工事を施す必要がありました。図中のB東大裏では土地の窪みを補正するために水路を嵩上げしましたが、サイフォン効果を利用したのでしょう。D鎗ヶ崎とG茶屋坂の隧道では切通しの道路の上に水路橋をかけて傾斜を保ちました。I目黒駅も高台を削って敷設した鉄道の上に水路を作りました。J白金台の導堤は、B東大裏と同じく自然の窪みを嵩上げしました。先の『ブラタモリ』で防衛省の構内にも水路橋があることが分かりましたので、『東京時層地図』の記録も加えて書き入れてみました。茶屋坂の手前(西)約200mと400mの所です。三田用水は高度な土木技術を用いて開削され、さらに土地の開発に適応するような改良を加えられて長く使われたのです。
ここで流末となる高輪台より先の勾配を見ると、三田上水も三田用水も急傾斜です。三田上水は高輪台から地中に入り、二本榎通りを通って三田・芝から金杉や西應寺に向かいました。地中を流れていたことを示すために高輪台から先の線を茶色にしました。高輪台から西應寺までの勾配は100mにつき70.8㎝と急で、とくに聖坂がある三田3丁目から芝3丁目までは100mにつき200㎝とかなりの傾斜です。聖坂の下に住む人たちは地下から噴き出すような水を使っていたのでしょうか。
左の写真は高輪台小学校で発掘された木樋の継手で、三田上水の支流の木樋をつなげた道具のようです。右の写真は芝の西應寺の門前です。三田上水はこの寺町を流れて入間川に落ちていました。境内を巡っていたという話もあります。私も西應寺の境内を歩いて流れの跡を探しましたが、よく分かりませんでした。辺りは幕末に名をはせた薩摩屋敷などの武家屋敷が並んでおり、これらの堀に水を注いでいたという話もあります。
次に三田用水の流末ですが、その水路は「文政十一年品川図」(1828)に細かく描かれています。幕府が編纂した地誌『御府内備考』(文政12年)によると、目黒から高輪台まで地表を流れてきた三田用水は、白金猿町でいったん地下に入り、町の下を39間(70m)ほど斜めに横切ってから再び地表に出ました。そして北品川宿の急斜面を下って平らな土地に入り、目黒川近くの小関畑で消えていました。今の小関橋交差点の少し南です。流末の水量が多い時は川に流れ込んでいたのでしょう。勾配を調べると100mにつき200㎝ぐらいあり、音を立てて勢いよく流れていたようです。このルートを歩いてみたのですが、前半は急な斜面の中腹を道場谷の谷底を避けるように折れ曲がりながら進み、池下と呼ばれた土地になるとなだらかに弧を描いて川岸まで流れていました。北品川宿や上大崎村の人々は、水が田畑に行き渡るように水路を工夫したのでしょう。
三田用水が流れる左の高台には中津藩主奥平家の屋敷があり、右の脇には仙台藩主伊達家の屋敷がありました。伊達屋敷の辺りは明治以降は島津侯爵邸となって島津山と呼ばれ、ツツジやモミジの名所として知られていました。季節には花びらや紅葉がはらはらと落ちて三田用水の流末を飾ったことでしょう。戦後は清泉女子大学のキャンパスになり、美しいツツジを今に伝えています。三田用水の流末は思いのほかイメージの膨らむ所です。(終)
(参考文献)
三田用水普通水利組合『江戸の上水と三田用水』岩波ブックセンター信山社、昭和59年/堀越正雄『日本の上水』新人物往来社、昭和45年/渡部一二『武蔵野の水路-玉川上水とその分水路の造形を明かす』東海大学出版会2004年/小坂克信「近代化を支えた多摩川の水」、とうきゅう環境財団、2012年/蘆田伊人編集校訂『御府内備考』第4巻、大日本地誌体系4、雄山閣、昭和45年/間宮士信他編『新編武蔵風土記稿・東京都区部編』第3巻、春秋社、昭和57年/『東京市史稿』上水篇第1・第2、東京市役所、大正8年、12年/『新修渋谷区史』上・中・下巻、東京都渋谷区、昭和41年/『目黒区史』『目黒区史資料編』東京都目黒区、昭和36年/『品川町史』上・中・下巻、品川町役場、昭和7年/目黒区ホームページhttp://www.city.meguro.tokyo.jp/gyosei/shokai_rekishi/
konnamachi/michi/rekishi/tobu/kayaku.html他。
(頁のトップへ)
2017.2.4

<はじめに>
2016年10月8日~10日、玉川上水・分水網の保全・再生をテーマにした展示会・講演会(主催:玉川上水・分水網を生かした水循環都市東京連絡会)が東京都庁・都政ギャラリー/都民ホールで開催され、関東5大学と玉川上水ネット(17の市民団体・10月8日現在)が参加しました。その内容は「江戸東京の発展を支えてきた玉川上水と分水網を再生して水循環都市東京を作り、また玉川上水と分水網を保全していく」ことです。私たち「渋谷川・水と緑の会」も玉川上水ネットの一員として参加させていただき、その分水である「三田上水と三田用水」の300年余の歴史と展望についてパネル(A1・4枚)を作成し、会場に展示しました。その際には玉川上水ネットの事務局の皆様に大変お世話になり、ありがとうございました。以下では私たちのパネルの内容と会場の様子をご紹介します。
なお、2016年12月21日に「玉川上水・分水網の保全活用プロジェクト」がめでたく日本ユネスコ協会の「プロジェクト未来遺産2016」として登録され、玉川上水及びその分水を広く世界にアピールする道筋ができたことを併せてご報告します。
Ⅰ. 展示パネル「三田上水と三田用水」の概要

会場の展示パネル
展示パネル①
展示パネル②
展示パネル③
展示パネル④
Ⅱ. 会場の風景
<おわりに>
展示と講演会が開かれた3日間、新宿・都庁の会場にはたくさんの方々が訪れて盛況でした。展示・講演の両方を併せて3日間でおよそ1000人の参加者がありました。私たち渋谷川・水と緑の会の「三田上水・三田用水」パネルは見学ルートの最後の所でしたが、多くの方々が見に来て下さいました。その中で長く目黒に住んでいらした方から面白い話を伺ったのでご紹介します。目黒駅に山手線を引いたときのことです。目黒駅では恵比寿や五反田と線路の高さを揃えるため、山を削って線路を通さなければいけませんでした。工事の結果、目黒の丘を通っていた三田用水が鉄道をまたぐ高架になったのです。その方の元治元年(1864)生まれのおじいさんは、現場で出た土をトロッコで運ぶ仕事をしていたそうです。おじいさんは親方から渡された木切れに1回運ぶごとに一筋の傷をつけてもらって、その数で給金をもらっていたとか。目黒駅の場所で三田用水が高架になった時代の様子がよみがえってきますね。他にも三田用水に詳しい方がパネルの前に来られ、いろいろと教えていただき勉強になりました。こうした機会がまたあると良いですね。(終)
(参考資料:事務局よりご提供)
|
水と緑の回廊・玉川上水と分水網
多摩から江戸・東京をつなぐ水循環の保全・再生
~東京オリンピック・パラリンピックを契機として~
展示の記録
日時:平成28年10月8日~10日 於:東京都議会議事堂1階都政ギャラリー
主催:玉川上水・分水網を生かした水循環都市東京連絡会
|
| 第1部「玉川上水・分水網と江戸東京の水循環」 |
|
展示:玉川上水・分水網を生かした水循環都市東京連絡会・事務局
|
|
ご挨拶
|
| ①玉川上水・分水網と地形 |
| ②玉川上水・分水網の形成過程 |
| ③羽村堰と小金井桜 |
| ④江戸の水道と玉川上水 |
| ⑤玉川上水・分水網と文化財 |
| ⑥明治中期の玉川上水・分水網 |
| 水循環 |
| 第2部「玉川上水・分水網と水循環都市東京」 |
| 展示:水循環都市東京シンポジウム実行委員会 |
| ①玉川上水の機能を活かして水都東京をつくる(山田正 中央大学理工学部教授) |
| ②水都東京をつくる外濠の新たなイメージ(陣内秀信他 法政大学デザイン工学部教授) |
|
③自然と歴史を活かし,災害に強い美しい世界一の水都東京を造る(天野光一 日本大学理工学部教授)
|
| ④水都東京に向けてーまち・かわ・ほり(宇野 求 東京理科大学工学部教授 ) |
| ⑤オリンピックと水~東京から世界へ~(沖 大幹 東京大学生産技術研究所教授) |
|
|
|
第3部「台地に刻まれた水と緑の回廊“玉川上水と分水網”」
|
| 展示:玉川上水ネット |
| 武蔵野台地と水路網 |
| ①今も残る集落のかたち~田村分水・熊川分水~(玉川上水遊歩道を考える会) |
| ②武蔵野台地の先駆者~砂川用水・柴崎分水~(玉川上水の自然保護を考え会) |
| ③小平用水路網50㎞は生きている(学び舎江戸東京ユネスコクラブ,小平ユネスコクラブ,ちい |
| さな虫や草やいきものたちを支える会) |
| ④市民がつくる水と緑のネットワーク~千川上水と仙川~(玉川上水を守り育てる武蔵野市民の |
| 会,武蔵野ユネスコクラブ,武蔵野の森を育てる会) |
| ⑤武蔵野台地に息を吹き込んだ砂川・品川・牟礼分水(三鷹環境市民連) |
| ⑥玉川上水の歴史と新宿(NPO法人新宿環境活動ネット) |
| ⑦品川用水に残る『面影』と出会うマップ(品川用水復活研究会) |
| 江戸の知恵「玉川上水網」保存・整備・再生支援(東京南ロータリークラブ) |
| ⑧三田上水と三田用水(渋谷川・水と緑の会) |
| ⑨玉川上水・いきものたちの通り道(ちいさな虫や草やいきものたちを支える会) |
|
(頁トップへ)
Copyright © 2021 Kimiko Kajiyama All Rights Reserved
|