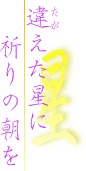
安倍晴明の孫にして陰陽寮
化け物の瘴気のせいで危うく寝込みそうになったものの、どうにか踏みとどまり、出仕するうちに体調も回復しつつある。
出仕するたびに悩まされていた
特に表立った問題や事件も起きておらず、束の間の平安といったところである。
年の瀬も押し迫った今の時期、直丁本来の雑用のほうが忙しく、昌浩は平和ながらもそれなりに慌ただしい日々を送っていた。
その日も細々とした残業があり、昌浩が物の怪を引き連れて
「本当に年の瀬ってのは忙しいんだねぇ」
「まあ、頑張れや。出仕して初の行く年来る年。明日は一応、休みだろう?」
「う〜ん、でも休みまくってるからなぁ………」
基本的に休みは月に五日と決まっているが、昌浩の場合、過ぎた日に長期休暇をとったばかりで、その点から見ればとっくに既定の休暇は超過している。まあ、休暇の種類が違うので休みといえば休みなのだが、視線が痛いことに代わりなはい。
ここは休暇返上で働くべきだろうか。
そんなことを考えながら、物の怪を肩にのせて歩いていた昌浩は、門のところに立派な牛車が止まっていることに気がついて立ち止まった。
物の怪がはたりと尾を揺らし、わずかに目を細める。
「なんだ? ここのところなかったが、晴明に客か?」
最高峰の陰陽師と名高い安倍晴明とその一族のもとには、それをあてにした貴族たちから様々な依頼が持ちこまれてくる。―――こういった、公務とは違う副業が薄給の宮廷陰陽師たちの生計を助けているのだが、引く手数多の当代随一の陰陽師である昌浩の祖父は面倒くさがって、左大臣藤原道長からの頼み以外は、余程のことがない限り、引き受けることはない。
あるいは、引き受けてもそのまま孫へと
いままでなし崩しに引き受けてきた諸々のことを思いだし、昌浩は半眼になってうめいた。
「………じい様、引き受けないといいなぁ」
「おや、あれは東三条殿の
「ええ、うそっ !?」
急に昌浩が走りだしたため、物の怪は肩から放りだされる羽目になった。ひらりと着地して、後を追いながら合点したように呟く。
「ああ、彰子か」
彼女の生家からの使者だ。まさか使いの者程度が彰子の顔を見知っているということはないだろうが、念には念を入れていまごろ邸の奥に隠れているのだろう。
近づいてくる昌浩に気づいた牛車の供人たちが挨拶をしてくるのとほぼ同時に、門より晴明が姿を現した。
その出で立ちに昌浩は目を見張る。
黄昏の暗がりのなかでもわかる、上等な白綾の狩衣姿だった。その下から、ちらりと覗く衣もやはり白。浄めと
孫の姿に気づいた晴明が、おや、という表情をした。
「おお、戻ったか昌浩や」
「ただいま戻りました。帰宅が遅くなり、申し訳ありません」
礼儀正しく昌浩が一礼すると、晴明は
「よいよい。年の瀬は忙しいものよ」
「………普段からは考えられない祖父と孫の会話だよなぁ」
のんびりと感想らしきものを呟いた物の怪を、昌浩がこっそりと睨む。
そんな昌浩をしばらく眺めていた晴明は、ふと思いついた顔で従者をふり向いた。
「そうだ。使者殿、この昌浩も連れて行ってもかまいませぬかな?」
「はい?」
昌浩はかぱりと口を開けた。牛飼い
「我が孫も、いまだ未熟ながら陰陽師の端くれ。陰陽師は一人でも多いほうが、御方さまも心安くあられましょうし―――」
言って、晴明はひょいと手にした荷物を掲げてみせた。布に包まれてはいるが、けっこうな大荷物だ。
「それに、こういった細々とした道具類を運ぶのが年寄りには少々重荷でしてな。陰陽術の道具ゆえ、従者がたにお任せするわけにもいきませぬし、そこの孫がちょうど適任で」
何のことはない、体のよい荷物持ちである。
残業続きで、俺けっこう疲れ気味なんですが、じい様。
左大臣が何を頼んできたかは知らないが、晴明の気の入れようからするとけっこう大きな依頼なのではないだろうか。果たして自分がついていってもいいものなのか。
もしかして、滅多にない依頼だから後学のために自分を連れて行ってくれるのか。いや、もしそうだとしたら、連れて行かれた先でいきなり「ほれやってみろ」とか言われかねない。できなかったらできなかったで「何だこれくらいのこともできんのか。あれほど手取り足取り丹念に教えてやったものを。ああ、わしは情けない、情けないぞよよよ」と袖でそっと目元を押さえられるに違いないのだ。これは如何にするべきか。
悩んでいる昌浩をよそに、晴明は従者と何事かを相談している。
やがて話はまとまったらしく、晴明はおもむろに昌浩へと向きなおった。
「というわけで、昌浩や。急いで衣をあらためてきなさい」
「あの、じい様………?」
衣をあらためろと言われても、何をどうあらためたらいいのか。
戸惑った昌浩に、隠行している天一が助け船を出した。
(左大臣の北の方が産気づかれました。白の衣です―――)
昌浩は目を見張った。
そういえば、初めて東三条殿に行ったときに、彰子の母親が五人目の子どもを身ごもっているのだと聞いたような聞かなかったような。
あれから、あまりにも立て続けに色々あったものだから、すっかり忘れていた。
「わかりました。着替えてまいります」
言いたいことや聞きたいことは色々あったが、とりあえず昌浩はそれだけを言って門の中に入っていった。
出迎えた
「彰子の妹か弟ってことになるよなぁ………」
「まあ、道長に正妻は二人いるが、東三条殿なら倫子のほうだろう。そう思って間違いないんじゃないか」
帰宅直後で疲れてはいたが、そうなると彰子のためにも行ったほうがいいだろう。今年の十月まで東三条殿にいた彰子は、当然、母親が身ごもっていることを知っているはずだ。生まれてくるのが弟か妹かも気になるだろうし、東三条殿の様子を見てきて、色々話してあげれば喜ぶだろう。
晴明もそれを見越して、折良く帰ってきた昌浩に供を命じたふしがある。
「と、じゃあ一応、顔だけは見せてから行かないと………」
そう言いながらも、足が向かう先は己の部屋だ。まあ、間違ってはいないのだが。
廊下を歩く昌浩の横を歩いていた物の怪が、不意に口を開く。
「昌浩よ」
「ん?」
「俺は行かないから、お前だけ行ってこい」
昌浩の足がぴたりと止まった。
「どうして? もっくんも行こうよ」
「産のときの陰陽師の仕事ってのは長時間の祈祷だ。退屈でかなわん」
どこか憮然とした口調でそういうと、物の怪は先だって歩きだした。
「それに………俺の属性は凶将だ。こういった祝いごとには向かん」
「そういうものなの?」
「そういうものだ」
「ああ、だから天一がいたのかなあ?」
何か、こういうことにいちばん向いてそうだよなぁ―――。
のんびりと見当違いのことを言われ、物の怪は危うく転ぶところだった。
凶将云々とはほとんど口から出任せの言い訳にすぎなかったのだが、昌浩が納得してくれたらしいので、何も言わずにおくことにする。まあ、天一が吉将なのは間違いではない。
子どもが苦手の物の怪と違って、昌浩はとても子ども好きだ。
出産の祈祷にしても、いままで一度も立ち会ったことがなかったから、内心けっこうわくわくしているのだろう。後学のためにも一度、晴明と一緒にやっておくのは悪くない。
「………ただいま。彰子、いる?」
言いながら己の部屋の妻戸を開けると、中にいた彰子がすぐに顔をあげた。案の定、
まだ装束を解いていない昌浩の姿を見て目を丸くしている彰子に、昌浩はかいつまんで事情を話した。
「………だからさ、俺も行ってくるよ。後で、見てきたことを話すから」
昌浩の言葉に、彰子がふうっと目を細める。懐かしそうな、切なそうな顔だった。
「うん………お願いね、昌浩」
「遅くなるだろうから、俺とじい様の帰りなんか待たずにちゃんと寝てて。暇だったら、もっくんが話し相手になるから」
「………おい」
勝手に決められた物の怪が抗議の声をあげる。
彰子は首を傾げ、物の怪を見下ろした。
「もっくんは行かないの?」
「うん、行かないんだって―――ああ、はい母上、いま行きます! じゃ、じい様を待たせてるから、行くね」
「うん、いってらっしゃい」
昌浩はひとつ頷くと、慌ただしく立ち去っていった。
昌浩を見送った彰子は、
物の怪も部屋に入ると、そのまま
「もっくんは、どうして行かないの?」
彰子の記憶の限りでは、昌浩が行くところ物の怪がいつも一緒のはずだった。
彼女がそう問うと、物の怪は何だか痛そうな顔をした。
「俺は式神だ」
それは以前聞いたから知っている。
彰子が頷くと、物の怪はぱたりと尾を打ち鳴らしてから、口を開いた。
「ああいう、極端に浄められた場である産所に、式神みたいな異質の気配があると、生まれたばかりの赤子にはあまり影響がよくない」
「でも、天一がついて行ったみたいだけど………」
「知っていると思うが、天一は傷を癒す力を持つ。晴明がふさわしいと判断して連れていったんだろう」
答える物の怪の口調がいささか元気がないような気もしたが、そういうものなのかと、とりあえず彰子は納得することにした。
彰子が納得したのを見てとって、物の怪は口をつぐむ。
途端に部屋はシン、と静かになった。
彰子は巻物へ視線を戻したが、すぐに東三条の母のことが気になってしまい、溜息をついて読むのをやめた。
もう正式な形では二度と対面できない母だ。
藤原道長の正妻・源倫子の長女『藤原彰子』は、別にきちんと存在するのだから。
母は知らない。娘が同じ顔をした異母姉妹と入れ替わってしまったことを。帝のもとに
近く、きちんと事情を説明すると父は言っていたが、産み月間近の母の体を気遣って、いまだ話していないだろう。
そして事情を呑みこんだ母に会えても、弟と妹にはもう会えない。彼らの『姉』は
彰子の様子に気づいたのか、物の怪がやや改まった態度で話しかけてきた。
「どうした、彰子よ。母親のことが心配か?」
素直に彰子は頷いた。
「案ずるな。晴明が行った。昌浩もな」
「うん………」
このご時世、いくら昔よりも増しになったとはいえ、お産は命懸けの行為だった。
母、倫子は比較的お産の軽いほうらしく、彰子自身を産むときにも弟妹たちを産むときにも、それほど危ぶまれることはなかったと聞いている。
それでも邸には何日も陰陽師や僧たちが詰めて祈祷をあげ、庭では
きっと今日もそうなのだろう。
生まれてくるのは弟だろうか、妹だろうか。
ふと、彰子はとある事実に気づいて目を見張った。
「そっか、そうなんだわ………」
物の怪が瞬きし、耳をひょんとそよがせる。
「どうした?」
「これから生まれる私の弟か妹にとって、姉君は真実、
物の怪は虚を突かれた。
見れば、彰子は灯台の明かりの輪のなかで、目を潤ませながら微笑んでいた。
「だって、これから生まれてくるんですもの。最初から姉君として会うのは章子様。
「―――彰子よ、それは、だな………」
ここで彰子が泣きだしたら、やはり泣かせたということで物の怪が昌浩に叱られるのだろうか。
どうしていいのかわからず、物の怪がおろりとしていると、彰子は両の指先で己の頬を押さえて、そっと呟いた。
「よかった………」
意外な言葉に物の怪が驚いていると彰子は、だってそうでしょう、と続けた。
「それだと、章子様も気を張って接したりせずにすむもの………弟かしら、妹かしら。………章子様をお慕いしてくれると、どんなにいいかしら―――」
己のさだめを肩代わりさせてしまった異母姉妹を気遣う彰子を見つめ、物の怪はなかば感心していた。
ここまで思いやりが及ぶ人間も珍しい。
「なら、お前のことは知られなくもいいのか? 自分が本当の姉なのだと」
道長が弟妹たちに真実を話すことはないと思われたが、ためしにそう問うた物の怪に、彰子はためらいなく頷いてみせた。
「うん、いいの。だって知ったら、章子様にもその子にも、よけいな物思いが増えてしまうだけでしょう?」
それにね、と彰子は続けた。
「その子が知らなくても、私は知っているもの。淋しくなんかないわ。晴明様や昌浩だって、今夜みたいにきっと時々様子を知らせてくれると思うし」
そう言って彰子はにっこりと笑った。
つくづく順応性の高い姫だ。
そして何と強い姫か。
(昌浩よ。今更ながらにお前の目はたしかだよ)
十二神将はたしかにとてつもない通力を持っているが。最終的にはどう足掻いても人には叶わない。いつだって最後には、人の想いが事を為す。
昌浩にとっては、この少女の存在が、最初に動きだすきっかけであり、また最後の
この心が昌浩を救うだろう。何度でも。
物の怪は軽く息を吐くと再び丸くなり、その紅い瞳を閉じた。
彰子は灯台を引き寄せ、巻物に再び視線を落としている。わからないことがあったら聞いてくるだろう。
そういえば、神様講座はどこまで話したのだったか。先月の同衾騒動以来、話していない。まあ、ねだられたら話してやろうか。
―――子どもは苦手だ。
すぐに泣くし、加減もわからず泣き続けては、えずいたり熱を出したりする。弱いし脆いし言葉は通じないしで、ほとほと困る。
それでなくても
だから物の怪は東三条殿には行かなかった。自分が行けば、これから生まれる彰子の弟か妹がどうなるかわからなかった。最悪、恐怖の余り、その小さな心臓を止めてしまうことになるかもしれない。出産直後は母体も赤子もひどく弱い。
泣かなかったのは、いままでただ一人だけ。
たった、一人だけだ。
今頃、出仕直後からそのまま突入した長時間耐久祈祷を行っているであろう、あの晴明の孫だけが、騰蛇を見ても泣かなかった。
目の前の姫との関係は前途多難。立ちはだかる壁の高さ
(………ま、頑張れや、孫)
物の怪は微かに目を開き、うっすら笑うと、それからまた閉じた。