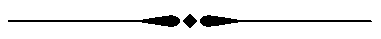鉄鎖とは
学生:『社会契約論』のはじめのところに、人間は生まれながらに自由だが、いたるところで鉄鎖につながれている、という有名な文章がありますよね。格好いい文章だなあ、と思ったのですが、何度か読んで前後との関係を考えているうちに、この文章が何を意味しているのか、わからなくなってきました。生まれながらに自由な人間なんているんでしょうか。 教師:この文章ですね。
| 人間は自由なものとして生まれたが、しかもいたるところで鉄鎖につながれている。他の人々の主人であると信じている者も、その人々以上に奴隷であること免れてはいないのだ。このような変化がどうして起こったのか。私にはわからない。それは何によって正当化されえているのか。私はこの問いなら解きうると思う。(第1篇第1章、12頁:p.9) *(日本語テクストの篇と章、頁数:フランス語テクストの頁数) |
| 私は、人間をあるがままの姿でとらえ、法律をありうる姿でとらえた場合、社会秩序(l'ordre civil=政治秩序)のなかに、正当で確実な統治(administration)上のなんらかの諸原則があるのかどうかを研究したいと思う。(第1篇、11頁:p.189) |
詳しく話そうとすると、この本のほぼ全体を一挙に説明しなければならないので、今は概略だけ言っておきます。ここでの「鉄鎖」は、統治が成立している政治社会の下にあるすべての人の義務を指しています。これがなぜ正当化できるかと言えば、「義務」はその成立以前の状態にある人々の自由な意思【*】によって合意されたものであれば正当で拘束力を持つ、という見方があるからです。自由な同意が人々を義務づけるというのは、ルソーに限らず、社会契約説全般の基本命題です。主権者の絶対性を強調するホッブズですら例外ではありません。もっとも、それなら約束を守る義務は約束以外のどこから生じてくるのか、というヒュームの強力な批判が出て来ることにもなるのですが。
【*】以下では、漢字表記は引用部分も含めて「意思」に統一しました。深い理由があるわけではなく、便宜的な統一です。
それはともかくとして、ここまでの作業工程は読者には見せません。次からが読者への公開版となります。今度は、しがらみのない、つまり、家族も言語も全部剥ぎ取った孤独な自然人を先頭にして、フィルムを逆回しする。そうすると、なんとなくコマがつながって本物の人類史のようになり、最後のシーンは疎外された文明人という、誰も完全には否定できない切ない現実になる。後世の「現象学的還元」みたいなことをしているわけです。孤立した白紙状態の個人という独我論的な見方を出発点にする議論の仕方は、認識論哲学の常套手段ですし、のちの実存主義や現象学にも共有されているみたいですが、その点は不勉強なので脱線はここまで。
話を戻すと、ともかく、孤独な自然人は、今述べたような理論的操作で成り立っている抽象観念でしかありません。実在のものではありません。ルソーはそのことをよくわかっているはずですが、彼は、抜群の想像力と筆力を駆使して、それを具体的な実在であるかのように描くことができたのです。この種の抽象を容赦なく批判するミルですら、ルソーの文明批判を、逆説的ではあれ価値ある部分的真理と認めたほどです。たしかに『社会契約論』でも自然状態への言及はありますが、その一方でルソーは、家族を「もっとも古く、そして唯一の自然な社会」(第1編、13頁)とみなしています。孤独な自然人にこだわるなら、家族も煩わしい不自然な「鉄鎖」になるはずです。応答しようとする問題に即した議論の立て方が、『学問芸術論』や『人間不平等起源論』と違っているからこうなるのです。人間は、太古の時代から、人間関係のしがらみの中で生まれ育ってきたのであって、そういうしがらみを全部しりぞけることにこだわり続けていては、政治を現実的かつ前向きに考察することはできませんし、ジュネーヴ国制擁護論は書けないでしょう。
学生:「現象学」とかの話はまだよくわかりませんが、フィルムの逆回しの説明はよくわかりました。次回は、社会契約そのものについて、質問してみたいと思います。
【補注】『人間不平等起源論』について一言。この本の本論は、『学問芸術論』と同じプロットになっていて、原始から始まり最後は荒廃した悲惨な状態の描写で終わるという、やりきれない議論になっていますが、冒頭の献辞では、そのような悲惨さを免れているジュネーヴが賞讃されています。なぜ、ジュネーヴに限って、恵まれた特権的境遇が可能なのか、という疑問が当然生じてきますが、その答が『社会契約論』で示されることになるわけです。その観点から見る限りでは、『人間不平等起源論』は、『学問芸術論』と『社会契約論』の中間に位置しているとも言えるでしょう。
ちなみに、『学問芸術論』や『人間不平等起源論』の疎外論的なトーンから現実の人間を前提とした政治学的探究へと反転していくルソーの姿勢は、『社会契約論または共和国の形態についての試論(初稿)』の次の一節に表われています。
ちなみに、『学問芸術論』や『人間不平等起源論』の疎外論的なトーンから現実の人間を前提とした政治学的探究へと反転していくルソーの姿勢は、『社会契約論または共和国の形態についての試論(初稿)』の次の一節に表われています。
| しかし、たとえ、人間たちのあいだに自然的で一般的な社会がないとしても、人間は、社会的になることによって、不幸で邪悪となるとしても、また、自然状態の自由のうちに生き、しかも同時に、社会状態の要求に従って生きる人々にとっては、正義と平等の法はなきに等しいとしても、それでもなお、われわれには徳も幸福もなく、神は人類の堕落に備える方策もなしにわれわれを見捨てたとは考えないで、悪そのもののなかから、それを癒すべき薬をひきだすよう努力しよう。できれば、新しい結社によって、一般的結合の欠陥を矯正しよう。(作田訳『社会契約論』、250頁) |
なお、以下も参考にしてください。「生まれながらの自由とフィルマー」