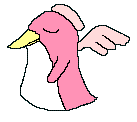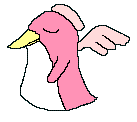あれは、長男がもうすぐ3歳になろうとしていたある冬の日。
夫と3人で動物園に出かけた。
外には雪が積もっていて、暖かい国からやってきた動物たちはみんな、
暖房の効いた建物の中でお昼寝をしていた。
狭い建物の中は動物の匂いが充満し、ちょっと頭が痛くなりそうだと夫が言うので、
外の動物たちを見て歩いた。
快晴の冬の冷たく澄んだ空気は、
氷壁の中を歩いているように、
スカートから飛び出た両足のすねをキンキン痛ませる。
正直に言うと外なんて歩く気分にはなれなかった。
だけど長男はとても嬉しそうに、
ビニール製の上下のつなぎの音をかさかさ立てながら、
精力的に歩き回った。
まな鶴やふくろう、白熊の檻を外側から眺めて、
冬の動物園を満喫していた。
そんな彼がふと足を止めたのは、
氷のプールの横に立つ、ペンギンたちの檻の前だった。
彼はペンギンと同じように、手すりを握り締めたまま、直立不動で
動かなくなった。
何度声をかけても、どこにも行かないここに居るの一点ぱりで、
よその子供が近寄ってきたら、
このペンギンは自分のものだから見るな、なんて言い出す始末。
20分くらいはそうして立っていただろうか。
あまりにも両足が寒くて、頼むからもう帰ろうと夫に説得してもらい、
なんとかペンギンから彼を引き離すのに成功した。
その間ペンギンたちは、だるまさんころんだをしている子供みたいに、
ひたすら一点を見つめて全く動くことはなかった。
帰りの車の中でしみじみ長男が言った。
ぼく、おおきくなったらペンギンになりたいと。
それから何年か過ぎたある夏の日。
家族の数は男の子がひとり増えて4人になっていた。
お弁当を作って湖にドライブに行く途中、
緑に覆われた峠の真ん中で、
『ママ、お空の雲んところに、ペンギンがいっぱい泳いでるよ』
ぽっかり浮かんだ大きな雲を指差して、
3歳になったばかりの次男がそう言った。
正直に言おう。
私の目に、そのペンギンは映らなかった。
でも、次男の目には、雲から空の海に飛び込むペンギンたちが、
はっきりと見えているようだった。
ほんの少しうらやましく思いながら、
空の色と海の色のおはなしをした。
海は大きな鏡だから、お空がそっくり映ってあんなに青いんだって。
だから海のペンギンも、本当はお空に居るのかもしれないね。
何日かして私は白い画用紙に、子供のリクエストに答えながら絵を描いた。
うさぎ、はい。
かめ、はい。
アンパンマン、はい。
ふいにペンギンが描きたくなった。
長男が最初になりたいと思ったもの。
次男にしか見えない不思議な生き物。
スラスラと勝手にペンが動いて画用紙に現れたペンギンに、今度は羽をつけてみたくなった。
本当は、ペンギンに羽はもうちゃんとついているけど、
あえて白い翼をつけてみたくなった。
まるでペンギンの天使だな〜。
こうして天使ペンギンpengelは、私の前にやってきた。
これがもうひとつのペンギン物語の全てです。
でもね、みんなに秘密だよ。
ここを覗いた人にだけ、そっと教えたんだからね。
|