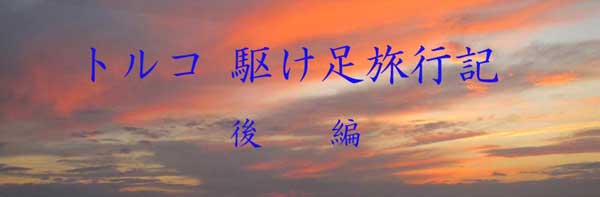
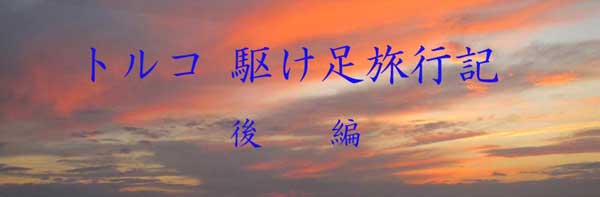
|
『前編』の最後は、コンヤ地区のメヴラーナ博物館まで掲載しました。この後スルダハンという町で、この地区最大規模のキャラバン・サライ(隊商宿)を覗いて、230㎞バス移動し、カッパドキアが今宵の宿泊地でした。
今回の旅行は、夜間に雨が降ったことはありましたが、日中は好天に恵まれ、誠についていました。
ついていたと言えば、この日のホテルは、次の写真のように岩山をくり抜いた、いわば洞窟宿でしたから、基本的に全室造りが違うのです。その為抽選で夫々の部屋を決めたのですが、我々には幸運にも、スイート・ルームのような部屋が当たりました。
|
 |
|
この日のホテル出発は朝7時でしたから、その10分前位だったでしょうか。ホテル最上階から撮った、この地名物の熱気球が上がるところです。もし又行くことがあれば、「絶対あれに乗りたいね!」と家内と話したことでした。
|
 |
|
日程5日目の今日は、これまた期待のカッパドキア岩石遺跡群およびギョレメ国立公園の自然・文化複合世界遺産の観光です。しょっぱなは「三人姉妹岩」です。
|
 |
| 「らくだ岩」です。どこの観光地もそうですが、猿とか象など、動物の名前をつけた岩が多いようです。 |
 |
|
ここに写っているのは本物のらくだです。
カッパドキアは、トルコの首都アンカラの南東にあるアナトリア高原の、火山が数回に亘って噴火し、その後浸食と風化によって出来た標高1,000㍍の台地です。
|
 |
|
ガイドからは何の解説もありませんでしたので、私が勝手に「水牛岩」と名付けました。
ちなみに、ラテン語のCappadociaとは、「美しい馬の地」という意味だそうです。
|
 |
|
カッパドキアを含む世界遺産は、約20㎞×20㎞の400k㎡の広さだそうですが、米国のモニュメントバレーに似た造形地です。これ、「きのこ岩」とか「しめじ岩」とか言っていました。
|
 |
| カッパドキアとはやや趣を異にする、これまた珍しいギョレメ国立公園の景観です。 |
 |
|
この地区にも多くの人家が見られますが、家の一部には、多分この岩山を巧みに活用しているんだろうと思いました。
|
 |
|
カッパドキア地区の、カイマルク地下都市では、岩に頭をぶつけながら歩きました。
この都市は、ローマ軍によるキリスト教徒迫害を避けて隠れ住んだという住居跡です。この写真に見られる穴も、そんな目的だったのでしょう。
|
 |
|
感激のカッパドキア観光を終えた後、途中トルコ石と絨毯の店に案内され、首都アンカラへ向かいました。ここのスーパーマーケットでお土産やワインとつまみを買い込み、22:30発「アンカラエキスプレス(1等個室寝台車)」でイスタンブールへ。
これは翌朝観光のオスマン・トルコ帝国の王、スルタンの住まいであったトプカ宮殿です。
|
 |
|
このモスクの正式名称は、やはりスルタン・アフメット1世の命により建てられたことから、スルタンアフメット・モスクと言います。
ただ内部の壁が約20,000枚の美しい青色のタイルで飾られているため、一般的にブルー・モスクと呼ばれる、イスラム教の礼拝堂です。 |
 |
 |
| 左がその青色のタイルで装飾された壁面。右はこれも大変美しく輝いた天井の飾り窓です。 | |
 |
|
イスタンブールで一番の賑わいを見せるイスティクラル通りです。路面電車も走っていました。この日は当地が土曜日だったため、人・ひと・ヒトでごった返していました。
|
 |
| 実質6日間、走りも走り、乗りも乗ったv移動、プラスtによる移動の、「駆け足旅行」も、あっという間に過ぎてしまいました。バスの中では、ガイドが気を利かせて、江利チエミの♪ウスクダラ♪や庄野真代の♪飛んでイスタンブール♪などの曲を流してくれました。
イスタンブールのバザールでは、ショッピングを、また、ボスポラス海峡のクルーズも楽しみました。
飛行機は、多少の「心残り」を乗せて、イスタンブール上空を後にしました。:::Q
|