|
時間と空間は重力で曲がるか
更新したのでCtrlキーを押しながらF5を押してください
アインシュタインの一般相対性理論によれば、重力によって時間と空間は曲がるとされています。しかし私はそういうことはないでしょう、と述べています。
太陽や銀河などの近傍を通る光の進路が曲げられるのは、強い重力によって周辺に集まったガスや宇宙ダストなどによる屈折作用だと思います。
屈折角θ は r を光の曲率半径、 dn/dx をガスの屈折率の傾斜とすれば、
で与えられます(下図参照)。
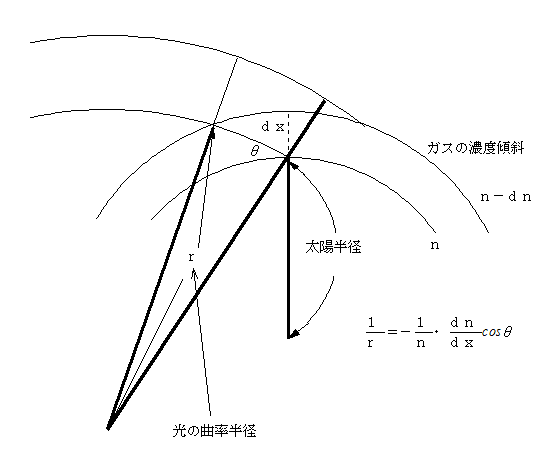
この事は『相対論はやはり間違っていた』(徳間書店刊/1994年)で発表した直後から、多くの電波工学を専門としている読者から「成層圏を横切る電波が進路を曲げられていることや、媒質によって波長が長くなることが観測されており、すでに実証されている」とのメールがありました。太陽の周辺でもガスの濃度傾斜によって、光の進路が曲がることは容易に説明できる現象であります。
「時間と空間は重力によって曲がる」というアインシュタインの一般相対性理論によるものではなく、ニュートン力学やマックスウェル電磁力学によって説明できるものと私は確信しています。
なお他項でも述べたように、遠い天体からやってくる光の波長が伸びるのは宇宙空間に散在しているガスや宇宙ダストによってエネルギーが失われ、波長が伸びるという私の提唱した「量子エネルギー効果」
も、電波工学では常識的に使われています。これを私は宇宙に応用したのです。
私自身、電気通信工学の出身ですが、意外なところで、アインシュタイン物理学よりも電波工学やエレクトロニクスの方が進んでいることを知り、戸惑いを隠せません。
重力が大きければ大きいほど、周辺に集まるガスは多くなるでしょうから、屈折角は大きくなるでしょうし、遠い天体ほどλが長くなる理由も説明できるのです。
赤方偏移とは、遠い天体ほどスペクトル輝線が赤い方にズレることですが、相対論宇宙物理学ではローレンツ因子で計算されています。間違っていても、とりあえず簡単な計算で宇宙の大きさを計算できるので、<これでいいよ>とされているのでしょう。
アインシュタイン宇宙論が間違っていることは天体観測から既に実証されている例があります。それは私たちの銀河の中に途轍もない大きな赤方偏移を有する天体が観測されている事です。ローレンツ因子で計算すると、何億光年にもなる遙か遠くの天体になってしまうのに、相対論物理学者は、これらを無視しています。
エディントン卿の捏造論文
ここで別項の一般相対性理論に補足を致します。
一般相対性理論が広く世界に知れたきっかけはエディントン卿(Sir Arthur Stanley Eddington(1882―1944)イギリスの天文学者、理論物理学者。グリニジ天文台の助手から1913年ケンブリッジ大学教授、翌年ケンブリッジ天文台長となる)の影響がきわめて大きく影響しています。
1916年に一般相対性理論が発表された当時はその理論の評価は低く、学会では無視されていたのですが、エディントン卿が孤軍奮闘、一般相対性理論の検証に努力を注いだのでした。
タイミングよく1919年の皆既日食を契機にアインシュタインの予言する “太陽の重力による光の進路の歪曲” を実証しようと観測隊を結成し、遠く西アフリカの海岸に近いプリンシペ島に出向いたのでした。そして見事アインシュタインの予言通りの光の進路の曲がりが観測されたと世界中に報道され、一躍一般相対性理論が脚光を浴びることになりました。その後もエディントン卿は一般相対性理論の普及に全力を注ぎ、数学的理論展開を進めて行きました。現在の相対論的宇宙論の草分け的存在はまさにエディントン卿だったと言っても過言ではありません。
しかし、エディントン卿の観測には多くの疑惑がある事が、最近の科学史研究で明らかになっています。
ここで京都府の杉岡氏のホームページから、その一部を掲載させて戴きます(杉岡氏の承諾済み)。
--------------------------------------------------------------------------------
2005/10/19追加 <エディントンの観測結果に重大疑惑>
1919年当時に一般相対論を検証するためにエディントンが行った観測結果には、重大な疑惑が隠されていました。これはまさに驚愕の事実です。
教科書で紹介される観測結果は、じつは真実のデータではなく、一般相対論に有利になるように(都合のいいように)、巧みに情報操作,データ処理がなされたものだったのです!
当HPを応援してくださっている平野様が、「七つの科学事件ファイル 科学論争の顛末」(H・コリンズ + T・ピンチ著,福岡伸一訳、化学同人)という本を紹介してくださり判明しました。本サイトでの同本の引用はファイルⅢ「相対性理論は絶対か」(p.79~p.121)の中のp.111~p.117から掲載させてもらっています。
まずこの本の概要をすこし紹介しましょう。この本は、科学の7事項を扱っており、その一つが相対性理論となっています。他に、太陽ニュートリノ問題、重力波の検出問題、常温核融合問題などの項目があります。
ある理論(仮説)を検証する上で巻きおこった論争というべき状況を、非常に詳しく解析しており、きわめて興味深い内容です。通常の教科書本には現れてこない、つまり歴史の闇に消えてしまった驚くべき事実も記述されており、有用な科学史資料となっています。
相対性理論の章では、前半でマイケルソン・モーレーの実験を、後半でエディントンらの観測実験を扱っています。
なんと、エディントンらは複数あったデータの中から、アインシュタインが予言した1.7秒の曲がりに近いデータだけを選んで発表するという暴挙を行ったのです。
ここの記述は詳細をきわめ、ずいぶんと長いのですが、そのクライマックスの部分だけを抜き出しますと、次のようになります。
「七つの科学事件ファイル 科学論争の顛末」p.111~114「遠征と観測」
エディントンによる観測実験は、実際には二つの部隊に分かれて実施された。第一部隊は二つ、第二部隊は一つの天体望遠鏡を携えていた。二つの部隊は皆既日食の見える二つの地点に分かれて赴いた。1918年3月のことであった。
A・クロメリンとC・ディビッドソンはブラジルのソブラルへ、一方、エディントンとその助手E・コッチンハムは西アフリカの海岸に近いプリンシペ島に向けて出発した。皆既日食に際してソブラル隊は持参したアストログラフィック望遠鏡で19枚、このうち1枚は雲のため不鮮明な写真となった。もう一つの四インチの望遠鏡では8枚の写真を撮影した。プリンシペ隊は、1台のアストログラフィック望遠鏡を携えていた。皆既日食当日は曇りであったが、彼らは何とか16枚の写真撮影を行った。このうち2枚だけが星をとらえていたが、いずれも5つの星をとらえていただけだった。数ヵ月後、ソブラル隊は同じ場所に戻って対照写真を撮影した。エディントン隊は、プリンシペ島ではなくオックスフォードで撮影を行った。これらの結果をもち寄り比較がなされた。
ソブラル隊が四インチ望遠鏡で撮影した写真がもっとも良いデータとなった。しかしこれさえ焦点は完全には合っていなかった。クロメリンとディビッドソンは、太陽をかすめて通過する星の光のズレは1.86から2.1の間であると算出した(値が幅をもって算出されるのは、統計学でいう確率誤差を含んだ値として計算されるからである)。この値は、アインシュタインの予測の1.7秒に近い。
一方、ソブラル隊がアストログラフィック望遠鏡で撮影した写真はあまり鮮明なものではなかったが、このうち18枚(1枚は雲のため使用不能)を用いて計算を行ってみたところ、ズレは0.86秒と出た(確率誤差の幅は計算できなかった)。この値はニュートン力学による予測0.84にかなり近い。
つまり大まかにいえば、ソブラル隊のアストログラフィック望遠鏡による結果はニュートン力学を支持し、四インチ望遠鏡の結果はアインシュタイン理論を支持したといえる。しかし、四インチ望遠鏡の結果は明らかにアインシュタインの予測よりも大きなズレを示しており、一方、ニュートン力学を支持するアストログラフィック望遠鏡の写真は不鮮明であるという問題をかかえていた。
プリンシペ島で撮影された2枚の写真は何とか星をとらえてはいたが、非常に不鮮明であった。それにもかかわらず、エディントンはこれらの写真から、重力の影響を「仮定」した複雑な方法でズレの値を算出した。最初にエディントンは、アインシュタインの予測値とニュートン力学の予測値の間をとった値を「仮定値」として用い、次にアインシュタインの予測値を「仮定値」として用いて計算を行った。この仮定値の違いが実際どのような結果の差をもたらしたのかは不明だが、重要な問題は、エディントンが星のズレの計算に最初からアインシュタインの予測値を用いた、という点である。この結果、不鮮明な2枚の写真から、星のズレは1.31から1.91秒の間にあると算出された。
確率誤差の幅は現代統計学でいう標準偏差に変換可能である。ソブラル隊の四インチ望遠鏡による結果は標準偏差を含めて1.98±0.178(平均値±標準偏差)、アストログラフィック望遠鏡の結果は0.86±0.48となる。エディントンが計算したプリンシペ島の結果は、1.62±0.444となる。現代統計学によれば、平均値を中心として標準偏差の1.5倍の幅の範囲内に真の値が含まれる確率は90%となる。・・・・
仮に、いずれの理論的予測値も知らない人が観測を行い、この結果を得たとすれば、どのような結論を導きだすだろうか。・・・おそらく次のように判断するだろう。ソブラルのアストログラフィック望遠鏡の値と、プリンシペ島の同型望遠鏡の値は、一方は大きく他方は小さく、しかも範囲が重なっており、結論が出せない。ソブラルの四インチ望遠鏡の値は1.7よりも大きな値となっており、いずれの値もバラバラである。
実際、第一の値は1.7から2.3の範囲、第二の値は0.1(ほとんどズレなし)から1.6の範囲、第三の値は0.9から2.3の範囲であり、いずれもばらつきが大きく一定の答えを引き出すことは困難である。にもかかわらず、1919年6月イギリス王立天文学会は、エディントンの観測結果によって、アインシュタインの理論が立証されたと発表したのであった。
この部分だけでも読者はひどく驚かれることでしょう。教科書で読むのと、えらく違っているなあ・・と。しかし、信じがたいことに、上記からエディントンらは強引に「アインシュタイン理論が立証された!」の方向にもっていくのです。次を見てください。
「七つの科学事件ファイル 科学論争の顛末」p.114~117
結果の解釈を求めて、このような強引な解釈がまかり通った背景には、エディントンや王立天文学会による巧みな論理展開があった。まず、実験結果の答えとして考えられるのは、三つの可能性だけしかない、という前提である。つまり、星のズレは観測できないか、ニュートン力学の予測値で観測できるか、あるいはアインシュタインの予測値で観測できるか、の三つである。
もし、この三つ以外の答えの可能性も考慮しなければならないなら、実験結果がその答えに近い場合、困ることになる。
たとえば、星のズレが2.0秒になるという理論的予測があれば、ソブラルの四インチ望遠鏡の結果がかなり近いので、その理論が正しいとされてしまう。実際、当時、このように別の予測をする学者もいた。しかし、エディントンらの議論は巧みにこれらの少数意見を無視して、実験は三つの可能性、すなわちズレは0.0か、0.8か、あるいは1.7かを決定するために行われる、という方向で進んだ。
もし、ズレの可能性としてもっと別の値も考慮されていた場合、エディントンの結果は、アインシュタイン支持で落ち着いただろうか?けっしてそうはならなかったはずだ。アインシュタイン支持という結論を出すために、エディントンたちはソブラルの四インチ望遠鏡のデータをもっとも重要視し、プリンシペ島の2枚の写真のデータをその支持材料として用いた。
一方、ソブラルのアストログラフィック望遠鏡で撮影された18枚の写真の結果は無視した。イギリス王立天文学会の発表後、この操作をめぐってさまざまな議論が巻き起こった。矢面に立たされた学会は、1919年11月6日、王立天文学会会長ジョセフ・トンプソン卿の呼びかけで会合を開いた。彼は次のように述べた。
「観測データを正確に解釈するのは当事者以外の人間にはいささか難しい問題となる。しかし王立天文学会とエディントン教授はデータを詳細に検討した。この結果、星の変位に関するデータは、大きい方の値がより確かであるという結論に達した」
しかし1923年、アメリカの研究者W・キャンベルは次のように記している。
「エディントン教授にはプリンシペ島における観測データをことさら重要視する傾向が見られる。しかし、ここにはわずかの星が数枚の写真に写っているだけで、決して良いデータとはいえない。むしろソブラルで撮影されたアストログラフィック望遠鏡のデータのほうが鮮明である。しかしこのデータは全く重要視されていない。このような取捨選択の基準が全く明確ではない」
エディントンは、ソブラルのアストログラフィック望遠鏡のデータには、「一定の傾向をもつ誤差」が含まれているのでデータとしては使えないと主張していた。普通、誤差はランダムに生ずるが、この場合、真の値を低くする傾向をもつ誤差が含まれていた、というのである。もしこれが本当で、他の二つのデータにはそのような問題がないのなら、エディントンの取捨選択にも立派な理由があることになる。
しかし当時、このような問題が本当に起こっていたのかどうかを彼は明確に証明することができなかった。それにもかかわらず、エディントンは観測実験の成果を立派な論文に書き上げ高い評価を得た。この論文では、ソブラルのアストログラフィック望遠鏡による18枚の写真に関しては全く触れず、四インチ望遠鏡による1.98というデータとプリンシペ島の2枚の写真に由来する1.62というデータのみが提示されていた。事情を知らない人が、この二つのデータを見せられて、ニュートン力学の予測値0.8とアインシュタインの予測値1.7とどちらに近いかと問われれば、誰もがアインシュタインに近いというのは当然である。
しかし、この当然さは、エディントンと王立天文学会を中心とした学者たちが、実験データを恣意的に取捨選択したことによってはじめて作り出されたものなのである。・・・・・・・・・
(窪田註:同117ページには次のような記述で締めくくられています。)
1922年から1952年にかけて起こった10回の皆既日食に際して、引き続き観測が行われた。このうち1929年に1例だけだが、太陽の端からその直径の2倍以内にある星をとらえることに成功した。このデータから算出された星のズレの値は2.24であった。他の観測ではこれほど太陽に近い星をとらえることはできなかったが、それぞれ観測データから計算が行われた。その結果はいずれもアインシュタインの予測よりも大きい値となった。つまり1952年の時点では、太陽の重力によって生ずる星のズレの値に関する決定的なデータはなく、むしろアインシュタインの予測よりもずっと高い値が算出されていたのである。しかし、当時これらのデータによって一般相対性理論には疑義があると主張されたわけではなかった。
(窪田註:以下、再びS氏のホームページから引用します。)
以上を読んで、読者はどう思われたでしょうか?
これが、一般相対論を立証した!とされる実験の姿だったのです。怒りをこえて、言葉も出ませんが、皆様も同じではないでしょうか。
<ヘイフリーとキーティングの実験は捏造だった!>で、飛行機に原子時計を積んで時間遅れを見た実験のデータが捏造されたものであったことを指摘しましたが、エディントンでも同様のことが行われていたのです。
本の著者に関して少し書きます。原著者のハリー・コリンズ教授は(Harry Collins)は、英国バース大学科学史研究センターの所長を務める社会学者であり、共著者のトレバー・ピンチ(Trevor Pinch)は、米国コーネル大学科学技術研究学科の准教授を務めています。(訳者あとがき参照)
この二人の著者はなまじ専門が物理学でないだけに、かえって冷静で公平なものの見方ができるのではないかと思います。物理学者ではここまで書けないでしょうから。(日本語本の出版は1997年)
この本は本当に面白く、今回紹介した後にも興味深い驚くべき記述が続きます。そして、最後に「相対性理論が本当の真理であると断定する確実な証拠というものは存在しないのである。・・・」と書かれています。
“真実は地中に眠っている”といえるのかもしれません。
冒頭で述べた通り、この本は科学の7つの項目を扱っています。
相対性理論以外で私が全部読んだのは、ファイルⅦ「太陽ニュートリノの謎」です。これもたいへん面白かった。(現在でも未解決のこの大問題は、私も気になっている問題ですから)
巨大な資金をつぎ込んだ実験なのに、理論とはまったく違う結果がでる異常事態。いくら実験方法を再検討してみても、実験に問題なし。理論どおりに結果がでない理論物理学者バコールの焦りと苦悩(計算予想よりも実際に太陽から飛来するニュートリノの数が少なすぎるということ)。
そして再計算しては、すこしずつ予測値を下げて“理論を正しいとしてしまう”バコールへの同僚からの批判。ファインマンの言葉等々。
これらを読むと、科学とはなにか?を再考させられます。
この「七つの科学事件ファイル 科学論争の顛末」(H・コリンズ + T・ピンチ著,福岡伸一訳、化学同人)は、本当に素晴らしく、いろいろと考えさせてくれる名著であり、科学を志す若者は必読の書であろうと思います。
やや古いので絶版となっている可能性もありますが、その場合は再版されればうれしいです。
--------------------------------------------------------------------------------
2006/9/30追加 <アインシュタイン、特殊相対論を横取りする>
K先生に勧められ、
①「アインシュタイン、特殊相対論を横取りする」(ジャン・ラディック著、深川洋一訳、丸善)を読んだので、少しですが感想を述べます。
じつは、
②「アインシュタイン相対性理論の誕生」(安孫子誠也著、講談社現代新書)という本をかなり前に読んでいて、アインシュタインがポアンカレ説を横取りしたことはほぼ確信していましたが、今回①を読んで、それは間違いないことだと再確認しました。
①は、ポアンカレがアインシュタインより前に特殊相対論を打ち立てていて、アインシュタインが実際それをヒントにして(いやほとんど丸写し!)相対性理論を作ったにもかかわらず、論文では、一切ポアンカレ説には言及せず、また有名になった後も、ポアンカレには全く触れようともしなかった、そして相対論は自らの発案であるかのごとく振る舞いつづけた20世紀最大のペテン師・アインシュタインを批判した内容となっています。
--------------------------------------------------------------------------------
2007/6/14追加 <130億光年先のクェーサー?>
ネットの天文ニュースに、「観測史上最遠のクエーサーを発見」との情報が出ました。これを見ると「さすが、現代の天文学は進歩したな」と感心して終わりが普通かと思いますが、しかし、ここには一筋縄ではいかない大きな謎が隠されています。
じつはクェーサーという天体はいまもって全くその正体がわかっていない謎の天体なのです。
「クェーサーは太陽の1兆~10兆個分という異常な明るさをもっており、非常な遠方(約100億光年先!)にしか存在しないという摩訶不思議な天体である」とされています。(①)
クェーサーは1963年第一号発見から現在までに10万個以上発見されています。100個や200個ならまだしも10万個以上ですよ!
たいへん奇妙なことに、そのほとんどが80億光年~120億光年という超遠方に集中して存在しているとされています。我々の銀河系の近くには全くない、つまり宇宙誕生の初期にだけでき、ある時から忽然と姿を消して、いま現在人類が観測しているというわけ。なにかおかしくないでしょうか?
クェーサーを解説した標準的な本でも、仮説につぐ仮説で非常に苦しい説明をしています。誰が読んでも、おかしいと思うにちがいない解説がなされています。
私は以前よりこの奇妙なクェーサーが気になって仕方がありませんでした。なぜこんなに奇妙なことになるのか?
その原因はクェーサーの異常な赤方偏移にあります。遠方の星からくる光の波長が長波長側(赤い方)にずれる現象を赤方偏移をいいますが(水素やヘリウム原子などいろいろなスペクトル輝線がずれる)、そのずれ方がクェーサーは極端に大きいのです。(赤方偏移値Z=約1.5~5.5と異常に大きい!計算にはローレンツ因子を使っている!))
その異常な赤方偏移を、現代アインシュタイン宇宙論ではクェーサーは遠方にあり、ビッグバンによって超高速で遠ざかっているからだ!一般相対性理論によって時間と空間が伸びているからだ!相対論的ドップラーシフトしているからだ!として計算しているため、どうしても①の奇妙な結論にならざるを得ないわけです。
しかし、その原因が、もしアインシュタイン宇宙とは無関係なことによるとしたらどうなるでしょうか?その可能性はないのでしょうか?
もし、赤方偏移の原因がアインシュタインの相対論的宇宙論によるものでなかったら、上記①のような奇妙なことにはなりません。たとえば窪田登司氏の提唱している「量子エネルギー効果」
が宇宙論で検討されるような事になればどうでしょう。この場合は同時にビッグバン仮説も崩壊します。
以上、杉岡氏のホームページから引用させて戴きました。
―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
目次のあるトップページは こちら このサイトだけは、何はともあれ読破して頂きたく存じます
|