|
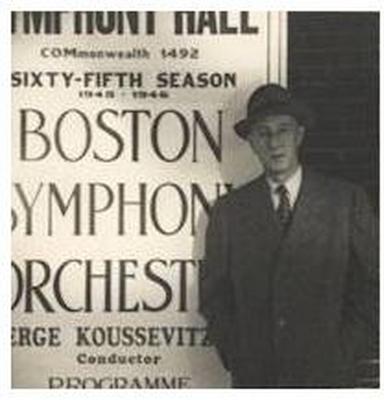 |
||
|
■ 序 章 ■ 「いま私の生活は“第6交響曲”に捧げられています。“交響的幻想”・・・何と豊かな世界でしょう。もう50年生きられるなら、私はマルチヌーの全作品を演奏したい」。これはかつて名指揮者ロジェストヴェンスキーが語った言葉である。 |
|||
|
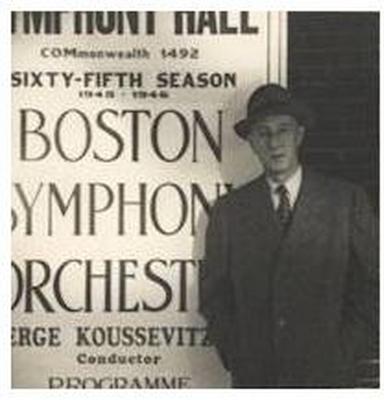 |
||
|
■ 序 章 ■ 「いま私の生活は“第6交響曲”に捧げられています。“交響的幻想”・・・何と豊かな世界でしょう。もう50年生きられるなら、私はマルチヌーの全作品を演奏したい」。これはかつて名指揮者ロジェストヴェンスキーが語った言葉である。 |
|||
![]()
マルチヌーの生涯
1)チェコ時代:
モラヴィアの中心都市ブルノの北々西60キロに、人口1万たらずの町ポリチカがある。由緒あるこの町は1845年の大火で多くの建物が消失した。再建された聖ヤコブ教会の鐘楼内に靴屋のF・マルチヌー一夫妻が移り住み、火災の監視にあたったのは1889年9月だった。翌1890年12月8日、聖母マリア祝日の鐘の音の響く中で男の子が産まれ、ボフスラフ・ヤンと命名された。
ボフシュ少年の音楽の素地を養ったのは、歌の好きな母親と民謡歌いの同居の靴職人、それに週3回ヴァイオリンを教えてくれた仕立屋だった。やがて土地の弦楽四重奏団に加わり、12歳ですでに弦楽四重奏曲を書いている。ヴァイオリン演奏の才が認められ、篤志家の援助でプラハ音楽院に入る。
しかし音楽院のカリキュラムには不満で、1910年に放校された。第1次世界大戦中は故郷の小学校で教え、1917年に音楽院時代の親友S・ノヴァークの仲介でチェコ・フィルの第2ヴァイオリンに席を占めた。祖国が独立した翌1919年1月のカンタータ「チェコ狂詩曲」初演で、作曲家としての第一歩を踏み出す。その春、国民劇場オーケストラの国外公演に加わり、とくにパリに魅せられた。その後ターリヒの指揮下で研鑽を踏みながら、図書館で印象派の作品を研究し、1922年には短期間スークに作曲を学んだ。
2)パリ時代:
1923年秋、奨学金を得てパリに遊学、ルーセルに対位法を学ぶ。1920年代は「六人組」やストラヴィンスキー、ジャズのイディオムをとり入れた作品を書いていた。26年秋にサーカスで知り合ったお針子のシャルロットと、31年春に結婚。30年代に入りるとブルノ音楽院からの招聘も断り作曲に専念、作風はバロック形式のものとなり、題材に故郷のフォークロアを用いるようになる。夏やクリスマスはいつも故郷で過ごしていたが、1938年9月末、屈辱的な「ミュンヘン協定」が結ばれてからは、二度と故郷の土を踏むことはなかった。ナチスの軍靴が響き渡ると、義勇軍に志願するが容れられず、代わりに「戦場のミサ」を書いた。9ヶ月にわたる苦しい逃避行の末、1941年3月新世界の地を踏んだ。
3)アメリカ時代:
以後12年間のアメリカ滞在中は、主としてニューヨークに居を構え、最も充実した創作に集中していた。1945年祖国は解放されるが、故郷からの第1信は、母と親友S・ノヴァークの死を伝えていた。プラハ音楽院から作曲科教授就任の依頼が来たが、同意の電報にその後、何の反応もなかった。マルチヌー夫妻は46年6月にパリへ戻る予定だったが、出発1週間前にクーセヴィツキーから、バークシャイア夏季講習の講師を依頼されたので、6月10日夫人だけがパリに向かい、彼は講習が終わり次第パリに飛ぶつもりだった。7月1日からバークシャイア講習の一部である、バーリントン学校で午前中8人の生徒を教え、午後に学生たちはバスでタングルウッドのコンサートに出かけ、マルチヌーも週に2回顔を出していた。だがその最中に誤って宿舎のバルコニーから転落、1ヶ月以上も入院した。その後も頭痛、耳鳴、難聴、書痙などの後遺症のため仕事もできなかった。受傷後はプリンストン大学などで教え、作風は軽快なものとなっている。48年2月末、祖国に共産政権が誕生し、3月には旧知で音楽にも造詣の深かった外務大臣ヤン・マサリク自殺(本当は他殺)の報に接し、帰国を断念した。
4)西欧時代:
1948年夏から3度ほどヨーロッパを訪れ、53年5月に旧世界へ戻った。ニース、ローマ、シェーネンベルクなどで過ごし、数多くの交響作品、各種協奏曲、ピアノ・ソナタ、カンタータ、「ギリシャ受難劇」などのオペラなどを書いたが、作風は新印象主義の色彩を帯びている。
58年11月に胃の手術を受けたが、手遅れの癌だった。小康を保った翌59年春には「イザヤの予言」やオルガン曲「徹夜祷」などを書いたが、8月28日夕刻、スイスはリースタルの病院で息をひき取った。子供がいなかったマ夫妻は生涯自分の家を持たず、ホテルや知人の別荘を渡り歩いていた。
「作曲家は幸せだ。音楽によって精神的帰郷ができるから」と言っていた彼の手もとには、ポリチカの写真と、少年時代のナイフが残されていた。1979年8月27日、彼の遺灰が20年ぶりに故郷に戻った。ティル劇場で慰霊祭が行われ、パーレニーチェクが追悼の辞の述べ、ノイマン指揮のチェコ・フィルが交響曲6番と、カンタータ「泉開き」を演奏した。前年に亡くなったシャルロット夫人や、兄姉の名前が記された墓石には、ボフスラフの名が加えられ、「泉開き」の中の”われ故郷にあり Jsem doma”の2字が刻まれた。
* * *
マルチヌーの作品には依頼作品が多いが、彼自身は室内楽の作曲に憩いを求めていた。影響を受けた作曲家としてはモーレイ、コレッリ、ドビュッシー、ストラヴィンスキーらがあげられ、作風はロマン派の和声と断片旋律、多調性、ピアノを含む色彩豊かなオーケストレーションを駆使し、変ロ長調、2度3度音程反復(トレモロ)、シンコペーションの多用、変拍子を好んだ。「音楽は美しくあらねばならぬ」がモットーの彼の作品は、心情を赤裸々に吐露したものである。
彼の作品には、オーケストラ曲約50、5曲のピアノ協奏曲を含む各種協奏曲約30、7曲の弦楽四重奏曲を含む室内楽約90曲、ピアノなど鍵盤楽器作品約100、歌曲集を含む声楽曲約90、合唱曲10数曲、カンタータ11、各16本づつのオペラと、バレエの他に、メロドラマや映画音楽などがあり、その数は400を越える。
H.はベルギーの音楽学者H・ハルプライヒ(1931年生)による作品整理番号。
![]()
マルチヌーの交響曲概観
マルチヌーは1913年から14年にかけ故郷のポリチカで、ドビュッシー的色彩を放つ後期ロマン風の「1楽章の交響曲」H.90(約9分)書いているが、実際に交響曲といえる作品に手を染めたのは、実に50歳になってからだった。それらは1942年から46年まで、毎年1曲づつのペースで第5番まで書かれていったが、46年夏の事故で中断してしまう。したがって第6番の完成はづっと後の1953年に持ち越された。
ハルプライヒは各交響曲を、1番:叙事詩的、2番:牧歌的、3番:悲劇的、4番:叙情的、5番:明暗交錯、6番:幻想的と特徴づけており、「楽章数」は、1, 2, 4番は4楽章, 3, 5, 6番は3楽章からなっている。
第4番は楽しげな音色、色彩豊かのオーケストレーション、バランスのとれた形式ゆえに、演奏される機会がもっとも多い。第3番がドヴォルジャークの「レクイエム」冒頭主題の引用であるロ・ハ・嬰イ・ロ音型で終り、第6番がヘ・嬰ト・ホ・ヘ音型で始まるので、「第6番は第3番の終った時点から始まる」といわれるように、各曲の随所にキリエ主題が引用されているのも特徴の一つである。
「楽器編成」は、木管は2, 3番で3332、 1, 5番で3333、6番で4333、4番で4432。金管はすべて4331、打楽器は全6曲にティンパニ、バス・ドラム、シンバル、サイド・ドラム、トライアングル、タムタム、1番と6番にタンバリン。ピアノは6番以外にあり、ハープは4番以降には含まれない。他に弦。
「演奏時間」は、最長が約35分の1番、最短は約25分の2番で、それ以外は30分前後となっている。
「本邦初演」は以下の順で行われてきた。
5番:1953年10月 8日、上田仁、東京SO
4番:1975年 5月14日、サワリッシ、NHK.SO
6番:1975年12月10日、ビエロフラーヴェク、日本フィル
1番:1979年 5月25日、ビエロフラーヴェク、日本フィル
3番;1984年 7月17日、イーレク、読売SO
2番:1998年11月21日、ヤルヴィ、デトロイトSO(豊田市)