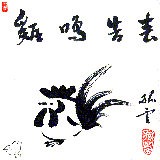 長嶋山妙興報恩禅寺と号す。尾張に杉田(過ぎた)の妙興寺とも称されている。本尊は如意輪観世音菩薩・釈迦牟尼如来。
長嶋山妙興報恩禅寺と号す。尾張に杉田(過ぎた)の妙興寺とも称されている。本尊は如意輪観世音菩薩・釈迦牟尼如来。 禅宗五家七宗の一つ。臨済宗は黄檗希運[断際禅師]の弟子臨済義玄[臨済慧照禅師]を宗祖とする。その法系はすこぶる栄え、我が国では建久2年(1191)明庵栄西[千光国師]によって開立された。栄西は最初比叡山において天台学を学んだが、文治3年(1187)再度の入宋の結果、臨済の禅風をもたらし、博多に聖福寺、京都に建仁寺を建立したのに始まる。
臨済宗妙心寺派の大本山、山号は正法山。本尊は釈迦如来。開山は大徳寺開山宗峰妙超の法嗣(師家から正しい仏法を受け継いだ者。)関山慧玄、開基は花園法皇。法皇は関山と同じく宗峰に参禅、印可(師家が修行者の悟りの状態を認め、修行が完成したことを証明すること。)を受けていた。建武四年、重篤となった宗峰は法皇の新しい参禅の師として関山を推薦、この時法皇は自らの離宮を禅寺に改め、関山を開山として迎えた。これが妙心寺である。室町時代には林下の寺として、大徳寺とともに五山十刹の制度に属さない独自の立場を貫いたため、幕府より政治的圧力が加えられ、さらに応永・応仁の乱の戦火によって一時は存亡の危機に直面したが、朝廷・織田・豊臣・徳川等有力者の帰依を受け復興、江戸時代になると大いに禅風を挙揚した。
江戸時代に伝えられた応燈関一流(南浦紹明[大応国師]―宗峰妙超[大燈国師]―関山慧玄[無相大師])の禅からは江戸時代に白隠慧鶴(1685〜1768)が出、その系統は現在の、臨済宗十四派の法系上の源流となっている。
創建開祖は妙心寺二十五世大休宗休。勧請開祖は十二世特芳禅傑。大永六年、大休が帰依者模堂清範尼の支援を得て、師特芳を請じて開創された。天文十二年にいたり大休は栂尾阿伽井房を移して方丈とし、隣接して書院を創建した。現書院は当時のもので、この御幸の間は御奈良天皇の臨幸に使われた建物でもあり、重文に指定されている。方丈は元禄六年の大休百五十年遠諱の時に改築されている。狩野元信筆の障壁画、「御奈良天皇宸翰円満本光国師号勅書」(いずれも重文)を擁することでも著名である。書院南の縮小式蓬莱枯山水は子建西堂の築庭で、史跡、名勝に指定されている。
清見原天皇(第四十代・天武天皇)の御世である白鳳年間(七世紀後半)に、清見ヶ関の鎮護の寺として、天台宗の寺院として建立された。その後、荒廃していたのを寛元元年に円爾弁円の法嗣(師家から正しい仏法を受け継いだ者。)関聖禅師(無伝聖禅)が清見長者の帰依によって再建し禅寺とした。
庭園が国の名勝に指定され、境内全域が朝鮮通信使遺跡として国の史跡指定を受けている。その他、数々の歴史資料を有する文化財の宝庫でもある。俗に「きよみでら」ともいわれる。
松島寺ともいう。青竜山瑞巌円福禅寺と号す。本尊は聖観音。もとは慈覚大師円仁を開基とし、天長五年に創建された天台寺院であったが、後に執権北条時頼が法身性西禅師のために再興、臨済寺院に改宗した。慶長年間、仙台藩主伊達政宗は海晏に要請して住職とし、伊達家の廟所とした。
瑞巌寺の名の由来は凝灰岩が寺の周囲を囲っていることによる。また、伽藍は安土桃山建築の代表作の一つであり国宝に指定されている。
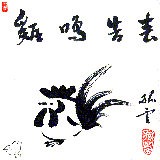 長嶋山妙興報恩禅寺と号す。尾張に杉田(過ぎた)の妙興寺とも称されている。本尊は如意輪観世音菩薩・釈迦牟尼如来。
長嶋山妙興報恩禅寺と号す。尾張に杉田(過ぎた)の妙興寺とも称されている。本尊は如意輪観世音菩薩・釈迦牟尼如来。
創建は貞和四年、尾張中島城主中島蔵人の第二子滅宗宗興禅師により勅願の道場として建立され、勧請開山として南浦紹明禅師[円通大応国師]を迎えている。
滅宗宗興禅師の在世中は衆僧常在二百余名が集まり、一大叢林になり、文和二年足利二代将軍義詮は祈願所とし、後光厳天皇から「國中無双禅刹」の勅額を賜わり、法幢は隆昌を極めた。