江戸時代の賄賂、役得などの習慣、感覚は現在のそれとは全く異なるものであった。
町与力の収入を調べると与力の家計で述べたように、本来の禄高に匹敵するくらいの収入が「諸家からの中元、歳暮、役頼」などで見積もられている。 これらの収入は決して賄賂ではなく「役得」とみなされていた。
賄賂はこの時代でも悪いものという観念があり、場合によっては身を滅ぼすもとにもなったが役得は公然と認められていた、というのが実情であろう。
しかし賄賂と役得、それに時候の挨拶に事寄せた贈り物の境界線はいつの時代も曖昧である。
このページでは江戸時代の賄賂と役得について考える。 また五郎左衛門に関わりのあった人たちの賄賂と役得についても調べる。
与力の役得 注)管理人が一部現代語に改めた。
|
与カ同心の役得・収賄ー元南町奉行所与力佐久間長敬の談話ー
問 与力内輪の役徳は如何?
答 役得が多いのは年番方、吟味方、市中取締諸色懸りの三役で、これらの役を勤めるものは老分重役である。その他、吟味方助役、市中取締諸色懸り手伝いを兼ねる者も役得が多い。
これ等の役々は町奉行所の重立った威権ある役柄なので、徳川御三家はじめ諸大名、上野寛永寺、芝増上寺の両山、両番頭、浅草の浅草寺に至るまで、町方に関係ある向々は御用願と称して、年始・暑寒・盆暮の贈りもの(上等白銀五十枚より下等金二百疋)、国産の織物、その他御土産、諸大名参勤交代の節も将軍家へ献上物余り配分と称し国産物、或は目録を送って来る。
老若その他の重役といえども役柄にかかわらず同様に送って来る。
この由来は、先祖以来の習慣で、その始めは奉行へ届け、老中まで内証文黙許を受ているのでしかるべき使者をもって玄関に持ち参り、取次の者は受取書を渡す。 この御用頼と称する者たちは願事について彼是不正を謀ろうとするものではなく、公務をスムーズに運ぼうとするためであるので、公務の余暇に願人から頼まれた事を処理する。贈答される目録・物品は山のように積み上げられるが、これについて尋問があっても答弁に苦しむことなく、良心に問ふに一つとして成規に背き、不正と思ふことなく、他より非難を受たることはない。
問 役徳の外に不正の役徳は如何
答 不正の役徳を得ることは色々あるが、その二、三を示す。年来の習慣で仲間にても敢て論ずるものなく、只々そのような役に昇進することを望むだけである。 無事に役得を得る仕方の例を二、三示す。
其一、老年与カに進み、いくつもの役を兼務する者は様々の名目をもって御三家ならびに諸大名より扶持米を受る。 多い人は二十人扶持、少ない人でも五人扶持くらいを受け取る。数十人扶持を受るひとかどの役徳であるが、仲間でかれこれ云うものはない。
其二、諸大名の勝手方より依頼で、金銀貸借の斡旋をして謝礼を受ける。
その一例を示すと、ある大名甲何某、町人より数千両を貸りているが、返済が滞っており、期限になって督促を受けて困難している。 こうした時に借り替え、あるいは融通の依頼を受ける。 与力は資産家を2、3人呼び寄せ、貸借の周旋をし、貸し主何某(乙)と出金者を決め、先きの貸主何某(甲)を呼び寄せ、元利精算させ、あるいは書き替え利息の分の何割かは切り捨てさせ、古い借金を清算し、新貸し主乙・丙両人より融通させる。このように処理する時は、いづれも不利益になることがなく、双方喜んでその取扱を謝し、相当の礼金を得ることになる。
其三、諸藩の国産ものを江戸蔵屋敷へ積み込む時、問屋を呼び入札払をさせようとする際、入札人が馴合い、安値に払下げようとする気配がある時は、入札を止め置き、共藩の国産掛役人より諸色懸り町与力へ願い来る時は、何か口実を設け、先例を添えて其筋の商人へ名指しで落札させる許可を請ふ。この願書の立案より手続を教へ、其諸藩より月番御老中へ提出させ、町奉行へ渡り、更に奉行より与力の手に入る。 そして直に許可の付箋をして返却する。
其筋の問屋の内、希望する人へ許可の時を経て、其藩の国産懸と謀り、名指し払渡し、利益を与える。 故に売買双方より相当の謝礼を受ることになる。公然と御老中より許可することなれば、商人仲間は勿論、他より云々申者なし。
其四、また御三家始め、宮門跡方にて様々な名目を唱へ、江戸町人或は武家へも貸付金あり。この返済が延滞した時、取立方の手におよひ難く、説諭を依頼することになる。其節は奉行所へ依頼するが、これは民事訴訟の取扱懸、則ち只説諭に止るものに付き、奉行は口出しせず、年番与カヘ渡して説諭させるのみである。与力は説諭の上、金額の取立を為して貸主へ渡すなり。貸方は手数料として取立のおよそ一割を自明に目録に直し、別の時み気侯見舞として、公然と表向より送って来る。与力は事柄故謹んで受納す。何方よりも云々申すものはない。
このように役徳があり、年分に相応の所得があるので、公事裁判においては賄賂を得ることは危いもの故よくよく慎み、成るべく謝絶して嫌疑を受けない様に注意する。
吟味役は与力の最上役であり、前々述べてように、其の地位が進めば多くの役徳あるので、右の外他事は公平潔白を以って名を顕はさんと心掛るものである。
|
|
問 同心役徳は如何
答 同心は分担の役儀により、役徳の多きは探索捕亡の三廻り役を以って第一とする。其他は吟味方下役である。大名からの御用頼と唱へ、送り物を受る事、与カの金額ほどではないが、各用弁によって増減あるが必ず役徳がある。 三廻りなどには町人の内重立ったものの多くが依頼し、居宅へも招き、奉公人の引負、其外取逃ものの取締を頼み、或は町々を見廻り、悪徒防ぎをして盗犯等ある時はこれを告げて捕縛を願う。
三廻りは町人と交際多いので種々の事件を認出、悪徒の召捕事も多く、御用弁のものとなり、随分役徳多きものである。
問 同心役徳の外に不正の役徳をとるや
答 不正役徳は秘密の悪事なれば、様々仕方があったが公然の不正に現われた其一、二のことを述べる。
其一、与力と同じく諸家より扶持方を受ることなり。
其二、岡引・目明しを使い、捕亡探索之事を命じ、法律を犯すものなり。袖の下を受ることあり。
其二、遊廓にて金遣いの荒い若者などを捕へ、自身番屋に連れて行き、金の出道を糺す。其者不正はないけれども、親懸り、又は主人持なのではなはだ恐縮して、様々に袖の下を送り、放免を乞ふ。然る時これ放免するなり。
其四、役威を以って人々の内事に干渉して周旋料を得ること。
其五、市中にて侍・小者など酒犯の上で立騒ぐものを取押へ、自身番屋へ預け置き、酔醒の後は恐れ入り、内分の所置の乞ふものを許し、謝礼を受ることなり。
問 聴訴に付、主任与力の不正は如何
答 聴訴に付、主任与力賄賂を受ることは甚た危く、尤忌み揮るなり。然とも曲者は必ず役人へ手を入、勝を得るか、或は曲直事にせんと欲するは人情なれば、手続を求めて申込み来るなり。若しこれを採用して、少し直者の方負色になる時は、直者も同しく手を入、賄賂を送りこれを防かんとして、権威ある役人か上向より手を入れ来る。終に主任掛り板はさみと相成、甚窮するなり。其時は突然奉行の再席にて裁決せしむることされども、仕損ずる時は甚手あまるなり。仲には双方よりうらみを受、様々と流言なといたし、役儀にも拘り侯程の不体裁を引起し侯故に、先づは大事に構へて、前に陳たる役徳にて充分として、聴訴事に付ては、専ら公平を旨として、彼れは賄賂を受けざる役人故、証拠と公平の議論にて争ひ、勝利得るより外なしと、町々の評判を得ること尤得策と心がけするなり。
若し手腕の利きたる裁判役は、随分左の二つの手段を以、人口にかからざる様に賄賂をむさぼりとる者あり。
其一は、直者より賄賂を得んと謀るなり。其手段は、始め原被の申口を尋問するに、是非曲直を本人に知らしめずして、能く証拠を糺し、十分に裁決の見込を付、直者を腹中にて定め置、彼れ十分理屈あれは、勝公事に捌き当然と見込者を、様々と難問を起し責め立るなり。斯する時は、曲者は却て油断し、我勝利か、或は曲直半に至らんと思ひ、様々と弁するなり。直者は大に驚き、負公事にならんことを恐れて手を入、賄賂を送るなり。充分に賄賂を受て後ち、弥決着の目に至り、俄に証拠・証跡を揃へ、曲者を責め、少しも弁護するの猶予を与へず、押詰る時は素より曲者のことなれは、;冒の申披きにも詰り、無余儀熟談済口を出すか、或は裁許を受るなり。
後にて曲者彼是申も、証拠の上にて曲なる故に、役人の取捌き不正と申者なし。勝利を得たるものも、賄賂は秘密のことなれば口外することなく、満足して無事済むなり。
其二、原被曲直半して、いづれにも勝敗の就くべき見込ある時は、双方の非分を厳敷難問して、原被両告をして勝敗の望を思に迷惑せしめい其時は必す双方より賄賂を送るなり。其時双方の非分を折衷して和解せしむるか、或は裁許する時は双方とも不充分ながらも、丸損になるよりもよろしとして承服するなり。手腕の利たる裁判役の賄賂は人口にかからず事済なり。
|
「江戸の情報屋」に紹介されているお救い米事件
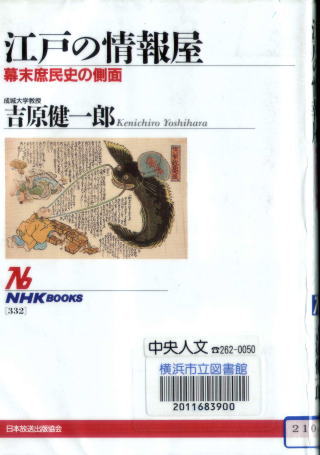 ここでいう江戸の情報屋とは、このホームページでも何回か引用・紹介している「藤岡屋日記」 ここでいう江戸の情報屋とは、このホームページでも何回か引用・紹介している「藤岡屋日記」
を発行した藤岡屋のこと。
上州藤岡出身の由蔵が、外神田の御成道(秋葉原駅の西側)に古本屋を開き、その傍ら、江戸城内の出来事、江戸市中の出来事を細大もらさず日記に書き留めていた。この日記が各役所や商家から大名家にいたるまであらゆるところで手軽に得られる「情報」として重宝され、後には「藤岡屋日記」という名前でその当時の世相を記す史書としても尊ばれるようになった。
仁杉五郎左衛門もお救い米事件に関連して、藤岡屋日記には何回も登場している。
NHKブックスの「江戸の情報屋」は、この藤岡屋日記の記事をもとに、江戸末期の庶民史あるいは民衆史を描いたもので、この中に汚職事件のひとつとして御救い米事件が取上げられている。
汚職事件のかずかず
米価の上昇にともなう庶民生活の困窮は、江戸だけでばなく、商品経済の浸透によって、日雇いなどその日暮らしをしている民衆が生みだされていた地方の農村や都市でも同様であった。天保7年(1836)だけをとっても、仙台藩の陸前渡波町では4月に打ちこわしがおき、6月には加賀の金沢町、信濃の飯田町など、7月には越前勝山町など8ヶ所、8月には駿河の駿府町(現静岡市)や甲斐の都留・山梨郡など8ヶ所、9月には大坂というように夏から秋にかけて、全国各地で打ちこわしや暴動がおきている((青木虹二『百姓一揆の年次的研究』新生杜)。このほか、この時期の都市における不穏な状態は、すべて米価高騰によるものだといえよう。
このような幕府政治の危機的状況のもとで、江戸では幕府の吏僚や商人たちが大汚職事件をおこした。不正の第一は市中救米に関するものであった。町奉行所与カや町年寄が米屋と結び、米間屋仲買が高価格で売買した取引高の手数料のうち一部を積み立て、これを町人の立替金にあてるという方法を実行せず、元来、積立金は米屋の自発的行為であったとして取り立てを猶予したというのである。
そればかりか、救米取り扱い懸りの与力であった仁杉五郎左衛門は買付米勘定帳面の不正報告を行なっている。たとえば、深川の米問屋が越後米買付に出張したさいの遊興費の一部を請求したり、さらに東国米問屋からの買付米を、実際に受け取っていないものを売り払ったように見せかけで一部を横領している。
ただし、この事件が発覚するのは後になってからであった。天保12年(1841)6月、南町奉行矢部左近将監(駿河守)定謙の役宅で、同心の佐久間伝蔵が同僚の堀口貞五郎を殺害し、おなじく高木平治兵衛に手疵をおわせて切腹した。伝蔵は堀江口貞五郎の父六郎左衛門らが、当時の不正の責任を伝蔵に押しつけていたため刃傷におよんだという。この結果、仁杉と堀口六郎左衛門、高木の3名をはじめ、町方御用達の仙波太郎兵衛、永岡義兵衛、内藤佐助らは入牢になった。
翌13年3月処分が発表され、仁杉は死罪(すでに死亡)、倅鹿之助と養子清之助は遠島、堀口は中追放(すでに死亡)となり、連座するもの50名におよんだ。町年寄喜多村彦右衛門は押込、手代6名は手鎖、仙波.長岡・内藤らは押込、東国米問屋12名は江戸払いなどの厳罰が加えられた。
さらに矢部定謙は事件当時町奉行ではなく勘定奉行であったが、内々に事情調査をしていながら、事件発覚後はもみ消しにまわったとして改易(断絶)になった。また事件当時の町奉行筒井政憲は謹慎を命ぜられた。
不正の第二は、水油(燈油)に関連してのものであった。7年12月上旬には市中に水油がいっさい出回らず、魚油ばかりとなった。勘定奉行矢部定謙の吟味により、油問屋、町奉行所与カが入牢し、その直後には無かったはずの水油が市販されている。調査の結果、水油の買い占めや、油に混物がなされていたこと、与力同心は賄路を貰って見逃していたことなどが発覚した。翌8年3月13日の処分では、与力谷村猪十郎の重追放をはじめ、関係者多数が罰をうけている。
この処分が発表された8年の春は、米不足が最高潮に達していだ。すでに幕府は正月の町触で髪結賃28文を26文、湯銭10文を8−9文、そぱ28文を15文にすべしとの値下令を出していた。2月初旬になると救小屋に入るもの1万人を越え、死者は千人以上という状況であった。
「非人、もの貰い、道路に死する者多し」といわれ、3月6日には江戸に流入する貧民対策として、品川・板橋・千住・内藤新宿に救小屋を設置するとの町触がだされ、打ちこわしを未然に防止するための宣伝が行なわれた。
米は高値を更新し、前年の暮に1両で3斗5升買えたのが、3月には1斗8升から2斗2升程度しか買えなくなっており、「毎日毎日相場不定」というありさまであった。中旬以後は表向き100文に4合5勺となっていたが、実際には3合5勺、ないし2合5勺しか買えなかった。しかも中心部の救小屋は希望者をさばけず取り払いとなり、4月1日からは名主の発行する切手によって春米屋から米を受け取るという方法に変更せざるをえなくなっている。しかし、「かくの如く困窮に侯得共、此節芝居は両座共大入にて」、大繁昌という現象も生じている。庶民の不満が芝居見物という形で発散されていると考えられる。
江戸時代の賄賂
江戸時代に限らず、わが国では(外国も同じだろうが)つい近年まで賄賂、付け届けなどは社会の慣習としてごく一般的であった。それがたとえ職権あるいは役得と考えられる場合であってもである。
五郎左衛門は天保飢饉の際のお救い米買い付け事件に連座して、投獄され牢死を遂げたが、追い打つように死後3ヶ月後に「存命ならば死罪」という苛酷な判決を受けた。
この判決で与力仁杉家は断絶、長男、次男も遠島処分となった。
五郎左衛門が問われた罪は、当時の社会通念ではごく当たり前の付け届けあるいは役得と考えられ、上司の町奉行も黙認していた。 しかし幕閣の中の権力争い、ポスト争いの材料としてその賄賂性が大きく取り上げられ、本人も周囲も思いもしなかった重罪に問われるこのになった。
そこで「五郎左衛門の犯罪」を検証するために、天保当時の賄賂の実態について調べて見た。江戸時代の賄賂については文献も多いが、ここでは下記の文献2件から引用して、天保時代の賄賂の実態を紹介する。
出るは出るは、この事件にかかわる幕閣の主要人物のほとんどが賄賂漬けだったことがわかった。
江戸の賄賂
童門冬ニ |
江戸時代の賄賂秘史 中瀬勝太郎 |
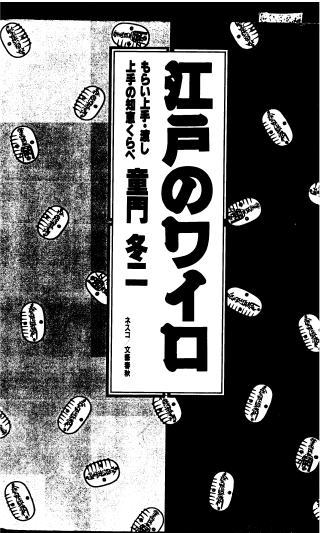 |
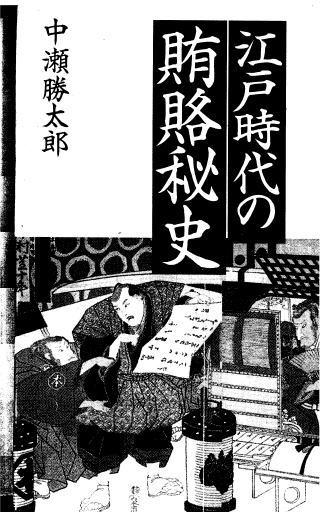 |
町奉行矢部定謙
五郎左衛門が投獄された時の直接の上役。 江戸市民からも評判の良い奉行だったが、「妖怪」と呼ばれた鳥居忠耀の陰謀により、わずか8ヶ月で奉行の地位を追われた。
奉行を罷免された翌年3月には「五郎左衛門への処分が甘かった」などの理由により、お家断絶、桑名藩へのお預けとなり、数ヶ月後には絶食という形で非業の死を遂げた。
一般的には水野越前守忠邦の収賄を露き、その心胆を寒からしめた名町奉行として、精錬潔白のイメージの人だが、町奉行になるまでには相当の賄賂を贈ってその地位を勝ち得たものである。彼の最も親交の厚かった、水戸藩の藤田東湖はその随筆にこんなことを言っている。
「矢部余に謂て日く、某は元来三百俵の御番士より斯くまで立身したるは才カあるに非ず、皆賄賂を以て、致したる事にて、大方の嘲りもあらんと思ふなりと、語れる風情。流石に取飾なし。且つ英雄の気象ある故、彪答て日く、賄賂を以て出身するは之れを誉むべきに非らざれども、茲に一つの説あり、全く自家の腺を貧り、富貴逸楽を希はんとて、賄賂を行ふもあり活淡無為に終身無カのみならず、上の為めに心カを尽す事もなし得ず、さらば少しく道を柾げて当路に出で国家の為めに力を尽し、名をも後世に揚げまほしとて自ら進んで求むる人もあるべし^。此二人は跡同じくして、意異にすと申しければ矢部も欣然として喜びけり」
人の罪悪を摘発し、これを裁くべき任にある裁判官の地位にある町奉行さえ、賄賂により、ようやく位、捷ち得、はじめて天下の裁判権を握りえられた時代であった。
水野越前守の収賄
五郎左衛門が処罰された時の老中首座、いわば首相である。
死罪に相当する判決は、町奉行や武士を管轄する目付で出すことが出来ず、老中の承認が必要であった。従って五郎左衛門処断の最終責任者は水野越前守であった。
この水野越前守も贈賄、収賄まみれの政治家だった。
当時、出羽庄内の酒井家が他に転封せられるという噂が専らであった。酒井家では時の老中水野越前守と太田備後守(遠州掛川の城主)とに各々三千両ずつ贈賄し、転封取止めの運動をおこした。
太田備後守は、即座にこの贈賄を押し返したが、水野の方は当時奥向その他多方面への付け届けや何かで、経費がかさんでいた折柄だったので喜んでこれを受納したという。(有也無也)。このことは時の町奉行矢部駿河守定謙の知るところとなり、暴露されようとしたため、あわてた水野は、直ちに当時の御金御用達の後藤三左衛門に依頼して一時融通してもらい、酒井家に三千両を返却して事なきをえたのである。
矢部は水野が取立てて町奉行にしてやったものだったので、以後大いににらまれついに職を免ぜられて伊勢桑名松平家にお預けということとなった。
彼はこの処分に憤慨し、食を断ってついに死亡したという。一方後藤の方は、水野とは切っても切れない醜い関係が出来、水野の失脚後、幾多の不正がありとして斬罪に処せられたのである。
水野の緊縮弾圧攻策はあらゆる方面に苛酷厳粛に行われた。加えて矢部の後任の町奉行鳥居甲斐守の冷酷苛政ぶりも実に言語に絶するものがあった。
しかしそれは表面上のことで、内面的には、彼も歴代執政者の轍をよくふみ、収賄については相当なものだったのである。当時江戸っ子が彼のために引札として、その施政の一端を誹謗したものを見ると中々面白いことがある。
引札
乍憚書付を以て奉申上侯
一、各様益々御機嫌能く、被遊御座恐悦至極に奉存侯、随而私役向之儀者、以御蔭日増繁昌仕、冥加至極難有仕合奉存候、尚又当十ニ月上旬より、諸品相改下直に売出申候間、不限多小、御用向被仰付被下候様奉願上候、尤其家格に不拘、御用向被仰付候御方は、御外見後外聞共宜敷様、御為第一に相考、御用向精々出精之内、成就仕候様差上申候間御願競被遊可被下候、依之諸品後直段左之通りに御座候
一、金紋御挟箱簑箱共 代金壼万両より
一、虎之皮御鞍覆 代金五千両より
一、御枕鑓井御打物 代金八千両より
一、宰相之御昇進 代金壼万両より
一、中将へ御昇進 代金五千両より
一、大将へ御昇進 代金五千両より
右之通に御座侯
其外侍従、以下御側衆、三奉行者、不及申、諸役に御役付御望之方者、代金思召次第に可相成、出精相働、御役付被成候様仕差上可申候、御大名方御役にても、金銀にて被仰付侯はば如何様六ケ敷御用、格別にて相働き下直に差上可申侯、且又金銀吹替之儀は、元来渡世に御座侯兼々金銀座へ申談し度々吹替之儀為相願申候、右古金者高直に頂戴仕侯、新金は下直に差上申侯間、何卒御用向不限多少無滞被仰可被下侯
遠国へ御差出し被遊侯御方にても、御徳分と相成侯様仕法仕度、別紙御触之通り相違無御座侯間、無遅滞御引替被遊被下侯様呉々も此段偏に奉願上侯恐惶謹言
本国遠州浜松 出張所江戸馬場先御門内
現金掛値なし
西ノ丸下角
水野越前大橡
取次売弘所向島
中野隠居
追て不遠奥州棚倉へ所替仕侯間、無御油断、唯今之内・御用向被仰付可被下侯様奉願上侯以上 (天言筆記巻二)
これによると、越前守もその地位と権威を利用して、以上のような賄賂を取り資格の引上げや売官をしていたことは、想像に難くない。
多少誇大に言っているところはあるが、事実無根のことともいえないのである。
さらにもうひとつ、越前守罪状捨札之写なる、諧謔断罪状がある。
「捨札之写」
遠州無城越前小僧 卯五十五
此者儀、厚き御恩沢を蒙り乍ら之れを忘却致し、私慾を長し其上金銀吹替に付、後藤三右衛門より三千両、長崎表高島四郎太夫より内々頼を請け金六万両にて御咎を免し、札差共より金三万両、弃損被仰出間敷儀を請合、江戸御府内は勿論諸国一同難渋に落し入れ侯段、重々不届至極に付、西丸下引廻之上、於品川重き罪科に行ふもの也』(天言筆記巻四十三)
これによると、さきに庄内酒井家より収賄した三千両を返却するため、後藤三右衛門から三千要借り出したということがあったが、今この捨札の記事を見、丁度あれに符合している処を見ると、高島四郎太夫からの六万両、差札等からの三万両も全くの夢物語りではなさそうに思われるのである。
もうひとつ、次に面自い落し咄しを紹介しよう。
「落し咄し」
比度水野金五郎御任官につき、家老水野泡太郎、御前へ出で申けるは、此度御任官御内意に付、御官名如何被成御願侯哉と御伺ひければ、殿申しけるは、成程をれも色々と考へたが、父の御恩を忘れぬ様にと、大監物と改めませふ。
家老夫れは如何の御思召で御座ります、殿父越前守出頭の時は、国々の大小名が金銀財宝は申すに及はず、珍敷珍物を山の如く権門に致したから夫れで大けん物と附くるのも、今領地減少致されても、何一つ不自由のないといふは、父忠邦沢山に取込まれた故に、其恩を忘れぬ為めさ、まだ一つある、其方も知つての通り、父御役御免の節、屋敷をこわされた時は、大勢群集致して、往来も留まるほど大けん物だ、家老成程夫れは結構な思召、では御座りますれど、父君忠邦侯の思召とは相違致しませう、父君は君の御代までも、金銀を沢山に取込様にとて、金五郎と御附けなされましたから、父君の御名を継いで越前守と成て又又御老中を勤る様に被遊まし。
殿いや越前守と成てまた、かぶらふより、其様な、こわい御役は大けん物だ。
世の人がおぞけふるった越前の、御息子さんと大の監物』 (天言筆記巻四)
越前守の世子金五郎は、弘化三年十二月十六目任官して大監物となったため、こんな落し咄しが流布されたのである。
これは当時の下層杜会に行われた越前守誹謗の落し咄しであるから、これに信を措くことは無論出来ないけれども、こういうものにかえって裏面の真相が伝えられているものも少なくはない。かならずしも看過することが出来ないものであるまいか。
老中太田備中守の収賄
水野忠邦と同時期、老中を勤めていた太田備中守は、前述のように庄内藩からの賄賂をつっかえして男を上げたが、実はこの人も五十歩百歩。欲望の妄念に勝つことは出来ず、阿部能登守より役付の依頼を承け、報酬として能登守所有の深川下屋敷を貰い受けて阿部を奏者番から寺杜奉行に推薦したのである。
能登守の持っていた深川の下屋敷というのは堂々たる天下の名園を持ち、また、建築の結構なること江戸に及ぶものがなかったと言われていたものである。
用心深い備中守は、只でこれを貰い受けたとあっては、後日どんな間題になるかも知れないと考え、これを買い受ける形とした。
しかし時価一万両以上もするこの屋敷をわずか千五百両で買い受けた如くとりつくろい、しかも実際に支払った額はその半分ほどだったという(有也無也)。
水野越前守に対抗して勢カ争いを続けていた備中守も、この事件から越前守の舌頭にかかり、老中を免ぜられて隠居の止むなきにいたった。
越前守は酒井家からの収賄が洩れたのは備中守のせいだとし、極カ彼を嫌って備中守がいつまでも老中でいるならば、自分は老中を被免されたいと将軍に申し出で、逆に彼を葬ったという。
鳥居忠耀の賄賂
この人の金品に対する欲望は松本清張の「天保図録」にも再々描かれている。
省略
上も上なら下も下の収賄、贈賄
奥祐筆組頭等が諸侯より貰う賄賂は非常なものであった。
日光の御修繕、お台場の新設、印旛沼の改修、何川の堤防修築というような大規模な土木工事を起す場合とか、新に御用金を命ずというような場合に、これをどこの大名に命ずるのが適当であるという原案は、老中が作成するのが普通である。
しかし殿様育ちの老中方に諾大名の財政状態などわかるはずもない。
そこで原案は秘書官の地位にある奥祐筆組頭の手になり、老中はこれに盲目判を押すということになる。この手伝いとか御用金と称するものは、一藩の運命を左右するほどのものであったから、各藩は戦々恐々としていた。
このため、各藩は親藩、外様にかかわらず、日ごろから奥祐筆に付け届けをし、大規模な工事や災害修復などの噂があると、その「お手伝い」に指名されないように多額の金品を贈ったという。
このように少なくとも江戸時代、人に何か便宜を受けたり、受けようとすると付け届をするのはごく普通のことであった。
また、役人がその職務が故に金品を受ける収賄も、事実上公認のようになっていた。
例えば、当時既に世界最大の人口となっていた江戸の治安は与力25騎とその下役の同心120人が定員の南北の奉行所が毎月交代で担当していたが、奉行所の任務は治安維持だけでなく、行政一般、裁判など広範囲にわたっていた。
このため、現在の警察力に比べると非常に少ない人数で江戸の治安を維持していたと勘違いしやすいが、実は同心が多数の岡っ引や下っ引きなどの手下を私的に雇い、犯罪の捜査や犯人逮捕に使っていたのである。
同心が充分な俸給をもらっていたかというとそうではなく、幕府役人の中では最低クラスの30俵二人扶持であった。この薄給では自分の家族を養うのが精一杯でとても私的な手下を雇うことは出来ない。
これを可能にしたのが公認の役得であった。
諸大名や旗本は家中でなにか事件などがあると公儀のおとがめを受けて、場合によっては領地の取り上げや改易になってしまう危険がある。
このために日頃から町奉行所の与力や同心に付け届けをしておき、何かあった時には有利な処理や事件そのもののもみ消しを依頼する。
市中の大きな店も同様で、有力な与力や同心には盆暮にはまとまった金子を届ける。
これらの付け届けは堂々と役所に持って来たそうだし、八丁堀の役宅に届ける場合は本人がいないことが多いから、奥方が受取(領収書)まで発行したそうでる。
これらの役得収入が本来の俸禄の何倍ももらえるから、同心が岡っ引などの手下を雇うことが可能となった。
賄賂、役得が江戸の治安を維持するに大きな貢献をしていたことになる。
江戸中期の幕府老中田沼意次は、そのよごれぷりに腹を立てた庶民に、
田や沼や濁れる御世をあらためて清く澄ませ自河の水
と指弾されて追放された。
白河の水というのは掛け言葉であって、白河藩主松平定信をさす。
定信は庶民の輿望をになって田沼に代わるが政界浄化は成功したもののいっこうに景気はよくならない。庶民はまた落首を詠んだ。
白河のあまり清きに耐え濁れる元の田沼恋しき住みかねて
失笑ものだが、しかし「庶民は勝手だ」といい切れないものがある。つまり田沼と松平のどっちが虚で、どっちが実なのかはわからない。しかしこの落首には一種の真実がある。
虚という極、実という極の間に存在する第三の極である。ワイロがけっして肯定されるものではなく、なければないに越したことはない。にもかかわらず絶えない。
|