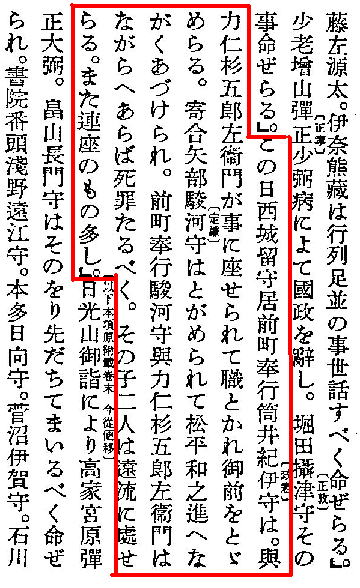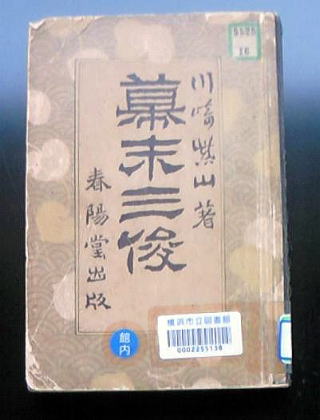| �����\�n�� �@
�@���ɍ������Ă���ܘY���q��̂����ɖ��オ�����\�n�������ł��낤���A���j���V���A���j���V�����߂����邱�ƂɂȂ�������A�����A����͏]�Z��łQ��ڂ̔��E�q��i�K�Y�j���Ƃ߂Ă��̂ƍl������B �@���̓��͑��̎����W�ґ����̏������\���n���ꂽ���A���쒬��s���䐭���A�O�쒬��s��茪�̂Q��̒���s�ւ̔����\�n���������ɍs��ꂽ����A���Ԃ̒��ړx�������A���쒉�M���L�A�V�����H���L�ⓡ�����L�ȂǑ����̎j���ɂ��̔��������c����Ă���B �@������I�̂��̓��̍��ɂ��Ȍ��ł͂��邪�A�E�̂悤�ɋL����Ă���B�@
���j�u������I�v�͖�������ɕҎ[���ꂽ�]�˖��{�̌����L�^�B�@��㏫�R��拍��������āA���ꂼ��̏��R�Ɋւ���L�^���w���Ƌ{����I�x�w�䓿�@�a����I�x�ȂǂƏ̂���B �u������I�v�Ƃ����̂͂������܂Ƃ߂����̂ł���B����ƍN����10�㏫�R�Ǝ��̑�̓V�����܂ł̎��ۂ�����ɋL�q���Ă���B �@�����U�N�i1809�j�ɋN�e�A�Éi�Q�N�i1849�j�Ɏ��̏��R�ƌc�Ɍ�����ꂽ�B���ꂼ��̋L���̏o�T���L����Ă��邽�߁A�]�ˎ����m���{�j���ƂȂ��Ă���B�@�����Ƃ̑�X���Ҏ[���s���A����������������I�Ƃ��ēV���ȍ~�̕Ҏ[�𑱂��A�������N�i1868�j�܂ł��L�q���ďI����Ă���B
�@�ܘY���q��ւ̔������͐��O�Y�i���R�j���u�����O�r�v�̖�x�B�̍��Œm�邱�Ƃ��ł���B �@���́u�����O�r�v�͖����R�O�N�P�P���P�W���ɏt�z�����犧�s���ꂽ�������ꂽ���̂ŁA���݂ł͓��荢��ȋM�d�{�ł���B�@ �@ �@���̑�\�Z�u�����v�Ƃ����͂ɁA���쒉�M�������s�����g���Đi�߂Ă���V�ۂ̉��v�ɑ��Ė�����͓I�łȂ��A����͖���Ƃ��������B�@�����͖��r���Ď��璬��s�̍��ɂ����Ƃ����_��������A��̍ߏ���ł��������A�X�ɕ�s���n�������̓��S���v�ԓ`���̉Ǖw�������̂����ĉ��đi��������Ȃǂ��āA����ׂꂽ���������ڏq������ŁA�ܘY���q��ւ̔��������u�����v�Ƃ����`�ŁA���̑S�����f�ڂ��Ă���B �@�����͕����ʂ�A���q���邢�͌����̂��Ƃł���B�@���̎���́u������`�v�ŁA�߂��̐g�ƂȂ�A�ᖡ����҂́A���̋��q�����㏑(���m�ȊO�ł͌����j�ɏ�����邢�͒܈�����āA���̓��e�ɂ�蔻�����邱�ƂɂȂ�B �@�������ܘY���q��͔����̂Q�������O�A�������X�ɍ������Ă���A�R���Q�P���̔��������ʂ����ČܘY���q�傪���q�������e�ŁA�ܘY���q�厩�g������������̂��ǂ����A�r���^��ł���B �@�������ɂ͂������̍ߏ���Ă���A���̍Ō�Ɂu�����Ȃ�Ύ��߁v�̔������L����Ă���B�@�@���ɂ��̌����Ǝߕ����L���B
�@������������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B �@�m���ܘY���q��A���̕��͋���V�ۂV�N�A�s����~�Ď戵�|���߂��܁A �@�Ă̔��t����p�B�ɐ\���t���A��g���Y���q����l��莞���̔������Ƃ����B �A���Y���q�̕Ĕ��t���x�ꂽ���A�x�ꂽ���R���������₢���������A���Y���q�������ė������q����َ̉q����������B����͌�ɕԋp�������̂́A���̎�����i�i��s�j�ɕ��Ȃ������B �B�Ă̔��t�̐i�����ǂ��Ȃ����߁A�����̈ꑶ�Ő[�썲�꒬�̖����q�Ƃ����j�Y���q�ɏЉ�A���Y���q�̎��Ƃ������ڂɂ��ĉz��ɍs�������B�����q����đ���בւ𑗂�悤�m�点�����������A���Y���q�ɑ���̒��B��\���t���A���ꂪ�o���Ȃ���Α��Y���q�̟�������肠���āA�����S�ۂɋ������ȂǂƋ����I�ɏo�āA�Ƃ��Ƃ��P�����̈בւ����点���B �C�����q�̔��t�Ă͂T�O�O�U�]��ɂȂ��������̕Ă̔��p���ƁA�ȑO����̕ĂƂ̑���Ⴂ�ŕ�����������Q�O�O�����������B �D�X�ɔ��t�Ă̊��菑����鎞�A���Y���q����l�ɁA�����q���z��Ŕ��t�����Ă��������Ă��̎��̑�������l�̏ꍇ�A�s�����͊���̕��ɑg�ݍ���ŁA�����Ƒ��Ⴗ�钠����ł����������B �E�܂��A���t�Ă��]�˂ň����ĉ��i����ɋ��͂����{�ޖؒ��̑����q�B�ɂ́A�V�K�ɕĖ≮�̒��ɉ�������悤�ɂƂ̊菑�������o�����A���̊菑�ɕM�܂ʼn����Ă��A�₪�Ċ菑�ǂ���ɓ����č��≮�̖��������ꂽ�B���̂���Ƃ��Ė≮��������A���߈ꔠ�A���U�T�����������B �F���̌㖈�N�~��Ɂi�����q����j�{�l�Ə��ւQ���Q���������Ă����B �G�܂����ɗ����������A�S�ʂƂ��ĂT�O����������B �H���q�̎��V�����^�͌��K���ɓˑR�Əo�����B���B���ˑ��̓������ɂ���Ƃ����b�������̓��S�A���v�ԓ`���ق��P�����ɂ���ĘA��߂����B�܂����V���͐g���������������g���̂Őm�������ɍ���A�����q����Z�ʂ��邱�Ƃ��������B �@���̂悤�ɁA��~�Ċ|���w�����闧��ɂ���Ȃ���A���V���\����i���Ƃ������Ƃ͐��ɋ�����B�����Ȃ玀�߂�\�t����Ƃ��낾���A�a�������Ƃ̎��B���������߂̎|�͏��m����B�@ �@�ܘY���q��ȊO�̊W�҂ւ̔����\�n�͎��̂Ƃ���ł������B �W�҂̏���
��E����ւ̔��� �@�ܘY���q��ւ̔��������n���Ɠ����A��x�͎�Ɠ���ɉ�i�I�Ɂj��ɂ����������n�����������B
��x�͎�ւ̔���
�@��~�Ĉꌏ�̎撲��C�ɂȂ����̂����R���q��сA��ɔ����������n�����̂���ڕt��������Z��ł��������A����s�Ƃ����d�E�ɂ������҂ɁA�Ɩ��f��A�{�l�͑��Ɨa���Ƃ����d�����ۂ���̂́A���{�̗��j�ɂ����ĂقƂ�ǑO�Ⴊ�Ȃ��B �@�����܂ňُ�Ȏ�i���Ƃ����Ƃ����Ƃ���ɁA�V����ȂƂ����ō����͎҂̈Ӑ}�̔��f�����������邵�A��ɑ��钉�M�̑����̐[���������Ƃ��̂ł��邪�A�����ɁA��̍ߏ�`���ɓ������l���A�܂�ڕt�̒����s���̑��݂����̂������Ƃ��ł��Ȃ��B �@��茪�������ɏ����遠���Ƃ������̔ƍ߂Ƃ͉����B��͂�قǂ̔ƍ߂����������悤�ɂ݂��邪�E�������̔���������Ǝ��̂悤�ɂȂ�B�@�܂��ƂɊ������܂镶���ł���B �@�V�ۂV�N�̂X���ɂ͖�͂܂���⒬��s�ŁA��������ܘY���q���Ƃ͉��̊W�Ȃ��B�X�����ɂ͍]�˂ɖ߂��Ċ����s�ɂȂ������A�ܘY���q��͒���s���̗^�͂�����A������W�ł���B�Ƃ��낪��̔������ɂ͌ܘY���q��̍ߏ���܂������Ă���B
�@�ȏ�̂悤�ɁA�������̑O�����ܘY���q���̐��O�́A��~�Ĕ������S�����̕s���������ċ��e���Ă���B�V�ۂ̋Q�[������Ȍ`�ʼn��E��ł���B �@�܂��Ă̔����t���ƍ]�ˏW���Ƃ������Ƃł͑���������Q�҂ŁA���ꂪ�剖�����Y�̗��B �Q�\�͉쎀�҂ނƓ����ɁA�����ƌ�p���l�̌����Ƃ����}����������o���Ă���B ����͂���Ŏ���𖾂̎j�������A����Ɩ�茪�Ƃǂ�����������肪����̂��B
�@��ւ̔����O��̏�i�́A�����`�v���u�V�ې��������v�̒��Ŏ��̂悤�ɕ\�����Ă���B
����I�Ɏ�i����s�����͘a���j�ւ̐\���n��
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||