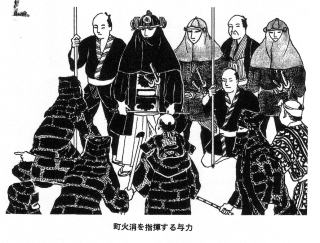|
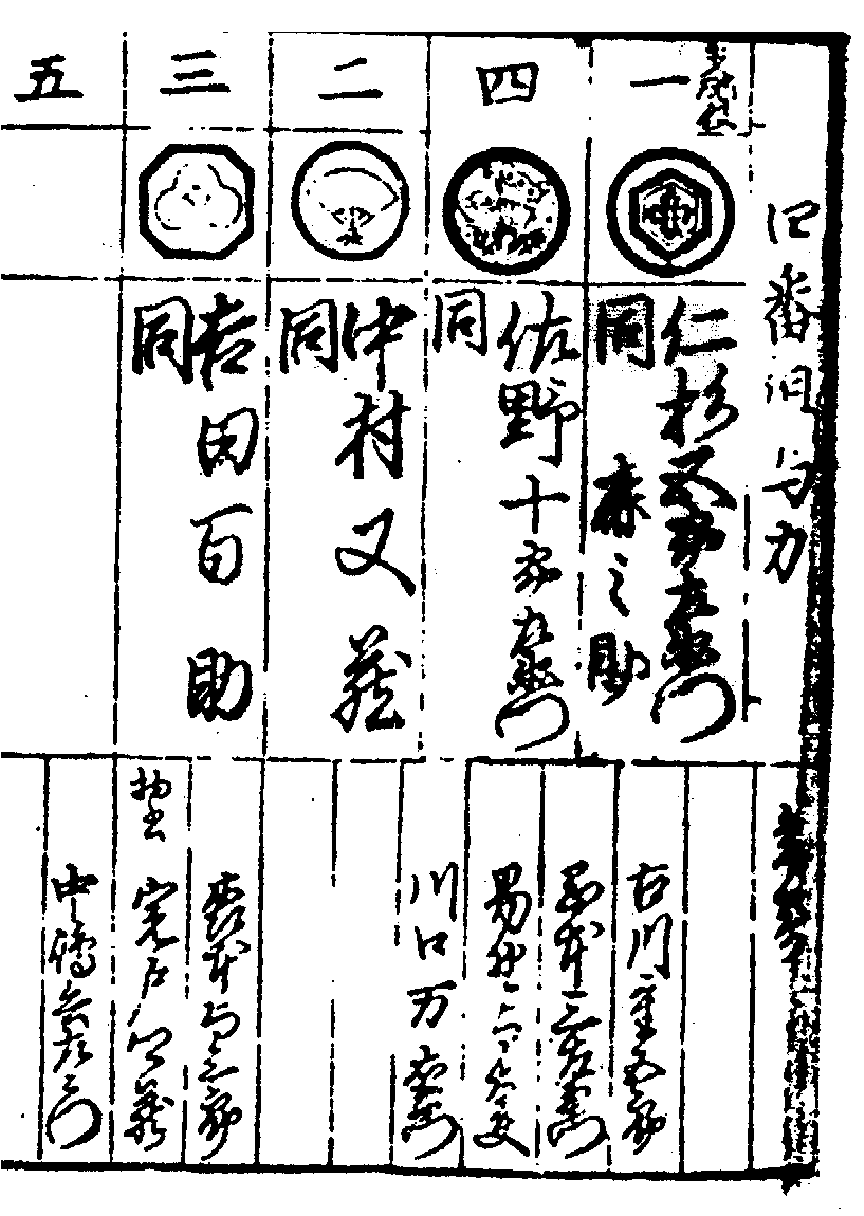 左は天保12年発行の町鑑、4番組の与力同心名簿である。 左は天保12年発行の町鑑、4番組の与力同心名簿である。
このとき、五郎左衛門は4番組与力の筆頭、すなわち同心支配役(支配与力、筆頭与力とも呼ばれる)であり、同心支配役5人の中から選ばれる年番方与力を兼ねている。
同じ枠の中に書いてある名前、あるいは「同」とあるるのは息子また養子で将来の相続予定者が無給または有給で与力見習をしているのである。
「鹿」と「康」が紛らわしく、一部の復刻版町鑑では康之助としているものもあるが、これは鹿の異体字、従って「鹿之助」が正しい。
この鹿之助は出来の悪い息子で五郎左衛門にとって悩みの種であったようだ。
鹿之助は文化14年(1828)の生まれと推定される。(天保13年遠島のときの29歳から逆算)
幼名千代松といい、父五郎左衛門は28歳であった。
仁杉家10代目として期待をかけられて育ったことであろう。
与力は「抱え席」といわれ、その代限りで任命される役職であったが、実際にはよほどの事がないかぎり相続が認められていた。
しかし一方、与力職は誰でも出来るものではなく、経験と知識が必要であったから与力の子供が13、4歳くらいになると与力見習となって、与力職の比較的簡単な役から経験を積むようなしくみになっていた。
鹿之助も与力見習になっていたが、どういう経緯があったのか賭博を取り締まる立場のものが賭博に手を出したようだ。
文化から文政時代にかけて社会の規律もゆるみ、賭博も盛んになっていた。旗本屋敷に住み込む渡り中間などが中間部屋に賭場を開き、町人や浪人などを集めて賭博を行う、それを取り締まるべき奉行所の役人も見ないふりをして若干の金をもらう。 こんな賭博が横行していた。
普段人のいない大名の下屋敷や旗本屋敷が舞台になり、一度摘発すると大勢の中間、浪人、町人が縛につき、奉行所の役人も何人も捕まっている。
このような賭場に出入りする息子を持つ五郎左衛門は南町奉行所の中心的な与力。その苦悩は想像以上のものだったと察せられる。
天保13年3月22日。評定所に呼び出された鹿之助は父五郎左衛門の判決を聞かされた。この年の正月早々に病死しているにもかかわらず、「存命なら死罪」という厳しい判決であった。
同時に鹿之助と養子の弟清之助はともに遠島処分となり直ちに伝馬町牢屋敷の遠島待ちの揚屋敷に入れられた。
お救い米買付けに関わる不正事件で処罰された五郎左衛門への判決文の中に倅、鹿之助に関する記載があり、公儀も鹿之助の行状については着目していたようである。
下記抜粋する。
| 又者悴仁杉鹿之助儀、与力見習中、風と家出致候処、武州瀬戸村藤助方に罷在由及承、同組同心佐久間伝蔵外一人差遣し、内々にて引戻し、或は鹿之助兼々放埒之儀有之、自然金子手廻兼、孫兵衛方より勝手賄賄金借受遣す次第も有之 |
「仁杉五郎左衛門の倅鹿之助は与力見習中にある時突然家出をしてしまった。普段から素行が悪かったようで、ある時突然家出をしてしまった。八方探した結果、武州瀬戸村の藤助方にいることが分かったので、五郎左衛門は腹心の部下である同心・佐久間伝蔵他一人を派遣して内々に連れ戻した。また鹿之助はかねがね放埓なところがあり、自然金詰まりとなり、孫兵衛方から勝手賄金を狩り出したりしている。」
というような意味である。
武蔵国で「瀬戸」がつく村は5箇所ほどあるが、埼玉県比企郡の瀬戸村か、横浜市金沢区の瀬戸村のどちらかであろう。
金沢の瀬戸村は瀬戸神社のあるところで金沢八景とうたわれた景勝地を持ち、物見遊山の客が押しかけていたから賭博場もあったろう。やくざ者と考えられる藤助の家があった村として、比企郡の瀬戸村より可能性が高い。
また孫兵衛というのは五郎左衛門が懇意にしている本材木町の商人で、お救い米を買付けしていたときに、新規に米問屋の中に加えられるよう骨を折ってやった米問屋の主人である。
このため五郎左衛門家にはお礼や、年賀、歳暮、見舞、選別などの名目で折にふれて金品が届いていた。 鹿之助はこの店に乗り込んで金をせびったのである。
公儀御馬預との諍い
幕末に名与力だった佐久間長敬が、明治になって質問に答える形で江戸時代の町奉行所について語った「江戸町奉行事跡問答」に、鹿之助について次のような逸話が書かれている。
問 火事場先にて与力と他の役々と喧嘩せしこと候や
答 山役先は役儀を重じ、自己の争はいたさざれとも、多き中にて間違いにて争論も出来ることあり。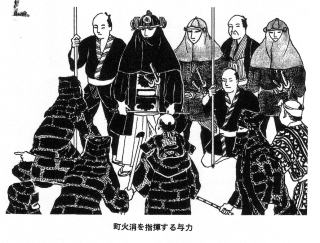
天保年間の頃、火事場掛り与力仁杉鹿之助と幕府の御馬乗様のもの所多一郎と云ものと争論山来候。其訳は御馬乗様のものは上の威権をかりて火近まで馬を乗込来り、馬の挙動を様(ためし)し候。其御馬には耳札(おもがい)と唱金色の小札へ葵の御紋印しあり。尻覆(しりがい)にも御紋あり。陣並・腰さし挑灯・口附別当までも一目して御馬乗りと云ことは知らるるものにて、其上いつれも馬上達者の若ものにて、途中諸藩の火の元も跡より御馬乗の駈来るを告れば遣を譲りて通し、若し不案内の国侍などこれに不敬を生ず。うしろより来りて乗抜けんとする時は、忽ち鐙を払らわれ突落さるるか、或は其藩の目印を被奪、必難題を被申懸、手数を掛けて詫入ことあるなり。虎の威をかる狐にて火毒にては□
の如く恐るるなり。
然るに仁杉鹿之助、兼々不快に思ひ居しが、本郷妻恋坂の出火にて同役二、三名と八丁堀の組屋敷より駈附候処、坂の中程にて跡より駈来る馬上のものはけしくむちにてしたたかに被打るを憤り、行違さまに十手にて打返したるに、其乗人にはあたらずして馬をしたたかにたたきしゆへ、馬は驚飛出せしに乗手は忽ち馬を乗戻し一場の戦となり。
鹿之助の火事頭巾を抜き捕へ、馬の前へ引揚げ、坂を駈登られんとす。同道のものこれを見るに忍ひず鹿之助を取戻さんと引止しは同組与力にて余の叔父原音五郎なり。この同人は所多一郎と面識のものなれは幸に仲裁し、鹿之助御馬と知らず不敬を働きしことを謝して同人を引戻し、名刺を与へて其場を済して職務を勤めたりしが、跡にて御馬預りより表向の掛合を受け、鹿之助は姶末書を出して事済たり。
此咄し後に余は所多一郎の馬術門人になり、神田橋外の幕府御厩へ通ひしゆへ、多一郎壮年元気咄しの一つなれなる。
記録もあれば実話を告げ右に示すなり。この外、火事場喧嘩咄しはいろいろあれとも、事ながけれは略す。 |
鹿之助は天保年間、まだ部屋住み(まだ一本立ちの与力職を相続していない)であったが、与力の職掌のうち比較的簡単な分課である町火消人足改方を担当していた。
出火の際は町火消しの防火進退を指揮し、町火消し各組の間の消口争いなどを取締まる役であった。
天保12年11月26日の本郷妻恋坂での大火に八丁堀から同役2,3名と出動した鹿之助が公儀御馬乗りの所多一郎と諍いを起こした。
所多一郎は将軍のお召し馬を預かり、調教する役目であるが、馬が火に驚くようではいざという時に役にたたないからと、火事と聞くと訓練のために現場に乗り出していた。
葵の紋入りの面懸、胸懸であるから、一目で公儀の御馬乗りとわかり、人々は恐れて傍らに避ける。 所多はこれをいいことに増長し、周りの者を蹴散らしたり、突きのけたりするので火事場掛の人々には迷惑な存在であった。
鹿之助はかねがねこれを不快に思っていたが、本所妻恋坂の中ほどで後ろから駆け上がってくる馬上の者が激しく鞭を打って来るのに憤り、すれ違いざまに十手で打ったところ、馬を激しくたたくことになった。
所多はたちまち駆け戻り、鹿之助の火事場頭巾を抜き捕らえ、馬の前に引き上げ坂を上ろうとした。
たまたまこの時一緒にいた与力の原音五郎が所多一郎と面識があったので仲裁し、鹿之助も将軍の御馬と知らず不敬を働いたと謝ってその場を済まし、火事場での職務を勤めた。
後日、御馬預かり所多一郎より表向きの掛合い(苦情申し入れ)があり、鹿之助は詫びの始末書を提出して事を納めた。
葵の御紋は大きな力を持っており、万一将軍御馬に怪我などがあったら御目見え以下の与力級では大変な処分を受ける事になる。
この一件は火消人足改役の鹿之助の方に歩がありながら、「虎の衣を借る狐」に詫び状を書いたのである。
与力同心務方書上帳 (嘉永二己酉年二月)
町火消人足改勤方之儀申上候書付
一、御月番之節者上役下役不残出火場江罷出消防差配仕、且町火消人足相改申候
一、御非番之節者上役壱人下役弐人者場所江罷出、御月番之御差図請相勤、上役壱人下役弐人者町火消朱引境江相詰、出火鎮候而引取申候、勿論相詰罷在候内及大火候欺、又者外出火等御座候得者、早速其場所江罷越申候、但、相詰罷在候内、御場所柄二候旨相分り候得共、朱引打越其場所江罷越申候
一、大火およひ候節者相伺、最寄二相詰候町火消共呼上申候、場所之様子二寄格別人足無数消兼候節者、呼上跡二而申上候儀も御座候
一、御曲輪内出火有之候節者、御曲輪廻り町火消共最寄御門外江相詰御差図之上消防二相掛ヶ申候、若及大火候得者両御番所前二相詰候町火消共呼上申候、但、御曲輸外武士屋敷之儀者時宜次第町火消相掛ヶ候心得二御座候
一、御城内江風筋不宜候節者、大手或者桜田御門外江町火消共呼上私共附添罷在御差図之上、御城内江入申候
一、御曲輸内其外御場所柄出火焼失跡下火御差図次第消鎮させ申候、場広二而消兼候節者相伺、最寄町火消呼上消させ候儀も御座候
一、町方出火下火之儀者薪材木等其外格別火気強分者消鎮させ、其余者町々申合下火消候様申付引取申候、但、御成前前夜又者御法事中杯者町方下火も消鎮候迄場所二罷在差図仕候
一、出火鎮候得者、下火等手当之ため出火いたし候町内組合之火消人足者残し置、其余町人足者混雑仕候二付、見計場所為引払申候
一、出火場所之儀火鎮候上、火元井凡之間数見計申上、格別大火二而間数難見積節者何町より何町迄と申儀御届申上候
一、遠火二而途中迄罷越候内鎮候得者、其段御届申上候、但御届書面者封候而町方江申付当番与力迄差遣、当番より差上来候
一、人足共消防二相掛怪我仕候節者為見分双方下役共差遣申候、其外風聞等御差図次第下役へ申付為承候儀も御座候
右之外場所之時宜次第相伺御差図請相勤、品二寄御出馬先隔罷在候節者見計差略仕、下役一同打込相勤申候、私共勤方荒増書面之通御座候 以上
酉二月 藤田六郎右衛門
金子兵七郎
|
高橋義夫の描く「不肖の息子」ぶり
高橋義夫の「天保世直し廻状」では鹿之助についてように描かれている。
(前略)
「鹿之助というもう30近い息子がいるんですよ。これが16,7のころからぐれて、深川一色町の藤助長屋というところへ入りびたって家に帰らなかった。藤助長屋というのは博突打ちの巣ですよ。
一度は仁杉の且那の頼みで、目明し連中が深川に踏み込んで、首に縄をつけてつれ帰って、与力見習いにしたんだが、すぐに逃げ出して深川に舞いもどったんです。
深川に情婦がいるんです。鹿之助がこしらえた借金のとりたてが、且那のところに来る。親馬鹿といやあそれまでだが、息子の命をとるか金をとるかと責められたら、金を出さないわけにはいかないでしょう」
仁兵衛は仁杉に同情する口ぶりだった。
(後略) |
鹿之助の妻子
天保13年、流刑となった鹿之助は当時29歳、妻も子もいた。 仁杉家過去帳に鹿之助の妻として
法雲院殿 天保5年3月23日 没
とある。 この年、鹿之助は21才であるからかなり若いうちに妻帯したことになる。
妻が若死したため鹿之助は再婚している。 天保13年3月21日の五郎左衛門他への判決文の中に
無構 仁杉鹿之助妻 みや
とある。
この後妻「みや」は仁杉家の過去帳にない。
鹿之助は三宅島に流され、長期間戻る見込みがなかったので、「みや」は仁杉家を出て、実家に戻るか再婚したのであろう。
また鹿之助には娘がいたようである。 過去帳の中に
真顔信女 安政2年4月23日 没
という戒名があり、「鹿之助娘」とある。
仁杉家の墓に入っていることから、他家へ嫁ぐ以前になくなったものと考えられる。
先妻の娘で天保4、5年生まれだとすると安政2年(1855)に21、2歳で亡くなった事になる。 また後妻の娘とすれば13から18才程度であった。
鹿之助のその後については長男は三宅島に流刑参照
|
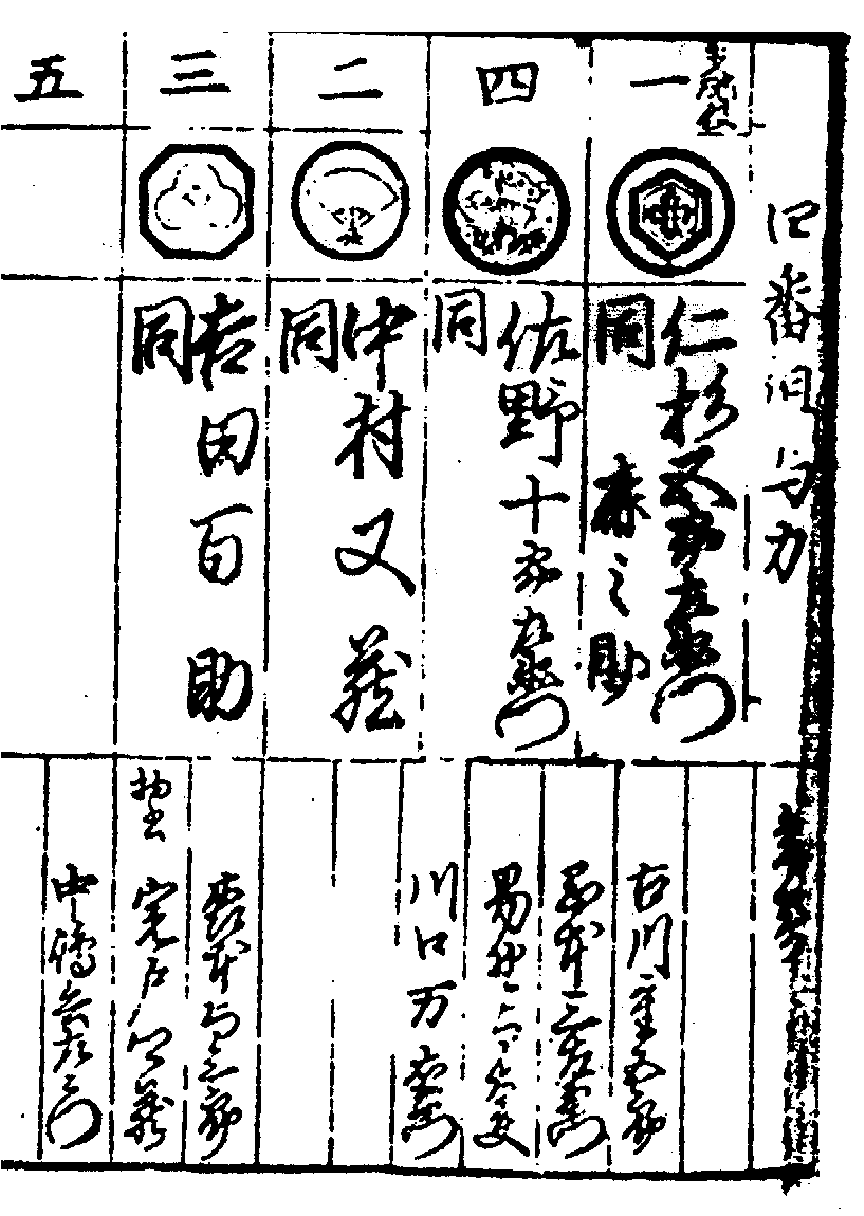 左は天保12年発行の町鑑、4番組の与力同心名簿である。
左は天保12年発行の町鑑、4番組の与力同心名簿である。